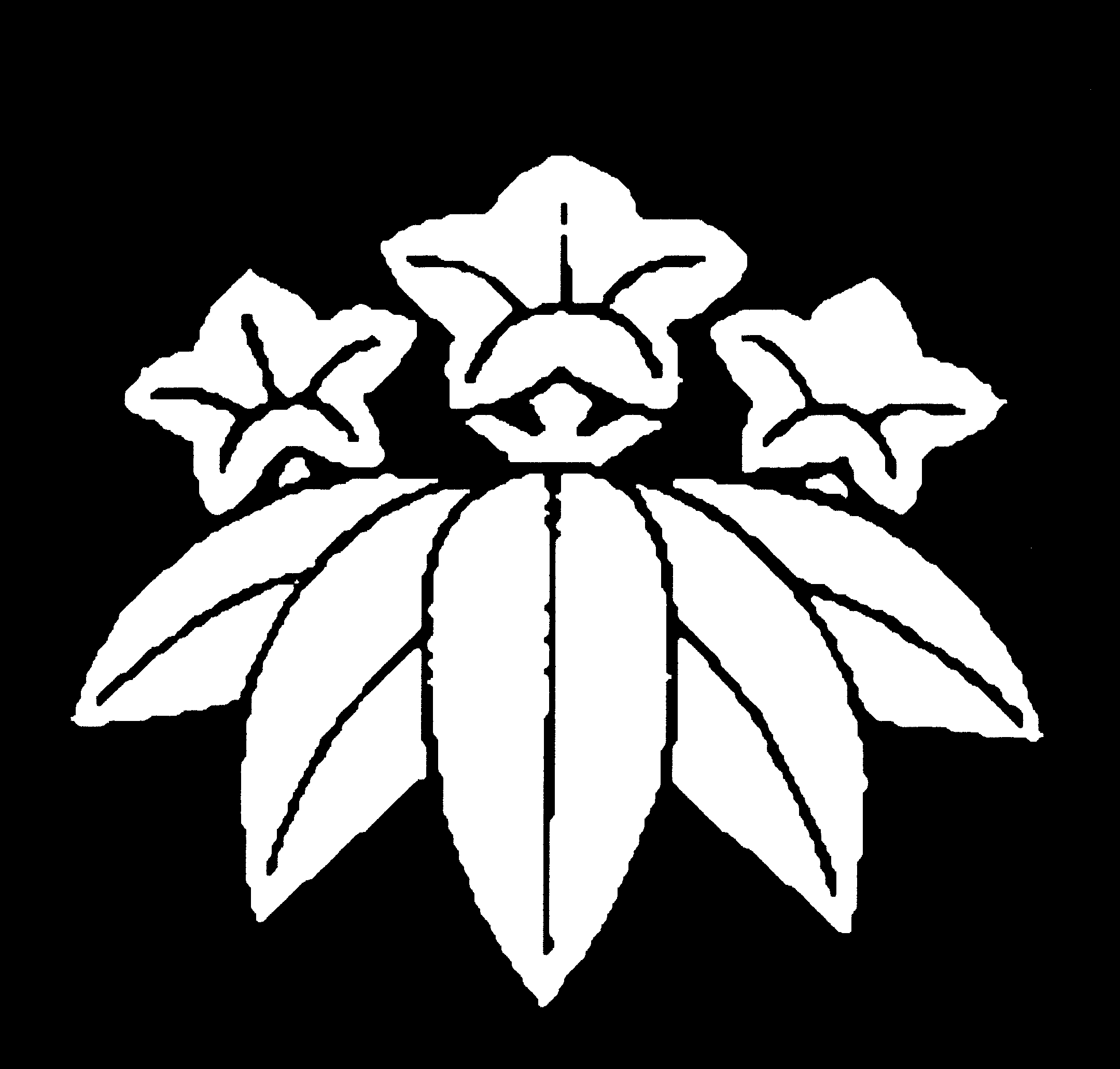Re: 伊勢青木家 家訓2
副管理人さん 2007/07/29 (日) 22:02
伊勢青木氏の家訓10訓
前回の「家訓1」に続き、今回は「家訓2」に付いて述べる。
この「家訓2」に付いては、「家訓1」の意味する所に付随しての内容となる。
「家訓1」の意味する所は、纏めると次の事となる。
「家訓1」 夫は夫足れども、妻は妻にして足れ。(親子にして同じ)
「家訓1」の関係口伝
”青木の家は「女」が家を潰す。”(口伝1)
”自尊心の必要以上に強い女は不幸”(口伝2)
”妻はお釈迦様の掌で遊ばせる心を持て”(口伝3)
”夫は第一番目の子供である”(口伝4)
”大事な決め事は夫が決めよ”(口伝5)
”「口伝」の下に、神が与えた「女の本質」を理解して、「母性本能」で妻は成長して、「妻は妻にして足れ」で「家=妻」で務めよ”としているのであった。
以下に夫々にその持つ「戒め」の意味するところを説明する。
「家訓2」 父は賢なりて、その子必ずしも賢ならず。母は賢なりて、その子賢なり。
「家訓2」の関係口伝
”教育とは学問にあり、教養とは経験にある”(口伝6)
”教育は個人の物(知識)”「素質と素養」(口伝7)
”父親は、「背中で育てよ」、母親は、「胸(肌)で育てよ」”(口伝8)
家訓3 主は正しき行為を導き成す為、「三相」を得て成せ。(人、時、場)
家訓4 自らの「深層」の心理を悟るべし。(性の定)
家訓5 自らは「人」を見て「実相」を知るべし。(人を見て法を説け)
家訓6 自らの「教養」を培かうべし。(教の育 教の養)
家訓7 自らの「執着」を捨てるべし。(色即是空 空即是色)
家訓8 全てに於いて「創造」を忘れべからず。(技の術 技の能)
家訓9 自らの「煩悩」に勝るべし。(4つの煩)
家訓10 人生は子孫を遺す事に一義あり、「喜怒哀楽」に有らず。
(家訓は禅問答的な表現方法で漢文的にて表現されていて判り難い、敢えて、現代用語として、書き改めて紹介をする)
解説
父のその能力で、その家の先頭にたって「家の事」を「仔細」に渡りすべて差配し考えを強要する家は、その子供は良い子供が育たず、又賢くならず、母が賢(家訓1)なれば家は纏まり、子供は良い子に育ち賢に育つ。
家訓1で言う「家」は妻が仕切る事の結果で、家は栄え、子供は賢い子供に育つとする。
それでは、ここで言う「賢い」とは、一体どう云う事か。
「賢」とは、「頭が良い」と言う事でなく、「総体的に優れた素質と素養」を身に付けた子供という事に成る。
その「素質と素養」は家訓1で言う「母の如何」に関わる事である。
それでは、父親が「賢」であっては成らないとするはどう云う事か。
父親という者は、その「賢」を家族の中では、決して曝け出しては成らないとしている。
子供は、曝け出したその父親の「賢」を見て、自らもその「賢」と成ろうとして無理をし、周囲との関係を無視し、偏りのある人物に成り、総体的な「素質と素養」が得られない。又、父親の「賢」を見て萎縮し、適性に成長せず、「素質と素養」を持つ事は出来ない。
この何れかの子供が育つとしている。
この結果、「家訓1」で言う「家」を継ぐ事と成った暁には、「家」は衰退させると説いているのである。
つまり、「賢」であっても良いが、曝け出しては決して成らないとしているのである。
では、家庭には、それを維持する芯なるものが必要である。では、どうして父親の存在や威厳を示せばよいかと云う事になる。
つまり、父親の「賢」は、直接見せるものではなく、[父の背中」で見せる事が肝要であるとしているのである。
父親が、(賢であろうが)、「愚」であろうが、子供はその「愚」を見て自らを律する子供になる事の方が、”総体的な「素質と素養」の持った子供に育つ”としているのである。
では、”父親が「愚」で有ればよいか””「愚」であっても良いのか”と云う事になる。
そう云う事だけを言っていない。あくまでも、「家訓1」の中にある「環境」の父親である事としているのである。
当然に、この「環境」とは、”大事な決め事は夫が決めよ”(口伝5)の範囲にある事である。
「賢愚」に於いて、曝け出しては成らないとしている。あくまでも、間接的な「背中で見せる行為」と「環境」の”大事な決め事は夫が決めよ”(口伝5)で家庭の「芯」なるものは維持出来るとしている。
父親の「賢」とは、同じく「頭が良い」と言うことを言っているのではない。「父親の賢」とは、「家訓6」で詳しく説明をする。
「家訓1」での補足では、男女の異なる「性(さが)の定」とする「家訓4」であるとしている。
「家訓2」での補足は、「家訓6」であるとしている。
(故に家訓4及び家訓6は相関するが、シリーズ中で解説する)
では次は、「父親の賢」とは、本質は何なのかと云う事になる。
つまり、家訓6に起因するので概容を述べる。
「父親の賢」とは、「教育」で得られた事ではなくて、「教養」を身に付けた事にあるとしているのである。
言い換えれば、(詳しくは「家訓6」で解説し説明する)”「教育」と「教養」は違う”と説いている。
「教養」は、「教育」を受けなくても自身の努力と経験にて得られるものとして「本質」は違うのである。
では、どう「本質」が違うのかと云う事になる。その差違は次の通りである。
この関係口伝では、主に、その主意は ”教育とは学問にあり、教養とは経験にある”(口伝6)としている。
つまり、”「教育」とは「育む」(はぐくむ)ものであり、「教養」とは「養う」(やしなう)ものである。”としている。
では、この事に付いて少し検証してみる。
必然的には、その論理的な差違は、人の社会では、次の様に定義付けられるのではないか。
定義
「育む」とは、学問的に得た「知識」で、更に「知識」を生伸し、「直線的拡大」を果たす事であり、大意は「枝葉」を伸ばす成長事を意味する。
「養う」とは、人生的に得た「経験」で、更に「徳識」を着実し、「増幅的拡大」を成す事にあり、大意は「果実」を着ける成長事を意味する。
故に、数式にすれば、教育=「育む」=学問=知識 教養=「養う」=経験=徳識 式−1 が成立する。
「家訓6」はこの「経験」(徳識)を重視しているのである。
父親の子供への影響は、関係口伝の”教育は個人の物(知識)”(口伝7)として、物(知識)は周囲(子供)には影響を与えないとしているのである。
父親の「知識」は、子供には、何らかの手段を用いなければ伝授できない。その手段とは「教育」でしか得られない。
何もしななければ、その「知識」は、子供には移らず「養う」事にもならず、その「着実」も成せない。
確かに個人のものである事が頷ける。だから、親は、この手段として、「教育機関」にて子供にも再び同じ「知識」を「個人の知識」として得させようとしてするのである。
しかし、その複雑な「経験」(教養 徳識)は、「父親の背中」で伝えることは可能である。
真にそれ以外に無いであろう。
人に依って異なる「経験」は、「教育」としてはこれは「教育機関」では得られない。あくまでも、「父親の背中」でしか伝えることは出来ないのである。
「言葉」で伝えてたとしても、しかし、「知識」は同じ量を記憶すれば、個人差が無くなる事から「即効果」であるが、「個人差のある経験」は、子供に取って「参考」にしかならないのである。
あくまでも、「経験」の滲み出る「父親の背中」で感じ取った「徳識」(教養)は、口伝の「環境」の中で、重厚な感覚として、無言で子供に充分な影響を与えるとしているのである。
故に、、「父親の賢」=「教育」+「教養」=「父親の背中」 式−2 が成立する。
依って、(式−1)+(式−2)+「母親の賢」=「子供の賢」=「素質と素養」 式−3 が成立する。
附帯して、「母親の賢」=「家訓1」=「母性本能」 式−4 が成立する
三段論法ではあるが、「家訓2」の連立方程式の上式が成立するのである。
昨今は、この説に対して、昨今の唯物史観が余りにも横行し、その視野が「父親の背中」と云うものの観念史観を許容できないで、このために「教育は教養」として定義付けられている様な風潮がある。
しかし、これは間違っている。「家訓6」で詳しく述べるが、”教育に依って教養が身に着く”かの事としているが、これはおかしい。
「教育」は「知識」であり、「知識」が身に着いたからと言って、教養が身に付くとはならない。
例えば、受験勉強中の様に、「知識」は覚え詰め込めば出来る。受験勉強した者が、「教養」が身に着いたとはまさか誰も思わないであろう。又、大學の教授が全て「教養者」であるとは限らない。
しかし、現代はここが社会の間違いの点で有ろう。
例えば、世間では俗説として次の事が言われている。
特に、テレビなどでは、論説を証明するために、”...大學の教授が言っている”などと巧みな手を使って持論誘導をしいている場面がある。
つまり、”学者の言うとおりにしていて、上手く事が運んだ試しは無い”
即ち”学者の説は、学者バカ”との説があるが、この様にそれを非難される点は、この「知識」での結論だけで、社会の「諸事」を論じるから言われる言葉であって、これは「教養」の不足に関わることから来ているのである。
つまり、総体的に優れた「素質と素養」の中から発する言ではない事に起因しているからである。
又、社会では、”父が家の先頭にたって「家の事」を仔細に渡りすべて差配し考えを強要する家”は、正論であるが如く言われる傾向がある。”これが何が悪い”と言う言葉が耳に入るが、全ては悪いと言う事ではないと考える。
しかし、この場合、ここに二つの問題があり、この点に関わると好ましくない。
一つ目は、”仔細に渡り”である。
「仔細」に事細かく口うるさく言うは、家訓1で言う「妻の立場」が無くなり、妻に依って育てられる「養育部分」が欠落し、偏った子供が育つ事になる。子供の育つ「養育部位」は殆どが母(妻)に依るところが大きいからである。
ゆわんや、”「母性本能」から来る愛情の部分が多い”とするのである。
この「養育部位」は「子供の基本部分」になると言うのである。
つまりは、愛情の部分=子供の基本部分=「母性本能」 式−5 が成立する。
故に、関係口伝では、母の愛情の発露である ”胸(肌)で育てよ”とされるのである。
”仔細に口うるさく言う”は、この式を欠落させた子供が育つとしているのであるから、子供は「賢」ではなくなるのである。
では、父親はどうすればよいかと言う事になる。
それは、家訓1の口伝5でも述べたが、「大事な決め事は夫(父親)が決めよ」と「背中で見せよ」の二つである。
関係口伝との結論は、父親は、「背中で育てよ」、母親は、「胸(肌)で育てよ」”(口伝8)と言う事に成る。
二つ目は、特に、男子を育てる場合にある。
昔では元服期(15歳頃)より18歳頃までの4年間の思春期は、父親の「指導」を必要とする。
これは、脳の中での「性(さが)の芽生え(目覚め)」により、「男子の自我」が生まれる。
これは女性としての母親の経験する思考範囲を越えているからである。
つまり、「母性本能」では処理しきれない「行動や思考」を示す事から来ている。(家訓4で詳しく解説し説明する。)
但し、この場合も、父親の”仔細口うるさく”では無く、あくまでも「背中で見せよ」であり、その「背中」が示す「人生経験」で、「強要」ではなく、「指導」する事にあるとする。
男子の子供には、父親で無くてはならない「特定の養育期間」があるとしているのである。
「世の中の成り立ち」や「男の性(さが)」に付いて経験を通して、「人生の先達、友人」として「指導」する事であるとしている。
参考 家訓4で説明するが、概略注釈する。
「男の性」には、意識でコントロールできない脳の中で起こる「深層思考の原理」の事であり、「理想、合理、現実」の三連鎖の思考原理が脳の中で無意識の内で起こる。
これを余りに追求する結果、「人間関係」の中で、「争いや問題」を誘発させる辛い性質を潜在させる。
因みに、「女の性」の「深層思考の原理」は、「感情、勘定、妥協」の三連鎖の思考原理が起こる。
これ等は、何れも良し悪しの問題ではない。各々の「性の仕組み」に合った思考原理に出来ているのである。
(参考 三連鎖の思考原理とは、物事に対して、脳は連鎖的に次の三つの反応で思考を纏める。
物事の処理に付いて、基本となる考え方[理想]を引き出し、それを基[合理的]に判断し、[現実思考]で実行しょうとして、瞬時に無意識の内で、綜合思考する脳の働きを云う。)
(但し、驚く事は、伊勢青木氏の「生仏像様」のご先祖が、現代の脳医学で解明されている事柄に近い人の仕組みを理解していた事である。この事柄に付いて調査した所、大概に合っているので、現代の解明されている仕組みで解説した。)
神が定めるこの世の全諸事に対応する6つの思考であり、この男女合わせて6つの思考で初めてこの世の1つの諸事が解決できるとしている。
故に夫婦は互いに持ち得ていない2種の思考を補い組み合わせて始めて1つと成る。
夫婦は、1種の思考の足りない所を補わせるのでは決してないのである。
(現代の世情はこの考えである所に問題の病巣がある。)
これは、「家訓1」のミトコンドリアのところで述べた神の成せる技である。
ゆわんや、「家訓1」にはこの点を補足しているのである。
だから、「家訓2」の特定期の男子にはこの「思考原理」が芽生える故に、父親の「背中と指導」が必要とされるのである。
この二つの問題事を、父親が上手く処理できれば、”何も言わない「愚」であると見えている父の姿が、それは「賢」と子供の心に残るのである”としている。
故に、必要以上に ”父親は「賢」を曝け出すな”としているのである。”「背中で見せる」だけでよい”としているのである。
つまり、”魑魅魍魎の世間で揉まれた後姿”で充分であるとしている。これは言い換えれば男の人生の「経験」である。
上記の(後姿=経験)であるならば、「教養」=「経験」であるとしていると、故に、「後姿」=「教養」 式−6 である事になる。
何も、俳句や活花やお茶等のソフトな事だけが「教養」だけではない。ハードな「男の後姿」も立派な「教養」であるとしている。
ここでも、次の事が言える。
家訓1では、女性(妻)が優位の立場を認識していない現状を訴えた。現代の病巣であると。
家訓2でも、男性(父親)の「後姿」が「教養」であり、父親の本来のあるべき姿である事が、認識されていない事に痛感している。
父親が、この”認識の無さから口うるさく言うこと”が「子供を教育」していると勘違いしていることから、「賢」なる子供が育たない病巣であると考えている。
又、母親も、この4年間の間の養育期間は、「父親の指導」を強く求められる期間である事を知るべきである。
青木氏の家訓にある事から、何時の時代にも、この「勘違い」が、強い母性本能からこの勤を見誤り起こっていると言う事であろう。
家訓1でも、記述したように、成人になれば、今度は、子供の妻(嫁)が育ててくれる事になる。それまでの家訓2である。
(注意 家訓1の別意である永遠のテーマ「嫁姑の関係」は、この戒めを守っていないことから始まる)
ここで、丁度、「家訓2」を説明出来る様な自然界の法則が起こっている「木の事」に付いてその成長過程を述べてみる。
面白いことが、起こっているので最後に参考に注釈する。
但し、判りやすくするために下記の用語は次の意味を持たす。
「果実」:賢なる子供 「3又枝葉」:夫婦 「中枝葉」:父 「着実枝」:母 「成長枝葉」:「育む」 「成養期」:「養う」
「変態期」:子供成長期(15-18) 「深切り」:背中 「雑木態」:曝出環境 「剪定」:大事な決め事 「選定の習慣」:経験
「着実」:素質ある子 「着果」:素養ある子 「葉色」:育と養 「記憶的学習」:知識 「木勢」:家庭 「木の経験則」:徳識
それは、この上記で説明した事柄の「家訓2」の「育む」「養う」等の過程が起こっているのである。
説明する。
木は、季節の春を得て芽を出す。この時、多くの木の木芽は「3又枝葉」を出す。つまり、5本の指の親指と小指を折った3本の形で枝葉を出す。この枝の真中の「中枝葉」は「成長枝葉」である。木を大きく伸ばしたい時は、この「成長枝葉」を残し、左右を剪定する。伸ばさずに将来に着実させたいときは、「成長枝葉」を切り落とす。そうすると着実のために「成養期」に入る。
この時期の「成長枝葉」を残すと勢力が「成長枝葉」に採られて、直線的に伸びる。余り着実せず収穫量が低くなる。これを続けると何時か、着実の悪い「木態」となる。
そして、この成長過程は7月/20日前後(「変態期」)を境にして、「生育」に突然に変化する。その変化は「3又枝葉」の何れもが「生育期」に入るのである。
そして、「中枝葉」を切り落とした場合は、残りの2本の「着実枝」は実を着ける為に枝を強くして準備する。
この時の「3又枝葉」の「葉色」は、左右の「着実枝」が次の年に実をつけるために出す「葉色」とは異なるのである。
この様に、木の「育と養の差違」は、「葉色で見分け」が外見でも出来る様にする。
木全体が来年、将来に向けて自らの木を大きくする。勢力は全てこの成長に向けられてしまって、枝葉の多過ぎる木態となり、次の年以降の着果は全体的に低下する。何時しか着実は殆ど無くなる。梅や柿はこの現象が顕著に表れる。
一度、この様な「雑木態」と成ると、「深切り」をして元の状態にしなければ成らないのである。この様に成ると、木は長い間の「記憶的学習」(年輪の記憶)を消されて、数年は元に戻るまで「着実」「着果」はしない。(最低は2年程度)
だから、この「変態期」までには必ず、「母性的な愛情」を掛け過ぎずに思い切って、「着実」の目的のために「父性愛的」な「剪定」をする事が必ず必要である。
そうすることで、「3又枝葉」の「着実枝」(左右枝葉)だけを養えば、次年度からは「熟実」が倍増的に拡大して行く。この枝に定量的に確実に着実する。
この二種の枝葉の「選定の習慣」で、「木の経験則」が起こり、そうすると見事な果実(賢なる子供)が出来る様に成る。
しかし、放置しては「木勢」は維持できず、着実しても着果せず自らの木態を守る為に実や葉を落とす。
但し、木には、成長過程の7/20(春)タイプと、逆の2/20(秋)タイプとがあり、木に応じて選択する必要がある。
真に、この「木の生態」は、「人の生態」(子供が賢に養育する様)と一致する。
この様に、自然界の神の成せる業であり、この「家訓2」は事の本質を意味する事になる。
この法則は木だけでは無い。筆者の専門域の自然界の鉄などを顕著として金属類にもこの法則の現象は起こっているのであるが、又、時間が有れば放談として何時か投稿したい。
兎も角も、「3つの口伝」を心得て、家訓2 ”父は賢なりて、その子必ずしも賢ならず。母は賢なりて、その子賢なり。”を理解してもらい子孫繁栄の一助に成ればと考える次第である。
次は、「家訓3」である。
主は正しき行為を導き成す為、「三相」を得て成せ。(人、時、場)
賢なり。
 - 01/22-09:15 No.148
- 01/22-09:15 No.148