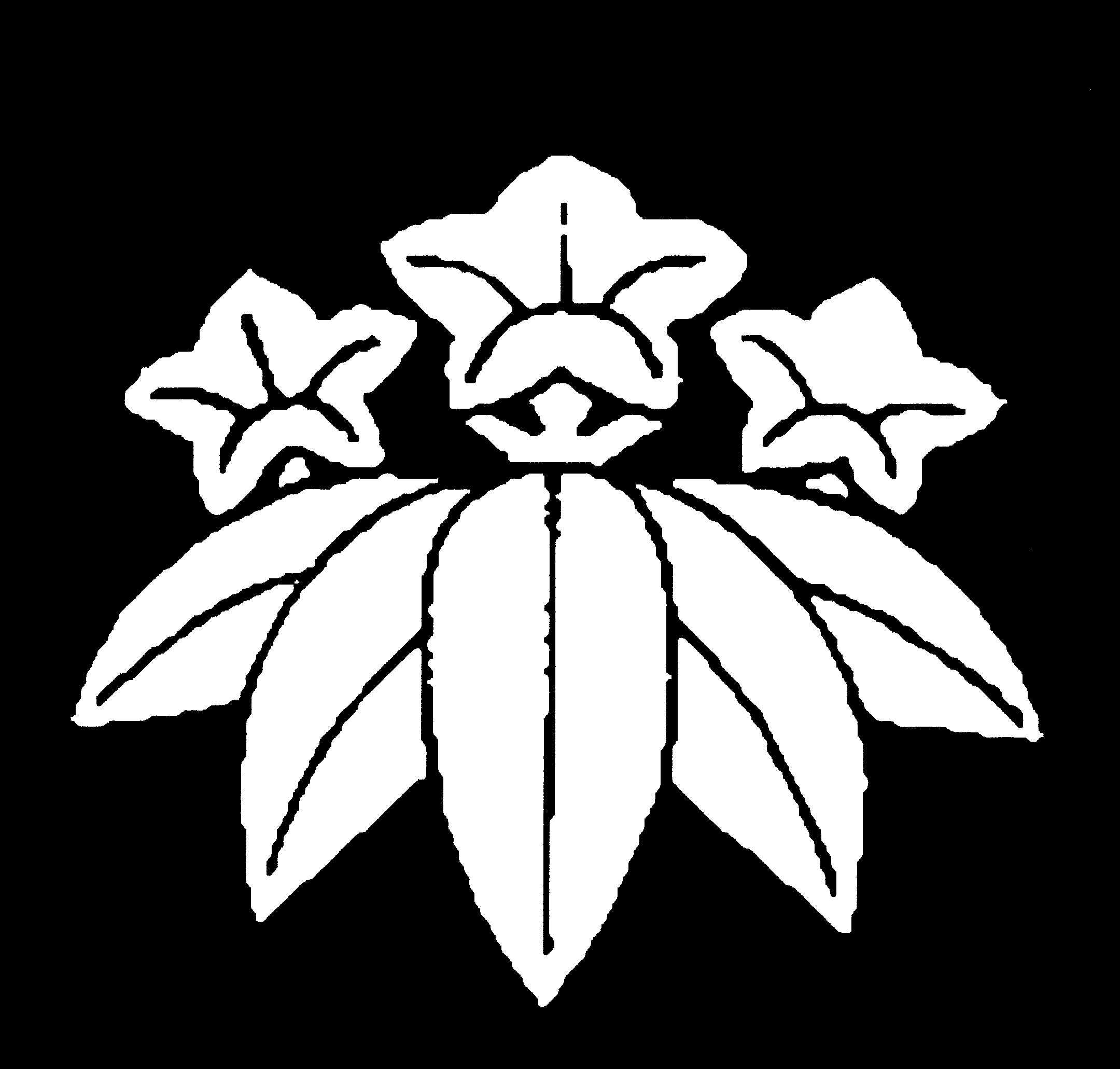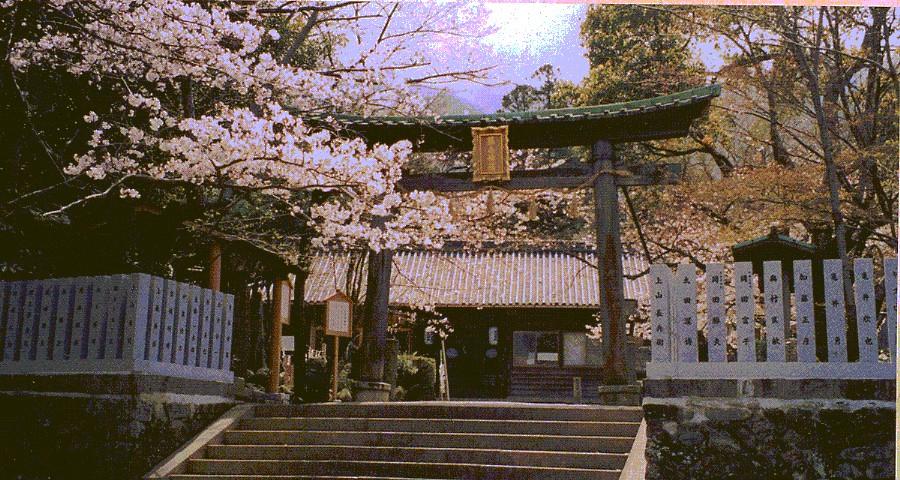このフォームからは投稿できません。
[
ホーム]
[
研究室トップ(ツリー表示)]
[
新規順タイトル表示]
[
新着順記事]
[
留意事項]
[
ワード検索]
[
過去ログ]
[
新規投稿]
[
管理用]
以下は新規投稿順のリスト(投稿記事)表示です。
※記事の投稿者は全て福管理人(副管理人)で、すべての文章ならび画像は福管理人の著作物です。
※この「青木氏氏 研究室」は掲示板形式ですが、閲覧専用で投稿不可となっております。
こちらの掲示板では回答できませんので、もしご質問のある方、さらに詳しく知りたいと言う方、ご自分のルーツを調べたいが、どうしてよいか分からないという方などは
お気軽に青木ルーツ掲示板でお尋ねください。
福管理人[副管理人]より -
青木氏には未だ埋もれた大変多くの歴史的史実があります。これを掘り起こし、研究し、「ご先祖の生き様」を網羅させたいと思います。
そして、それを我等の子孫の「未来の青木氏」にその史実の遺産を遺そうと考えます。
現代医学の遺伝学でも証明されている様に、「現在の自分」は「過去の自分」であり、子孫は「未来の自分」であります。
つまり、「歴史の史実」を求めることは埋もれた「過去、現在、未来」3世の「自分を見つめる事」に成ります。
その簡単な行為が、「先祖に対する尊厳」と強いては「自分への尊厳」と成ります。
この「二つの尊厳」は「青木氏の伝統」と成り、「日本人の心の伝統」に繋がります。
この意味から、青木氏に関する数少ない史料を探求して、その研究結果をこの「青木氏氏 研究室」で「全国の青木さん」に提供したいと考えています。
そして、それを更に個々の青木さんの「ルーツ探求」の基史料としたいと考え、「青木ルーツ掲示板」を設けています。
どうぞ全国の青木さん、その他ルーツ、歴史に興味がある方、お気軽に青木ルーツ掲示板までお便りください。お待ちしております。
※雑談掲示板はこちら、、宣伝・募集ははこちら。
|
 ワード検索 ワード検索 |
- 疑問がある場合やご質問の前に同じ内容の記事が無いか検索してください。
- 複数のキーワードを入力するときはスペースで区切って下さい。
- ページ内だけでの検索は「ページ内検索」をご利用ください。キーワードがハイライトされます。
 最新記事 最新記事 |
Re: 先祖と宗教(キリスト教の教え−2 主題4)
副管理人さん 2007/10/20 (土) 10:07
4「キリスト経の教え」
キリスト教の設問として、1番の続き、2の問題の説明に入ります。
1 他宗を少なくとも先ずは強く排他している事。
2 教えがかなり強引である事。
3 キリスト個人を神扱いにしている事。
4 兎に角にも、”先ずは信じよ”である事。
5 人は全て悪の子供であると否定する事。
6 中間的考え(柔軟性)は無い事。
7 全体が闘争的な発想に成っている事。
8 特定者(若い者)には受け入れられ易い合理的な教えに成っている事。
9 先祖に対する考えは全体として希薄である事。
10 「民族的」と言う考えを認めていない事。
2番目の事です。(教えがかなり強引である事)
1の事がある故に、キリスト教は自説を教委するは当然の事でしょう。
「信じよ」を先ずはじめに来て居ます。信じなければ救われないと言う事に成ります。そんな不公平な神は存在しません。神は万民に公平ですから、信じなければ救われないとすると、それは神ではなく普通の人間のする事です。神を前提としている神が、人間と同じレベルであるとすると矛盾しています。
かなり、矛盾をはらんだ強引さを感じます。
仏教では、「信じよ」とは云っていません。般若心経でも、「悟れ」(理解)と説いています。
突き詰めると仏教の教えは「色不異空、空不異色」「色即是空、空即是色」であろうと考えます。
ここから全ての教義の発端が理解され解読出来ます。
つまり、この世はこの一つの教義であり、その「理解」から”人としての「行為と行動」が生まれ、強いては、人としての悩みは解毒するで有ろう”と説いています。
これは、信じなくても、この”理解が成せば成るほどに人としての悩みから救われる”としている訳です。
つまり、誰でも、仏教に帰依しなくても救われると言うことです。
この「理解」が得られた場合に於いて、”人は冷静で、正しい「心根」が得られ、それに依って、人の本来の正しいあるべき「道」が開かれる”と説いています。
これを学問として、仏教から「禅宗」(禅問答)と言う教義が生まれたのですから、「宗教」とするよりは「宗教学」(人生学)とする方が適切ではとも思います。このことからも、つまり、「教えが強引」からは程遠いものと成ります。
ここに、他教との違いが大きくあると考えます。「学問的宗教」とも云えます。
但し、ご利益信仰とは別にします。
日本人の仏教への「信心の姿」は、他教の姿とは違うのはこの点にあり、個々の人の「自由な姿」に委ねているところです。つまり、「色即是空、空即是色」の教えどおり、決められた「信心の姿」を自由にしている所です。イスラム教やキリスト教のように、”信心はこう云う姿ではなくてはならない”とする仏教の教義は何処にも有りません。好む範囲でやればよいという事でしょう。
この様に「教え」に対して、”信じよ、されば救われん。”の拘束としての強引さは有りません。「強引さ」は「色即是空、空即是色」の先ず第一教義の意に合致しません。
この背景は、物部氏と蘇我氏の戦いの後の結末と始末に関わる歴史的処理から来ています。
つまり、先ず、最初は朝廷が主体としていた「神道」を、「仏教」への宗派変えでは、一応は取り入れたものの朝廷の存続をも否定する結果とも成りかねず、過半数以上のそれまでの多くの「神道の民」の不満と反発を招きます。そこで生まれたのが、「神道と仏教」との「融合文化」の天智天皇による「天神文化」であります。(研究室の大化改新の新説への反論を参照)
(仏教導入の直ぐ後の天智天皇は、伊勢に国の守護神として伊勢神宮を建立し、「天神文化」を発展させた事で証明となり、各主要な氏は、氏神を建立し「神道」を誇示し、氏独自の先祖を祭る菩提寺をも建立して「仏道」とし2つの融合を図った事も証明)
つまり、宗教の「神」と民の間には、「仏」とするものを存在させて融合を計ったのです。そして、その「仏」は先祖であるとして身近な宗教としたのです。
これが「天神文化」です。この「天神文化」は現在までに引き継がれているのです。
この「天神文化の融合」が「仏教の教義」を緩やかにして、上記の[強引さ」を排除した所以でありますし、「仏教学的扱い」と成った所以もここから来ています。
又、他国の仏教国の教義とは違う点でもあります。
要は、「信じようが、信じなくても」、その「理解」の「行為と行動」の中で、「人としての道」(冷静で正しい)が生まれれば、「万民は救われる」と説いているのです。
そして、それは、”自ずと、「神」「仏」に自然に導かれる”としているのです。
さすれば、”死する時は、「4つのみ」から発生する煩悩を脱却した「仏」として、他次元で存在する”と説いているのです。仏教では基本的に故に強引さは有りません。
次は3番の事に続きます
Re: 先祖と宗教(キリスト教の教え−1 主題4)
副管理人さん 2007/10/20 (土) 09:51
ご意見の内で、次の文意に対する問題として、
1「呪いの意」
2「時間の逆行性」
3「行為と行動の進行性」
4「キリスト経の教え」
5「仏教とキリスト経の妥協の余地」
以上に付いて私観を述べたいと思います。
超論文に成りますので、シリーズで記述する事にしますのでご理解ください。
4「キリスト経の教え」
さて、4の主題の「キリスト教の教え」に付いて。
下記の設問(1−10)です。
そこで、前々回の設問の末尾に次のようなことを書きました。
”信仰すれば、こうしてくれる”は信仰とは云わないのではないかと言うことを書きました。
兎に角、私は「宗教」に対して「ご利益信仰」が主体と成っている事に疑問なのです。
つまり、”こうすれば、こうしてくれる”と言う見返りを求める信仰はここでは論じないでおきます。
次の設問の「キリスト教」は、この傾向が説話の中で多すぎると感じています。
”信じよ、されば救われん。”には納得できません。信じなくても救われる筈です。信じたら神のご利益があると言うことは真さに、この事です。
仏教は、”信じよ”とは云っていません。”理解せよ。”です。
つまり、”理解すれば「静かなる心根」を得て、必然的で、間接的に救われる道に自ずと向かい成るだろう”と言うのです。そして、”その理解を日々増やせ。さすれば、より「深い心根」が得られるであろう”と説いています。
更に、キリスト教は、”人は悪の子供”(罪深き子)と設定していますが、仏教では”悪の子供(罪の子)であるも普通であり悪(罪)と拘るな”であります。それが「人」だと説いています。
これが私の若い頃にキリスト教の説法を4年間聞きに行って知ったポイントでした。
多少の自分勝手な歪みもありますが、なんとなく心の底から納得できないところがありました。そして、説話の解読が”何か攻撃的である”と印象を持ったのです。
これは多分、”民族的な遺伝子の違い゛では無いかと思いました。
そこで、質問をしました所、帰ってくる答えは、何か頭に引っかかるもので、”日本民族のレベル(民主主義のレベル)が低い”のであるかのニュアンスの答えと感じ取りました。
これは当然の答えでもあるかも知れません。当時は、まだ日本は戦後15年程度しか経っていませんし、復興途中ですのでアメリカ人から低く観られていたと考えます。我々のほうがそう云う風に受け取っていたとも考えられますが、やや、彼らの心中にその様な心を一部に宿していた事も事実でしよう。
しかし、中に仏教を勉強していた牧師というか宣教師が居て、仏教との違いを認めていたのも事実でした。その違いは「蛮な宗教」として排除していた言葉を説話の中で聞き及んでいました。同席していた友人たちと牧師との間で、議論になったことを覚えています。
しかしながら、後に仏教も含めて正しく勉強し直した結果は、次の様な事柄でかなり近い調査結果でした。
確かに、その調査結果の違いは、次のような事でした。
1 他宗を少なくとも先ずは強く排他している事。
2 教えがかなり強引である事。
3 キリスト個人を神扱いにしている事。
4 兎に角にも、”先ずは信じよ”である事。
5 人は全て悪の子供であると否定する事。
6 中間的考え(柔軟性)は無い事。
7 全体が闘争的な発想に成っている事。
8 特定者(若い者)には受け入れられ易い合理的な教えに成っている事。
9 先祖に対する考えは全体として希薄である事。
10「民族的」と言う考えを認めていない事。
本来、仏教では、”宗教は「万教帰一」である”と説いています。少し違い過ぎているという感じがしました。
そこで、上記の事に付いて、その違い際を出す目的で論じてみたいと思います。
そうする事でその違いの全体の論所が見えてくるのではないかと思います。
1番目の事です。(他宗を少なくとも先ずは強く排他している事)
どの宗教の教義も、良く似た傾向がありますが、仏教では、他宗を強く否定することは有りません。
「万教帰一」と説いているくらいですから、少なくとも、仏教のどの宗派もほぼ同じ教義です。
しかし、はっきりとキリスト教は仏教(他教)を否定しています。世界の宗教はキリスト教しか存在し得ないとも云っていますから、ここの排他的なことが明確な違いの一つです。
最近はトーンを落としていると聞きますが、紛争地での世界のキリスト教の布教の行動を観ると変わっていないと思えます。
本来、宗教は少なくとも「人」を救う事を目的として存在しています。これはどの宗教も同じ筈です。
その救う手段(教義)が異なると言うことだけですが、然し、突き詰めれば人を「救う理由」は、どの民族でも「悩み」としては同じである筈です。だから”キリスト教以外には存在しない”は疑問です。
確かに、夫々の宗教は、その「民族の発祥をベース」に成っていることは確かですので、そこで起こる「民族の生活程度」や「遺伝子的な民族の悩み」のそれから来る悩みの大小はあっても、「救う理由」は同じです。
当然、その「理由」に対する「教え」は突き詰めると、同じ程度のものになると考えられます。
しかし、ここが「違いの原点」になるのでしょう。その理由の大小に対して、何処の部分に重点を加えた教義にするかで異なってくる事は否めません。
しかし、否定する理由としては問題です。
現に、キリスト教、ヒンズー教、イスラム教、ユダヤ教、仏教、儒教、等の宗教で、例えば、キリスト教はローマ時代の乱れた民衆の不満をベースになっています。ユダヤ教は「ジプシー民族」をベースに出来ていますし、イスラム教はその定住する位置と多民族の構成でその置かれている立場(アジア民族とヨーロッパ民族の混血族)から生まれたものです。
従って、「戦い」をベースとして居るために、宗教として最も「戦い」を排除しなければならないのに唯一教義として「聖戦」を認めています。
宗教ではどう考えても「聖戦」は疑問です。民衆の手段としては考えられるが。
この様に、夫々の発祥をベースとしています。
しかし、仏教は、インダス文明として多くの宗教が生まれた中で、小さく拡がりながら中国より日本に司馬氏の始祖の仏師の司馬達等が最初に私伝したものであり、古来より居た神道の物部氏と、百済から渡来した仏教の蘇我氏との戦いの結果、国政として仏教を導入したものであります。正式には後の594年の「仏教興隆の詔」(仏、法、僧)であります。
仏教は、日本以外での成り立ちがどうであろうと、日本での伝承は、奈良時代の「天神文化」として一つの国政上の理由から発達したものであります。
つまり、神道と仏教との「融合文化」で仏教は成育したものであります。
これが奈良期の「天神文化」であります。
「天神文化」、つまり、「人の悩み」を基とした教義というよりは、人間としての有るべき姿、即ち、「信義、道義、徳義」を求めて、そこから人としての悩みを排除しようとした教義であります。
「般若心経」は真さにこの「心経(こころのみち)」であります。従って、その目途して、必然的に他教の教義を否定する必要性は考えられないし、人の有るべき姿、即ち、生きる「道」を説いている宗教であります。
布教に際する教義の説法は、他国のビルマやタイの仏教との違う点は、神道と仏教の融合文化(天神文化)の末に生まれた教義でありますから、独自の宗教といえます。
「武士道」もこの融合文化の仏教と神道の融合教義から生まれた「教道」であります。
事程左様に、融合であるが為に他宗を否定するに至りません。
しかし、キリスト教等はその発祥の基が異なることに成りますので、その布教は必然的に他教を肯定する訳には行きません。ここが、教義の前提の大きく違う点に成ります。
次は2番の事、即ち、教えがかなり強引である事。に続きます。
Re: 先祖と宗教(行為と行動の逆進性-主題3)
副管理人さん 2007/10/13 (土) 08:22
設問
1「呪いの意」 (般若経の一説:仏教は何故呪うのか)
2「時間の逆行性」 (時間は逆行しないのだから仏教の仏=先祖は疑問)
3「行為と行動の逆進性」 (先祖が成した行為と行動は逆行しないのだから「仏」は疑問)
4「キリスト経の教え」 (仏はキリスト教の教えと異なる)
5「仏教とキリスト経の妥協の余地」 (根本的な違いの考察)
以上に付いて私観を述べたいと思います。
長い論文になりましたので、ゆっくりとお読みください。
尚、人生観と宗教論ですので、硬い話と成りますが、ご興味のある方の論文と成ります。
出来る限り科学的な論所を以って論じていますので、全てが抽象論とは異なります。
青木氏を研究する中で、”先祖とは何ぞ”の疑問を解く過程での得た私観です。
では、次をお読みください。
今度の第3の設問は「行為と行動の逆進性」(先祖が成した行為と行動は逆行しないのだから「仏」=先祖は疑問)です。
設問の理由説明
第3の設問のこの[行為と行動と逆進性」、つまり、”先祖が成した「行為と行動の結果」(実績)が変化しない(その影響力は無くなる)。又、時間に対しても逆行しない、又は、変化しない。だから、「先祖」が彼世で「仏」に成って、その「行為と行動の結果」を続けて持ち込んで、その影響力を以って子孫を導くという「力」のその基に成るものは無い筈だ。故に、仏教で説く、「先祖」が「仏」になって子孫を導くと言う事はあり得ない”と言う事に付いてですが、私は次の様に考えています。
結論からしますと、”行為と行動は逆進する”と結論付けたいのです。
但し、この事は、”現世に於いてのみは通常はない。”であります。しかし、他次元的な関連として思考するなら、つまり、宗教的な思考原理からすると、”逆進する”。であります。
そして、この現象は、”現世に於いてある条件下で存在する。”であります。
矛盾している様ですが、実はその立証は困難であるからであります。
恐らく、多くの方はこの現象に一度は必ず出くわしていると思います。そして、それが不思議な事として頭の記憶の中にしまっている事だと思います。
「行為と行動」の現象(流)
その不思議な事を引き起こす「行為と行動」の現象とは、(その逆進性とは、)私は「流」(ながれ)という摩訶不思議な現象だと思うのです。
皆さんは、この「ながれ」「流」と言うものを経験していると思います。特に人生経験を深くして歳をとられた方なら承知していると思います。そして、その受け入れの心得なるものを会得されているのではないでしょうか。
つまり、”この様な「流」の時は、この様にするのだ”と、特に、「古からの言い伝えの教え」では”静かにしているのだ”が一般的ではないかと思います。然しこの「戒め」も今では全く聞かれません。
正しく真剣に「行為や行動」をしても、その「結果」がどうしても「行為や行動」に一致する事の答えに至らない。
すればするほどに、”何か見えない大きなものに流されていて、決められた方向に逆進する。”
そして、”結果は本来あるべきものとして得られないで、何時か、何処か、誰かで決められた方向にたどり着いてしまう。”という現象を経験していると思います。
六十数年の間に私にもこの体験を何度かありました。そして、その体験中はその「ねらいの意識」対して違う答えが頭の隅の方でなんとなく見えているという何れも不思議な経験でした。
「行為と行動」の現象(流)力<「静かなる心根」=悟り(理解)=(1と2の設問の理) (A)
この「流」の強さの力(押し流される力)は、1と2の設問でも記述した「静かなる心根」即ち、「悟り」(理解)を獲得すれば、”その「流」の力に勝り、「ねらいの意識」に対して、その差を理解させて、「神仏」が導く方向の意が見えてくる。”という事であります。
「流」の現象の正体
では、これは一体何なのでしょうか。
私は、これが、「他次元との連携による力が働いての結果」と観ています。
普通は、意識しないでいれば”何の事”と成るでしょう。
しかし、その”何の事”の生きる姿勢ではなく、世の成り立ちを正しく理解すると言う意識が現世に生きている人に生まれれば、見えてくる現象であると云う事です。
つまり、自分の「行為と行動」とは違う「ながれ(流)」の方向になる「他次元性の力」が、この「逆進」の現象を意味し、その「違う結果」の「最終の形」が、「相反する形」になる事から、現世に現れる「逆進の形」であると考えられます。この「逆進の形」が運命的で、神仏がその様に仕向けたとしか考えられない結果になる現象です。
本来、どんなに手を尽くしても「他次元性の力」の力が働き「1+1]=2と成らないこの現象です。
「ながれ(流)」=「逆進の形」 (B)
「数理的不思議」
例えば、論理的数理的であるのに、「1*1」=1と成る様に。「1」は有量です。然りながら、「1」と言う量を持つのに、しかし、結果は基の[1]なのです。この有量の二つのものを掛け合わせれば本来の意識では増量と成る筈です。「2*2」=4の有量のものを掛け合わせれば増量する様に。(数と量の数学定義を無視して観ると)つまり、「1」の次元上で起こる1次元と1次元の積では2次元と成らない何か間尺に合わない現象です。
ここには「固定意識」(固定観念)という「1次元的感覚」が存在する所以から起こる現象で、人間の「錯誤意識」がこの数式を理解できない「破目」に追い込んでいるからです。そのために数学では、この錯誤を防ぐ為に「但し書き」を「定義」として「前置き」をします。
「固定意識」(固定観念)=「錯誤意識」=「1次元的感覚」 (C)
「前置き」の消失
私は、人間は、この「前置き」に付いて、約千年程度の歴史の中で、漸次失われて来た「意識」であると考えています。
即ち、それは「他次元性」又は「現世と彼世」、突き詰めると「彼世の先祖」としての「但し書き」の「前置き意識」ではないかと考えているのです。
この「前置き意識」が無いが為に、「流」に流されていると錯誤しているのだと考えています。
本来は「現世と彼世」が有って、初めて「人の世界」なのだと考えています。
古の「先祖」はまだ「この意識」が多く持っていたのではないかと考えています。
「人の世界」とは、現在では「現世」(+)だけとされている気がします。
故に、+の片方から観た結果の判断と成ってしまっているのだと思うのです。そして、「違う結果」と認識してしまっているけれど、しかし、(+)と(−)の世界から見た結果の判断が本当は正しいのだと思うのです。
ある問題が起こったとします。その時、裁定者は両方の意見を聞き正しい結論の裁定を下す様に導きます。
ところが、「流」のこの他次元性に及ぶ問題が起こると、前置きの消失意識と固定観念がある為に、それを裁定する自分には一次元的感覚の錯誤意識が起こり、「違う結果」と受け取ってしまうのだと考えます。
それは(−)の意識がある事で「当然の結果」と受け取れるのだと思うのです。
故に、「当然の結果」と受け取れるには、「静かなる心根」(設問1と2)にて(−)の消失した意識を取り戻す事が出来るのだと成ります。
だから、「昔からの戒め」として”静かにしているのだ”と成ったのだと考えます。
「行為と行動」+「前置き意識」(消失意識)=「人の世界」=「現世と彼世」 (D)
「違う結果」+「静かなる心根」=「当然の結果」 (E)
「違う結果」−「錯誤意識」=「当然の結果」 (F)
「迷信と混同」
その証拠に私の小さい頃には、この事(現世と彼世との意識)に関わる「行動と行為」は、未だ周囲の年寄りや自分の行動に付いて日常の生活の中に沢山あり、何の疑問も感じないで受け入れていた記憶がまだ有ったと認識しているのです。
ところが、時代と共に付加価値が増えて必然的にその必要性の無さから消えうせて行ったのではないでしょうか。
そして、今や「迷信」と言うものの中に、この意識が取り残されて現在では殆どなく成っている感じがします。
むしろ、真偽は別として、「他次元性の戒め」としての「迷信」と言う言葉さえも聞かなくなり無く成ってしまった感じがします。若い者に「迷信」と言うと”それ何”と言われる始末です。
概して言うと、この「消失した意識」とは「迷信」であった筈です。
この「他次元性の意識」([消失した意識」)として余りに生活や宗教会の中で多く存在させた為に、中には不適当なものも入ってしまった結果、「迷信」とレッテルを貼られてしまったのではないでしょうか。
まだ、山里の田舎に行くと、この「迷信」を他次元性の意識として生活の中で生かしている筈です。
例えば、烏が執拗に鳴くと「不吉」なことが起こるとか、黄色の夕焼けが起こると「自然災害」が起こるとか。夜につめを切ると人が死ぬとか、この様に生活に密着した人の行為と行動に警告(戒め)を他次元性を絡めて発している「迷信」なるものがあります。
先祖が遺した他次元と繋げた「諺」(ことわざ)や「口伝」等の一部もこの「消失意識」ではないでしょうか。
これも「迷信」と共に核家族化で消えてしまったのでしょう。その意味で「先祖」の遺した無形遺産は大きいと認識しているのです。
自分の人生に於いて、より「当然の結果」として理解できる様に「先祖を知る事」をテーマに長年努力を積み重ね試みた一つでもあります
兎も角も、その過程で、私はこの「消失した意識」が「拘った固定観念」を生み出し、強くして、結果として社会の乱れを生み出し、人の思考を歪ませて、根底から(+)の現世からのみの視観となってしまっていると考えたのです。
(現世と彼世との意識)=「迷信(混同)」=「他次元性の戒め」=「昔からの戒め」 (G)
「相対の原理」(現世と彼世)
もし、「相対の原理」がこの意識問題に適用されて真理とすると、「現世」を「+の世界」で、「彼世」は「−の世界」として考える事が出来る姿が、人本来の基本思考である筈です。この世のものが全てこの「相対の原理」で成り立っていると言う事実から考えると、この思考が時代と共に消滅した代表的な思考ではと考えます。
つまり、「思考に偏りが出来た人々」の我々が「−の世界」に関わる事が起こると、これを摩訶不思議と観てしまっているのではないでしょうか。
そして、そこに他次元性の意識消失の結果に依って生まれた「拘りの意識」が多すぎると、それが余計に「摩訶不思議」となり「違う結果」と観てしまうのでしょう。
つまり、我々現代人は残念ながら「悟り」(理解)が小さいと成ります。
この事から「相対の原理」が真理である限り、バランスある思考を保つ為にも、「彼世」の「−の世界」の意識を持つのが普通ではないでしょうか。
「違う結果」+「拘りの意識」<=「摩訶不思議」 (H)
「現世」の「+の世界」=「相対の原理」=「彼世」の「−の世界」 (I)
以上このことを念頭にして、本論を展開したいと思います。
そこで、次の様に解りやすく数式論を伴い更にこの観念論を進めてみます。
本論
(A)から(I)の数式定義を念頭にご理解ください。
まず、定義を数式で現すと次のように成ります。
「流」=「行為と行動の逆進」を仮定する 0
「行為と行動の力」の結果<「他次元性の力」の結果 1
「行為と行動」の形<>「他次元性の逆進」の形 2
と言う事に成ります。
「逆進の信憑性」
「呪い」や「時間の逆行」でも記述しましたが、明らかに現代の医学では解明がされていない現象の「2つの器官」と「2つの脳波」の存在でも判る様に、「何かの力」=「他次元性の力」が働いていることは明らかで、それを成す器官が人間に持っているという事実を鑑みると、この「行為と行動の逆進性」も完全否定は出来ないものと考えます。
数式で現すと次のように成ります。
「流」=「行為と行動の逆進」=「2つの器官」と「2つの脳波」の働き 3
「何かの力」=「2つの器官」と「2つの脳波」の働き=「流」の力=「他次元性の力」 4
ただ、それは、現代医学では完全に解明されていない範囲である事だけの否定でしか有りません。
そして、むしろこの不可思議な現象が、「2つの器官」「2つの脳波」の医学的証明と、古代史実からも「状況証拠」として認められて居り、むしろ、「否定方向」ではなく「証明される方向」にあると言うことです。
だとすると、必ずしも、現世に於いては、”「原則進行性」の前提ではあるが、「他次元性逆進」もあり得る”という考えに我々の思考として(A)から(I)のことも踏まえて、現代人として到達させて置く必要があるのではないでしょうか。
ところが、現代人は「時代の付加価値の増加」に伴い、必然的に、この「拘り」の心を多く強くせざるを得ず、「多元性の意識」と「静かなる心根」を維持するに難しい情況と成っているものと考えられます。
「拘り」説法の意
そこで、必要なのは”「原則進行性」の前提ではあるが、「他次元性逆進」も有りうる”とするこれが、仏教でいう現世に生きる人としての「思考姿」、つまり、”「色不異空、空不異色」「色即是空、空即是色」”の「否拘りの説法」(設問1前説)であると考えます。
(参考 設問1から転写)
では、この一節をどの様に理解したら良いかと言うことですが、私は次の様に理解しています。
「色」即ち、この世のあらゆる物質は全て色(いろ)を有します。故に、その「色」(いろ)のある環境、つまり総意としての「現世」であると理解出来ます。
数式で現せば、「色」=「現世」(うつせ)だとします。
「空」即ち、物質として存在しない空(から)の世界とし、色(いろ)を有さない世界だから、つまり総意としての「彼世」(かのせ)であると理解できます。
数式で現せば、「空」=「彼世」(かのせ)だとします。
そこで、「色は空と異ならない 空は色と異ならない」、故に「色は空であり、空は色である」と説いています。
つまり、言い換えると「現世は彼世と異ならない 彼世は現世とは異ならない」、故に「現世は彼世であり、彼世は現世である」と成ります。
究極の大意の数式で現せば、「現世=彼世」であるとします。
つまり、、「現世=彼世」法の「理」は、”物事に色があるから無いからとどうのこうのと言い立てるな、空だから無いからと騒ぎ立てるな”と言っていると思います。
言い換えれば、究極は”「物事に拘りすぎるな」”となるのではないでしょうか。
つまり、以上の参考での般若経一節の私説の通り、換言すれば、”静かなる心根(悟り:理解)を得る事、”即ち、”「他次元性の失われた意識」を取り戻せ”と成るのではないでしょうか。
ところが、上記した「他次元性の失われた意識」が易々と戻らない為に、かなり強い力で、「拘りという意識」のバリヤーを取り除かなければ、「流」が見えないものと成ってしまうと解釈できるのではないでしょうか。
仏教でのこの「説法の意」としては、漸次消失して行った何時の世も、現世の人の「意識の消失」の経緯から、「人の道」(心の経:みち)として説いている「般若心経」一節は強調しているし、この上のニ行を意味していると思うのです。
「流の正体の解明」
このことでは、”何のこと”となると思います。この「流の正体」が解らなければ”如何に”と成りますので、その「流」(ながれ)を具現的に説明したいと思いますが、人それぞれの種々「流」の経験は異なると考えますので、「流」の内容に付いては(異文ともなるので、)読者の経験談に委ねたいと思います。その上で次の一般論でご理解ください。
「逆進の現象」
この様に、”兎も角も、先ず、1 本人の意思や周囲の意思に反して、その方向とは次第の結果は別の方向に進んで行く。
次に、2 あがくと更に進むと言う現象が起こる。
更に、3 「環境」が整うと今度は、逆に境遇も本人の意思に関係なくどんどんとよくなる。
そして、4 最後に、被者があれば、(天罰が降るが如く、)本人外の周囲の「環境」はそれなりに悪くなる等の現象が起こる。”
この「4つ現象」の変化が一般的なものとなると思います。そして、この「4つの変化」には人の特長から「強弱」が起こります。
この「強弱」が人の「流の差」と成るのだと思います。
数式で表現すれば、人の「強弱」=「4つの現象」=「流の差」 4-1
これが「行為と行動」に付いて人それぞれの「流の結果」が異なってしまう「逆進現象」と考えます。
「逆進の起源とメカ」
この様に、何か附合一致して、これだけの「行為と行動」に対する「環境」を相対的に変える事や、整えることがバランスよく出来るのは、この現世の出来事ではない事と思われ、且つ、確かに何らかの力が他次元から引き起こされいるとしか考えられません。
この場合は、「流」では良い方向(幸せ)に向かう場合もあれば、この逆の例の「戒めを受ける事」(苦労)も世の中には沢山あるだろうと思います。
さて、上記の事で、この「差」は、どこかで繰られているのかと言う疑問が湧きます。
私は結論から言うと、”当事者のこの世に対する「理解」の差で異なる”と云う感じがするのです。
数式で表現すれば、「流の差」(4-1)={当事者のこの世に対する「理解」の差}で異なる。 4-2
しかしながら、どんな場合でも、「神仏」との「連携」が成されるとは限らないのではと思います。
それは「仏」が言う「ある理解」、又は[悟り]の状態を得ている時に起こると考えられます。
そして、それをキャッチする器官は、「2つの器官」であり、その「理解」の差は「2つの器官」の”センサーレベル”によると見られます。
この「ある理解」(悟りの状態)とは、次の過程(イからホ)を経て得られると思います。
イ 「心」を「拘り」から「脱却した差」による時に起こります。
数式で表現すれば、「ある理解の差」(悟りの状態)=「脱却した差」(拘りの心)=センサーレベル 5
ロ そして、本人の「無我」の「心」の「よどみ」が失せた事による時に起こります。
数式で表現すれば、「ある理解」(悟りの状態)=「無我」の「心」の「よどみ」=0 6
ハ この2つ状態(5、6)の何れかに成った時、静寂にして最高の感度を得え高まります。
数式で表現すれば、(5、6)=MAX(センサー) 6-1
ニ この「2つの器官」の本人のセンサーに、先祖が送り届ける波長が合致します。
ホ これ(イからニ)を経て、得て、この時に「神仏」(「先祖」)は、手を差し伸べてくるのではないかと考えます。
数式で表現すれば、「2つの器官」(センサー)=先祖の波長=神仏の加護 7
次に、脳医学的な過程の検証として次の様になります。
「論理的検証」
人間には、脳幹という電池の芯に相当するものがあり、これには地球をマイナスとしてその上に存在する物質はその高さのレベルに相当して電位がかかり、その電位は脳の中心にある脳幹のレベルを変動させる事が出来る仕組みになっていて、これに依って電流が流れて、脳神経細胞を経由してキャリパー(Naイオン)の液に到達して、電子が液イオンに乗って継電してその反対方向に電流が目的の所まで流れて脳が働く仕組みと成っている。
この仕組みはその「神経(心経)の集中力の差」にて脳幹温度は高まると電位は高まり比例的に電流値は変化する。
この高まった電流が流れた時、「2つの器官」のセンサーレベルもこの「集中力」によりこの差に比例して高まる。
これに添って同レベルで「2つの脳波」も動作する。
この「2つの器官」と「2つの脳波」とは連動連携しているのではないかと予測する。(設問2記述)
そして、その「心」への信号は、高レベルの前記の「2つの器官」を使って、本人や周囲の関係者に作用を及ぼす事に成る。
この及ぼす力はこの時の関係者の「理解」と物事の「拘り」の如何に関わるのでは無いかと考えます。
そして、そのセンサーレベルに達していない場合には”届かない”となるのではないかと考えます
数式で表現すれば、集中力の差=電流値の差=センサーレベルの差 A 8
数式で表現すれば、Aの差=「2つの脳波」の差 B 9
数式で表現すれば、Bが高い(HIGH)とき=他次元との連動 C 10
上記の数式の場合のCのLOWでは、「行為と行動」に対する「環境」」と「2つの器官」のセンサーレベルが合致に至っていないから「他次元との連動」を起さないと考えます。
これは、”「親、先祖、仏、神」を敬い養護する姿勢の有無の如何の差”に依ってセンサーレベルが定まるのだろうし、又、、「行為と行動」に対する「環境」」に合致し、このセンサーレベルが受けられる関係者が居た場合は違う展開が起こっていただろうと観られます。
ところが、その展開に付いて、普通、現世に生きる者は「勧善懲悪」と期待するが、前提として、必ずしも神仏は「勧善懲悪」ではないと私は考えています。
「勧善懲悪」の3つの式(11、12、13)
この事に付いて仏教でも、次の様に説いています。
”正しいものは常に正しいという事ではない””悪いものは常に悪いとは限らない”はと説いています。
むしろ、禅宗などは、更に、突っ込んで、問答では”悪いものは正しいと云う事もある””正しいものは悪いと言う事にもなる”と云っています。
そして、それは”「三相」(人、時、場所)の如何に関わる”と説いています。
参考 この事は上記した”結果は本来あるべきものとして得られないで、何時か、何処か、誰かで決められた方向にたどり着いてしまう”を裏付けています。
そして、更にこの状況(良悪、正否の判定)は”社会の付加価値の変化にて進む”と説いています。
数式で表現すれば、 正しいもの=悪い 悪いもの=正しい 11
数式で表現すれば、 正しい=<「三相」(人、時、場所)>=悪い 12
数式で表現すれば、(良悪、正否の判定)の変化(進化)=社会の付加価値の変化(進化) 13
判りやすく云うと、現代のように、社会が近代的(科学的)になり、付加価値が増え、原始の社会の「原理原則」が成り立つ易い「環境」と比して、社会構造が複雑になり正しさが異なることが起こるから、仏教では”正しいから正しいと拘るな”とする一つの理由になります。
”何時の世も「良悪、正否」とする社会環境は変化する”ということであります。
「勧善懲悪」の「3つの説」(abc:141516)
この「勧善懲悪」を仏説で考えると、次の様になると考えます。
先ず、(a)”全て正しい者は「神仏」からの常に正しい適切な処遇を受ける”とは思われないのです。
そして、(b)”「先祖」が考える多くの要素を踏まえ未来過去の要素を配慮した形に持ち込む”と考えます。
更に、それは、(c)”「4つのみ」から脱却した「仏」の成せる業技である”と思います。
上記「勧善懲悪」の「3つの説」(abc)が成り立たなくては、それでなくては、人間であり、仏ではありません。
つまり、「仏」が「4つのみ」を脱却するとはこのことを意味すると考えます。
数式で表現すれば、「勧善懲悪」の「3つの説」+「3つの式」=「仏」(「4つのみ」を脱却) 13-1
「脱却の意」の4原則
数式で表現すれば、仏(先祖)の判断<>正しい適切な判断 14
数式で表現すれば、仏(先祖)の判断=未来過去の要素を配慮した形 15
数式で表現すれば、仏(先祖)の判断=仏」の成せる業技−「4つのみ」 16
数式で表現すれば、仏(先祖)の判断>人間の領域 17
では、「脱却の意」の4原則で行われない「勧善懲悪」とは、その辛い「しがらみ」の中で、人間が考えた切なる願望であるに過ぎないし、それを仏、神が成してくれるものとして勝手に考えている事です。
つまり、仏教が否定する「ご利益信仰」に過ぎないからです。
「ご利益信仰」を宗教と考えている人が大方であるが、「ご利益信仰」は「宗教」ではありません。単なる「人間のエゴ」に過ぎないと考えています。
「ご利益」とは「静かなる心根」を得て、結果として「間接的に得られる幸せ」です。
それでなくては、仏前に手を合わせて、打算を願い出れば、簡単に得られれば、全て誰でも何処でもいつでも得られるという事に成ります。
数式で表現すれば、ご利益=「静かなる心根」=間接的な結果幸せ 17-1
もし、それが叶うのであれば、悩みなどは直ぐに仏前で手を合わせれば叶う事に成り、このするところの意味は、結果として宗教はいらないと成りますし、宗教は当初より存在しません。当然仏壇も寺も神社も生まれなかった筈です。
数式で表現すれば、「勧善懲悪」=「ご利益信仰」=「人間のエゴ」>「宗教」 18
神仏のそれは、そんな人間が考える次元の範囲であるとは思わないのです。
もしそうであるとすると、それは「神仏」では有りません。人間そのものであります。つまり、人間の「4つのみ」を持っている「神仏」となってしまう。そんな事は有り得ない事です。
もし、この「4つのみ」から脱却した「仏」であり、「仏」から遊離したの「神」であるなら、「神」が考える最も良いとする形に持ち込む筈です。
その形の「良悪、正否」の事は、現世に居る我々には理解できない範囲にあり、「三相」に関わるとしか判らないのであります。
「神仏のみが知る」であります。
数式で表現すれば、「良悪、正否」の事=「神仏のみが知る」=社会の付加価値の進化 19
だから、人は長い人生の中で、日々より多く悟り理解して、「神仏のみが知る」の範囲の僅かでも読み取ろうとするのであります。
従って、上記する「流」は多くのステップで構成されています。そして、人間が考える「流れ」の一ステップを捉えて「良悪、正否」を評価しても、全体を見た中で判断しなければ、「神仏」が決めることは、人間の範囲を超えている故に、正しい答えは出ないと考えます。
故に、(A、B、C、D、E、F、G、H、I)の前提下に於いて、「行為と行動の逆進性」は、現世に於いては通常の「流」の中では無いとし、しかし、「神仏」又は「先祖」が看た他次元的現象(0から19)が起こった場合に於いて、「2つの器官」「2つの脳波」を媒体として「神仏」加護の下で「逆進性」は起こると成ります。
以上、論理的に数式論にすると、人間には、消失した意識が多く起こり、遂には多くの思い込みが出来て、結局は拘りが強くなり、究極は絶え難いエゴが出たとする局面が私には見えてきます。
皆さんは如何でしょうか、現在、何か消失して居ると感じていないでしょうか。
一度、この「行為と行動」の論で振り返ることも必要ではありませんか。
参考(行為と行動の逆進性の数式論の記述)
「行為と行動」の現象(流)=「静かなる心根」=悟り(理解) (A)
「ながれ(流)」=「逆進の形」 (B)
「固定意識」(固定観念)=「錯誤意識」=「1次元的感覚」 (C)
「行為と行動」+「前置き意識」=「人の世界」=「現世と彼世」 (D)
「違う結果」+「静かなる心根」=「当然の結果」 (E)
「違う結果」−「錯誤意識」=「当然の結果」 (F)
(現世と彼世との意識)=「迷信(混同)」=「他次元性の戒め」=「昔からの戒め」 (G)
「違う結果」+「拘りの意識」<=「摩訶不思議」 (H)
「現世」の「+の世界」=「相対の原理」=「彼世」の「−の世界」 (I)
数式で表現すれば、「流」=「行為と行動の逆進」を仮定する 0
数式で表現すれば、「行為と行動の力」の結果<「他次元性の力」の結果 1
数式で表現すれば、「行為と行動」の形<>「他次元性の逆進」の形 2
数式で表現すれば、「流」=「行為と行動の逆進」=「2つの器官」と「2つの脳波」の働き 3
数式で表現すれば、「何かの力」=「2つの器官」と「2つの脳波」の働き=「流」の力=「他次元性の力」 4
数式で表現すれば、人の強弱=4つの現象=「流の差」 4-1
数式で表現すれば、「流の差」(4-1)={当事者のこの世に対する「理解」の差} 4-2
数式で表現すれば、「ある理解」(悟りの状態)=「脱却した差」(拘りの心)=センサーレベル 5
数式で表現すれば、「ある理解」(悟りの状態)=「無我」の「心」の「よどみ」=0 6
数式で表現すれば、(5、6)=MAX(センサー) 6-1
数式で表現すれば、「2つの器官」(センサー)=先祖の波長=神仏の加護 7
数式で表現すれば、集中力の差=電流値の差=センサーレベルの差 A 8
数式で表現すれば、Aの差=「2つの脳波」の差 B 9
数式で表現すれば、Bが高い(HIGH)とき=他次元との連動 C 10
数式で表現すれば、正しいもの=悪い 悪いもの=正しい 11
数式で表現すれば、正しい=<「三相」(人、時、場所)>=悪い 12
数式で表現すれば、(良悪、正否の判定)の変化(進化)=社会の付加価値の変化(進化) 13
数式で表現すれば、「勧善懲悪」の「3つの説」+「3つの式」=、「仏」(「4つのみ」を脱却) 13-1
「脱却の意」の4原則
数式で表現すれば、仏(先祖)の判断<>正しい適切な判断 14
数式で表現すれば、仏(先祖)の判断=未来過去の要素を配慮した形 15
数式で表現すれば、仏(先祖)の判断=仏」の成せる業技−「4つのみ」 16
数式で表現すれば、仏(先祖)の判断>人間の領域 17
数式で表現すれば、ご利益=「静かなる心根」=間接的な結果幸せ 17-1
数式で表現すれば、「勧善懲悪」=「ご利益信仰」=「人間のエゴ」>「宗教」 18
数式で表現すれば、「良悪、正否」の事=「神仏のみが知る」=社会の付加価値の進化 19
一般的「4つ現象」の変化
1 本人の意思や周囲の意思に反して、その方向とは次第の結果は別の方向に進んで行く。
2 あがくと更に進むと言う現象が起こる。
3 「環境」が整うと今度は、逆に境遇も本人の意思に関係なくどんどんとよくなる。
4 最後に、被者があれば、(天罰が降るが如く、)本人外の周囲の「環境」はそれなりに悪くなる等の現象が起こる。”
「ある理解」(悟りの状態)過程(イからホ)
イ 「心」を「拘り」から「脱却した差」による時に起こります。
数式で表現すれば、「ある理解の差」(悟りの状態)=「脱却した差」(拘りの心)=センサーレベル 5
ロ そして、本人の「無我」の「心」の「よどみ」が失せた事による時に起こります。
数式で表現すれば、「ある理解」(悟りの状態)=「無我」の「心」の「よどみ」=0 6
ハ この2つ状態(5、6)の何れかに成った時、静寂にして最高の感度を得え高まります。
数式で表現すれば、(5、6)=MAX(センサー) 6-1
ニ この「2つの器官」の本人のセンサーに、先祖が送り届ける波長が合致します。
ホ これ(イからニ)を経て、得て、この時に「神仏」(「先祖」)は、手を差し伸べてくるのではないかと考えます。
数式で表現すれば、「2つの器官」(センサー)=先祖の波長=神仏の加護 7
Re: 先祖と宗教(時間の逆行性−主題2)
副管理人さん 2007/10/09 (火) 23:07
設問
1「呪いの意」 (般若経の一説:仏教は何故呪うのか)
2「時間の逆行性」 (時間は逆行しないのだから仏教の仏=先祖は疑問)
3「行為と行動の逆進性」 (先祖が成した行為と行動は逆行しないのだから「仏」は疑問)
4「キリスト経の教え」 (仏はキリスト教の教えと異なる)
5「仏教とキリスト経の妥協の余地」 (根本的な違いの考察)
以上に付いて私観を述べたいと思います。
では、「呪いの意」 (般若経の一説:仏教は何故呪うのか)に続いて次の2番目の設問に入ります。
2「時間の逆行性」 (時間は逆行しないのだから仏教の仏=先祖は疑問)
普通、時間は逆行しません。
しかし、宗教では逆行はすると言う説法が多くあります。
前問の「呪い」のところで、「4つのみ」から開放された躯体の持たない魂の「仏」は、死後1週間は「魂」として現世に残るとされています。
そして、この魂は「躯体」を持つ現世の者に語りかけると説いています。
実体験
実は、私の両親と親族の3度の葬儀の後に、この現象に遭遇したのです。
この事の話は、現実にも近隣でも良く聞く話で、叔父も同じ経験をしていると聞いていましたので、まさかという感じでした。確か叔父も周りの人には信じてもらえなかったといっていた事を覚えていて、実は私も経験して驚いたものでした。
葬儀の後に、親が住んでいた仏壇の母屋に入ると、かなり大きい声で話し掛けられるようになんとなく語りかけて来る話し声が耳に入って来たのです。その語意ははっきりとはわかりません。この現象は長い時間で暫くすると止まります。その現象は矢張り1週間続きました。
話していることは確実なのです。周囲は明るい部屋です。方向もなんとなく判るという程度です。その声は父親であり、又母親であり、兄弟であるとする事もはっきりと判りました。
側には家族がいましたが、聞こえないと言いますが、周囲を見渡しても音のするものは有りませんし、家族は静かだと言います。外に飛び出してみても何もありません。理解し難い現象です。
この親族の葬儀の後の経験は3度もありましたので、2回目の時は、”あっ又だ。確かにある。”として、今度は慎重に、静かにして、何を云って居るのかを確かめようとしてみましたが、矢張りわかりません。しかし、印象として、家の事を託すようなことを話しているという直感が起こりました。
これは多分、自分の置かれている立場を自分が知っていて、それを直感として浮かんだのだ、或いは浮かび上がらしたと後で思いました。
それで、私の職業柄であり性格でもあるので、不明快な事では居てもたっても居られません。この現象に付いての調査を始めたのです。宗教的、脳医学的に起こる原因があるのかとの調査です。
そして、双方の点に確かにありました。
この時の現象では、先ず、「直感」に付いては、「仏」が超元的な方法で、私に「直観」を起させ訴えるという方法を採ったという結論に至りました。
仏教でも、脳医学でも、直接「言葉として話し掛ける」と言う連携ではなく、「直感」に訴えると言う方法が起こる事もわかりました。
この現象に付いては、「時間の逆行」の体現がないので、どのような体現として得られるかは判りませんでした。
私は現世に居ます。従って、時間は逆行することはありえません。しかし、躯体をなくした魂の「仏」は他次元(4次元)の世界に居ます。よって、この制限は有りません。
起こるとすれば、「仏」の方からの現象である事は理解できます。
「魂」のみとなった「仏」が話し掛けるとする事は、次元を現世に戻している事に成ります。そして、その現象を「直感」という方法にて出現したのです。
故に、他次元から現世に戻しているのですから、これは明らかに、「仏」の「時間の逆行」を示す現象です。
しかし、この「直感」に訴えると言う体現反応は、脳医学的に論理的に証明出来得る可能性があることが解りました。
(この事に付いては下記に記述します。)
論理的な可能性の理論
つまり、死んで躯体をなくし「魂」のみの「仏」となった者が、「過去の自分」を「現世に戻した」とする現象です。時間は戻っています。
ところがこの不思議な現象を「脳医学」で理解できるものがあるのです。
人間には、「野生本能」というものが存在し、その「本能」を司っていたのではないかとする未解明な不思議な「脳器官」が2つあるのです。
現在でも、あまり、進んでいない野生動物の一部に、この2つの器官が存在して作用している事が解っています。
それは、次の通りです。
「2つの器官」の説明
一つは、「第3の目」といわれるものです。
動物には主に二つの目があります。然し、元はどの動物にも「副眼」というものがあったとされていますが、その必要性が環境の変化で退化してしまったのです。
その「第3の目」的働きをする器官は、現在では、人間では、脳の中心の最下部のところにうずくまるように小指の先くらいの大きさで存在します(前松帯)。これは本来は「前頭葉」の額の上部に存在していたと考えられていて、これが、人間のように脳が進化した為に下に押しやられて、その目的が少なくなり、低下して退化したとされています。
人は、何かを真剣に考えるとき、全思考勢力を額の中央付近(目圏)に集中させて考えるという仕種をしませんか。多分、この時に次に記述する部位が働いているのだと思います。
古い奈良時代の仏像には額の上部に複眼を持った仏像がありますが、これはインダス文明の古来から人間にはこの複眼的機能がまだ比較的強く働いていたことを示すものではないでしょうか。
では、そこで、その事に付いて述べて、論理的にこの現象を解いて見ます。
論理的現象
この「第3の目」は現代では、感情的な予知や未来に対する予測の補助として使われている事までは解っています。
これ等の働きは、人間では左脳の学習的記憶データーから読み取り、無意識の深層思考原理の働きとして使われているために補助的な働き程度にしか使われていないのです。
特に、この「第3の目」のこの現象は、特に顕著に女性に観察さられる現象とされていて、感情的なインスピレーションの働きとして出て来ます。
女性の本来の「性の役目」に基づき「深層思考原理」の「3思考パターン」の「感情、勘定、妥協」により、この最初の脳の無意識の動作の「計画思考」の段階での「感情の補助」として動作されていると研究はされています。
女性の「性の役目」からその必要性は頷けます。
(女性の思考パターン:「感情的」に思考を計画して、「勘定的」に思考基準を取りまとめ、「妥協的」な判断で実行を動作させる。この働きを無意識のうちで瞬時に回想する脳の仕組みで、これを脳幹の後ろの左側の餃子程度の大きさの「脳陵帯」と云う所で管理されている)、
しかし、この器官の詳細は未知や将来の「予知能力的」、又は、「透視力的」な器官であると考えられており、猿人期の原始の時代に確実に強く動作していたのではないかとされています。
現在でもこの「第3の目」の器官をもつ生物や動物は沢山認められています。例えばトンボ等の複眼類や鯨類や原始猿です。
この「第3の目」が、人の脳の最下部には今でも存在することから、女性のインスピレーションの鋭さは透視的なものとして、この器官が理性と感情を司る「前頭葉」と連動して作用していると考えられています。
二つ目は、「未来予測脳」とするものです。
人の記憶機能を司る左脳内側の真ん中の付近の所に「線状帯」と云うところがあります。このところの真ん中あたりに「中紀帯」というところがあります。これも小指の先程度の脳器官です。
この器官は、男性にしか反応しません。
この器官は左脳にあるあらゆる学習的記憶データを駆使して推理し未来を予測予知する超能力部です。
男性は上記の「深層思考原理」は、無意識下に於いて、「3思考パターン」の働きとして、「理想、合理、現実」として、脳は無意識のうちで、連鎖的に瞬時に動作して、諸事に対処します。そして、行動の有意識の中でここれに基づき働きます。
これは原始の時代に、その「性」の定めにて周囲の環境に適応して生存競争の敵から身を守る為に、無意識のうちのこの深層原理のパターンに成っている訳ですが、この為には、周囲の環境の「予知」を働かさねばなりません。
現代に於いても同様ですので、男性にのみ「脳陵帯」に保護されて、この「中紀帯」は働きます。
しかし、まだこの部分の働きの具合は良く判ってはいません。
「現世」と「仏」の他次元との連携的働きをしていたのではとも考えられています。現代でも退化せずせに人の強弱あるにしても男性に働いています。
つまり、この「二つの器官」が、「現世」と「仏」との何らかの働きがあるのではと考えられています。
原始の時代では、人はこの器官が盛んに多次元的に働いていたと予測されています。
しかし、次第に社会の付加価値の増加とこの器官の働きを補助する科学進歩で退化していったと考えられます。
歴史史実
邪馬台国の卑弥呼は、「仏」「神」即ち、他次元との連携を司る体現者であり、他次元からの「神のお告げ」として、この前器官を強く反応させ持つ能力のある人であったと見られます。
その様な説を説く学者も多くいます。
多分、未だ3世紀前後の時代には、現代と違い、この感覚を退化させずに、強く働かせる能力を持ちえていたのではないかと見られているのです。その中でも卑弥呼は特に優れていたと考えられています。
というのも、当時、この邪馬台国では、指導者が会い立たず潰れていて、その乱れた騒乱の中、卑弥呼の巫女としての他次元からのお告げの能力が、周囲を圧倒するだけのものを持ちえていたからこそ、周囲は納得し、巫女の立場から、一躍、邪馬台国の王としての立場までになり得たのではないかとみられます。
ただ、でたらめに予言するのでは、この立場までにはならない筈で、直ぐにボロは出る筈です。
故に、この第3器官が大きく働いていたと考えられています。
多くのインカやマヤを始めとする大古代文明の全てには、この他次元との連携者や預言者が居て、大きな他次元との連携建造物を造り、そのお告げにて政治を納めていた事は学問的に定説ですから、この器官の働きは古代までは強く働いていたと考えられます。
むしろ、万事万象がこのお告げ(この器官を使った直感)であった事から、むしろ、退化させず、特に進化させていて、先鋭化していたと考えられます。
時代事の変化に合わせて、この器官の退化進化は変動していた事も考えられるのです。
自然を追い求める心の強さから、この「2つ脳器官」も、現代では、退化の中でも、やや進化のゆり戻しの時代に入っているのではないかと考えられます。
脳器官全般に於いて使わない器官は、退化が進み、使う器官は進化が起こるのは学説経験上の定説ですから、ゆり戻しはありうる事であります。
そして、当然に、個々の人には、この現象の強弱がある事も判っています。
経験の検証
多分、私の3度の経験は、この器官の動作が起こったとも考えられます。
それは、人の死を経験した直後の脳の働きが顕著に鋭敏になり、少し違っていたとも考えられます。よって他次元との連携が起こったと見られます。
当然に、この現象は他次元からも「魂」のみとなった「仏」から発せられた信号との連携であったのであろうと考えます。
だから、電波の如く周波数が一致しないと聞こえることは出来ないものとして、丁度、家の世話をしていた私との連携となったと理解しています。
当然、この「中紀帯」が人一倍に強いのかも知れません。その様な感覚がします。自分のことで客観性がないので恐縮ですが、記憶力や推測力は強い気がしています。(これが私の人生に良い結果を生むのではよいのですが)
人の脳には、他次元との連携の可能性を秘めたこの「二つの器官」が存在することは確かであり、動作している事も事実であります。
伝達手段
2つの器官が働いたとしても、この伝達手段が脳の中に無ければ、役には立ちません。
実は、更に、これを裏付ける他次元と繋げる脳機能があるのです。
つまり、「二つの器官」の動作を伝達する「情報伝達器官」と言うべきものです。
「2つの脳波」
人には、脳から発せられる「2つの脳波」があります。
それは、アルファ波とベータ−波であります。
ベータ−波は特異なときに発せられますが、このアルファ波が、上記の器官の高まり(精神的な集中力に影響)に依って強く顕著に発せられる事になり、他次元との連携が可能になるものとして考えられていますが、アルファ波、特にベータ−波は未だ充分な解明が進んでいないのが現状です。
脳死は、この脳波を捉えて停止状態になった時のパラメータとしています。
つまり、生きているときに何らかの経緯で一時に著しく強くなり(フラッシュバック)、他次元との連携が可能になり、上記の現象が起こると考えられているのです。
同時に、推測の域は出ないのですが、この躯体をなくした「魂」の「仏」からもこの死と共に発していて、それが、この「2つの器官」を鋭敏にして脳波とのセンサーの役目をして、この現象を起しているとも考えられてます。
実は、推論として、私は、この「魂」とは、この死の直後に発する顕著な末路の「脳波」が「魂」の本質ではないかと推測しています。
(仏教では、魂説は定義しているが、(初七日として葬儀行事として定めているが、)長期間では彼岸の入りとしての祭祀行事までで、それ以上はこの「魂」が存在し続けるとははっきりと定義していない。)
「論理的な科学例」
故に、物理学では、万事万物万象の末路には「フラッシュバック現象」が起こり莫大なエネルギーと振動波を発します。
この事は、この核がなくなるとき物質の基となる「核の分裂」(核分裂:物質の消滅:死)のエネルギーの大きさを証明する事になるし、 同時に、特有周波も発する事実と符合します。
例えば、太陽の核分裂の爆発により、太陽から発する7つの可視光線は、この物質の核分裂のときに発した波長であります。
黄はNa、赤はFe、青はCuのように400n(赤)−700n(紫)の波長を発します。そのすごいエネルギーで振動波としてこの地球まで届いているのです。
その波長は空気中の微細な物質との衝突で色を発します。虹や焼けの色の変わる現象はこの空気中の水分やチリなどで色が出て、透過する波長が変化して色が変わるのです。
この現象は、科学では「炎色反応」として確認出来るのです。
物質の微粉末が燃え尽きるとき核の破壊が起こり振動波を発して周囲の物質と衝突して特有の色を発する試験方法です。
この様に人を含むこの世の物質は上記の現象を起します。
つまり、人の場合、このフラッシュバック時の脳波と、上記の敏感になった「2つの器官」の連鎖反応が、他次元的な働きをして、即ち、「魂」と「人」の連携反応を起すのではないかと考えます。(私の「魂」の本質説)
ところが、この現象がはっきりしないと言うのが現実です。何故なのでしょうか。(この事の推論は下記に説明します)
「2つの脳波」の存在理由
その前に、ここで、「2つの脳波」というけれど、一体この脳波が人間の機能にどの様な直接的な働きをもっているのか、何故振動波を発し、そして、存在するのか、と言う疑問が湧きます。
人間の機能には無駄は無い筈です。だとすると、機能はあるのだろうか。
「脳波の機能」
確かに人間は地球の電位体に対して、ほぼ身長に応じた(+)の電位を有します。電位を有することは起電流が流れます。
これで脳の神経を通じて神経のつなぎ目(継電部)に、キャリパー(Naイオンのアルカリ液体)を媒体として、電流が流れて脳が働き、体の各所に信号指令を送る仕組みに成っています。
しかし、この2つの脳波で動かしている機能は無いのです。
脳波が出ると言うことは、脳が常時振動波を発している事になるので、脳がわざわざ意味の無い振動を起こし無駄なエネルギーを使ってする事は無い筈です。。
とすると、何か、元は目的があってして、それが何かの発達でこの目的が退化したと考えられます。
普通は、人間の機能は使わないと退化するのが普通であるので、ではその退化をさせた「何かの発達」は何なのかという疑問が湧きます。
振動波であるのだから、先ず最初に浮かぶものは「情報伝達」の媒体と成ります。
「媒体の推測」
野生猿から人間に変化して変わった情報媒体では、関連する内容としては「脳機能の拡大」と「言葉の使用」と成ります。
「脳機能の拡大」では、「左脳の拡大」(学習記憶情報量の変化)と「前頭葉の拡大」(付加価値増大の感情量の変化)となります。
「言葉」では、「意思伝達の拡大」が起こりましたが、これは、言葉の伝達で「記憶量」が増大し、言葉の伝達で「感情量」が増大します。
結局は、この事で言葉は「脳機能の拡大」をが助長させたことに成ります。
つまり、結局は、「記憶量と感情量」は「左脳の拡大」と「前頭葉の拡大」としての「脳機能の拡大」が大きく変化した事に成ります。
そこで、「左脳の拡大」と「前頭葉の拡大」は、上記の説の通り、次のようになるのではないかということです。
「2つの器官」の「左脳の拡大」では、上記した様に、左脳の中央部にある中紀体の「未来予測脳」であり、「前頭葉の拡大」では、前頭葉の額の上部(現代では脳中央部下部)の「第3の目」の複眼となるのでは無いでしょうか。
この「2つの器官」の退化で、「2つの脳波」の目的が無くなり退化したと考えられます。
この事は上記の「2つの器官」の論所と「2つの脳波」の論処とは、符合一致しますので、論理的に無理はないと考えます。
当然、「情報伝達」には、「発信受信媒体」と、「伝達媒体」が必要です。
人間には、この「発信受信媒体」として「2つの器官」、「伝達媒体」として「2つの脳波」と成るのではないかと推測しているのです。
この二つの媒体(「2つの器官」と「2つの脳波」)が、ある条件下で他次元までの伝達と成っていたと考えているのです。
ただ、これが全ての人間に保有していた機能とは思えないのです。それが「ある条件下」です。
極度に心を沈めることが出来て、非常に集中力を高められる能力を保持する者にしか働かないと思うのです。
インカやマヤなどの祈祷師や預言者、邪馬台国の卑弥呼などの者がこれを保持していたと推測しているのです。
より高い能力を持つ者は、他次元との連携をこの器官を使って出来ていたのではないかと考えているのです。
普通の者は、私の体現程度か、それ以下の伝達程度に成っていたと考えます。
この「脳機能」は4世紀ごろのまでの人間の社会にまだ少し存在していたのではないかと考えられます。
とするのは、例えば卑弥呼が予言した事柄を周囲の者が信じる現象は、ヤマト勢力と覇権を争っていた九州勢力を押さえていたこの者達全般にも、この脳機能の能力をある程度まだ維持していたから、卑弥呼の「予言」と言う不確定なものを信じた前提なのではないでしょうか。
又、上記した5−6世紀頃の仏教の仏像の複眼等もこれを裏付けるものとなるのではないでしょうか。
だから、仏教がインドで誕生時期から観て、人の死後の「初七日」の行事とか、「魂」説とか、「仏」=「先祖」説とかもただの説ではなかったのではないでしょうか。
この「第3の目」に関しても、平安期前期の仏像に額の真ん中に「複眼」をつけた仏像がありますが、これは、多分、仏教ではこの事を過去からの伝えで使用していた事を意味します。
つまり、仏教でもこの現象を認めている事を意味します。
以上、この論処事が私の体現の論理的説明となると考えています。
そうする推論で考えると、多くの世間で話されている死の直後の有り得る他次元との他の特異現象は、このことで説明がつくのではと考えています。
無と有の思考の効果
事程左様に、広範囲の科学論理的根拠や学識から調べるとそれ程に「無根拠」ではない事が判ります。
「無」と「有」と決め付けない「反意」で、思考すれば、この様に真実の根拠は見えてくるものであると考えます。
他次元の世界を「無」として決め付ければ(拘れば)、この様に、見えるものも見えなくなり、「有」と理解すれば「二つの器官」の存在も観え、そして、最後には、「時間の逆行」もあるという判断が出来るように成ります。
さすれば、より高く、より正しく、より冷静に、根拠に基づく上記の「理解」が得られる事につながると考えます。
言い換えれば、”「無」であるから「無」と拘るな””「有」であるから「有」だと拘るな”さすれば、般若経が云う「悟り」即ち、根拠ある「理解」のところにたどり着くとしています。(呪いの設問の解読説)
禅宗の座禅は、この様な基となる「静かなる心根」を高め得ようとする修行では有りませんか。
そして、その禅問答はその「静かなる心根」で「悟り」即ち「理解」を修練する行為では有りませんか。
確かに、技術の仕事していたときには、頭から湯気が出るほどに、一つの事に拘っていたときは「見えなくて」、その「拘り」から開放されたときの一瞬には「見えた」という事が沢山あり、何かあの世から知恵を授かった、貰ったというような気になって、技術的に解決したという経験は多くありました。
多分、この時に、この器官が動作していた可能性がありますね。皆さんはいかがですか。
学説では、頂点に達すると、この時にベータ−波が出て、脳は切り替わり、拘りは消滅し、脳の能力最大限に働くと言われています。
スポーツなどでもこの極限に達すると、その極意を得ると言われていますので、優秀な選手はこの域に達しようとして訓練を行うのであります。
「心頭滅却すれば、火も又涼し」であります。事実真実です。
私は、この現象は、「宗教的」な感覚ではなく、医学的にも、人間に本来に備わった「野性的本能」がまだあると観て、それがある条件下で働いていると考えています。
故に、「無」即ち、”ない”と限定し舞わないで、[有」もあわせて考える姿勢と思考が大切と考えます。
つまり、この経験の「有無」が上記した「差」として、積み重なるものと考えます。
私は、論理追求として働く物理技術者でしたが、一面、この様な現世に於いて論理外の思考もするところがあります。
しかし、つぶさに見てみると、上記のように、その否論理的なことを論理的に捉える習性が存在する不思議な性格かも知れません。
結論として、上記の「2つの器官」と「2つの脳波」の働きから、「呪い」の設問の(1)から(22)の数式の結論下で、故に、「時間は逆行する」であります。この世の相対の原理から云っても、あり得る事です。
その事から観ても、「先祖」「仏」の「連携」はある条件下で成り立つと定義できます。
だから、連携の不可思議、その事も含めて、「先祖」を知る事、「先祖」を敬う事は、現代の遺伝子学での結論の「過去の90%の自分」を敬う事にも相成ります。
故に、先ずは、「先祖を知る」事から始めるべきと考えます。
先祖を知れば自ずと先祖を敬い、先祖を祭る行為は生まれ、自身の心は上記の「拘り」の少ない心へと進みます。これが仏教の説くところでしょう。
実は、私は、「宗教」というものを「信仰」はしていません。仏教の説でも正しいとされるものを信じているだけです。
次の設問の徐として。
如何せん、兎角、「宗教」は「ご利益信仰」が主体と成っている事に疑問なのです。
”信仰すれば、こうしてくれる”は信仰とは云わないのではないでしょうか。
次の設問のキリスト教は、この傾向が説話の中で多すぎると感じています。
”信じよ、されば救われん。”には納得できません。信じなくても救われる筈です。この世の中でキリスト教を信じていない人は救われないと言う事でしょうか。そんなことはありませんね。
仏教は、”信じよ”とは云っていません。”理解せよ。”です。理解すれば静かな心根が生まれ、良い方向とへと進むとしています。
キリストは、”人は罪多き悪の子供”と設定していますが、仏教では”悪の子供であるも普通であり悪と拘るな”であります。それが「人」だと説いています。
次は、「行為と行動の進行性」への設問です。
先祖と宗教(般若経の呪いの意-主題1)
副管理人さん 2007/10/09 (火) 12:11
先ずはじめに、青木さんから雑談掲示板に投稿されていました事に付いて、本サイトの一つの目的である「先祖」と言うキーワードに関連する事なので、特に広く論じて理解を得る必要があるとして投稿しました。
その経緯は、キリスト教徒の方から見て、仏教の教義に疑問が提起されました。それにお答えした論文でした。
その掲示板の内容は次の1−5の設問でありました。
そこで、青木さん以外の全国の皆さんにも広く観て頂きたく改めて、僧の説法を聞く側からの雑念の中での私観をまとめ直して投稿しました。
最近、日本人には、特にその「先祖」という言葉の意味、又は意義が薄らいでいると感じています。
「先祖」と言う言葉が我々の日常の生活の中に遺伝子的に無意識の中で浸透しているのですが、これを改めて認識してもらい本当の日本人に戻ってもらいたいと常々思っていました。
そこで、その方法として、何とか解りやすくする為に、その「先祖」を仏教とキリスト教とを対比させる事で明確に成るのではと考えました。
この対比事項としては、雑談掲示板に設問された次の内容5つが「先祖」を説く上で適切と見て限定して論じてみました。
そこで、早速ですが、本題に入りたいと思います。
投稿
先ず、掲示板の御意見を拝聴しましたが、私は少し違う考えを持っていますので、ご披露したいと思っています。
ご意見には突き詰めると「先祖」に関わりのある事が大いに認められ、それ故「先祖」という定義からその思考を述べる事でお答え出来ると思います。
ご意見の内で、抜粋した次の設問に対する内容(問題)として、(...)を大意として示しています。
設問
1「呪いの意」 (般若経の一説:仏教は何故呪うのか)
2「時間の逆行性」 (時間は逆行しないのだから仏教の仏=先祖は疑問)
3「行為と行動の逆進性」 (先祖が成した行為と行動は逆行しないのだから「仏」は疑問)
4「キリスト経の教え」 (仏はキリスト教の教えと異なる)
5「仏教とキリスト経の妥協の余地」 (根本的な違いの考察)
以上に付いて私観を述べたいと思います。
注釈
4−5の設問に付いては、本論はキリスト教との対比を特にします。
但し、このことは決してキリスト教を非難するものではなく、日本人には無意識の中で脳に対して染みこんでいる宗教に対する遺伝子的なものが存在し、それにキリスト教の教えがマッチングしないのではと考えているので、その差違を現したものです。
前置きとして、文内の表現の差違は、仏教とキリスト教との間にこれだけの違いがあるのかと言う程度にご理解ください。
注意
そこで、超論文に成りますので、シリーズで記述する事にしますのでご理解ください。
シリーズの途中から読まれる場合は、継続性がある為に理解が出来ないということも起こりえます。従って、この設問から講読下さい。
念の為、本論は観念論であるが為に、理解し難いことです。従って、文中で、多少の問題はありますが、各所で使用する数式は結論を何とか解りやすくする為に用いています。
本文
1「呪いの意」(般若経の一説:仏教は何故呪うのか)
では先ず、文面で般若経にある「呪い」と言う事に対する「嫌悪感」に対する疑問の件です。
般若経の一説 「是大神呪 是大明呪 是無上呪 是無等々呪 能除一切苦 真実不虚」
現代の言葉で「呪い」とは如何にも恐ろしげな行為であると観られますが、般若経で言う「呪い」とはいったいどう言うもので、どう言う事かと言う設問に入り、且つ、それを解明すれば我々の凡人は全体像の理解が出来ると思いますので以下に進めます。
では、それは一体何なのでしょうか。二元体の人の世界に起こる「呪い]です。よって、その人間の「心の動き」である筈です。
その「心の動き」の「呪い」として出て来るものは、私は次の「4つのみ」であると思います。
それは、仏教で云う、人として ”最も無くさなくては、或いは、少なくしなければならない「人間の性(さが)」”であると思います。そして、それは説法で言う「4つのみ」だと思います。
つまり、この性の「呪い」を構成しているものは「4つのみ」と言うことです。
数式で現せば、「呪い」=「心の動き」=「4つのみ」と成ります。 (1)
では、その「4つのみ」とはどのような「性」なのかと言う事ですが、それは次のものだと思います。
数式で現せば、「4つのみ」の構成要素 =「うらみ」+「つらみ」+「ねたみ」+「そのみ」だと考えます。 (2)
この人の「4つのみ」から誘引して「心の乱れ」を引き起こす結果、その映像として「呪い」が生まれるのです。
そして、この「心の動き」の一つの「心の乱れ」は「人の拘り」へと変わります。
数式で現せば、「心の動き」=<「心の乱れ」=<「人の拘り」=<[呪い」に繋がります。 (3)
数式で現せば、「4つのみ」=「心の乱れ」=「人の拘り」=「呪い」=「性」(さが)と成ります。 (4)
では、この「性」、即ち「心の乱れ」、「人の拘り」を人は無くせるのかという疑問です。
結論から私は出来ないと考えます。”それは何故なのか。”です。
もし、無くせたとしたら、この世に「宗教」というものが存在しません。
この「4つのみ」があるからこそ、世の中は乱れるのです。だからそれを少しでも救おうとして、人は「宗教」というものを考え出し頼ったのです。
ましてや、この「4つのみ」を無くせば、それは、「現世の人」では有りません。
この「4つのみ」をなくした者が、「仏」であります。ゆわんや「先祖」であります。
数式で現せば、「4つのみ」=「現世の人」 つまり、「仏」=「現世の人」−「4つのみ」 (5)
「先祖を理解する事」は、即ち、「4つのみ」が原因した「先祖の生き様を知る事」であります。
数式で現せば、「先祖を理解する事」=「先祖の生き様を知る事」+「4つのみ」 (6)
そして、それは「4つのみ」から少しでも軽減し、同じ苦しみを味わってきた「先祖」、即ち、「90%程度の同じ遺伝子を引き継いだ自分」を見つめる事が出来る唯一の手段なのです。
現代医学では血液型を同じとすると85−95%の遺伝子が同じであります。これは殆ど「自分」という事になります。
数式で現せば、「先祖」=「90%程度の同じ遺伝子を引き継いだ自分」 (7)
つまり、「先祖の自分」に対して、そこに起こる「自分への尊厳」と「先祖への感謝の念」が、人の心を豊かにし、開放させられます。
そして、その心が「4つのみ」への「拘り」を理解する事が出来て、軽減さしてくれるのだと考えます。
何もしないで、「4つのみに拘るな」と云っても、拘わらない事すら難しいのに、「4つのみ」所の話ではありません。
それこそ「負担」であり、[苦」に成ります。
その「拘り」の救いは、先ずは「先祖」を知ることであり、強いては「4つのみ」から開放された「先祖」即ち、「90%の過去の自分」即ち「仏」を知る事になるのだと考えます。
それは(先祖とは)、「4つのみ」から発祥した育枝種にして分離した「108つの煩悩」から解き放たれた「魂」のみの「仏」なのです。
数式で現せば、「108つの煩悩」=「4つのみ」*N=A 「仏」=「魂」−A (8)
但し、ところが仏教では、この「4つのみ」を”無くせ”とは云ってはいません。
むしろ「無くせない」と説いています。
仏教では、「無」(無くす事)を主張するのではなく、「有」(ある事)を認めていて、「有りのままに生きよ」と説いているのだと思います。
ただ、これだけでは「宗教の教え」にはなりません。
この「4つのみ」の「処し方」として、「拘るな」(気にするな)と説いています。
「拘るな」(気にするな)は、人として可能な行為であります。
そして、「拘り」を「捨てる」、或いは、「軽減する」ところから、”人の生きる世界から、又は、「性」(さが)から解き放たれる”と説いているのだと思います。
この事は、即ち、般若経の「色不異空、空不異色」と「色即是空、空即是色」であると思います。
この1節の理解の如何に関わるものだと考えます。
では、どの様に理解したら良いかと言うことですが、私は次の様に理解しています。
「色」即ち、この世のあらゆる物質は全て色(いろ)を有します。故に、その「色」(いろ)のある環境、つまり総意としての「現世」であると理解出来ます。
数式で現せば、「色」=「現世」(うつせ)だとします。 (9)
「空」即ち、物質として存在しない空(から)の世界とし、色(いろ)を有さない世界だから、つまり総意としての「彼世」(かのせ)であると理解できます。
数式で現せば、「空」=「彼世」(かのせ)だとします。 (10)
そこで、「色は空と異ならない 空は色と異ならない」、故に「色は空であり、空は色である」と説いています。
つまり、言い換えると「現世は彼世と異ならない 彼世は現世とは異ならない」、故に「現世は彼世であり、彼世は現世である」と成ります。
究極の大意の数式で現せば、「現世=彼世」であるとします。 (11)
つまり、、「現世=彼世」法の「理」は、”物事に色があるから無いからとどうのこうのと言い立てるな、空だから無いからと騒ぎ立てるな”と言っていると思います。
言い換えれば、究極は”「物事に拘りすぎるな」”となるのではないでしょうか。
では、何故この数式が成り立つのかと言う疑問が出ます。
それは、「現世」と「彼世」の間には「仏」が存在し、その「仏」は「4つのみ」から離脱した「先祖」であるとしているのです。
数式で現せば、「現世=仏=彼世」or「現世=先祖=彼世」の数式が出来ます。 (12)
上記の数式では、「先祖」=「90%程度の同じ遺伝子を引き継いだ自分」、故に、「現世=自分=彼世」 (13)
数式で現せば。「現世=仏=彼世」or「現世=先祖=彼世」or「現世=自分=彼世」・・(B) (14)
故に、(9)から(14)までを合わせて解釈すると、その大意はいずれにしても「自分如何の世界」だから「拘るな」と成ります。
これでは合点し難い所があります。そこで「俗意」としては、次の様になると考えます。
[拘るな」とは、”「現世」「彼世」は自分が関わる世界であるのだから、地獄極楽も「現世」の仕業、だからこの「現世」の所業になんだかんだと理屈を立てて言い張るな。決め付けるな、考えし過ぎるな。気にし過ぎるな。そして、それより、先ずはこの「理」を悟れ、つまり、理解せよ”と成るのだと考えます。
数式で現せば、(B)数式の理を解する事は、「悟り」=「理を解する行為:理解する」=「拘りすぎるな」=「気にしすぎるな」 (15)
そして、これを理解すれば、この「呪い」の般若経の2行のくだりの最後には、「能徐一切苦」「真実不虚」と説いています。つまり、”一切の苦しみを除く事が出来て真実は虚にはならないから”と言う事だと思います。
仏教では、「一切の苦しみ」とは、「108つの煩悩」とされます。
つまり、そうする事(15)で、「4つのみ」で発展した「108つの煩悩」が「呪い」を引き起こします。その「呪い」が起した[心の動き」の拗れた「心の乱れ」が、納まり、そして、”「静かな心根」が得られ、その結果、「現世」の自分に「真実」(誠)が近づき、自然と「苦しみ」から逃れられる”としているのだと考えます。
「現世の理」を「理解する事」で、、「自分」に”「静かな心根」”が生まれると言う事が大切であるのだと考えます。
そして、”その判断が回りの茨の道に踏み出さない結果になる”のだと説いていると思います。
数式で現せば、「悟り」=「拘りを無くす事」=「現世の理」を「理解する事」=”「静かな心根」” (16)
そして、次の「苦しみ」から少しでも逃れられるのだと考えられるのではないでしょうか。
数式で現せば、「呪い」=「108つの煩悩」=「4つのみ」*N=苦しみ 「仏」=「魂」−(苦しみ) (17)
次に、前節の「是大神呪 是大明呪 是無上呪 是無等々呪」では、私は次の様に解釈します。
この行のくだりのお経を理解する事の大切なことは、般若経の「大神」と「大明」の意をどのように理解し解釈するかの如何だと思います。私は次の事と解釈しています。
数式で現せば、「大神」=「神」 「大明」=「仏」 (18)
そして、”その「呪い」とは、「神」や「仏」の「呪い」であり、それ以上の「呪い」は無く、それは、神仏の「戒め」であり、この上記の「理」を理解すれば、「呪い」は無くなるのである。”としているのだと思います。
そして、”一切の苦しみを除く事が出来て真実は虚にはならない”とし、つまり、そうする事で、”静かな心根”が得られ、「真実」が近づき、自然と「苦しみ」から逃れられる”と説いていると解釈します。
「神」とは仏の中の得心した「仏」であるのだから、次のような考えとなると思います。
数式で現せば、「呪い」=「神」、「仏」の「戒め」=先祖の「戒め」=自分からの「戒め」 (19)
仏教では、「呪い」即ち、自分からの「戒め」を知ることは、それは「悟り」と説いています。
その「”悟れ”の本質」は”静かな心根”で「理解せよ」”としています。
数式で現せば、「”悟れ”の本質」=”「理解せよ」”と成ります。 (20)
そして、本設問の「呪い」に対する「嫌悪感」の結論は、以上(19)、(20)の様になると思います。
そこで、”「理解せよ」”とは、他の一節「所業無常」(諸行無常)の反意では、”業と行は常(恒)ではない。だから所業(行)の全てを一度に理解するのではなく、日々の所業(行)の中で、所業の「理」を知り、積み重ねよ、そうすれば究極は悟れる”としています。つまり、”何時の時か「即身成仏」と成るであろう。それに近いものに成るであろう”であります。
”無常のない行と業の中での”「急ぎの理解」は「拘り」の所以である”ともしています。
数式で現せば、「急ぎの理解」=「拘り」 (21)
決して仏教では、キリスト教のように、”先ずは、「信じよ」(キリスト教)”とはいきなりに説いてはいません。
それは、ただ「信じる」ことだけでは、「根拠なし」のものとなるからです。
仏教の「理解」(悟り)は、日々の精進の理解を経て、この「根拠」を得て初めて「理解」と成ります。
これが、ご指摘のキリスト経と仏教の決定的な差であります。
般若経では、その字句のそのものの意味ではなく、その字句の持つ「反意、真意、深意」を如何に知るかに関わると思います。
私の経験では字句の意味だけではどうしても理解ができませんでした。
ここに書いている事は、この「3つの意」(「反意、真意、深意」)から得たものです。
「人」は「仏」では有りませんので、「呪い」から現世では逃れることは出来ません。
それを無理に排除しようとする所に無理(拘り)が生まれ、現代社会の問題の露出と成っているのだと思います。これは「仏」でなくては出来る事ではないではありませんか。
だから、仏教では万能の「神」との間に、人間社会の「4つのみ」から生きてきた躯体をなくした「御魂」となった「仏」を置き、理解しやすくしているのだと思います。
そして、この精進した「仏」から「神」へと進むのだと説いています。
突き詰めれば、「仏」は「神」であり、「仏」は「先祖」であり、「先祖」は「90%の自分」であるとしているのです。
そして、三段論法では、終局、「仏」は「90%の自分」、「90%の自分」は「神」の元であり、この世とあの世の間には、「躯体」と「4つのみ」の有無の差であると説いているのだと思います。
この論理の結果から、「神」の居る「極楽」は、「この世」という事になります。そして、それは
「4つのみ」の「理解」という行為のことから、自分の目前には「極楽」は作られると考えます。
その「不理解」の行為は、「地獄」という事になります。
数式で現せば、「4つのみ」の「理解」=「極楽」 「不理解」の行為=「地獄」 (22)
つまり、「4つのみ」の「理解の如何」の差が、「極楽」と「地獄」の差となって現れると般若経は説いていると思います。
そして、未だ「仏」でない躯体を持った人のこの「理解の差」に対して、仏教は「縁無き衆生 動し難し」と説いています。
即ち、「極楽地獄」は本人次第としています。”無理に導くな”と説いています。
その差は「仏」となった時に、次に「神」になれない「仏」であるとしています。
「般若心経」は、この「4つのみ」(色)と「躯体」(舎利子)の事のと取り扱いの考え方に付いて述べ、”「万事所業」は、この世では「無」ではなく「有」として「理解」して生きよ”と説いているのだと思います。
しかし、”「有」だから、「有」と主張するな”と説いています。それは結局は論理的には、”「拘り」の元となる”と説いている事にも成ります。
そして、その「心の持ち様」の秘訣は”あの世とこの世との差の「先祖」にある”のだと暗示していると考えます。
私は、故に「青木氏の先祖の研究」と言うものに取り組んだひとつのきっかけでした。
この「4つのみ」から起こる先祖の生き様が、良く判ったと思っていますし、今の「心経」の糧となったと信じています。
人それぞれにいろいろな考えがあろうと思いますが、「呪」の意は、以上の22の数式で表現した様な事だと思いますので、当然のこの世の事として、それ程に疑問を持っていません。
この22の数式は全て等号(=)で繋がると言う「呪い」の意であると思います。
故に、当然の起こりうる「結果」として受け取っています。むしろ、人間社会を維持して行く限りに置いてありうるべき「事柄」かなとも考えます。
ただ、それを出来る限り、避ける「理解」の修行を怠らないようにしています。
その修行とは、”「22法の理」”を知り、”先祖を敬い”と”心静かに”の「心根」(拘りのない平常心)を保つ事であろうと思っています。
現世では「4つのみ」から起こる「呪」は、別には「社会の悪」と対峙し炙り出すテストペーパーでもあり、悪い事ばかりでも有りませんよね。
数式の整理
数式で現せば、「呪い」=「心の動き」=「4つのみ」と成ります。 (1)
数式で現せば、「4つのみ」の構成要素 =「うらみ」+「つらみ」+「ねたみ」+「そのみ」だと考えます。 (2)
数式で現せば、「心の動き」=<「心の乱れ」=<「人の拘り」=<[呪い」に繋がります。 (3)
数式で現せば、「4つのみ」=「心の乱れ」=「人の拘り」=「呪い」=「性」(さが)と成ります。 (4)
数式で現せば、「4つのみ」=「現世の人」 つまり、「仏」=「現世の人」−「4つのみ」 (5)
数式で現せば、「先祖を理解する事」=「先祖の生き様を知る事」+「4つのみ」 (6)
数式で現せば、「先祖」=「90%程度の同じ遺伝子を引き継いだ自分」 (7)
数式で現せば、「108つの煩悩」=「4つのみ」*N=A 「仏」=「魂」−A (8)
数式で現せば、「色」=「現世」(うつせ)だとします。 (9)
数式で現せば、「空」=「彼世」(かのせ)だとします。 (10)
究極の大意の数式で現せば、「現世=彼世」であると成ります。 (11)
数式で現せば、「現世=仏=彼世」or「現世=先祖=彼世」の数式が出来ます。 (12)
上記の数式では、「先祖」=「90%程度の同じ遺伝子を引き継いだ自分」、故に、「現世=自分=彼世」 (13)
数式で現せば、「現世=仏=彼世」or「現世=先祖=彼世」or「現世=自分=彼世」・・・(B) (14)
数式で現せば、(B)数式の理を解する事は、「悟り」=「理を解する行為:理解する」=「拘りすぎるな」 (15)
数式で現せば、「悟り」=「拘りを無くす事」=「現世の理」を「理解する事」=”「静かな心根」” (16)
数式で現せば、「呪い」=「108つの煩悩」=「4つのみ」*N=苦しみ 「仏」=「魂」−(苦しみ) (17)
数式で現せば、「大神」=「神」 「大明」=「仏」 (18)
数式で現せば、「呪い」=「神」・「仏」の「戒め」=先祖の「戒め」=自分からの「戒め」 (19)
数式で現せば、「悟れの本質」=”「理解せよ」”と成ります。 (20)
数式で現せば、「急ぎの理解」=「拘り」 (21)
数式で現せば、「4つのみ」の「理解」=「極楽」 「不理解」の行為=「地獄」 (22)
本論は観念論ですので、できる限り論理的な証拠と数式的手法も取り入れて進めたいと思っています。
私は、元の職業柄か性格的な事からも、常々、観念的なものに「理」を求め、それを医学的や動物学的な「論理的証拠」で証明したいと常に思って取り組んできました。以降の論調はこの手法に基づいて論じています。そのつもりでご理解ください。
次回は、堅い話にはなりますが、本来無い筈の「時間の逆行」の私観を述べてみたいと思います。
上記の事にも関わりますので、ご留念下さい。
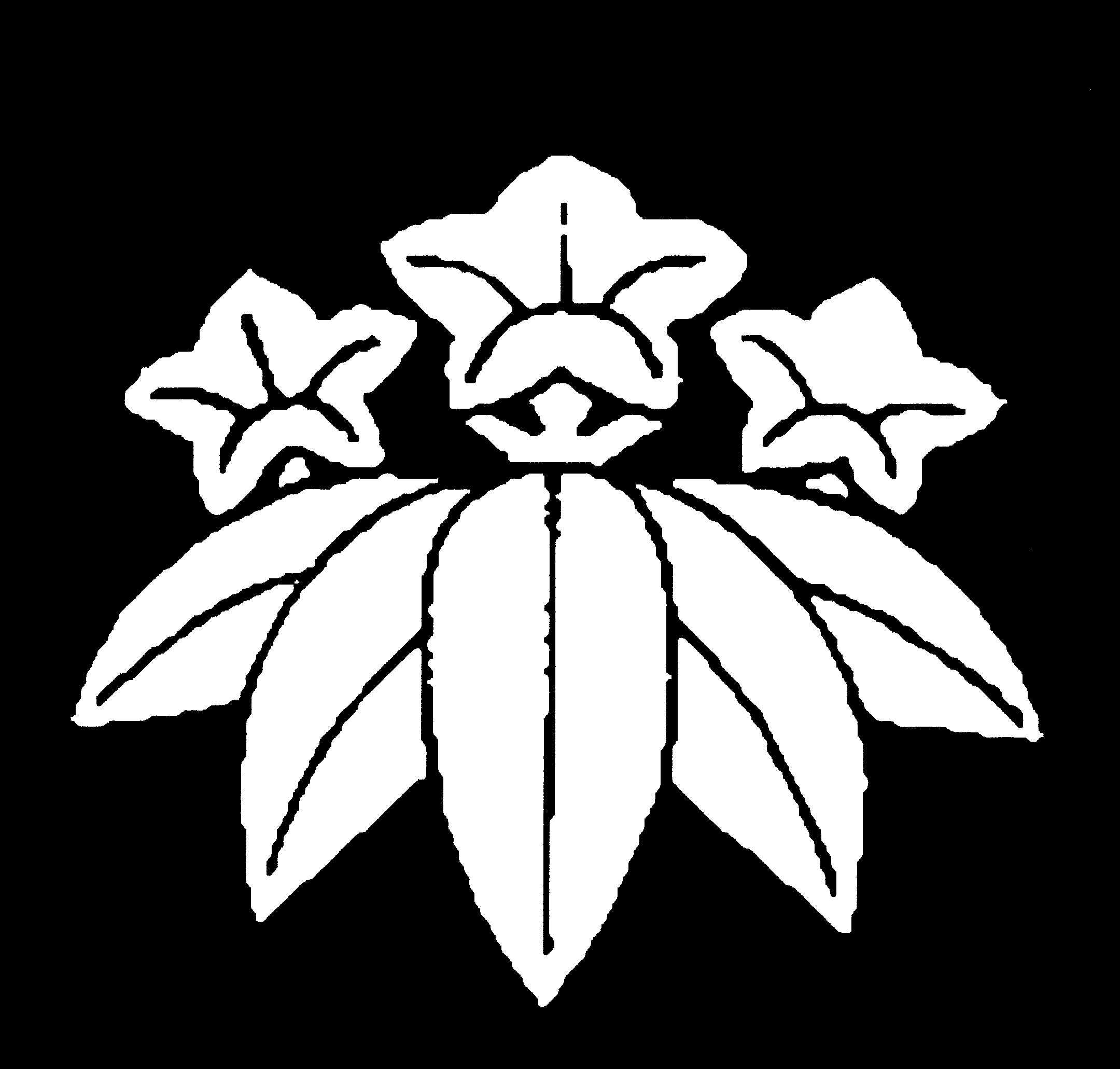
青木氏の綜紋は「笹竜胆紋」である。
(笹竜胆紋の写真添付)
この「竜胆文様」には47の文様がある。
この内、「笹竜胆紋」は、家紋200選に菊紋の次ぎにトップに上げられている文様である。
その中でも、「笹竜胆紋」は天智天皇から発祥し、光仁天皇までの5家5流の皇族賜姓青木氏と、同族の嵯峨天皇期から発祥し、花山天皇までの11家11流の源氏一族の「綜紋」でもある。
(後日の説では源氏16代と成っているが、12代から16代目では源氏としての意味は全く無く、15代と16代は南北朝の時代の者である。後日の徳川氏を始めとして大名に成った者の系譜搾取偏纂の結果であり、実質11代目までである。)
この皇族賜姓青木氏と、皇族賜姓源氏の二つは、次の経緯(概要)で発祥している。
(これ等の以下の記述内容に付いての詳細は、家紋掲示板と研究室の右メニューから適切なものを選んで参照)
[賜姓青木氏と賜姓源氏の発祥経緯]
先ず、「皇族賜姓青木氏」は、天智天皇より光仁天皇までの男性天皇(間に女性天皇あり)の5人の天皇から出ている。
各天皇の「第6位皇子」を、天皇の「親衛隊」として臣下(侍)させて、天皇より直接「青木氏」の賜姓を授けたものである。
この5人の天皇は、「天智天皇」、「天武天皇」、「聖武天皇」、「文武天皇」、「光仁天皇」(施基皇子の子)である。
「賜姓と臣下の理由と目的」は、概ね次の通りである。
「大化改新」が起こり、「蘇我氏との反省」と「財政的改革」から、「天智天皇」(中大兄皇子)は、手始めに天皇の「皇位継承制度の変更」を実施し、それまでの「第4世皇位第6世臣下」の「世」方式から、「第4位皇位継承第6位臣下方式」の「位」方式に厳しく変更した。
そして、天皇家の「財政的軽減」を図った。
この時、更に、66国に配置する「王位」に付いても、それまでの第6世(第7世は臣下 坂東に配置)までとしていたところを、第4世までとして厳しくして天皇家の負担軽減も図った。
これが第1の目的であった。
その理由として、天智、天武の両天皇の皇子は、総勢34人と、その他の皇子や上位王位を入れると、約50人以上にもなっていた。
これ等に掛かる費用は、天皇家の財政的な大負担の状況であって、これが天皇家を弱くしていた原因であった事と、施政に対する財源の捻出がままならず、「大化改新」の改革のネックと成っていた。
つまり、天皇家の「内蔵」の財政が、朝廷の「大蔵」の財政を圧迫していたのである
又、更には、天皇を護る自らの護衛隊が無く無防備であった事が、蘇我氏の助長を招き、渡来人の軍事集団の漢氏(又は東漢氏)を支配されていた事などで天皇家が圧迫を受け、思いのままにされていた事。この反省により皇子を臣下させる方策(天皇の親衛隊)に出た。
これが第2の目的であった。
当時、後漢の民である帰化人が持ち込んだ技能集団(即ち、第一次産業の「部制度」)による経済的収入源は、朝廷の財源(大蔵)を大きく占めていた。これが蘇我氏の管理下に置かれていて、経済の実権(政治、軍事含む)を完全に握られていた事。これを「公地公民の制」を敷く事で天皇家に実権を集めて解決し、これを上位の王位等の守護王に監視させた。
これが第3の目的であった。
[初代青木氏の発祥]に付いて
それまで「伊勢王」であった「孝徳天皇」の皇子(2人の兄弟皇子は同日病死)から変えて、「第6位皇子」として、「中大兄皇子(天智天皇)」の皇子の「施基皇子」を臣下させて、伊勢国の王位を与えて護らせた。
そして、この王位には賜姓として青木氏を与え、そのステイタスとして「鞍作部止利」作(日本最初の仏師)の「大日如来坐像」(大日像)の仏像を与えた。
(現在も青木氏宗家が保有 仏像は家紋掲示板に転写)
(参考 その際、特別に第7位皇子(川島皇子)にも、近江の佐々木村の地名を採り賜姓し、近江の「佐々木氏」を与えた。 後に宇多天皇の滋賀の佐々木氏も発祥)
「天智天皇」は、ここに天皇家の守護神として「伊勢神宮」を置き定めて、祭祀を行ってここを伊勢国の天領地とした。
(その後、天武天皇が正式に守護神と定めてた)
そして、「賜姓青木氏」を伊勢神宮(守護神)を護る伊勢の国の「守護王」としたのである。これが(藤原秀郷流青木氏を含む全ての青木氏)最初の伊勢の青木氏である。
(参考 藤原鎌足から北家8代目の秀郷は、「平の将門の乱」で勲功を挙げて、貴族の身分と下野武蔵の国を与えられたが、貴族となった事により、自ら武力を使えない定めから、天皇家の青木氏に習って第3子の「千国」を侍として藤原一族の専門の護衛役の任を与えた。(藤原秀郷流青木氏116氏に広がる)
賜姓青木氏も母方に藤原氏の血筋を保持する家柄である事から、この時(900年頃)に、朝廷に対して禁令(嵯峨期禁令ー明治初期)のある青木氏を使用する事を申請して同族と見なされて許可された。これが藤原秀郷流青木氏である。(藤原秀郷主要5氏の一つ)
「守護王の配置の経緯と理由」は概ね次の通りである。
当時、隋が滅亡し、唐(618)が建国して中国全土を制圧したが、この時、後漢の「光武帝」より21代の末帝の「献帝」の孫の「阿智使王」と曾孫の「阿多倍王」(「石秋王」の子供と孫)等は、後漢の17の県民(200万)を引き連れて北九州に上陸した。
この阿多倍らは、瞬く間に九州全土を制圧し、殆ど無戦の状態で支配下に治め、その後、争いを避けて朝廷に対して帰化を申請した。
この後漢の民は、あらゆる面に於いて高度で進んだ技能集団で編成され居た。このために土地の者は、その進んだ技能(部技能制度)を吸収して生活程度を向上させた事から各地で進んで支配下に入ったのである。そして、遂には、中国地方から関西の手前まで支配下になった。
当時の国は66国であり、この内の32国を支配下に治めたのである。このため、朝廷は後漢の民(渡来人)の帰化を認めて、更に、続々と入国してくる帰化難民を中部地方にも配置させたのである。
天智、天武天皇より後に、都として定めた近江国を除き、美濃と信濃と甲斐国は、未だ未開の土地であったが、この結果、進んだ技能により未開の地は、主に大きい外来馬の飼育等の目的で開墾が進み、大和国の主要国と成りつつあった。
これ等の理由により、聖武天皇以降の天皇は、上記の賜姓青木氏による守護王を配置して、北部の未征圧の国の民族から彼等を護ったのである。
又、この5つ国は、更に、「国防、交通、穀倉」の地帯の要衝地でもあり、5人の天皇は「第6位皇子」に賜姓して青木氏を与えて、これを護る「守護王」としても配置したのが「5家5流の青木氏」の経緯である。
(後に賜姓源氏もこの5つの主要地の国司となる。)
この初代伊勢の国に続き、近江国、美濃国、信濃国、甲斐国に国府を置き、上位(八色の姓制 朝臣)の「守護王」として配置し、その5つ国に国司を派遣したのである。
これ等の国の賜姓青木氏は、後に5家5流は24氏と末裔を広げた。
「笹竜胆紋を持つ2つの賜姓族(青木氏と源氏)」の経緯は次の通りである。
この「光仁天皇」の次に一人空けた「桓武天皇」は、律令国家の完成を目指して国体を作り上げた天皇であるが、この時、政治に対する影響力を持っていた賜姓青木氏との軋轢が起こり、5国の国司などを変更し派遣して、この青木氏に圧力を掛けて勢力を弱めさせた。
この結果、伊勢の青木氏をはじめとする賜姓青木氏は衰退した。
(伊勢国は、国司を2年間藤原秀郷の祖父の藤原藤成に変更し派遣して、守護王の青木氏に圧力を掛けた)
(この後、伊勢青木氏を始めとして、その守護王の力と実務の実績を利用して、土地の産物などをさばく豪商となり、「2足の草鞋策」を採った。
伊勢の青木氏は、伊勢北部伊賀地方付近から産出する和紙を扱い、和紙を中心とする問屋を営み、明治35年まで1000年も続く伊勢の豪商「紙問屋の紙屋長兵衛」として栄えた。長兵衛は信長の伊勢攻め(3乱)で伊勢シンジケートを使ってゲリラ戦を展開した。小説「名張の小太郎」など有名)
「第6位皇子」の「賜姓青木氏」を中止して、これに変えて、「桓武天皇」は、自分の母(後漢の渡来人で、名は「高野新笠」 阿多倍の曾孫 伊勢国を分轄しての伊賀地方の半国国司 800年頃)の親族一族を引き立てて、「たいら族」(京平氏)として日本の氏を与えて賜姓したのである。
(半国司とは、天領地などと成っている一国を、「守護王」を一人として、分轄して「国司」を置いて複数で管理させた方式を言う。 伊勢、薩摩などがある。この二つは何れもが、後漢の帰化人の阿多倍に与えた国である。伊勢は伊勢北部伊賀地方を分割し”伊勢衆”と呼び、薩摩は大隈を分割し”大隈の首魁”として呼んだのである。
別に後には、伊勢は永嶋地方を分轄して3分轄として村上天皇の流を組む北畠氏を半国司として任した。)
「伊勢の北部伊賀地方の住民の阿多倍一族と青木氏の関わり」に付いての経緯は次の通りである。
後漢の首魁の「阿多倍」(薩摩半国の大隈国の首魁)は、これらの勲功により、都近くの伊勢の国にも半国を与え、更に、この後、「敏達天皇」の曾孫の「芽淳王」の娘を娶り3人の男子をもうけて、准大臣に任じられた。
三人の息子の長男は、坂上氏の賜姓を受け朝廷の軍事面に任じせれ、坂上田村麻呂として征夷代将軍として北部民族を征圧する。(青木氏は天皇家の親衛隊として勤める)
次男は、朝廷の3蔵の内の大蔵を担当し、大蔵氏(後に永嶋氏を名乗る)の賜姓を受ける。
三男は、内蔵を担当し、内蔵氏の賜姓を受ける。
(斎蔵は藤原氏)
その後、政治部門でも律令制度の完成に貢献し、軍事、経済、政治の3権を実務に握る結果となり、それまで青木氏を中心とする皇親政治は彼等に取って代わられる事となった。
この帰化人の阿多倍等の台頭が、先ず最初に訪れた5家5流の青木氏の衰退の苦難でもあった。
上記の後漢の阿多倍の子孫の「国香、貞盛」の親子より始まった勢力拡大は、勲功を重ねて、5代後(惟盛、正盛、忠盛、清盛)には「平の清盛」の「太政大臣」までに上り詰める結果となるのである。
しかし、「承久、保元平、治の乱」を経て、「源頼政」(孫の京綱による伊勢青木氏の跡目を受けた)の「以仁王の乱」(1180)をきっかけに「源平合戦」が起こり、「坂東八平氏」等(ひら族)の後押しで「平清盛一族」(たいら族)を倒して、取り戻し、再び、「皇族賜姓青木氏」と同族の「賜姓源氏」の時代となり鎌倉幕府(1192)が樹立したのである。
この時、源頼朝は北条氏らの反対を押し切って「平氏没官僚策」や2度の「本領安堵策」を実施して、賜姓青木氏や賜姓源氏らの一族の復興を計ったことで、これらの皇族賜姓族は、再び、勢力を盛り返した。(これが原因で頼朝暗殺計画は進む)
以上がこの間400年に起こった青木氏との概ねの経緯である。
(京平氏のたいら族は、坂東に配置された皇族第7世族の「ひら族」(坂東八平氏)とは異なる)
話は戻して。
この後、この「桓武天皇」の施政に対する賛成派の次の「平城天皇」(桓武天皇の長男)が、病気で短期間で譲位し、次に天皇となった「桓武天皇」の子供(弟)の「嵯峨天皇」は、これを嫌って「賜姓青木氏」より「賜姓源氏」として変名して皇族賜姓に戻したのである。
「皇族賜姓の経緯と綜紋」に付いて
この時、第4位皇子の皇位継承方式では、対象者がこの時代では不足し、天皇の皇位を保てなくなる事態の問題が発生し、嵯峨天皇期に詔を発して、「第4世皇位第6世臣下方式」に改め、第4世までの間の皇子の内、臣下の賜姓は、第6位皇子としたのである。これが源氏一族である。
これが11代の天皇に続いた11家11流(嵯峨天皇から花山天皇)の源氏一族である。
そして、「青木氏」は、第4世までの皇族の者が、臣下又は下族したときに名乗る氏名とした。
11代の天皇の中で17人の対象者が居たが、青木氏として氏名を遺したのは3氏に留まった。
3氏とは、島左大臣(真人族)の青木氏と、丹治党の青木氏(朝臣族)と、橘諸兄(宿禰族)の青木氏である。
天智天皇の伊勢青木氏から賜姓源氏まで合わせて16代の天皇から出て16家16流となる。
これ等は全て同族で、その綜紋は「笹竜胆」紋である。
5家5流の皇族賜姓青木氏は、後に、清和源氏との同族の血縁を結び、より一体化した。(1170-1185)
(当時の慣習で同等身分の血縁が主流であり、純血を保つ為に同族血族結婚が主流)
その中でも、初代の伊勢青木氏は、清和源氏の「源満仲」の嫡子の宗家「源頼光」より4代目の「源三位頼政」(以仁王の乱の首謀者)の孫の「源京綱(仲綱の三男)」が、宗家「伊勢青木氏」の跡目に入る。
以後(1150年頃)、伊勢青木氏を含む賜姓青木氏は同族の源氏一族と一体化する。
「笹竜胆紋の家紋」の経緯に付いて
文様の竜胆紋の内、「笹竜胆」の文様は12文様がある。
本来、賜姓青木、賜姓源氏の笹竜胆紋は、副紋、陰影紋、丸付き紋等は皇族系として使用していない。
室町期以降の乱世からこれ等の文様が用いられて12文様までに成った。
特に、家紋200選にも入る「丸に笹竜胆紋」は、源氏一族と名乗る者等がこの文様を多く使い増えた。
笹竜胆紋を使える一門としては、5家5流の賜姓青木氏と11家11流の賜姓源氏が使用できるものと成る。
特に、賜姓源氏は清和源氏の一族の頼信系一門が栄えて子孫を多く遺したが、後に、「京平氏」に圧迫されて子孫は衰退し殆ど抹殺された。
(11家11流の内、子孫を遺し得る者としては全17人となるが。結果的に清和、宇多、村上天皇の3天皇が子孫を遺した。その他は門跡院や比叡山僧侶となって子孫を遺す事は出来なかった。)
従って、史実から残存するこの直系5氏とは、賜姓青木氏、近江佐々木氏(天智天武)、滋賀佐々木氏(宇多)、伊豆大島氏(頼信系為朝)、伊勢北畠氏(村上)、摂津太田氏(頼光系頼政?)である。
ただし、北畠氏は、伊勢を始めとして、4代で勢力を高めての織田信長に潰された一族であるが、青森、千葉の等の4箇所にあるが、丸付き紋の笹竜胆紋と表示する書籍が多い。
これ以上の11の文様の笹竜胆紋は、源氏の何らかの支流、分派、分流の血筋を受けてることを理由に源氏一族と名乗っている氏が多いが、徳川氏の様に室町以後の「系譜搾取偏纂行為」(3期)による可能性が高く検証は困難である。
その為に、竜胆の花と笹の間の軸を微妙に変化させて一見して見分けがつかない様な笹竜胆紋が多いのである。
「笹竜胆紋の由来」に付いて
そもそも、この家紋は、竜胆の花と葉で意匠したもので、葉が笹に似ている所から、笹竜胆と呼ばれている。
竜胆は、秋に咲く花で花色が藍の高位の色とされ、賜姓青木氏などの皇族氏の花とされた所から用いられたとされている。
この家紋の文様の記録は、村上天皇期ごろからの書物に出て来るようになり、その使用は、賜姓青木氏以外に、嵯峨天皇期の令により皇族系の者が、臣下する時の氏として青木氏を名乗る通例から、皇族方の公家や皇族賜姓青木氏などが用いる象徴文様とするものと成って行った。
このためにこの象徴文様が、家紋として「大要抄」等の史書に出る事となった。その後、象徴文様は、この文様を使っている賜姓青木氏や賜姓源氏が、統一の家紋としての「綜紋」として扱われるように成った。
(青木氏の元となる大化期からうまれた伊勢青木氏の総宗本家は、代々この家紋を維持して来た。)
これは、次の「青木氏」の氏名の由来にも関わっているのである。
「青木氏の氏名由来」に付いて
この青木という氏名は、”青木”と言う常緑樹から来ている。
樹の軸の色は濃青で、葉も同じく濃青であり、秋にも変色する事は無い。又、経年で著しく枝と葉は大きくなり茂り成長する。
そして、この樹には真紅の10ミリ程度の実を多く着実する。そして、この真紅の実は長期間に着実する。
この樹の特性から、榊などと同じく当時は「神木」として扱われていた。
その理由は、樹の常緑と成長は、永遠を意味し、軸と葉の濃青は、健康の体を意味し、真紅の実は命を意味し、その真紅は血を意味するとされ、このことから全ての「永遠の命」の樹木として「神木」として崇められていた。
天智天皇は、この樹の意味を採り、「第6位皇子」が臣下する際に氏名を青木氏として賜姓したのである。
そして、この”青木”樹の「神木」から民を正義の下に導く高位の者である事を示したのである。
次の嵯峨天皇は、賜姓青木氏を源氏として変名した事も、この意味合いを持たす事にあつた。
つまり、源、即ち、全ての「みなもと」を示し、上記の「神の木」は、「全ての物の源」を意味する事から、同じ意味を持たす事で、変名の賜姓を源としたのである。
今まで(八色の姓の制)第6位皇子を除く宿禰族までの皇位継承から外れた皇族の者が、全て門跡院や比叡山にて僧身したが、下族し臣下する際に使用する氏名が無かった事から、この時、「青木氏」は、これ等の者が、使用する氏名とする事を詔を発して統制した。そして、他の者が、使用する事を禁じたのである。
このことは、原則的に明治3年の苗字令まで原則維持されていたのである。
(ただし、室町末期と江戸初期の混乱期では、無視され、ルーツと家紋の持たない第3の青木氏が多く生まれた。)
以上、2つの青木氏に関わる家紋として、史実から33文様がこの氏の家紋となる。
本来は、総宗本家が維持する次の2つが綜紋と成る。
皇族賜姓青木氏は、「笹竜胆紋」を綜紋とする。
藤原秀郷流青木氏は、綜紋を「下がり藤紋」とする。
これが、次の通りに末裔を広げた。
「皇族賜姓青木氏」は24氏に血縁族を広げた。
「藤原秀郷流青木氏」は116氏に血縁族を広げた。
この二つの青木氏の氏の家紋は、33文様になるが、この内で、「桐紋」(1)と、「職業紋」(3)としての家紋を持つ第3の青木氏の4家紋も特別に意味があるとして記載して含んでいる。
|

Re: 鈴木氏発祥地と周辺の環境
副管理人さん 2007/04/05 (木) 20:34
鈴木邸と曲水園の池
今回、青木氏を離れて鈴木氏ルーツの地元に関わる昔のお話をします。
この鈴木氏が発祥した由来は前回の「鈴木氏のルーツと青木氏」のレポートで紹介ましたが、大変に読まれていますので、その意を汲んで、今度はこの発祥地がどのようなところかを説明して、昔のこの鈴木邸周辺の雰囲気を味わって頂きたいと思います。
又、周囲が概ねどのような自然環境にこの鈴木邸があるのかを、全国の青木氏を代表して、全国の鈴木さんに紹介したいと思います。
では、鈴木氏のご先祖がどのような所に住んでいたかを先ずは偲んでください。
そのためには一部、前回のレポートと重複するところもありますが、ご理解を得て雰囲気造りに努力します。
鈴木邸周辺に纏わる話。
この鈴木氏発祥の藤白の有名な事柄に付いて述べてみます。
この鈴木氏の発祥の場所は世界遺産の熊野古道の最初の出発点(社領の第1鳥居)より約1KMくらいの坂の上の所にあります。坂に沿って右手には直ぐ近くに海が観えるところです。
先ずその付近の環境に付いて述べて行きます。
「藤白神社」と「鈴木邸」と「紫川」
周囲の環境
前回のレポートでも述べました様に、後醍醐天皇や後白河院達の一行が、熊野古道詣での途中で、この熊野権現の第一社目の藤白神社に宿泊し毎回歌会を催しました。
この時、藤白神社の宮司の日高氏の歌の上手さに感嘆して、その功によりその席で「鈴木瑞穂」(すすきみずほ)の姓と名の賜姓を賜ったものですが、ところが日高氏の宮司には子が居なくて近くの農家の氏子の三男を養子に貰い受けて賜姓鈴木氏を継がせました。
これが鈴木氏の初代の三郎であります。
その神社隣には鈴木邸があります。
熊野詣で天皇の一行は藤白に一泊しそこで歌会をいつものように催しましたが、熊野詣では後醍醐天皇は23年間の間に24回訪れたと伝えられています。後白河院は33回と言われています。
この藤白神社からは直ぐ後ろの藤白山(370M)の峠越えを行なわなくてはならないのです。
途中で山越えになると夜になるので、全ての人はこの藤白の山麓の熊野権現の第一社の藤白神社や鈴木邸で一泊するのです。
この藤白神社の社領には参集殿や儀式殿や広い母屋があります。
神社東隣には500坪程度(2500平方)の木々が生い茂る鈴木邸があります。
この神社と鈴木邸との北側20M位の所に大理石の大鳥居がありましたが、この大理石の大鳥居は60年程度前まで海辺の近くの所にありましたが、今は直ぐ近くをJRが通っていますのでこのために移されて母屋横の北側正門前に有ります。
そこより一段低い所(7M)の20M程度の離れた所には海が直ぐに控えており、藤白の浦といわれている入り江がありました。その藤白の浦の西先には「お崎浜」と言う小さい干潟がありました。
(現在は沖合いの1KMところまで埋め立てられているので一部を残してなくなりました。)
神社の南は直ぐに藤白山でその裾の所には孟宗竹の藪があり、この藪より直ぐに急な角度で段々畑の山が控えています。
西側の神社敷地端には、この南の山から流れ込む山水が谷川となり、直ぐに神社に隣接する所には5M幅程度の急激な勾配で、大石の点在する水の豊富な谷川(紫川)が流れております。
更に谷川は200M程流れて、この水が鯔場(イナと言う魚が住んでいる海に繋がっている池)に流れ込み、そして隣の「お崎浜」の海に直に流れ込んでいます。この景色は昔と今も余り変わっていません。
この谷川の両側には、藪椿でびっしりと覆われて目白や鶯等の小鳥が鳴きながら飛び交っている静かなたたずまいの環境です。その小鳥の鳴声は山に響いて自然が作り出した「枯れ山水」の様です。
この神社中央を「熊野古道」(八尺:2.4M)が東から南に貫いていて、神社横の「紫の谷川」の橋を越えると「藤白坂」が始まり峠に向けて続いています。まだこの付近は「藤白の浦」や「名高の浦」が右手に見えています。
この途中で、神社西端の「紫の谷川」の橋から50M上った所に「中大兄皇子」(天智天皇)と皇位継承で争った「孝徳天皇」の子供の「有間皇子」の墓があります。
狂気を装った有間皇子は南紀「白浜温泉」の帰りのこの藤白のこの地の所で、「中大兄皇子」の蜜命を持った「蘇我赤兄」に依って絞殺されます。(蘇我赤兄は中大兄皇子に娘を差し出して皇女を産んでいる)
この神社境内には1000年もの老大楠が境内いっぱいに覆い被さっています。
その境内には、隣の「紫川」から引き込んだ「名水」と詠われた井戸があり、この井戸には亀の形をした紀州名産の大青石盤の蓋が被せられています。(青石は紫石と並んで庭石としては高級石でこの付近で採れる紀州名産)
この亀の形をした青石盤は現在は神社の南側にある本殿の左横に祭られています。
その理由は、鈴木氏の始祖の兄の「鈴木三郎」に続いて、牛若丸(源義経)の第3番目の家来となり、この亀の形の蓋の井戸に因んで、「亀井の姓」を名乗り「亀井六郎」と名乗りました。
この名元と成った謂れの石なのです。鈴木三郎と亀井六郎とは兄弟です。
この兄弟は神社の氏子で「紫川」の橋を渡り藤白坂道を10M行った所に6人兄弟で農業を営んで住んでいました。
藤白神社隣の鈴木三郎の鈴木邸にも、この名水が西側端から引き込まれて、2M程度の小滝を経て、苔むす庭と欝蒼とした木々で覆われた「枯れ山水」の庭の池に流れ込みます。
この滝池の西庭にはS字のようにゆっくりと鯉と共に流れる小川があり、苔生す中央の曲水園の池に流れ込んでいます。
この鯉の住む中央の池をやや東よりに位置する本宅座敷の縁側より眺められるように配置されています。昔はこの縁側で平安歌人達は歌を詠んで楽しんだのでしょう。
この曲水は、更に本宅の南横を通過して東に向けて小川の如く流れて行き、東側にある正門の近くまで届き、ここに小さい菖蒲が生える溜池があり、この池に留まります。
この庭園内の小川の南側には古道が走り、邸より2Mほど高い位置にあり、その斜面には藪椿などの花咲く木々が50M程度の距離に植えられています。
この溜池と東正門通りの真ん中に大きな雄松がありその横には御影石で蓋をした井戸がありました。
実はこの雄松には次のような逸話があります。
牛若丸(義経)は平清盛に追われて熊野権現に庇護を求めての途中、ここで弁慶の交渉の結果を3月も待っていました。
この時、鈴木の三郎と六郎(後に亀井を名乗る)が身の回りの世話をしました。この縁で兄弟は義経(牛若丸)の人柄に惚れて家来にしてもらう様に懇願し許されたのでした。
義経は直ぐ近くの藤白山で山狩りなどをして過ごしましたが、この時に弓を立てかけたと言われる松がこの大松なのです。現在はその3代目の雄松があります。その松の名を「義経弓立ての松」と言います。
この松を巻き込む様に北側には馬小屋と納戸があり、その横を通って一段下の所へと、溜池の水は小川となり20M程度を流落ちて行きます。
そして神社と鈴木邸の北側真ん中下あたりに二つ目の孟宗竹で覆われた大溜池に注ぎ込んでいます。
鈴木邸の曲水園から流れてきた紫川の水は絶えることなくここに流れ込んでいるのです。
この水は直ぐ下の細波静かに繰り返す入江に注ぎ込んでいたのです。(現代は埋め立てられてない)
この様な神社と鈴木邸の静かで花咲く木々で覆われた小鳥が飛び交う環境の中で平安人の「曲水の宴」を催すのです。
更に神社と鈴木邸の静かなたたずまいの中で、神社と鈴木邸とを繋ぐ北側面には桜並木の坂道があり、この桜下では曲水の宴だけではなく、周辺住民の庶民の唯一の憩いの場として、また歌会や大桜宴会が恒例の如く昔は行われていました。
この桜は何度か枯れて現在のはソメイヨシノの桜でと成っています。
この様な環境と雰囲気の中で、天皇や天皇家の人々と大勢のお供の人々の「蟻の熊野詣」で知られる人たちは、ここで恒例の大歌会を催し、一泊の楽しい一日一夜を過ごしたのです。
明日の峠越えを控えて、この「紫川の名水」と地元の地元酒を飲んで英気を養うのでした。
この時、弁慶の郷里でもあり実家でもある熊野権現の宮司でもあつた豪族日高氏(庵沈清姫の物語で知られる日高地方)から派遣されていて、この藤白神社の宮司になっていた一族の日高氏は、毎回にこの歌会に参加してその歌の技量に大変な評価を受けていました。(熊野権現の主な氏 日高氏、久鬼氏、音無氏、田所氏、吉田氏、榎本氏、和田氏、宇井氏、玉置氏)
ある時、天皇は喉が渇いたので水を所望しました。
宮司はこの神社付近の川の水を引き込んだ井戸(亀井の井戸)から汲み上げた水に歌を添えて天皇に差し出しました。
この水の美味さに加えてその歌の余りにも上手さに感心して、歌を返して返礼しました。
この時に歌われた中にこの川の水を絶賛してそれを後醍醐天皇は「紫川」(紫は最上位の色)と詠み名付けられたのです。
この意味は、紫の色は当時では最高の美しい色とされ官位の色付けでは最高位の色とされていました。
例えば朝廷が僧侶に与える階級の最高位の色はこの「紫」であり、「紫の衣」として有名であります。
つまり、最高の褒め上げた水を意味したのです。
以来、この川を「紫川」と称されました。
参考に、「紫」の語源は野に群がって咲く5ミリ程度の小さい野の花の色が、大変愛らしく美しく、万葉の世界では好まれた花であります。
この花が群がって野に一面に咲くので“ムラ”と“サク“でこの草の色を「紫」と呼ぶようになりました。紫の語源説は幾つかありますが、これが語源の元となったものです。
鈴木邸で詠まれたこの紫色の歌があります。
万葉集の詠み人知らずの歌
紫の 名高の浦の 真砂地の 袖のみ触れて 寝かなりてなむ
「名高の浦」はこの藤白神社の北側の直ぐ前に見え拡がる松並木のある海が「名高」と言う地名の所で、その前に小さい入江干潟があり、ここを「名高の浦」というのです。鈴木邸からは藤白の浦の隣の浦で領方の浦は一望できます。
この様な歌を詠って一夜を過ごしました。
そして、明日は峠越えです。
熊野詣の人たちは、難所のSの字の藤白坂を登るのです。
約3時間程度の登坂であります。
その真ん中ほどの平になった山道の途中には、「名所」の「筆捨て松」という所があります。
ここで疲れが出て熊野詣での人たちは一休みをします。
ここからは、遠い先の「瀬戸内海国立公園」の「和歌の浦」が全望できる絶景の名所です。
高いところから眺望すると、和歌の浦は藤白の浦と名高の浦の北側の山向こうある大きい入り江干潟の浦です。
この眺望を詠った万葉の歌
和歌の浦 潮満ちくれば 片男波 芦辺をさして 鶴鳴きわたる 山辺赤人
この「筆捨て松」には逸話があります。
その逸話は概ね次の通りです。
墨屋谷から藤白坂を登って行くと、「筆捨松」というところがあります。
この松の由来は、宇多天皇の御代(887−897)に画家の巨勢金岡(こせのかなおか)が熊野詣の途中「投げ松」の所に来て、眼下のすばらしい景色にみとれて、写生をしようとしていた時、峠の方から少年が降りて来たのです。
この少年もあまりの美しさにひと休みをしました。
お互いに話がはずみ、金岡は「君は何をしに来たのか」と聞いたところ、少年は「私も画がすきで勉強に来たのです」と答えたので、二人は意気投合して絵の書き比べをしようということとなりました。
先ず金岡が松にとまったウグイスを描きました。
次いで、少年は松にカラスの絵をかきましたが、双方とも甲乙つけがたい立派なものでした。
そこで”手をたたいてこの鳥を追っぱらった方を勝ちとしよう”ということとなり、お互いに手を打ってみると両方とも鳥は画面から飛び去ってしまい、またも勝負がつかなかったのです。
困りはてた二人は思案のすえ、今度はその鳥を呼び戻そうと話は決まり、まず少年が手をたたいたところカラスは帰ってきたので、次いで金岡が手を打ってウグイスを呼んでみたが帰って来ることはなかったのです。
無念の金岡はいたたまれず、手に持っていた筆を松に向かって投げ捨てて、少年の勝ちを認めたのです。
このことからこの松を「筆捨松」と云い伝えられるようになったと言い伝えられています。
この少年は熊野権現の化身であったいい、当時、飛ぶ鳥も落す勢いの金岡を諌めるためでもあったというお話です。
その眺望の良さの意味も含めての言い伝えであろうと思います。
(注 巨勢氏は大和朝廷の前の4世紀の半頃の連合政治族の4族の一つで、平群氏、巨勢氏、葛城氏、紀氏であり、巨勢氏は和歌山北部の大豪族と、紀氏は和歌山南部の大豪族であった。巨勢氏は8代将軍徳川の吉宗の母方が巨勢氏である。)
熊野詣の人たちはこの眺望を見てここで一時の休みをとると、後半分の登坂に向かって再び頑張るのです。
再び登り始めると一時間程度経つと、峠の頂上に到達します。
藤白峠の頂上には10軒程度の村があり、この村の真ん中には大きい池があり、大鯉が住んでいます。この上がり切った丁度村の入り口の右手のところに墓所があり、その中には平安時代のものと思われるものがあり、中には源氏の氏名の墓石の古いものもあります。ここで落命したのか村人の先祖の墓かは判りませんが源氏の古を忍ばされます。この付近の清和源氏族には紀州の新宮太郎と云う者が居ました。この末裔でしょうか。
そして、頂上の上がりきった中央のところには小寺があり、村の人たちが住職を代々続けています。
寺の後ろ上側には大きい広場があります。この広場からは和歌山市や海南市が全望でき、実に見晴らしの良いところであります。
「藤白塔下寺」
今では1年中、特に秋になると紅葉になり全国からやって来た人々や遠足で近隣の小学生や中学生等が山ウォーキングします。そして、必ずこの広場で弁当を開きます。見晴らしのよいところでの楽しみの一時を過ごします。
村の池の側には青石で石垣を積み上げたいかにも古を偲ばせる邸宅があります。
熊野詣の人は止む無くここで宵闇になると村人の家に泊まった事でしょう。
ここから暫く下り坂になって棚田の畦道に沿って降りて行きます。
降り切った所に岩屋山という俗称お寺があります。毎年獅子舞や餅投げなどをしての熊野権現のお祭りがあります。ここは加茂郷と言うところです。山と海が控えた土地柄です
熊野権現の影響で平安の頃、紀州の人々が全国に熊野神社の宣伝(熊野神社宣伝隊が編成されたと伝えられている)の為と、紀州の漁業の伝播の為に各地に移動してその土地に定住しました。
全国の熊野神社の加茂神社系はここから全国に広まったとも云われています。
加茂郷や湯浅郷の人たちだと言われていますが、特に静岡、千葉、徳島、土佐に進んだ漁法を伝えたとされ、今でも各地に紀州の地名と同じ地名が多いのはこのためです。
その伝えた黒潮ならではの有名な漁法が在ります。紀州は陸の直ぐ近くまで黒潮が流れていますが、その漁法とは船の後尾に糸を何本も流し、その糸の先には木で作った木の葉の形をした板を流します。この板は釣の「ウキ」の役目をすると同時にこの「ウキ下糸」の下の針に付けた餌が、ウキの波に跳ねる動きに従い餌が生きた餌のように動くのです。この漁法が大変当時(現代も)としては画期的な収穫高の多い漁法でした。この漁法を請われて全国に指導し広めたのです。
現代では世界的に広まっています。カツオやマグロ漁法で使われています。この漁法は紀州から世界に伝わったのです。(俗称パタパタ漁)
この他にも、醤油や味噌造りなどもここ紀州のこの付近の土地から広まりました。これらの為に移動した紀州人が故郷を偲んで加茂神社が祀られ広まって行ったのです。
他にはある高僧が中国から持ち帰った「金山時味噌」の作り方を紀州の人たちに伝えました。
この味噌は色々な野菜と大豆とを加え醗酵させて直に食べるのです。しかし、ある時放置していたこの味噌からうまみの成分のだし汁のような液体が出ました。それでこの液体だけを取り出して製造しましたが大変調味に合うことから作り出されたのが醤油で、その発祥はこの藤白峠を下った所の加茂郷から湯浅地方でした。これ等の技法をこの熊野古道から伝えたのが全国に広まったのです。
そして、これ等の紀州の人々はこの藤白の熊野古道を平安以後も生活道として使われ通って行きました。
この行動は長く続いていました。この熊野権現の第一の鳥居の海南藤白から岩屋さんまでは昭和25年くらいまで海沿いではなく近道の熊野古道を利用し、天秤で担いで海産物や農産物の運搬で人々の盛んな往来がありました。
今では、この山道筋は山道で荒れていますが、山の散策道としては大変に利用されています。。
昔はこの辺までが”藤白の山”と云われいました。
以上が鈴木邸のある藤白圏のこの藤白の神社と鈴木邸の環境です。
次に上記しました亀井氏の発祥の地の由来に付いて更に詳しく述べてみます。
「亀の井」
(亀井の井戸)
亀井の井戸は「紫川」の水の件以来、この川の水を引いたこの井戸のことを「亀井の井戸」と呼ばれる様に成りました。
この井戸は今でも神社中央に遺っています。
この井戸の呼ばれる元になったのは、この「井戸の蓋」が亀の形に似ているので「亀の井」と名付けられたのですが、今でもその蓋は本殿の直ぐ左横に祭られています。
この蓋の石は和歌山原産の「青石」であり、この「青石」は庭石では最高級品の物です。
この「青色」は「紫」と同じく奈良時代末期からこの「青色」は神霊で尊き諸源の色されていました。
又、朝廷儀式では紫に次いで最高位の色として使用されていました。
最も美しい色と好まれた「紫色」と、階級職色の「紫」と同じく、この「青」の色を代表する樹として「青木」の木があり、古来より「神木」として用いられていました。
そして、神官の祝詞では(今でも)「アオキ」ではなく「オオキ」と発音されていました。
この由来は「木の色」とその実の「赤い色」の二つの色に起因するのです。
つまり、常葉の「青色」はすべての物の諸源を意味し、実の「赤色」は血を意味して命の根源を意味したのです。
参考として、この「青木」の樹木は恒葉樹であり、絶えることのない物質の生命の根源を意味したのです。
「青木」姓はこの意味を持つ氏として、天智天皇より賜姓(第6位皇子の施基皇子に与えた氏名)を受けた日本最初の氏名であります。(青木氏の由来)
参考
現代の藤白神社の宮司は吉田氏で、平安初期から朝廷の神職を司る由緒ある官職の持つ氏であります。
吉田氏は現在は藤白神社3代目です。
上記の由来どおり青木氏は皇位の門跡者を祀る神職を司る氏が多い。
この亀の井戸に因んで名乗った亀井氏は現在も鈴木邸横に本家筋の住居があります。
ここも鈴木氏と同じく亀井氏の発祥の地でもあります。
鈴木氏の鈴木三郎と亀井氏の亀井六郎とは、牛若丸(源義経)と武蔵坊弁慶に伴って一度京に戻ります。その後、平泉の藤原京に向かうのです。これよりその鈴木亀井の両氏の兄弟はぴったりと常に寄り添い平泉から逃亡にも付き従ったと言われています。前回のレポートに記述しています。
上記した「青と紫の石」に付いては、鈴木邸付近の藤白山で取れる高級石ですので詳しく述べておきます。
「青石の園」
「青石」は上記した由来からの様に、平安初期から最高貴重品として用いられたものです。
庭石としても高級品である。庭石は主に敷石やふすまの様に立石として用いられる。これは石が平石が多いことによります。
この石は又アルカリ性が強くコンクリートの原料として使用されつい最近まで藤白の山で採取していました。
現在ではこの青石も少なくなり、県外不出の条例が出ている現状です。
鈴木邸付近の山の産物なのです。
この鈴木邸にもこの石が敷き詰められています。
「紫石」と「紫の硯」
この「青石」と同時に、「紫石」もあり、この「紫石」は平安期から和歌山市の浜の宮から海南にかけて採取された石で、これも上記した「紫色」の由来から朝廷内で「飾り石」として用いられました。
又、日本初国産の「藤白墨」と同じ時期に、「紫の硯石」としても加工され高級品として朝廷内で使用されていました。
当時は「市場経済」ではなく「部経済」(べ制度)として殆どの加工品は一度朝廷に納入され、その後に市場に払い下げられると言う方式であったので「紫の硯」は「藤白墨」と同じく専売品として庶民には手に入る物ではなかったのです。
この様に「紫の硯」は「藤白墨」と「紫の硯」とは一対として庶民には手に入らない品物として扱われました。
注 「部制度」とは全て一次製品はその専門の職人が集団となって作り上げ、その作り上げた製品は一度朝廷に納められ、その後余った製品は市場に払い下げられると云う経済方式でありました。
この技能集団は、例えば、服を作る集団であれば「服部」(はっとり)と言い、陶物を作る集団は「陶部」(すえべ)、海のものを加工する集団は海部(かいふ)等全て後ろに「部」が付く姓はこの子孫であります。
そして、更に、この子孫は中国後漢の民で渡来人であります。(詳細は青木氏氏のサイトの研究室にレポートしています)
「大化の改新」(645)前後を挟んで200万人の17県の民が、後漢の光武帝より第21代の献帝の子の石秋王とその子で、阿智使王とその孫の阿多倍王の二人の王の下に共に大和国に帰化して来ました。そして、66国中32国を征圧しました。
この阿多倍王は天皇家(敏達天皇の曾孫の芽淳王の娘)との血縁で発祥した子孫の坂上氏、大蔵氏、内蔵氏であります。
後に大蔵氏は永嶋氏に変名します。特に関西より西に多く子孫を残しています。平家の清盛の一族とその5代前の先祖はこの阿多倍王の子孫です。
坂上氏は北陸に子孫を遺しました。この3氏の勢力は朝廷の3権(3蔵と言う)のうちの2権を握りました。
この部を管理していたのは蘇我氏で、天皇家より勢力を握ったのはこの「部制度」とその渡来系の一団を管理していたことによります。朝廷の役職は「国造」(くにのみやつこ)です。
万葉集 詠み人知らず
紫の石を詠んだ歌
紫の 名高の浦の なびき藻の 心は妹に よりにしもを
さて、次は周辺にはこの鈴木邸より20M東に戻った所に日本最古の「藤白墨」(紫の硯石と共に)が採れました。
この藤白墨の採れる場所を「墨屋谷」と云います。
「藤白墨」
奈良時代より中国より輸入されていた墨は平安中期に後醍醐天皇に命じられて日本各地で墨の試作を試みられたが中国産に勝る「墨」は見つかりませんでした。
そこで、朝廷は「熊野古道」沿いに「炭焼き」する村を見つけました。
この村で、「熊野神社」の「第一の鳥居」の近くに「藤白村の炭」がある事を発見し、この「炭焼き」で出来る「煤」をかき集めて、それを練り、牛の皮を煮詰めた「にかわ」で「墨」を固めて作ってみました。
ところが、この「墨」が中国産より優れ、「紫色」を滲ませる墨色であったので、大変に喜ばれて以来、朝廷の専売品として生産されて、その後、大々的に生産されて、徳川時代まで、その時の幕府専売品として扱われました。
この「藤白墨」は徳川時代までに四、五種類のものになっています。
この「藤白墨」は海南から有田地域まで分布する「うばめ樫」の木を用いて造られました。
この「うばめ樫」はどんぐりの木の仲間で、通称「ばべの木」と呼称されています。
この藤白村で生産される「藤白墨」の生産場所は史跡として指定されています。
この「うばめ樫」は海南地区では今も現存します。
又、この生産場所も当初はこの場所を古来より藤白の「馬の背坂」と呼ばれていました。
丁度、馬の背中のような真ん中が下がったような形をしている坂でありました。現在は道拡幅の為に少し変わっています。
藤白のこの付近ではうばめ樫の木が少なくなり江戸時代には南紀の有田方面に生産場所を移動して行きました。
しかし、鈴木邸付近周辺のところには時々は藤白墨の片鱗が出てきます。
この「藤白墨」と「墨拓」も個人が所有して現在も保存されています。日本国産最古の墨です。
(現在でも宮内庁正倉院にはあるのではないでしょうか。大正14年にはあった事が確認出来ています。)
「熊野一の鳥居」
本来、熊野古道と呼ばれる最初の起点は、この藤白の入り口の鳥居のあったところから始まるものです。
つまり、この「鳥居」は熊野神社の「最初の鳥居」であり、「熊野神社」の社領の入り口と言うことになります。
藤白の「馬の背坂」を北に下り、「日限坂」との交差する点に存在しました。
古道の由緒ある「一の鳥居」です。ここから藤白峠に向けて坂が始まるのです。
1キロ程登った所から、馬の背のようになった道が鈴木邸まで続き、この「馬の背坂」には「熊野古道」参詣の「道宿」として二つの「王子」(参詣のための道中の宿)があり、「一の鳥居」から50メータほど古道沿いに東に寄ったところにある「祓戸王子」と、「藤白神社」のところに「藤白王子」とがありました。
この王子は一般には寺や神社が営んでいました。
天皇の熊野詣では一行はこの王子に分散して宿を取りました。天皇は藤白神社や隣の鈴木邸に泊まります。
「藤白王子」と「祓戸王子」
上記した様にここには一般の人たちが泊まる「藤白王子」と「祓戸王子」と言う「熊野古道」の2宿が存在しました。
「熊野詣での蟻の行列」として平安朝から呼ばれてこの8尺程度の狭い道を参詣者は途切れることなく歩いたと言われています。
現在でも3.6Mの道幅ですが、古道の出発点としてのこの静かな環境の周辺が「熊野古道の世界遺産」の影響を受けて、昔と同じ様に古道を訪れる人でいっぱいなのです。
そして、昔の参詣者は藤白山の難行の「藤白坂」を目の前にして、ここで一泊して休息して朝早くに起きて「藤白坂」に挑んだのです。宿はいつも一杯だったと言う事です。
泊まれないときは寺社や民家や3キロ程度戻った所の春日王子に戻って宿泊しました。
当時は約1里(3.75=4キロ)程度毎に王子がありました。
宿は泊まりが中心で食事は周辺の農家の人たちが仕出しをするという方式で現在の旅館とは違っていました。
この時、この王子に留まった人たちはこの藤白神社から西の方に向かって「藤白の浦」と「名高の浦」と「和歌の浦」の景色を見てその美しさに感嘆しまた登るのでした。
ここで詠まれた万葉時代の歌は多く遺されています。
代表歌として
和歌の浦 汐満ちくれば 方男波 芦辺をさして 鶴鳴きわたる。
「鈴木」と「亀井」の館
先ず、鈴木姓の発祥について上記した歴代の天皇が参詣した中で後醍醐天皇が藤白坂を上るに際して前日にこの藤白神社に投宿した時、恒例の宴を催しましたが、この時、天皇はこの日高氏の宮司の歌を褒め、褒美として「鈴木」姓を賜姓しました。(名は瑞穂)
しかし、この日高氏には子供は居なかったので、氏子の亀井(後に名乗る)の家から三男の三郎を養子に貰いうけて鈴木姓を継がした。
丁度、この時に鞍馬山の牛若丸(清和源氏の分家筋の頼信系の九郎)は平家に追われていた。
弁慶の父が田辺では熊野神社の宮司の一人であつた事からその庇護先を求めて弁慶と共に熊野神社に向かった。
この時、牛若丸と弁慶の一行はこの藤白神社に立ち寄り弁慶だけが実家の日高に向かいその後、熊野神社に向かったのです。
この間、この牛若丸の身の回りの世話をしたのがこの「鈴木」の養子となった鈴木三郎でありました。
そして、3月ほどの滞在のうちに、この「鈴木三郎」は牛若丸の家来になる事を許されました。
そこで、この三郎の実家の弟の六郎も牛若丸の世話をしていて兄弟二人が家来となったのです。
この六郎も姓が必要となり上記した有名な「亀の井」にあやかり「亀井」の姓を起して「亀井六郎」と名乗り武士となり、牛若丸に付き従いました。
弁慶は熊野神社から庇護を断わられて戻り、共に家来の三人と共に再び京の都に戻り、その後、一行とこの兄弟は奥州藤原氏を頼り平泉へと向かうことになつたのです。
これが鈴木と亀井の姓の発祥となり、全国的に子孫を広めた原因ともなりました。
この後、この藤白の鈴木と亀井の縁者は身内を応援するために、平家の監視を逃れるために「熊野参詣宣伝」を名目に各地に向かい子孫を増やす作戦に旅立ったのです。
当時は自らの勢力を広げるために旅に出てその土地毎に子孫を遺していざと言うときにはこの子孫が駆けつけると言う戦略を取るのが普通でこれを「戦地妻」と呼ばれました。
その結果、八島と壇ノ浦の平家との戦いには12000人の身内の軍勢が義経の周りに集まったとされています。
頼朝から派遣された「坂東八平氏」の力を借りずに、この身内の軍勢が先陣を切り勝利を決定付けたのであります。
「義経弓立て松」
歴史上で義経一行は二度ここ鈴木屋敷を訪れたとされています。
この時、一度は上記の牛若丸時代の時と、二度目は二つの戦いの時に、熊野水軍と紀水軍と攝津水軍と伊勢水軍を味方に引き入れるための説得工作に赴いた時に訪れています。
「曲水の園」(曲水の宴)
この鈴木邸には平安朝時代に和歌を詠み、それを山から引いた「紫川」の山水を邸の池に流しこみ、その流れに乗って流れる短冊を入れた小船に和歌をすばやく詠み返歌して返してゆくという平安朝の歌儀式の社交池です。
熊野神社参詣に来る貴族達の一時の休息の場となりました。
この曲水の池は今も現存します。(上記)
そして、この曲水の園は自然の景観に溶け込み「枯れ山水」の形式に造形されていて、その曲水の池と溶け込み自然の景観を造り出しています。
この「枯れ山水」は人間の作り出した創造美ではなく、「自然の力」による美を強調し苔や自然の石組み樹木の成り立ちを生かして園として作り上げたもので、渓谷の谷川の成り立ちを思わせる自然美を追求したものです。
古来よりその美は作られていたが戦国の時代に廃れ、再び桃山時代からその美が見直されるようになりました。
しかし、昭和期には再び創造美が求められて消えました。
然し平成期の安定期に入り再現され始めていますが、世と人の心の安定に左右される落ち着きのある美です。
この鈴木屋敷の「曲水の園」と「枯れ山水」は現在に於いて貴重な美の財産でとして遺されているものです。
この時に歌われた万葉の歌は次ぎのとおりです。
黒牛潟 潮干の浦を紅の王裳 裾ひき行くは誰が妻 (潮干:ひかた 現在は日方の地名 黒牛潟:黒潮潟の昔の呼称)
古に 妹とわが見ぬばたまの 黒牛潟を見ればさぶしも
黒牛の海 紅にほうももしきの 大宮人しあさりすらしも
紅の海 名高の浦に寄する波 音高きかも逢わぬ子ゆえに
紫の名高の浦の名告藻の 礎にまかむ時待つ我を
(読み人知らず)
鈴木邸付近には、現在は絶滅したと言われている平安人に大変好まれた「まゆみ」という花がありました。
この花は「恋歌の花」として親しまれていました。
「まゆみの木」
この木は平安朝の時代にはこの熊野古道沿いに沢山生息していたとされ、この木の持つ印象から沢山の歌が万葉歌として読まれています。
この上記した曲水の宴でも読まれたことであろうことが想像されます。
しかし、現在はこの木は殆どなくなっています。
この木の花は淡い赤紫の花と真っ赤な実をつけて長く咲き誇る花で、その花の形は少女の可憐な姿を想起させ、其処からは清廉な恋心を詠んだ万葉歌が多いのです。(万葉集二歌選択)
「まゆみ」とは、基字は「真弓」とされ、真の意は語源は「目一杯」の意を基とし、真実は「目一杯の実」、つまり、「目一杯の誠」となります。この様に、「真の弓」となり、「目ッ一杯に弓を引いた射する寸前の状態」をさします。
況や「まゆみ」の意は「目一杯の愛」であり、純心無垢く、清廉な熱愛とし、「少女の愛」とされます。そして、その意に合う、何とも云えない真っ赤な花色と半年も長く咲く花とその愛らしい花の形をしていて、葉は1年近く紅葉しても落葉しない性質で次ぎの葉が出るまで落葉しません。その葉の形が弓を一杯に引き込んだ弓形をし、木の軸は花と葉に出過ぎぬ様に葛のように頼りなさを表しています。しかし、花火が開いた時のように柳のように垂れ下がり大木になるのです。
大変、繊細な木で環境や土壌が少しでも変わると枯れたり、花を咲かせずに居ます。
「まゆみ」にはオスメスの2種があり、雄木ははしっかりしていてなかなか枯れません。
詠われている「まゆみ」は雌木の様であります。
この様な何とも云えない愛のはかなさの木質から繊細な万葉の歌人はこの木を男女の恋愛歌と観たのでしょう。
絶滅種の雌雄の「まゆみ」は現在、神社の近隣のある個人の家で何とか育植されています。
彼の有名な「てるてる姫」で有名な歌人で官僚の小栗判官もこの藤白神社の「馬の背」付近で姫に宛てて詠んでいます。
恐らく、昔は、この「まゆみ」が熊野古道沿いに一杯咲いていたのでしょう。
ちなみに、二首を次ぎに示します。
みこもかる しなぬのまゆみ わがゆけば うまひとさびて いなといはむかも
解説
信濃の弓を引く様に、私が貴方の気を引いたなら、あなたは都人の様に、嫌ですと云うでしょうか。
みこもかる しなぬのまゆみ ひかずして しひさるわざを しるといはなくに
解説
貴方が信濃の弓を引くこともしないのですから、私が嫌ですともいいともいえる訳がないでしょう。
この様に、沢山のこの「まゆみの花」の歌が詠まれています。
現在では京大の調査では熊野古道の新宮付近の山奥に生息するのみとなつています。
しかし、この花は現代では熊野古道の万葉歌としてその花名の愛らしさと花のその可憐さが愛好家には好まれています。
鈴木邸の周辺環境の一つとして、藤白峠の始まり点で、神社より直ぐ近くで、このところから氏子の民家が存在する所ですが、”やれやれ”と峠を下りきって”鈴木邸で一休み”という所で気を緩めたところで絞殺されたと見られます。
鈴木邸と有間皇子は550年位の時代差がありますが、周辺では一つとして捉えています。それは有間皇子も鈴木三郎も同じ悲運の者だからです。
「有間皇子」
皇位継承問題で痴呆を装う有間皇子は白浜の湯に行き、その帰りに藤白の坂の麓で蘇我赤兄に絞殺された事件が起こる。
有間皇子は孝徳天皇の子供であるが、中大兄皇子との権力闘争に巻き込まれて狂気を装い白浜に逃げ延びるが中大兄皇子の意を受けた同行の蘇我赤兄に絞殺される悲しい事件の場がここで起こります。
この直前に遺した歌があります。
家に居れば いい盛る椎も草枕 旅にしあればしいの葉に盛る。
現実には山に生息する椎の葉には飯は盛れないけれど、いい(飯)とかけて詠んだもので椎の木は山の意から旅の意味を含み、皇位継承問題で狂気を装いそして旅に出なければならないわびしい気持ちを詠んだ歌です。
昔は旅に出た時は柏の木の葉に包んだ乾し飯を食べていました。
地方に依っても異なりますが、和歌山地方では柏の木は少ないので、ハート形したさる茨の葉を用いました。
五月の祝いに作る柏餅はこの葉で作る習慣は未だ残っています。
「小栗街道」
熊野の「蟻の熊野詣で」の通り、一年に一回は参詣するためにこの熊野街道を通りました。
この時、天皇に同行した歌人の「小栗判官」と「てるてる姫」の逸話の通り、この「馬の背坂」付近で「藤白の浜」見て「てるてる姫」に宛てて詠んだ歌が有名です。
此れに因んで歌人の間ではこの付近の丘の事を「小栗街道」と呼ばれる様になりました。
この浜は現代の位置とは異なり、この古道の直ぐ崖下が波打ち際でありました。
昔は「藤白の浜」または「藤白の浦」と呼称されていました。
「藤白獅子舞」「藤白相撲」
熊野詣での朝廷の人たちにはこの獅子舞を見せたとされています。
藤白の獅子舞は熊野権現の各社で行われている五穀豊穣の祭りに神に奉納する行為の一つです。
この獅子舞は日本各地の熊野権現の支社では行われているものです。
平安中期ごろからこの獅子舞は行われていて歴史上伝統ある祭りの奉納する行為の一つです。
この舞はその昔神の使いの命が獅子を退治して村を平安に保ったという言い伝えから来たもので、獅子とは架空のものだですが、この世の全ての悪を獅子に見立ててこれを退治して平安を願う庶民の祭りです。
これと同時に藤白には「藤白相撲」も奉納されていました。
最近まで行われていて、50年前位までは祭りに「子供相撲」が夏に奉納していたものです。
「藤白桜」
この藤白神社と鈴木邸には昔から周辺に沢山の桜が植えられていて、春には山越えをして遠方からも訪れて周辺が見物人でいっぱいで立つところもないくらいの盛況ぶりでありました。
当時も鈴木邸付近では花見の見物と熊野詣ででいっぱいであったことが予想できます。
未だ、この時分は神社の鳥居の直ぐ坂下は浜辺であり、その景色は万葉の人が褒めちぎるほどの景観を示していました。(上記の歌)
現在は世界遺産の決定で再び桜見物はもとより、古道散策が盛んになり、この狭い古道は昔の「蟻の熊野詣で」と同じくらいに賑やかになっています。
そして、その景色と共に「藤白の山」と「藤白の浜」と「藤白の桜」として平安の古来より有名でありました。
この景観を詠った詞が地域の小学校の校歌として残っています。
桜は主に現在は染井吉野桜と山桜の群生であります。
現代はその一部の子孫の桜が残っている程度です。
この様に、鈴木氏発祥の土地の鈴木邸の周辺の環境は万葉の時代を偲ばせる雰囲気が多く残る所ですし、名所旧跡の多いところです。
周辺にはまだ鈴木氏や亀井氏の一族末裔が多く残る所です。
しかし、残念な事ですが、周辺は鈴木邸近くまで住宅が立ち並び、住民の歴史意識が低下し土地の謂れを知らない人たちが殆どとなり、次第にこの伝説が消えつつあることが気に成ります。
この鈴木氏のレポートをする事で、出来るだけ多くの各地の鈴木氏や歴史ファンの記憶に留めて欲しいと思います。
敢えて、現在の青木氏のブログでは「鈴木氏のルーツと青木氏」のレポートが青木氏以外の多くの人たちに読まれていることを考えて、青木氏ブログサイトから「鈴木氏の環境」のレポートをした次第です。
以上。
|
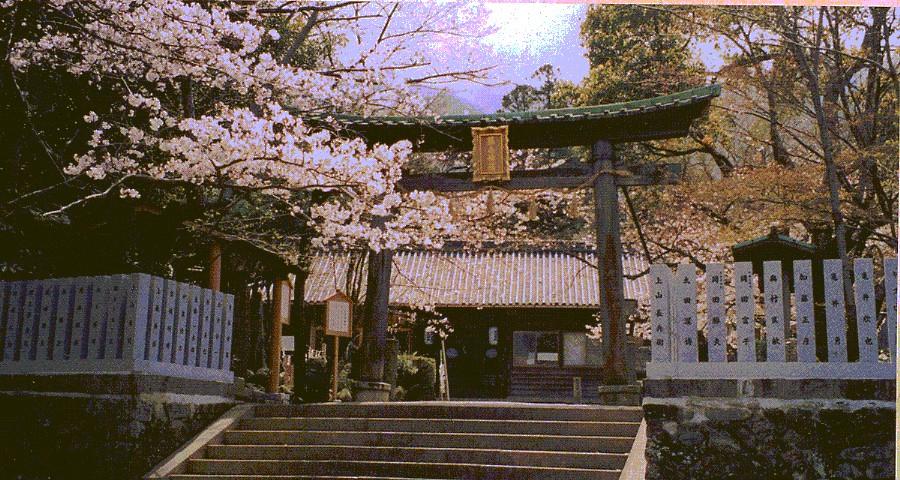
本文では少し青木氏と離れて鈴木氏の子孫が広がった理由に付いて検証してみたい。
鈴木氏と云えば日本の姓のなかでも非常に子孫を広げた氏の一つですが、この氏に付いてどのような経緯から発祥して広がったかに付いて見てみる。
鈴木氏は今NHKの大河ドラマの義経に家来として本来は出て来るはずである。
多分、ドラマの喜三太とか云う義経の身の回りの仕事をしている家来が鈴木三郎であると思う。
この鈴木氏の発祥は熊野古道の熊野詣で各天皇が詣でたことから興った氏である。
後醍醐天皇は24年で23回も詣でたと云われているが、後白河上皇は33回で年に一回程度である。
この熊野詣で和歌山県海南市藤白に熊野古道の熊野神社の第一の鳥居がある。正式にはここから熊野古道と言われる。
つまり熊野神社の社領の一番最初にある鳥居の事である。
この鳥居から藤白坂を登って1キロ程度上りきったところから、古代の呼び名の「馬の背」という坂道を通り(馬の背中のようになった坂)、200メートルくらいのところに藤白神社がある。熊野系列の第一番目の神社である。(熊野神官5氏の一つ日高氏が宮司)
千年以上の歴史を思わせるような大きな楠木に囲まれて静かに佇む神社である。後ろには静かに流れる谷川がある。この谷川は「紫川」といって非常においしい水が飲めるきれいな川で、万葉の歌にも多く謡われている。
この神社の隣に鈴木屋敷がある。
神社の北東の方向200m海よりの鈴木屋敷から見える所に鈴木氏の菩提寺専修寺(浄土宗)がある。
この神社の宮司は元は日高氏である。 (現在は18代目吉田氏 吉田氏は奈良期の朝廷神官官僚)
日高氏は南紀(和歌山の南地域)にある日高川の付近の土豪で熊野神宮の宮司の一族である、この日高氏の宮司がこの藤白神社の宮司になった。
日高川は歌舞伎で有名な庵陳清姫の舞台となったところである。
又、武蔵坊弁慶も日高氏宮司の末裔である。
このり藤白神社は毎年熊野詣で訪れる天皇の一団をもてなしをする。
この藤白神社からは372メータの藤白山の山越えをするのでここで一団は泊まる。
この泊まるところを「王子」と云う。
この付近には熊野詣で尋ねてきた人を留める春日王子、祓戸王子と藤白王子とがある。藤白坂山頂には塔下王子があり、この4つの王子で人々は宿泊する。
この王子や周囲の民家の屋敷に泊まって一団は歌会を催すのが恒例である。
小栗判官や山辺赤人や柿本人麻呂など平安歌人が多く通ったところである。
そして、又この地は習字の墨を日本ではじめて作った場所でもある。(藤白墨)
この墨は後醍醐天皇に命じられて日本各地に探し求められたが見つからず、熊野詣でこの地に来て海南地方から少し南にある湯浅地方に分布している「うばめ樫の木」(通称ばべの木)で地元の炭焼きの者が造っている炭を観て、その煤で作ってみたのである。
ところが、この墨が其れまでは中国から輸入していたが、それに勝るとも劣らず墨が作れる事に気付いたのである。この墨が日本最古の墨で「藤白墨」と云うのである。
他の墨と較べて紫色の色調を示す墨色である。特に植物花鳥にその独特な色合いと柔らかさを深く表す優れた墨である。
この墨は天皇家だけに納入された特別品であつたし、後の代々の将軍家に納入された。そして、最後は徳川家の専売特許とされた。この墨を保存されている天皇家から拝領した最後の墨が個人の家につい最近まで保存されていたが、盗難紛失した。
しかし、使用中の片鱗の幾つかと魚拓ではないが「墨拓」は保存している。天皇家の保存品以外には日本最古の墨の片鱗だろう。
これが現代では多くに使われている備長炭の炭である。
(この藤白墨が取れた場所から50メータも行ったところに鈴木屋敷がある。)
この馬の背の坂から昔は万葉の唄で知られる和歌の浦も見渡せる位置にあり、この景色や藤白の浜の藤白の歌を謡った万葉の歌は多く残されている。
和歌の裏 潮満ちくれば 片男波 芦辺をさして 鶴鳴きわたる。(山辺の赤人)
後醍醐天皇は此処に毎年の様に泊まり歌会を催した。この時、この宮司が天皇にもてなしといつもの様に献歌を披露した。
この藤白山から流れる谷川(紫川)の歌を披露した。
この歌を聞いた天皇は大変に感心して、褒美としてこの日高氏の宮司に「鈴木」という氏と名を「瑞穂」(ほずみ)として与えた。所謂賜姓である。
(鈴木姓は穂積と言う言葉から来ていると言う説もある。瑞穂の襲名の名は穂積から来ているものと思われる。)
大変に喜んだ宮司だか、この宮司には子供がいなかった。
そこで、神社より15メーターほど坂を登ったところにある農家の氏子(後に亀井姓)の三男を養子に貰い、鈴木姓を継いだ。これが最初のルーツの鈴木氏である。
丁度、その時、鞍馬山の牛若丸が僧侶になる事を迫られて、これを拒否して平氏より追われていた。
この時、五条の橋で家来になった弁慶が居た。この弁慶は日高地方の田辺郷地方の熊野神社別社の宮司の日高氏の息子であった。(藤白神社も縁者日高氏である)
この弁慶は大変に乱暴であり、土地で問題をよく起していた。
そこで困り果てた宮司の父親は比叡山の僧兵として送り込んだ。
しかし、ここでも問題を起して追い出される始末である。
この後、五条の橋での弁慶と牛若の言い伝えである。
この主従は平泉に逃れる前に、熊野神社の本宮の宮司に牛若丸の庇護を願い出るために旅をしてこの藤白神社まで辿りついた。
此処で、弁慶はこの藤白神社の縁者鈴木氏に主を預けて熊野神社に交渉に出かけた。
この時、この牛若丸の面倒をこの鈴木氏の養子の三郎に委ねた。ほぼ3月滞在することになるが、この時、この三郎の弟の六郎も牛若丸の下働きをするようになった。
その後に兄の鈴木氏は牛若丸の家来になつた。このせいもあり、六郎も牛若の家来になった。
六郎はこの神社の天皇から褒められた紫川の美味い水の井戸の蓋の形が亀の甲羅の形に似ているので「亀の井」と呼ばれていて、この亀の形の蓋を採って「亀井」と称した。
今でもこの井戸と蓋は藤白神社に祭られている。
つまり、このような経緯から、鈴木氏と亀井氏とはルーツは兄弟である。そして、弁慶と養子であるが鈴木三郎も縁者である。
この二人の鈴木氏と亀井氏との兄弟は弁慶の帰りを待った。
弁慶は熊野神宮の拒否された答えを持って帰ってきた。
熊野神宮は牛若丸を庇護を拒否することで、平家との摩擦を避けたのである。この頃は熊野神宮は平家側に味方していた。
天皇もまだこの頃は平家にたいして対抗していなかったことから、天皇から保護されている熊野神宮の立場であったから、断わったのである。
鈴木の三郎と亀井の六郎の兄弟の家来と弁慶は、牛若丸に付き従い京に戻り平泉に旅立つのである。
NHKのドラマは史実と若干異なる。小説なのでやむ終えないことであるが。他にも2、3史実と異なる事があったので実は私はNHKに意見を申し上げた。
このはっきりした史実の家来の構成も異なっているのであるが、上記した喜三太の役柄は鈴木三郎と亀井六郎の牛若丸の家来としての役目である。
この二人の兄弟は義経の最後までつき従ったのである。
そこで、義経の生存説は、この二人の兄弟の逃亡のための段取りをつけて寺の句里の後ろがわから逃亡したのである。
そして、蒙古に逃げ延びたとするジンギスカン説が生まれたのである。
この説の根拠として、ジンギスカンの紋章は真さに「笹竜胆」の源氏の紋と非常に似ていてそっくりである事と、ジンギスカンだけこの生い立ちは、かの放牧民の中で不詳であり、記録には”天から舞い降りてきた救世主”として記録されているのである。(疑問)
そして、このジンギスカンの後ろに何時も影の様につき従う二人の家来が居たと記録されているのである。
このジンギスカンが現れる前はこの集団を率いる一族の子孫は居たが、この突然天から現れた者に統率力があり、周囲の各豪族の集団はこのジンギスカンに任す事を決めて、本来成るべき元の子孫を掟により抹殺したと記録されているのである。蒙古の掟として実力のある者を長とする定めに従いジンギスカンを主としたとするのである。
(この蒙古では各豪族の集団指導体制でこのなかから戦いにより武勇実力に優れた者を首長として決める掟があり、絶対に出生がわからないと言うことはないのである)
ジンギスカンの顔かたちと義経の顔かたちとは非常に良く似ている。
そして、弓と馬の操作が上手く機敏であり、恒に戦いの先頭にたち突き進んだと記録されている。平家との戦いと類似し物語る。
他国のジンギスカンの紋章が源氏の紋章とが類似一致することは偶然を超えている事と2度の蒙古襲来もこの説を説明する要素に成り得る。
句里の中に入った義経の遺骨は発見されなかった事と、弁慶の仁王立ちの理由もこの時間を稼ぎ、縁者の鈴木三郎と亀井六郎を伴なわせて逃す手立てであった筈ずである。突然に攻められたわけでもないので十分に検討する時間はあった筈である。
また、北陸地方には逃亡中にこの主従を一時匿ったとされる別名で「判官さん」と言う一族がある事も突き止められているのである。
十分に考えられる内容である。
さて、この二人の兄弟の鈴木氏と亀井氏が何故に子孫を増やしたかという事であるが、義経には初期に付き従う土豪集団はなかった。”いざ源氏”という時に源氏の味方として従う一団をつくらねば成らない。
そこで、各地を移動するときに、必ず当時の慣習として、「戦地妻」といって土地の豪族との血縁関係を持ち生まれた子供は源氏の支流一族の者との朱印状を受けて、土豪側は一族の安全を図り、義経側はいざと云うときには駆けつける味方とする目的があり、盛んに此れを行ったのである。時には娘を、場合に依っては妻を出すということまで行ったとされている。
このことは現代の常識では異常であるが当時としては氏家制度の中で特別な社会慣習であつた。
特に、この兄弟は義経の直の家来としてこの役目を負っていたのである。
義経は清和天皇の第6位皇子(経基王)の孫(満仲の子)三男頼信の末裔である。故にこの戦地妻行為は出来ない。
従って、この兄弟の二人には、地元記録によると紀州にもこの「一族造り」の応援団が出来て、「熊野詣宣伝隊」と称して密かにこの二人を追って手伝いをして地域毎に鈴木氏と亀井氏の子孫を多く残してくる旅をして応援をしたと記録されている。
名目は「熊野宣伝隊」であるが、この宣伝隊は既に、天皇が一年に一度以上も熊野詣でする位で、「別名、蟻の熊野詣で」と称されるくらいであった。何もいまさら宣伝隊ではない。
仮りにするとしても、新宮の熊野神社の膝元から始まればよいものを一番熊野神社から遠い神社の藤白からその宣伝隊が興るのはおかしい。
平家の目をくらます藤白の鈴木氏と亀井氏の一族の応援であったのであろう。
その証拠に義経が一の谷の戦いの時は義経の12000の直属の一族の兵が各地から集まったと記録されている。「ひよどりの崖落」の1200は直近の武者たちであったとされる記録から観ても納得できる。つまり、各地の鈴木氏と亀井氏の血縁者、伊勢の三郎の血縁者等が集まったことである。だから義経は強かったのである。
義経に頼朝から監視役としてつけられた坂東平氏の熊谷氏、梶原氏の主軍を使わずに義経自らの軍で行動を起す軍力があったからこそ成し得た単独行動であった。
全く直属の家来の無い頼朝と違う所である。
義経の”源氏一族で幕府を”とする考えと、坂東八平氏の裏打ちされた頼朝の考えとの食い違いによる兄弟の摩擦である。結局は幕府3年以内には頼朝と頼朝の子孫は全て抹殺されてしまい、坂東平氏の幕府となってしまうのである。
この義経を裏から支えたのは鈴木氏と亀井氏の二人のであり、その貢献は実に大きいのである。しかし、このことは余り歴史上には出てこない。今回の大河ドラマにも出て来ないのである。
しかし、この鈴木氏と亀井氏との子孫を増やす作戦に出た事が大きな成果を生んだ。この一族最後まで義経に付き従い、北陸への逃亡も付き従ったことが子孫を各地に残す結果となったのである。場合に依っては蒙古にも鈴木氏と亀井氏の子孫がいることにもなる。
実は私は海南市の藤白神社のこの全国に広まった鈴木氏の本家の最後の末裔の人を知っているのである。本家鈴木氏は絶えたが、亀井氏は依然として、この鈴木屋敷の側に本家が現存するのである。地元では遺された氏子の実家が亀井氏を名乗ったところから亀井氏は大変多い氏である。鈴木氏は三郎が移動していたので比較的少ない。
全国の鈴木氏と亀井氏とは元は兄弟である。
このような経緯によって鈴木氏は発祥した。そして同じく亀井氏も同じルーツで発祥したのであるが亀井氏のことは余り知られていない。
亀井氏も鈴木氏と比べて多くの子孫を各地に分散して残した。
この様に子孫の広がりに付いて何が原因しているのかと言うことを青木氏と比較してみる。
皇族賜姓青木氏や源氏一族等の子孫の広がり方は全く異なる。青木氏には家柄と言う当時では絶対視された考え方で、子孫を鈴木氏や亀井氏の「戦地妻的な血縁」で増やしたものに対して「政治的な血縁」で増えて行くのとではその勢いは異なる。
藤原秀郷の青木氏や進藤氏や長沼氏や長谷川氏等は守護などの官職の赴任でその土地に子孫を残してゆく「戦略的な血縁」と阿多倍の一族のような渡来系族の部制度による「経済的な血縁」と「武力的な血縁」で子孫を一時多く遺した京平氏と「集団的な血縁」で子孫を温存した坂東八平氏等色々な形がある。
そして、その形はその氏の宿命的立場に依って関わっていることに気付くのである
この様に、子孫を遺す方式を研究すると、「戦地妻的な血縁」「政治的な血縁」「戦略的な血縁」「経済的な血縁」「武力的な血縁」「集団的な血縁」のパターンがある事に気付くが、現在から考えた場合、どの血縁が一番子孫を遺したかは一概には云えないが、結果としては家紋200選の中では、「戦地妻的血縁」が確実に子孫を多く遺していることになる。
これは、一族に関わる全ての”しがらみ”の大小が原因しているのであろう。
この”しがらみ”のパラメータで並び直すと子孫を多く遺した順に並ぶような気がするのである。
そして、「各地に散在して血縁」していることも原因している。
この点から考えた場合は、賜姓青木氏は少ない事に納得する。
賜姓青木氏はしがらみも多いし、5地方に限定し散在の血縁もしていない。
青木氏を研究していてこの事柄から心配をしていたが、しかし、賜姓青木氏の直流支流分流の24氏の現代においても確認出来たのはすばらしいことである。
又、藤原秀郷流青木氏の直系1氏直流4氏支流4氏分流あわせて116氏は「戦略的な血縁」で拡がった子孫であるが激しい戦乱の時代を潜りぬけて関東地方に確実に根をおろして現存する力強さは他のどの子孫よりも優秀である。
このことは賜姓青木氏のように今は、「パラメータと散在の血縁」では低いが、その歴史が物語る様に子孫を遺そうとする血筋に持つ「粘り強さ」が影響していることに気付いたのである。
少ない子孫を確実に残すことから粘り強さが生まれているのである。逆に、少ない小さいしがらみと散在の血縁タイプでは数を多く遺して確率で遺すタイプは粘りが無い事に気付いたのである。
これは真に「虫の生存原理」である。人間の子孫を残す行為にもこの原理が働いていることに改めて感心したのである。
研究室のレポートの如く、我が2流の青木氏の先祖が子孫を残すことの方法は別にして、全力を尽くしたことを感謝して、今後とも青木氏諸君は大いに良い子孫を育て頂きたいものである。そのためにもこのサイトのレポートが役に立つことを期待する。
以上。
青木研究員
|
Re: 仮説 今年の温暖化は。
副管理人さん 2007/02/28 (水) 12:39
不明なところのご質問がありましたので、追加します。
人間の増加量とこれに対するマイナス要因の食料等の消滅による減量との差に対する疑問でした。
詳細に書きませんでしたので追記します。
それは次ぎの論理によります。
普通は、そう思いますよね。そこでお尋ねの”人の成長”に就いて2つのことが考えられます。
先ず一つは食料です。二つは外的熱量です。
この二つの事が人間の増加に影響を与えます。
では一つ目ですが、
植物は光合成にて食べても出てきますから再生のサイクルがほぼ同等に働きます。
動物から採る食料もある一定のサイクルで再生します。
そして、この二つは食物、動物連鎖が起こります。よって段々と人間が増えるに従い食料は「比例」して減ると言う事にはなりませんね。
よって(人間の増加)−(食料連鎖)=重量増加 と成ります。
次に、外的熱量は主に石油です。
後40年程度で枯渇しますので、有限ですから確かにマイナス要因です。
しかし、これは40年という地球の寿命から見た年数としては短期間ですし、人間の増加式の2*Nと比較すると小さいものと成ります。
この増加重量に対しては、埋蔵石油は大した重量にはなりません。。有限ですので、その後は枯渇を含めてこの影響(40Y)はなくなります。
現在、枯渇しない代替エネルギーが開発されてきましたのでこの熱量のマイナス要因はなくなります。太陽熱や風力や原子力や化学反応熱や植物エタノール等はマイナス要因にならないエネルギー熱源ですので、40年以内には完全移行が可能です。
そこで現在は、将来は益々化学が進歩しますので、より人間の増える速度は2*Nの影響が大に成りますので、先ずこの増加速度に叶うマイナス要因は少なくとも見当たりません。
そこでレポートでも書きましたが、人間の増加分に見合う植物食料の再生する能力が起こるかです。
現在では食料はなくなると見えますが、これも太陽熱による植物再生に頼らないエコの食料調達が可能になってきました。無限サイクルの再生システムです。
多分一時的に人口増加はこの食料の問題で横ばいになると見られますが、2*Nの速度が勝り再び増加に転じます。
文明の進歩で人間の増加だけは「無から有」ですから増加へ転じます。
既に、45億から65億に変化していますが、その分食料を含むエネルギーはへっていますか。減っていないから20億増えたのですね。そのために22.3から22.8度に傾いているのです。
だれも宇宙から地球を傾けたと思わないですよね。
多分、文明の進歩不足からアフリカで一時的に食料調達の困難から人口は減るとみられますが、その分文明国では2*Nでより増加します。
この人間増加理論の2Nに勝る速度の持ったものは無くなったかもしれませんね。
文明は、神様が考えた理論を越え始めているのかも知れません。
アフリカ、中国で何か、人類上で大きな事を神様は起こすかも知れませんね。
でも、最後は人口増加2Nは勝つと思います。
中国も経済発展していますが、それは国土の1/10以下のところでの変化ですし、奥では、未だ、アフリカと同じ人口増加を遂げているのです。いまだ、去年始めて実施しましたが、まともな国政調査が出来ていないのですよ。
地球上の1/10の人口国です。これに2N理論を当てはめて考えてください。
それに、中国の発展には2つの疑問があります。
一つは、GNPの基と成っている輸出企業の8000社の6割は日本が絡んだ企業です。
そして、そのGNPの四割はこの日本企業がらみの数値です。これに外国企業分を入れた場合は3割程度と実質はなるでしょう。
言い換えれば3割の国力しかないのです。そこに国体が共産国で、経済が資本主義では必ず矛盾が起こります。
つまり、実態と大きくかけ離れた国情を持った国で、バブルの途方も無い破裂が起こる危険性をもっている事になりますよね。
次の疑問は、奥地では暴動が頻発して、これにたいして、つい最近、中国は止む無く「個人財産」を認めましたね。現実の矛盾の「資本化」が起こっていることです。
そこに日本のそれと異なり、体質的に自らの新製品開発能力が有りません。
私の勤めていた企業も遂には中国から引き上げましたが、人件費が1/10であるので運送費を差し引いても利益が出るとの計算ですが、ところがそう甘くありませんでした。
働く者はあまりにも知恵を出さない体質であり、国から4年くらいすると投資した最新型の機械等の物を置いて、別のところにうつれと言われる始末ですよ。置いてゆかなければ移り先は言わないとの説です。止む無く損害を出して引き上げると言う事に成ります。既に1年で30%の引き上げ状態です。これを警告した高官がひきづり降ろされたらしいですね。
これ程に矛盾を多く持つ国情の人口増加量2Nは歯止めが利かないと思います。
アフリカはちょっと論外です。
ですから、人口は確実に増えます。
少子化対策も大事だけれど、こちらも大事。矛盾ですね。
だから、必要以上の2Nの式の成り立つところで人口を減らす工夫が必要ですが、そんなこといえませんね。
アメリカも中国には若干弱腰。ここをつく事が戦略上必要ですね。
日本は上記のターゲット握っていますから、腰を据えていることでしょう。
お判りいただけたでしょうか。
Re: 仮説 今年の温暖化は。
本当に暖かいですね。今朝のラジオで富山ではチューリップフェアの前にチューリップが咲いて、始まる頃には萎むんではないかと言ってました。
そこで必死に発育を止める措置を取っているのだそうです。
あと380年で人間ロケットになってサヨナラですか、わははは
これは面白い説ですね。地面にロープで体を縛っておかないとダメですな。
お金をかけずに誰でも宇宙旅行にいける時代が来るって言ってましたけどこの事か・・・
その前に長身の連中がわんさか増えだして、凄いことになりそうです。
面白い話をありがとうございました。
きくされている臭いがします。
仮説 今年の温暖化は。
副管理人さん 2007/02/25 (日) 18:36
今日は。ちょつと面白い話をします。
まずその前に、その現象のすこしの現れを季節と言う変化で先ず述べてみます。
今年の春は20日程度早くて、春の景色は様変わり。
どの様に違うかと言うと、先ず花種が多く、香種が多いことです。
未だ咲くはずの無い花が咲き、それが一度に咲き乱れていることです。
例えば、梅、椿、じんちょうげ、水仙、藤花、草花に至っては福寿草や紫草が咲き乱れるほどです。
ただ、梅にしても種類が多く未だ咲かない紅梅やしだれ梅も、200種もある椿でも最初に咲く侘介、次に咲く藪椿、更に後で着く白椿、源氏椿と一緒に咲いてしまうと言う現状です。
これでいいことは、花が一杯で経験した事の無い「花世界」で、そして、香りの漂うあたりの空気が春榛ではないこの世の極楽の感がするほどに漂う匂いです。
小鳥の多いこともこの事が原因して賑やかさが倍増して変な感もするほどの春のこのごろです。
普通は段々に咲くように庭木を植えているのですが。
ミツバチが飛ばない春は果実は大丈夫かとの心配もあります。
その内に早咲き桜やスモモの花や梨の花もつぼみが大きくなるほどですから、全て咲いたら一体どうなるの。
60年間の初めての経験です。亜熱帯化していると言う事ですね。
菅原道真も、東風が吹かないので咲く梅の花は咲いたけれど匂いが届きませんので残念でしょうね。
彼も、このようなことを1000年も前に想像していたでしょうか。
本当にCo2が温暖化の原因?。
一時は、フロンが原因で(両極の空のポケットが原因)と言われたときもあるけれど違ったですよね。
どうも少しCO2の量だけの影響ではないと感じているのです。
というのも、その疑問としては、CO2が出来ても光合成で吸収しますし、上空にあがれば上昇過程で太陽熱での温度と水分とで反応してH2CO4になる事もありえます。
上空の低圧と低温でドライアイス的な現象も起こりますし、高い上空の強力な紫外線による分解反応も起こります。
森林の光合成により吸収されるCo2により酸素が放出されますが、酸素は炭素と反応するときは反応熱を吸収してかなり高い冷却効果が起こります。
地球上で自然連鎖で余剰に熱を発生させCo2を増加させ出すものとしては、唯一化石燃料以外にはありません。
これも後38年で枯渇しますから、又、Co2は低下し始めます。
雨が降れば空気(28.8)よりも水分に吸収されて重く成ります。
CO2(30)+水分>空気(28.8)となり下に下がってくるので一概に温室効果にはならない筈です。(Coは28で徐々に上昇中に空気中の酸素と反応してCo2となり44となり空気より重くなり陸と海面上に落下してくる。炭酸ガスは平均的には30程度となる)
下がってきたCo2は、海に吸収されますし、吸収されたCo2は海の生物にとつて生存するに必要な物です。ましてや、海は地球の80%に成ります。地球の20%に発生したガスは4倍の海に吸収されるのです。海にそれを吸収する能力が落ちたとは思えません。
海上に落ちたCo2は圧力と温度と水分と酸によりCo3となり海中に吸収されて海中のミネラルのCaと反応して炭酸水素カルシューム(CaHCo3)となり珊瑚などの大切な源となる。
陸では鍾乳洞の元となる。
空気の28.8に対して、Co2ガスは30程度ですから、地球の状空まで上がることは無く、その間に雨風にさらされて、水分に弱いCo2類は吸収し低下してきます。まして、温度や紫外線などのファクターで分解される事も起こります。
アルゴンなどの不活性ガスではありませんから浮遊する性質はありません。、必ず低下して海に落ちる事に成ります。
まして、化石燃料は、元は1万年前に地上のCo2の炭酸ガスを吸って、化石となったものです。
これが、再び、地上に出て来た訳ですから、量的にはイーブンです。増えたと言う事ではありません。もし、この影響で、温暖化が起こったとすると、1万年前には温暖化が起こっていた事に成ります。その時のガスを吸い込んでいる訳ですから。
4倍もする海に吸収したCo2が海の生物の生存の元と成っているわけですから、当然にCo2とすると海にも生物の影響が出て来るはずです。海中汚染でのことは納得できますが、Co2による絶滅は見られません。
化石燃料の枯渇は38年と言いますが、この点から考えても、宇宙年数1の要素で考えると、地球年数の要素は約100年と成りますので、その1/3となり、0.3年の分と成ります。
地球に与える影響は一瞬で僅かです。
又、地球のマッハの自転の回転と公転で、大気の変動も起こりますので、Co2の濃度の変動も起こります。
ですから、CO2も影響でしょうが、それが直接的影響に成っているとは思えないのです。
私は、地球が重くなっていることが、大元の原因と思っているのです。
その根拠は、地球の回転移動に要する地軸の傾きが22.3度から22.8度に変化していることが原因と見ています。
つまり、この結果でどのようなことが起こるのかということですが、それは傾く事で日本側の位置ですると、太陽の光が直接当る位置つまり、赤道が、北極側に移動する事で起こっているのではと思うのです。(南半球は南極側に移動する。)その現われとして太平洋の海流の温度が高く成っていることです。つまり、エルニーニョ現象等ですね。台風の起こる位置も上(日本側より)になっていますし、竜巻も起こりやすく成っていることも地上と上層の温度差がありすぎる事から低い方から高いほうへと上昇気流がおこり竜巻が強くなる原因ですよね。
この0.5度の傾きとは、地球が重くなると回転に必要とする回転傾斜角が0.5度傾いている事に成ります。直角では地球は回転は止まります。回転を傾ける事で自転が起こり、その自転に外側に加速度が起こりますので、公転が起こるのです。コマを廻すとわかりますね。
コマが重くなればなるほどこの軸の回転角が傾かなくては回りません。
そこで、ちょっと面白い想定をして仮説を考えてみます。
地球の重力を変化させる要素は一つあります。
その一つは、人口です。300年前はこの地球上には45億人の人口でしたが、現在は65億人となっています。つまり、300年程度で20億程度増えているのです。
15年で1億増えている事に成ります。
そうすると、地球の−引力は日本で見ると980kg/m/sec2とすると、当然に重くなるとこの加速度の+の引力は変化して大きく成ります。(地球の引力の表現方法を重力加速度として定義する)
因みに、赤道では中心半径部なので低く965-970程度です。傾くと加速度は日本であれば上側に大きく成ります。
そうすると、つまり重いほど加速度がつきますからこの数字は大きく変化してくるはずです。
つまり、引っ張られている力は緩く成ります。では、この地球に引っ張られている力と、加速度で外側に跳ねられる力とのバランスが等しくなった以上の時に、地球上の物、特に人間が宇宙に向かってロケットの様に勢いの加速度で飛び出す事に成ります。
自動車に乗って高速でカーブを回るとドア側に体が寄せられる現象ですね。
あれの著しい大きいのが起こり飛び出すのです。
では、引力に負けて加速度が勝って宇宙に飛び出すこの地球の変化の限界はいくらかと云う事をちなみに計算すると、概ね、85−90億人と成ります。
そうすると、(65-25/300)*(90-65)の式で375年と成り380年くらい経つと地球の持つ電気的マイナス引力に負けて回転加速度が勝り、人間ロケットとなって宇宙にサヨナラと飛び出すと言う現象が起こる事が計算上で出ます。
380の年数は、この原因にて食料の不足で人口が減るし温暖化で減る事もあるので一概には言えないが、増えるのは確実です。人間はこの地球上で「無」から「有」への唯一の物体です。
人は、地球のマイナスの電位の負荷で、その上に立つ物は相対の原理で、この引力に対してプラスの電位の負荷を持ちます。これが地球の半径方向に引っ張られている原因なのです。
1.7M背の高さの人は170ボルトのプラスの電位の負荷で引っ張られていて、980の引力が勝っているので飛び上がっても下に落ちるのです。
地球の重力が増えると170ボルトの電位負荷+回転加速度の変化分の力が、この引力に勝ちロケットになるのです。
話は戻り変わりますが、
人間は脳の中心、つまり、毛の渦のあるところがこの+電位の電極の位置です。これがあるから人間は生きているのです。だから、頭を使うと触ると渦のところが暖かいですね。(脳幹)
この電極から能に電流を流して、脳神経をリードして通じて能の各部に伝達するのですが、この伝達にはつなぎ目があり、このつなぎ目のところにキャリパーと言うNaのアルカリ性の液体が流れて、この液体の流れている間(0.2Sec)にこの電流が流れる仕組みです。そして、この電流で刺激されるとその脳の部分が反応するのです。
この時、この液体が流れている間電流が流れるのですが、長く流れている間はその感情や機能が続くと言う事に成ります。
女性の感情や母性本能など長く続くのはこの原理です。又うつ病はこの現象ですね。
この電気回路の原理は地球の上に立っている事に寄ります。宇宙に行くとこの現象が低下するので訓練が必要と成ります。
この元はNa(ナトリューム)があるからです。能にはNaが必要なのです。
例えば心臓はMg(マグネシューム)の電気的刺激反応により心臓の筋肉が動きます。
体に栄養を送り出すのはCa(カリシューム)と反応して栄養分を体中に送るのです。
だから、動物はこの3つの要素を含むミネラル(塩分)が必要なのです。
そして、この3つのミネラルを反応させるにはこの電位から起こるのです。
この地球の引力と、重力による回転加速度の増加と地軸の変化(温暖化も含む)の3つによって引き起こされる電位変化が、(体の仕組みに起こる変化の現象が、)この地球上での問題として起こる事の方が大と思うのですが。ずいぶん先のことですがね。
つまり、温暖化だけではないことが起こるのです。
地軸の回転傾斜度での日本の亜熱帯化の温暖化よりこの方がよほど恐ろしい事になるのではとも思うのですが。
当然に、地軸変化により北半球側は温暖化が、南半球側は温冷化起こる筈です。
この温暖化と温冷化は自然界に与える影響の現象は良く似ていますが異なります。
当然に、オーストラリア側付近では、温冷化の自然現象が起こる事に成りますが、現実に起こっているのです。
これは地軸の変化で物理的には回転速度の変化と温冷化で極点上空でのポケットの原因として考えられます。(その証拠に、つまり、フロンではなかったのです。)
人口が増加するとCo2の排出は増加しますので、これが原因とされているのですが、元は人口です。人口を減らせれば全て解決できます。
増加した人類の増加分により、化石燃料のCo2を除いて、人間が排出するCo2の方が大きく働いてきます。この量を無視できません。
無から有と成った人類は、その増加分に見合った食料と燃料を知恵とするものに依って、増産する能力を確保しましたので、増加の一途を遂げているのです。
もし、この知恵が無ければ、他の動物と同じく種の増加と食利用はイーブンとなり増加は成し遂げられていません。従って、唯一、この世で、無から有と成った生物です。
そして、これからも、人口を増やす可能性は高いと見られます。
地球上での多少の差がおこりますが、必ず増加しますので、人間から出すガスと消費する燃料を無視する事が出来なくなり、地軸の変化と重なって、相乗的効果で温暖化が進む事が考えられます。
あくまでも、化石燃料外の影響です。
最近では、原子力、ソーラー、風力、バイオ、以外に大変有効的な手段が開発されました。
それは、太陽熱を人工衛星で受けて、それをレーザービームで地上に送り、地上局でそのエネルギーで発電して熱利用源とする方法が実験的に出来たのです。
このシステムは、原子力一基の4倍に相当する莫大な発電力と成ります。当然、無限ですし、無公害と成ります。現在の発電設備の1/4で可能と成ります。当然このエネルギーを使って食料の増産も可能と成りますので、食料と熱量が確保されれば、無から有の人口増加は成し得ます。
この増加で起こるガスと人口の増加分の重量が大きくなってきます。
Co2の影響などは元あったものですので、大した影響では有りません。
事の問題はいずれにしても、人口の増加の抑制です。
しかし、世界人口を減らせとはいえませんね。倫理的、政治的にも。世界がパニックに成りますし、それを世界に向かって云う人は居ないでしょう。
というには、人口の増えている地域は特定域だからです。もし、云うとその内に世界戦争が起こりますよね。生存競争の利害が絡みますからね。
最終、熱利用の問題と食料の確保と温暖化で、人口は逆に後進地域は激減する事が見込まれます。
特定域の一つの中国では「一人子政策」で意識してかしないかして人口を押さえようとしていますよね。そして、中国の大陸が大きく砂漠化が起こっています。一年に日本の一つの県が無くなるくらいの面積で。これも共産国だからできる政策ですね。
もう一つの特定域のアフリカはそれを実行するその力はありません。人種の発生の元が人種の滅亡の基に成りつつあるという皮肉な現象ですね。
最悪はたとえ、Co2が減ってもこの悪のスパイラル自然現象は一度起こると止まらないと考えています。
月にでも人口を移さないと解決しないでしょうね。この時は私達は生きていませんがね。
「環境時計」は危険域に達したと云われていますが。Co2の問題の裏には、化石燃料の枯渇の問題に対する利害の政治的思惑が働いて、矛盾するCo2要因説が話が大きくされている臭いがします。
> 「青木氏の伝統 60」−「青木氏の歴史観−33」の末尾
>
この「山県昌景の判断ミス」とは相対的であるのだ。
> これが「青木氏族」に遺した「始祖の施基皇子の教訓」の「青木氏の氏是」の意味する処なのである。
> 躊躇なく直ぐ様に執った「戦線離脱の行動」では無く、其の侭に「山県軍の別動隊の追尾」や「武田軍の本隊」に向けてこの「銃口」を向けていた場合は、間違いなく「歴史」に名を遺し、周囲から警戒されて其の侭では済まなかった筈で、泥沼化していた事は間違いは無いのだ。
> これは「青木氏の氏是」の「発祥以来の伝統」に反するのだ。
「青木氏の伝統 61」−「青木氏の歴史観−34」
(注釈 「三河戦記の詳細な検証」
「三河の事に関わる戦記」には主に五つある。
この「三河戦記A」や「甲斐戦記B」から総合的に読み取る事が出来る「額田青木氏に関わる事柄」を拾い出して、この「二つの事に含まれる脚色部分」を外して、そこからその更に“「細かい処」”を検証して読み解いてみる。所謂、詳細経緯である。
そうすると「言葉の使いまわし」等から意外に“普通なら見逃している情報”が潜んでいる事が多く、「青木氏の歴史観・無脚色」と突き合わせて観ると判る事が出て来るのだ。
そこを突いて観る。
取り分け、「三河戦記A」には「脚色・矛盾」が実に多いのだ。
そうすると、先ず「前段までの注釈」でも論じた様に「詳細な行動の経緯」が見える事が出来る。
先ず、「武田軍の背後・堀江城行軍」を「銃力で背後から圧力を掛けた事」に付いては「額田青木氏の銃隊」の「独自の判断」であった事が解る。
「三河戦記の事を書いた五記」からも「命令が出ていた事」は何処にも書かれていず結果だけである。
「書いている事」は、詳しくは「一言坂の偵察隊の事の前後の部分」だけではあるが、判る事は「言葉の隠された意味や隠れた読み解いた経緯」からで、それを繋ぐとこの時の「全体の行動」が見えて来る。
何は兎も角も最も「全ての経緯」の「決め手」と成ったのが「籠城の経緯のキー」である。
どの戦記でも此処は見逃していない。
「武田軍の全軍」が「大軍」であった事で、仮に「松平軍」が「浜松城籠城」を選んだとすると、「浜松城」を攻めるには「補給等・二俣城・山県軍の別動隊が整えた・史実」を受けながら「波動作戦」で、「三方ヶ原・宿営地・補給基地」から「当初の作戦」として何度も攻めて来る事に成っていた事が判る。
この「一連の経緯」から読み解くと、その“「準備の為・掃討と補給」”に「山県軍の別動隊・二俣城」は「三方ヶ原」にやや遅れた事が先ず判る。
その証拠に、「戦記」では、現実に「武田軍の本隊」に遅れて「別動隊・山県軍」は「二俣城」で「周囲の掃討作戦」と、その“「補給路の準備」”に入っていた事が判っている。
その「遅れた主な理由」は、「落城までの期間・2月」と、その勝敗の様子を観ていた「周囲の地侍」が反抗し、これを鎮圧するまで「補給拠点」は最初の二俣城落城前までは造れなかったのだ。
然し、遂に「水攻め」で崩れて開城し、この「様子見の地侍」も「武田氏」に靡いて遂には襲われる事も無く成り「補給路」は出来たのだ。
ここで「青木氏の歴史観」として注目するべき「決定的な情報」があるのだ。
それはこの「二俣城」には「副将」として「青木貞治・三方ヶ原で戦死・駿河秀郷流青木氏」が居たのだ。
この本論の「最大の史実」は、「額田青木氏の南下国衆」に影響していた事に成るので下記でこの点の「詳細経緯」を論じる。
この経緯から「10/16日・元亀」から攻めて、12/19日に落城させて、12/20日まで掃討し、12/21日に「補給路作戦」を開始し、12/22日に西に向けて移動している。
これに「三河五戦記等の信頼できる記載」を合わせると、「補給作戦拠点造り」に苦労して「二俣城」を必要以上に時間を掛けて「北の山際」を西に向けて進軍して来ている。
つまり、これはこの「三方ヶ原」が”「宿営地」”と云うよりは”「補給基地」”であった事を間違いなく物語るものである。
仮に、違うのであるならば「武田軍の本隊が辿った道」を「山県軍の別動隊」は南下するのが通常である。
然し、「山県軍の別動隊」としては「補給基地」は、同時に「守備隊の宿営地」と成り得るので、戦記では“「補給基地・補給拠点の意味含む」”として記しているのだ。
又同時に、この事でも他説の「山県軍の別動隊」が、「天竜川沿い」に南に進軍せずに、「北の山際」に沿ってこの当初の「補給基地・補給拠点」の「北の三方ヶ原」に向かっていた事が読み取れる。
そもそも「武田軍の本隊」も、この「三方ヶ原」を「補給基地・補給拠点」として確保するならば「北の山際」を通って牽制しながら「堀江城」に向かうのが戦略的に距離的にも最も合理的である。
ところが先にこの「南のルート」を使ったのだ。
当然に、「山県軍の別動隊」も、「補給基地・補給拠点」としないのであれば「同じルート・南ルート」を辿って「武田軍の本隊」の後を追うだろう。
ここがよく読み切らないと判らないところであり、故に、「武田軍の本隊」と「家康」との「一言坂の戦い・二つの説」が起こったのだ。
さて、「一言坂」と云うキーを元に、故に、ここからが「青木氏の歴史観」の「額田青木氏の南下国衆の事」と「青木貞治の事に関わる事」に絡まって起こる事に成るのだ。
「三河戦記」の一つの説は、「二俣城」の南下している「武田軍の本隊」に向かって城から出て「野戦」を仕掛けたとする説と、「一言坂」に到着した「武田軍の本隊」に城から出て「野戦」を仕掛けたとする説の二つの説があるが、「詳細経緯のタイムラグ」から観て、前者は成り立たず、後者が正しい事に成る。
普通なら、ここでは遅くとも12/20日で「西・堀江城」に向かう筈であった事が判る。
要するに、この「4日間」の「山県軍の別動隊」は「浜松城籠城作戦に対する為の準備」をしていた事に成る。
この為にも、同時に「武田軍の本隊」が「浜松城」を攻めるには「北の三方ヶ原・宿営地・補給基地」にするとして必ず来ると「松平軍」は観ていたのであろうし、寧ろ、作戦的には先に「野戦の戦場の確保」と「補給基地・補給拠点」を阻止する為に「三方ヶ原」としたとも執れる。
これには「南下国衆の銃隊の一連の行動」に執って「意味する処」があり、何れかであるがどの「三河戦記」にも「甲斐戦記」にも“何れか”を記されていない。
唯単に「三方ヶ原」とし主にはその意味合いから「宿営地とする説」が主流である。
それについては疑問がある。
先ず「経緯の行動」から読み込むと、当初は「堀江城」を「本陣・武田軍の本隊」として、「二俣城の拠点・補給拠点・山県軍の別動隊」にする案が検討されていた「形跡」があると観る。
何故ならば、「信玄の戦い方」の全体を観れば、「野営地を本陣とする戦法」を採らないのが「信玄の戦略のポイント」なのである。
彼の戦記では「周囲の大城・本陣」を落として必ずそうしている。
必ず、「本陣」を戦場と成る所を見計らって「1k〜1.5k程度の処・城館」に安全を期して離している置いた戦術を採っているのだ。
「一言坂の周囲」には「2k圏内」には「8つの出城」があり、この何れかに「本陣」を構えた筈である。
何故ならば、「一言坂」より少し「東・18k」に離れて「遠江と駿河との国境域」には堅固な戦略上の拠点と成る「掛川城」と「高天神城」の二つの城があって、これを先ず落とす必要があった。
その「掛川城」は三方ヶ原の戦いの前の「永禄12年5月・1569年」に落城させた。
これは「三方ヶ原の戦い」より「3年前の事」であるが、ここを「本陣」とするには遠すぎる。
ところが、「高天神城・掛川城より南8k」は「天正2年5月・1574年」に落城させた。
「三方ヶ原の戦い」より「4月後の事」であるが、「掛川城」と同じく遠すぎる。
戦略的に先に「掛川城」を落として於いて「西側の城の処置」に掛かり、この「西側」が片付いたらその余力で「高天神城」を落とし、その間は「掛川城」から「東側」に睨みを利かしていたと云う事であろう。
故に、「三方ヶ原の戦い」では、東に「高天神城」の一つの城を残して落とさずに其の侭に直ぐ近くの「一言坂」に入っている。
「三河戦記」では、「二俣城」の手前まで出向いて牽制しようとしたが、その前に「武田軍の本隊」が迎え撃つ様に「一言坂手前」まで進軍し逃げる「松平軍」を追尾し「一言坂」で追い払い、再び、「文面の流れ」からこれをあやふやに“本隊が二俣城に戻つた”様にと記されている。
明らかに上記の後者説であって、「一言坂」に到達した「武田軍の本隊」に城から出て「野戦」を仕掛けた事に成る。戦記では前者説は「偵察隊」と記しているが現実には「野戦」であって、「偵察隊」ではあり得ない「5000の兵」を向けているし、後者説では「野戦」と記されているので後者説が史実と成る。
ところが、この「一言坂の戦い」は、この日が「三河の戦記・松平氏」では「10/13、又は10/14」としていて、ところが「甲斐の戦記」では、「武田軍の本隊」は「10/15」は「匂坂城」を落としている。
「二俣城に戻ったとする様な説」と「匂坂城の説・10/15・一言坂より北4k・天竜川沿い」とには「2日の行動の無理」が起こる、又戻ってもいないのだ。
然し、「甲斐戦記」では「二俣城」には、「山県軍の別動隊・11/中旬・15日頃」に合流し、「本隊」と共に「水源」を破壊して落とした事と記されていて、「武田軍の本隊」が戻ったとは成っていなく、この後、直ぐに「目途」の着いた「二俣城」を「山県軍の別動隊」に「周囲の国衆の掃討」と「補給路の構築」を任せて「二俣城」を離れて南下しているのだ。
実際は、先ずこの「二俣城」は無血開城したが、未だ「周囲」の「国衆・土豪」は反抗を続けていて現実には終わっていない。
これを「武田軍の本隊」も“未だ「二俣城」に居た”と勘違いしたか、「脚色のネタ」にした可能性があると観られる。
この説では、“「偵察隊」”としていて、その軍勢が家康本隊が3000で、本多・大久保等の隊は総勢2000としていて、合わせて合計5000である。
これは松平軍の全勢力であって、そもそも「偵察隊」であれば、「家康・大将」も出ないし、精々100程度で済む筈である。
ところが更にはそもそも「偵察隊」であれば戦わず手前で引くのが常道でありながら、引いたが追いついたとして脚色している。
「武田軍の本隊」が“自動車にでも乗っていたのか”、「どれだけの速さ」であったのか脚色もここまで来ると笑える。
ここにもこの説の無理があり、矛盾だらけで「負けた戦」に江戸期に脚色して虚勢を張ったのだ。
「一言坂」から「二俣城」まで直線で16k、徒士で最低で4hの道則であり、そもそも疲れた兵が戦い後に1日の工程では「大軍の進軍」は倍と成り無理であり、再び、「一言坂」まで戻ってくるのは戦略的に無理であり、そもそも無駄であるし、更にはこれでは「一言坂」の遠江の周囲の「出城8つ」を落とす時間は生まれないし、当然に突然出張った松平軍を追ったとすれば「武田軍の本隊」の「補給態勢」が続かないのだ。
又、そもそもその期間に「2月のずれ」があるのだ。
「甲斐側の戦記」とには修正できない点が生まれて其の侭にして脚色したのだ。
「三河戦記の脚色」は後勘で墓穴を掘った形であるが、江戸期ではこれでも良かったのであろう。
筆者の感覚では敗戦した「甲斐の戦記類」の方が「矛盾と脚色」は少なく「祐筆衆の原稿通り」に「史実」を伝えている気がするし、普通は逆であろう。
もう一つは、「一言坂」へ進軍中の「武田軍の本隊」に向けて城から出て「一言坂」で「野戦に依る戦い」を仕掛けたとしている説があり、天竜川を越えた域当たりで「野戦」と成り敗戦したとする説でこれの方が矛盾は少ない。
そもそも地形的な面から観て、「浜松城」からは、この付近は”「圷の平地」”であったので、「武田軍の本隊」の「一言坂付近の進軍」の「動向の状況」は見えていたので矛盾はない。
其の後の詳細経緯を追うと、ここで、「松平軍を追い払い・11/15日頃」、「軍の態勢を立て直し」、「補給路を確保」し乍ら、その間に「8つの出城」を落として、この間に一時、「約1ケ月間程度・12/20まで」を「浜松城の様子」を観察しながら駐留したのだ。
そして、前段の時系列の通りの行動と成って行く。
12/21 本隊 朝頃一言坂発進
12/21 銃隊到着−額田青木氏の銃撃戦
12/21 17時半頃浜松城通過
12/21 20時頃堀江城到着・開戦
つまり、この経緯から故に、「武田軍の本隊」が北三河を制圧して合流していた「山県軍の別動隊」に「二俣城の処理」を任したが、然し、「二俣城」から「南下」して途中で左に折れて直接に「三方ヶ原」に向かい、「本陣とするべき城館」の無いそこを「宿営地」として、そこから「浜松城」を攻めて、その後に「堀江城」を攻め落とし、それから「本戦の西・三河に向かうと云う戦略」では元々無かったと云う事である。
然し、史実は直接に南下して「浜松城の東・12k−2.5h」に位置する「一言坂・兵站・六間街道―盤田街道・天竜川から東5.5kの坂・盤田目付」まで到達している。
この「東坂下」では「松平軍」と「一度目の野戦・一言坂」をしているのである。
要するに、仮に、何故か「宿営地」としていたとするならば、この史実と矛盾するので「三方ヶ原」には向かっていないのだ。
この様に多くの「三河戦記の説」とは矛盾するのであり、「江戸期の脚色の矛盾点」である。
寧ろ、「二俣城」を落としている限りに於いて先に宿営地としているのなら「二俣城」から直接に「藁科街道・静岡県―本坂街道・愛知県」を西に向かって「三方ヶ原」に向かう筈であり、この西に向かわずに「天竜川沿いの東」の「二俣街道東」を通って南下して「盤田街道」を西の「一言坂」に向かっていて、且つ、そこで無駄な「仕掛けれられた野戦」もしている事に成るのだ。
然し、そもそもこの「三方ヶ原に向かう方・藁科街道」が前段で論じた「時間のずれ」などの事は、一切の問題は吸収出来ていて「無駄」が無く成り「合理的」であった筈である。
故に敢えて、「天竜川沿いの東」の「二俣街道東を採った事」には意味があった事に成る。
つまり、この詳細経緯では、戦略は当初から最も三河寄りの湾際の「堀江城」を本陣に据える筈であった事に成る。
これは過去の戦歴の「信玄の戦略ポイント」に一致する。
だとすると、「二俣城」から「三方ヶ原の南横」を経由して「湖東町交差点」を西にルートを採れば、「三方ヶ原」などに対する「戦略的印象」も効率的で、最も「堀江」に「近いルート」と成り、「両者の籠城戦の考え方」に執っても意味があった筈であったが、史実は違ったのだ。
ここに「両戦記」の「記載の牽制策説」の生まれる所以と成っているのだが、これは飽く迄も「三方ヶ原が野営地・本陣」の「前提の説」に成り、「武田軍の補給基地説」ではない事に成る。
史実は「武田軍の本隊」からは「浜松城の真下・城南」を通過しているので「多少の牽制の考え」はあった事に成る。
況や、「三河戦記」の多くの主説の「信玄の牽制策・脚色」では無かった事に成る。
この説では従って「三方ヶ原」の「信玄の本陣説・脚色矛盾」では無い事に成る。
では、そこで問題に成るのは、上記の“天竜川沿いの東の「二俣街道東」を通って南下して「盤田街道」を西の「一言坂」に向かって”の史実は何なのかである。
確かに「8つの出城を潰す事」もあったろうが、「他の全ゆるルート」では解決でき得ない点の「決定的なポイント」があった事と成る。
それが、次の事だと観ているのだ。
筆者は「二俣城の副将」の「青木貞治・駿河秀郷流青木氏一族一門・駿河水軍」の存在であると観ている。
そもそも、このルートを採ったのには、この「駿河青木氏の青木貞治」の背景には、「日本一の大勢力」の「遠州と駿河と相模と武蔵の国衆の出方+秀郷流一門361氏+秀郷流青木氏116氏」の「出方」を伺ったと観ているのだ。
要するに「青木貞治の駿河青木氏」に繋がる「東勢力」を気にしていたのだ。
「軽視し無視の出来ない勢力・青木氏116氏+青木主要五氏の一族361氏」である。
これは「一族の直の勢力」であって、これにこの一族と血縁を持った国衆も存在するのだ。
信長も秀吉も家康も手を着けなかった相手であった。
此れを下手に動かす様な事にも成れば幾ら「戦い上手な信玄」でも人溜まりもない。
平安期から元々、“「戦闘的ではない寝る子」は起こすな”である。
何せ「一言坂の盤田」の「姫街道沿い・本坂街道」の「直ぐ横・1k」の所に「駿河青木氏の青木貞治」の「一門の菩提寺西光寺・大寺閣の平館城」があるのだ。
これを誰が観ても解らない馬鹿はいないだろう。
この周りは要するに「一言坂の戦場と成った地域」であり、「一族の住処・東域」で一族一門としても放置できない事で、古来より「氏是」として直接に攻撃侵攻はしないが、「入間総宗家の判断」があれば一団と成って救出する。
これが寝る子の「青木氏族の掟」である。
「第二の宗家」としていた「遠江駿河の青木貞治」を始めとする「秀郷流青木氏116氏」はこれを護った。
いざと云う時には、「伊勢」から「伊勢水軍を廻す事」もあり、「駿河水軍にも救助を求める事」も出来、最も東に近いの一族が居る「藤枝」か「青木」からは直ぐに動ける「1日生活圏」の「40k=10里の位置」にもある。
この様に「援軍救助と云う点」では全く問題は無かったし、「武田軍」は「水軍」には全く弱く「補給路」は陸路に限られていた。
故に、「武田軍の本隊・東駿河侵攻」ではこれに対して「藪蛇の戦略」と成らない様な戦略の必要性に迫られていたのだ。
それには「唯一つの策」があった。
それは「戦記」から観ても、「松平軍を攻めた」が「周囲・菩提寺付近」は荒らさず手を付けていないのだ。
何故ならば、「一言坂の戦場」と成った「盤田の西光寺」も「一族の過去帳」や「墓所」等が遺る位に消失していないのだ。
これを観た「遠江と駿河と相模の秀郷一門の勢力」と「伊勢の抑止力の勢力」は連携して「攻撃すると云う事」はせず結果として動かなかったのだ。
故に、「武田軍」は、この寝る子を起こすような事をしなければ、“一言坂を通る南周りの行軍路を選択した”のだ。
同然に、「二俣城の副将・青木貞治等」とその「兵・1200」を開放するに及んだのだ。
これを「甲斐側」から観れば、「遠江と駿河と相模の秀郷一門の勢力」を戦う事なく間接的に抑えた事に成り、「松平氏側」からすると、逆に「背後」を及びやかして欲しかったであろうが、「駿河侵攻・松平氏支配・1568年頃からの4年」では余りに短くその勢力は浸透していなかったのだ。
要するに「戦略の狂い」であった。
上記の“天竜川沿いの東の「二俣街道東」を通って南下して「盤田街道」を西の「一言坂・姫街道」に向かって”の「史実」は、「東の勢力・青木貞治の一族一門」を間接的に抑えたと云う点では「戦略」では「信玄の方」が一枚も上であった事に成るのだ。
つまり、「家康と重臣」は「二俣城の副将の青木貞治の存在・背後の勢力」を低く見ていた事に成る。
「元今川氏の家臣・松井氏」と云う事もあったろう。
要するに「菩提寺」が、“直ぐ傍にあると云う事”を放念していたのだ。
そんな処で「戦いをする事」がそもそも可笑しいのだ。
因みにこの「二俣城の時に、本家分家共に「5人の甲斐時光系青木氏・重臣」が参加していたが、この内の内部紛争で「二人・分家」は積極参加していないのだ。
他の三人は、「三方ヶ原」と「長篠」で「戦死・滅亡」であった。
この「二人」は、後に「武蔵鉢形」に移住させられ「徳川氏の家臣」と成り、一人は孫の「柳沢吉保・青木吉保」であるが、この時のこの一族が「青木貞治の秀郷流一門との関係性」は無かった事が二つの系譜上で判る。
要するに、元々、甲斐とは古来より犬猿性が歴史的にあって、「繋がり」は働いていなかった事に成るが、“働いている”と成っていれば「青木貞治の様子」は違っていただろう。
唯、「二俣城の開城」の“「条件」”から観ると、確たる「証拠」は無いが、甲斐側は“何らかの横の繋がり”を持っていての事かも知れない。
つまり、この無血開城の“「条件」”に疑義があるのだ。
「水攻め」で負けたが、その「開城の条件」が良すぎる。
普通なら、無血開城の場合は「主将と副将」は切腹で始末するのがこの時代の常道である。
それを「城兵1200」と「主将と副将」の「退散」で何と「浜松城に入場」までもを許したのだ。
“これから攻めようとする浜松城に”であり、「敵の勢力を高める策」では無いか。
本来であるなら歴史の定説では解かれていないが「青木貞治隊200」は全滅であった筈で、それが生き遺させた何かが働いたと観るのが普通であろう。
それが上記で論じた「遠州と駿河と相模の秀郷流一門の説」であると説いている。
「青木貞治の秀郷流一門との関係性」を誰かが「甲斐の青木氏・重臣の信種か信秀か等の二人」を通じて「条件」として「青木貞治」に持ち込んだとする説である。
実は、この「信種」は「法名」を「浄賢」と称し、「僧門に入っていた事」から「秀郷一門の事」に詳しく「駿河攻め」に帯同しての「信玄の参謀」を務めていた事が判っていて「「浄賢は重臣参謀の者」であった。
「藪蛇の戦略」や「寝る子を起こす」の様な事の無い様に「逃避説」を説いたのではと観られるのだ。
それに成功したとすれば、“「1200兵の開放」”は「等価の条件と判断した」と考えられる。
場合に依っては、「駿河青木貞治」、又は、「甲斐青木信種」かの何れかが、“「条件」”としてこの「参謀の信種」に話を通したのではないか。
筆者はこの推論は先ず間違いは無いだろうと観ている。
だから、「青木貞治」は「三方ヶ原」で「責任を執つて戦死・旗本から責任を問われた」のだし、「青木貞治隊200」は「南下国衆の銃隊の援助」を受けた事もあるが、その後の掃討でも「西光寺」に逃げ込み無事に生き延びられた所以であろう。
これは「青木氏の歴史観」として絶対に見逃す事の出来ない点であるのだ。
さて、ここで念の為に記するが「青木貞治の一族」は、「遠江の盤田」に「西光寺の菩提寺」があるが、「遠江青木氏」では無く「駿河青木氏」であって、「秀郷流青木氏」の「駿河青木氏の西の勢力末端」に分布して平安期から鎌倉期に子孫を拡大させた裔系である。
この「駿河」は、平安末期の富士川の合戦・源平戦に参加して敗退して逃げて来た「近江青木氏」と「美濃青木氏」と組んで「源平戦」に参加して滅亡した「駿河水軍の駿河青木氏」である。
其の後、織田勢に「尾張と三河の神明社」を全て破壊され、この為に「額田青木氏」を「国衆」として鍛え上げて「フリントロック式改良銃」を秘密裏に堺で独自製作し、これを「額田青木氏」に持たせて南下させて「古跡神明者の神職」が定住していた「三河伊川津」に家族と共に定住移住させた。
この時、「伊勢」は、この「駿河」には「滅亡した駿河水軍の末裔」を探し出して「伊勢」で「訓練・1540年〜1545年頃から」を着けさせて「大船一艘」を与え、「糧」を与えて、再び、水軍の「駿河青木氏の裔系・28年〜30年間」を拡大させたのだ。
その「復元駿河水軍」の「30年後の裔系」が、「国衆」として仕えた「元今川氏の国衆連」であったが、「今川氏衰退」で「松平氏の家臣・下記」と成った「青木貞治一族」である。
その意味で、「水軍を持つ国衆の駿河青木氏」は「松平氏」に執っては魅力であったのだ。
さて、この「青木貞治一族」の「秀郷一門を背景とする勢力」を軽視し、16k離れた「二俣城」に配置していたのだが、ところが、更に「松平軍」には弱点があった。
つまり、この「弱点」を「武田軍の本隊」に読み込まれたのだ。
「浜松城」と先に落とされた「掛川城」と後で落とされた「高天神城」の「間・28k」には「護りの城」が無く、その中間の「一言坂」を突かれたのだ。
周囲には「8つの出城」があったが、この「青木貞治一族」の「庄地・盤田」に「出城」なり「平館」を造れば、「駿河水軍の威力」はより戦略的に働いたのだがそれをしなかった。
「秀郷一門を背景とする勢力」の「補給や兵力」も含めて「臨戦態勢」が構築できるのだった。
その様にできれば、「織田氏」では無く、「松平軍+東の勢力・秀郷一門・江戸転封で構築」の「武田軍を凌ぐ勢力圏」を築けていた筈であった。
もっと云えば、この「青木貞治の駿河水軍」を使えば「浜松城の籠城戦」の勝利は可能であった筈であった。
当然に、背後を突ける「伊勢水軍と伊勢の財力」をも使えたのだし、「鬼に金棒」であったろう。
つまり、「青木氏の歴史観」から観れば、この様に悉く、「現場的な戦略性の無い家康」は「青木貞治の使い方・旗本の嫉妬と怨嗟」にも失敗していたのだ。
後勘と成るが、筆者ならそうする。
さて、結局は「一言坂の東」を制し「向後の憂い」を無くし、戦略通りに西進しこの「堀江」に向かったのだ。
此処からは、この「青木貞治論」に於いて、「額田青木氏の南下国衆の銃隊」の詳細経緯に関わって来るポイントに成るのだ。
そもそも「堀江城」は、「武田軍の本隊の本陣」としては、「今後の西三河尾張攻め」としても「最高の戦略的位置」である事は、「甲斐戦記」での「言葉の使いまわし」で「読み取る処」ではあり、「三河と甲斐の両記類」でも「両軍が認めていた」とする節があるのだ。
この事は、「武田軍の本陣」とに関わらず、「二俣城」と共にどの「三河戦記・戦略拠点」としてのその表現には“「最重要拠点」”との意が記されている。
“「最重要拠点」”と表現する内部に含まれる「幾つかの意味」を持っている。
その「意味」の一つには、「武田軍」にしても「松平軍」にしても「二俣城」は、「補給の拠点」、「堀江城」は「指揮命令の本陣」とする事、又はその様に成る事に“重きを置いていた”という事に成る。
逆に云えば、「松平軍」に執っては戦闘で最も重要となる「差配・命令」の出る「本陣化の危険城」と観ていた事に成る。
然し、「一言坂・元亀3/11/13?・勝利」に向かい、且つ、最後には「堀江城・元亀3/12/22落城」に向かい、ここで一度、「補給」などをして「軍立」を直して「元亀3/12/22 ・1573/1/25」に直ぐに「三方ヶ原」に向かったのだ。
定説と成っている「三方ヶ原の野営・宿営地の説」は、これで崩れるのだが、然し、ここで改めて「疑問」があっ。る。
第一に、況してや「武田軍の本隊」は「一言坂の野戦」をして周囲を掃討した後に「堀江」に向かったのだが、何故、「浜松城の前」を素通りして、その後で、「定説」と成っている「三方ヶ原・宿営地」に「情報」があったのなら、何故に堀江より先に向かわなかったか?と云う疑問もあるのだ。
但し、「松平軍」は「堀江城陥落後」に松平軍が「籠城」から「野戦」を選び、この「補給拠点を攻めると云う説」もあり、この説が正しいと云う事は上記の論で解明できているが、それならば「堀江」を攻められるというも「一言坂の地点」で既に判明しているのだ。
だとすると、此処で「松平軍の軍議」は、何故、「野戦」としなかったのか?である。
「情報」と「野戦決定」との間には、「1月程度の大きなタイムラグ」があり、これは有り過ぎる。
要するに、ここには「額田青木氏の南下国衆の銃隊」が大きく関わっていたと観ているのだ。
先ずは、「籠城戦」にしろ「野戦」にしろ「銃隊の効果」は大きいので何れにせよ「吉田城」から呼び出すまでの期間を待ったとする説論である。
現実には呼び出した後の「軍議」では、そうならず何と「350の銃隊の大勢力・松平氏軍勢比7%」を「吉田城」から呼び出して置き乍ら、”城外”に「偵察隊」として放り出した結果と成った。
注釈として、そもそも、「火縄銃の銃力」は「兵力の10倍」と云われていて、額田青木氏の南下国衆の連射式のフリントロック改良銃では20倍以上となろう。
とすると、「7500の兵力」に相当する事に成り「松平軍の1.5倍の兵力」を外に放り出して「偵察隊」としてしまったのだ。
そもそも、「吉田城の守備隊」であったものを{浜松城}に呼び出して置いて、「偵察隊」とする戦術的に「低い命令」を何故に下したかである。
既に、そもそも、「浜松城」からは平坦地にいる「武田軍」は東に見えているのである。
何故、意味の無い、又は「低い命令・偵察」を出したかにある。
何れにしても「額田青木氏の南下国衆の銃隊」は、そもそもの「三河国衆の初期の目的・条件」とは異なっていた事から、そんな「危険な位置に加わる事・銃隊を陣形の中心に据える事」をこれを「軍議で拒んだ事」は、「銃隊の指揮官」からの伊勢への手紙の資料等の内々の「やり取り・不満」からも読み取れる。
つまり、ここは「駿河青木氏の青木貞治」と、「武田軍」にしても「松平軍」にしても「判断の分かれ目」に関わっていたので詳細に検証して観る。
その“「判断のカギ」”は、その前に“「武田軍の本隊に起こった出来事」”であろう。
それの大元は、「額田青木氏の南下国衆の銃隊」との「一言坂の偵察隊との遭遇戦」にあったと観ているのだ。
先ず、その内容はこの「遭遇戦」に勝利して無傷で「西の坂下」に戻った「南下国衆の銃隊の行動」にあったのではと考える。
そして、それは「額田青木氏の南下国衆の銃隊」が、「浜松城」の「城」、或いは「城付近・北東の小丘」に「陣取つた事」にあったと考えるのだ。
つまり、先ず「信玄の頭」に「1年前の第一次吉田城の籠城戦の経験」が過ったと云う事だ。
少なくとも覚えていただろう。
そこで、「信玄」は「一言坂の銃隊の偵察隊」に対して「吉田城の敗戦時・撤退」の「印象記憶」とから、「浜松城通過の間」に、先ず「第1回目の変更の作戦方針」が替えられてたと云う事であろう。
“これは拙い”として「武田軍の初期の目的」の「堀江の方向」に向かったと成るのだ。
つまり、「浜松城」の必要以上の“「牽制行動」”は「銃隊の存在・追尾」でこれ以上は危険と察知したと云う事に成る。
ここの直前までは、未だ“「牽制行動の一策」”として「山県軍の別動隊・補給基地増築使命」の到着までの期間として、「三方ヶ原の補給基地・宿営地・浜松城攻略」に行くか、直接にこの「牽制行動の如何」の為に「堀江城の攻略」に向かうかの「判断」は出ていなかったと観ている。
そこで、「一言坂の坂下」を下りて「浜松城の北東の小丘」に手痛い思いをさせられた「額田青木氏の南下国衆の銃隊」が「浜松城の右横」の「北東の小高い丘・公園の右側・140〜150m」に陣取った事を観たのだ。
ここは「一言坂の平地」と違って此処から下に向けて銃弾を浴びせられれば抵抗できない為に“全滅もあり得る”と、信玄は「2度の経験」から観たのだ。
「三方ヶ原の宿営地・浜松城攻略の作戦」では、「額田青木氏の南下国衆の銃隊」を「相手にする事」に成る為に、「信玄の判断を先送りした」と考えられるのだ。
そこで、「浜松城の城周り」を廻って「館山街道」を北に進んだ。
未だこの段階では「三方ヶ原の補給基地・宿営地・浜松城攻略」に向かえる道である。
つまり、「第1回目の方針変更地点・城」から離れて「武田軍の本隊の後尾」を「額田青木氏の南下国衆の銃隊」が「追尾してくる事」を「武田軍」に「情報」として後尾より入っていた。
ここで、この「情報」に依って、更に「第2回目の方針変更地点」で「判断」を更に替えさせたのである。
それは「牽制行動の中止」の「最終的な決定方針」である。
つまり、「三方ヶ原」に向かうか、将又、「堀江城」に向かうかの「最終的な判断」に達して此処で方針を確定させたのだ。
その「二つの判断のポイント」が、「西と東の街道の交差点・湖東町交差点付近・館山街道」にあったと観るのだ。
同然に、「浜松城攻略」が「最後の作戦」と観ていれば、「二俣城」から南下して進軍してきて、其の侭に「三方ヶ原」に向かい宿営して「山県具の別動隊」を待って「浜松城攻略」を進めれば良い筈である。
その後に「堀江城を落とすと云う戦略」もあった筈だが、この場合は「本陣」が「野営と成る欠点・奇襲攻撃」を持っていたがそれを嫌ったのだ。
要するに、「信長の桶狭間の奇襲作戦・1560年」の例があったからなのだ。
その「奇襲攻撃・南下国衆の銃隊」は、「松平軍」と云うよりは、つまりは、直前の「一言坂」で遭遇した偵察隊の「額田青木氏の南下国衆の銃隊の攻撃」を予想していたのだ。
そうすると、「一言坂を通るという事」の詳細経緯の結論は、先ずは「余裕」を以て「浜松城そのもの」をある程度に牽制して置いて、後に「堀江城」に向かい当初から「三方ヶ原に陣取る予定」では無かった事に成る。
この事は、「一言坂の野戦」の「兵の数」と「織田軍の援軍」も無いと観ていた事に成る。
「織田軍の援軍」があれば、「一万近い兵」が「浜松城」には入り切れないし、「兵糧作戦」から「織田軍」は「補給路」を確立して、「城」の近くに「野営」をしていた筈である。
西には「堀江城からの挟み撃ち」や「大軍の織田軍の補給路」も断たれる事が起こるし、「援軍」は無いと観ていた筈である。
そもそも「織田軍」もそのような愚策もそうしないであろう。
兎も角も先ずは、「銃隊も攻撃してくる様子」も無いとして、その「牽制であった事」に成る。
然し、何れの戦記にも「野営と補給路の記載」は無いの通り、「織田軍」にしても「松平軍」の何れにも「野営」は現実に無かったのだ。
「浜松城」の近くに「野営」が無ければ「松平軍の戦略」は「籠城戦」である。
当然に、「一言坂の坂下」に降りた「額田青木氏の南下国衆の銃隊」も「城近く・北東の小高い丘」に「野営していた事・隠れる」は判っている。
現実には「軍議の内容」では、「織田軍の軍目付・軍艦」と「松平軍も」からも、間違いなく「籠城戦」としてその様な傾向に成っていた筈である。
「銃の牽制力の戦略的効果」を上げながらの「南下国衆の銃隊」も、「軍議」で拒否して外に出された以上は城に入れずに、そのつもりで攻撃せずに追尾だけにしたのだ。
ここで検証は「駿河青木氏の青木貞治」に関わって来る。
然し、「館山街道」の追尾中に、「軍議」に参加している「駿河青木氏の青木貞治隊」から“「驚くべき内部情報」”が齎されたのだ。
つまり、「一言坂の偵察隊との遭遇戦」で、暫く、「武田軍の本隊」は進軍に於いて「隊の再編成」を整えていた「時間・4h〜8h」の間に、この「松平軍の浜松城の夜間の軍議」が成されたと云う事に成るのだ。
これに対応した上記の経緯の変化点で、「追尾中の南下国衆の銃隊」は、“「信玄の臨機応変の二つの命」に待つ”という事、つまり、どう出て来るか待つ事に成ったと考えられるのだ。
「武田軍の本隊」には、「松平軍」に放っていた「隠密からの情報」が入っていたと観られる。
そこで、「一案・第1の方針変更」は、「城」を通過して廻って「三方ヶ原」で宿営して「山県軍の別動隊・補給路確保」を待って「浜松城」を攻めると云う「危険策」であった。
つまり、これは「二俣城の作戦」と同じである。
次に、「二案・第2の方針変更」は、被害の大きく出る「銃隊の行動」を観て、これを逸らして「堀江城」に向かう「安全策」である。
その「判断の起点」が、「西と東の分岐点の湖東町・館山街道」で現実のものと成ったのだ。
同然に、これは「額田青木氏の南下国衆の銃隊」にも同じ事が云えたのだ。
この時、「額田青木氏の南下国衆の銃隊」は、未だこの時点でこの「三方ヶ原」が「武田軍の宿営地・補給基地」で「籠城戦」と成ると考えていれば、“三方ヶ原方向の東に向かわずに、「もと来た道・館山街道南下」を採り、城には入れないので、「城の近くの丘に陣取る事」に戻る筈である”がそうは成らなかったのだ。
ところが、然し、ここで所謂、上記の「青木貞治の軍議情報」が入り「東の三方ヶ原」に向かっているのだ。
では「内部情報」を得たとしているが、「南下国衆の青木氏の情報源」は判るとしても、気に成る処は「武田軍の本隊」は何処からこの「情報・隠密説」を獲得したかである。
「情報源」が無かったとして「籠城」から「野戦」と変更されるタイミングは「城」を出た時であろう。
然し、これでは「三方ヶ原」を確保され、「補給拠点築造の山県軍の別動隊」は危なく成り遅過ぎる。
少なくとも「内部の情報源」で無ければ無理である。
そこで「内部に情報源」があったとして、「松平軍の軍議」に参加できる国衆は、凡そ200以上を持つ豪族である事になるので、「190居たとされる国衆」の内の“1割にも満たない数”である。
一つ考えられるのは、「時光系甲斐青木氏の五氏」である。
然し、この二つは「長篠の戦い」に消極的態度を採った「分家筋・巨摩郡と柳沢郡」であり、更に一つは安芸・女系の縁者から養子で継いだ分家の本家であって、「戦い」が始まると直ちに安芸に逃亡した。
依って、「甲斐時光系青木氏の武田氏系」と縁組をした本家筋の二つであった。
この「二つの青木氏」が「青木貞治」に「繋を採ったと云う事」も考えられるが、古来より甲斐とは「犬猿の縁」にあって「繋がり」は本来は無かった筈である。
唯、「二俣城」で「武田軍参謀の信種・浄賢」が「二俣城の開城の条件」として「青木貞治を救った事・副将200」があったが、この誼で「お返し・恩義返し」として、「額田青木氏の南下国衆の銃隊」に「内部情報」を提供したと同じ様に情報を提供したのか。
これは疑問であるが、“一族温存の為に”この「情報」を提供したか、又は、要求されたかの可能性があり、「戦乱の世」に於いて否定は出来ない。
元々、「松平氏の家臣」では無く、今川氏の家臣の「松井氏の家臣・近江での縁」であった。
この「松井氏」が潰され、「松平氏の家臣」の「中根氏の配下・二俣城の主将」の「副将」として入っていたのだ。
この事は、飽く迄も「流れの推論」であり、「一切の資料」からは読み取れず、且つ、「戦記」からも同然である。
然し、何も「情報源が無いと云う事」は考え難い。
もう一つは、追尾していた「額田青木氏の南下国衆の銃隊」の「突然の行動・三方ヶ原に向かった」のを観て、「異変を察知した事」も充分に考えられる。
つまり、この場合は「青木貞治が間接的に情報を提供した事」には結果として成る。
筆者はこの説を採っている。
そうすると、「額田青木氏の南下国衆の銃隊」の「銃力の威力」では、“「山県軍の別動隊・補給基地築造」が危険”に陥るとして警戒して「武田軍の本隊」が、これを護るために急遽、予定を超えて行動を起こした事も考えられる。
然し、「堀江城」から「三方ヶ原」に向かう途中で「魚鱗の陣形」を途中で編成しながら「三方ヶ原」に向かった「武田軍の本隊の行動経緯」を観ると、違うかなとも考えられる。
然し、場合に依ってはそのつもりで「進軍中」に、「松平軍が居ると云う事」に判り、更に「編成」を強めて後尾に居た「赤兜の騎馬隊を前に出した事」からすると充分に有り得る「詳細経緯」である。
「武田軍の本隊」からすると、城に入らず追尾して来た「額田青木氏の南下国衆の銃隊」が、「独自の行動」で「三方ヶ原・補給基地・宿営地」とする処に向かったとは考え難いだろうし、幾ら「脅威の銃力」を保持していたとしても一つ間違えれば極めて危険な行為の判断と観たのではないか。
「武田軍の本隊」は、その「南下国衆と成った初期の目的」は知っていたかであるが、「吉田城の戦い」や「一言坂の偵察隊の遭遇戦」から観て“「松平軍の銃隊」”と未だ観ていた事が考えられる。
「松平軍の軍議」で拒否し城外に外された事は未だ知り得ていないであろう。
故に、「南下国衆の銃隊」が「東の三方ヶ原の方向に走つた事」で察知し確信したのだ。
恐らくは、この時点で同時に「武田軍の幌者」を確認の為に「三方ヶ原・8.4k・馬0.8h・徒士2h」に走らせたであろう。
「南下国衆の銃隊」が「三方ヶ原に到着する前」に「幌者の往復」で充分確認はできる。
この時点で、少なくとも「籠城戦」では無く、「二度目の野戦との情報」が確認でき、この「情報源」が、実は上記の通り「額田青木氏の南下国衆の銃隊・下記詳細」にはあったのだ。
然し同時に、「松平軍」からすれば「武田軍の本隊」も「堀江に向かっている事」で直ぐに踵を返しても、この段階では「三方ヶ原」に来ない事は判っている。
とすると、この状況は少なくともこの時点、つまり同じ「西と東の分岐点の湖東町・館山街道」で「籠城戦」から「野戦」に「作戦が変更された事」の「情報の入手」を示すものと成ったのだ。
追尾していた「南下国衆の銃隊」が「三方ヶ原に向かった事」と合わせて間違いは無いとしたのだ。
「武田軍の本隊」と「松平軍」の両軍方に執っても「両軍に作戦が変更された事」に成る。
「松平軍の変更」で「武田軍」が変更したのか、将又、「武田軍の変更」で「松平軍」の変更が成されたのかは記録からは判らない。
「流れ・詳細経緯」から上記の通り「松平軍の方」であった事は判る。
但し、「三河側の戦記」では匂わしているが、「松平軍の変更」とは定説では成っていない。
一方の「武田軍側の戦記・資料」では、「堀江城を落とす事」に変更したとする程度で明確な表現が無いし、「三方ヶ原への変更」も明確な記載がない。
故に、「松平軍の変更」と成っているが必ずしも決定づけられない。
何れにせよこの「地点・西と東の分岐点の湖東町・館山街道」が「三者の運命の共通地点」という事に成る。
ここで、「武田軍本隊」と「松平軍」と「山県軍」と「南下国衆の銃隊」と「青木貞治隊」のこの「五者の全てのサイクル」が“「狂い始めた地点」”であるのだ。
ここで何故、「松平軍」が、まだ決まってもいない「堀江」に居る筈の「武田軍の宿営地・補給基地の予定地」を、先に「野戦・決戦場」と決めて、「三方ヶ原」に来たかと云う疑問に成る。
それには、「合戦の戦略上の常道」として、“「合理的な堀江を拠点にすると云う作戦」”もあった筈で、「武田氏側の戦記」では、「堀江城」を「長い時間・延4日」を掛けて落とす程にこの城に対して「大軍」を投入して“「注力」”を注いだのだ。
何も大軍を投入する程の城勢力では無かった。
これに付いて「両戦記で物語る事」は、「堀江城・武田軍本隊の指揮拠点」と「三方ヶ原・山県軍の別動隊の補給所の役目」の「二極拠点化説」が「武田軍側に在ったと云う事」である。
そこでこの事を後で知った「松平軍」は、この「三方ヶ原、山県軍の別動隊の補給所」を「野戦で攻める目的・補給拠点の破壊と場所の確保」であったとする事が頷ける。
然し、これには「高いハードル」が二つあった。
一つは同勢の「山県軍の別動隊」を打ち破る事である。
二つは「補給拠点」を絶たれた「武田軍の本隊」は必ず攻めて来て「決戦と成る事」である。
何れにしても「周囲の城を完全に落とされている事」から「敗戦見込みの賭け」で「織田軍援軍の時間稼ぎである事」は判るし、「織田氏の軍目付・軍監・3氏」も当初より「時間稼ぎに最も効果的な籠城戦」のその発言をしている事が戦記でも記されている。
最終的に「織田軍の大掛かりな援軍・援軍の意思なし・時間稼ぎ」は得られず、結局、「軍目付・軍監・3人・1200・美濃尾張の守備隊」の内の「平手軍の小部隊・主将戦死」のみが「三方ヶ原」で合力をしたし、元より「織田氏」は「武田軍の尾張進軍の時間稼ぎ」を「狙い」としていて「積極的な姿勢」では無かった。
故に、「平手軍」は「この時間稼ぎの一つの策」としての「作戦変更」に止む無く賛同して「合力・戦死」したのだ。
この事で後に「信長」に「軍目付・軍監の二人」は戦記の通り「信長」より「酷い叱責・追放」を受けたのだ。
この「後の史実」が「三方ヶ原」に出たのは「野戦で攻める目的・補給拠点の破壊と場所の確保」を証明している。
そこで因みに、この「補給拠点の破壊と場所の確保」には観えて来るものがある。
「堀江城、三方ヶ原、二俣城、浜松城、一言坂」の「五つの点の地形的な関係性」に付いて検証して観ると、この“「堀江城」の「武田軍側の二極拠点化説」”に対して頷けるものが見えて来るのだ。
先ず、この「五つの点」には次の様な「正三角形の位置関係」にあるという事である。
「一言坂」からは「5点の全体」は、当に“「正台形の位置関係」”を示しているのだ。
「堀江城」からやや北東側に「三方ヶ原」があり距離は8.5kある。
この「三方ヶ原」から同じ「線状A」の12.2kの位置に「二俣城」がある。
「堀江城」からほぼ「中間点の位置」に「三方ヶ原」があると云う事だ。
そして、この「三方ヶ原」から「線状A」に「垂直の位置」の「9.7kの位置」に「浜松城」がある。
この「浜松城」から南西側の「堀江城」に結ぶ距離は12.5kにある。
「浜松城」から北東側の「二俣城」までの距離は18.5kにある。
「一言坂」から「二俣城」までの距離は15.7kの位置にある。
「浜松城と三方ヶ原」の「線状A」を「左右対象の位置」に左に「堀江城」、右に「二俣城」があると云う事だ。
つまり、地形的に「三方ヶ原」は戦略上では、「武田軍側の拠点化」には「最適な位置関係」にあり、「籠城戦」とした場合は、「武田軍の本隊」の「三方ヶ原の野営」よりは「堀江城の本陣・指揮所」としてはより「最適な位置」にあったのだ。
この「武田軍側」のこの「二極拠点化説」には合理性がある。
言い換えれば、西の「織田軍の動向」を堀江から睨みながら、この「堀江城の存在」は同時に「浜松城籠城戦の長期化を予測していた事」をこの説は物語る。
「織田軍の援軍」はこの「堀江城」を攻め落とさなければ「浜松」には、上記の補給の問題もあるが、「入る事」さえも出来ないのである。
「三河戦記の定説」と成っている「援軍説」は無理であった筈である。
現実に「長篠の戦い」で「堀江城と二俣城」は歴史に遺る程の抵抗戦が繰り返された事が記されている。
という事は、この説からすると、「家康」はこの「補給拠点」を奪取して上手く行けば上記の「二つのハードル」を突破して、この「二極拠点化説」を撃ち砕く作戦に無理に出た事に成る。
この「補給拠点」を造ろう、或いは護ろうとしているのは「同勢の山県軍の別動隊」である。
其れで突如、「作戦」を変更して「浜松城」を早く出て、「三方ヶ原」に「鶴翼の陣で構えて待つ作戦に出た事」に成るだろう。
然し、この「作戦」は「信玄」に「館山街道湖東町の交差点の動き・南下国衆の動き」で悟られていたのだ。
定説とは異なり、密かに「家康」は「情報・定法の漏れる事」を恐れて「タイミング・山県軍の別動隊の動向」が来るまで心中に秘めていたかも知れないのだ。
何故なら、それは遠江では「190以上の国衆の寄せ集め軍・脆軍」であったからだ。
筆者は、この「きっかけ」は、間接的にも「青木貞治の南下国衆への情報」から興った事で心持ちこの気がする。
さて、この時の否定されている「鶴翼の陣形の妥当性」であるが、「山県軍の別動隊」と「同勢」、或いは「やや多い兵力」であるとするならば、「松平軍」が戦った場合は必ずしも負ける前提の陣形では無い。
何故なら「山県軍の別動隊」は、「二俣城の陥落後」に「二俣城」より経由して「三方ヶ原」に「補給基地を構築する使命」を帯びていた。
「甲斐戦記の通り」にすると、「山県軍の別動隊5000」とあるが、この内訳は記されていないがこの「使命」は明記されている。
とすると、この「使命」から「実戦兵・守備兵」は「約半分のと2000〜3000」と見込まれる。
「松平軍」は実質は「190以上の国衆の寄せ集め軍・脆軍」であっても、5000>2000〜3000とすれば「家康」は密かに勝てると見込んだ事が予想できる。
だから「鶴翼の陣とした」とも取れるのだ。
これは当に「甲斐側の戦記通り」である。
この場合からすると、当然に“「松平軍」が東側に陣取った”ので、「山県軍の別動隊」が西側に陣取る事に成ろうし、又、必然的に結果として「西の堀江城をからの応援を求める事」に成るので間違いなく、止む無くして「北の山際」を西に向かって廻り込む様に「西」に陣取る事に成る。
この「西向きの鶴翼」の是非は、「山県軍の別動隊・補給隊と戦後処理」には、「早くて突撃性の強い赤兜の騎馬隊」を有していないので、「攻めて来た兵」に対して相手がどんな陣形であろうが、随時、波状的に包み込む様に戦う事で互角には戦え問題は無い事に成る。
唯、「鶴翼の陣形の欠点」の一つは、「鶴翼の開閉」が出来ず「早くて突撃性の強い赤兜の騎馬隊・6000」の様な勢力に弱いと云う事である。
弱ければ疲れれば「本陣・大将」に突き抜けて仕舞うと云う事だ。
「山県軍の別動隊」にこれが出来たかと云う事であって、「補給基地を築造する使命」から、その「築造兵」を連れている以上は当然に出来ない事は一般として判る。
「三方ヶ原」で勝利すれば、「補給基地の使命」を帯びていた事から「浜松城の掃討」もしなければ成らない事に成る。
そうでなけれは「補給基地」は成り立たないし、次の「西三河攻略」の「第一補給基地」にも成る拠点でもあるのだし、それには「松城城の掃討」も「一連の重要な使命」であった筈である。
そもそも「戦い」は第一義的なものとして何れの戦いも「補給」無くして戦いは成り立たない。
これを危惧した「武田軍の本隊の上記した行動」に繋がったのだ。
因みに、早くて突撃性の強い「赤兜の騎馬隊・6000」の様に、「関ケ原の真田幸村」も大阪城から突き出した様に「廓柵・1km・馬防柵」を造り、周囲から攻撃されない様にして「本陣近く・家康」に近づき「騎馬隊」で突撃してこの「作戦」に出て成功している。
同然に、又、騎馬隊よりも早い銃を無視して頼り過ぎた面もあるが、この「赤兜の騎馬隊」が「武田軍の強み・本隊所属」でもあったのだ。
更に、参考として「家康」は、長篠後に、この「赤兜の騎馬隊・6000の勢力」をそっくり陣営に加え配下に組み込んで兵力を高めた位である。
故に、「松平軍」にはこれが無い以上は「鶴翼で同格に戦うと云う戦術を採った」と云う事にも成ったのだ。
中間説を採る戦記の「突撃性有無論の説」である。
もっと云えば、「堀江城の本陣化」は「今川氏真の失敗」を承知していて「家康」は充分に知り得ていた筈である。
だから、遠州が自分の手に入ったのだから知らない訳はない。
今その手に入れて遠州を「信玄」に「滅亡寸前」まで攻められているのだ。
「三河戦記」では定説とされている「本陣」を「三方ヶ原」に置くなどの事は露も思わなかっただろう。
要するに、故に「家康」は、“心の中に秘めていた判断”として「定説」とは違い、“補給拠点を破壊する”、又は、“確保する”と云う「戦術」に急変した事に成るのだ。
唯、とは云えど、これも「堀江城陥落の後」に、間違いなく奪回に「武田軍の本隊」は「三方ヶ原」に駆けつけて来ると云う難題があって、その時間内に勝利しなければならないし、再び、勝利しても奪回されるのは「時間の問題の課題」があった。
その時は、「城に逃げ帰る事」に成っていて、此処で「籠城戦に持ち込む」と云う「時間稼ぎ」にあったのであろうし、これであれば始めから「籠城戦」では無く、「織田氏の援軍の同意・軍目付・軍監の同意」を獲得できると云う「妥協中間策・時間稼ぎ」を執ったと考えられるのだ。
この「武田氏側の戦記」での仮説では、何処かの資料を以て史実に基づいて論じているかは別にして、この様に観ていたと云う事なのだろう。
これに賛同したのは「軍目付・軍監」の内の一人の「織田氏家老・平手汎秀」だけであったという事に成る。
故に合力して戦死しているのだ。
現実には、「武田軍の本隊」は「三方ヶ原」に出向いて来たが、出向いてきた理由は“補給拠点を破壊する”、又は、“確保する”事に対する作戦行動であったとしているのだ。
恐らくは、故にこの「説・二極拠点化説」の意味する処は此処にあったと考えられる。
だとすると、「軍勢とか陣形の是否」では「合理性に基づいた行動」として符号一致しているのだ。
本来であれば、江戸期で「戦記として論じる事」には「有利な立場」に成った「松平氏側の戦記・幕府」でも正しく論じられるものではあるが、そうでは無く不思議に冷静に筆者の上記の“青木氏の歴史観から観た考え”に似た「詳細経緯」が、「武田氏側の戦記の一つ」が論じているのだ。
気になるのはこの「論処の合理的な所以」である。
どうもこの「武田氏側の戦記」と云うか、「甲斐の戦記」と云うかの「研究資料の根拠」は「武田氏の戦略・戦術を決める立場の者」の傍に居た「家臣の書き記し・日記等」に基づく「総合論」である様だ。
明記はされていないがそれが「松平氏側の戦記」との「江戸期の照合論」である様だ。
この戦記資料は、江戸期初期には余りにも幕府自らも進んで行った「松平氏側の戦記」の“有利性を持たした美化の脚色論”に対しての「反論」であったのではないかと観られるのだ。
筆者は、「徳川家康・1563年に改姓後・長篠後に多用する」は、長篠後、多くの武田氏の家臣をそっくり抱え込んだが、この中の者が密かに「名・ペンネーム」に変えて「擁護論」を展開したのではと考えられる。
それが誰かは正確には判らないが筆者の見立てでは二人居る。
それをできる者として、先ず、綱吉の側用人の「柳沢吉保・甲斐青木吉保・時光系青木豊定の孫」が密かに家臣の誰かに命じて纏めさせたものでは無いかと考えている。
もう一人は、「松平氏の重臣」で「二俣城の副将」の「青木貞治・三方ヶ原で戦死」の「子孫・戦功を揚げる」が「無駄死にした先祖の名誉」の為にも「真実・史実」を書き記し遺したと観ているのだ。
この「駿河青木氏の青木貞治」の「子・長三郎・伊賀越えの功労者」とその子孫は、「御側衆3500石・上級番方」に取り立てられ破格の出世をしたのだ。
では、此処で、「柳沢吉保・青木吉保」の事は前段でも充分に論じているので、もう一人の上記でも論じた「額田青木氏の南下国衆の銃隊」に「貴重な情報を齎した者」は誰だったのかであるが、其れは「二俣城副将の青木貞治」である。
当然に、「伊賀青木氏の銃隊・荷駄隊50」にも、又「伊勢シンジケート・香具師・伊賀隠密」も参加している事は当然の事として、「伊勢隠密」も放っていた。
そこで「情報経緯」として、「松平氏の内部の情報」をどの様に「情報」として獲得したかを解明して置く必要がある。
実は、「額田青木氏の南下国衆の銃隊」の「指揮官」と、「国衆として銃の取り扱い訓練」の「指導者」として、前段でも論じた様に、「伊勢秀郷流青木氏」がこれに当たったし、且つ、「三河」に「開発業や殖産業」をして「長篠後」にも爆発的に子孫を多く遺した。
ところが、前記の「松平氏の重臣」で「二俣城の副将」の「青木貞治・三方ヶ原で戦死」は鎌倉期までこの地の「秀郷一門の豪族・駿河秀郷流青木氏」であった。
「全国24地域116氏」のここは「州浜族と片喰族」と呼ばれた一族の24地域の一つの定住地の一つであったのだ。
平安期には「駿河の最西端」の遠江との国境に定住した水軍族であって、伊勢屋信濃の制止を振り切って「源氏化」して源平戦に参加して滅亡したが、「伊勢」に依って再び探し出され「伊勢」で訓練を受けた「復興一族・女系」であった。
この「三方ヶ原後」の「青木貞治の子孫・長三郎」は「家康御側五人衆と呼ばれた者」で、「本能寺の変」の時、「堺に居た家康」を護っていた「御側五人」の中の一人であった。
この時の「伊賀越えの事件」には、「青木貞治の子孫・長三郎」以外にも「実家の駿河水軍」には他にも功績を挙げた者らが居たのだ。
伊勢の資料を繋合わせると、その詳細経緯が記され判って来る。
これによると、「本能寺の事件」と「青木長三郎から持ち込んだ家康救出作戦」が伊勢で採られた。
「堺の伊勢青木氏・仮名を使う・摂津店の商人」に先ず話を持ち込み、「伊勢シンジケート」を使って「伊勢福家」に連絡し、更に「一族の伊勢秀郷流青木氏」にも話を通し、「伊勢青木氏」が「伊賀青木氏・伊勢シンジケート」に指示して「伊勢」まで擁護して「四日市・青木氏」まで救出し一時休息させた。
そこから更に「青木氏資料の白子湾説」、又は他説では「長太浜説」より、「伊勢水軍」が周囲を保護して「青木氏の船」で「三河の大浜」まで運び助けたとする有名な歴史的経緯があった。
「伊勢水軍の伊勢衆」は後にこの事で家康から「お墨付き」を貰い江戸までの「永代の廻船業の許可」を得たとして記されている。
又、「伊勢シンジケートの情報」により「出迎え」に廻って海から警護に当たったこの「駿河水軍・実家」も「家臣・水軍」に加えられたとしている。
つまり、これが「駿河青木氏の青木貞治」の裔で、「伊賀越えの御側衆」で貢献した「駿河青木氏の青木長三郎の実家」であるが、この実家も家臣と成ったのだ。
これは「家康」には、「徳川軍に水軍の必要性」を感じさせた事件でもあり、「三方ヶ原の青木貞治と子の長三郎」の実家先の「駿河水軍青木氏の存在」をも認めさせた「勲功・褒章」であったのだ。
今川氏、松井氏、中根氏から遂には独立して、「近習衆・近番衆・近侍衆・近国衆の三河衆」の旗本に対して、「家人衆」と呼ばれる「関東の秀郷流一門・官僚族」が成った関東の「旗本」に加えられたのだ。
但し、注釈としてこの「伊賀越え」では、「家康を助けた者」では「堺の商人」も「伊勢の青木氏」やその「船などの所有者」もを「青木氏側」では一切直接に名を出していないのである。
「内部の資料・祐筆の記録」にもこの件の行動が記載されて遺されてはいるが、「本名を出さない仕来り」のこれは、全て“「青木氏の古来からの仕来り・青木氏の氏是」”である。
因みに、前段でも論じたが、もう一度この事に少し触れて置くと、その一つとして「信長の伊勢攻め」で「戦いの出城」として「松ケ島城」を建築したが、この際に、城の築城建材の一切を「堺商人・伊勢青木氏・伊勢屋支店・名変える」が請負い掛け合っていたが、物価高騰を理由に「高額な値」を付けて織田氏を財政的に影から揺さぶり、「伊勢シンジケート」を使って城建築の現場に職人を送り込み、建築材の遅延を理由に工事を遅らせ、挙句は「伊勢シンジケート」に依って出来上がつた城を燃やしたのだ。
この時も、「堺商人」は「伊勢」に害を及ぼさない様に「実名」を隠して接したのだ。
歴史書には時々出て来るこの「二人の堺商人」は当に「伊勢青木氏の人物」である。
「秀吉の長島氏攻め」でも同じ手を使って出城建築を遅らせたのだが、これを秀吉に気づかれて「自らの兵」を使って吉野の山から木材を切り出すと云う破目に成ったのだ。
この「偽名の手段」は、「堺支店の掟」であり、「堺」に限らず「全国488店の支店」にも適用されたと記されている。
この様に都度、「名」を変えたとしているのだ。
これらの事は、「青木氏の資料の行」のみならず「江戸期の物語風の戦記・二つ」にも成っているのだ。
通常は、要するに「超豪商」は「名」を変えるか、「顔」を見せないか、「人」を変えるか、時には「店」を変えるかして対応していたのだ。
この掟は別には借財も抱える等もしている「武力の持つ者」からの害を防ぐ目的があったのだ。
最大の目的は二足の草鞋にあって「商い」の行為が「賜姓臣下族青木氏の格式」に尾よ場無い様にする為の掟であった。
一般的にも超豪商は「テレビ物語などの様な実名を出す様な事」は決してなかったのだし、「伊勢青木氏」には奈良期からの「格式の氏是」があったのだ。
「伊勢青木氏」は「朝廷の命」で「紙屋院」として「925年頃」から「商人」も兼ねる「二つの顔」を持つ様に成ったが、これ以来に基づく「商人」としての「厳しい掟」があったのだ。
取り分け、実務の「堺支店の堺商人」や全国に店を持つ一族の「伊賀青木氏の香具師・隠密商人」等にもこれが求められていたし、これが大正期まで続いていたのだ。
これ等は明治期初期に「維新政府の命」や、「火付け打ちこわしの嫌がらせ」の圧力も受け無償放棄で「本店関係」を残し解体したのだし、「伊勢の青木氏部」も同然であった。
其の後には、広大な大字の本領地の土地までも、又、債権も無償放棄する結果と成り、この掟等は遂に歴史を閉じ霧消したのだ。
「伊賀青木氏の香具師等の各地の店」も一部は昭和初期までとし多くは大正15年頃までに各地に「影」を残し解体されるが、「明治期の厳しい締め付け」が緩み改めて大正期頃から各地の支店であった定住地では「掟」を無くして「青木・・店」として再出発している。
正しく理解する為の青木氏の歴史観として上記を付記する。
戻して、これ、即ち、「伊賀越え事件」は「渥美湾の制海権」を獲得した「9年後の事」である。
この「駿河秀郷流青木氏一族」の「菩提寺の西光寺・青木貞治」は「静岡県盤田市目付」にあって現在もある。
「南下国衆の指揮官」であった「伊勢秀郷流青木氏」の「三河伊川津田原」の「古跡神明社の隣200m」の所にも「菩提寺・西光寺」があるのだ。
この「二つの西光寺・秀郷流青木氏菩提寺」は真東西に「54kの位置」にある。
「伊勢の青木氏の裔系」とは「四掟」に基づき古来より「女系」で何度も網の目の様に繋がり、互いに助け合って来た。
当然に、「三方ケ原の戦い」の中でも容易くに「情報交換」はあったと考えられ、「内部の事情」は間違いなく把握出来ていたと考えられる。
故に「伊勢の家人等に遺されている手紙」などの「資料」には、信用度は高く資料の行の各所には「伊賀越えの事件」の一節等が記されていたのだ。
長い間の一族でありながら「情報を遮断すると云う事」は100%あり得ないだろう。
公で無くても提供しあっていた筈であるし、上記の通り「伊勢からの資金援助」も充分に有ったと考えられる。
そもそも「青木貞治等」には、「滅亡した駿河水軍の駿河青木氏の子孫」を探しだし、「伊勢」で教育して大船一艘を与えて駿河に帰しているのだ。
勿論、俯瞰し合っている「青木氏一族」のみならず「松平氏」にもである。
「松平軍」はこの「莫大な資金」無くしてこれだけの「長い間の戦いの戦費」は「石高」では何もできない。
「家康」も、「二俣城の副将・青木貞治」に据える位であるとすると、「青木氏」に於ける一族関係は承知していた事は間違いなく頷ける。
故に、だとすると、これが“「額田青木氏の南下国衆との初期の約束」”をぎりぎりのところで護った事になろう。
そもそも、氏家制度の社会の中であり、その様に考えるのが普通である。
寧ろ、筆者なら大いに利用したが、ところが「青木氏の氏是に基づく信念」を貫き、「提供」が結果として「青木氏に危険を招く」として、「資金の提供」はあったとしても「銃の提供」に関してだけは応じていないのだ。
又、「銃の保持」は、「青木氏の氏是」に関わらず、「銃」は「銃シンジケート」に依って掟の範囲で隔離され、仮に「金銭」が有っても「仲間の約束」は護り「調達」は難しかったのだ。
そもそも「青木氏の銃」は「貿易と財力と高度な熟練」を無くして手軽に保持できる「銃型」では無かった。
ハッキリ言えば、この「三つ要件」を身内に備える、況や“「青木氏銃」”であって「青木氏族」にしか使えない銃であったのだ。
それだけに飽く迄も「保持の前提」は、「額田青木氏の南下国衆の護身用の改良銃」であって、「松平氏・この頃から徳川氏を頻繁に名乗る」は、それを「国衆の戦力」として観てこれを「味方に持つ事」と引き換えに、「渥美湾の制海権の獲得の条件」を認めたのだ。
その意味では、“戦力と云うよりは抑止力的効果を期待していた事”も一部では読み取れる。
況や、この意味でも、「青木氏族の一員」の“「青木貞治とその子孫の松平氏の内部の活躍具合」”が読み解けるのだ。)
「青木氏の伝統 62」−「青木氏の歴史観−35」に続く。
> 「青木氏の伝統 56−1」−「青木氏の歴史観−29−1」の末尾
> 「青木氏」と同様に、主家が「神職族」であると云う格式から、つまり、高い「宿禰族」であると云う格式から、本来は「姓」は広げられない。
> 従って、「額田部氏」だけを何とか護ろうとしたが、結果として「神社」は遺せたが「氏名」は遺す事は出来なかったと云う説が頷ける。
> 「青木氏」は、「神明社」が有りながらも「由緒ある柏紋の神職・青木氏」を別に作り、これを徹底して「女系の四家制度」で切り抜けたのだ。
> 故に「神職青木氏」は各地で遺ったのである。
>
> 恐らくは「神職と云う事」から長い年代を「男系」だけでは難しかったと考えられる。
> ここに差が出たのではと考えられる。
> 筆者は全国に広がる“穂積氏で繋ぐ”と云う選択肢もあった筈なのに其れもしていない。
> それだけに「伝統を重んじた氏」であった事に成る。
>
> (注釈 江戸初期の「神社の統制令」の内に入り「で500社程度を有する神明社」を幕府に引き渡した。
> 江戸幕府は財政的にも管理し切れず荒廃は極端に進んだ。
> 但し、「伊勢と信濃と美濃と伊豆」では密かに「祠」で隠して護り通した。)
>
> 「額田部氏の系譜」の中まで入れないので、この「推測論」に成るが恐らくは間違いは無いだろう。
> それの遍歴が、現在は姓名が違うが「伝統」を護った「額田の宮大工」として遺ったとしているのだ。
>
> だから「施基皇子の裔の青木氏」には,当に、“「墳墓からの付き合い」”と記されているのは、“この事を察して護った”とする暗示の「青木氏の説」があるのだ。
「青木氏の伝統 56−2」−「青木氏の歴史観−29−2」
さて、前段の「額田青木氏・蒲郡青木氏」と「伊川津七党の青木氏・吉田青木氏等」のところに改めて戻る。
これには「別の面」からも考察が必要で、これに依って「青木氏の歴史観」が多く出て来るのだ。
この両者の「美濃の青木氏」は、「源平の美濃の二戦」で「近江佐々木氏や近江青木氏や佐々木氏系青木氏・近江三氏」と共に滅びた。
そして、別行動を執っていた「美濃」の「彼らの生き残り・伊勢の裔系」は、「加茂・木曽の山間部」に逃げ込み、「信濃シンジケート」として「伊勢等の支援」を受けて、密かに細々と「伝統」を守り生き延びた。
この間、平安末期からは「約300年以上」であった。
其の後、「額田を拠点」としてと「信濃までの山間部」で「原士・伊勢の裔系に付き従った官僚族」と共に生き延びた。
「美濃」で戦った「近江佐々木氏や近江青木氏や佐々木氏系青木氏・近江三氏」の一部も、「加茂・木曽の山間部」に逃げ込みんだとする一説もあるが、共に、この一部がどれだけ生き残り出来たかは判っていない。
筆者は滅亡したと考えている。
後に、「彼らの傍系支流一部」を探し出し、”「摂津」に匿った”とする「青木氏の資料」を採用している。
所謂、前段でも{論じた「摂津支店の支援」を受けた「摂津青木氏」である。
その意味で、この史実がある限りその一部が「加茂・木曽の山間部」に逃げ込んでいた可能性は否定出来ないだろう。
恐らくは、鎌倉期に入って暫くして「近江に戻る事」を望んたが、流石に「近江」には戻る事が出来ず、近くに居て、「摂津支店の保護」を受けて「商いの手伝い」をした事に成ったと考えられる。
そもそも前段でも論じたが、“「美濃の青木氏」は滅びた”と論じているのは、この“「美濃」”には「(aの族)と(a−1の族)と(a−2の族)」と「(bとcの官僚族)」の「四つの族」が居て、其の内、「(三野王の裔系のaの族)とその系列の(a−1の族)」の「全部」が滅びたのである。
つまり、「源氏化を進めた美濃族」である。
然し、「(a−1の残り・朝臣族、浄橋と飽波の裔系)」とその裔系の「(a−2・血縁族)」と、美濃の「(bとc・低位官僚族)」は、全てが「源氏化に賛成する者等」だけでは無かったし、元来、長い間に「多少の血縁性」は在ったとしても、「族としての関係性・氏族」は無かったのである。
要するに、「三野王を祖とする族(aの族)」とその「皇子族(a−1の族)」が「源氏化」を進め滅びた族であるが、「(a−1の族一部)(a−2の族)と(bとcの族)」の中には、上記の「浄橋飽波の裔系族」とは別に、彼等は、多少の所以を持つものの“「三野王に関わる美濃族」”としては“関わらなかった族”であった事に成る。
筆者は、「源氏化に反対」なのか、将又、「同族間の勢力争い」なのかは判らないが、何らかの理由で、恣意的に関わらなくしていた族”が居たと「状況証拠」から考えているのだ。
歴史的には記録として、激しい「同族間の勢力争い」があって衰退していたとする記録がある。
その原因は、「源氏化」なのかは明記されていないが、恐らくは、「源氏化に対する路線争い」であると思われる。
そもそも「平安末期」には、「美濃の土豪」であった「土岐氏」と血縁した「賜姓土岐氏系青木氏」が存在している以上はそう成るだろうし、この結果として「土岐氏の台頭」が目立つ故に、この゜土岐氏」も平安末期には完全な「源氏化」をしている。
「源平戦」で完全に滅びる事なく一部が何とか生き延びたが、室町期には弱体し乍らも存在している。
従って、「三野王系の中」には、「源氏化に反対していた勢力」が居たと考えられるし、その勢力も得て「浄橋、飽波の裔系」も早くから互いに「協力体制を採った流れ」の中に居たと観られる。
ところが、少し進んで、記録的には室町期の「織田勢力」が其処に付け込んで「美濃」にその「勢力」を拡大させたと成っている。
そこに存在していた「青木氏の影の勢力排除」の為に、その「信濃シンジケートの連絡網」、つまり、「命綱の断絶」の「神明社の排除」を図ったのだ。
困った「伊勢青木氏」と「信濃青木氏」は、この「別の命綱」の別の構築に入った。
「伊勢から美濃信濃経由の縦の陸路」を遮断され、周囲に危険が迫っていた事から「三河の松平氏」に「国衆」として入った。
そして、「370年程度」の間は現地に潜んでいた(a−1の族一部)(a−2の族)と(bとcの族)の「末裔」が、これを機に「伊勢と信濃の青木氏の説得」で創った集団の「国衆」であった。
その「支援」を受けた「国衆」のその「戦力(鉄砲とゲリラ戦)」を「売り」にして三河の伸長している「松平氏」に「国衆として合力」したと前段でも詳しく論じた様にである。
(注釈 松平氏の「三方ヶ原の戦い」の「戦記」に、「195の国衆」の中にトップに「二つの青木氏」としてのその行動が詳しく記載が在る。
結局、この「三河の三つの記録」に依れば「美濃の青木氏」は、「額田青木氏」と「伊川津七党の青木氏」の二つを纏めて“「渥美の青木氏」”と記載されている。
この「記録」では、「前者の国衆の傭兵」は多く戦死し、「後者の国衆の傭兵」は生還と成っている。
つまり、この「記録」に依れば、「後者」とは、「額田の青木氏」であり、(a−1の族一部)の事である。
そして「前者」とは、武蔵から各地の国衆を経て「信濃」に移動し、そして最後に「美濃」に、更に「三河」に移動した「武蔵7党の丹治氏系青木氏」、つまり、「嵯峨詔勅で青木氏を名乗った族」の事である。
つまり、上記の(a−2の族)と(bとcの族)の事ではない。
この「前者」は、この後に、豊臣に付き、形勢を観て土壇場で徳川方に着いて摂津麻田藩を獲得した。)
(注釈 この時の戦記には、主に「松平の戦記記録」と「甲斐国志録」と「物語風の伊能文」とか外にも「複数記録」がある。)
注釈として、前段で詳しく論じた「一言坂の戦い」の「武田本隊の先鋒隊」と「額田青木氏の国衆の偵察隊」とが「坂の上下」で対峙して、その「遭遇戦」で戦死と成っている。
「青木氏等の記録」や゜他の二つの記録」では、「三方ヶ原での戦死」と成っている。
これは恐らくは「一言坂での戦い」は、抑々記録でも二つあって、一度目は「松平本隊」が野戦を仕掛ける為に、つまり、「土地の有利性」を生かして「武田軍本隊」を迎え撃つ為に「一言坂の東」で戦い、完敗して浜松城に逃げ帰った。
もう一つは、この後に、「吉田城」から呼び寄せた「350の銃隊」を「偵察隊」として「一言坂」に派遣し坂上で、遭遇した戦いで、この二つを混同して記録したものであろう。
然し、一概にこれには「混同」とは考え難く、江戸期にこの「無謀な野戦」を脚色して美化したと考えられる。
そこで、この時の「350の銃隊の偵察隊」に付いて記録から検証して観ると、この時の事が良く判る。
「額田青木氏の国衆・蒲郡青木氏」は「250人程度」であったとされる。
「渥美青木氏の国衆・田原青木氏等」は「100人程度」であったとされる。
合わせて、「南下した額田の裔系の国衆」は「350人」とある。
この内、「50人」は「伊川津七党の50人」としている郷土史らの説もある。
恐らくは、この「50人」は荷駄隊に従事したと観られるので、差配は「250人程度」の50人であると考えられ、要するに「土豪3氏の内の一部」であったと観られる。
今川氏が滅亡し駿河に隣接するその「東三河」には多くの「溢れ国衆等の残存兵」が居た。
これを重臣の「酒井氏や池田氏」に依って纏められて、「東三河軍・2000人」にして2軍制にしたのだが、ここに「額田の南下国衆・350人」は組み込まれたとある。
「松平軍」はこの時の「軍勢」は未だ「3000人」であったと成っていて、「西三河」と合わせて5000人に成ろうとしていた。
「350の銃隊の偵察隊」は何と全体の「約1割の国衆の勢力」であった事に成り、本来であればその「発言力」は相当あった事には成るが、現実は「旗本の西三河侍」に依って阻害された経緯を持っている。
筆者はそもそもこの「兵数の違い」には、前段で論じた「準備段階前の移動の証」と成ると考えている。
そもそも、「額田の子孫数」から観て「逆の兵数」に成ると観られ、そうすると「(bとcの族)」を分散させて「主力」を「額田青木氏の国衆・蒲郡青木氏」の方に置いたと考えられる。
これが「兵の役割」にもあった事は否定できない。
前段でも論じた様に、つまり、この記録の「350人」は、「美濃の伊勢の裔系の末裔」とすれば「約800年間」として、その「子孫力」の「4Nの2乗論」からすると少なすぎると考えられる。
前段でも論じた様に「人口に合った耕地面積」を「額田部氏」に依って開拓開墾灌漑され、その糧は充分にあった事を証明した。
つまり、これらが「家族とそれを護る一団」が先に「渥美」に移動させたとする確実な証拠にも成るのだ。
要は、「国衆の南下後」に家族を移すか、「南下の前」に移すかの選択にある。
当然に「国衆」がひしめき合う「美濃」に於いて「家族の移動前」の「国衆の南下」は危険すぎて無い。
前段でも検証した様に「家族」などの「一族郎党の移動集団の規模」は、「1500人程度」あった事が検証から判るが、南下前の更に「事前準備に入る前」に移していた事も判っている。
(注釈 前段でも論じた様に「田原にある古跡神明社の神官族・伊勢青木氏」を頼りにして、事前に「1500人もの家族」が「渥美と伊川津と田原と吉田域」の四域に移したが、武田軍の東三河の駿河と三河西から攻め入った軍勢に対し、「東三河」ではその攻撃の的は、当然に駿河に隣接する「吉田城と二連木城の攻撃」と成っていた。
そもそも、「豊橋の吉田域」は前段と上記で論じた様に、「伊勢青木氏の神官族」の古来よりの定住地であって、そこに「伊勢の神職の家族」などの一族郎党が奈良期より入っていた。
当然に、「国衆」と成った「一言坂の戦い前」の「8年間の歴史的空白期間」は、当に必然的に絶対的に護らなければならない「地域」であったし、そして、その地域を護る「二つの城」でもあった。
この「二つの城」は、「豊川」の川際に建てられた「平城の吉田城・豊橋今橋」と、そこから真東・2kmの「朝倉川」の際にある「300m高さ」の「山城の支城の二連木城・豊橋二連木」であった。
前者の「吉田城の経緯」は、土豪の「牧野氏と戸田氏との攻防」の後、最終は「戸田氏の城」と成ったが、1565年に「三つ巴戦」で「家康の手中」に入った。
この「東三河」には「武田軍」は「1571年・第一次」に攻め入った。
そして、「二連木城」を簡単に攻め落とし「1572年に吉田城」に攻め込んだ。
この時、「三河の戦記」に「二連木城の兵」は「吉田城」に入ったとある。
ところが、「平城の吉田城」が落ちず犠牲が大きく成つた事から「武田軍」は一度甲斐に引き上げた。
前段でも論じたが、明らかに「山城の二連木城」より簡単に落ちる「平城の吉田城」が落ちなかったのは、「額田青木氏の国衆」の「近代銃による銃隊」で雨霰の様に打ちかけられた事に依るものであった。
其の後、「今川氏の衰退」により「松平軍」は駿河を獲得したが、「武田軍の第二次」が始まり劣勢に置かれた。そこで、直ぐに「額田青木氏の国衆」の「近代銃による銃隊」は呼び出されて「吉田城」を出て「浜松」に向かい、その後に「一言坂」に偵察隊として向かったのである。
「一言坂の戦い」と「松平本隊の野戦」の「本戦の内容」は、「三河の三戦記」に記載はあるが、この「吉田城の戦記」では、何故か詳しく無く「田原吉田の兵」が戦った事だけが記されている。
要するに、ここで云う「田原吉田の兵」とは前段でも論じた様に「伊川津七党の事」である。
つまり、「小さい館城」を持っていた「渥美氏と戸田氏と牧野氏と西郷氏」の「4土豪」と、その「運命共同体の関係」にあった「額田青木氏の伊勢の裔系族とその原士族」の事で有り、当初は「4土豪」とで結成された「伊川津七党」であった。)
そこで、この「吉田城の経緯」を検証する。
牧野氏・1490年―戸田氏・1506年―松平氏・1529年―牧野氏・1535年―戸田氏・1537年―松平氏・1540年―(牧野氏・家臣―戸田氏・家臣)―今川氏・1546年―今川氏・1560年―松平氏・1565年―酒井氏(松平氏)・1571年
以上の様に、目苦しい経緯を持つていて、「松平氏・1560年」から渥美の伊川津で松平氏に関わっているのだ。
以上の「注釈の論」は、「青木氏の歴史観・三河での戦歴」を決める為には重要であり、唯、そこでこの活躍の「国衆」として南下したこの「活躍した350人」をどの様に決めたかにある。
前段での検証から、「地積拡大」から観て「40000人」と計算されたが、これは「三河域・青木氏の定住地」も含んでいる事も考えて「額田の域」だけでは「山間部含み」であった事から、「最大1/20」として「最大2000人程度弱」は「糧=人口の原理」から居たと考えられる。
又、「10里四方・40k四方の面積」の「拠点額田域の税の負担」から観てもこれ以上は無いであろう。
要するに、「350/2000≒1/18」で「残り」は「家族とその一族一門の集団」と成り得る。
これを数段に分けて徐々に移動させた事に成る。
兎に角も、この「350人のその役割」は「銃を持った偵察隊」と成っている。
つまり、記録としては「銃隊」である為に、前記の通り「吉田城の後」は「先鋒隊・偵察隊」に指名されたのであろう。
然し、これは「銃隊配置の原則の戦法」としては考え難い。
これには何かがあった事に成る。
そもそも「銃隊」は、「陣形の前方」に置くのが「常套手段」であるので「先鋒隊・偵察隊」は可笑しいし、それも「350と云う相当の数」である。
これ程は入らないでろう。
この事から考えると、「両者の合わせた戦力」は「280〜350/3000」とすると、単なる割合でも約10%〜12%とも成り、「松平軍」の中では「相当な軍力・発言力」と成っていた事が判る。
其処に、「平城の吉田城」で「武田軍」を退けた「300丁の超近代銃」を持っていると成ると、この前段でも検証したが「数倍の力・10〜20倍」を持っていた事に成る。
現に、「信長」が{武田軍27000」を「1000丁・傭兵}で殲滅した「戦歴の史実」の事から考えると、「350の銃隊の威力」は兵力に換算すると、其れも「単発の火縄銃」では無く、「4連発の近代銃」であったので、「数倍の力・10〜20倍」は充分に納得できる。
とすると、「350の銃隊の威力」は「松平軍本隊3000」と同じ軍力を持っていた事に成る。
此の論理からすると、「額田国衆の発言力」は最大であった筈である。
何度も論じているが、「西三河の旗本の嫉妬」、又は、「無知」は「異常のレベル」であった事に成るし、「家康」も歴史で美化されるほどに「青木氏の歴史観」から観れば大した事は無かった事に成る。
“一言坂の「先鋒隊・偵察隊」の扱い”のみならず「三方ヶ原の本戦の扱い・鶴翼の陣形」も「異常中の異常」であった。
筆者は元より「美化の方」が先行していて余り「家康」を買っていない。
故に、当時の伊勢は、“早々に国衆を引き払らう事を支持した”と考えられる。
そして、記録通りに「武田軍本隊(20000)の先鋒」と「全面戦に成った事」で観てみると、矢張り、「一言坂の戦いの遭遇戦」と云われる位に、僅か1%で対決出来た事は、普通では出来ない筈である。
(注釈 「西三河の松平軍本隊は3000」とあり、「武田軍の攻撃」を受け護り通した「東三河の吉田城」より参加した「東三河の酒井氏の支隊2000」とで最後は5000と成った。
「二連木城」より「吉田城」に移り参戦し「武田軍」を甲斐に戻させた「額田青木氏の国衆の銃隊」は「東三河軍の吉田城」を離れ本隊に参加し「一言坂の戦い」に偵察隊として入る事に成った事の経緯は判る。)
この戦歴は「相当な鉄砲等の火器/300丁・商記録から算出」と、「得意とするゲリラ戦」を駆使して対抗出来た事を示すものである。
況して、「三河戦記の記録類」にある様に、「三方ヶ原」で「騎(額田青木氏の当主)・隊長」が戦死した「額田青木氏の国衆」の一部と、「渥美の青木氏の国衆」が無事に生還した事を考察すると、前段でも検証した通り、「武田軍本隊の追撃」を躱すだけの「相当な戦力の保持」があった事に成る。
その意味で、「本能寺の変」を境に弱体化した「元今川氏」の「北三河域」の「額田地域一帯」に「青木氏の勢力圏・縦の陸路・第一と第二の陸路」を「国衆」として拡大構築して“「命綱」”を更に蘇えさせる戦略に出た事がこの事からも良く判る。
恐らくは、この「兵数と銃力」は相当に「家康本人」からは信頼されていた事を物語るものであろう。
ところが「西三河の旗本」は嫉妬で別であった。
そもそも、「二連木城」を物ともせず押し寄せた「勢いづいた武田軍」との「平城の弱い吉田城」から退けた「戦いの功績」が「額田青木氏等の銃隊の功績」の記録として遺さなかったのは疑問である。
「吉田城」と「二連木城」は、そもそも「戸田氏と牧野氏の争い」の為に「城づくり」が成された城であり、
それだけに「護り」は弱いのである。
それを退けたのであるから「相当な戦歴」であった筈である。
「武田氏の資料」には“全滅に近い犠牲が出る”として“甲斐に建て直しの為に引き上げた“とある。
それ程の事が起こったのである。
記録を遺さない程の嫉妬であったのであろうし、青木氏の資料に依ればこれが「江戸の享保期」まで続いたとある。
それは「平城」で戦うには「20000の軍」を退かせるには「10〜20倍の力を持つ銃」以外には無い。
そうすると。2000+1000+7000=1万
重臣の守備の酒井氏は「2000の兵」で守備していた。
家康はこれを助ける為に西三河から駆け付けたが脆くも負けたので「残存兵」と共に「吉田城」に入ったとある。
この時に、“渥美や田原や吉田や西郷等の土豪衆・伊川津七党も西から入った”とある。
そうするとこれで、「松平の守備力」は「2000+1000+7000」=1万と成る。
然し、これは2万>1万では無い。
これは「入り乱れての戦いの勢力」の時の論理である。
「2k先」から「命中率90%以上の威力」を持つ間断なく打ち込んで来る「弾幕の超近代銃」なのである。
つまり、「2万の軍力」には意味を持たない事に成る。
それも完全な北に川が控える北本丸のある小高い丘の上にある土盛りと素掘りの平城である。
城門は東向きに当初あって、松平氏はその後に南門を付け加えた。
従って、敵は三方から主に南門と東門から攻め立てる事に成ったが、普通であれば「土掘りと素掘りの平城」で何の強みも無い城は「総攻めの兵力」で簡単に堕ちる。
然し、二つの記録に依れば「4倍の兵力を持つ武田軍」は「総攻め」で堕ちる事に成るが、ところが「銃隊」が存在した事からはほぼ水平に的を得て打ち込まれたとあり、このの範囲に近寄れば何もしないでも全滅である。
然し、「2000の兵」の「二度に渡る攻撃」を掛けて、“「全滅」に近い相当の犠牲を負った”とされていて、「全滅」を恐れて断念して「建て直しの為」に軍は「二度目の撤退」と成り“「甲斐に帰った」”とあるのだ。
(注釈 織田軍の側面からの脅威論もある。
然し、この説は矛盾である。東三河を攻めれば松平氏が全滅し東が武田勢に堕ちれば「織田軍」に執っては好ましくないとしている説であるが、この事は始めから判っていた筈である。
そもそも、「甲斐に引き上げる理由」には成らない。
「甲斐の戦記」にはこの事に何も触れていないのだ。
「信玄の病気説」もあるが、これを隠し通して先ず「三河」を落とした上で織田との本戦に備える為に三河に守備隊を置いて「甲斐」に引き上げれば済む筈である。
何れにして長期戦であった事から「甲斐」に一度は引き上げなければならないであろう。
現に、歴史は「吉田城の戦い・1572年3月」から丁度一年後に「三方ヶ原の戦い・1573年1月25日」と成っている。
その前の「一言坂の戦い・1572年10月13日」が起こっている。
「織田脅威説」にしろ「信玄病気説」にしろこの間に何も状態は変化はしていないのである。
明らかに、「思い掛けない手痛い犠牲」を負って「態勢立て直し」の為に国に引き返した事に成る。信濃にも引き返しているが、それ以上の問題が戦術的にあった事に成る。
恐らくは、「吉田城の経験」から「今後の戦い方」として当然に「銃戦に対する対策」であった事に成る。
故に、「甲斐の戦記」には幾つもあった中の一つの戦いの「吉田城の事」が記されているのだ。
そして、「三河の戦記」に「家康の談」として“長篠城の壁は銃の穴だらけであった”と記されている。
「武田軍」は「吉田城の戦い」で「甲斐」に帰り、この「難しい銃の入手」に一年間奔走した事に成る。
前段でも論じたが、念の為に「銃の数」は「戦記の中」では不明であるが、一年間で入手できる範囲は「精々150丁から200丁・火縄銃」であろう。
「近江、日野、堺、雑賀、根来」の「生産地の能力・総合産業」から当時は未だ最大でも「年間で計300丁程度」とされた。
その「雑賀と根来」は「長篠」までは未だ「織田の銃の傭兵軍団」であった。
其の後に、「犬猿の仲」と成る。
従って、「近江、日野」か「堺」と成るが、「堺」は「伊勢青木氏の商いの取引先」にあって難しいし、「雑賀」と「根来」も「伊勢の商い先」であって「資産投資先」でもあった。
従って、堺からの資材供給で成り立つ「近江」から、起きた破りの裏ルートの何らかな方法で獲得する以外には無かった筈である。
然し、上記の通り「銃」は「ある特定の商人」の“「専売品」”で、先に“「一括発注」”されて生産されるシステムにあって、「一般の市場品・市販品」では無かった。
「伊勢の紙屋」の「伊勢屋のシンジケート」と「今井神社シンジケート」と「近江の商いの特定組合」の手中にあった。
従つて、“「政治的絡み」”が大きく、獲得しようとした場合、「裏ルートの獲得」と成った。
つまり、此の頃から、“裏ルートを獲得した者が天下を取る”と云われていた。
さて、そうすると、「伊勢屋の青木氏」が専売で特注し獲得した“「近代銃と云われる物」”は「300丁」と「商記録」が成っていて、この「期間」を割り出すと、「額田の国衆」に渡し、「伊勢秀郷流青木氏による特訓」の訓練をした時を、「1540年〜1545年の間」であるとすると、これに「運び渡すまでの時間」を遡れば、「伊勢で調達出来た時間限」が判る。
これが、「準備期間の開始」を「1540年期限」だとすると、「商記録の記載日等の資料」を探ると「約1年弱程度の期間」が掛かっている事に成る。
「300丁/11〜13」が「堺と、又は雑賀と根来」の特注での「銃生産力」と成る。
これは資料から、“「新式銃・超近代銃」”とするものであったので、「普通の火縄銃の生産」と合わせると、「三カ所の全生産力」は「600丁〜800丁」を超えないものであったろう。
但し、これには「条件」があって、「主生産地」は「湊を持つ地域」で、それは「堺と雑賀」であり、紀州の奥の「根来」は、「同族雑賀」からの「下請けの流れ」の中での生産に成っていた。
「近江と日野」は「雑賀―根来」と同様に「一地域の流れ生産」であり、港は持っていないので生産は低いと考えられる。
「雑賀と堺」は「銃」に必要な「鉄生産と火薬や檜等の用材」を全て持つていた「生産地」である。
恐らくは、「貿易」に関わっていた事から「最新の銃の情報・西洋の情報」を掴み、高額を叩き「見本」を得て“秘密裏に特注した”と考えられる。
注釈として、「銃の型式」は確実には解っていない。
それは下記した様に、「火縄銃・1543年」で無かった事が解る。
「火縄銃類」でなければ、「読み取り」から「種子島から後の事・1543年伝来」であれば“「近代銃」”である事に成る。
「国衆としての準備段階」に入ったのが「1540年」であるとすると、その「2年後」に伝来し、これを「国衆の武器」に逸早く採用しようとしたのは1545年頃と成る。
「外国貿易」をしていた事から「銃の情報」はもっと早かった筈である。
恐らくは、「1540年頃以前」に「中国からの情報」を得ていたと考えられる。
「銃の歴史」は「1411年・ヨーロッパ」が「最古」であるとして、「1430年」には遺されていて、「1473年」には、「汎用的」に外国では取り入れているし、「1499年」には“「マスケット」”と「火縄銃の総称」として呼ばれる様に成っていた。
恐らくは、「貨幣経済」が進んだ「室町期中期」で「巨万の富」を獲得した“「時期・1454年頃・倭寇時代」”と見做される。
早くても「1454年〜1473年」には少なくとも「見本」を取り入れて“「堺」”で「伊勢屋の許」で密かに、つまり、「種子島の100年前」には“「試作」”が施されている筈である。
そして、「1500年頃〜1540年頃」には、「伊賀や伊勢水軍」では「貿易の倭寇の護身用」として持っていた可能性がある。
「戦乱期である事」から、当初は「密かな商い用」であったと考えられる。
それが、試行錯誤しながら「1535年頃」には「改良型の新型の近代銃」の「試作量産」に入れていたと考えられる。
そして、「国衆の訓練・1540年〜1545年」頃には間に合わしていたと考えられる。
そもそも「伊勢秀郷流青木氏・梵純」が、この時、既に「結城氏を護る為」に「兵」を北と東に動かしていて、「額田国衆の訓練の指揮官」も「1540年頃」には引き受けている事から考えると、この経験から「指揮官」そのものが「額田国衆」の「近代銃の訓練」で来ていた事に成る。
だから、「織田勢や秀吉勢に対抗する力・銃力」を持っていて、つまり、既に、まだ「珍しい銃」を持っていて、背後から迫る「伊勢秀郷流青木氏・梵純」を恐れられたのであろう。
「陸奥」から「北陸商用道」を使って「歴史に遺超す程」の「醜い退却」をしたのである。
この事は、既に、「伊勢秀郷流青木氏・梵純」には「1543年の前」には「伊勢青木氏・伊勢屋」は密かに生産していた試作のものを彼等に渡していた事に成る。
其れで無くては、「伊勢秀郷流青木氏・梵純」の「僅かな兵力を恐れる事」は無かった筈である。
前段でも論じた様に、「伊勢の人口」は「不入不倫の権」で抑圧され「全国平均の1/20程度」しかなく、取り分け、「北勢」は“「聖域であった事」”からこれを護る為に少なく成っていた。
それ故に「中勢以南」に「人口」が集中し「室町期中期」には「全国平均並みの92万人」であったとされる。
「北勢に住む秀郷流青木氏」を含む「伊勢藤氏」が、史実の通り「対抗軍」を編成したとしても最大で「1000人〜2000人程度」であろう。
この「勢力」が背後に迫ったからと云って、「兵糧攻め」している中で慌てて「攻める事」を止めて「一般道」を通らず「北陸商人道」と云う「特別の険しい道」を通って「大坂」まで逃げ帰る事まではしない筈である。
何かが無ければ何処かで「陣構え」をして「迎え打つ事」はこの「人数・2万に拡大」では充分に出来た筈である。
結果としては「1510年頃」から“「北陸の戦い」”は始まり、「1575年・天正の乱」と「戦い」は続き、更に移り「1590年」に遂に「奥州仕置き」と発展し、「奥州の白川結城氏」は衰退し滅亡した。
この間の「織田勢の奥州攻め」の「支城一戦・1540年頃・三戸城等の在郷領主連合軍」である。
この“「奥州攻め」”では「陥落した城や領主」を勢力下にして「軍力」を大きくして行ったのである。
「種子島鉄砲伝来」より前に、既に“「試作」”が成され、その間、僅か乍ら“「量産」”に持ち込んでいた「伊勢屋」は、これを出来つつあるものから「伊勢藤氏」と「伊賀原士」と「伊勢水軍」と「秀郷一門一門」、或いは「信濃・諏訪含む」や「伊豆」に護身用に密かに渡していたのでは無いかと考えられる。
つまり、「種子島の100年前」には、「欧州・フランス」から兵用に使っていた銃を見本として取り寄せ、“「試作」”が何度も施され、そして、「1500年頃〜1540年頃」には「試作量産化」が成され、「1535年」には「火縄銃」を超えた「新型銃の試作と量産化」と成っていたとすると、間尺が合う。
それだけの「財力」は充分にあった。
そして、それが「伊豆」を救い「額田青木氏」を救う事が出来るのだと執念に燃えていたのだ。
何しろ、「奈良期」からの“「紙屋院の称号」”を獲得し「高位族」で在り乍らも“「造部」”を支配下に置き、自らも「青木氏部」を持ち、唯一、「商いの出来る特権」を得ていたのであり、それを更に発展させて「朝廷の財政・献納」を潤していた。
その「伊勢屋」は「貿易」をしていたのである。
この「状態」は前段でも論じた様に、明治中期まで続いていたのである。
そもそも、「進んだ銃の存在」を“「知らないと云う方」が可笑しい”であろうし、「造れない方」が可笑しい。
それを連携して叶えていたのは要するに「堺の呼称」なのである。
そもそも、奈良期から最も「海外の情報」を手中に収めていた「氏族」なのである。
“「銃の事」に関しては何事も条件は揃っていた”のである。
寧ろ、“何でも出来ると云う立場”にあった。
「青木氏の歴史観」はここにあるのだ。
これを忘れては「歴史の考察」は間違う。
その前提の意味で「全ゆる資料の行」の「一字一句の持つ深い意味」を読み解いているのだ。
この「銃の事」も同然である。
故に、密かに持つ「近代銃の力」で「1000〜2000の兵」としても「2万〜4万の戦力」と成って討ちかけられれば“全滅”として恐れられ、一時は「額田青木氏・蒲郡青木氏」の一部が「桑名」に引き上げた「史実」と成ったと考えられる。
「伊勢」と詳細を打ち合わせの為に戻った可能性が高い。
この「試作近代銃」を得て「伊勢の伊勢梵純の戦力」は「2万〜4万の戦力」と周囲から見做され、その兵力で「織田氏の勢力」を「大阪」まで追いやり、そこで陸奥の「小峰族の血筋」の無い「生粋の白川結城氏の一族末裔」をその「本家の永嶋氏」の「茨木結城・永嶋氏」に救い出した事に「伊勢梵純の戦記史実」として成ったのであろう。
そして、この何度も「試作量産銃」を「伊勢藤氏に渡す事」で「伊勢全域を護る血縁族の抑止力」ともしたと考えられる。
そこで、気になる処はこの「銃」を「信濃」に渡していたかであるが、手を尽くして色々な可能性を調べたが判らない。
「信濃」は唯一の奈良期からの「同族血縁族である事」から「伊勢藤氏」と同じ様に渡していた可能性は高いと考えている。
後段でも論じるが、「状況証拠」として「諏訪青木氏」の武田氏本隊での「一言坂の活躍」でも判る。
上記した様に銃が得られない状況の中で、「一言坂の遭遇戦」で僅かながら持ち得ていた事が史実として判っている。
武田軍の中で獲得出来得る国衆は信濃諏訪族の裔系以外に無い。
これだけ渡す「間口」が広ければ数から観れば“「試作」”では終わらなかった筈であり、額田は勿論の事、「全青木氏」の“「内々の量産」”であったと観ている。
戦国の世から「青木氏を生き残らせるための策」であったと考えている。
筆者はこの前提は、前段からも論じている様に、「室町期」に入り「下克上と戦乱期」に入り、「青木氏族の危険性」が極度に増し焦ったのでは無いかと考えられる。
そして、その為にもこの「抑止力」を高める為にも「青木氏の奈良期からの利点」を生かして“「財力」”を蓄えたと考えられ、幸いにも「紙文化」が花咲き「巨万の富」を獲得した。
そこで、この「財力」を使って「兵」を待たずとも出来る「銃の様な防御力・抑止力」を何とか確立させようとしたと考えているのだ。
それが、この「銃の先取りの試作」であったと観ていて、それが「美濃の国衆の近代銃」に繋がったと観ているのだ。
「公式の記録」では、「1543年の種子島」と成っているが、既に秀吉や家康は薄々は「伊勢青木氏」が背景で「堺」で「寡占的」に「秘密裏」に何か「変な飛び道具」を作っていた事を知っていたと考えられる。
然し、“懐疑的な面もあった”と考えていただろう。
故に、「梵純の兵」を“極度に警戒した事に成った”のであろう。
(注釈 この秀吉が銃を持った時期の歴史は次の通りです。
実は1588年に「刀狩り」があります。
その時の絵図にも「鉄砲」は描かれていて「記録」は遺つています。
つまり、これは「武士以外の者」が持っていた事に成る。
「1575年の長篠の戦い」では「雑賀と根来衆の銃の傭兵」で「信長」は獲得します。
これは「秀吉」が「信長」に進言し「調達」を「今井神社シンジケート」に「調達」を試みたが失敗に終わり、結局は「雑賀と根来衆の銃の傭兵」で「決着」が着く。
これはこの頃、「特殊な武具の情報・銃」を既に掴んでいた事に成る。
これは「蜂須賀小六の子分時代に知った事」に成っている。
秀吉は「1537年〜1598年」で、少年時代(15祭頃)に「蜂須賀頃の子分」に、「信長」に「草履取り」で「1558年」に、つまり「21歳の時」である。
「少年時代に情報」を掴んだとすると「15歳〜21歳」で、「信長・1532年〜1582年」に進言したのが仮に「2年〜5年」経っての事として、“「1560〜1563年」”に成る。
「種子島鉄砲伝来・1543年」とすると、「1558年」までには「15年経過〜20年経過」している。
この「1560年」は「桶狭間の戦い」で「今川氏」を衰退に追い込んだ時期である。
「1568年に上洛」、「1570年に姉川の戦い」、「1573年に室町幕府潰す、そして「武田軍」との「長篠の戦い・1575年・銃隊」と成る。
これが「実戦の種子島の経緯記録」と成る。
火縄銃の規制では、「秀吉の刀狩り1588年」と、これを「15年後」に引き継いだ「家康の1603年の銃規制」と成る。
故に、原則として「1560年〜1563年」までは誰も「銃」を持っていなかった事に成るのだ。
“入手できるとか出来ない”と云う前に、「銃価格」が「この時期」では余りにも入手出来ない程に「高価」であり過ぎたし、当然に「生産量」が無かった。
故に、「シンジケート入手」として独占化していたのである。
そもそも「生産態勢に必要とする財源」の供給が無い限りは無理であった事から「独占寡占化」して「シンジケートルート」に成っていたのである。
従って、「雑賀根来の銃傭兵」の方が可能と成るのだし、「銃を扱える熟練度」も必要としていたが未唯、その様な者は「生産者が財源元の支援者以外」には育っていなかった。
「シンジケートルート」と成り得る根拠があって、要するに「銃に依って得られる利益」は「販売で得られる利益」より「シンジケートを維持する事に依る利益」の方が遥かに大きかった事と、販売する事に依って「自らへの危険度を増す事への警戒度」が大きかったのである。
つまり、この集団を浮力に依って獲得して勢力を拡大させようとする危険度である。
これ等を無くすには、「シンジケートルート」しかないのであって、とは云っても「財源の補償」をしてくれる「バック」が必要であった。
当然に”口を出さずに”である。
そうなれば、「七割株の豪商」と云う事に成り、「商い」だけが成り立てば必要以上には”口を出さずに”に居たのが「伊勢屋・伊勢青木氏」であったのだ。
この「伊勢屋」が「氏是」で“銃の世間への広まり”を危惧していたのである。
飽く迄も、「抑止力の前提」の許にあったのだ。
ところが、又もや、「近江・日野」がこの「掟」を密かに破つたのだ。
この「近江日野」には「資材の供給の停止」と「財源の補償の制裁」を加えたのだ。
これが、結果としてその「職能」は空気感染を起こし各地に飛び散った。
「伊勢屋」はこれを止められなかった。
然し、幸いに広まった「火縄銃」は旧式で「マスケット」を超えていなかったのだ。
それでも「秀吉と家康」は抑え込もうとした事はいい方に働いた。
注釈として さて、そこで歴史に遺る「正規の火縄銃の生産経緯」はどの様なものであったのかである。
重要な歴史観を決める要素である。
「歴史の経緯」が記載されている説では、次の様に成る。
「根来寺の杉の坊算長(津田監物)」が自ら種子島に渡り、「鉄砲と火薬の製法」を習い、これを「根来の地」に持ち帰えったとされる。
その「鉄砲と同じ物」を根来の坂本に住む、「堺の鍛冶師、芝辻清右衛門」に製作させたのが「本州最初の鉄砲」と言われている。
実際は違っている。
上記で論じた様に「筆者の資料・近代銃・フリントロック」では、「貿易」で「種子島より相当前」に密かに入手し、それを「堺・持ち株7割・伊勢屋支店」で造らしていたとある。
「火縄銃」とは全く書いて居ず火縄銃ではないと考える。
出来るかどうかも判らない「フリントロックの改良型」を追求していたのであった事から銃名を書かなかったと考えられる。
「伊勢青木氏の資料」と同じ「歴史経緯に乗らないルート」を論じている説が他に「三説」がある。
一つ目は、「近江佐々木氏の青木氏研究論」に葉、”種子島”とは書かずに相当前に入手していたとする「行」がある。
これは「伊勢青木氏の資料の事」と同じで恐らくは「伊勢屋の事」を言っていると考えられる。
二つ目は、歴史の経緯の公的に成っている「記載説」に、「但し書き」として、“「種子島」は決して始めてでは無い“とする「添え書き」による入手事前説がある。
唯、生産していたとは明記していない。
三つ目は、二つ目と同じく「但し書き」であるが、「伊勢」では無く「近江の日野」とあり、「近江商人」をイメージする表現と成っている。
但し、三つ目は二つ目を参考にして論じたとものと推測できる。
合計4説があり、「青木氏説」も入れて「二つ」が「事前説」を強調し、「残り二つ」はそれらの“「種子島より事前説」”もあると説いている。
これ等の「4説の根拠」は二つある。これを分類すると次の様に成る。
一つは「青木氏の説」と同じく“「貿易説」”である。
二つは“「銃の長短説」”に基づいている。
「貿易」に依って「100%に情報」が早い。
そうでなければ「抑々論」で「貿易」は出来ない。
これに基づいて「貿易」は成されている。
要するに゜情報の遅い貿易」はあり得ない事に成り、完全に納得できる。
「銃の長短説」では「火縄銃」は大した訓練を要せずに使える。
然し、「天候」に左右され、「命中率」も低く、硝煙の火薬は貿易に頼るし、「飛距離」も短いと云う欠点があり、「西洋」では「個人的な使用に類する使い方」に限られていた。
これが「マッチロック式マスケット銃類・火縄銃類」と云うものである。
ところが、この「マッチロック式マスケット銃類・火縄銃類」の「欠点」を改良したのが「ホイールロック式銃」か、更に改良した「フリントロック式銃」であって、「欠点」は「火縄銃の裏返し」である。
「フリントロック式銃類」は、「活動性(軽量・移動)」を重視し、訓練で熟練度を必然的に挙げる事が出来るので「軍隊」に早くから広く採用されていたのだ。
この「軍隊」に広く採用されていたとすれば,“「貿易」”で「国内に情報」が入らない方が可笑しい。
故に、では何故、この「ホイールロック式銃」か、「フリントロック式銃」かが入らなかったかという事に説明が到達する。
入ったのは、“「個人用」”としてに持ち込まれた汎用的な“「火縄銃」”が先で、其れも「10種類」ほどある中の「初期の銃」であった事に成る。
そもそも、この「火縄銃の旧式銃」を日本に高く売り込んで「商い」とすると云う「外国の戦略」であった。
「伊勢の伊勢屋」が見本を入手した「銃」は、上記で検証した通りの「ホイールロック式銃・見本銃」か、「フリントロック式銃・近代銃」であったのかは確定は出来ないが、「汎用的火縄銃」を目的としたもので無かった事は明確と成る。
見本として入手したのは状況証拠から「フリントロック式銃」であろう事が判り、これをよりに日本人向けに、更に、「活動性(軽量・移動)」を重視した銃に密かに堺を使って改良を重ねたと云う事に成る。
急激に高まった「下克上と戦乱」の「極度の危機感」からの生き遺る為には「全財産・巨万の富」を使てでも獲得しようとしたのだ。
要するに、「銃に関わった理由」は、上記した“「青木氏の抑止力」”を「強化させる事」を“目的としたもの”であった事に依る。
(注釈 前段で論じた「美濃の額田青木氏の南下国衆の携帯した近代銃」は、上記した「1588年の刀狩り」では、既に“「商人の陸運業」”としてだけでは無く“「武士の護衛団役」”として帯同していた事であり、“「刀狩り」”は適用されずに逃れられた事を意味する。
この1588年時は、既に、「三方ヶ原の戦い後」の「1572年}で「国衆」を辞め「強力な陸運業」に専念した15年後の事であった。
当時は、未だ「盗賊山賊」が多く危険で「元美濃原士」であった「繋がり」もあり、襲っても「軍隊」でも「瞬時に潰せる能力」の持った「陸運業・伊勢屋の仕事」であってその相手では無かった。
この「刀狩り」には掛かったとする記録はない。
問題は、「大名」に課せた「1603年の銃規制・火縄銃」にはどの様に対処したのかは、「対象の大名」では無かった事からも、殆どは、「五つの記録」や「江戸期の小説」にも記載は無い。
「陸運業と開発業と殖産業」に成っている事は知られている。
その裔が行った有名を馳せた「額田青木氏の一言坂の戦い」を知っているし、例え、山賊や盗賊でも戦いを挑む馬鹿は居なかったであろう。
寧ろ、逆であったと考えられ、「遠方運送の場合」は連携して「協力態勢」を執って「糧」を得ていた可能性の方が高いだろう。
宿で隠密の様に,“次の連携について打ち合わせた”とする資料はある。
筆者は、この「一部の資料の行」を読み解くと、常時、使う陸路の場合は積極的に潰したか、その仲間に糧を与えて組み込んだと考えている。
「運送荷駄団」の「側面護衛」を前提にしている以上は、この考え方の方が自然であり、「抑止力」としては「美濃の国衆の役目」の様に「伊勢式」で、当時としてはこの記録は「1000年の歴史」を持つ「氏是」に沿っている。
この様に「強力的で協力的な抑止力で済んだ筈」である。)
さて次に、上記した様に「信長」が果たせなかった“「伊勢攻め」”で、今度はこれを引き継いだ「秀吉」は、「伊勢と紀州の勢力」を「紀州攻め」で、「銃」を生産し、且つ持つ「銃勢力」を潰しに掛かった。
上記した様に「秀吉」は「1552年頃」に、この「銃シンジケート」を知っていて天下を取ると逸早く潰しに関わった。
「銃生産と保持者」のみならずその「影と成る財源力」も潰しに掛かったのである。
「信長の雑賀根来攻め」は、「1577年、1581年、1582年」と三度である。
これには伊勢側は何とか「ゲリラの抑止力」で絶えた。
然し、これを引き継いだ「秀吉の紀州征伐」は「1585年」であった。
歴史に遺る「秀吉」の「信長」を超える「残虐な酷い殺傷の戦い」をした。
この時、「伊勢青木氏」は逃亡してくる「紀州門徒衆」等を匿ったし、然し、この為に「松阪の蔵」や「菩提寺・本寺」を焼かれた。
「銃生産の財源の背後」と知っていた「秀吉」の「長島の戦い」でも抵抗した。
最後には、「青木氏の旧領地・弱点」の「南勢の奈良期からの旧来からの氏人・郷士」の“「湯川衆攻め」”までして仕掛けて来たのである。
そもそも、この「南勢の湯川衆」は確かに「旧領地」と云えど政治的にも秀吉に抗した訳でも無く、「直接の関係衆」では無かったが、それでも「牽制の為」にも攻めたのである。
「氏人の伊賀攻め」も同然で仕掛けられた。
然し、これを「氏是」を護りながらも「秀吉の弱点」の「ゲリラ戦の抑止力・伊勢シンジケート」で抵抗したとある。
「観えない相手と戦う事」に疲れた秀吉は、これで「南勢の湯川衆攻め」から手を引いた。
然し、「北勢の攻め」も「伊勢青木氏に関わる攻め」たけは「深入り」をしなかった。
これ全ては「銃に関わる背後関係」から来ている筈である。
矢張り、“「ゲリラの本格戦」”ともなれば「三河の伊勢の裔系」からも「近代銃の陸運業隊」が駆けつけ、更には「銃」で既に防備していた「全国の秀郷流一門」や「伊賀衆」をも本格的に敵に廻す事に成るとして「得策」では無いとし、秀吉は「単なる牽制」で終わったのである。
「伊勢水軍」や「摂津河内水軍」や「堺衆」や「雑賀根来衆」も「力を盛り返して来る事」に成り、「秀吉の兵力」を遥かに超えて「無傷で上回る事」を意味していたのである。
それが「ゲリラ戦」と来ていると成れば手は出さないであろう。
「信長の紀州攻めの失敗」も知っている。
これは当に、密かに「伊勢青木氏」が「銃生産」で「抑止力」として「相当な銃力を蓄えていた事」を知っていた事に成る。
故に、「見せしめの牽制策」として、徹底して「根来一寺」を滅ぼせば、「紀州の諸豪族は刃を交えず降伏する」と見込んで、「根来勢の徹底壊滅」に乗り出したのである。
「すさまじい勢い」の「秀吉軍10万の大軍」を相手に「根来勢」は、「積善寺」をはじめに、千石堀、沢、畠中と次々に出城寺を攻め落とされ、最後はこの「本拠地の根来寺に逃げ込んだ農民等」に対し、「秀吉軍の本隊」が着いた時には、「寺衆・農民庶民」では既になく「抵抗する者」は全く居なかったと伝えられている位の殲滅状態であったとされる。
それでも、寺門から出て来た「戦力の持たない農民庶民」の全てを殲滅したと「記録・6000人」に遺されている。
さて、この「銃の事前獲得」に就いて、凡そ「資料の行」から、新たに、この“「300丁の銃」”を整えるとしていて、その「二つの銃(ホイールロック式、又はフリントロック式)」を整えるには、“「新型の事・フリントロック式・試作銃」”もあって纏めるには、「資料の存在の意味合い」から観ても「最低5年〜最大7年程度」は要したと考えられる。
この「二つの近代銃」は、“「扱い」”が難しく“「熟練を要した」”とだけ記されている。
“どの様な熟練度を要求していたのか”を他の資料と共に探るとする。
それは「火縄銃」は、上記で論じた様に、その「飛距離」、「命中度」、「殺傷力」、「環境力」、「時間差」の「5点」が低かったとされる。
ほぼ後に「欧州」で開発されたものは「小銃的・短銃」なもので「個人性」を有していて、一部でこれを「軍用」として「日本」では使おうとしたが直ぐに失敗したとある。
其れは“弓より劣る”とする理由であったとされる。
この「5欠点」を全て改良した結果、再び、何が起こったかと云えば、「射撃発射時の反動の悪化」であったとされる。
この「反動」があると、行き成り焦点を合わして構えるのではなく、肩に沿えた構えで「縦膝姿勢」で「反動」に耐えられる様にして、先ず、「銃」を上から下側に下ろして来るとしている。
そして、「狙いの位置」で引き金を引きシリンダに込めた弾丸を火打ち石で発火させて連続に打ち始める。
この時、1発目から4発目まで撃つ度に「長い銃身」が反動で少し上側に上がる。
これを“「訓練で少なくする事」”にあった。
然し、これを小さくする手段として「伊勢」が求めたのは、この「訓練」は兎も角も、“銃身を短くする事”にあったとしている。
これには意味があった。
この「銃身を短くする事」は、「飛距離を短くする事」になるが、「火縄銃」と違い「飛距離を短くなる事」には「黄鉄鉱の火花の爆発力を高める事」でより補い、それは上記の「活動性を高められる事」に成ったとしている。
然し、依然としてこの「反動」は高く、これを「打つ姿勢」を良くする事で「訓練」に依って、この「反動具合」が身に就いて来ると、“一定率に熟す事”が出来る様に成ったとして記されている。
恐らくは、この「発想の根拠」は、丁度、“「日本式弓の連射」に完全に相似している”としているとして採用したと観られる。
恐らくは、「銃に対する考え方」として「武器」と云うよりは、「弓道」に匹敵する「銃道」と観ていた可能性があるのだ。
この「銃道の考え方」の方が「青木氏」としては自然では無いか。
これを「額田青木氏」に「伊勢」は求めたと考えられる。
飽く迄も「護身術の一つ」として考えていたと観られる。
従って、それまでは「武士の嗜み鍛錬」として熟知していた「飛び道具の弓矢隊」が「銃隊に特化する事」に成るに等しく、“この「銃の熟練」には問題は無い”としている資料が遺されている。
中には、“人間の本能が蘇らせる”とまで書いている。
だから、この「近代銃」の生まれた「西洋の合理的考え方として」では、逸早く「火縄銃」を捨て、早くから100年も前から「高価」であっても、「威力の高い銃・小銃」を好んで”「兵用」”として用いられたのであろう。
日本では、「日本式弓の連射」がこれを導いたとしているが、手の届きそうでは無い「高価・4千両〜2千両/1丁」であって、更には前段でも論じた様に「三河武士」にあった様に“旧態依然としての感覚”がこれを排除していたのである。
それが「刀狩り・1588年」と「銃規制・1605年」に表れているのだ。
つまりは、“天下を治める”には、「絶対的武力差をける事」で「安定化を図る方式」と、逆に、「威力の高いものを排除」して「安定化を施す方式」かの「主観差」であろう。
然し、結論としては、「青木氏一族一党」はそもそも「天下安寧の目的」では無く「抑止力を増す方法」としての“「前者を採用したと云う事」”に成るのだ。
「積極的に威力として使う目的」では無かったから、「弓の延長」として“積極的に「近代銃」を先駆けて採用した”と考えられる。
“「殺戮の道具」としてでは無い”と云う事に成る。
「秀郷流一門」も“この「考え方」に同調していた“と云う事に成るのだ。
不幸にして「武力化・源氏化」で「近江佐々木氏」は滅亡に貧したが、これらの資料を「青木氏族の一員としての研究論文」に、生き遺った「原因回顧の反省」として記載して遺したのであろう。
故に、銃の説明では無いた為に「不明瞭」なのであると観ている。
さて、そこで「遺された資料」から考察すると、「フリントロック式の改良型」の「青木氏仕様」として上記した様に幾つかの「銃の型式」が考えられるのだ。
その一つを検証して観る。
そもそも、先ず、「江戸期初期・1605年」に「銃の規制」が敷かれたので、「近代銃」は元より「火縄銃の発展」もそもそも進まなかった。
それは「世の中の安定」もあって「銃の発展」は「秀吉と家康」に依って二度止められたのである。
その意味では、「秀吉と家康」は「青木氏仕様」に「近い考え方」があった可能性がある。
然し、”物事を術化する癖のある日本人”に比べて、その考え方のない外国は発展した。
筆者は、「鎖国」そのものがこの「主原因」では無いかと観ているのだ。
「銃の持つ威力」に対して「日本文化」に合わない、将又、「破壊する」として“拒否した事”でもあろう。
そこでその「銃の事」を記されている事を集めて纏めると次の様に成る。
1 外国から取り寄せた「見本」の「特注の発注」であった事
2 その頃・1540年〜1545の間で生産・量産された事
3 「4充填式」の「手動回転式シリンダ」を使っていた事
4 原理は「火縄銃・マッチロック式・マスケット」では無かった事
5 ケーベル式リボルバー銃であった事
6 「ホイールロック式」では無かった事
7 「フリントロック式」に最も似ている事
8 雨にも強く命中率も良く飛距離もあったとしている事。
9 「取り扱い」に「熟練」を要したとしている事
10 「手が出ない程の高価」であった事
以上の事から考察すると、「フリントロック・黄鉄鉱の火打式の改良型・シリンダ型」であった事に成る。
前段で論じた様に、「外国の兵用」に用いた「マックル式銃・パーカッションロック式・キャップロック式銃」の“「原型」”とする考察もあるが、これには多少疑問もあり、これは「フリントロック式」を更に「自動式にした銃・シリンダ」であり、「開発途上の銃」を指している様である。
其処までは、「自動式近代銃」であったかは判らないが、「時系列・完成1810年頃」から先に“日本に入って開発段階”を経たとしても難しいと考えられる。
然し、仮にこれらの形式は入ったとしても、日本では「極めて高額であった事」から発展しなかったし、獲得できる者は居なかつた筈で、獲得したとしても1丁程度と成るだろう。
故に、日本では拡大しなかったのである。
出来たとしても幕府程度で、その幕府自身が「江戸初期の銃規制」で「火縄銃以外」は認めなかったのである。
この「形式銃」は、従って、既に、江戸初期頃の西洋の外国では“「兵用」”に一般的に用いられていた。
従って、江戸期から明治期まで「火縄銃の開発」は進まず「堺の銃生産・江戸初期前」も低下し中止した。
又、最終は、「火縄銃式・マスケット・マッチロック」しか認めなかった事から、「一丁当たりの価格」も当初の「1/20〜1/30程度・20両程度」に急激に下がり、「生産の対比効果」がそもそも無くなったのである。
(注釈 「堺の銃生産」は、「秀吉と家康の厳しい取り締まり」で、「堺」が攻められ、「堺の人」を護る為に「堺の銃生産」は江戸初期全後頃で中止したとある。投資の中止である。)
(注釈 念の為に追記すると、「江戸期での銃規制」で「一頭は1200兵」と規制して、これに対して「火縄銃1丁」を「所持の規制範囲」とし、逆に“騒乱を避ける為に義務付けた”ものであった。
仮にこれに依れば「5000の兵」に対して“「火縄銃」”は「5丁〜6丁」と成る。
これでは「攻撃用」とするよりは当に「防御用」であろう。
室町期では、「一頭は2200兵」とし、「火縄銃1丁」を基準としていたらしいが護られなかった。
室町幕府にもこの規制があった事は、三幕府共に銃の武器としての殺戮性に危惧を抱いていた事を意味する。)
そこで、検証に戻して観る。
「吉田城の戦い」から「一言坂の戦い・遭遇戦」、又は、「三方ヶ原の戦い」までには「約7ケ月から10ケ月の期間」があった。
この間に「立直し策」の「銃の必要性」で、調達出来たとしても「近江・日野からの銃」の「裏ルーツ」の入手であり、且つ、「シンジケートの専売品の銃・普通の火縄銃」をどの様に調達したかにある。
出来たとして、「伊勢屋」とは「犬猿の仲」の「近江商人」と成るだろう。
又、この「近江商人」も「近江・日野」に対しては「大きな発言力」は無かった筈であり、「資材や財源」は「堺」と繋がった「近江と日野」であった。
この事から「近江商人とする説」には多くの「説の矛盾」はここにある。
さて、ところが此処で問題に成る事がある。
「銃の専売品システム」は何故出来たのかである。
それは簡単である。
上記した様に“「政治的な絡み」”があったからで、この時は「室町幕府」は最早、弱体化して「幕府の絡み」は最早無かった筈である。
合ったのは“「商いの絡み」”に特化されていたのである。
「銃生産する事」には「武力勢力」に侵される。
これに「対抗する充分な抑止力」が彼等を護らなければならなかった。
そこで、紀州の「雑賀族・鈴木一族」と「根来族・津田一族」は「同盟と血縁」を進めた。
そして、自らが「銃の軍団」を組んで自らを護つたのである。
要するに、この「自己防衛と銃の傭兵軍団」は、この「二つの一族」は元より「民衆から成る銃兵」を編成して造ったのである。
「紀州山間部」に住んでいた「鍛えられた平家郷士(龍神・戸津川・北山)」も「鈴木氏の縁」からこれに参加したとある。
この「雑賀と根来」で「1000丁の軍団」であったとされ、上記検証の20倍を掛け合わせれば「20000の軍団」に相当する事に成る。
故に、恐らくは記録では「火縄銃の1000」と成っているが、実際はもっと「大きな軍団」を組めていたと考えられる。
(注釈 「鍛えられた平家郷士」が組しているのであるから、「野戦の実戦」にも強かった筈である。
現在でも「戸津川郷士」と云えば「剣道の名手」が多い処であり、後に紀州藩は「伊賀原士」とは別に、「紀州の五平家集団」を「吉宗」は“「原士」”として地域の安定の為に「准家臣」にして扱った事は有名である。)
これに、「雑賀と根来」には「古来からの付き合い」により背後に「伊賀原士」を中心とする「五平家原士・紀伊郷士」等を含む「伊勢青木氏の伊勢シンジケート」を持っていた。
これが「生産地」のみならず「危険な銃の搬送」等に護衛し貢献したのである。
故に、「武田氏」は、要するに「精度の良い銃」のみならず「火縄銃」を簡単に大量に入手する事は出来なかった筈である。
現実に、「家康の発言」として、“「長篠の城壁の銃弾跡」”の「戦後の発言」があったが、これから観て、既に、数は別として、この「1年間の間」に何らかの方法で確保した事に成る。
これは「近江・日野の銃」である事には成るが、「経済的な問題」よりも入手出来ても「1年程度の期間・三方ヶ原」では、前段でも論じた様に、精々、「生産能力」から最大でも「100丁〜150丁程度」では無いだろうか。
最大は先ずあり得ない。
それは「堺」で「資材の原材料の供給と財源」をコントロールされていたからである。
「額田青木氏の国衆」に執っては長篠は「無関係の戦い」ではあるが、「長篠」では「吉田城の手痛い敗戦」の「3年半程度後」とすれば、あり得ない事ではあるが、全て「近江・日野の分」が流れたとしても積算で最大「300丁〜450丁」という処かである。
恐らくは、各大大名も「近江・日野」に集中しているので、「銃の認識度」は急激に高まり「銃値段」は上がったとあるので、「武田の支払いの経済力」から判断してもこの半分程度以下では無いかと考えられる。
注釈として、そこで前段に次いで、これに付いて検証を重ねてしてみると、「種子島の値段は2000両/2丁」であった。
ところが「室町期末期」の「この時期の値段」が、資料に依って異なるが、「約450両から800両の値段」が着いたとされている。
判断材料としては(450〜800両)・450丁=「36万両となり大金」である。
これは、凡そ「9000人の兵の数」に相当するもりと成り、こんな大金を一度に払える大名は居ない。この為に「家臣の武士」では出来ず「専門の傭兵屋」が居て「農兵の傭兵・経験者」を周囲から集めたとされる事となろう。
当時の資料よれば、これが戦乱期であった事から、「5〜10両/1人・銃兵」で「傭兵」にしたとする事から、「45000両の分」と成る。
簡単にこの時期は「銃獲得金」とも含んで「傭兵金」を合わせて「武田氏」は果たして払えるかは甚だ疑問である。
先ずは無理な事である。
そこで更に検証すると、「武田氏」は「甲斐」では「22万石 360億円」、当時価は「前渡金」は「約10万円/1両」であったので、「36万両」であった事に成る。
「銃価+傭兵価」で「40.5万両」と成る。
これは「1年間の米収穫量」の何と113%に相当する。
この時、「信濃域・25万石」も「甲斐の支配下」にあったとして、「769億円・70万両」と成る。
「信濃域」と合わせても60%と成る。
論理的に到底無理である。
そもそも「最大450丁」は、「戦費も要る事」なので到底無理であるし、「近江・日野の1年間の生産量」からしても、全てを獲得したとしても「300丁・14万両・20%」である。
「銃を獲得するルート」や「20%」も含めて「300丁」も絶対に無理である。
多ければ多い程に寡占と成るので「城価格・800両」に近づく。
そうすると、金額から観ても「最低の線」で「100丁・450両=4.5万両」が「精々の能力」と成る。
然し、これたけでは絶対に獲得は出来ないのだ。
後の課題の一つは、「銃取り扱い」に慣れた「傭兵の獲得」である。
先ず、全く「甲斐」には無かったと判断できる。
「額田青木氏の訓練」でさえ、「訓練指揮官」に「伊勢秀郷流青木氏の専門の家臣」を依頼した位である。
この事を配慮すれば、とりあえずは「50丁以内」と成ろうし、少なくとも訓練を要する。
然し、これでも無理なのである。
爆発させる「硝煙」は日本では生産は殆ど無いのだ。
「貿易」に頼るしか無かったのだ。
入手した火縄銃を使い続ける為には、この「硝煙」を入手できる「手立て」が必要で、要するに「豪商との繋がり」が必要と成るのだ。
「入手」のみならずこの高額の「硝煙の財源の確保」も必要と成るのだ。
先ず、無理であった筈で、それよりも「弓矢の方」が余程、現実的であった筈である。
況して、「移動性が無い銃」では「戦術」としては籠城か鶴翼利陣形でしか使えず先ず避けるであろう。
確かに「弓矢」は「殺傷力」は無いが、この室町期にはこれを補完する意味で「毒矢」が使われていて、戦術的には多用されていたのだ。
さて、然し、最早、「額田青木氏」はこの時は既に「三河国衆」から手を引いている。
「長篠の戦い時の松平氏の銃」はどの程度かは判っていない。
「鶴翼の陣形」を「三方ヶ原の戦い・銃が使えない陣形」で組んだ事から上記の論から考えても「銃」は未だ確保できていない筈である。
これは松平氏も、且つ、「魚鱗の陣形の武田氏」もである。
「魚鱗の陣形」の先端に置くとすれば「銃隊」を置くのが通常であるが、実際はそれに類する「赤兜の騎馬隊」であった。
「突撃型突破隊」であるが、「火縄銃」は」移動性」が「銃の特性」のみならず「荷駄隊」を伴う為に極めて低いのだ。
つまり、「赤兜の騎馬隊」で有名を馳せていた武田軍に執っては「魚鱗」で構えられる程の「銃隊」は無かった事に成るのだ。
然し、この「近江・日野」も「生産地」は「地理上の事」もあるが、主に「生産」に対して「護衛」が無かった事から周囲から武力的にな浸食されて危険に晒されて絶えたとする説もあるのだ。
充分に有り得る説で全く無かったとは云えず、細川氏等はこれを勢力内に居れようとして画策していた記録がある位である。
そもそも、前記した様に、この「近江・日野の生産体制」は、単独で生産出来るものでは無く、「堺からの資材供給と財源と搬送の許」にあったのだ。
恐らくは、「掟を破つた事」から「商いの青木氏の影響下・70%持ち株」にあった「堺」から「供給等の圧力」を受けて直ぐに衰退した。
従って、「武田氏等」は少なくとも「三方ヶ原」では「50丁」も無かった筈である。
「武田軍の敗因」は「建て直し」で必要な「充分な銃・財源」を獲得する事は出来なかったと判断できる。
「赤兜の騎馬隊の過信」もあったのであろう。
従って、「3年後の長篠」でも「織田軍の銃撃・雑賀根来傭兵軍」に応戦する事なく「全滅する破目・7割」と成ったのである。
(注釈 「一言坂」では「額田青木氏の300丁銃隊」に対して「坂途中の3000」と「西坂下の3000」の「待ち伏せ兵」に僅かな「原始的火縄銃」が配置されていた事は確かに記録には遺る。
恐らくは、「本隊から廻された6000の兵」であった事からこれが「全ての50丁」で在ったろう。
但し、入手できる国衆が居たのだ。
これは「青木氏の歴史観」に関わるので後段で論じる。)
故に、「近江・日野」の「銃職人」は,“「伊勢」に逃亡したとする説等”が起こり、その後に“雑賀や堺に入った”としている説があるのだ。
一部は薩摩に移動したと説もある。
この「銃職人」を「根来」は、「根来寺」で完全に地域支配されていて「排他的な所・宗教の縛り」があって引き取らなかったのでは無いか。
江戸期に成って「銃規制」により「堺と雑賀」が残り、そこから先ず「雑賀」が脱落し衰退し、遂には「堺」が中止した。
現在は伝統しかない事も同じである。
(注釈 江戸期に成って「近江・日野の銃職人」は、「伊勢と堺」以外にも、「備前、土佐、薩摩、稲富、関」に分散したと記録にある。
この様に、江戸初期には「銃の生産地が増えた事」が大きく「投資」と「値段」と「生産地」と「銃職人」の激減に繋がっていったのである。
恐らくは、然し乍ら依然として「その利権」は「シンジケート」に握られ入手困難であった事から、「大大名」はこれらの「銃職人」をかき集め“密かな軍事力を高めた”と観られる。
その意味で、「伊勢屋」は「独占的な利権保護」を保持する為に、「近江・日野の銃職人」を寧ろ積極的に記録にある様に「伊勢に掻き集めた」と考えられる。
秀吉より「伊勢屋の青木氏」は敵対され続けた所以は此処にもあったと考えられる。
遂に、「堺」にも「圧力」が掛かり「発注と投資」を「中止する結果」と成ったのである。)
「吉田城の事」に説明不足があるので触れて置く。
この時、「酒井氏の城兵」は「銃隊の応戦」に任せ「籠城」であった事に成る。
故に、家康も無事であって、記録に依れば直ぐに城から出て西三河に帰ったとされている。
つまり、上記の通り戦績は「武田軍の戦記」からも総合的に明確であって、明らかに“「銃隊で命を救われた戦績」”であった事が明確であった。
これだけ「戦績」が明確に成っているのに、況やこれが「銃の威力」なのに「吉田城の銃に関する事」や「額田青木氏の事」に付いて「三つの三河戦記」では何も記録されていないのである。
江戸期に消された可能性が高い。
況してや、応援に駆け付け負けて逃げ込んだ「家康」もこの城に居たのである。
そもそも「戦記」としては書かない方がおかしいであろう。
その記録は、単なる“渥美や田原や吉田や西郷等の土豪衆が「吉田城」に入り活躍した”とあるだけで終わっているのである。
他の「二つの記録」や「武田の戦記類」では明確に記されているのに「三河」では記録はない。
(注釈 この時は「吉田城の経緯」から既に「戸田や牧原」は「松平氏の准家臣」に組み込まれていた。
従って、「伊川津七党だけの戦績」である。)
これはまぁ兎も角も、元より前段から論じている“「伊川津七党の事」”の事ではあるが、この中には「額田青木氏」の要するに「渥美」で「四家」を構成していた「伊川津青木氏」が入っていたのだ。
そして、これが「銃隊の主」であり、“「吉田城」で戦った”と云えば、「伊勢の裔系の国衆額田青木氏の一族」であった事ははっきりしている事でもある。
流石に「一言坂の戦い」の様に、「単独の戦いの事」であったので「額田青木氏の国衆の事」を詳しく明記したが、「吉田城の戦い」では一緒に居た「家康の手前」から書かなかった事になるのかである。
これ程に「西三河の旗本」は「戦記」を書く時にも「意地」を張っていた事に成る。
これ等の「戦記」に付いては「三河の記録」では「三記録」であって、他に「二記録」がある。
この後の「二記録」からも凡そは知る事が出来る。
「銃の事・威力等」を先に論じたが、この様な「銃威力」を持ち得ているのに、「三河」では評価が低かった。
「保守的な力」が未だ全体を占めていたと云う事であろう。
これも何時の世も同じで否めない事ではあるが、然し、それにしても「旗本の嫉妬」には悩まされていた「額田青木氏等」の「三河の銃戦績・吉田城・一言坂・三方ケ原」のこれが此処に至るまでの経緯である。
要するに、「事前移動行動」と「準備期間・前期と後期」と「予備戦・吉田城」と「本戦・一言坂・三方ヶ原」と「その後の行動」の「五つの経緯」である。
恐らくは、筆者の推測ではあるが、少なくとも「三河国衆」としては「渥美湾の目的」が達成されているので、「長篠前までの計画」で進めていたのでは無いかと思われる。
ところが、上記した様に、当然に「目的達成」と「戦況悪化」もあったと思われるが、主に「銃認識低さと旗本嫉妬」から、「資料の文面の行」から観ても、“この侭では危険”と察して「三河の額田国衆」から手を引いたと判断しているのだ。
「長篠の戦い」で「織田徳川連合軍」が「武田勢」に勝てたとしても「三河の額田国衆」の「発展」は“これ以上に無いと観ていた“と考えられるのだ。
それは、「織田軍」には「雑賀根来の銃傭兵」で「主軍として固めての戦い」であった。
これは「織田軍」には“「銃認識低さと旗本嫉妬」が無かった事”を意味しているからだ。
逆に云えば、この「織田軍の考え方」が「松平軍を飲み込む」と観ていた可能性がある。
然し、旧態依然として「松平軍」には下記注釈の通り「3年」も経っていながら無かったからだ。
(重要な注釈 「長篠の戦い」とは、そもそも「三つの場所の総称」であるが、「長篠・設楽原・鳶ケ巣山岩」の「三つの戦い」を以て云うが、ある「長い期間の三河の研究記録」によると、この「古戦場」には、「戦い後」のすぐ後に調べた記録として、“「火縄銃の残骸跡」は全く発見されていない”とあるのだ。
「戦場を直ぐ整理した者等の発言」を取り纏めた「寺に遺された郷土史」にはその様に記されている。
これは「雑賀・根来の銃傭兵軍団」であった事から、「銃の発見の無い事」は充分に頷けるし、「戦場の後始末」は、“「勝った方」が誠意を以て行う「仕来り・請負」であった事”からも見つらなかった事もあるし、更には「戦場荒らし」が当時は横行した事もあろう。
然し、「鉛玉」はあの「広い戦場」に於いて発見されたのは、何とたった“「12個」”であった事は何かを物語っている。
「鉛銃弾」を戦後に貴重である為に、又鉛害の為に拾い集めたか、「武田軍の7割死傷者」に持ち込んだとする考え方説もあるが、“直ぐの集めた者の調査行為”であるとして、それを信じるとしたデータとして考えれば、そもそも、そして、その「発見分布」が、この「鉛弾玉」は「織田軍後方陣地」と「前線」と、この前線より「武田軍側」の三カ所にだけ発見されており、「松平軍陣地」には全く発見されていないとする記録もある。
これに付いて「明治後の周囲の自治体」を巻き込んだ「郷土史の調査団体」の「長年の現地調査研究記録」があるのだ。それなりの信用が出来る。
これによると「色々の事」が判って来る。
別に「松平軍陣地・6000・織田含み」には、「酒井忠次の東三河別動隊」に「200の銃」を与えたとし、自らは「300の銃」を持っていたとする説もあるが、別に「東三河の隊」は「臨機応変の奇襲隊・銃隊」として役務が与えられていたとしている。
とすると、これに依ると誇張気味に“銃は500であつたとする説”もある。
この研究はこれに疑問を投げかけいるのだ。
果たして、「信長」が「雑賀根来の1000の傭兵銃」なのに、上記で論じた様に「松平軍500の銃」も持つ事は絶対に無いだろう。
恐らくは、「三方ヶ原の額田青木氏の国衆の銃・300丁・東三河の酒井軍の支配下・吉田城・1572年・史実」にあった事からの、これを其の侭で採用した推論であつたと考えられる。
然し、「青木氏の資料」では「額田青木氏の国衆」は「三方ヶ原・1573年」で「国衆」から手を引いているのだ。
時代考証は可笑しい。
唯、「吉田城の戦い・家康本隊」の後、直ぐに「一言坂の戦い」の「偵察奇襲隊」を命じられて城を出ている。
この時に、「幾らかの銃」を置いて行った事は考えられるが、この「近代銃」を持ったからとして、「火打ち石の黄鉄鉱と鉛玉の弾丸」を特別に供給しなければ使えない。
唯、これには問題があって、「貿易」に依って得られる為に、当時としては未だ「極めて特殊な黄鉄鉱と硝煙」のこれを入手できるかにあるのだ。
「黄鉄鉱の生産能力」が地元にあるかである。当然に無い筈である。
この説では記録は発見されていないが、「松平氏」には難しいと考えられる。
故に、「上記の研究記録」では「戦場の状況」と「「技術的能力の問題」から無理であったと観ているのだ。
後段でも論じるがこの説によれば、「最も古いタイプの現存する火縄銃」は「滋賀近江の厳浄寺で観っかった銃だとしていて、「松平氏の火縄銃保有説」は時系列が合わないとして否定している。
(注釈 尚、記録に依れば、「滋賀県近江」と「滋賀県日野」で「火縄銃」は造られていたと論じているが、この何れにも「厳浄寺」があって、その所縁から「彼等の菩提寺」としてこの寺が遺されている。
琵琶湖の中央部に位置して直ぐ東横にこの「滋賀県近江の厳浄寺」があり、此処から「滋賀県日野の厳浄寺」が南東方向に22k、この「日野厳浄寺」から北東に10k、「日野厳浄寺」から「近江厳浄寺」まで北西に20kのほぼ「二等辺三角形の位置」にある。
ここで、「近江銃、即ち、厳浄寺銃」が造られていたのだ。
「厳浄寺銃の説」はこれでも信用できる。)
(注釈 即ち、鉄には「フェーライト」と「パーライト」と「オーステナイト」と云う「結晶組織の違う鉄」があり、これらは「加熱温度」に依って「炭素の結晶構造」が異なる事に依って起こる。
これをある程度の速さで冷やすと常温でもその結晶構造が得られる。
この「炭素量の多くしたパーライト状態」に「硫黄」を多く加えると「黄鉄鉱」と呼ばれる「極めて脆い金属」が出来て、叩くと簡単に「酸化火花」が出る。
「硫黄」は「鉄」に執っては「不純物」であり、「結晶の間」に食い込んで来る為に弱く、打つと結晶が破壊されて「空気中の酸素」と反応して酸化して「火花」が飛び散るのである。
「黄色の色」をしていて摩耗する。
これを「火打ち石の代わり」にして「硝煙」に火をつけ爆発させる仕組みである。
従って、「専門的で進んだ論理的な銃」と云う事に成る。
これは「火縄銃の仕組み」としては疑問である。)
要するに、「資料不足」の“「美化の2年の誤差」”を無視しての論説と成る。
「青木氏の歴史観」から観ても「長篠の戦記」には問題が多い。
これも「江戸期の書き換え」であろう。
「青木氏の伝統 56−3」−青木氏の歴史観−29−3」に続く。
「青木氏の伝統 62」−「青木氏の歴史観−35」の末尾
この遠江松井氏に付いての系譜次の通りである。
宗能1―義行―貞宗2―信薫3―宗重4―宗恒5―宗親6―宗直7
1 御厨領家の土地を授与 1513年
2 宗能より平川郷堤城主 主要家臣 1528年
3 二俣城城主 1529 病死
4 宗信・弟 二俣城家督 1529 桶狭間戦死 1560年
5 宗恒・弟 二俣城家督 1560年 「駿河青木貞治」は桶狭間に出陣
6 宗親・一族 二俣城城主 徳川氏調略・飯尾氏謀反で今川氏謀殺する。1563年
7 松井氏衰退 武田、徳川氏、今川氏に三分裂後衰退 徳川氏旗本 1590年
そうすると、「駿河青木氏・青木貞治」は「伊勢」にて1540年〜1545年に「訓練・5年間」の後に「大船一艘」を与えられ、「駿河」で「駿河青木氏・伊勢より嫁す」を「再興・1550年頃」し、「糧」を得て「子孫」を拡大、遠江―駿河―伊勢―「渥美・三河」―伊豆―「相模」で「活躍・1550年〜1555年頃」し、「財」を成す。
「今川氏―松井氏」の「国衆」に成る。
以上の経緯を持っている事に成る。
この経緯から「松井氏」との「繋がり」は、先ず判断として「宗信〜宗恒〜宗親」に持ったという事に成る。
「早期の経緯論」としては、「活躍・1550年〜1555年頃」し、「財」を成している段階で、「国衆の段階」を経て「松井氏家臣」に成ったのは「1555年〜1560年」で、この経緯が成立するかである。
「中期の経緯論」としては、「5の宗恒」であるが、病死で直系尊属者無く「一族の者」の「6の宗親」に家督継承されている。
ここで、今川氏と決裂し、徳川氏が関わって来る。
「終期の経緯論」としては、「7の松井氏」の「衰退・分裂」が始まり、徳川氏方が勝利し、徳川氏家臣と成る。)
以上が前段末尾である。
「青木氏の伝統 63」−「青木氏の歴史観−36」
(注釈 「駿河青木氏と額田青木氏の銃隊の関係」
この一族の青木氏の関係の中に存在する疑問を詳細経緯として解いてみる。
「重要な幾つかの疑問」があり、これが判れば「青木氏族」はより理解され「青木氏の歴史観」と成り得るだろう。
そこで何故、「駿河の青木貞治一族」に「額田青木氏」と同じ様に、この「特殊銃」を与えなかったかの「疑問」が残るが、それは「実戦銃」を目的とせず「護身銃・抑止力銃」であったからだ。
「青木貞治隊」は大いに希望し「秀郷流一族一門」からも求められた事は間違いなく考えられるが、上記の「三つの要件」を備えていながら頑固に然し渡さなかったのだ。
勿論、「伊勢」から観れば、「実戦銃」を目的とせず「護身銃・抑止力銃」であった事ではあるが、もう一つは「松平氏の中での位置関係」に従を渡す事に依って起こる“「歪みが生じる事」”に強い懸念の配慮があったと観ている。
これが「額田青木氏の南下国衆」の「伊川津での例」に漏れず「旗本との軋轢」を受ける結果と成っていたのであろう。
それは「銃の威力を持つ事」に依る「権力闘争の歪み」である。
それ故に、「壊滅状態の三方ヶ原」で無理にでも近づく事の出来ない「銃弾幕」を張って「銃力」で以て「青木貞治隊」を救い出したのだし、救い出せれば「秀郷流一族一門」に対する「伊勢の立場」は保全出来る。
「2年後の長篠後」でも「貞治の子の青木長三郎隊」はこの抑止力で生き残れているのだ。
尚、「江戸期初期」に入ってでも「秀郷流青木一族」は、「伊勢」に於いても「徳川氏」と血縁し、中でも「家康の孫娘・勝姫末裔が入った事と伝えられている。
これには、そもそも「勝姫」とは「天崇院(1601年 - 1672年)」の事で、 「 徳川秀忠の娘、松平忠直の妻」の「裔」としているが、「勝殿の呼称」で記されていて特定が不明ではあるが、これには明確な不明の理由があった。
然し、「忠元家の青木氏・伊勢秀郷流青木氏」と「信定家の青木氏・伊勢青木氏」の融合族の「二つの血筋」に三つ目が加わり娶り、「青木氏の四掟の伝統」から外れた「徳川氏の血筋・立ち葵紋」が「四家」に加わったとされているのだ。
改めて「五家目の融合族」の「姓血縁の伊勢四日市殿」と成ったとされている「五家目の家」なのだ。
この様に新たに「徳川氏の姓血筋」を入れて安定化を図ったが、「平安期からの融合の青木氏族」の「四日市殿」と云う一族を「姓血縁の四日市殿」を構築しているのだ。
これが「青木氏族の以後の立場」を保全させたのだ。
「青木氏の安定化」と云うよりは「青木氏の財と格式向上」を徳川側が間違い側がなく狙ったものであろう。
「秀郷流青木氏宗家」を中心として「秀郷流一族一門」が裏で幕府と動いた事であろう。
この「勝姫時期」は「紀州藩初代頼宜との良好な関係」や「紀州藩の殖産への貢献」や「近習番頭と成り出世したと貞治の子の長三郎等」の裏の活躍があったと考えられ、そう云う風に成る条件が揃い過ぎている。
ここで参考として「不明の理由」だが、そもそも「勝の姫の呼称には、「徳川氏の姫の総称の呼称」であって同じ呼称を歴史的に観て6人も使っている史実がありこれは「伝統」であったらしい。
「伊賀越えの事件」で逃亡中に、「徳川氏との血縁族」のこの「伊勢の四日市・辰野青木氏の融合族の四日市殿」にて一時休息したのもこの事の縁から来ていると観られる。
この様に、この「青木貞治の内部の活躍具合」が無ければ、前段で論じた様な「青木氏の氏是」を護り通し、この様な「活躍・繁栄」は無かったと考えられのだ。
これが、即ち、「青木氏一族の鍵」であったとも云える。
「三河国衆に合力する事」も始めとして相当に「渥美湾の制海権の獲得の条件」の時にも「秀郷流駿河青木貞治一門」の「内部での一連の活躍」はあったと観ているのだ。
さうで無ければ、急に“これだけの事”を「好条件」に導き出すには「伊勢との直接交渉」だけでは難しかったと観ているのだ。
「情報獲得の面」でも、「籠城戦」から「野戦に変更した事」を「短時間」の間に「内部の情報」を掴んでいるのだ。
つまり、「浜松城」から「館山街道の湖東町交差点」の「短い間」で「内部事情」を掴んでいるのだ。
そして、「理由・目的」は兎も角も「東の三方ヶ原」に踵を変えたのだ。
この時、「二俣城開城」で「城の兵・1280」は「武田軍と協議」の末に「浜松城」に解放されているのだ。
「東の三方ヶ原に踵を変えた理由」には、「伊勢側の資料」では「様子見」であったとしているが、この「青木貞治」と情報提供時に「何かの交渉・接触」があったのではないか。
この後、「情報提供の後の三方ヶ原」で「南下国衆の銃隊の指揮官の一族」で「駿河青木氏伊勢との血縁もある」の「青木貞治」が「戦死している事・戦記では覚悟としている」を考えると、「松平軍の情報」を詳細に示唆し、始めから「伊川津に戻る事」を示していた事が予想できる。
「青木貞治の隊」はどの位置に配置されていたかは正確には判らないが、「駿河国衆青木氏・四騎200」であるので、記録からは右か左かは不明だが西向きに陣取った事から駆けつける方向からすると左側でありこの状況証拠から「鶴翼部の左付け根域に居た事」は充分に予想できる。
でなければ救い出せなかった筈である。
根拠は無いが「状況証拠」から「東左鶴翼」に居たと推測する。
この隊の少し「東の付け根の位置域」に影の様にして「銃隊が位置した事」から観て、目的は別として「戦況の様子見」ではあった事が先ずは判るし、これを「補完し助ける意味」でも、「軍議情報を得ていた事」からこの隊の少し「東の付け根の位置」にしたのではないかと観ているのだ。
「青木貞治隊」を“一族である”のなら放置する事は先ず100%無いだろう。
いざと云う時には、「武田軍の本隊」に対して「銃射撃の弾幕」で助け出す事を目論んでいたと観る。
現実に「山県軍の別動隊の突然の突撃」でその様に成って仕舞ったのだ。
「左翼面に居た青木貞治隊」を「東の付け根の左位置」から「左斜め」に向かって「銃の連続弾幕」を張っての煙幕の中から救い出した事に成る。
この時、同時に「前方右鶴翼側面のやや斜め方向から「山県軍の別動隊」が突然突撃して来たのだ。
左方向と右方向の左右に弾幕を張る難しい結果と成ったのだ。
現実にはこの方向の流れに動いた。
然し、「山県軍の別動隊が突撃して来たという事」で「銃隊自らも危機」と成り、応戦して撃退したが、この同じ位置関係の混乱の中で「駿河の青木貞治」も「伊勢の青木・・の指揮官」も共に「原因」は別として戦死したのだ。
可成り混乱した可能性がある。
「銃隊」はこの混乱で「次の差配頭・伊勢秀郷流青木氏の者」が「指揮を執っていたという事」に成るが、故にこれが「伊勢の資料」では「一族の二人の戦死」が重複するような「不詳の内容の原因」と成っているのだと観られる。
恐らくは、歌や俳句の様に「文面の表側より内側」を察すると云う「当時の言葉の使い分け慣習」があって、それでそれを会得していない筆者には読み切れ無かったのであろう。
「駿河の青木貞治の一門の隊」は、後に、上記した「堺からの逃亡・伊賀越え事件」で「戦功・勲功」を揚げている事から、一族全員が生き残ったと観られる。
「山県軍の別動隊」が突撃して来て「銃」で応戦したが、この時、「銃隊の一部」が「駿河の青木貞治の一門の隊」を護る為に、「武田軍の本隊」の先端に「銃弾」を浴びせて「事前の計画」としても開戦より相当に早期に「200兵の全部」を救い出したのではと考えられる。
そうでなければ戦況の結果から無理であった筈である。
突撃して開戦と成ったが、救出が全部とすると開戦と同時であった事が云える。
相当に慌てた事になったろうが、「青木貞治隊」は東に逸れて天竜川沿いに「盤田見附の西光寺・菩提寺」に目がけて走ったのだ。
そのタイミングは「山県軍の別動隊の突撃後」の直ぐ後と云う事に成る。
故に、「伊川津の西光寺・現存」より「54k・船1日」の「真東の盤田見附」に「菩提寺・西光寺」が今も遺しているのだし、ただこの時、“見捨てて逃げる”だけでは、それ以後も「一族関係」が保たれている訳はないが保たれていたのだ。
当然に、これは「副将青木貞治の子孫」に於いても云えるものである。
そして、「示唆の通り」に「予定通り」に「戦線離脱」して「伊川津に戻ったと云う事」に成る。
この時の状況には確認しておく必要がある事は、直接、「二俣城の副将・青木貞治」であって「二俣城開城後」に「浜松城に戻っている事」とすると、この「大きな犠牲の敗戦要素」と成った「山県軍の別動隊」の事は、「二俣城」で「青木貞治」は承知していた筈で、“何れの日にか「武田軍の本隊」に合流する”と見抜いていた事にも成る。
そして、直に「詳細な内部情報」を掴める「作戦会議」には「副将」であるので参加していた筈である。
問題は、“何時来るか”の「時間の問題」は判らなかったのであろう。
それは「別動隊の使命」として「補給路の確保」があったからで、「戦う」と云うよりは「二俣城」の「戦場処理・戦後処理・補給体制」に重点を置かれていた筈で、「武田軍の本隊」だけでも戦っても“松平軍は負ける”と「副将青木貞治」は観ていた可能性はある。
但し、この前提は「籠城戦である事」だった。
そこで、「別動隊の使命」として、「三方ヶ原に補給拠点を構築する事」で何時かは早い内に来るだろうと観ていたのだ。
「二俣城開城後」は開城であって落城で無い以上、周囲の勢力は未だ抑えきれていなかったのだ。
これに大分時間が掛かったのだ。
そこで、「松平氏の作戦会議」では、「青木貞治」の「山県軍の別動隊の行動」を詳細に論じた可能性がある。
それを聞いた「家康」は、この「補給拠点を破壊・確保」の為に「籠城作戦」を急遽、変える決心を密かに決めたと云う事であろう。
「一言坂」で野戦し敗戦して「家臣の犠牲」のもとでやっとの体で「浜松城」に逃げ帰ったと云う経験がありながらも、「堀江城の落城」を聞いて「冷静さ」を無くし、これの「経験」を生かさずに再び異常にも「野戦」に変えたとする定説には一類の疑問を感じるのだ。
「密かに決めたと云う事」が周囲から判らず、「冷静さを無くし」に判断されたのであろう。
この「作戦変更」で、「三河戦記」にも記されている様に「二俣城の開城の敗戦の責任」を執る為に死を覚悟したとする定説に導いたのであろう。
そもそも、「青木貞治の個人の心の中」をどうして判ったのかである。
筆者は偶然にも「貞治と銃隊の両指揮官の戦死」に「疑問イ」を持っているのだ
では、その時の「二俣城」の「譜代家臣の主将・中根正照」と「副将の松平康安」はどうしたかであるが、「三河戦記」の中に戦死者としてこの二人は含まれていないのだ。
故に“副将の青木貞治だけが死を覚悟したとする定説”は疑問で、もつとその前に「責任」を執るべき「二人」は居たのだ。
では、先ず、其れには「軍議」にあって、この「軍議の中」で“青木氏貞治に何が起こったのか”の「疑問ロ」である。
「戦記」でこれだけの事を定説として記されている以上は、何も無かったと云う事には成らない筈で、「戦記に残す右筆衆」が「戦場の全体を見下ろせる安全な所」から観ていた筈だし、且つ、戦後、生き残りに聴取して正確な資料を纏めていた筈である。
これを「当時の仕来り」では「家康」に「論功考証の為」にこの「右筆衆」は報告書を提出している事に成っている。
つまり、「疑問イとロ」の様にこの「右筆衆の原石」はこの様には書いていなかった筈である。
筆者は詳細経緯として、確かに形の上では「責任を採った事」には成っていて間違は無い様に観えているが、その「責任の取った理由」、将又、「採り方」に「疑問イとロの本当の問題」があったと観ているのだ。
上記した様に、「青木貞治」は「額田青木氏」に「内部の情報提供時」に「一族の者・200の救出」を城外に放り出された「南下国衆の銃隊」に依頼したが、この「救出の際」に弾幕を張って救い出したが、そうだとしたら「敵の目」を騎馬上から「混乱の中」で自分に“敵の目を引き付けた”と筆者は先ずは観ている事に成るのだが、この考えだとすると、「混乱の状況の時系列」が変だ。
そもそも、他に「青木貞治隊」にも犠牲は出ていた筈だし、「銃撃」をされている「騎馬隊」には相当の犠牲が「銃弾幕」で出ていた筈だ。
果たして“敵の目を引き付けられた”かの疑問が出る。
この場合では、又、騎馬隊と山県軍とが交差する事にも成る。
つまり極めて味方同士で混乱してしまうし、「本体の騎馬隊」は動けなかった筈だ。
そんな戦略は絶対に信玄は執らないであろう。
「山県軍の別動隊の突然の突撃」を観て「騎馬隊」は進軍を待った筈だし、現実には「弾幕」が救出の為に「武田軍の先頭」と「突撃の山県軍」に目がけて前が見えない程に連射されているのだ。
“観ているが精一杯の事”であった筈である。
「青木貞治は有名な将である事」は、「武田軍の本隊」は「二俣城」で承知していて、突然に敵前に向かい、この間に「武田軍の本隊」が近づけない様にした上で「南下国衆の銃隊の弾幕の誘導」で救出したのであろう。
それ以外に他の隊員の無傷で救い出す事は出来ないだろう。
何故ならば、「青木貞治」もこの弾幕の中に包み込めば救出は隊員と同然に容易であった筈である。
然し、「向後の憂い」を無くし、この事で「弾幕の中に入る事」はしなかったのかだ。
つまり、何を云わんとしているかと云うと、「松平軍の軍議」に於いて相当に「二俣城の無戦開城の責・水攻めの責任」を問われる前にその最初に責任を執るべき人間がいたと云う事だ。
然し乍ら、これを「三河旗本衆」に問われたのではないかと云う事だ。
「家臣の主将・中根」と「軍目付・軍監の松平康安」の二人も居たのである。
確かに「全員戦死の覚悟」で「二俣城」でも「時間稼ぎ」を求められていたが、「譜代家臣の主将の中根」の責を問うのでは無く、「旗本」ではない「副将の青木貞治」に非難が集中したのではないかと予想しているのだ。
要するに「軍議」での「庇い合い」であり、「副将の貞治」に押し付けたのだ。
「松平康安・18歳初陣」は、「大草松平氏の出自」で「曾祖父」は「家康」に反抗したものの裔であり、「軍目付・軍監」して「二俣城」に派遣されていたのであった。
この「二俣城」は、そもそも元は「今川氏の家臣の松井氏の居城」で、縁あって「青木貞治」は「遠州国衆・経緯下記」としてこの臣下にあった。
恐らくは、「旗本との間」でこの「関係」に「糸を引いていた事」と考えられる。
然し、この事に就いて「右筆衆等」が、「何かの形・郷土史や手紙や寺や一門記録」で残しているかと観て調べたが遺されている資料は無い。
「無いと云う事」は、これは「家康の用人」として、将又「青木貞治の子孫」が重用されている立場として、“江戸期に成って「幕府の権威」を下げる様な「史実」を世に遺すのは好ましくない”として消し去った可能性が高いのだ。
それは、実はこの事に及ばず「秀郷流青木氏の資料」が研究にも具する程のものも遺されていない「理由の一つ」としても此処にあるのだ。
一族全員がそっくりと家臣と成った「秀郷流青木氏」には遺せなかったのではないか。
その「残念な理由」とは、「秀吉天下の対応」で「徳川家康」は「武蔵転封・1590年」と成ったが、この際、武蔵の「秀郷流一族一門」を「味方」に着ける為に「一族一門の者の一切を家臣・官僚族・旗本家人衆」に抱え込んで「味方」に着け、自らも「藤原の朝臣」とし「氏名」を名乗る程に慎重に扱ったのだ。
其れも、「平安時代の習い」に従い、「徳川氏の御家人・天皇家の家人扱い」として「特別な格式」を与えて、「旗本」とは別に幕府で「事務官僚・本領安堵」の「家人衆旗本」として重用したのだ。
当然に「格式の無い旗本・近習衆」はこれに猛烈な反発をした。
それ故に、「幕府の権威を下げる資料」などの保存は悉く抹祥されたのだ。
これが所以の一つなのである。
ここに至る「詳細経緯の始点」も“「駿河青木氏の貞治」”に始まるのだ。
そこで、この行の“「一族一門の者の一切を家臣・官僚族」に抱え込んで「味方」に着けた”に付いての浚っておかなければならない「疑問」があるのだ。
それは、“「徳川氏」が何も無しで「この状況」を作り込んだか”である。
この「氏家制度」の中ではこれはあり得ない事で、個々に「家臣に成る等の事」は一切出来ず、もし、それをすれば一族一門から排他され滅ぼされる始末の世の中で、「互いの結束」に依って身を護っていたのだ。
当然に、今論じている「額田青木氏等」と「伊勢」を始めとして「全青木氏族」も同然であった。
故に、「武蔵入間の総家」との「繋」が無ければ成り立たない「時代事」であった。
筆者は、この「徳川氏の繋ぎの役目」を果たす事が出来た唯一人の人物は、「青木貞治の子の長三郎・御側衆・上級側衆・最終は上級番方に成る・3500石・1400貫・国衆から旗本に」であったと観ているのだ。
何せ役柄と云う点からもピッタリである。
「本能寺の変頃の伊賀越え」から「江戸期初期」の「長三郎の役目柄と子孫」もその様な立場にいて、「最終」は「名誉格式を持つ上級番方頭・家人旗本」に成っているのだ。
「本論の詳細経緯」の特筆するはここにあり先ず間違いは無い。
後勘から観ると、これが「伊勢青木氏等の青木氏族」に執っても「生き方」を「良い方向」に向けた「所以の起点」と成ったのである。
唯、その「起点」を作った「初代・青木貞治」には「波乱万丈の人生」であったと云える。
何事もこの世は初代は、波風の人生を送るは世の常庸であった事は理解できる。
この「波風の人生」を物語る「徳川氏の出現」は、「長篠後」に奪還したこの「二俣城」を何と「最大旗本の大久保忠世」に任しているのだ。
これを観てもこの「人物の旗本」には、「駿河青木氏」のみならず「伊川津の額田青木氏」に於いても「同じ仕打ち」を受け続けていたのだ。
それだけに「松平氏・1563年改姓の徳川家康・上野国土豪得川の先祖」から「徳川」と解明したが、これを「長篠後」に大いに使う結果と成った。
「改姓する事」に依って「今までの三方ヶ原での印象」を「これからの長篠での印象」に変えようとしたのではないか。
この「松平氏・徳川氏」に執っては、「二俣城の敗戦」は厳しく「戦略上の重要拠点」であったのだし、その「不満の矛先」を「軍議」では、「主将中根」や「軍監の松平康安」に向けられずに戦記の表現の通りに「青木貞治に向けた」と考えられるのだ。
然し、「所以の起点」を造り出した以上、つまり、その後の「江戸期」では、この「御家人と旗本と御側用人と上級番方・家人衆旗本」と合わせて「格式のある家筋の立場・秀郷流青木氏」に成った以上は、「旗本」は「怨嗟と嫉妬」から来る「不満の矛先」を簡単に向け難く成ったと考えられる。
然し、前段でも何度も論じたがからは「吉宗」を裏で将軍に「仕立て、且つ、「親代わりの役目」として、共に「江戸向行」し、「享保の経済改革」を市中で実行した「伊勢青木氏・伊勢屋」でさえ、矢張り、「大久保・本多の旗本」等の旗本から「不満の矛先」は益々向けられたのだ。
「伊勢」に限らず「信濃青木氏」にも同然に酷い仕打ちを受ける結果と成った。
流石に「信濃も受ける羽目」と成り、「晩年の吉宗」もこの「不満の矛先」に加わりこれを止める事さえも出来ず、江戸では遂には「危険が生じる事態」と成り、急いで「伊勢に戻る羽目」と成ったのだ。
其れだけではこの「不満の矛先」は依然として治まらず、「奈良期の天智天皇」より「伊勢の永代不入不倫の権」と「伊勢の事お構い無しの家康のお定め書」をも無視され、結局は「青木氏族・伊勢屋と伊勢シンジケート」と、関西を仕切る幕府の「伊勢の山田奉行所・吉宗も同調・史実記録」との間でも「戦い寸前・ゲリラ戦・関東秀郷流青木氏が動き見せる」までに及んだのだ。
「三河旗本の嫉妬怨嗟」は、此処までも続く傾向は斯くの如しであって、これが「軍議」の「青木貞治」にも向け背れていた事は後勘から観ても先ず間違いは無い。
結局は、追記するが上記の「伊勢の件」は「紀州藩・伊勢藤氏の青木氏一族が全家臣に成る」が強力に介入し、間に入り「治まり」を着けたが、今度は、その「紀州藩」に「謀反の嫌疑」が架けられたが耐え偲んだのだ。
「格の如し」で「青木貞治」だけに及ばず「青木氏族全体」に「不満の矛先」は向けられそれが先鋭化して行ったのだ。
世の中で殆ど消えて行く中で今未だ比較にならない程の「格式力と財力と抑止力」を持ち続けそれを以て正統に活き、それを背景に「政治」も裏で動かす「唯一の氏族」には「姓族の姓社会」では我慢が成らなかったのだと考えられる。
この「嫉妬怨嗟」は、「人間社会」では人間である限りに於いて変わらないし否定はしないし、無くなる事は先ず無いのだ。
然し、「青木氏族自身」もそれを特段に取り立てたものとして考えてはいなかったのだ。
「青木氏の氏是」や「戒めの家訓10訓」を観れば、それが良く判り「普通の人間が生きる範囲」であったのだ。
故に、「青木氏族以上」には「その過去と現在」に付いて周囲が必要以上に「意識を高めた行為」であったのだ。
取り分け、「一向宗を概念とするこの三河族」に執ってはその「教義」から影響してやや「三河者の意識を高めたと云う事」であろう。
さて、話を戻してそこで、更に「詳細経緯」を論じる。
この「苦しい環境の中」で、「青木貞治」は次の手を打ったという事だ。
この時に上記した様に「堀江」に向かい始めた「武田軍の本隊」を「南下国衆の銃隊」は追尾していたのだが、そこで急いで「南下国衆の銃隊」に「情報提供した」と考えられる。
然し、「詳細経緯」として「青木貞治」は、何故、“追尾していた事を知っていたか”に掛かる。
それは先ずは“「何かの連絡網・情報手段」”が「青木貞治との間」に構築されていた事に成る。
それが、「伊勢」から派遣されていた「南下国衆の銃隊」に影に成りながら帯同していた「伊賀青木氏の忍者衆・香具師・隠密商人」にあったと観ているのだ。その形跡が資料の隠れた意から伺える。
「青木貞治隊」と「連絡」を取れる様に「伊賀青木氏の忍者衆・香具師」が隊の中に入っていたのだと云う事だろう。
筆者は、寧ろ、二俣城開城後に「青木貞治隊200」に「兵」として「伊賀青木氏の忍者衆・香具師の援軍」を送っていた事が考えられる。
其れは「浜松城に呼び出された時」に「記録」では、訓練を受けたのは「額田青木氏の南下国衆の銃隊300」であったが、突然にその後の「記録」では「南下国衆銃隊350」と替わっていて行から「荷駄隊50」が加わっていて、これは前段でも「伊賀青木氏」と「伊勢秀郷一門」の「合流隊」と説いた。
然し、当然に「青木貞治隊」にも「武蔵の秀郷流一門からの援軍」と「伊勢からの援軍・伊賀青木氏の香具師」が加わったのではないかと「必然的な流れ」から「当然の事」として考えられるのだ。
その時期であるが、「伊勢からの援軍」は、時系列から可能な時期は、矢張り「吉田城」から“「浜松城に呼び出された時」”であろう。
従って、時系列から「二俣城が開城した後の事」に成る。
又、「武蔵の秀郷流一門からの援軍」の場合は、時系列から当初から「副将」として入った「二俣城の時期」と成る。
さて、そもそもその前に論じる事がある。
それは、“何故副将と成り得たか”と云う事である。
「副将」とする為には、当時の慣習から「青木貞治の兵数」を増やし「武蔵の秀郷流一門からの援軍」とした可能性がある。
何故ならば、因みにこの検証として、「駿河青木氏」の「今川氏の時代の国衆の知行」は次の様であったらしい。
「江戸期」では、上記した様に「3500石で家臣数200で1400貫」と記されている。
ところが、「室町期」の国衆時の当時の「圷の野」であった「盤田域の庄面積」は、次の様であった。
約1800反程度弱≒1800石程度≒6000平方坪程度以下と成る。
そうすると当時は、1貫≒2.5石 7貫≒1兵 1反≒1石≒300坪≒1人の原則があった。
「1家」を5人として360家、この内の「農民の家」は8割として288、残りが「武士の172家」であり、「戦いに参加出来る者」が「最低家1人」とすると、「ave(172)≒約170人程度」と成る。
この「最低の基準」の「ave(172)≒約170人程度」に達しない場合は、農民の次男三男が「農兵・荷駄兵」として事前に金を渡され駆り出されるのが当時の戦時下の仕組みであった。
そうすると「戦線に義務付けられた基準」は先ず「720貫 兵102人:1800石」と成る。
つまり、兵としての「兵数」が「約68人程度・援軍」が増えていた事に成る。
然し、これでは「副将」とは成り得ないのだ。
つまり、この差が「援軍・68+X」であった事に成るのだ。
当時は、「1将」に対して「4騎」が着き、「1騎」が「50兵」と云う基準があったので、「200の兵」でやっと「将」と扱われ、「軍議に参加できる基準」であったし、故に「副将扱い」に成ったのだ。
これで「秀郷流青木氏・第二の宗家」が中心と成って「駿河青木貞治」には「兵数」が足りないので何らかの手を打った事に成る。
そこで、「援軍を送る事」で「松平氏の中」で「副将扱い」に成る様に「秀郷流青木氏一門」は計らった事に成る。
そうするとこの「Xは28」と成り、「合計98人以上」を「援軍」として送る必要が出て来たのだ。
敢えて、少なくとも「約100兵程度を援軍」として送り副将にして「発言力を着けさせた事」が判る。
これを当に「数字」が援軍と云う策を執ったと事を物語っているのだ。
故に、本来なら「軍議」に充分に参加できる「額田青木氏の南下国衆の銃隊300+荷駄50」が「軍議の命令」を拒否し、何と「城外」に放り出された。
それは国衆の契約条件に反しても「銃」を陣形の前に出して戦う戦法を拒否したのだ。
以上は、「駿河青木貞治」は「軍議の情報」を彼等に流し、これらの「援軍」と共に「救出」を依頼したのである。
「額田青木氏・指揮官伊勢秀郷流青木氏」としては、「情報の救出依頼」があったとしても必然的にも「両者の援軍」を救出する事は、「疎遠・血縁」で無かった以上は「一族として義務」も負っていた事に成り得る。
それには絶対的に「戦術的な内部情報」が必要であって無暗には手は出せなかったのだ。
「救出が義務」であるとしても下手をすると「銃隊に大変な犠牲を負う事」にも成り得る。
これ等の「内部情報」を獲得するには元を返せばそれには少なくとも「決定権のある副将」である必要があったのだ。
「詳細経緯」としては、この「義務」を果たす為にもこの「銃隊の指揮官」も「青木貞治」と共に、これでも“相当に際どい戦いと成った事”が判る。
故に両方の指揮官が「戦死したと云う事」でもあろう。
“「堀江」に「本陣」を置いて「二極化拠点」として構築している可能性もある”と、戦略的に考えて「追尾行動」をしていた「南下国衆の銃隊」に対して、故に、「青木貞治」は、「軍議の内容」から“これは危険”と観て、得た「軍議の内部情報」を「銃隊の指揮官」に対して提供出来たのだ。
そもそも、「負けると判っていた戦い」に「一族の者を援軍として送る事」は先ず無いだろうし、この「援軍」は「戦うと云う勢力」よりも「将にする事」に依って「内部情報の獲得の手段」を主目的として有利に導こうとしていたと云えるのだ。
其れならば、「籠城戦」から「野戦」と成り前提は異って仕舞ったので、参戦し野戦と成った以上は「青木氏族」には後は「救出してもらう事」しかなかったのだ。
それには、”無事に救い出す”には「額田青木氏の南下国衆の銃隊の銃力に頼る」と云う事に成り得り得たのだ。
それが「銃力・弾幕」で「武田軍の本隊の進軍」を一時止めさせてその隙を突いて「救い出す作戦」に切り替えたのだ。そしてその「準備」を始めたのだ。
それには逃げ込む道すじ・場所・タイミング・合図や銃隊の引き上げ時期等詳細な打ち合わせが両者に執って必要であって打ち合わせたのだ。
其処に、「山県軍の別動隊」に対しては良しとしても、結局は1h〜2h経てば「武田軍の本隊」が別動隊を救出に来る事は必然で、この「愚策の鶴翼の陣形」と成れば「銃隊の指揮官」に執ってはこんな危険な事は先ず無かっただろう。
「総崩れに成る事」は戦前でも充分に予想できただろうから救い出すには「一瞬の隙」を作るしか無かったであろう。
「伊勢の勢力」も「額田青木氏の南下国衆の銃隊」も「援軍の秀郷流一族一門」も「青木貞治隊」も4者共に慌てたであろう。
そもそも、この事は「開戦」と同時に問答無用に「救出の必要性が迫っていた事」に成り、故に「南下国衆の銃隊」も救出後に即座に「戦場離脱に迫られていた事」に成るのだ。
何故ならば、「補給拠点での野戦・三方ヶ原」と成れば「武田軍の本隊」は「山県軍の別動隊」を救う為に「堀江城」を出て「三方ヶ原」に向かうと観ていたのだ。
そうなれば、「山県軍の別動隊」との「西東の挟み撃ち」に成る可能性が出て来て、「300の銃隊」と云えども、再び「一言坂の遭遇戦」を再び呼び起こす結果と成り、“「危険」”に陥っていたのであった。
この時、ここで「安全策」の一つとして「西の伊川津に戻る策」もあったが、そもそも「一族を放置する事」が出来ず、一族の「駿河国衆の青木貞治の隊」を「何とか守り救出する為」にも、且つ、充分な「様子見の為・場所取り」にも急いで「三方ヶ原」に向かったのだ。
そもそも、「急いだ事」は、「戦い」の「場所取り」では無く最も「物見」によって“救出に適した位置取り”と「離脱場所の位置取りの点」にあったと観られる。
然し、前段でも論じたが「事態」は急変していたのだ。
予想通り、「武田軍の本隊」でも充分に戦えるとして「山県軍の別動隊」が「補給拠点築造の使命」で、“北の山際に待機するかも知れない”と観られたし観ていたが、何とこの「補給拠点築造隊」で「挟み撃ちの作戦」に突如出たのだ。
それは、「青木貞治」が位置している前線と松平軍に対してであって、結果として「左鶴翼の付け根部分」に位置取りしていた「南下国衆の銃隊」にも巻き込まれる可能性が充分に出て来たのである。
そこで因みにそもそも、主に「戦い方」には中国から伝わった「八陣形」と呼ばれる陣形が平安期からあって、「魚鱗、鶴翼、雁行、彎月(偃月)、鋒矢、衡軛、長蛇、方円 他には「決死隊の長滝等」があった。
「武田軍」は「赤兜の騎馬隊・本隊用」を持っていたので、これをそれぞれの陣形に合わして配置して特徴を出して陣形を強め「無敵の騎馬隊」と呼ばれていたのだ。
「赤兜の騎馬隊」を持たない「山県軍の別動隊」は、それが逆に戦力の弱い「補給基地築造隊も含んでいた事」から、これが上手く行けば戦力の弱い「補給基地築造隊」を戦わす事なく護れるので、これを「背後」に廻して一列に並んだ「長蛇陣形」の「鶴翼突破型の全軍側面突撃」の形に似ていたのだ。
ところが作戦通りに「長蛇陣形」が良かったが前段でも論じた様に思い掛けない事がここで起こり違ったのだ。
突撃と同時に突然に何と強力な銃弾がとぎれる事無く、其れも先頭から後尾までに一斉に遠方から命中率良く一斉同時に浴びせられたのだ。
寧ろ、逆に「長蛇の陣形」が痣を成した形と成って仕舞ったのだ。
「銃隊の存在」を強く意識していれば、「鋒矢の陣形」で「補給基地築造隊」を包み込む様にして「敵中突破の突撃」を仕掛ければ犠牲は少なかった筈であった。
つまり、これでも「銃隊の存在を読み違えた事・下記」が判るのだ。
筆者は、「救出用の隠れての位置取り」であった「南下国衆の銃隊」が「見え難かった説」を採っている。
つまり、北の山際から観て左斜め鶴翼の付け根部域であった事で「松平軍の影」に成って正確に存在を見分けられ無かったのであろう。
「三方ヶ原の補給拠点」を、急遽、「野戦」に出て「松平軍に確保された事」で、この情報を得た「堀江」に居た「武田軍の本隊」が、「三方ヶ原の奪還」を目指して東に向かいこの「山県軍の別動隊」も遅れて到着した。
この事で「三方ヶ原の補給基地」を築造後、ここの「守備隊」として「山県軍の別動隊の使命」として着く予定であった事はこれで「当然の事」としてこれで判る。
戦略上では、「先に守備隊として確保したものを奪う戦い・奪還作戦」は難しいのは何時の世も先に奪取するのが「戦略の常道の知識」である。
故に、家康は、突然に「籠城」から秘密裏に「野戦」に変更し先に確保しようとしたのだ。
それには「家康の考え」は取り敢えずは成功した。
「別動隊の使命」に基づき「補給拠点構築隊」も引き連れていた「山県軍の別動隊」は、「本隊」に合流せずに、「援護守備兵であった事で遅れた事」もあって、「鶴翼の右側面の山際」に開戦ぎりぎりで陣取った。
「拠点の三方ヶ原」を「先に奪取された事」で「使命の達成」が出来なく成って仕舞ったのだ。
そこで本来であれば「武田軍の本隊と松平軍との戦い」に成ると、遅れた事の道中で「山県軍の別動隊・目的が違う」は「北の山際での駐留」まで考えていたのではないか。
ところが、ここに到着して観れば、「二つの事の異変」に気づいたのだ。
一つは、「弱小の松平軍」が何と「予想の戦術・魚鱗の陣形」では無く「鶴翼の陣形」を採っていた事である。
二つは、「西向きに陣形」を向けていた事である。
本来であるなら「浜松城を背景に陣形を北向きに採る」のが常道である。
西から来る「武田軍の本隊」と東から来る「山県軍の別動隊」が合流して北を背景に陣形を組むのが常道である。
この「南北の陣形の向き」であれば何れも両軍に執って「有利な位置取り」である。
ここで遅れて来た「山県軍の別動隊」に執ってだけに「不利な事」が起こったのだ。
それは、「西向きの鶴翼であった事」に依り“武田軍の本隊と合流出来ない”と云う事が起こったのであった。
「遅れた事」に依って「北側の山際」に“単独軍として離された形と成った事”であった。
「松平軍・家康の命令」はそれを狙っていた事にも成る。
そこで「予想していた事と違った事」が起こって、「戦況」を其の侭に観ているか、さもなくば「武田軍の本隊」より前に行動するかに迫られたのだ。
そこから「別動隊」であった以上は「状況」に応じて「独自単独」に移る事が出来る。
今度は何と「松平軍」に執っては予想外の“「援護守備兵」で「鶴翼の右側面・弱点」に本隊よりも先に突撃して行った”のだ。
「山県軍の別動隊」に執っては、その「行動の判断」は「同時」や「後」は「武田軍の本隊の行動」を遮る事に成り、且つ、「敵が鶴翼陣形」である以上は著しい混乱を招く事に成る。
これは「得策」では無いとして、先に、最早、“「使命達成」は当面は不可能”と判断した。
そして、「二俣城」からの「移動の行列」が、丁度、「長蛇の陣形」である事から「鶴翼側面」を「後尾の補給基地築造兵」を護る為にも「一点集中の突撃突破」で攻撃に入ったのだ。
これを観た「武田軍の本隊」もこれに引き続き「魚鱗の陣形」で「総崩れ」と成っている「鶴翼の松平軍」に向かって前進し完全掃討し勝利したのだ。
唯、この時、復もや「山県軍の別動隊と武田軍の本隊」とに「思い掛けない事」が「南側」で起こったのだ。
それは、「南下国衆の銃隊の存在」は「一言坂」と「追尾」で承知していたが、まさかの「額田青木氏の南下国衆の銃隊」の「戦いへの参戦」であったのだ。
「武田軍の本隊」からはそう見えていた筈である。
恐らくは、「牽制程度の事」はあるとは判っていて、“本格参戦は無いであろう”と見込んでいたのだ。
それを示す「三つの証」としてある。
そもそもその「破壊的威力の持ち主の銃隊」でありながらも、“積極攻撃をして来ない事・証イであった。
「一言坂からの追尾」”までと、「堀江城への援軍攻撃」が無かった事・証ロと、「三方ヶ原」に到着して観れば“攻撃の仕難い「鶴翼の位置取り」”とにあった事・証ハなのだ。
「武田軍の本隊」は、この「三つの証」を観て少なくとも“攻撃的で積極的ではない”とその様に考えていた事に成る。
この事から考えても、「銃隊」としては「鶴翼の付け根部に位置していた事」が判っているので、射撃すれば味方も撃つ事に成る「相当難しい位置取り」にあった事である。
これが「救出目的」であるとは観ていなかった事・証ニが考えられる。
然し、「青木貞治隊の救出」と「山県軍の別動隊の思いもかけない突撃」で、止む無く「銃の攻撃」を仕掛けたのだ。
何方も、“思い掛けない予想外の一瞬の出来事が起こった”のだ。
そして、「武田軍の本隊」に向かって「弾幕」を張って先ず「進軍」を止めて、何か弾煙の中から「救出作戦を起こしている光景」が「信玄の目」に入ったし、先に突撃をした「山県軍の別動隊」の「山県の目」にも累々と「戦死者の山の光景」が目に入ったのだ。
どうしようも無い「開戦の一瞬の出来事」であったであろう。
つまり、それは「予想外の事」が「勝利の武田軍」にも、「敗戦の松平軍」の「両軍の目」に入ったのだ。
「弾幕の煙」で一時戦場が観えない程に成ったと予想できる。
開戦は午後の四時頃であったので「谷風・海風」が吹いていて、南から北に向かって谷筋に「三方ヶ原の戦場」に向かって吹いていた。
なので、「弾煙」が消えては、又弾煙が出来ると云う光景が起こっていて、その「武田軍の本隊の混乱中」の間に、この「救出劇」が起こって兎に角にも先ずは「東」に逃がしたと「詳細経緯」としては考えられるのだ。
「山県軍の別動隊」に執っては射撃音以外に何処から弾が飛んでくるかは正確には判らなかった筈だし、武士道の通じない生死の「経験のない恐怖」が先行して「逃げ隠れの出来ない処置無しの状態」であったと考えられる。
故に、比較的に「救出」は容易に犠牲も無く成功したし、「北・戦場」に向かって連射しながら「荷駄隊」と共に、無事に西に後退する「戦線離脱」も容易であったと観られるのだ。
「近づく者」は恐らくは移動しながらの「空砲の煙幕」でも充分であったろうし、「一言坂の経験」の様に100%居なかったと考えられるが、執拗に近づけば実弾連射して撃滅戦を繰り返しながら「戦線離脱」したと考えられる。
この「戦線離脱した南下国衆の銃隊」を「仮・現実には無理」に追撃したとしても「館山街道の例の交差点付近」までであろうし、此処からは「武田軍の本隊」としても戦略上踏み込めなかったと考えられる。
史実はここの状況は何れの戦記にも記されていない事から“追撃は無かった”のではあるが、ところがその前の「やるべき事」が「武田軍の本隊」にあった。
それは「戦場の掃討作戦」と「山県軍の別動隊の支援」にあった筈で、「補給基地の三方ヶ原築造を使命の別動隊である事」を前提にしながらも、「軍事行動」を起こして突撃した事、且つ、「別動隊として浜松城を陥落させる使命もあった事」も考えると、これを支援しなくてはならない「本隊としての役目」が「戦いの流れ」としてあった筈である。
現実に、史実の詳細経緯は、「脚色された三河側の多説」が多いが、「掃討作戦と別動隊支援している事」には間違いは無い。
「救出後の武田軍の掃討作戦」も、「青木貞治一族」が隠れていたこの「西光寺」では、「武田軍の本隊の2度の印象」の中には、“銃隊の一部が未だ居るのでは”と連想し近づく事は出来なかったと考えられるし、命令なしに掃討が出来ない寺であった事は間違いは無い。
何故ならば、そもそも「寝る子の東の秀郷流一門361氏」と、「第二の宗家の位置づけ」の「秀郷流青木氏116」を起こして仕舞う危険性があったのだ。
「青木貞治隊」が「逃げ込んだ盤田見附の西光寺・平城館の大寺」が不思議に戦記上では掃討された事は記されていないのはこの事に依るだろう。
そもそも逃げ込んでいるか否かは別として、「武田軍の本隊」が進軍中に「一言坂の此処」で一時停留しているので、破壊は無いし、確実に「掃討カ所としての確認をすべき拠点」である事は知っていたし、「青木貞治隊」に限らず位置的に観て「松平軍の残兵」が少なくとも一時的にもここに潜んでいる拠点である拠点には間違いは無い。
この様な「一族の菩提寺の西光寺」から「青木貞治隊」が再び“城に入った”と云う記録は無い処を考えると、「武田軍の本隊」が「浜松城」を攻めた場合とか「掃討作戦」で「西光寺の方」が「平城館」の様にして「寺の周囲」を固めれば安全であると考えたのであろう。
故に、「生き残れた一族の勢力」は、江戸期には「御側用人衆・上級番方」として出世して禄高を史実の通り1800石から3500石に倍増させて「駿河青木氏の子孫」は栄えたと成るのだ。)
(注釈 「額田青木氏と駿河青木氏の生き遺りに付いての論」
さて、上記の詳細経緯に至る内容を先に論じて置く。
「三方ヶ原の戦い」に勝利した後、ここに当初の目的通りに「補給基地」を築造せずに堀江城と二俣城などの出城に「守備隊」を残し「甲斐」に全軍を引き上げている。
2年後の「長篠の戦い」の際には、この二つの出城の「守備隊等」は松平軍に対して「善戦をした事」が何れの戦記にも記されている。
つまり、そこで「周囲」がまだ「武田軍の守備隊」に囲まれているこの2年間の「西光寺の駿河青木氏の動向」が気に成る。
この事に関する記録等を探ったが、唯一つ何かを物語る行が「伊勢」にあった。
それは「伊勢水軍」であった。
「出城の山国の武田軍・少数」には「水軍」を持っていないので、伊勢水軍と駿河水軍は「渥美湾に船を廻す事」がある程度可能に成っていた。
「駿河水軍」と連携して「伊豆」まで廻る「商い等の運搬に盛んに従事している行・商記録共に一致」である。
つまり、これは何を意味しているかである。
「三方ヶ原」から伊川津に戻り「陸運業」に逸早く転身し、「縦の陸路1と2」を構築して「信濃」に繋いだし、「三方ヶ原」より「武田軍」が予想外に「甲斐に戻った事」と、「織田氏の西三河への伸長浸食」で「武田軍の脅威」は低下して「渥美湾の制海権」は何とか獲得出来ていたのだ。
この時、この為に「松平軍」が「力・財源を持つ事」に警戒した「織田軍」は、「伊勢」で水軍を造ろうと懸命であって、遂に「熊野水軍の内の九鬼水軍」を味方に引き入れた。
そして、「伊勢青木氏」が「7割株」を持つ「伊勢水軍の伊勢衆・50衆」に対しも「楔・調略」を打ち込んできたのだ。
「伊勢衆の掟」を破り「4組」が「織田軍の調略」に落ちたがこれを「掟と財源」で食い止めた。
然し、結局は1組だけが調略に応じたのだ。
そもそも、「伊勢衆」は「伊勢青木氏の女系の重複血縁の古来からの氏人」であった。
最も尾張に近く縁の薄かった「東の知多一族」が落ちたのだ。
然しながらも、当然にこれに伴って結果として「陸運業」と「海運業」は動ける様に成った。
そうなると、「松平氏の敗戦」に依って「青木貞治の彼等の糧」は失う事は必然である。
そこで「駿河水軍の裔の駿河秀郷流青木氏の一族」は、この「陸運業」と「海運業」にも更に関わる事で、且つ、「武田軍の追及を逃れる事」も出来たのだ。
伊勢が復興させた「駿河水軍・1艘の廻船」を「伊勢・伊勢水軍と伊勢屋4艘」からの「海と陸の中継点」として「伊豆や武蔵」にも繋げる事が出来て糧を戻したのだ。
この「2年間の彼等の糧」はここにあったのだ。
これは「元駿河の国衆」の強味の所以であった。
そもそも、「敗戦し弱った松平氏の家臣」の中に「水軍」を持ち「それに依る財」を持つ「御側衆」はいなかったのだし、「東の大勢力の秀郷一門」を背景にした「家臣」もいなかったであろう。
身分以上に力を持つ「家臣・関東家人衆」に対して、「三河旗本・近国衆」には“かなわない”とする「嫉妬怨嗟の渦の波」が「額田青木氏」と同じ様に押し寄せていた筈である。
「浜松城の松平氏」は、危険な隣の織田氏に近い「西三河」を残し、「北三河と東三河と遠州での糧」を失っていた。
その「衰弱した松平氏」にも経済的に劣らない「身分以上に力を持つ家臣・関東家人衆の御側衆・青木貞治の裔」は他にいなかったであろう。
ところがこれが、「伊勢勢力」を背景とした「額田青木氏」の「三河での商い」と共に、「松平氏の強み」とも成っていたのだ
敗戦被害を受けなかった「西三河の軍勢」には「2000人」を与えられていて無傷で残った。
そこで「松平氏の力」を検証する。
そうすると、尾張に隣接する「西三河」だけが遺っていたので、「1貫≒2.5石 7貫≒1人家来」の「軍制の仕来り」から、最大で1万4千貫≒3万5千石となるが、「信長と秀吉」に依って弱みを突かれて国境の「西三河の浸食・三好域まで」が起こりこれが「2万石」にまで減石されていた常態と成っていたのだ。
これではどう考えても「旗本以外には養えなかった事」に成る。
「三方ヶ原」で全滅に近い敗戦をしているので、どの記録を観ても最大時に「国衆」を掻き集めてやっと合わせて「兵5000・脚色戦記」に成ったとしているが、実際は戦後は「敗残逃亡兵2000程度以下」には成っていた筈である。
先ずは「旗本程度」を養えると成るが、「国衆等」は「自らの糧」を「何らかの力」で得なければ生きては行けない事に成っていた筈だ。
「駿河青木氏」は未だこの時期は、上記した様に一族から援軍を得て「駿河国衆の副将レベル」であった。
上記した様に長篠後に成って「旗本・家人衆」に加えられたのだ。
故に、「駿河青木氏」は「伊勢の青木氏の経済力・商い」を背景に「元の駿河水軍の糧」に勤しんでいたのだ。
そもそも「伊勢青木氏」に依って平安時代に女系で繋がっていた事の所以で末端の裔を何とか探し出され、相当に「駿河青木氏」は「伊勢」に依って呼び興されて訓練を受けた。
そして「船一艘」を与えられて、再び、その「裔系」は「水軍・水運の商い・伊勢―伊豆に運送」で拡大して行ったのだ。
それが「裔系の長」が「青木貞治」であったのだから、「江戸期・長三郎」に成っても「旗本の上級御側衆・上級番方」を務めながらも、この「水運の商い」は辞めなかったのだ。
この様に資料では「相当に豊かな駿河青木氏の裔」を構築して繁栄していた事に成る。
そこで、この詳細経緯として、江戸にも子孫を広げているだろうが、盤田見附に「菩提寺・浄土宗西光寺・再興」の「伊勢青木氏部」に依って大寺を建立できるまでに成り、それを持てるまでに「子孫」を拡大させている以上は、青木氏等の地名や所縁のものが遺されていると考えられるのが普通で、その割には「青木氏とその類証」が「水運業」を生業としているこの地域に矢張り少ないのが気になるのだ。
何故だろうか検証して観る。
天竜川と太田川の二つの大川の間に挟まれた「圷の野」と、この「ほう僧川」の支流を合わせて、「砂丘」の中で出来た「唯一の港・西光寺より南東8k」の地域に「大船が停泊できる港」は、「天竜川」から東に離れて「圷の影響」が無くなる「福田地区」、ここから「海底深度」が良くなるその“「福田港」”がある。
ここに少なくとも先ず「仮泊」を置いて「駿河湾・34k」と「伊勢湾・白子泊」を常用していた事が資料から判っている。
つまり、「福田港の此処」からは「伊豆青木氏」と「秀郷流青木氏・本拠地」を含む「一門の領域」と成るのだ。
この地域には「青木氏に関わる地名などや春日社」も全く無く現在もである。
全て、この「福田港」から「34k離れた地域」から東に急激に「青木とそれに関連する地名」も含めて大量に何もかも出現して来る。
つまり、この差であるる
平安期と鎌倉期と室町期初期の三期までは「青木氏や永嶋氏等の勢力」が伸長していたが、ところが、室町期中期より勢力を東に押し返されて引いていたのだ。
この時の「名残の先端」が突出した「遠州西光寺域の庄」であって、厳しい乱世の中で衰退しながらもここを遺し得たのは「水軍衆の所以」であったと考えられる。
其れを逸早く裔を救って呼び寄せて訓練して戻して伊勢と繋いで生きる力を着けさせて遺し、其の後は前段の論に成るのだ。
結果として全体は「駿河の青木氏」の「名籍」が存在する所まで引いたと云う「歴史的経緯の事」に繋がるのだ。
大まかな時代性としてはその「引き際の処置」で起こった事であったと考えられる。
それだけに「源平化した事」から狂い出し、遂には「源平戦敗退」により「子孫」は元より「遺物」も遺し難かったのだ。
「近江と美濃の源氏化」に対応した様に「伊勢信濃の忠告」は女系で深く繋がる「駿河」にも当然としてあったと考えられる。
と云う事は、その証拠は「駿河青木氏の子孫」の多くは、現在名の静岡県静岡市駿河区の「青木の地名・現在も青木・盤田見附から東54k」が遺る所にあったと云う事に成る。
「伊勢」が「盤田見附」からか「駿河区青木の庄」の何れから「支流末裔」を見つけ出して「額田青木氏」と同然に世に出したと云う経緯である。
「一族の藤枝の秀郷流青木氏・集中」では無く、再び、“「母方の伊勢」”に呼び出して「商いや水軍」等の訓練をさせてから「30年後〜40年後」には、室町期初期から「消えていた盤田域」に「一人前の青木貞治が出た・100裔人」と云う事に成るのだ。
唯、ここで検証しなければならない事は、「盤田見附域の元の庄」を再び獲得するには「財力と武力」が要るし、「菩提寺」を建立し直し維持するには“「相当な財力」”が要る。
其れを如何したのかである。
この「財力と武力」を以て「庄の民・農民」は信頼して従う。
「武力」は「財力」で補完できる。
問題は失った元の庄を獲得するには、上記した「盤田域の庄面積」の「1800反程度弱≒1800石程度(≒6000平方坪程度以下)」の“「地権」”を買い取る必要が先ずあり、奪還する程の武力は未だ無いしそれ以外にも無いし、武力による獲得は「青木氏族の氏是」ではない。
それには、「駿河水軍の水運」だけでは元の庄の獲得は無理で、この時期、必然的に「今川氏の国衆と成る事」が先ずは前提と成る。
その前に、「青木氏族」とは全く縁が無いが、調べた範囲としてこの事の解決に導いてくれた者、況や、「松井氏」に付いて記して置く。
元今川氏の二俣城主であった「松井氏」は、「山城国の御家人・松井氏一族」が建武政権を離脱し「足利尊氏」に味方し、足利氏一門で宿老の今川範国に属して戦功を揚げた。
その恩賞として「建武5年駿河国葉梨荘(現在の静岡県藤枝市・青木氏定住地)」に「地頭代職」を与えられて移住したと定説ではある。
1513年には「今川氏」から「遠州鎌田の御厨領・盤田見附から真東3k・同庄内」を「領」として与えられ、1528年には「平川郷堤城主・盤田見附から真東21k」とも成ったとある。
この「近江から来た国衆の松井氏」は、最終的にこの「天竜川から菊川」の「南一帯の豪族」と成ったのであった。
そうするとこの「地頭代職時代」にこの「藤枝」に定住する「郷氏の秀郷流青木氏・賜姓族の格式」は松井氏を当然に知り得ていた筈であるし、「山城・近江南部・天領地・公領地域」の「御家人・松井冠者源維義」であるとすると、源平戦で衰退はしたが「近江青木氏二氏・賜姓族格式」を完全に知り得ていた筈である事に成る。
この「近江青木氏」と「川島皇子の裔の佐々木氏」とは奈良期末期まで「相互重婚の一族」であって「伊勢」と「近江4氏」とは血縁の縁で繋がっていた。
「松井氏の祖」が「山城の御家人」と成れば「駿河青木氏」とも少なくとも縁は深い事に成り得るがそこまでは縁を追えない。
奈良期の古来より「近江」には「伊勢青木氏一族」は「施基皇子の時代」から全く縁が無かった訳ではない。
そもそも「近江の日野等」は、奈良期から「日本書紀等」にも記されている通り「賜姓五役」の一つとして「令外官」として「鉱山探索・鉄の産地・鉄穴役」を命じられたが、その所以あって、そこを「領地」として与えられ「統治」を任されていた事が判っている。
そして周囲には「一色の地名の字名」があって現在もある。
この事に青木氏の歴史観に意味があるのだ。
後には前段で論じた通りその所縁から室町期には堺を通して「火縄銃等の生産」にも関わっていて、「近江国浅井と高島の二郡」の「鉄穴・カンナ地区・鉱山」を「字名」として所領としていたのだ。
ここが最初に発見された「鉄の地」で「滋賀国長浜浅井の土倉鉱山・琵琶湖の真北端より北東二里の地・現在の西浅井」で発見されたのだ。
この事は「伊勢の資料」や「日本書紀等」にも記されている。
更に需要に応じて「鉱山開発」が朝廷の命で「伊勢の財」を投じて「東近江」でも進み、もう一つは「平安期末期」には「滋賀国湖南の高島鉱山に広がり、「室町期の開発」では「琵琶湖の真南端の東四里の中東域の一帯・甲賀を起点に日野を含む半径15k圏内」の「白水鉱山と雲井鉱と弥栄鉱山と御池鉱山」等までに広がったと成っているのだ。
その様に添書に記されている。
丁度、それを物語るかの様に「近江青木氏」や「甲賀青木氏」や二里ほど北東に離れた「日野の庄」までもこの圏内に含まれているのだ。
これ等の経済圏でその運輸に関する淀川に出る古来からの「中継点の松井の庄」であったのだ。
要するに其の後の経緯としては、「摂津堺の商い」として「中継点」のこの「松井の庄」を経由して淀川を通して「荷駄の運搬等の中継点」として大いに利用されていて、その歴史は奈良期から始まり浅からず江戸期に至っても変わらなかった様だ。
又、「商い」だけに関わらず隣の「蒲生の庄」の「秀郷流蒲生氏郷一族との血縁関係」も持ち、この「松井の庄」は「青木氏族」に執っては欠かす事の出来ない庄であったのだ。
それだけに「駿河青木氏の貞治」は「伊勢での訓練を受けた以上は元より「青木氏一族」として知っていなければならない「松井の庄」であった筈なのだ。
それが青木氏に関わる者であるとすれば「民」であろうが「商人」であろうが「武人」であろうが「万人」が知っていたのだ。
これは当然に秀郷流一門全ても等しく知り得ていた歴史観で忘れてならないものであつたのだ。
この「近江の鉄穴・カンナ地区・鉱山・鎌倉期まで伊勢と共に本領安堵された」が深く「青木氏族」に関わっていた事を知る事は歴史観に大きく左右するのだ。
故に、百々の詰まりは「額田青木氏の銃隊の由縁」もここから来ているのだ。
念の為にこの「巨万の富・献納」は、「紙文化・紙屋院」のみならず、「銃の武器・近江の鉄穴・カンナ地区の発展・殖産業・青木氏部」の「拡大・伴造」を支配していた事もあって、影で朝廷とも繋がり「無限の富・商い」を獲得していたのだ。
その象徴の一つが「松井の庄」であったのではないかと判断する。
他に「商記録」から「商い」として殆どは「貿易で得る事」で賄っていたらしいが、かなり古くから「銃用」ではなく上記する「近江の鉄穴・カンナ」に「鉱山の爆薬」としても「国内産」にも天皇より命じられて取り組んでいた事、つまり、「山部」や「工部」等の「部人」を統率し管理する「専門の官僚族」の「伴造を統率していた事」が史記にもされいる。
その書の記述には「乳母女樫の炭紛と糞尿を乾燥させものを混ぜ合わせて利用した「近江の硝煙開発と製造・703年頃」にも秘密裏に関わっていた事があった事が記され判っている。
前段でも論じたが当初は「宋貿易」で入手していたが、その後の平安期に成って「紙屋院」のとして「墨や硯石等の開発」の殖産に取り組み、「乳母女樫とその炭紛」は「伊勢紀州の特産品」であり、その副産物としての其処から密かに「爆薬用」として近江に運ばれていた事が記されている。
つまり「紙屋院」として墨用に開発したものの「粉」を集めて「近江の鉱山」に運んで「爆薬用」にこれを利用していたとされ、後には「弾薬用」にも転用したものであるとされている。
「額田青木氏のフリントロック式改良銃の弾薬用」に、更にはこの「近江の硝煙製造」にも「伊勢青木氏・伊勢屋」は更に力を入れていた事が判っている。
後の「室町期」にはこの「鉱山の爆薬用」から一部は「火縄銃用」にも用いられていた事が資料から判っていて、「近江の硝煙の道・ゆず街道・山懐静かな里の一角」を「代名詞」の様に使って密かに呼ばれていたのだ。
「青木氏の伊勢屋の貿易」とは別に「室町期の銃用」にはここを別の勢力に抑えられると困る事から密かに床下に隠して生産していたと記録されているのだ。
恐らくはそれだけでは無く硝酸塩発生を促す為に「温度一定」を図っていたと考えられる。
因みに「硝煙の製造法」は、残された一部の資料に依れば次の主に二つの方法が発見されていたらしい。
一つ目は、中国から伝わり古代では原始的で生物の死骸等の50年以上経過した腐敗堆積古土壌から浮き出て来て来た結晶の「硝酸塩」を抽出し、それに「炭粉」を混在させる方法で生産していた要するに「古土法」である。
この中国の記録を貿易で獲得してそれを青木氏の殖産として真似たのではないかと考えられる。
二つ目は、更に上記の方法を強引に起こさせる「培養方法」である。
石灰土に干草や糞尿を交互に重ね合わせて堆積し、発酵させて硝塩土を造り浮き出て来た「硝酸塩」を抽出しそれに「炭粉」を混ぜ合わせる方法である。
三つ目は、室町期に至ると更に「二つ目の方法」を大量生産型に変更した。
「硝石土の土山」を強引に造り出し、発酵後に浮き出る「硝酸塩の結晶」を取り出して、これに「炭粉」を混ぜ合わせて生産していた。
この「根本原理」は「一つ目の方法」にあるが、日本ではこの地質学上から自然堆積層が無く上記の方法で細々と造り出す方法で古来より生産していたのだろう。
「資料」にはそれを思い出すかの様な表現での様に記されている。
参考として「チリ―一帯の石灰層や硝石層の自然堆積層」は国土全体に及んでいて有名である。
因みに記されている資料に依ると、「混ぜる炭紛の品質」にも問題があって発火能力・爆発能力」にも差があって、それは「紀州と伊勢一帯」でしか採れない「固くて炭化精度が良く微粉末」に成る「伯母樫の木」の「備長炭の炭粉」が最良であった事を知り、「令外官の伊勢青木氏の研究」で到達していたのだ。
結論は「炭の内部の結晶構造」が均一で細かい事にあった事が記され、従って、古来より「国内産の爆薬」は「紀州伊勢産」が優れていた事も上記する「近江鉱山」は発展したと成っているのだ。
さて余談と成っているが「額田青木氏」が持つ「銃の爆発力の高さ」は「輸入の弾薬」に比する事なく此処にあったと考えているのだ。
故に、「額田青木氏のフリントロック式改良銃」は銃そのものも然る事乍らこの微細炭紛にもあったらしく、故に外に真似される事が無く「青木氏族の範囲」で留まった所以もここにあったのだ。
その「原始の方法」がこの論じている「近江の鉱山」から始まったのだ。
これを「天皇の命」で手掛けたのだが上記する「令外官」として「伴造」を支配下に置いていた「伊勢青木氏」ではの事であったのだ。
前段でも論じたが、故に一族の代々の諱号は「光仁天皇」より「伴、又は大伴」に纏わるものを号とする事を天皇から許されていた事が判るのだ。
「永代の令外官の所以」であったのであろう。
注釈として、では、この「実作業」を誰が実行したのかである。
他では、多くのプロジェクトに関わった記録があるのだが、この「近江の鉱山開発」に関わったとする明確に記された資料が少ないのが不思議の一つである。
前段でも論じたが、当時の朝廷の「技術職人集団のトップ」に位置して「施基皇子」と仲の良かった「伊勢の額田部氏」、つまり、後に「桓武天皇の遷都計画」に応じ無くて「飛鳥の斑鳩」を追い出されてこれを救って「伊勢の施基皇子」が「桑名」に隠したがその「額田部氏」であったと観られる。
時代性から観ても関わったとすれば何の不思議もない。
最終は、この「額田部氏」は「施基皇子の仲介」でその数々の功績を評価されその名誉を回復し更にはあり得ない程の「特段の出世」をしている。
間違いなく「鉄穴や爆薬の開発」にも大きく関わっていた事が判るし評価されたのであろう。
「額田部神社」を独自に「守護神」として持つ事を許された「技術職人集団」なのである。
前段でも詳細に論じたが、「土木の職能集団・地形地質を観る集団」で、「干拓灌漑、墳墓等」も手掛ける「土木専門技術集団」で、当時としてその技量は「和気氏や結城氏等」よりも優れていたのだ。
「近江の東」に和紙が生産できる様にした「干拓灌漑と土壌改良」などを手掛けた史実も持っている事から、同然にも「伊勢青木氏」が命じられた「近江の鉱山開発」にもその「地形地質の知識」を以て大きく関わったと考えられる。
寧ろ、関わらないと「青木氏」のみならず他の集団も出来なかった「国家大プロジェクト」であったのだ。
少なくとも初期の「滋賀国長浜浅井の土倉鉱山開発」と、「近江の硝煙開発と製造・703年頃」は青木氏だけでは無理であった筈で、その記録は何処かにあった事が考えられるがその「額田部氏に関連する記録」はその頃の一般は未だ竹簡木簡であった事から記録は消えた事が考えられる。
遺る記録は紙に遺された記録だけに成っていて「青木氏の紙屋院」ならではの記録と成るだろう。
後発の「滋賀国湖南の高島鉱山」では本格的に「額田部氏の活躍時代」に入っているので、その記録は見つかるのではないかと期待しているが未だ確かな記録は無いし、有ってもその存在範囲は「青木氏族などの関係者範囲」に限定されるだろう。
「土木用の爆薬開発」に関しては上記した様に一部であるが遺されているので「額田部氏に関する関わり」が憤怒建設や干拓灌漑の記録はあるので何かの資料の行の中で発見される可能性もある。
当にそもそもその「土木用の爆薬などの高度な知識」は朝廷では「額田部氏」を除いて有していた集団は無かったと考えられるからだ。
それは「青木氏の貿易」との関わりから多少の記録は得られたものであろう。
この様に「伊勢青木氏」は「額田部氏の力」を借りて「鉱山開発」と「硝煙開発」にまでに及んでいたのだ。
話を元に戻して、それだけにこの後の所縁の「松井の庄」を介して「駿河の松井氏」と「駿河の青木氏」は知り得ていて“「歴史のある特別な親近感」”を持ち得ていた事に成るのだ。
そこで、だとすれば、最早、無駄な論として行うが、取り敢えずは「系論」として、仮に「御家人・松井冠者源維義」であるとすると、「近江戦」と「富士川の戦」の源平戦で共に源氏化していた一族として味方と成って戦っていた筈である。
先ずこれだけの縁があるとすれば戦っていた事には間違いは無いだろうが、敗戦後、一族が浪々の身に成り、それが共に再び“遠州で会った”と云う事に「流れ」として成り得たのであろう。
且つ、ここが「室町期末期」まで「秀郷流蒲生青木氏・伊勢秀郷流青木梵純の出自元」でもあって、恐らくは「縁の鎖」の様に何らかの関係を「松井氏」とは確実に持っていた筈である。
要するに、それ故にこの「縁」を以て「国衆」と成ってこの「松井氏の配下・家臣株獲得」に入り、そこで「元の盤田見附」を「地権で獲得した事」に成る所縁と成るのだ。
そして、その「国衆と成った証拠」として今川氏の最西端の其処に「氏としての城」の「平城館・寺閣城」と成る「菩提寺・西光寺」を「再建した事」を意味するのだ。
つまり、この所縁には「国衆に成る事」にしても、「家臣に成る事」にしても、「菩提寺の平城館・寺閣城を建造する事」にしても、「地権料を払う事」にしても、「家臣を養う事」にしても、「水軍を維持する事」にしても、「水運業で得られる糧」では到底無理で「大財源が必要であった事」に成る。
当然に、その「財源の出処」は「伊勢青木氏」か「武蔵青木氏宗家・江戸長島屋」かであるが、この所縁の流れとしては「伊勢青木氏・伊勢屋」が「額田青木氏」と同然にこれを賄ったと考えられる。
要するに戦略的には、同時期に“西に「額田青木氏」、東に「駿河青木氏」を興した”のであって、前段で論じた様に「信長」に依る「尾張域の神明社破壊」やこの事で起こる「伊豆や信濃との連携が難しく成る事」を防ぐ為にもこれは“「当初からの戦略」であった”と考えられるのだ。
その結果、「盤田見附の西光寺」だけを遺して「神明社」も「春日社」も「清光寺」も影形を全く無く成っていた「遠州」に於いて、「伊勢」にしても「武蔵」にしてもここに「青木氏の拠点の復元」を成さねば成らなく成っていた事、又は追い込まれていた事に成る。
それで「乱世の中」で「東西の青木氏の同族」が生き抜ける為には、再び途切れた「西と東」が繋がれば“「強大な抑止力」が働く”と考えていた事に成る。
その為の「財源拠出」は問題は無いと観ていたのだ。
「室町期の紙文化開花」で「巨万の富・紙屋院」や「鉱山等の多くの殖産」で獲得した「財源」を遺憾なく此処に投入したのだ。
それには、「青木氏族」に執っては「相手」は当面に「武田氏」であって「織田氏」でもあったのだ。
そこで筆者が感じる処では、「伊勢系列と信濃系列」を始めとして「青木氏族」に執つては疎遠であった「武田氏系青木氏の関与」は、もう少しの「関係性」を見つけられるのではと観ていたが、「二俣城の浄賢」だけであるのは何か間尺は合わない。
それは、「武田氏」が完全に滅んだ「長篠」より、「甲斐の五つの青木氏」が「伊勢」では無く「秀郷流青木氏を頼った事」なのだ。
確かに「甲斐青木氏・甲斐冠者系の源光系」と「嵯峨期詔勅で名乗った時光系」は「嵯峨天皇派」であって「犬猿の仲でった事」は否めないが「伊勢信濃」には彼等は頼って全く来ていないのだ。
“受け付けなかったと云う事”もあつたかも知れないが、そんな資料や記録の行は無い。
このすっきりしないのは「史実」である。
そもそも「武田氏系」には、「源光系青木氏・1氏」、「時光系青木氏・5氏」、「諏訪族系青木氏・3氏」があった。
「源光系青木氏・1氏」は不参戦で甲斐で衰退し、「時光系青木氏・5氏」は、「分家2氏」は徳川氏に味方し武蔵鉢形に移住させられ、残る「1氏」の「分家養子・安芸」は早めに戦線離脱し、後に安芸松平氏の家臣に成る経緯を辿っているのだ。そして「本家筋2氏」は完全滅亡している。
「諏訪族系青木氏・3氏」に付いては、「武田氏系の1氏」は衰退したが、「諏訪族系の2氏」は「相模の秀郷流青木氏」に救出され、其の後1氏の一部が下野に配置、残りの一部も「越後秀郷流青木氏」を頼り、4流に分流した。
「長篠後」にこれだけの「関係性」を保持しているのに何もないのは腑に落ちない。
当然に「三方ヶ原前」にもあったと観るのが普通であろう。
現実に、江戸期には「甲斐青木氏・正定系と豊定系」とはある程度の関係性は出来たと考えられるが、この敗退した「甲斐青木氏」が、「秀郷流青木氏一門を頼った事」で「血縁の繋がり性」は出来た事も「史実」である。
平安期と鎌倉期には確かに「賜姓」は「青木氏」を中止した代わりに「桓武派」と「嵯峨派」の争いで「仲介案」を採って「伊勢青木氏出自の嵯峨天皇の皇子・嫡子」が“「甲斐青木冠者蔵人・源光系・准賜姓格式」”として「甲斐」に配置されたがそれでも関係性は基本的に無かったのだ。
極めて疎遠で犬猿の仲であった事は資料からも解る。
上記した様に「青木貞治と主従関係」にあった「山城・近江南部・天領地・公領地域」の「御家人・松井冠者源維義・河内頼信系源氏」と、「賜姓扱いの格式」を与えられた「甲斐青木冠者蔵人・源氏族では無い・後に源光系と成る」として「甲斐」に配置されたが、この「源の源光系青木氏・嵯峨源氏」とは要するに「源氏族」で無関係では無かった筈であるが、「繋がりの詳細経緯」に付いてはこれ以上は今も資料は見つからない。
然し、そもそも遺すだけの力が無かった事も云えるのだ。
「賜姓伊勢青木氏と賜姓近江青木氏」とは、奈良期から平安期まで「相互血縁の同族」であった事と、「近江青木氏の定住地」とはほぼ同じの「松井氏との関係性」は完全否定できないだろう。
間違いなく「源氏・11流」とすれば「皇族としての嵯峨源氏」は「9つの縛り」を護らなかった「賜姓源氏族」と、「源氏化しなかった伊勢と信濃の青木氏・嵯峨源氏9つの縛りを護った」とは「四掟の範囲」では無い事に成り、それ故に頼る事は出来なかった事には成るし、又、決して四掟で受け付けなかったであろう。
その意味では、「円融天皇賜姓族藤原秀郷流青木氏・伊勢信濃とは女系で血縁」は「同じ青木氏」として頼り易かったとは云えるが、「血縁性の有無」は最早これ以上は辿れない。
そもそも、「正式な源氏賜姓・11家11流」は「花山天皇」で終わったが、この「花山天皇」の前の「冷泉天皇の発狂事件」が起こり、これに代わって異母弟の「円融天皇・11歳」と成り、「源氏賜姓」を止めて「伊勢信濃の母系族」であった「藤原秀郷流一門の宗家嗣子の第三子」を「永代・始祖は千國」に賜姓させる事としたのだ。
「外戚の藤原氏内紛」で16年後に「冷泉天皇の嫡子・花山天皇」に譲位した。
この「花山天皇」も「外戚の藤原氏の内紛」で2年も待たず退位した。
ここで「嵯峨詔勅に基づく皇族」の「正式な源氏」は途絶えたのだ。
つまり、其の後の「正式な賜姓」は「藤原秀郷流一門の宗家嗣子の第三子」を永代に「青木氏の賜姓をさせる形式」と変わったのだ。
これが要するに最終は「賜姓が元の母方系青木氏」に戻したとする「詳細経緯」であるのだ。
その前には「摂関家の藤原氏との戦い・藤原仲麻呂事件・恵美押勝」で翻弄され「孝謙天皇の白羽の矢の事件・伊勢青木氏の施基皇子の四男の白壁王と井上内親王」の問題が起こっていたのだ。
その「皇族との血縁の基」は、「賜姓」を権威づける為にも「混血融合」を避ける為に「四掟と云う縛り」を設けて、代々に「伊勢信濃との青木氏の母方・女系族である事」で権威格式付けしたのだ。
これが効果を発揮して「円融天皇の思惑通り」に何と「116氏に及んだのだと云う経緯」を持っているのだ。
況や、この経緯があるが故に「四掟前提としている以上」は「甲斐との血縁性は無かった事」には成るのだ。
先ず間違いなく詳細経緯を押し切るだけのものは無かったであろう。
唯、この「秀郷流青木氏族」と呼ばれる「秀郷一門内部での血縁族の主要五氏」とにはこの「縛り」は適用されなかったのだ。
依って、この「秀郷流内の青木氏族内」の「主要五氏・青木氏永嶋氏長沼氏進藤氏長谷川氏」の範囲での「甲斐青木氏との血縁・源光系と時光系」はあり得る事は否めないのだ。
然し、この血縁は、「二つの四掟で繋がる青木氏族」の中には出て来ないし、伊勢側から其処まで踏み込めず調査は難しいのだ。
従って、前段でも論じたが、厳然とした「噂」があるのにも関わらず「資料・記録」が無い為に判らないのだ。
唯、「諏訪族」とは「信濃青木氏との重婚族」であり、古来より「諏訪族青木氏・立葵紋」であって、この「裔系・抱き角紋」が「武田氏の血縁族」を構築していて、「相模に逃げ込んだ事」も史実であり、頼った事には「何の問題・疑い」も無い。
「秀郷流青木氏―伊勢と信濃青木氏―信濃青木氏と秀郷流青木氏―信濃と諏訪族青木氏―諏訪族と武田氏」であれば、直接、血縁無くしても「血縁の濃度」は別としても「間接血縁族」として頼れる事は可能であったであろう。
現在筆者はこの様に観ている。
そして、その仲介を担ったのがそれが何と本論の長篠後の「駿河青木氏の裔祖の相模青木氏」であったのだ。
これは、「三方ヶ原―長篠」の後に興したより「青木氏族」であった一族の歴史の“自然が興した再結集現象”と成り得たのだ。
この「不思議な自然の血筋の流れ」は江戸期に向けて濁流の如く留まらなかったのだ。
但し、そこでその基と成った「駿河青木氏を家臣」として抱えてくれた「松井氏」に付いては、“山城の「河内源氏」である”とする事にもう少しその根拠と成る歴史観を説いて置く。
そうすればこの「松井氏の位置づけ」がより判り、「駿河青木氏の青木貞治との関係性」も詳細経緯としてより理解が出来るだろう。
「松井氏の祖・平安期」と主張する根拠には、「山城の何処かの家人・天皇家・公家・賜姓族・皇位族」であったとしていても、その「家人」と成り得る「氏」としては「頼信系の河内源氏」であるとしているのだ。
“何処かの家人”としているが明記されていない事にも「疑問1」であり、“河内源氏”としているのも「疑問2」である。
しかも当時は、「嵯峨期の9つの縛り」を全く護らなかった事で「皇族系の氏族としての格式」を認められていなかった「河内源氏」である事に認識はなく「疑問2」は記載している。
認識なく名乗っていたのかも知れないが、間違いなく“「松井」”と「姓名」を名乗っていた事には間違いは無いのかも知れない。
だが、「疑問1」から「傍系卑属系の支流族」であった事には「格式」を前面に押し出す程の家柄では無かった筈であった事だ。
故に、「疑問1」と「疑問2」が欠落して仕舞っていた事に成る。
「一族の伝統」とは支流の一家が忘れていても本家筋の他家は覚えているものでそんな欠落する程のものではそもそも無い。
故にそれが起こるとする可能性のある「傍系卑属系の支流族」であった事に就いて詳しく検証して観る必要がある。
「疑問1」と「疑問2」はそもそも護らなくてはとする「伝統意識」が低く、且つ、「伝統」そのものは違う。
故に、「傍系卑属系の支流族」では起こるであろう。
現に伊勢や信濃では未だに意味しない伝統は浸み着いて忘れ去れずに何らかの形でほそぼそと持ち得ているものだ。
「9つの縛り・嵯峨天皇が後に纏めた新撰姓氏禄」に依って「天皇家・公家・賜姓族・皇位族」はそもそも「諡号の姓・第一の姓」を持つが「第二の姓」はそもそも持たないのが掟だ。
これも「伝統の一つ」であり、だから未だ「青木氏」は統一して「青木氏」であるのだ。
従って、「天皇家・諡号と諱号」を除き「氏名だけの範囲・青木の氏や藤原氏」で名乗ったのだ。
唯、例外として「藤原北家秀郷流一門」は361氏と成り、「氏名や諡号や諱号」では一族一門の系統を格式管理できなく成り、「仕来り」として「三つの縛り」を設けてこれを判別する様にしたのだ。
其れは、前段でも論じたが次の通りであり忘れ去られていないでいる。
第一に、「役職名」を藤原氏の氏名の藤の上に付けて名乗る。
斎藤氏・工藤氏等
又は、許可を得て「役職名」を名乗る。
結城氏
第二は、「国、又は地域名」を藤原氏の氏名の藤の上に付けて名乗る。
伊勢藤原氏の伊藤氏・加賀藤原氏の加藤氏等
長沼藤原氏・長沼氏 永嶋藤原氏・永嶋氏等
第三に、「特徴名」を藤原氏の氏名の藤の下に付けて名乗る。
藤田氏・藤井氏等
第四に、以上の三つより更に「事情」により拡大して派生した氏は同名の「字」に替えて名乗った。
長嶋氏、長島氏等がある。
当初は先ず「兼光系」と「文行系」の二派に分かれ、其れより更に分流して「文行系利仁流」や「文行系修行流」に大分流した。
「秀郷流青木氏族」と呼ばれる「秀郷流青木氏」と「秀郷流永嶋氏」と「秀郷流長沼氏」は「兼光系」であり、「長谷川氏」と「進藤氏」は「文行系」であり、「秀郷流青木氏族主要五氏」と呼ばれ血縁性は取り分け高い。
これを以て「氏の総称」を「藤氏」と呼び、地域事に「伊勢藤氏・讃岐藤氏」等として大別した。
これで「系統や格式レベルや血縁関係」を判別するようにしたのだ。
唯、「秀郷流青木氏24地域・116氏」だけは秀郷一門に劣らず大氏一族ではあるが、「賜姓族の特別の格式を有する事」で、「嵯峨期の9つの縛り」に基づき「伝統の仕来り」として「氏名」だけとしたのだ。
要するに本論の「駿河青木氏」もその一つであるのだ。
ここで、更に「皇位族の賜姓臣下族の朝臣族」だけには、もう一つの「判別する仕来り」があったのだ。
それは上記で記した、「好名」とは別に「字名・あざな」であった。
天皇より「皇位族の者」が成した「功績」に従って「所領と民」を与えられた。
その「所領と民」は「小字と大字」に分けられそこに「民」が替わり振られ「特別の名」がつけられたのだ。
この様にその「場所」と「民」にはそれを「特定する名」とする「特定の仕来り」があったのだ。
それが、拝領時に「天皇」から「指名される賜姓」とは別に「賜名に値する字名・あざな」があったのだ。
その「字名・あざな」はその功績の都度に別の「字名・あざな」が与えられた。
この「字名・あざな」は其処の「氏人」も「民」も「名誉」とするもので扱われたのである。
何故ならば、当時は「国造」として「民」は「天皇」から与えられたもので「氏族の氏上に所属する仕来り」であって、「民の字名」は「一色の・・・」として「姓・代名詞」にも代わるものであったのだ。
故に、「青木氏の定住する所」には民の為にも必然的に「字名・あざな」を必ず持ったのだ。
その「字名・あざな」にはその「皇位族に関連する賜名」が読み込まれていたので、これで区別していたのだ。
従って、重なる事が起こるので特定する代名詞として一族以外の別人がこの「字名・あざなの慣習」を使う事は許されなかったのだ。
朝廷が認めた氏族に限り許された慣習であった。
言うなれば「賜姓」と共に「一族の賜名」であったのだ。
これを「一族の裔の者が住む土地の代名詞」として使っていたのだ。
当然に近江もである。
例えば「伊勢王の施基皇子」には、主に伊勢では「四つの大字名」が賜名されていた。
例えばよく使われた「字名」では、「一色や色や一志や一円や志基」等があるが、江戸期には「日本全国60カ所」にも及ぶ「一色関係の大字名」があるが、この殆どは「秀郷流青木氏を含む青木氏の定住地」に広がつているのである。
但し、国抜制度があった為に正式な移動定住は考え難く一部に真似たものもあるが、約8割は関係地と認められる。
これは「四掟に基づく女系の妻嫁制度」で全国に定住している「秀郷流青木氏の嫁家先」にもこの「字名」を興した所以でもある。
言い換えれば、「秀郷流青木氏の定住地」には伊勢、又は信濃から嫁いだ「女(むすめ)」がもう一つの同じ「伊勢、信濃の青木氏」を女系の優秀な嗣子に里の青木氏を興させたと云う事にも成るのだ。
つまり、況や、最早、重婚を重ねる事に依る「二つ血筋を完全融合する二つの青木氏」のこれが「60にも成っていた事」を示すものに成る。
よく似たものに「伊豆の青木氏」や「伊勢や信濃の氏人・郷士衆」がある。
筆者は、この「60の数」から観て江戸期には、最早、この「賜名の字名」は「格式名」の前に「完全な代名詞化」を興していたと考えているのだ。
つまり、「判別名に成っていた事」に成るのだ。
現実に「四掟」に基づきながらも「京の公家先」に嫁いだところでは「賜名の字名」は興っていないのだ。
所謂、これは「代名詞化する程の事」では無かった事を意味する。
唯、注釈として説明して置くのは、この「近江」にはこの「始祖の施基皇子」に基づく「賜名の字名」がそれなりの数であるのだ。
これを上記した様に如何見るかである。
この「近江」は、そもそも「施基皇子」の兄の「川島皇子・近江王の始祖地・佐々木氏」の守護地であったのであるが、ところがここに「施基皇子の賜名の字名」があるのだ。
これには「日本書紀」に基づけば次の「三つの説」が挙げられる。
一つは、平安期直前まで「川島の皇子と施基皇子」は当時の「臣下族の習慣」として「相互重婚の唯一の天智一族」であって、其の事から「施基皇子の賜名の字名」が「近江」に遺したのだ。
二つは、その結果として「二つの青木氏」が発祥した。
つまり、「近江青木氏」と「佐々木氏系近江青木氏」である。
この結果として、「施基皇子の賜名の字名」を遺したのである。
三つは、上記した鉱山開発を命じられてそこに「伊勢の青木氏の裔系子孫」を遺した事が云える。
その結果として、二つの鉱山付近に「施基皇子の賜名の字名」を遺したのだ。
ところが「近江佐々木氏の研究資料」には、この「川島皇子の賜名の字名」の事が何故か書かれていないのだ。
そうすると、「近江青木氏」は前段まで論じて来た「五家五流賜姓族の近江青木氏」では無く、一色からから来る現地の子孫、つまり「伊勢の裔系」の「近江青木氏」であった事にも成る。
つまり、「鉄穴から来る一色の大字名説」と成り得る事も考えられるのだ。
「佐々木氏系青木氏」は別としても、将又、「五家説の単独青木氏との両方での存在説であった事も考えられる。
筆者は、「近江佐々木氏の研究資料」からもこの事に就いて散見できないし、「両方での存在説」を今の処採っている。
恐らくは「伊豆」の様に「三つの混在血縁融合」が興っていたと観ているのだ。
「川島皇子の賜名の字名」は間違いなくあった筈であるが今では確認できない。
「日本書紀」に依れば「始祖の施基皇子」と同じく「合計封戸は500戸を授かっている事」から「近江」に「字名の賜名」は持っていた筈であるが、「好字令・713年・諸国郡郷名著好字令」の施行で消えた可能性がある。
それ程に「川島皇子の賜名の字名」は弱かった事にも成る。
唯、「天武天皇の崩御後」の際に「川島皇子の裔系」はその「行動・大津皇子事件」を「持統天皇」に疑われた史実があり、この事で「近江佐々木一族」は、其の後、「不遇の扱い」を受けた史実がある。
其の事から、「川島皇子の賜名の字名」は「賜姓」と共に「近江」で遺せなかった事と、源氏化に依って遺せなかった事が考えられるし、逆に「伊勢信濃」は発展し、その差から、完全な疎遠と成って仕舞った事を示すものと成る。
もともと「近江」の「真砂の不毛の地」は「伊勢」が「額田部氏に依頼しての開拓開墾」であって、その後の開拓開墾は成功し、「楮の生産」で一時「財」を成したが「源氏化」でその財源も失って「字名」も遺し得なかったのだろう。
故に、「佐々木氏の研究資料」には不思議に「字名の記載」がない所以であろう。
従って、先ず遺しえる力は無かった事が確実に云える。
と云う事は、だとすると「近江の遺る字名」は「施基皇子の賜名の字名とその裔系」であった事も云える。
つまり、一つと三つの事に依って遺した事に成る。
つまり、斯くの如しで「施基皇子の賜名の字名」は「松井氏の論説」をも裏付けるものと云えるのである。
と云う事は、これは「摂津」を「起点」として「近江」までにも「伊勢信濃の勢力」は「商い」のみならず「子孫力」でも伸びていた事を示すものだ。
筆者は、「日本書紀」にもある様に、「鉱山力」に強く注目して「銃に関わった事」の以外に「青木氏の歴史観」を広げる為にも「賜名」も研究しているのだ。
この事に就いては前段でも論じているので「本サイトの検索で・字名で検索」されたい。
「嵯峨期の詔勅禁令」でこの「賜姓」は「青木氏」か「ら賜姓族・源氏」に変更した事を論じたが、この時に「青木氏の慣習仕来り掟を真似る事」をも同時に禁じた。
この禁令は鎌倉期より室町期ではこの「禁令・朝廷の権威」が緩み「格式の搾取」が「格式の無い姓族」に依って激しく横行した。
この時にこの「賜名の字名」が「一部の者・地頭等」に依って「格式権威」に使われたのだ。
鎌倉幕府は治めるに必要としたので敢えて使う事を黙認したのだ。
それは「守護職」から変えて未だ馴染みのない「地頭職」を幕府は置いて治めようとした。
朝廷は幕府からの申し出の「地頭職」のこれを当初認めなかったからで、つまり権威の無い役職と成って仕舞ったので敢えて「権威付け」の為に「字名の使用」を強行した。
これには「嵯峨期の禁令があった事・青木氏の慣習仕来り掟の使用禁令」から逆らう事が出来ずにこれを黙認したのだ。
頼朝の地頭制度の最初は「伊勢の伊賀の地頭職」で、次は「三河の西尾の地頭職」であった。
取り分け、三河は「荘園」が多く、「七郡・碧海郡、額田郡、賀茂郡、幡豆郡、宝飫郡、八名郡、渥美郡」 から成り、「豊穣の地」として「荘園支配権の簒奪戦」が起こっていたのだ。
そこで鎌倉幕府はこれを鎮める為にも「地頭職・西尾氏」を始めて送ったのだが周囲を統治するだけの権威は無く効果は無かった。
そこで、この「西尾氏」に「施基皇子の字名」の「一色」を使わさせて権威づけさせて統治させようとしたのだ。
何故ならば、その近くにの「額田端浪の一色」には、三野王に嫁した桑名殿の「浄橋と飽波の裔系・額田青木氏」の一族が住んでいて、「始祖施基皇子の伊勢の字名・不倫の権」の「一色」を「仕来り」に従い名付けて権威化を図り周囲に「デリバリー」をこの地域に構成していたのだ。
これを利用して「西尾の圷」にも「一色の字名」で「伊勢の荘園」であるかの様に見せて従わさせる策に出たのだ。
伊勢の「伊賀地方」も同然で、「惣国地」でもあったここに「鎌倉幕府」は「足利氏・栃木県足利」を送って地頭を最初に置いたのだ。
そして「伊賀青木氏」と同化を図って一色姓を名乗ったが任期が過ぎると早々と現地孫を遺して足利に戻った。
「権威ある字名」はこの様に使われたのだ。
これがもう一つの判別する仕来りであったのだ。
(注釈 「駿河青木氏の青木貞治」の詳細経緯)
前段までに論じた詳細経緯で「青木貞治」は戦乱の中で歴史的に「青木氏族」に大きな影響を与えた人物であった事が云える。
そこで、従って、改めてその経緯を更に辿つて論じてみると、次の様に成っている。
「駿河青木氏の青木貞治」は、先ず「今川氏」の「土着国衆・土豪」と成った。
其の後に、今川氏の「渡り国衆」に成っていた「松井氏」が、そして「勲功」を挙げて遂に「今川氏家臣」と成り、「重臣」とも成った「松井氏・二俣城城主」に対し、「駿河青木氏の青木貞治」は「松井氏の国衆」と成り、「家臣」と成った。
ところが、「今川氏・桶狭間戦死」は衰退し「二俣城の松井氏」も衰退し、分裂した。
ここで「青木貞治の裔系」はその三つに分裂した松井氏の徳川氏側方に着いてこの松井氏は「今川氏から徳川氏」に「今後の命運」を架けた。
結局、優勢を保持した「徳川氏側の国衆」と成り、「松井氏の二俣城」は結局は「徳川氏の物」となった。
この「元二俣城の松井氏」と「遠江駿河土地」と「国衆の所縁」を以て「二俣城の守備隊・家臣中根氏」と成ったのだ。
そこに「駿河秀郷流青木氏」、及び、「武蔵秀郷流一門」の「後押し」で、「兵の支援・100」を受けて「二俣城の副将格・兵200」を獲得した。
「駿河国衆」より「遠江国衆」として成り得て「徳川氏の国衆―二俣城家臣」と成り得たのだ。
先ずこれを前提にすれば、「早期の経緯論」に成り得る。
4 宗信・弟 二俣城家督 1529 桶狭間戦死 1560年
結局はこの経緯から「駿河青木氏の青木貞治」が仕えたのはこの“「松井宗信」”であった事に成る。
だとすると、この直ぐ後の「桶狭間の戦い」で主君の“「松井宗信」”は戦死したが、同じ松井隊にいた「青木貞治隊・兵100」は何とか生き延びた事に成り得る。
そこで疑問・AとBが生まれる。
A 何故、生き延びたのであろうか。
其の後の「{二俣城」では徳川氏の中で子孫拡大どころかそれ以上に確実な地位を固めているのだ。
もう一点は、歴史的時系列では、丁度、この時、「額田青木氏の銃隊」は南下して「三河国衆」に成っている。
B 何故、この時期に「訓練中の額田青木氏の銃隊」が「三河国衆・1560年」と成ったのかである。
但し、この「桶狭間の戦い・1560年」には記録上では未だ「額田青木氏の銃隊」は参戦していないのだ。
国衆に成って4〜5ケ月後の事である。
「駿河青木氏の青木貞治隊」は参戦したのだ。
この「二つの何故の事・A、B」に就いて「手掛かり」と成るの詳細な記録は無い。
特異な青木氏に依る歴史観である為に独自の時系列で追うしかない。
そこでAに付いて、気に成る点がある。
「桶狭間の戦い」の中心と成った付近の「ほぼ南300mの所」に「神明社・伊勢信濃の青木氏の守護神・現存・古跡社」が在った。
そして、ここから「北東7.5k・2里」に「春日社・2社・秀郷流青木氏の守護神・古跡社」が在り、何れも現存する。
この「神明社」と「春日社」は、何れも「二つの賜姓族の青木氏社」として朝廷より「不倫不入の権・朝廷」を得ている「古来の高井神格の伝統」を保持した「最高の社格式」で、室町期はその「拘束力」は弱まったとしても未だ敬われていた。
ここで改めて、「奈良期の伊勢信濃の賜姓青木氏の神明社」と、「円融期の賜姓秀郷流青木氏の春日社」で、「古来奈良期からの伝統的神格概念・社」とは異なる「伝統的神格概念」を緩めた「神社格式」ではないのだ。
故に、一段上の神的社のものとして「神社格式」とは別により特別に敬われていたのだ。
念の為に、簡単に論ずれば「社格式」とは、「神を崇拝する原理主義概念・奈良期の古来概念」であり、「神社格式」とは、「仏教的概念」をある程度含有した「神を崇拝する進歩的概念・平安期」であつた。
「Aの推論」としては、この「神明社」か「春日社」に「青木氏」として逃げ込んだ事で掃討を免れた事が云える。
唯、「信長」はこの「特権」を否定していたが掃討していた家臣等がこの伝統を敬い黙認したとも考えられる。
何れの「社」の「神職」も「四掟の嫁家制度」の「女系で繋がる青木氏・賜姓の同族」である。
この「神職・青木氏」が「社門」で盾に成った可能性がある。
この時、元信・家康は「大樹寺(松平家菩提寺)」に逃れ住職の助けを受けて助かっているのだ。
当時は、「戦場やその近隣の民」は難を逃れる為に「神社や寺」に上記の意味で逃れるのが一般であって、そこに身を変えて逃れたと考えられる。当時はこの高い格式の国幣社格に逃げ込むと兵は一般に手を無理に出さないのが伝統であった。
因みに、何度も論じた事であるが、唯、「秀吉」は「信長」よりもっと厳しくこの習慣を否定したが、流石に攻める事まではしなかったが、然し殆ど「焼き討ち」は掛けたのだ。
「紀州根来寺」などは民や僧兵と共に6000人と云う人を焼き殺した史実はその典型である。
何故ならば、戦乱期はこの様に「逃亡兵」がこの習慣を使って寺社に逃げ込む事が多かったのだ。
他に平安期に平家に追われた日向に配流と成った「源宗綱等他2人」が「以仁王の乱」で敗退し、配流罪で隠れ住んだ「廻村の者」と「薩摩大口村の浄土寺・現存・5人」まで逃げ込んで間一髪で「伊勢青木氏」を名乗り難を逃れた。
伊賀で関係を持っていた“青木氏を攻める事は出来ない”として「九州平氏・平氏の始祖の伊賀平氏の高野新笠・青木氏出自の光仁天皇・白壁王の妃」は再び「日向」に戻った史実があるのだ。
これが「日向青木氏の大口青木氏・現存」である。
この様な史実に、「永代不入不倫の権」を持つ「官幣社の最高社格式社」は乱世とは云ど最小限の処で保護されていたのだ。
又、室町期には「足利幕府」からも改めて「青木氏族」は「律宗族」としても認められ「侵犯」に付いて「特別保護」されていたのだ。
筆者は、そこで、A 何故、生き延びたのであろうか。?では、上記の「北東7.5k・2里の春日社」では無く、「南300mの神明社」に逃げ込んだ説」を採っている。
ここであれば逃れられる。逃げるとしても「北東7.5k・2里の春日社」は遠すぎるし、そこから「遠江」に逃げ帰るには地理的に困難であろう。
「尾張」を避け「三河の国境・現名 みよし」を廻り「三河」の「青木氏の所縁の安全な地等・岡崎から豊橋等」を経由して「遠江の西光寺」まで約100k・1日以上を所要する。
然し、「突発的に起こった襲撃」を躱すには「戦場の地に在る神明社」の方が先ずは「最適な避難所」であった。
況してや、「駿河青木氏・青木貞治」と「伊勢」は母方実家・で血縁族で訓練して興して貰った「第二の里」であり、且つ、この唯一つ残る「神明社の神職」は当然に「伊勢青木氏」であり、身を挺してでも一族を護ったであろう。
其の後、「伊勢」に連絡して「伊賀者」を動かし警護に着けた事もあり得るし、小舟で導き「神明社の傍」にある戦場を流れる「鞍流瀬川と石ケ瀬川」の支流を経由して「境川」を下り「三河湾」に出れば、最短距離と且つ安全に「渥美湾」で「伊勢水軍」か「実家の駿河水軍」が待つ船で助けられ「遠江」に戻れる。
筆者はこれくらいの事は出来たと考えられる。
そのキーポイントが現在・緑区桶狭間に在る「神明社」であったと説く。
ここに逃げ込めば後は何とでも成る。
筆者はこれを突っ込んで寧ろ次の様に考えている。
「桶狭間の戦い」は、1560年6月12日である。
これに「青木貞治隊」は「今川氏の国衆」として「松井宗信隊」に所属し、参戦している。
「額田青木氏の南下国衆の銃隊」は、この戦いの直前の2〜5月頃に「国衆」と成って南下し、其の後、「伊川津の三河国衆・西三河」として定着した事に成る。
この後、ところが松平氏が違約して「東三河隊」に所属させられ、「吉田城守備隊・1565年・武田氏の侵攻予測」と成っている。
「武田氏との第一次吉田城の戦い」は、「守備隊7年後」の1572年の「三方ヶ原の戦い」の1年前の事である。
当然に、この時、既に「伊勢青木氏と伊勢水軍」は約束の通り「渥美湾・2h」に廻船を始めていた。
「桶狭間の前」には、既に「伊勢と伊勢水軍の廻船」は「蒲郡の石切り湾」を拠点にして動いていた。
とすると、「1560年6月の戦い」では、「伊川津の南下国衆と家族を護る事」と、参戦している「駿河青木氏・青木貞治を護る事」の為に、万が一の場合に備えて、「警戒の帯同」の為に「陸・伊賀青木氏・情報」、「三河湾の配置」の為に「海・伊勢水軍・救出」と、綿密に作戦を組んで動かしていたと観ているのだ。
当然に、「駿河水軍」も「伊勢からの指令」で「三河湾」に集合し待機していた事が充分に考えられる。
其れを行うだけの「充分な財力と抑止力」が在るのだから躊躇なく筆者なら絶対にそうしているし、何もしないという事は100%無いだろう。
それが「青木氏族の氏族」の長く生き延びる為の「戦略行動」であって、奈良期から生き抜いてきた「青木氏族」であってこそ、そんな間抜けな「伊勢・福家」では無かったと自負しているのだ。
「織田軍と今川軍」が衝突する様な場所は、凡そは予想が着くとするならば、又、其処辺りには「神明社と春日社」が在るとするならば、上記の様な戦略を事前に立てるし、事前に「駿河青木氏」や「額田青木氏」には「事前連絡・伊賀者」は着けていただろう。
何せこれを行う「情報・伝達組織」には「伊賀青木氏の香具師」が存在し全く苦労はしない。
「行軍・戦い時の兵糧の運搬・駿河青木氏」もあるとすると、「伊勢水軍・駿河水軍」と「伊賀青木氏の香具師の隠密行動」も必ず必要であった筈である。
これ等の事は「他氏には絶対に出来ない行動」であり、「氏族の強みを生かす事」でもあったのだ。
前段や上記でも論じた様に、「額田青木氏の銃隊と荷駄50」と「駿河青木氏の隊・100」には「伊賀青木氏」を組み込んでいたと論じたが、当にこれを証明するものである。
上記の論だとするとして、これに「追加する事」として、訓練中であった「額田青木氏の銃隊」は「桶狭間の前の前哨戦」の「小豆坂の戦い」の「一次戦」に「軍事演習的行動」として依頼されて参戦しているが、この事も考え合わせると、「額田青木氏の銃隊」の「一部」が「伊賀青木氏」と共に、「伊川津域」に国衆として定着する「少し前・4〜5月程度」の「桶狭間」に、“「一族の誼」”として「駿河青木氏の青木貞治隊」にも密かに合力していた事も考えられる。
だとすると、桶狭間の敗戦では“上記の筋書き通りに簡単に安全に脱出出来た”と観られるのだ。
その証拠に、故に、記録に遺る事もない程に「駿河青木氏の青木貞治隊」は犠牲無く脱出出来ているのだ。
ここに後に「完全に生き残っている事 イ」と、「二俣城の副将と成り得ている事 ロ」の「論の焦点」が来るのだ。
そして、その後に「松平氏の家臣・御側衆・旗本 ハ」と成り得ている事のイ、ロ、ハと下記のニ、ホを勘案すると、「上記の筋書きの状況証拠」は成立するだろう。
況や、「桶狭間」で二俣城城主が討ち取られる「大犠牲の大混乱の真中・逼迫戦」で奇しくも「青木貞治隊」が生き残り得たとすれば、例え、「松井氏の衰退」で「徳川氏・松平氏側」に着いたとしても「松平の国衆 ニ」にも成り得なかった筈であるし、又、其の後の「駿河・相模青木氏の支援」を得て「兵力・200」に増やし「二俣城副将 ホ」にも成り得ていなかった筈だ。
要するに、「青木氏族の生き遺りの為」に、「戦乱の中」では「唯一の抵抗手段」の「大抑止力」は働いていたと云う事になろう。)
「青木氏の伝統 64」−「青木氏の歴史観−37」に続く。
Re: 先祖と宗教(キリスト教の教え−8 主題5)
副管理人さん 2007/10/24 (水) 09:44
以降、8番目の設問の説明とします。
(特定者(若い者)には受け入れられ易い合理的な教えに成っている事。)
キリスト教ではこの様な全体として比例式のように論理的です。わかりやすい説き方です。
若者には、論理的に受け入れやすい人には、好まれるものと思います。
仏教では、「色即是空、空即是色」ですから、何のことと成ります。
キリスト教では、悪と聖(善)とに分けると言う数理的合理的な説法です。
仏教では、「悪善」と分けずに、これも人の成し得た性(ごう、さが)として「拘るな」としています。
人間は、知恵を出し、社会に付加価値を大きく生み出しました。この結果、付加価値の少ない時代の事と較べて、物事の始末と結末が、合理的、数理的、論理的に判断できない環境と成ってしまったのではないでしようか。それだけに世の中は考える様には行かずに行き詰まり、うつ病やこれ等に絡む犯罪が増えているのだと思います。
多分、原始社会やローマ時代まで当りの社会では殆どの物事はこの定理で納まったと考えます。しかし、産業革命から以後、付加価値が増え続け現代に至って定理だけでは納まらない社会になったと考えます。勿論、自然の物理現象も解明が進み、人間が自然に考える思考の殆ど、80%程度はこの通常の社会定理(通念)が納まらない社会成っているのであると見ています。そして、社会通念はこの辺のところまでとし、次ぎは未経験の宇宙通念成るものが生まれて来る事もそろそろ始まる時代へと進むのではないでしょうか。
多分、化石資源を中心とするエネルギー源の枯渇と、中国、インド、ロシアなどの経済成長により鉱物資源の枯渇等の現象から、ソーラーやレザーによる衛星からの太陽熱源の活用と、月世界の鉱物資源の活用対策となる事は明らかですので、これからもどんどんと宇宙社会の新しい定理が生まれて、観念論だけの思考では生きていけないほどになると見ています。
既に現在のソフト科学に付いていけない人が多く成っているのではありませんか。
そこで、その完成社会は特にその中でも女性に影響を与える事になると考えられます。それは女性の生まれながらの「性」(さが、ごう)に大きく影響すると考えます。
前論でも書きました様に、女性は無意識下の深層思考(感情、勘定、妥協)に大きく影響してくると予想しています。
時代進歩の付加価値が増えれば増える程に、「感情」で処理できない現象が増え、「勘定」で数式的に評価が出来ない事態が出来て、「妥協」で処理し切れない始末が出て来ると思えるのです。
つまり、本来のあるべき自然の人間の姿(性善説的)ではない否人間的(性悪説)に近い思考が増えると思えるのです。
言い換えれば、「時代の進歩の付加価値」はある面でこの性善説を壊す事を求められるという事です。
男性にしても、社会の数理、合理、論理の社会の思考が先鋭化して、本来の性(さが:理想、合理、現実)であるにしても究極の思考原理が要求される事から脱落者も増える事と成ろうと考られます。
そして、どの様な社会が生まれるかと言うと、例えば、付加価値に依って”正しい事は正しい”と出来る社会は益々と低下してしまうと思うのです。
むしろ、”正しい事は正しくない事、又は最悪の場合は悪い事”の現象がその社会情勢の変化が先鋭化して評価基準が変わる時代となると考えます。
現代でも、、”正しい事は正しくない事、で処理した方が上手く行く”と言うそれが多く成っているのではありませんか。
少なくとも、精神面の思考では「正しい事は正しくない事」が起こり、「善と悪」の中間的な思考の”正しい事は必ずしも正しくない”という数理性、合理性、論理性の少ない評価基準の社会が出来上がるのではないでしょうか。
このことから、男女の若い者はこの状況に悩み、求めるものとしてキリスト教的な教義に向かうことが考えられ、
|
| | 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| |
 ワード検索
ワード検索