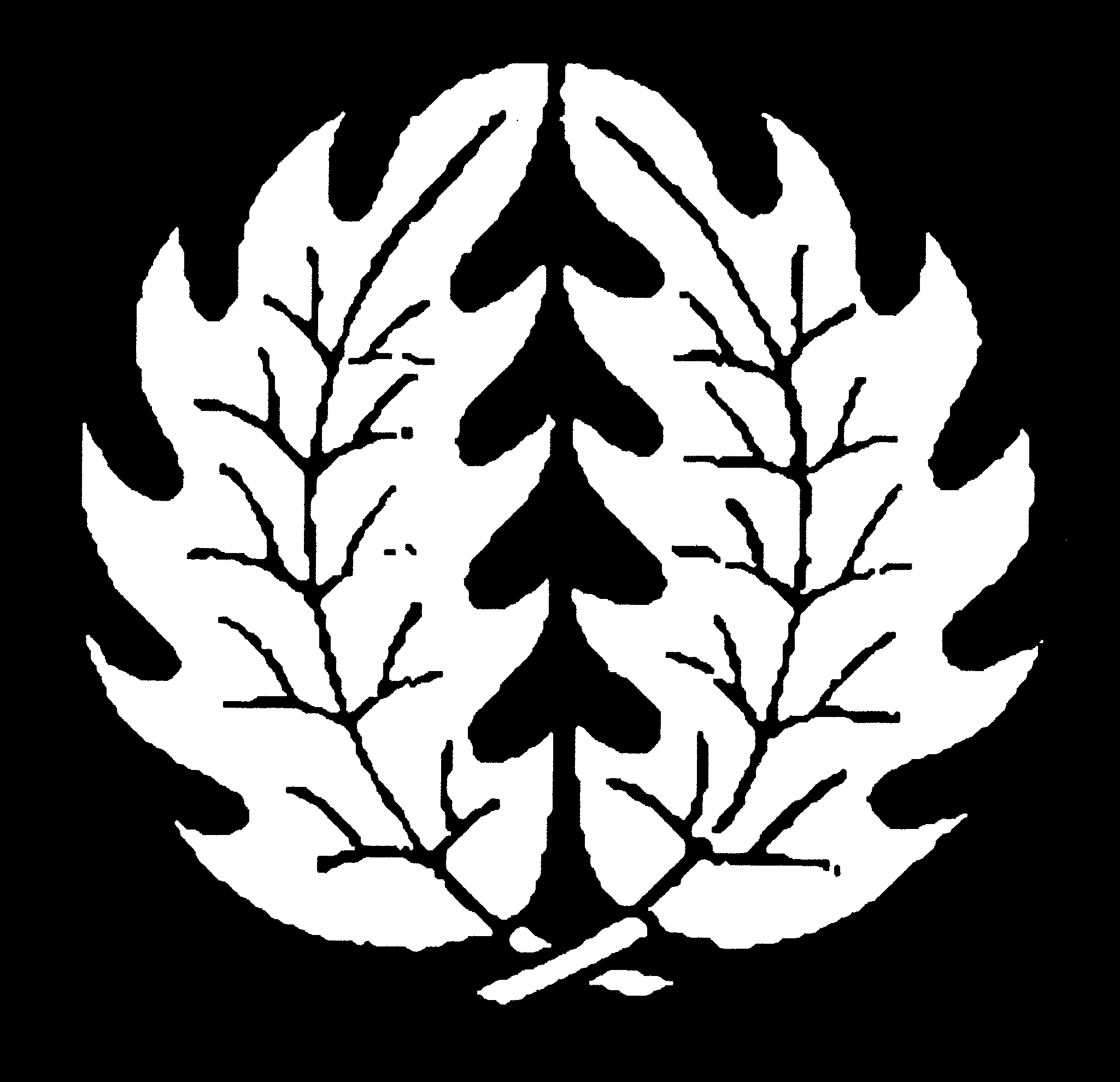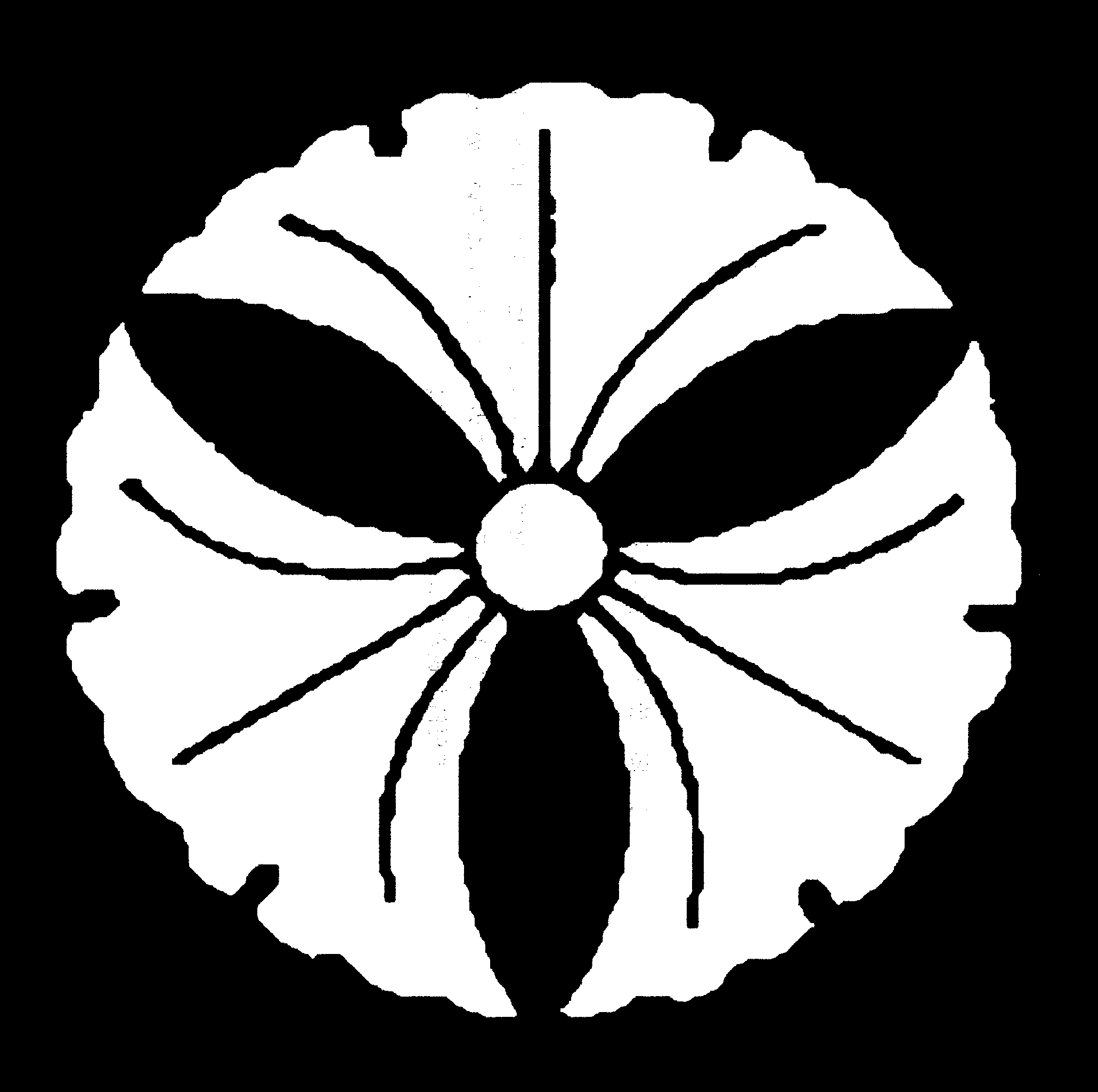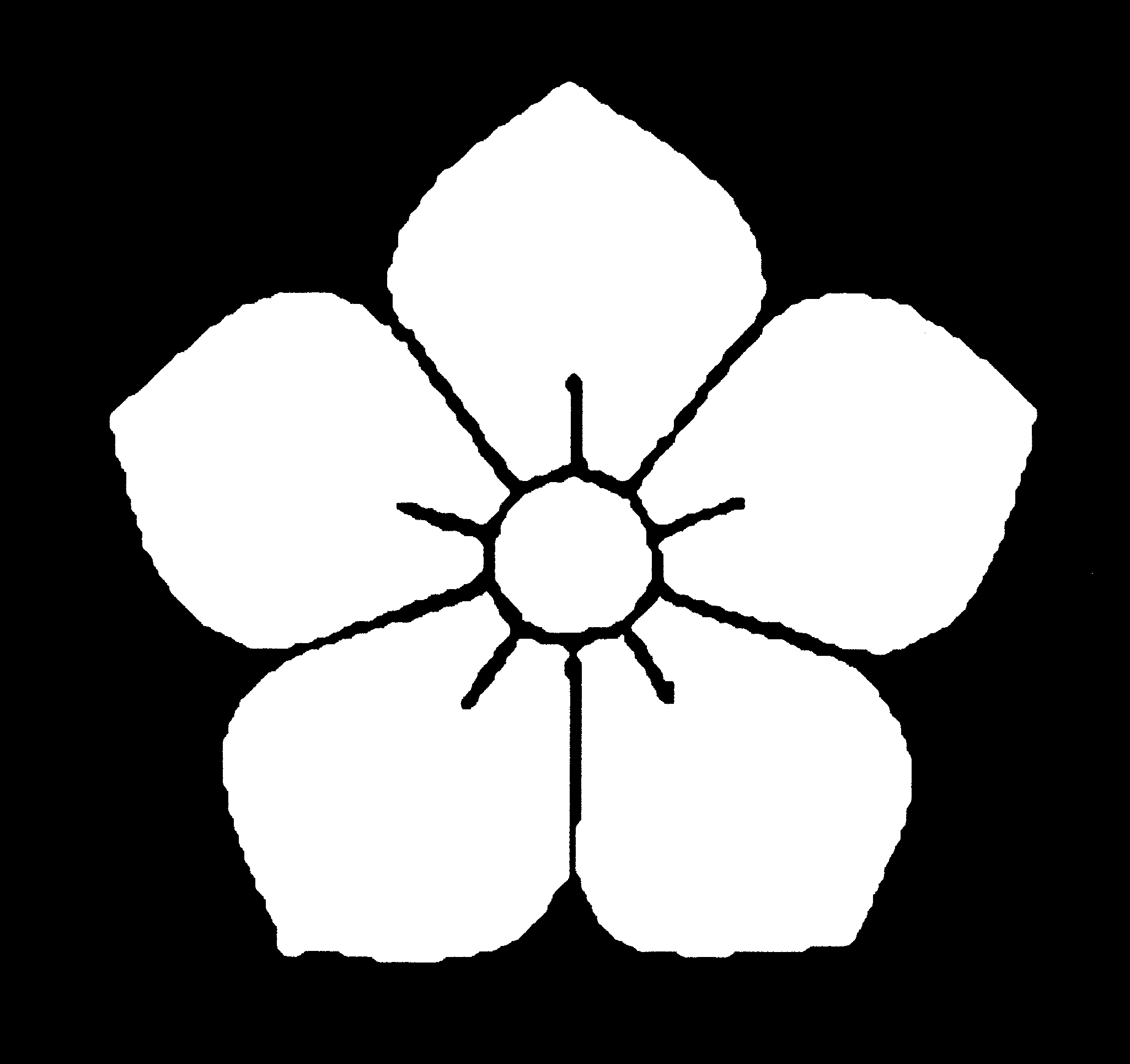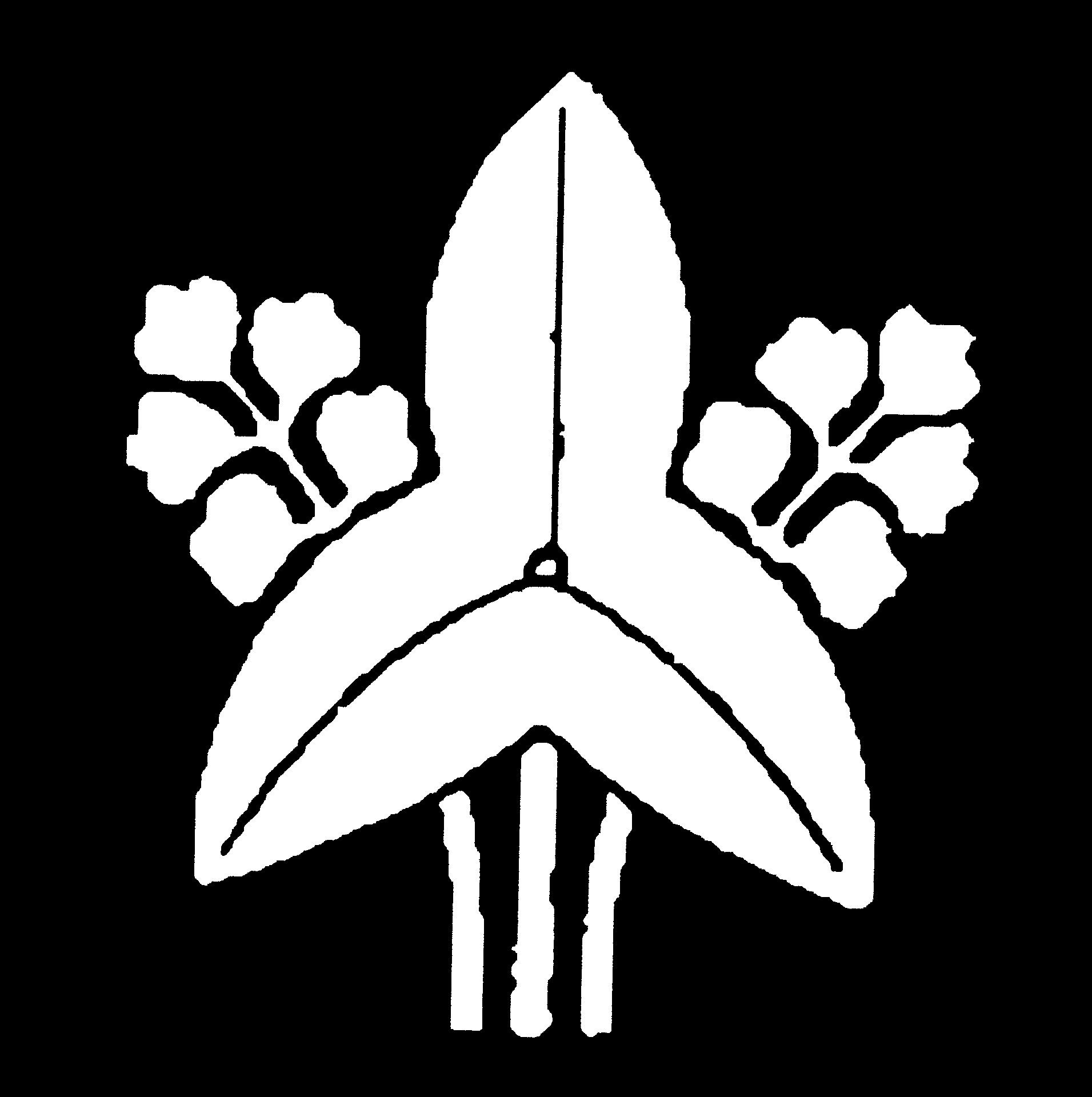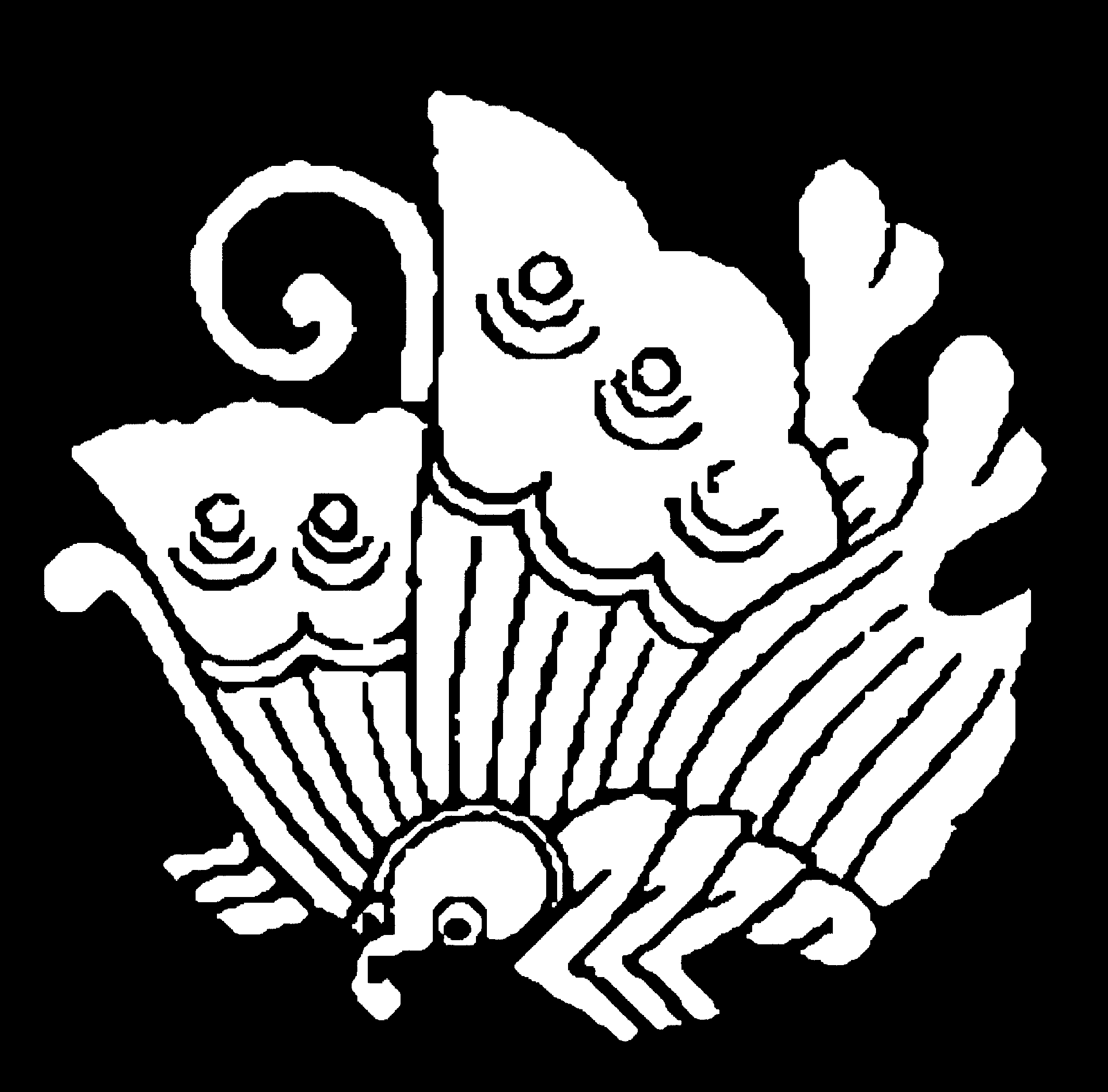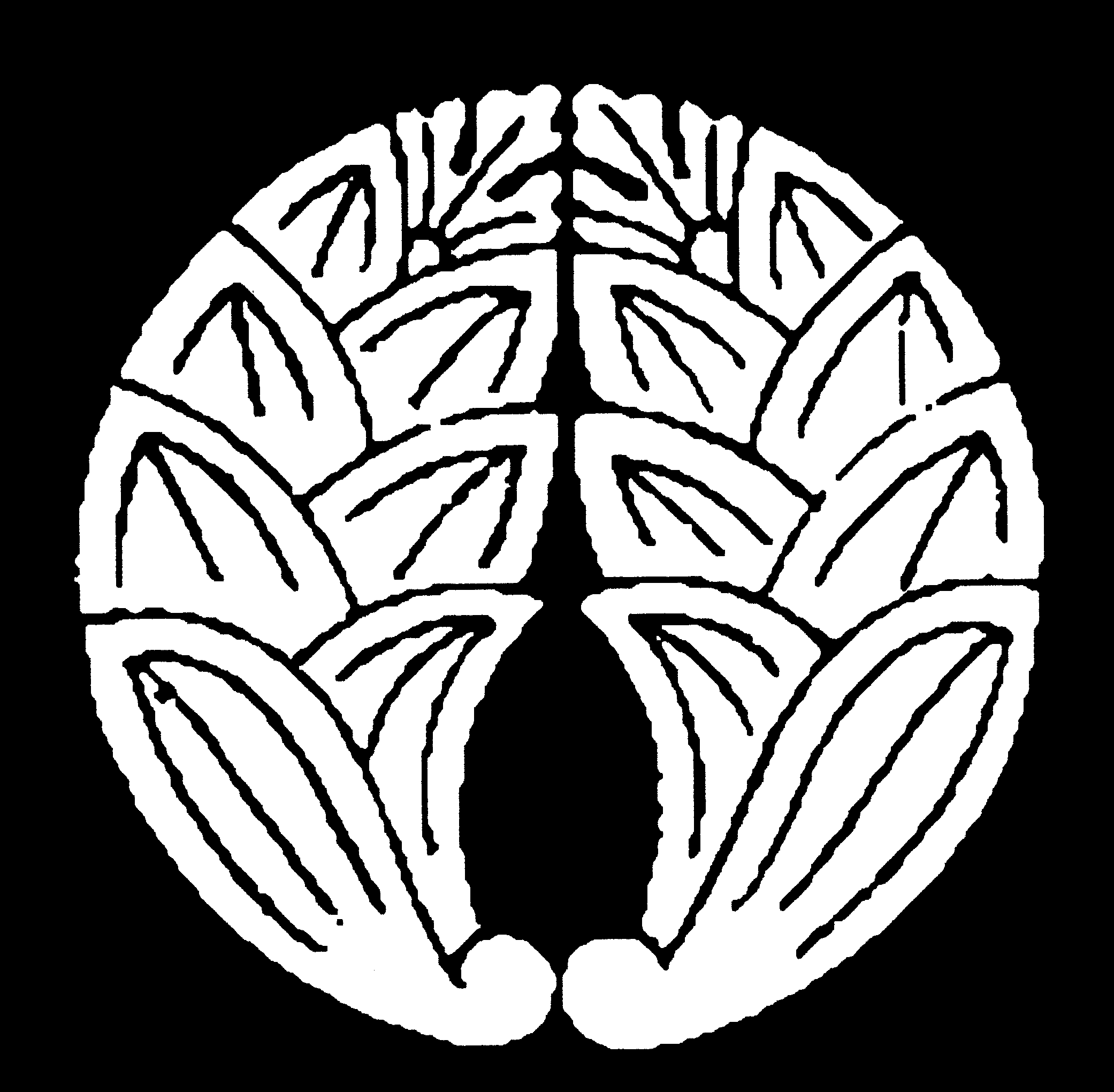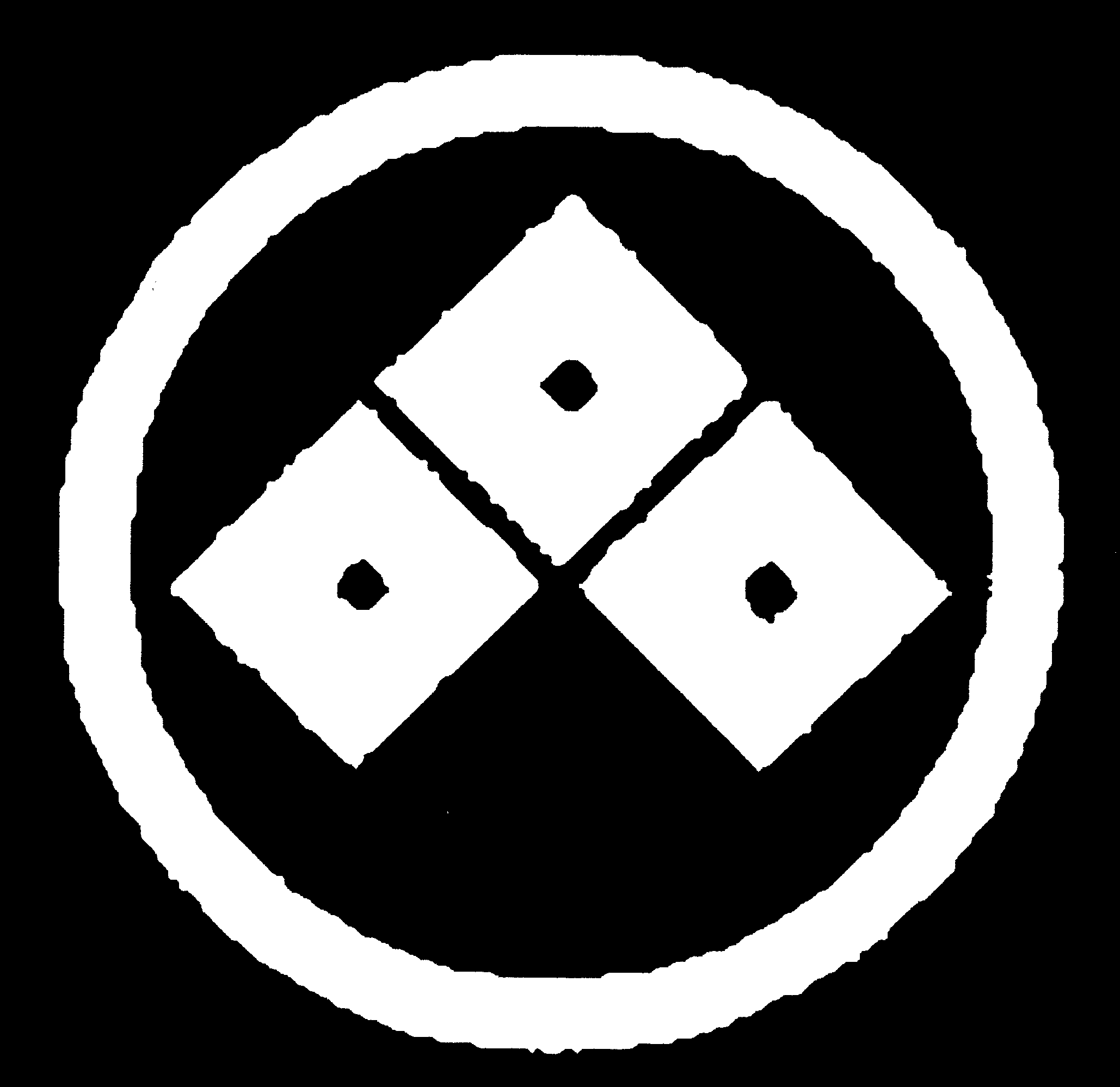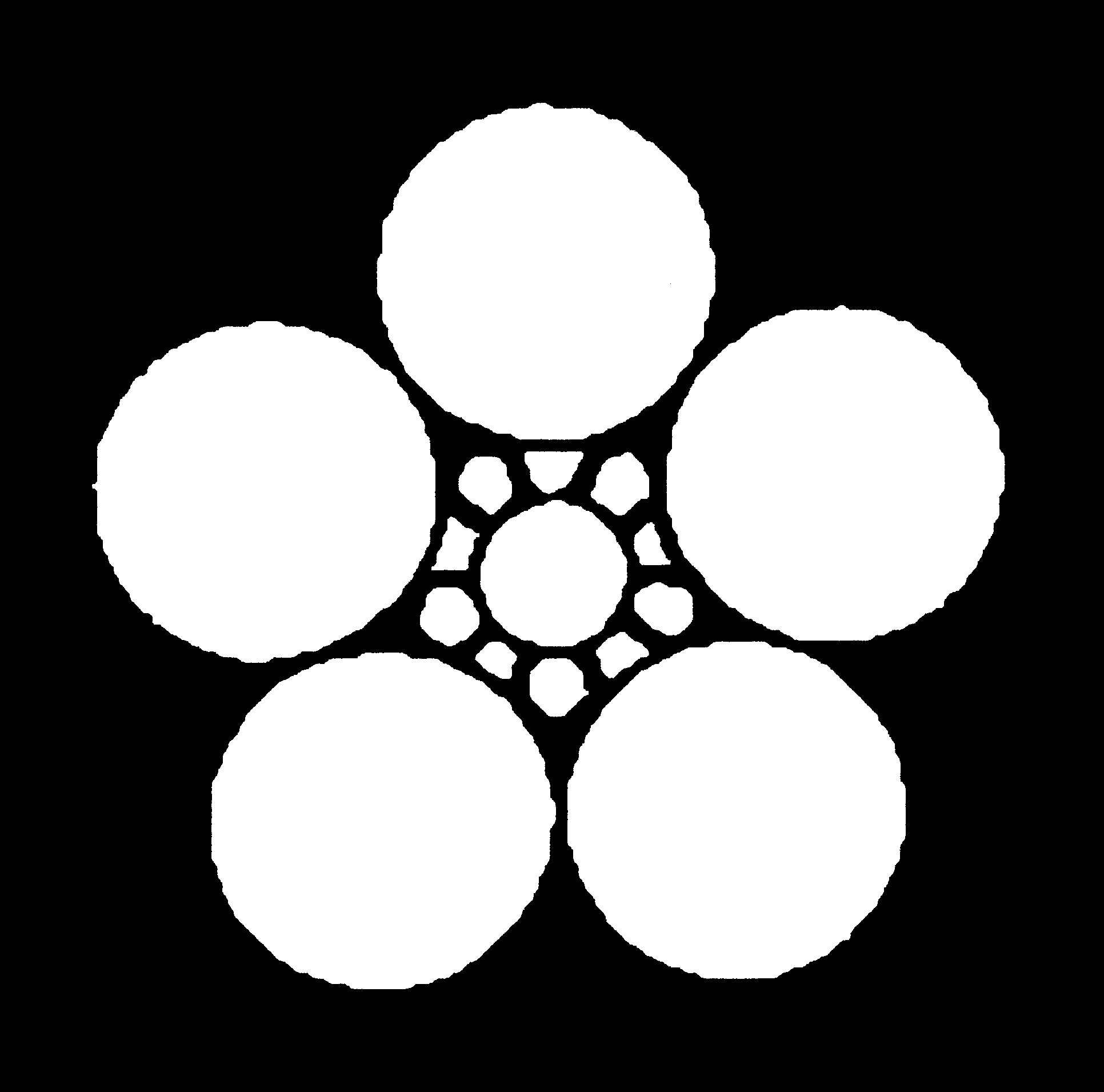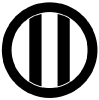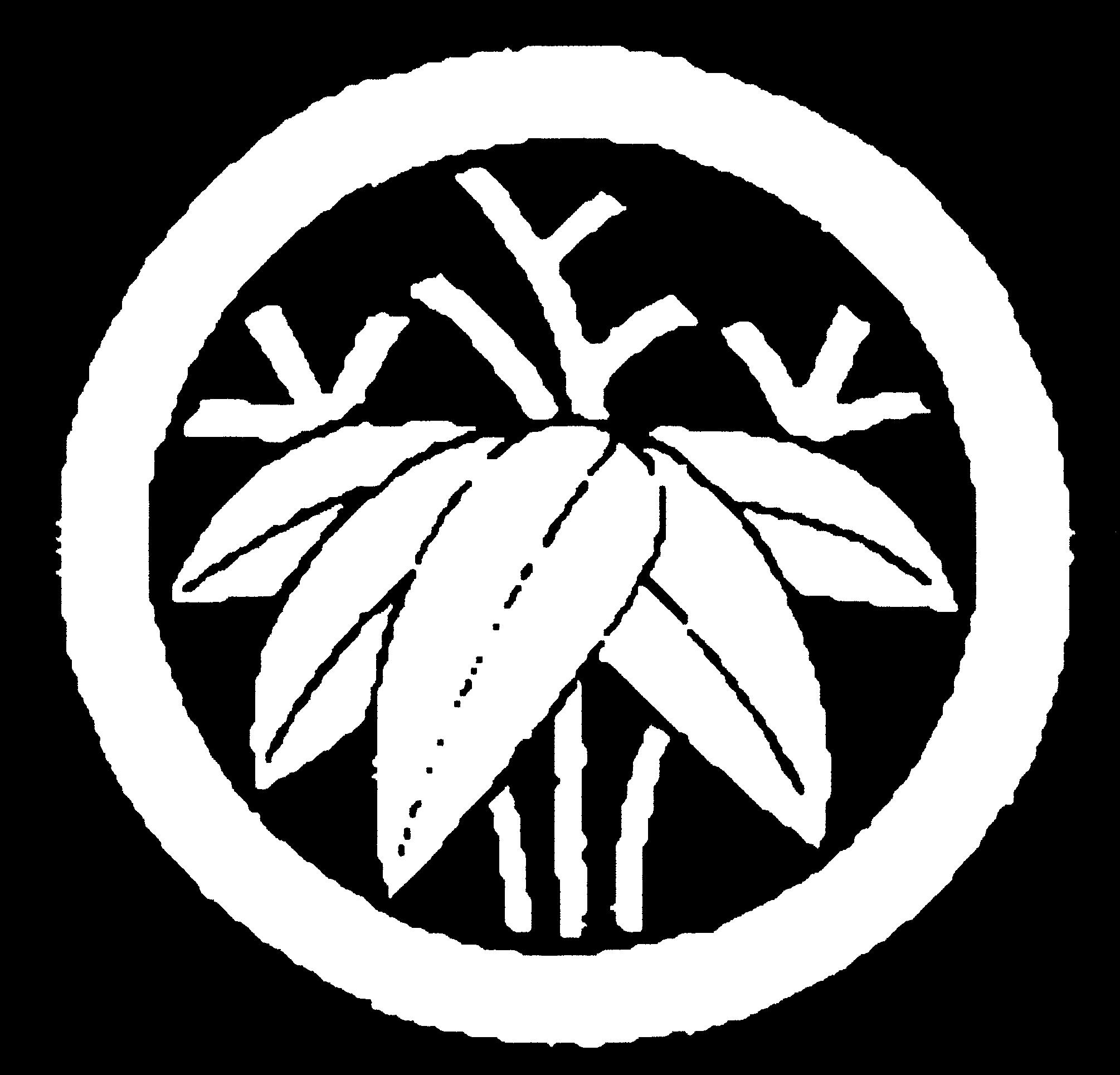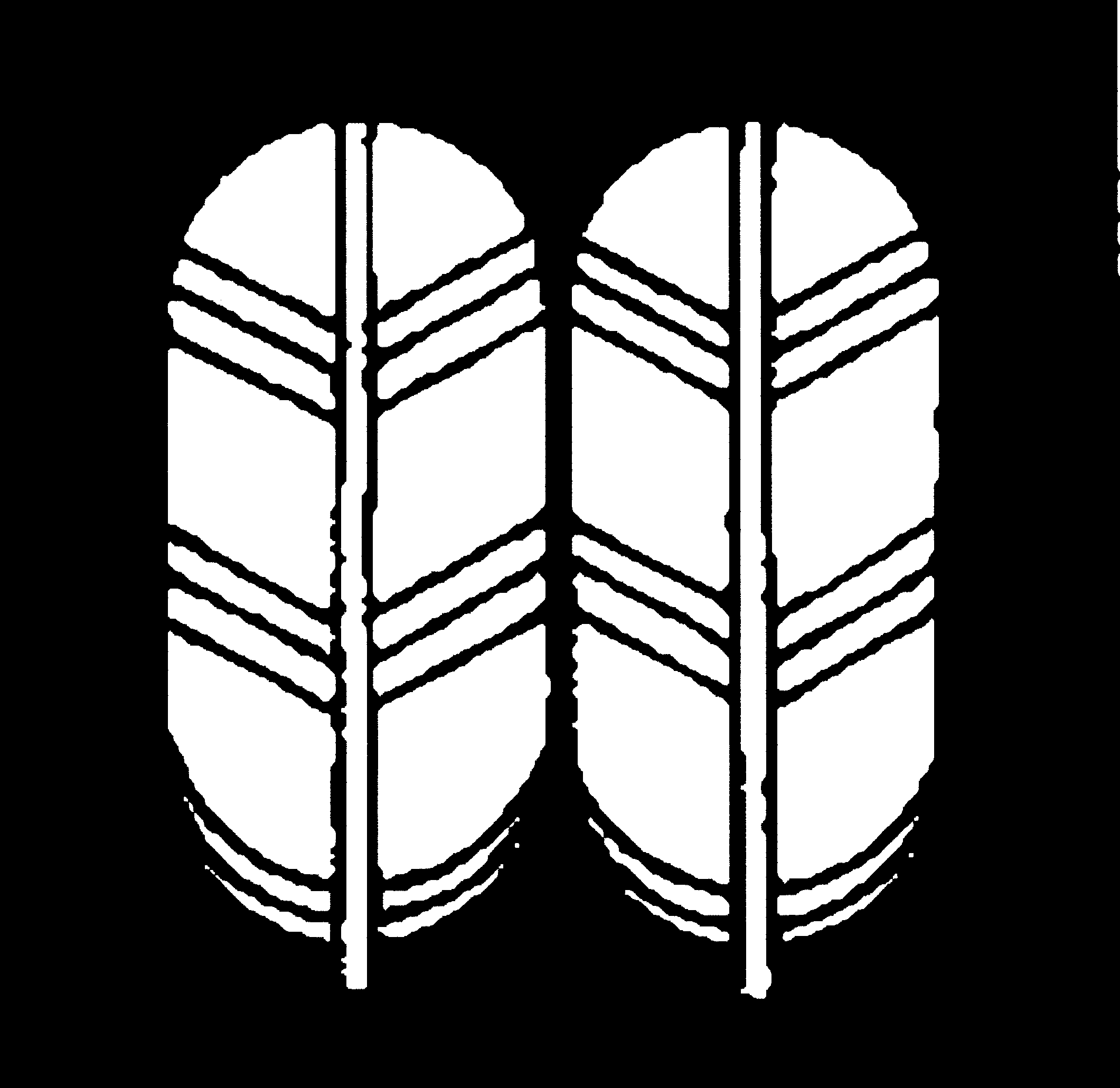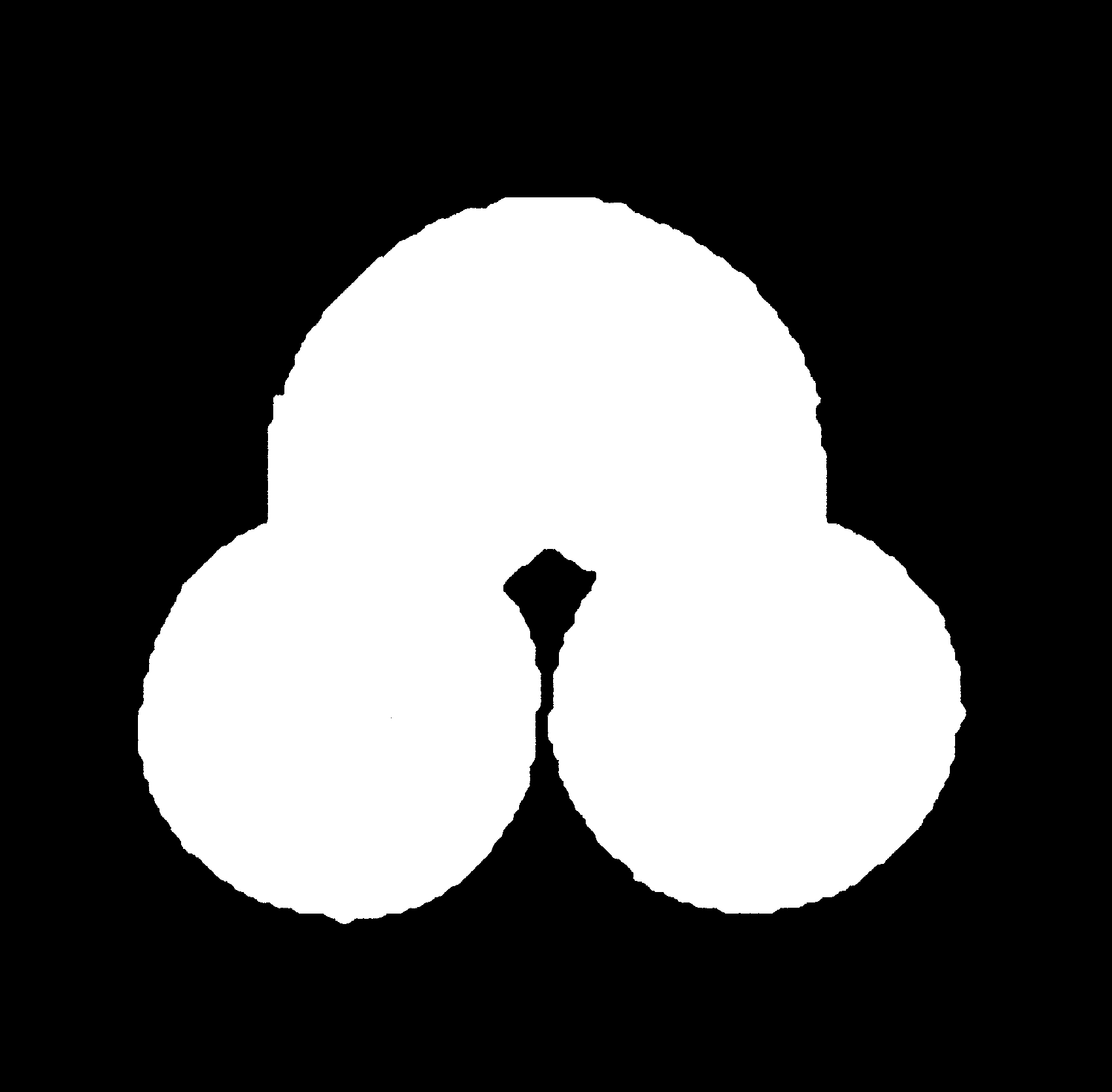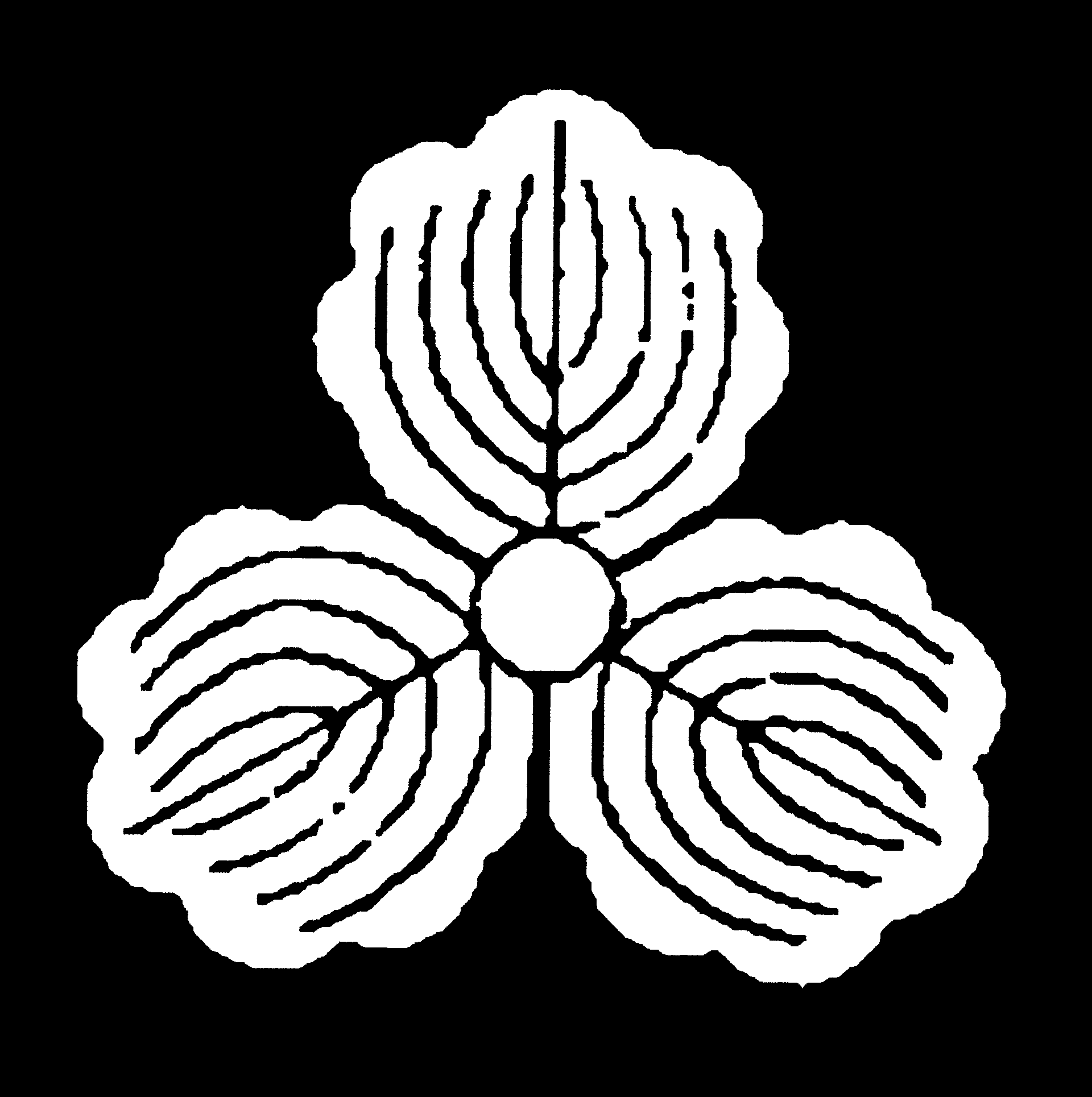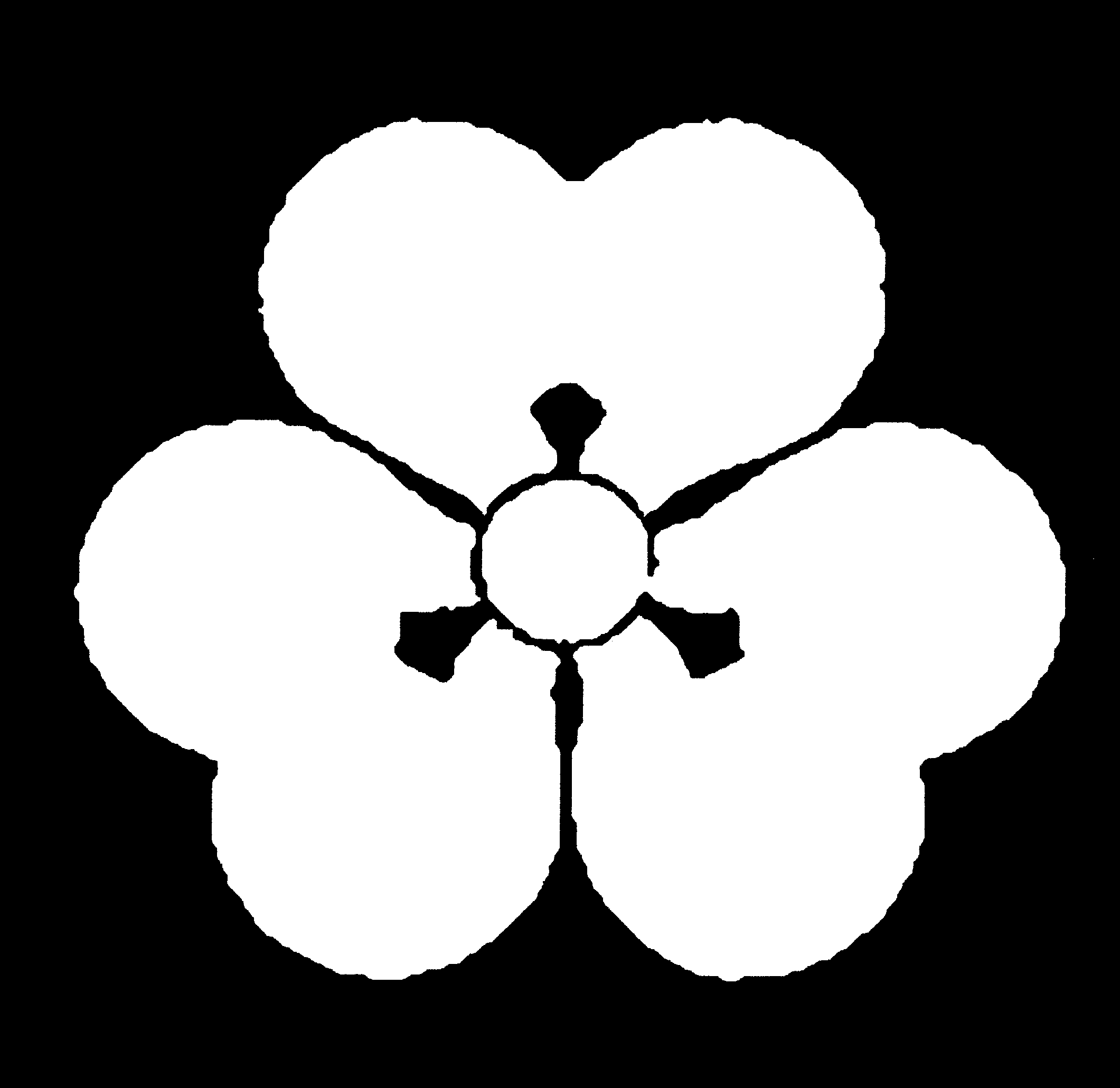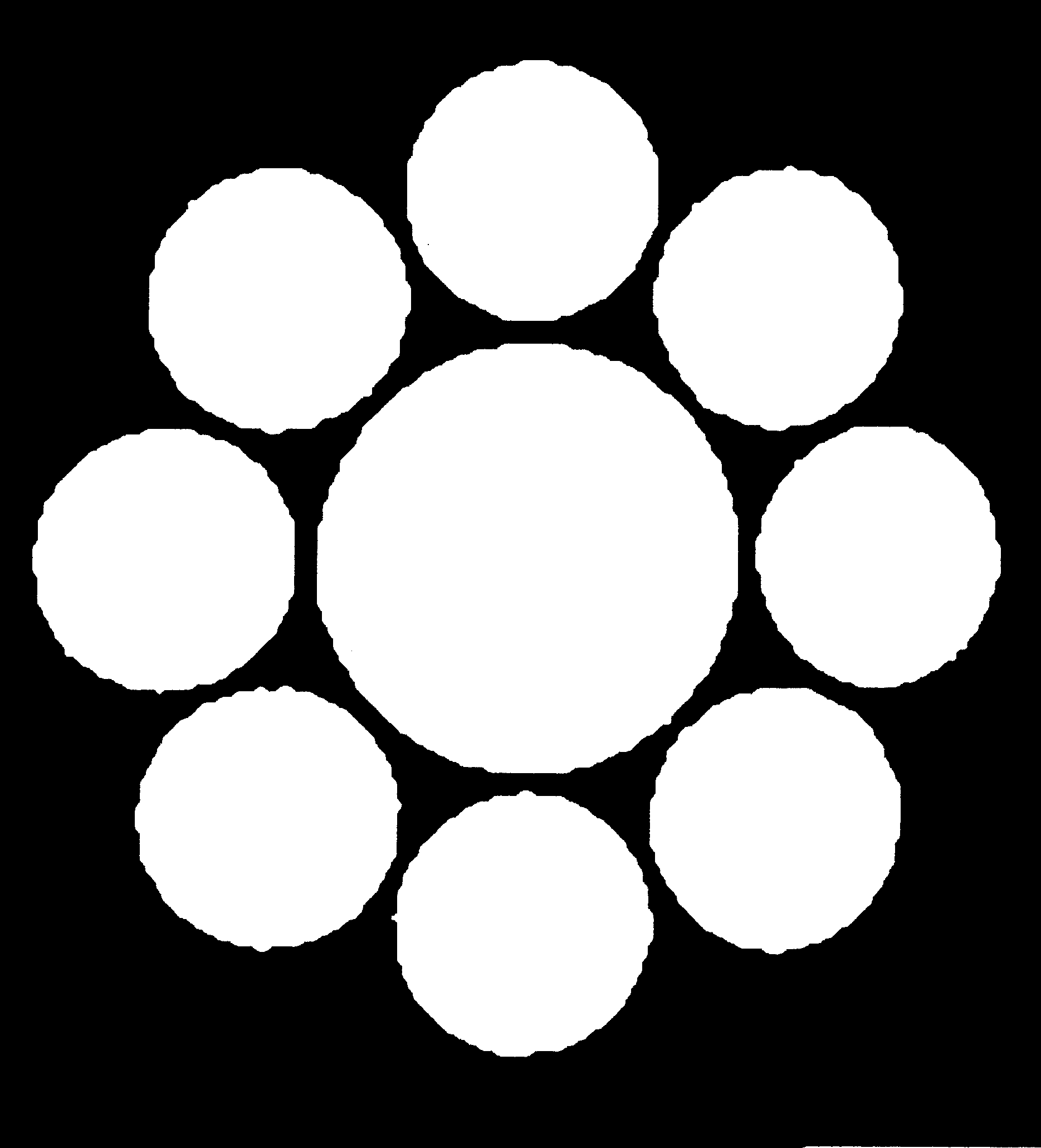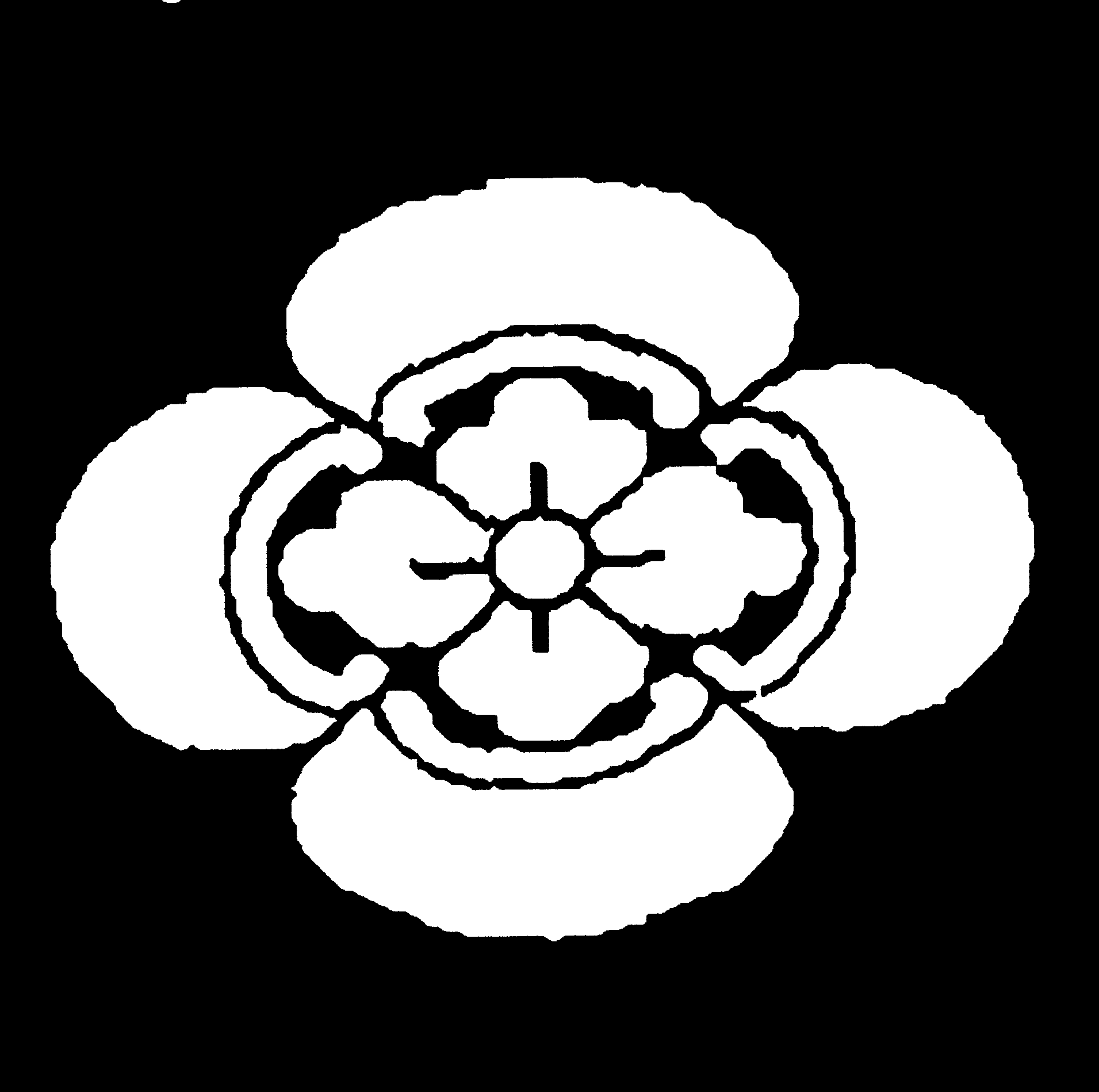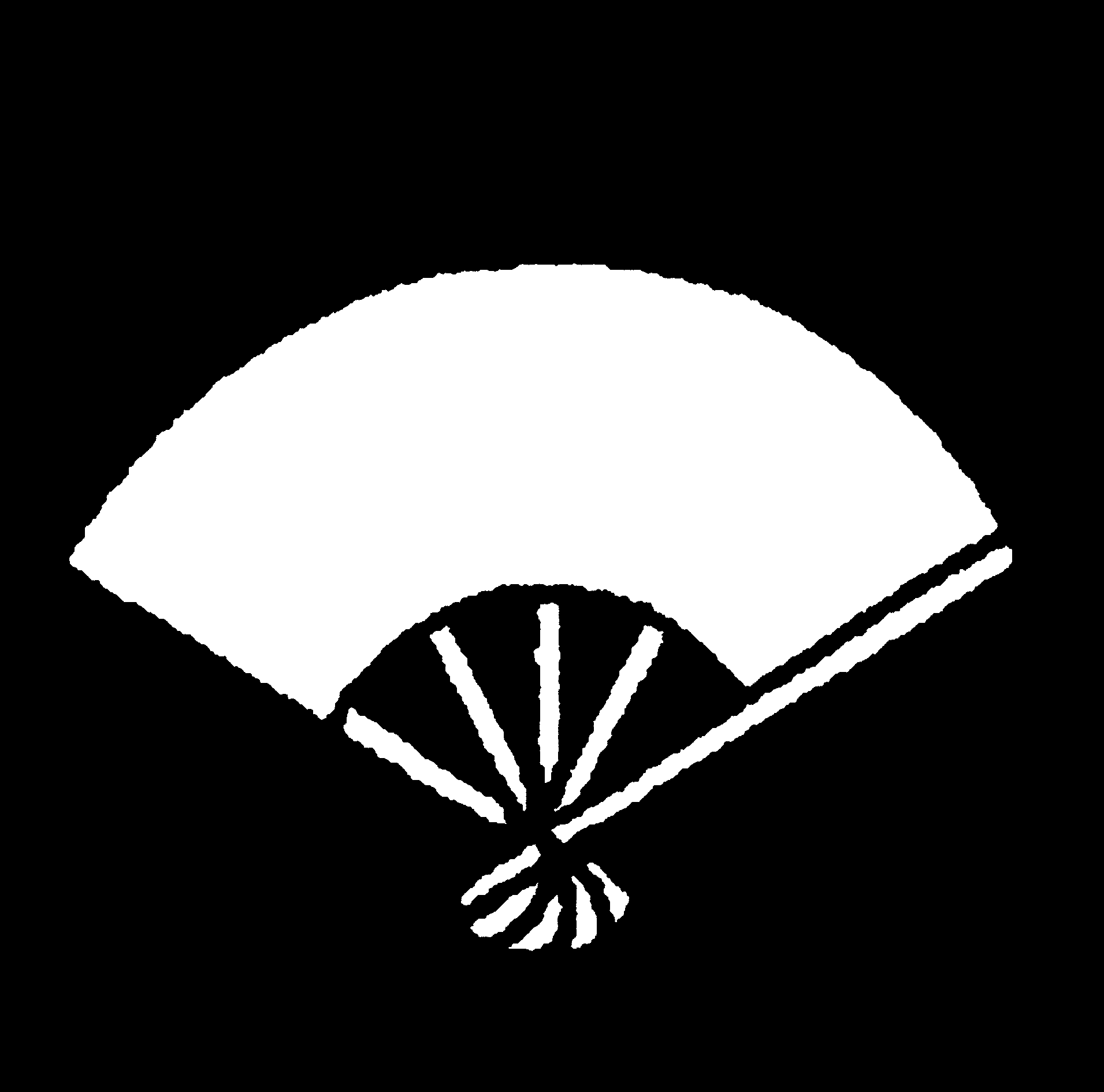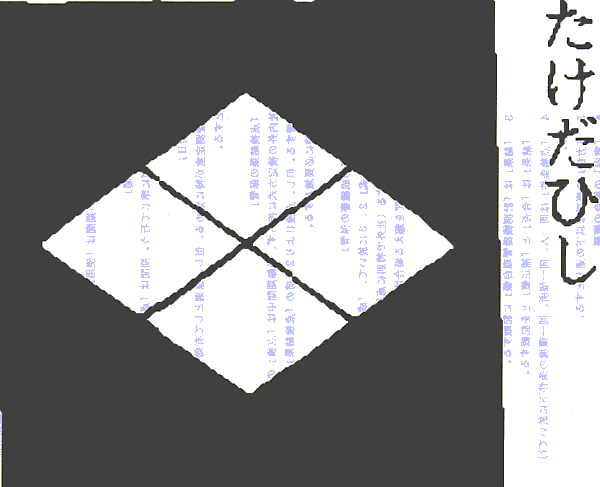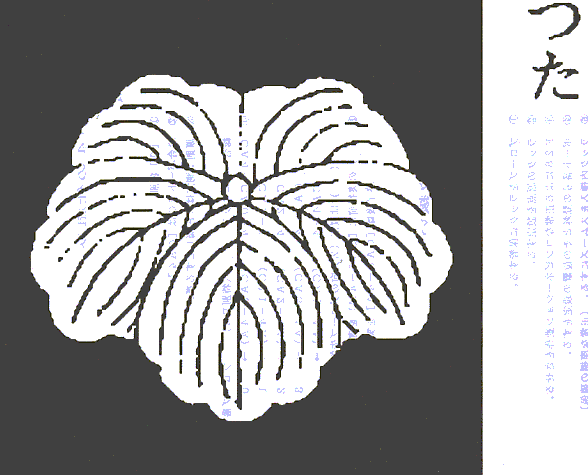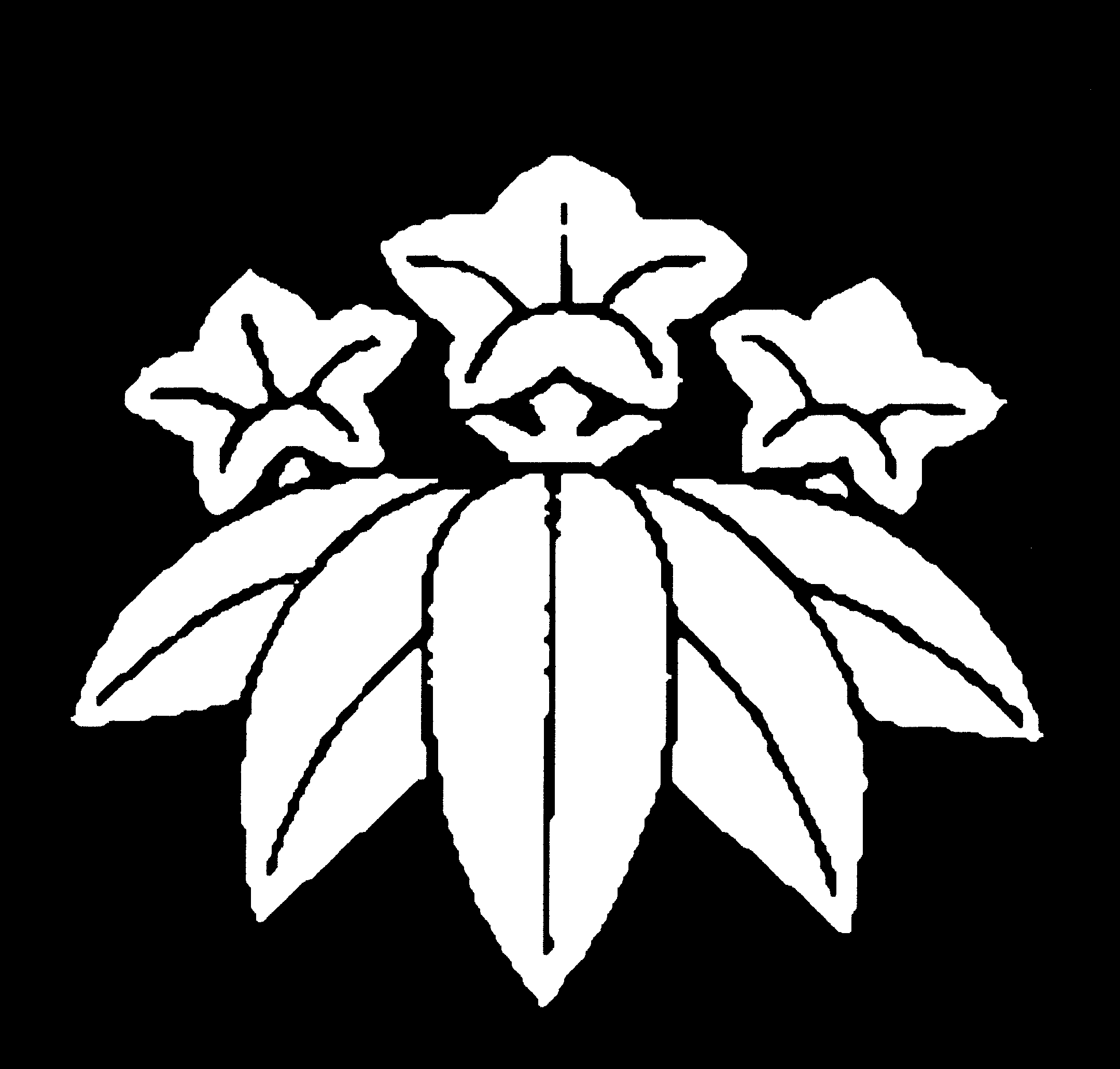このフォームからは投稿できません。
[
ホーム]
[
研究室トップ(ツリー表示)]
[
新規順タイトル表示]
[
新着順記事]
[
留意事項]
[
ワード検索]
[
過去ログ]
[
新規投稿]
[
管理用]
以下は新規投稿順のリスト(投稿記事)表示です。
※記事の投稿者は全て福管理人(副管理人)で、すべての文章ならび画像は福管理人の著作物です。
※この「青木氏氏 研究室」は掲示板形式ですが、閲覧専用で投稿不可となっております。
こちらの掲示板では回答できませんので、もしご質問のある方、さらに詳しく知りたいと言う方、ご自分のルーツを調べたいが、どうしてよいか分からないという方などは
お気軽に青木ルーツ掲示板でお尋ねください。
福管理人[副管理人]より -
青木氏には未だ埋もれた大変多くの歴史的史実があります。これを掘り起こし、研究し、「ご先祖の生き様」を網羅させたいと思います。
そして、それを我等の子孫の「未来の青木氏」にその史実の遺産を遺そうと考えます。
現代医学の遺伝学でも証明されている様に、「現在の自分」は「過去の自分」であり、子孫は「未来の自分」であります。
つまり、「歴史の史実」を求めることは埋もれた「過去、現在、未来」3世の「自分を見つめる事」に成ります。
その簡単な行為が、「先祖に対する尊厳」と強いては「自分への尊厳」と成ります。
この「二つの尊厳」は「青木氏の伝統」と成り、「日本人の心の伝統」に繋がります。
この意味から、青木氏に関する数少ない史料を探求して、その研究結果をこの「青木氏氏 研究室」で「全国の青木さん」に提供したいと考えています。
そして、それを更に個々の青木さんの「ルーツ探求」の基史料としたいと考え、「青木ルーツ掲示板」を設けています。
どうぞ全国の青木さん、その他ルーツ、歴史に興味がある方、お気軽に青木ルーツ掲示板までお便りください。お待ちしております。
※雑談掲示板はこちら、、宣伝・募集ははこちら。
|
 ワード検索 ワード検索 |
- 疑問がある場合やご質問の前に同じ内容の記事が無いか検索してください。
- 複数のキーワードを入力するときはスペースで区切って下さい。
- ページ内だけでの検索は「ページ内検索」をご利用ください。キーワードがハイライトされます。
 最新記事 最新記事 |
藤原秀郷主要5氏と家紋の研究−家紋200選 −1/10
副管理人さん 2008/08/11 (月) 22:02
(藤原秀郷主要5氏と家紋の研究−家紋200選)
史料1
「家紋200選」
藤原秀郷主要5氏との家紋を中心として血縁関係等を理解する上で、この「家紋200選」の事を検証し、考察すしておく必要がある。このレポート全体は青木氏外の氏でも関係する内容となる。
そこで、先ずその意味からも次の内容から入る。
「氏と家紋の経緯」
平安時代から明治初期までに約8000といわれる家紋類の中で隆盛を極めた氏の家紋である。
主に江戸中期までを主体としている家紋類である。
氏の家紋的扱いは、当初、「奈良時代」から始まる。その目的は先ず「瑞祥文様」として使われ、式服や幔幕等の単純な装飾の「文様」して使われていた。
次ぎに、それが進み奈良時代末期では律令の法体系化が起こり「八色の姓制」や「冠位制度」等が定められるに連れて、極めて限られた皇族賜姓青木氏などの一部の高位の身分や家柄の「ステイタス文様」として使用が許される様に成って行った。
この「ステイタス文様」は天皇などから勲功や賜姓をうけた皇族が使うもので、誰でもが使用できる習慣ではなかった。
それが「平安初期」に入り、律令制度が整い、それを実行する皇親政治の天皇と云う権威から「賜物」を受ける事で、天皇家を始めとして皇族や公家や高官の「象徴紋」として使われるように成った。
依然として、皇族、公家、などの特定の身分の「40程度の氏」に対して特別の部分(源氏車等諸道具)などの「判別使用の目的」の為に許されていて、それは自由に使える慣習ではなかったし、一般の者もその必要性は生活習慣の中には無かったものである。
しかし、それが平安中期ごろ皇親政治で「氏家制度」と「律令体制」が完成するに従い、法順が整うにつれて次第に身分を表す「権威紋」と化して来た。
この頃、勲功に対して賜姓が多く発せられる等して、権勢のある者はそれを受けようとしたが、「八色の姓」制度や冠位制度等もありながら、遂には、皇族公家のみならず大豪族等も勝手に氏を名乗るようになり始め、その氏発祥に対して朝廷は危惧を感じて特定の使用を禁じる嵯峨期の禁令の詔を発する程になった。
「判別使用の目的」から徐々に勢力を現す「権威の標」として進み「家紋」の様相を呈するように成り「80程度の氏」が使用した。
しかし、「瑞祥文様」−「ステイタス文様」−「権威の標」とこの状況は進み、平安末期には武士の台頭勢力により、その軍団の武力による「力の象徴」として、「氏の標紋」として使用されるように成った。
しかし、まだこの段階では「200程度」の限られた身分や軍団のものであり、源氏一門、藤原氏一門等の武力集団等の氏で家紋であったし、普通の家臣の上級武士はおろか庶民のものではなかった。
この経緯が、鎌倉期に入り、完全に武士の時代となり、地頭、御家人制度が始まり、武士は家紋の持つ統一された軍団に帰属して、個別の氏の家紋では未だ充分になかったが家紋化が始まった時期でもあった。
挙って、その軍団長の主な公家や上級武士などが使用するよう成り、急激に「800程度」と膨れ上がる事になった。
しかし、ここで必然的に膨張した氏の勢力争いの戦いが激しく起こり、軍団の破壊が起こり、個別化し、夫々の小個別軍団化して家紋を持つ様に成った。
まとめると、この間の経緯は次ぎの様に変化した。
この間、大化改新の国体上の歴史期間は、約550年程度である。
「瑞祥文様」(1:天皇家)−「ステイタス文様」(10:皇族)−「象徴紋」(40:公家:身分)−「権威の標」(80:皇族と賜姓族:政治)−「力の象徴:標紋」(200:侍:武力)−「家紋化」(800:武士:氏家)−*
室町初期から始まった下級武士団の「下克上]で傀儡勢力の「打ちこわし」や、「戦国時代」での「氏の生き残り」の殺戮戦が繰り返される状況となった。
益々細分化の軍団化が起こり家紋は増加する様に見えたが、細分化は当然死滅する憂き目もあり、むしろ、この傾向が逆に起こった。この為に家紋の持ち主が変化して、家紋は細分化したが減少したのである。新しい家紋を持つ軍団(氏の集合体)の再編成化が起こったのである。
逆に、「象徴と権威と武力」を示す家紋を持つ旧大軍団は分裂し衰退した。
「氏と家紋(標紋)」のこれ等の反動と変化は、長期間の戦いに突入し、再び、氏は激減し「400程度以下」に戻ったのである。この時は、まだ上級武士階級の「権威紋」であった。
室町末期では氏や家紋の持たない庶民の「立身出世」が起こり、武士から転進した商人や技能者等の庶民に於いても室町文化の影響を受けて、この時期には多くの転進武士の大豪商が増え、それらが商標として、又一部では「家紋的な標」として持つ様に成った。
それら2つの動きがまた何の制限もなく自ら氏を起し、その「判別と権威」を誇示する行為と出て、「家紋」はもとより軍事「旗印」としての「判別標」的なものとして用いられる様にも成った。
「判別と力と権威」(旗印、判別標:「家紋」)の幾つかの家紋と氏を持つ小軍団が組織化されて、再び大きい軍団の下に集約されて行った。
次第に戦いは安土桃山に入り終結期へと進み、氏は再び爆発的に増えて、何時しか「旗印」から色々な意味合いを持ち、未だ限定的であるが、本格的「家紋」的扱いの方へと重点が移って行った。
これで激減した「家紋や氏」は再び「800から1000程度」にも成った。
この頃より家紋類が「族を表す手段」として意味を持ち、「下克上」「戦国時代」などで衰退した「象徴と権威」の「過去の氏」を引き出して「家柄身分」の意味合いも持たして名乗りだし誇示する様に成った。
そして、安定期に入った江戸時代初期には、各大名の家臣等や下級武士を含む旗本等が挙って自前の家紋を持つ様に成り、本格的な家紋として「2000程度」と爆発的に急激に膨れ上がった。
この時点では江戸初期前から中期以降は、下級武士の家紋みならず、武士が商人に成ったり、郷氏、郷士、豪農に転進する事が頻繁に起こった事から国民のかなりの階級まで「家紋」は広がりを示した。
むしろ、家紋を持たない者は立身出世のみならず、異端児扱いの風潮も起こっていたのである。
意味は大してないが、もつ事に意味があるという風潮が広まり、この傾向は更に明治維新に持ち越されて、明治3年と8年の「苗字令」、「督促令」に基づき全ての国民は苗字をもつ事を「義務」付けられた。この時の風潮に伴ない組織化、統制と目的のない自由な氏と家紋も平行して増えた。この時点では最終「7000から8000」とも言われる程と成った。明治政府は特定の家紋使用の禁令を発したが無視された。
しかしながら、無視はされたが、この時点でその氏や家紋は全く意味を持たなく成り始めたのである。
以上が家紋から考察した「氏の経緯」である。
「家紋・氏の経緯」
この間(1240年)の経緯は次ぎの様に成ります。
(家紋・氏数:種:目的:期)
1・「瑞祥文様」(1:天皇家:単純文様:奈良期)
2−「ステイタス文様」(10:皇族:真人朝臣姓:奈良期末期)
3−「象徴紋」(40:公家:身分冠位:平安初期)
4−「権威の標」(80:皇族と賜姓族:政治:平安中期)
5−「力の象徴(標紋)」(200:侍:武力:平安末期)
6−「家紋化」(800:武士:氏家:鎌倉期)
7−「判別と力と権威」(400:武士と商人:旗印・商標:室町期)
8−「限定家紋」(1000:中級武士と商人:家標:桃山期)
9−「本格家紋」(2000:下級武士と豪農:身分出世の具:江戸期)
10−「紋」(8000:国民:無意味:明治期)
11−「*}(2000:*:*:平成期)
現在は、氏は維持しているが、近代化と人口の低下や核家族化が急激に進み、個別の氏や家紋の必要性は失われて、意味を持たなく成り、慣習は無くなり、意識の中に忘れ去られて「2000程度以下」に戻っているのではないかと考えられる。
しかし、これでも明治初期の人口(4000万程度)からすると、0.02%程度になる。
つまり、一つの氏では平均5000人の集団となる。家紋も同等と考えると、大した集団ではないと考えられるが、江戸初期では、更に数字外の事であっただろう。
それだけに明治初期頃に作られたこの「家紋200選」の持つ意味は格別である。
この家紋200選の選別条件は次ぎ様な事に成る。
選別条件を調べると、家柄などに拘らず、先ず、根底に、”隆盛し子孫を大きく残した氏の家紋”の条件が観える。
次ぎに、象徴的な歴史を残した氏の象徴紋、時の政治を主導した権威紋の条件が出て来る。
象徴や権威に関わらず、時代に一生風靡し名を遺した職能紋も条件として出て来る。
分家の家紋が選択されているのに、本家紋がない、この家紋があるのならこの家紋もある筈だ、この家紋が何故選択されている等の疑問が湧くが、調べてみると、良く「歴史」と「子孫」を遺した事が検証されて納得できる事が観察される。
江戸期と明治初期前は封建社会の最低の仕組みは遺されている時の調べであるから、現在から観ると「疑問」と観えるが理解が出来る。
まあ、8000に対して200(2.5%)であるので、統計的には多少のバイアス(10)は認められる事で頷ける。
分家、家紋があり本家家紋がなければ足して理解してもその信頼度は変化しない事に成る。
歴史を研究する場合には色々な判断に使えるので、この「家紋200選」はその様に理解して利用されたい。
家紋200選(順不同:数字は分類)
1 笹竜胆、丸に笹竜胆、石川竜胆、竜胆車
2 下がり藤、丸に下がり藤、上がり藤、丸に上がり藤、加藤藤、軸付き藤輪
3 桔梗、丸に桔梗、中陰桔梗
4 抱き角、丸に抱き角
5 武田菱(四つ割り菱)
6 橘、丸に橘、丸に三つ足橘、井筒に橘、隅切り角に橘
7 丸に花菱、丸に剣花菱、中陰花菱、丸に三つ割り花菱、四つ花菱、七宝花菱
8 丸に三階菱(三階菱)
9 唐花、中輪に唐花
10 片喰、丸に片喰、剣片喰、丸に剣片喰、四つ片喰、丸に四方剣片喰
11 丸に一つ引き、丸に二つ引き、丸に三つ引き、丸に縦三つ引き
12 木瓜、丸に木瓜、陰木瓜、糸輪に陰木瓜、四方木瓜、丸に四方木瓜、立ち木瓜、剣木瓜、庵木瓜
13 丸に州浜、(州浜)
14 揚羽蝶、丸に揚羽蝶、浮線蝶、向かい蝶
15 立ち沢瀉、向こう花沢瀉、丸に立ち沢瀉、沢瀉に水、抱き沢瀉、中輪に抱き沢瀉、(沢瀉)
16 抱き茗荷、丸に抱き茗荷
17 三つ柏、丸に三つ柏、丸に変わり三つ柏、丸に牧野柏、蔓柏、丸に剣三つ柏、丸に一枚柏
17 丸に並び柏、違い柏、抱き柏、丸に抱き柏、中川柏、三つ追い重ね柏、丸に尻合わせ三つ柏、
17 丸に尻合わせ鬼柏
18 五三の桐、丸に五三の桐
19 鶴の丸、舞鶴、丸に鶴の丸、噛合い向かい鶴、向かい鶴
20 丸に三つ葵、(立ち葵)、丸に変わり花立ち葵
21 蔦、(丸に蔦)、中陰蔦、石持ち地抜き大割蔦
22 木瓜(丸に木瓜)、織田瓜、唐五瓜唐花、五瓜に桔梗、五瓜に丸に三つ引き、五瓜に四つ目、五瓜に立ち沢瀉
23 丸に違い鷹の羽、丸に右重ね違い鷹の羽、中輪に陰違い鷹の羽、阿倍鷹の羽、隅切り違い鷹の羽、丸に並び鷹の羽、亀甲に違い鷹の羽、
24 八つ鷹の羽車
25 梅の花、梅鉢、丸に梅鉢、星梅鉢、陰陽裏梅、剣梅鉢、中陰八重向こう梅
26 丸に雁金、(雁金)、丸に結び雁金、丸に二つ雁金、増山雁金
27 松皮菱、丸に松皮菱、三つ松皮菱、五つ松皮菱
28 丸に三つ星、渡辺星、丸に渡辺星、七つ星、丸に七つ星、九曜、丸に九曜
29 左二つ巴、右二つ巴、左三つ巴、丸に左三つ巴、尾長巴、左金輪巴、右金輪巴
30 丸に違い丁子、左二つ丁子巴、右二つ丁子巴、右に三つ丁子巴、丸に右三つ丁子巴
31 平四つ目、新四つ目、丸に隅立て四つ目、丸に平4つ目、十六目
32 中輪に三つ銀杏、向かい銀杏
33 丸に5本骨扇、丸に日の丸扇、三つ反り扇、丸に並び扇、中輪に地紙、檜扇
34 丸に九枚笹(根笹)、丸に根笹、丸に陰若根笹、仙台笹
35 竹輪笹に向かい雀、丸に竹向かい雀
36 丸に三つ鱗
37 櫛松、丸に左三階松、丸に荒枝付き三階松
38 亀甲花菱、亀甲剣片喰、三つ盛り亀甲に花菱、持ち合い三つ盛亀甲に花角
39 丸に立ち梶の葉
40 月に星
41 八つ鶴車
42 撫子、丸に撫子
43 唐団扇
44 陰源氏車
45 角田
46 並び矢、丸2違い矢
47 桜、丸に桜、三つ割り桜
48 半菊一の手、菊水、菊菱
49 丸に抱き花杏葉、別所鼻杏葉
50 左廻り一つ稲の丸、包み抱き稲、抱き稲、丸に抱き稲
51 丸に角立て井筒、丸に井筒、組井筒
52 石車
53 角立て稲妻
54 丸に輪違い、三つ輪違い
55 蛇の目
56 丸算木
57 丸に並び枡
58 細輪に三つ頭合わせ蛤
59 糸輪に向かい鳩
60 丸に笠
以上「家紋200選」である。
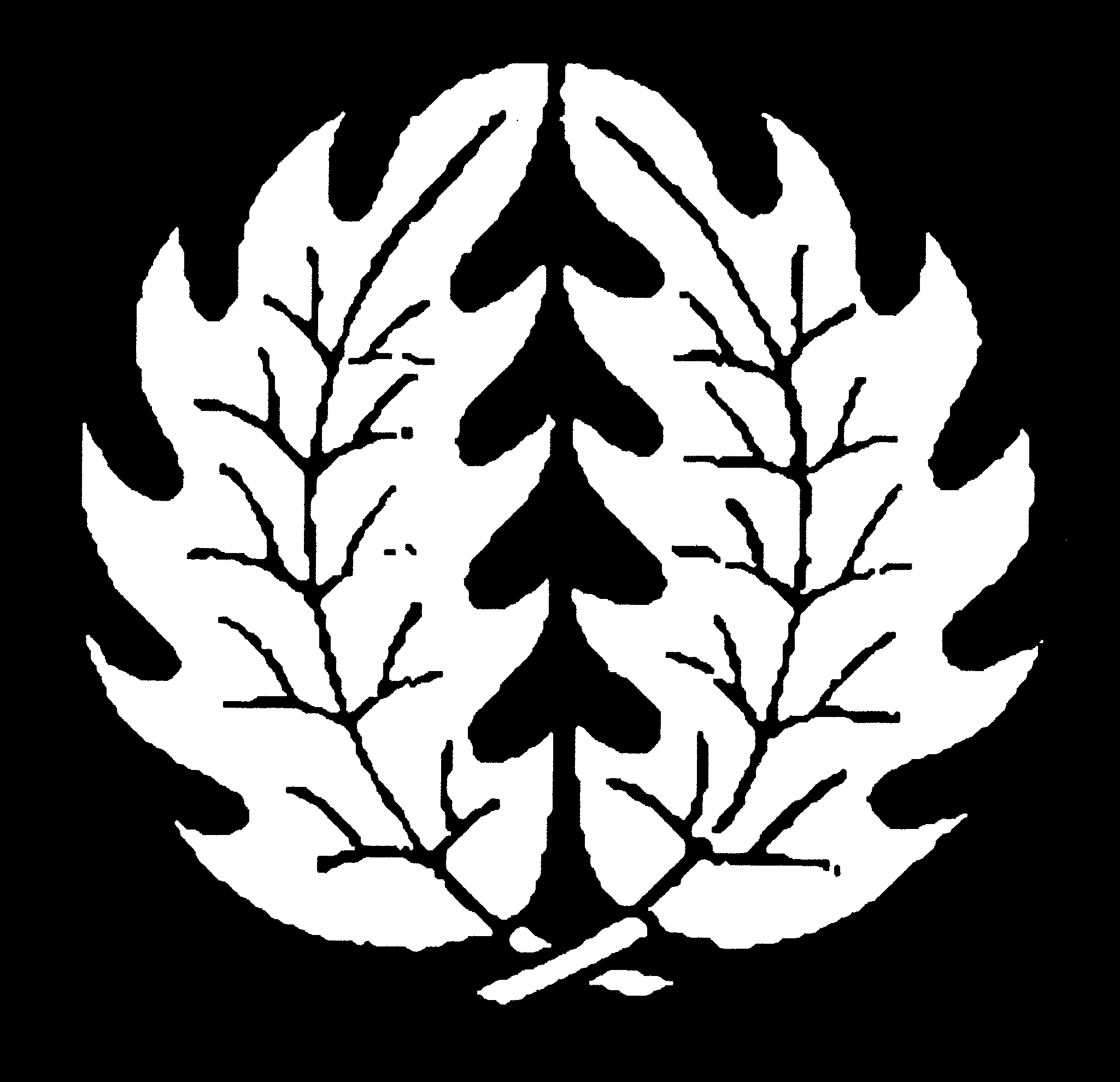
Re: 青木氏と血縁族(家紋)-24(柊紋)
青木研究員 さん 2006/08/31 (木) 23:23
第23/33番目紋様である。
この紋様には全部で40の紋様がある。
この紋様に関わる青木氏の家紋は次ぎの2つである。
第1番目は抱き柊紋である。
第2番目は蔓柊紋である。
この紋様は江戸時代に用いられたものでこの紋様を最初に用いたのは
次ぎの氏である。
下野国の黒羽藩主の大関氏、と近江国の仁正寺藩主の市橋氏である。
他に山本氏、早川氏、林氏がこの家紋を使用している。
特にこの青木氏は大関氏と関係があるもので、この大関氏は武蔵の国の武蔵7党の一つの丹治氏の出であるとされる。
この丹治氏には青木氏が存在する。この青木氏は丹治氏流青木氏である。
丹党はその昔武蔵の国の守護職に任じられた丹治比氏の末裔とされる
この丹治氏は又は丹氏とも云う。
この丹治氏の発祥は、平安中期の左大臣の島が真人族(皇位継承権を持つ第5位皇子までの一族の氏階級 八色の姓制度)となつた。この後この子孫の8代目が武蔵守に任じられている。
第29代宣化天皇(6C前半)の十市王の孫の多治彦王の子供であるとされているが他説もある。
この4代目が丹党と称し後に武蔵7党と成る。
しかし、時代性が合わない。
この丹治氏から分流した青木氏であるとするのは、この左大臣島の子孫とされているので、皇族の者が下俗するときは青木氏を名乗る事に成っていることから、その子孫は青木氏を名乗ったとされる。
しかし、この島は後に朝廷より武蔵の国に配流された史実があり、この時にこの地に住みつき子孫を遺したとされる説もある。後に島は京に戻される。
武蔵の守護説と配流による説とがあるが、武蔵守であるから青木氏を名乗る前提に無い。
配流説が真人族であるが為に史実に基づくものであろうが確定は出来ない。
兎も角も、この島氏の子孫であるとするならば青木氏には異論は無い。
皇族青木氏の一流である。嵯峨期に源氏を賜姓して変名した後に第6位皇子の5家5流の皇族賜姓青木氏とは別の嵯峨期の令による青木氏である。
実質この嵯峨期の令による下俗者や還俗者の青木氏の対象者は17人に及ぶが青木氏を名乗り子孫を遺したのは確認出来る範囲としてこの丹治氏の青木氏だけである。
殆ど、比叡山か門跡寺院などにて僧侶となり末裔を残していない。
この武蔵の国と下野の国とその周辺の国には藤原秀郷流青木氏が存在する。
特に丹治氏の青木氏は同じ藤原秀郷の根拠地の入間郡に住んだとされているが、当時の慣習から見てありえず系譜を作成した時の作者の勘違いではないかと見られる。
この丹治氏青木氏は児玉、秩父、比企、に分布する青木氏であるとみられる。
此処が丹党の土地であると納得できる。
しかし、室町期と江戸期にはこの住み分けは少し壊れている。
鎌倉幕府が樹立してから一族は職と土地を失い多くは離散したので、藤原秀郷一族の鎌倉期以後の住み分けであれば入間郡の存在は考えられる。
この意味で系譜に2つの疑問が残る。
この丹治氏系青木氏が江戸期に同土地の藩主の同丹治氏の系列の大関氏との間で血縁を結んだものとされる。
しかし、この青木氏の家紋に付いては何時に「抱き柊紋」の家紋にしたかは不明で確証が取れない。もとより同紋としていたのかも。
本来ならば「丸付き紋の柊紋」も青木氏の分家として長い間に確実に起こるはずであるが、この丹治氏系青木氏には「丸に柊紋」の家紋の持つ青木氏は無い。1000年間に嫡男だけで分家がなかつたことを意味する。ありえない。
これも疑問の一つである。
賜姓青木ついては「笹竜胆」が綜紋として定められているのであるが、この丹治氏系青木氏は幾つかの家紋類がありどれが綜紋か確証も取れない。
蔓柊紋の青木氏は同土地の者であるがこの丹治氏系青木氏の系列の青木氏で有ると見られるが詳細は不明。江戸期の血縁による氏であろう。
確実なデーターは保持していない。
この柊は葉を図案化したもので葉数で分けられる。
この柊は魔よけの意味を持つものとして珍重された。
堅い木の特長から樫のと同じく昔は武具に使用していた。
又この家紋は家紋掲示板にも投稿します。
|
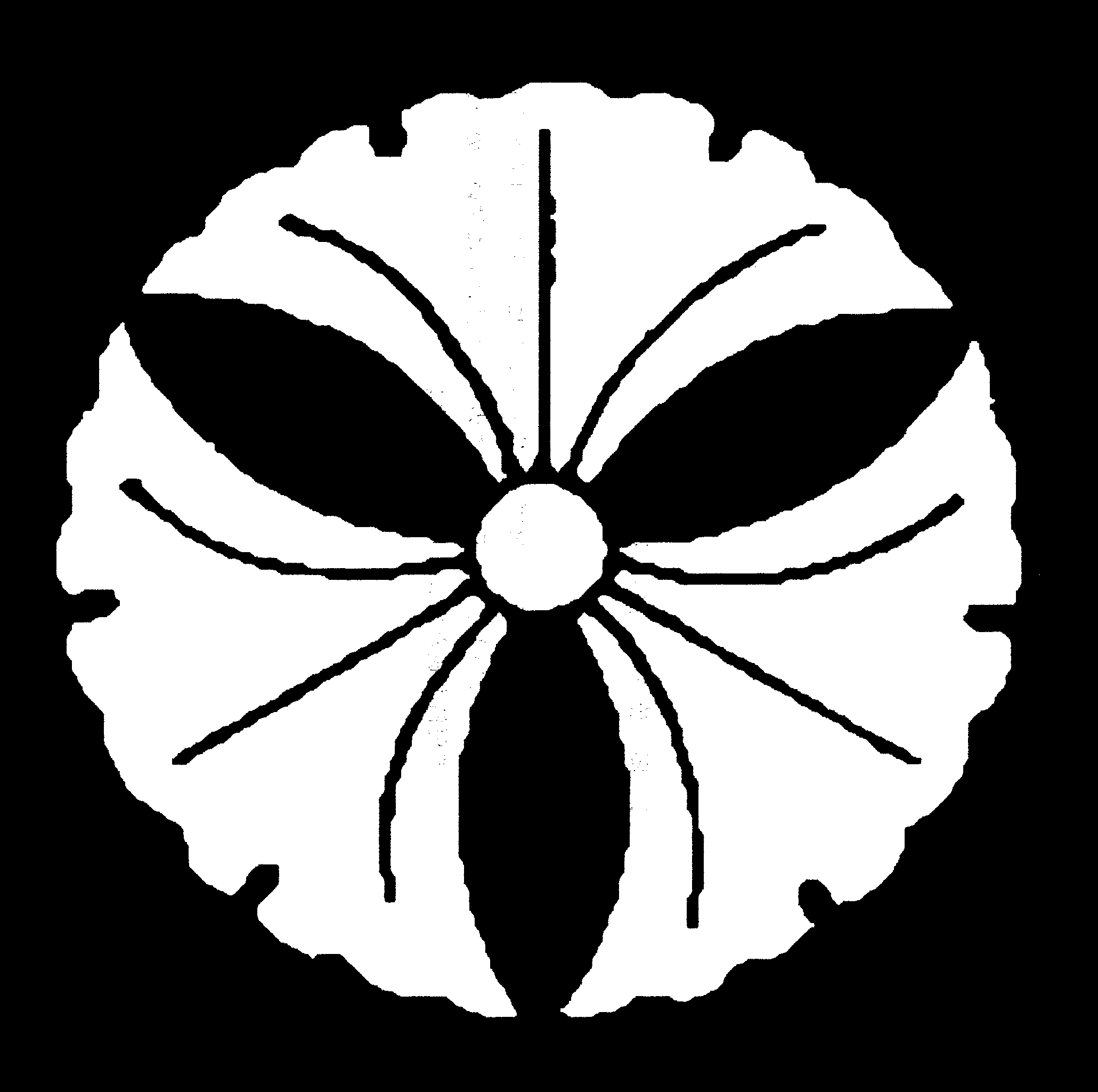
Re: 青木氏と血縁族(家紋)-23(銀杏紋)
青木研究員 さん 2006/08/24 (木) 22:22
この紋様は第22/33番目の紋様である。
この紋様は使用されたのは古く平安末期頃と見られ公家の紋章として用いられている。
しかし、多くは江戸時代に使用されたものである。
この紋様は79の紋様がある。
この家紋に関するものは家紋200選に無い。
家紋200選に無い事は確証するルーツと資料は明らかでない。
この内青木氏に関する家紋は2つである。
第1番目は『三つ銀杏紋』である。
第2番目は『二重亀甲に銀杏紋』である。
この79ある紋様中、この二つの銀杏紋はこの紋様を多く使用している氏から見ると安芸国に見られる紋様である。
因みに、この三つ銀杏紋を使用している氏として、大石氏、土方氏、水島氏、間部氏、長谷部氏等で夫々の氏は中国地方中部から南部にかけて分布する氏である。
忠臣蔵の大石氏、長州の土方氏、水島工業地帯で有名な土豪水島氏、などである。
参考として、間部氏や長谷部氏は下中国後漢の国の末帝献帝の子の阿智使王と孫の阿多倍王が後漢が滅亡して17県民を引き連れて大和の国(九州)に帰化してきたもので、その一団の者である。
その中には職人集団としては定住した一族が陶部氏を中心としてと共に中国地方に上陸して不戦で制圧し大勢力を持つた一団で、この時の職人集団の間部と長谷部氏である。
「二重亀甲に銀杏紋」を使用している氏は中国地方の小豪族の連合体で、亀甲紋紋は出雲大社の神文であり、出雲大社を中心として結束を固めていた氏の集合体である。
広島、岡山地方に多く分布している。
藤原秀郷流青木氏は讃岐地方から移動した氏と近江から移動した氏とがこの一族との血縁をしている。
この三つ銀杏紋の中に青木氏が存在する。
したがって、この紋様を用いられた時期から考えて、藤原秀郷流青木氏の三つの流れからの青木氏と見られる。
しかし、この青木氏の紋様は新しいので確定は出来ない。
先ず、その一つは近江国に赴任した藤原秀郷一門の脩行に護衛役として同行した青木一族で、その後に領国に帰らず安芸の国に移動したとされる藤原秀郷流青木氏が史実として見られる。
次ぎに、讃岐に赴任した藤原秀郷一門(文紀)に同行した青木氏で鎌倉期に領国に帰らず定住して、その後、末裔が瀬戸内海の海向こうの岡山、広島に移動した一族で史実として見られる。
第三として、出雲国に赴任した藤原一門の藤原宗綱に同行した同じく藤原秀郷流青木氏である。
この土地の氏と血縁した藤原秀郷流青木氏であろうと見られるが、いずれもかが混乱期を2度経ているためにルーツの確証できない。どちらにしても藤原秀郷流青木氏の可能性はあるが。
上記した血縁する武士の氏は下級武士であつた事から、発祥などは確証できず不明が多いのである。
そもそも、この紋様は銀杏の葉型が良いことから古くから家具や装飾品に使用されていたものである。
其れが公家の飛鳥氏、あるいは飛鳥井氏の紋章として家族毎に銀杏葉の使用を変えて使用されていた。其れが家紋化したものである。
使用もとは古いが一般に使用され始めたのは江戸期である。
その後に、末裔が不詳と成る江戸期に上記する一族との血縁を結んだと見られる氏である。
|

Re: 青木氏と血縁族(家紋)-22(松紋)
青木研究員 さん 2006/08/09 (水) 10:53
第21/33番目の紋様である。
この紋様は全部で114の紋様がある。
この紋様は家紋200選にある。
この紋様のうち青木氏に関わる紋様は2つである。
この二つは次ぎの通りである。
第1番目は丸に三階松紋である。
第2番目は抱き若松紋である。元は同族で三階松紋の方が宗家となる。
この紋様の丸に三階松紋は次ぎの氏が使用している。
五条氏、岡山氏、宮村氏、石原氏、中川氏、小池氏、中根氏、内山氏、辻氏、前田氏、下島氏である。
讃岐藤原氏と何らかの遠縁による血縁関係にあると見られる。
このいずれかの氏との血縁を結んだ青木氏であり、この青木氏は次ぎの青木氏である。
この紋様の抱き若松紋は次ぎの氏が使用している。
松尾氏である。
この松尾氏と血縁を結んだ藤原秀郷流青木氏である。
北家筋の藤原秀郷氏の本家の末裔が朝廷の命にて讃岐の守護として赴いた際に護衛役として同行した藤原秀郷流青木氏で、この子孫が讃岐の土地の豪族と血縁を結び土地に根付いた一族である。
この一族は一部は領国の武蔵に戻っている。
この一族の3方がこの研究室に投稿されている。
この松紋は最初に使用したのはこの讃岐に赴任し土地に定着した讃岐籐氏と言われる一族である。
(藤原秀郷の宗家の者が讃岐守護となり土地に定着した一門の事)
この讃岐籐氏には次ぎの氏が存在する。
西隆寺氏、豊田氏、柴野氏、平尾氏、有岡氏,竹田氏、成宗氏でこの讃岐籐氏の支流の庶流氏である。
これ等の氏に関係して上記の丸に三階松紋の諸氏が存在すると見られる。
四国讃岐一帯に分布している氏である。
この四国にはもう一つの青木氏が阿波国に存在する。
藤原秀郷の末裔の宗政、時宗親子で、この親子に護衛役として同行した藤原秀郷流青木氏で土地の五瓜に剣片喰紋の青木氏が存在する。
更に、讃岐の青木氏は讃岐の海向こうの岡山と広島に子孫を広げている。
この子孫は3つの氏との血縁を結び更に子孫を広げているが、元はこの讃岐に残存した末裔の藤原秀郷流青木氏で、家紋の綜紋は元は下がり藤紋である。
この宗家は雁紋の副紋使用している。(結び雁金紋)
何れも末裔が男系跡目の継承が出来ずに家紋掟により変紋を余儀無くされた藤原秀郷流青木氏の子孫である。
この紋様は竹と梅と松の慶賀の印のもので、松の常緑樹を祝い常に緑である事を賀して子孫繁栄の印として用いたものである。
調度、器具などにも紋様として用いられている。
特に、この紋様は114もあるのは江戸時代に家紋の持たない者で家を興し武士と成ったものが用いたもので、中には先ず氏を松の姓にして後に松にちなんだ家紋として用いたものが武士では多いのである。
三階松紋にも殆ど見分けの付かない紋様が大まかには9つもある。
しかし、丸つき紋であるがこの丸なし紋の三階松紋は無い。何らかの前頭文字を入れて呼称している。
三階松紋とはこの9つの全体の呼称である。
丸に三階松紋が主要紋である。
若松紋用には4つある。抱き若松紋が主要紋である。
この抱き若松紋に付いては岡山と広島にはこの末裔の亀甲族と血縁した亀甲内若松紋の氏がある。
亀甲族とは三階松紋も血縁を結んでいる。
亀甲族は中国地方の小豪族が神社を中心にして結束して亀甲族一団を形成して生き残りを図ったが結束力が不足して分散したので少ない。
この紋様に関連して、研究室の讃岐の青木さんのレポートも参照して下さい。
この松紋の讃岐の青木氏の紋様を家紋掲示板に掲載します。
|
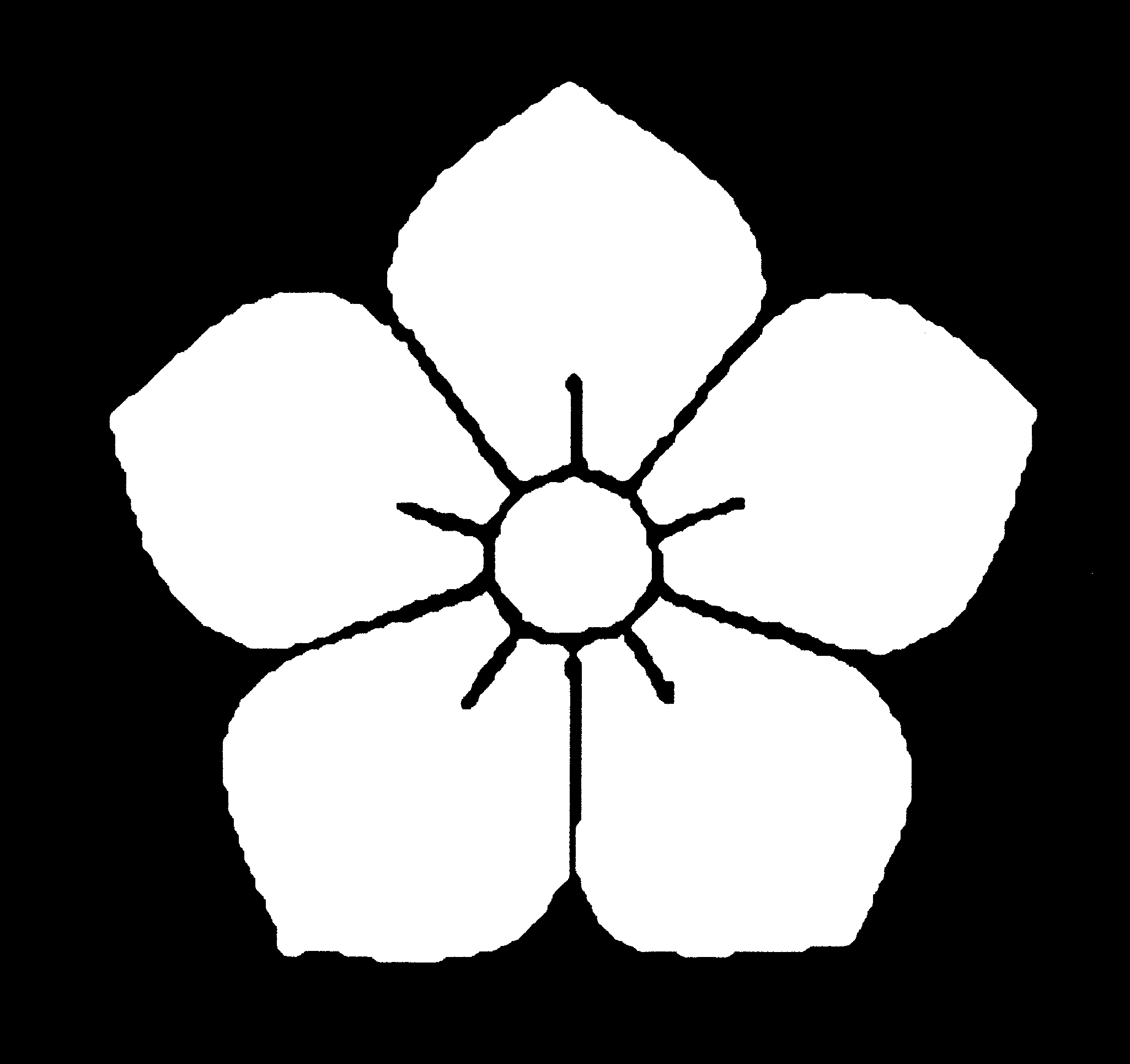
Re: 青木氏と血縁族(家紋)-21(桔梗紋)
青木研究員 さん 2006/07/20 (木) 17:26
第20/33番目の紋様である
この紋様は家紋200選にある。
この紋様は126もの紋様がある。
この紋様の青木氏に関わる紋様は次ぎの2つである。
第1番目は桔梗紋の青木氏である。
第2番目は丸に桔梗紋の青木氏である。 第1番目の分家である。
この家紋を最初に使ったのは美濃の土岐氏である。
その後に江戸初期にこれ等の土岐氏に何らかの関係の持つ者が桔梗紋を変紋して自らの家紋にした結果、126もの紋様が出来た。
この126の家紋は美濃と飛騨などに多く分布している。
皇族賜姓青木氏の5家5流の美濃の賜姓青木氏が土地の豪族土岐氏との血縁にて土岐氏系青木氏が発祥した。
土地の豪族土岐氏は甲斐の武田氏、信濃の足利氏と同様に清和源氏の3代目の三男の頼信より数えて4代目の義光より8代目の時光(1195)から発祥してこの時光から11代目(不祥)の者が皇族賜姓美濃青木氏を継承した。
(義光から19代目)
この一族から末裔は5流に分流した。
(参考) 甲斐の賜姓青木氏は末裔は5流に分流した。
頼信より4代目の義光(1055)から8代目の源光(1195)が甲斐の賜姓青木氏の跡目を継承した。源光の兄弟の時光は武田氏系青木氏を継承し、その時光より15代目の義虎が更に武田氏系青木氏の跡目を引き継ぐ。
(参考) 信濃の賜姓青木氏は末裔は4流に分流した。
頼信より2代目の義康が足利氏の跡目に入る。この義康より3代目の実国が皇族賜姓信濃青木氏の跡目を継承し、頼信より4代目の義光から数えて16代目(不祥)が足利氏系青木氏の跡目に入る。
この皇族賜姓美濃青木氏の5流に分流した中の一族が土岐氏系青木氏である。
この土岐氏系青木氏が桔梗紋である。この桔梗紋から分家が出たものである。
(皇族賜姓青木氏の5家5流は24氏に分流している。近江、伊勢、美濃、信濃、甲斐の賜姓青木氏より分流24氏)
この時期、賜姓の清和源氏は同族の賜姓青木氏の5家5流の跡目を戦略的な意味から固めた。
この桔梗の家紋はもとより桔梗を図案にしたものである。
この家紋で有名なことは信長と明智光秀との軋轢の原因として水色に染めた桔梗紋の問題が出て来る。
信長は平家の支流の流れを汲む一族であるが、光秀の家紋は上記した様に清和源氏の支流の土岐氏の家紋である事をねたんでの事。
家柄で負ける信長のひねくれによるものとされた。
桔梗紋には土岐氏の綜紋の桔梗紋と土岐氏一門の土岐桔梗紋がある。
土岐氏系青木氏は主要紋の桔梗紋である。
桔梗紋を変紋した紋様は余りにも多いのでここでは説明は割愛する。
詳細は研究室の皇族賜姓青木氏のレポート関連を一読ください。
主要紋は左隅に掲示します。
家紋掲示板にも掲載します。
|
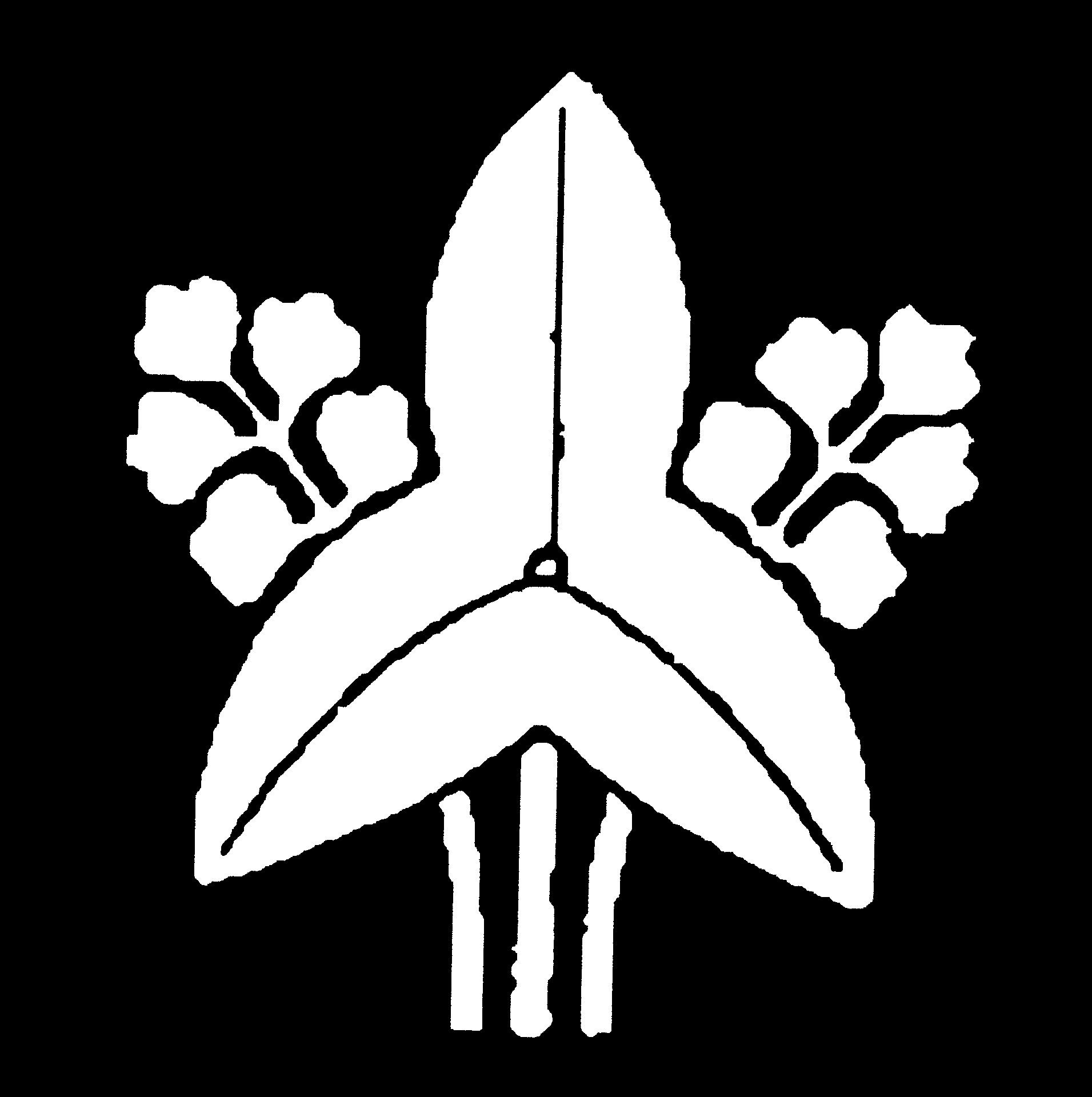
Re: 青木氏と血縁族(家紋)-20(沢瀉紋)
青木研究員 さん 2006/07/05 (水) 14:57
第19/33番目の紋様である。
この紋様は82もの紋様がある。
この内青木氏に関わる紋様は3つの紋様である。
この紋様は家紋200選にある紋様である。
この3つの紋様は次ぎの家紋になる。
第1番目は立ち沢瀉紋である。
第2番目は丸に立ち沢瀉紋である。1番目の分家筋である。
第3番目は抱き沢瀉紋である。
先ずこの立ち沢瀉紋は次ぎの氏に依って使用されている。
松平氏、椎名氏、酒井氏、堀氏、土井氏、稲垣氏、中村氏、水谷氏である。
抱き沢瀉紋は次ぎの通りである。
堀越氏、町野氏、間宮氏、清水氏、蔭山氏である。
この立ち沢瀉紋を見ると明らかに1地域の氏に集中している。其れは全て松平氏の重家臣団である。
同じく抱き沢瀉紋も同様であるが立ち沢瀉紋のように重役氏名ではないが松平氏の家臣団の氏名である。
つまり、元の発祥地域は駿河、尾張、三河地域となる。つまり、徳川幕府の立役者の氏である。
この青木氏となると次ぎの二人が上げられる。
藤原秀郷の子孫で藤原景頼がこの地域の駿河権守に任じられてそれに護衛役として同行した青木氏がありこの地域に定住している。
又、其れより後役として藤原公則が任じられている。此れに護衛役同行した青木氏があり何れも定住している。
藤原秀郷流青木氏が鎌倉幕府樹立で藤原一門共に離散したが、この地域に定住していた青木氏は戦国期に信長と共に勢力を拡大した時期の松平氏に仕官し守り立てた立役者ばかりである。
元は下がり藤紋であったが男系相続が叶わず土地の松平氏の一門と血縁を結び変紋を余儀なくされたものである。
当然、この地域の権守の藤原宗家の一族も仕官したと見られ、そのこの地域の一族の氏名の中に例えば椎名氏などの藤原氏一門の氏名が見つかる。
この家紋は元は平安末期から鎧兜や直垂に用いている。
しかし、この82に及ぶ大半は戦国末期からで江戸期に入って多くの家臣が変紋して使用したものである。比較的新しい家紋類である
この紋は豊臣家臣にも使われている。尾張の出の豊臣秀次の馬標に使用し、秀吉の妻木下家の豊後日出守の家紋でもある。
又、福島正則も家紋としている。
何故この地域のものが沢瀉紋を使用したのかと言うことであるが、この地域の水辺にはこの沢瀉草が群生していたことから使用したと見られる。
殆どの82の紋様の氏はこの地域の一族である。
この沢瀉紋となった藤原秀郷流青木氏は主要9氏のどの氏から出ているのかは確定は出来ないが、この赴任した藤原秀郷の宗家の二人の位置付けから見て直流4氏の青木氏から出た116氏の内の一つの一族と見られる。
丸に立ち沢瀉紋は当然に立ち沢瀉紋の分家筋になるのでこの一族も末裔を広げていた事がわかる。
又抱き沢瀉紋の一族はその家紋を使用している一族の氏名から中級家臣である。この地族と血縁した青木氏は立ち沢瀉紋青木氏の分家に当る一族ではと思われる。
この立ち沢瀉紋は82の沢瀉紋の主要氏であるので、先ず藤原秀郷流青木氏のこの地に定住した本家筋が主要氏である一族(13)の立ち沢瀉紋の主家と血縁を結んだ事となり、更に分家筋が抱き沢瀉紋と血縁したと見られる。しかし、この抱き沢瀉紋も抱き沢瀉紋の16中では主要氏であり、82の沢瀉紋のなかでも立ち沢瀉紋に継ぐ位置にある。
藤原秀郷流青木氏は強かにこの地域に根付き、末の勢力拡大を見て徳川氏を盛り守り立ててその末は幕府の権限を握った重家臣団の一族の一つに成っていた事になる。
小豪族であつた松平氏は武田軍団と諏訪族の軍団を家臣団に加えただけではなく土地に明るい藤原一族おも家臣団にしていたことを考えると天下取りの徳川勢力は多きかった事が頷ける。
だから、下から成り上がった者の家臣団だけではなく最も古い歴史と高い伝統のある諏訪族青木氏を含む赤兜の諏訪青木武田軍団と、歴史と伝統と各地に広がる藤原秀郷一門のある藤原秀郷流青木氏の軍団のおかげが後には幕府を開いた原因とも言える。
このように見ると皇族賜姓青木氏と同じ藤原の血筋を持つ藤原秀郷流青木氏一族は合同で天下を取り戻したとも考えられ強かである事に感心する。
両青木氏が持つ伝統とは、無意味な物ではなく歴史をこのように見ると大変重要である。そして、其れは一青木氏ではなく各地に散在した一族の末裔がいざ戦いの時にあつまりその力を発揮した事を物語るものである。
左隅に主要家紋を掲示します。
家紋掲示板にも近日3つの家紋を掲示します。
|

Re: 青木氏と血縁族(家紋)-19(矢紋)
青木研究員 さん 2006/06/25 (日) 15:24
第18番目の紋様の矢紋である。
この紋様は全部で36ある。
家紋200選にある紋様である。
この内、青木氏にかかわる紋様は次ぎの2つである。
第1番目は丸に違い矢紋である。違いや紋の分家である。
第2番目は丸に六つ矢車紋である。
これらの紋様は比較的新しい紋様である。
この紋様は勿論弓矢の紋様を家紋としたものであるが家紋に対しての氏が明確に確定できないほどに成っている。
判る範囲では主に矢部氏とか、矢田部氏とか、矢吹氏とか、矢葺氏とか矢田堀氏とかである。橋爪氏や橋詰氏のように爪のついた氏もこの矢の家紋を用いているので殆どはこの職人集団の姓である事からこの末裔と見られる。
この一族は「部」が付いているので元は後漢の渡来系の人々で弓矢を作る技能集団として奈良期に帰化してきた一団の末裔であるとみられる。
他には有名なところでは3つ矢紋の松平一族の松平深溝氏で、矢車紋の荒川氏、違い矢紋の恒岡氏である。職人集団の居た地名を採った氏と見られるが、この一族紋の矢紋は武士の紋所として扱われているので室町末期に武士となった紋であろう。
これ等の氏の情報が少なくてこの青木氏は何れの青木氏に属するかは確定は出来ない。
しかし、皇族賜姓青木氏5家5流の24氏の可能性は低い。
この青木氏では地域性や系統は全て確立していてそれ以外に子孫を残す謂れが嵯峨期の詔にてない。
又藤原秀郷氏の主要9氏の116氏に関わる青木氏としての断定もできないが、別の研究資料説によると藤原秀郷流青木氏の116氏の中に組み入れる説もある。しかし、その理由はない。
藤原秀郷流青木氏との何らかの関係を持った事から室町末期から江戸初期前に後に出世した時に関係族のあった血筋の青木氏を名乗ったと見る向きが強い。
藤原秀郷の一族が赴任した24地方のところに定住した青木氏としても地方性が確認出来ないので困難であり、各地の矢の着いた姓を調査しても出ない。
多分この原因は江戸初期が室町後期に氏として名乗り出したものではないかと見られる。
多くは矢のついた氏を名乗っているところから見て、先祖の職業は矢や弓に関係する職人であった事からルーツとしては江戸初期の安定期になったころにいずれかの青木氏が男系不継によりこの矢のつく氏との血縁にて家紋としたと見られるが確証は取れない。
明治の第3の青木氏や室町期の混乱期での第3の青木氏である可能性も否定出来ない。
家紋掲示板にも掲載します。
|
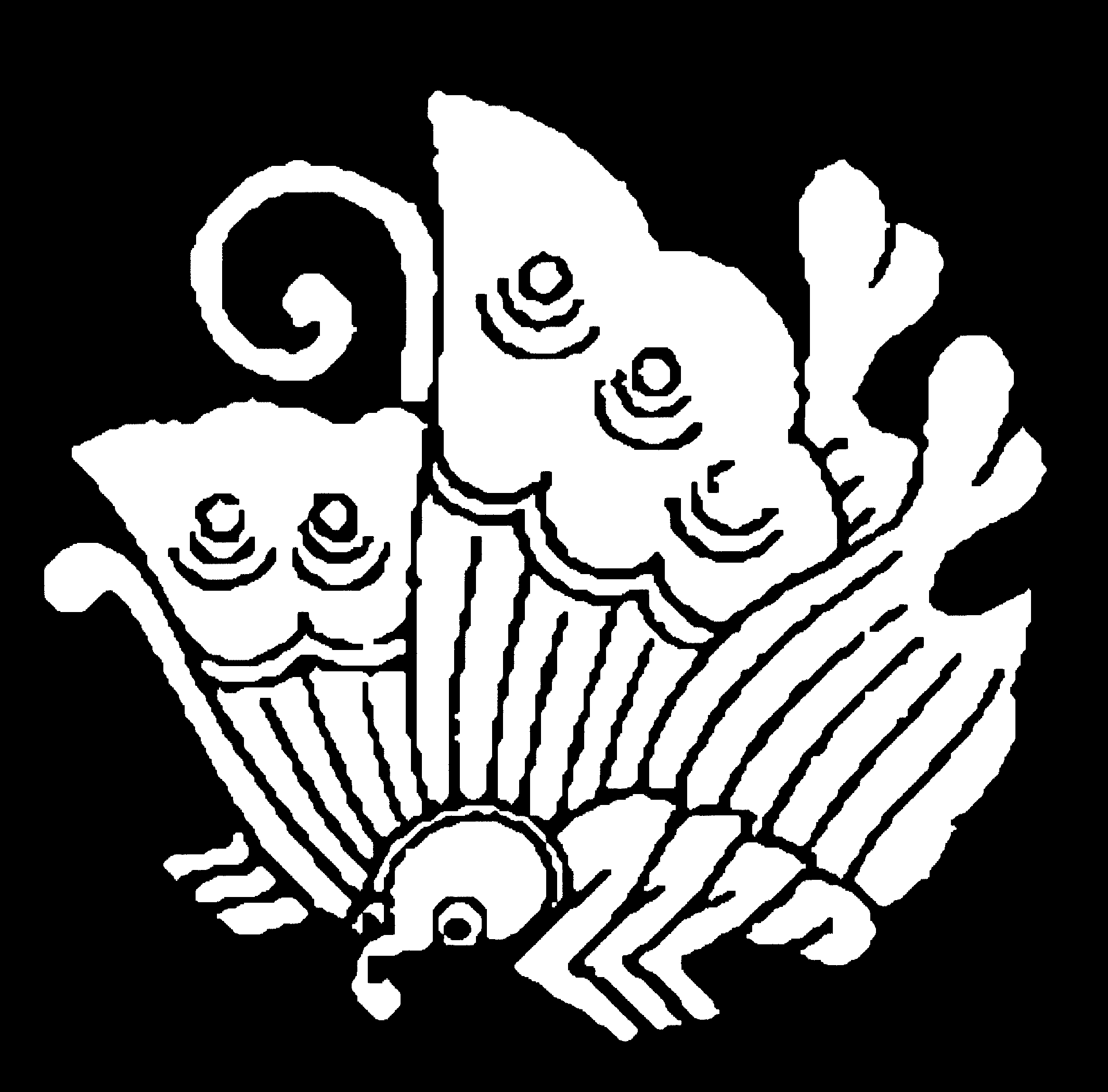
Re: 青木氏と血縁族(家紋)-18(揚羽蝶紋)
青木研究員 さん 2006/05/21 (日) 22:12
第17/33番目の紋様です。
この紋様には97もある。
この紋様は家紋200選に選ばれた紋様です。
この紋様に関わる青木氏の家紋は次ぎの紋様である。
第1番目は揚羽蝶紋である。
第2番目は丸に揚羽蝶紋である。 第1番目の分家に当る。
この紋様は平安中期頃に京平家の平重盛等が鎧や車紋もなどに用いたのが最初である。
蝶紋のうち揚羽蝶紋は桓武平氏が最初に用いたものである。
桓武平氏とは後漢の末帝の献帝の子の阿智使王と孫の阿多倍王らが孝徳天皇期(645)に漢の東国と北朝鮮の朝鮮族の17県の民200万を引き連れて九州の北側に上陸して大和の国に帰化してきた。この阿智使王と阿多倍に率いられた民は瞬く間に九州全土を殆ど無戦の状態で統一した。この200万の民は全ての技能集団を引き連れていたが、この技能を土地の者に伝授し平和裏に同化したのである。
この一団の一部は次第に中国地方に移動しこの地方でも陶族が勢力を持ち全土を制圧した。更に移動して最東信濃と美濃地方まで移動してここを開拓した。
この渡来人は技能集団として海部、服部、綾部、陶部、土師部、鍛冶部、磯部、渡部等の「部」のついた姓はこの技能集団の末裔である。
この軍事集団で有名なのは蘇我氏に仕えた漢氏や東漢氏や直文氏である。
この技能集団は現代の第一次産業の殆どの基礎を作り上げたのである。
この技能集団は朝廷の政治形態を3蔵という形態をとっていたがこの3蔵のうちの2蔵を占め、この政治官僚として日本の律令政治の基礎を作り上げた。
この3蔵とは「大蔵」で朝廷の財政を、゜「内蔵」で天皇家の財政を、「斎蔵」で政治を含む祭事や祀事を司っていた。この内、「大蔵」「内蔵」はこの阿多倍一族が占めていた。
「斎蔵」は鎌足の藤原氏である。故に後には藤原氏は朝廷の政治を司る摂関家となったのである。
後にこの二つの「蔵」の功績から天皇から賜姓を受けて次男は「大蔵氏」と三男は「内蔵氏」と長男は「坂上氏」の3つの賜姓を受けた。
長男の坂上氏は阿多倍の率いた軍事部門を統括して征夷大将軍となり東北から北海道を制圧した。この坂上田村麻呂が初代である。
今までは、天智天皇期から第6位の皇子が臣下して5代の天皇から出た青木氏が天皇家の親衛隊として皇族賜姓族の役目であつた。
其処にこの渡来系の阿多倍の集団が朝廷の軍事部門を担うようになり青木氏との間に軋轢が生まれた。
桓武天皇は律令政治を完成した天皇としてこの青木氏の発言力を排除して自らの母方の一族を頼りに推し進めたのである。
さらには後にはこの阿多倍は敏達天皇の曾孫娘を娶り天皇家と縁戚となり朝廷の全権を握った事にもなった。
この阿多倍の率いた一団は大和の国の経済的基盤と政治的基盤と軍事的基盤を確立した程に貢献した。ここの功績に報いるために桓武天皇は阿多倍の死後にこの阿多倍の高望王を大和の国の「高尊王」として扱いこの一族に「たいら族」として渡来人に初めて日本の氏をあたえた。そして、この子孫に伊勢国北部伊賀地方を切り裂いて与え、不入と不倫の権を与えた。
この一族の貞盛が「平の将門」の乱を藤原秀郷と共に5年もかけて鎮めた功績で天皇に寵愛され5代後に「平の清盛」の太政大臣まで上りつめた。
これが「桓武平氏」である。
この桓武天皇の母はこの阿多倍の子孫である。
この為に、この桓武平氏の阿多倍一族を引き上げるために総宗本家の伊勢青木一族をはじめ5家5流の青木氏は桓武天皇から圧力をうけ、伊勢青木氏と5家5流の青木氏は一時守護の職を失う。
この時、藤原秀郷より2代前祖父の藤成なる者が一時伊勢の守護となることが起こり、これ等を契機に5家5流の青木氏と後の嵯峨天皇から始まった賜姓青木氏から変名した皇族第6位の賜姓源氏も平家の台頭で力を失う。
これを嫌った次の天皇の嵯峨天皇は皇族第6位皇子の賜姓方式を元に戻して青木氏から源氏に変名したのである。
この時、藤原秀郷はこの伊勢守護の時に伊勢伊賀北部の平家から妃を求めて縁組をし、この子供の藤原秀郷の第3子の千国が青木氏の元祖となる。
この青木氏は直系1氏、直流4氏、支流4氏となり、ついには116氏の藤原秀郷流青木氏が出来る。
この支流4氏のうちの3氏はこの揚羽蝶紋の家紋である。
この3氏中の1氏が主流であり、元は嶋崎と岡本を名乗り後に元の藤原系の青木氏に戻る事となりこれより揚羽蝶紋の青木氏が分派して子孫は拡大する。
つまり、中国後漢の光武帝の子孫の阿多倍王の渡来系人の血筋を引いていることになる。更に同系の京平氏の子孫ともなる。
この子孫と同じ血筋を元祖に持つ青木氏はほかにもある。
甲斐武田氏の諏訪族の武田系諏訪族青木氏である。
阿多倍らが引き連れた帰化民が甲斐の国の開拓民として入植して大型の外来馬を飼育して生計を立てた。
この地に定住した末裔の諏訪族とこの地の守護としての皇族第6位皇子の青木氏がこの地の甲斐王として赴き後にこの諏訪族との間に血縁をもち青木氏を発祥させた。
後に武田氏とも皇族賜姓青木氏と血縁し、諏訪族は武田氏とも血縁する結果となる。この青木氏も元祖には阿多倍の血筋を持つ事になる。
藤原秀郷の主要5氏は永嶋氏と青木氏と長沼氏、それに進藤氏と長谷川氏であるが、この永嶋氏は京平氏との縁組にてその子孫は青木氏と永嶋氏を発祥させたが元は阿多倍の大蔵氏からであるので名乗ったもの。
つまり、阿多倍と敏達天皇の曾孫娘との間に出来た子供の「大蔵氏」は、後に九州に於いて「永嶋氏」に変名する。
この永嶋氏一族はその勢力を背景に中部地方から以西にたちまち広まる。
中部地方から以東は藤原秀郷流永嶋氏である。
よってこの永嶋氏は阿多倍の末裔の平家族の血筋を持つ青木氏と同じ母方元祖の血筋を引いた藤原秀郷流永嶋氏とは同血縁になる。
藤原秀郷にはこの様に京平家の血筋を持つ氏が2氏もある。
ここで注意が必要なのは「坂東八平氏」と言う一族が関東に居たが、この坂東八平氏とは全く別である。こちらは京平家の「たいら族」に対して゜平族(ひらぞく)」という。
桓武天皇はこの「ひら族」になぞらえて渡来人を「たいら族」として賜姓した。
この「ひら族」は皇族第7世以上の者が天皇が代替わりするたびに生まれる7世以降の者が関東に定住しその末裔が「坂東八平氏」である。
京平家を伊勢者と言うがこれを主流として関氏や織田氏らの支流が出た。
伊勢者に対して関東は坂東平氏と言う
この2氏の揚羽蝶紋の京平氏のながれを組む支流の藤原秀郷流青木氏である。
主要紋を次ぎに掲示します。家紋掲示板にも掲示します。参照して下さい。
|
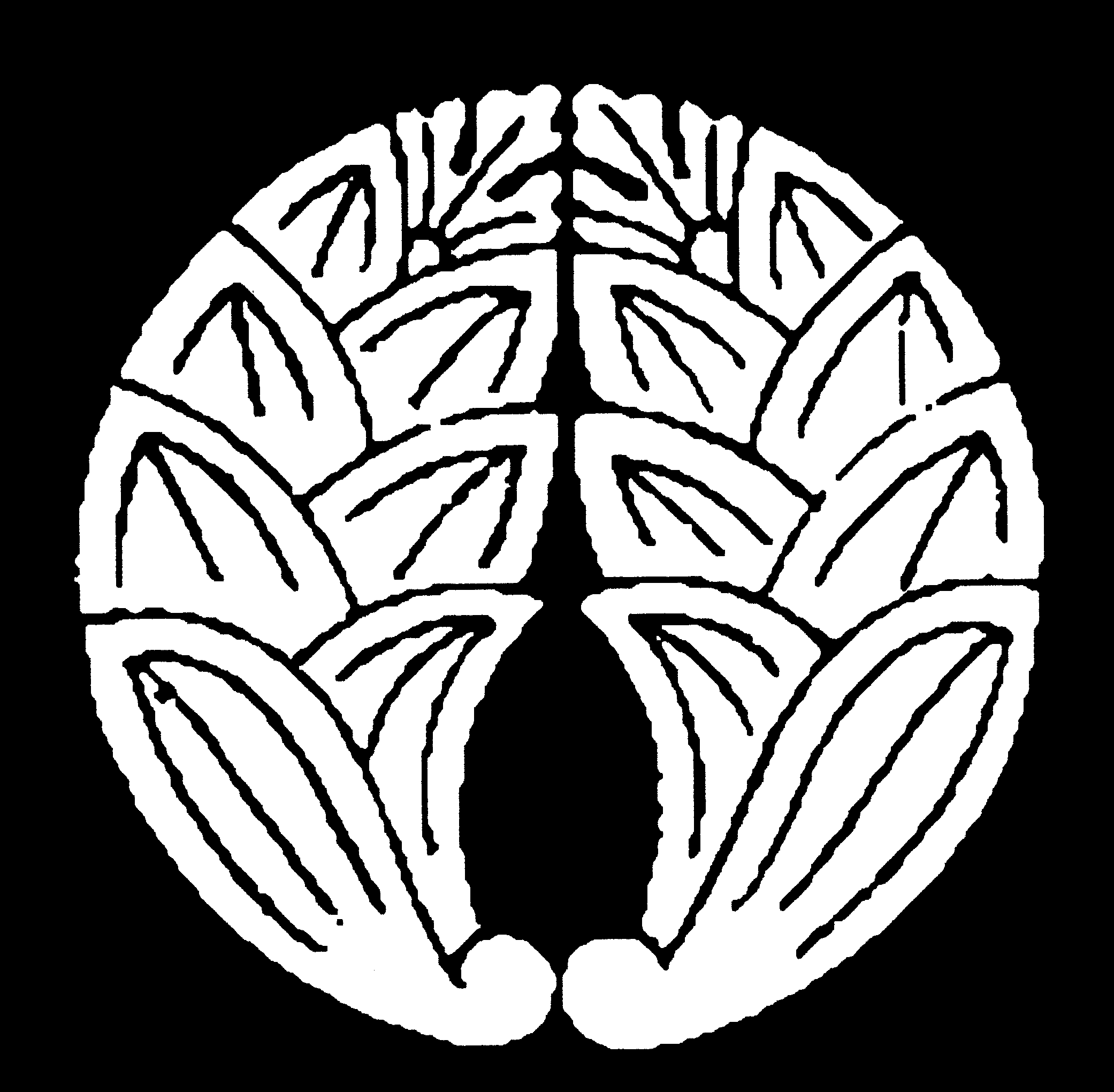
Re: 青木氏と血縁族(家紋)-17(茗荷紋)
青木研究員 さん 2006/05/07 (日) 14:37
第16番目の紋様である。
この紋様には61の紋様がある。
この内、青木氏に関わる紋様は次ぎの3つである。
第1番目は抱き茗荷紋である。
第2番目は丸に抱き茗荷紋である。 第1番目の分家筋に当る。
第3番目は抱き茗荷菱紋である。 第1番目の支流である。
第1番目は志摩地方の鳥羽氏がこの紋様の抱き茗荷を家紋として使用している。
この全体の紋様は関西地方に多く散在し、近江地方の山下の稲垣氏もこの家紋を使用している。又、小沢氏もこの抱き茗荷の家紋である。
何れも新しく江戸時代になってからである。
この2氏は二宮氏、鳥羽氏の支流一門と見られる。
最初に使用したのは近江地方に広く分布する二宮氏である。
土地の地名を採った鳥羽氏は系譜の確認は江戸期であるのでとれないが、この二宮氏の系列と見られる。又、稲垣氏、小沢氏も同様と見る。
この紋様は元は比叡山の天台宗の神紋であり、この紋様を戦国期を経て江戸時代になり家紋の持たない者が侍となってこの紋様から引用して家紋としたものである。
特に関西系の旗本100氏程度がこの紋様を使用した。
したがって、この3つの家紋の青木氏の系譜は江戸期になってのものであり、5家5流と藤原秀郷流青木氏の2つの青木氏との確定は困難である。
この二宮氏と鳥羽氏を元とする抱き茗荷の家紋を持つ本家筋が2つのいずれかの何らかの血筋で青木氏との繋がりがあり、江戸期になり家紋と共に名乗ったものであると思われる。
後の二つはこの分家筋と更に分家分派した支流の抱き茗荷の一門である。
関西を中心としての氏であるとすると、伊勢の青木氏か、藤原秀郷系統の伊藤氏に付き従った青木氏とも考えられる。
しかし、伊勢の青木氏との可能性は分布と地域と二宮氏と鳥羽氏との関連から極めて低い。
この伊藤氏は、藤原秀郷系の藤原氏で平安末期前半にこの伊勢の半国司を務めていて、鎌倉期になり、この地に留まり伊藤氏を名乗っている。つまり、伊勢の藤原氏である。この時に護衛役として従った青木氏であると見られるが近江滋賀の二宮氏との地域の関連が取れない。
つまりこの鳥羽氏と二宮氏の先祖はどちらが先きにあるかと云う問題で歴史上からみては鎌倉期の二宮氏となっているが、鎌倉期前から鳥羽地方に古くから定住していた者の藤原秀郷流青木氏の一部が近江に移動したとも考えられる。
その根拠は当時は勝手に一族が土地を離れることは「国抜け」として出来ないが、鎌倉前にただ一つ出来ることは藤原秀郷一門の「守護職の赴任地移動」に伴って勢力を保持したままに青木氏のみが動くことができたことである。
これが現地に子孫を残す戦略を採っていた藤原一門の方法でもあつた。
この近江地方には秀郷一族の「藤原脩行」という者が鎌倉末期に守護としてとして移動している。
伊勢鳥羽永嶋の半国司でなくなった時に青木氏は伊勢の志摩鳥羽地方に残っていたが、その後、伊勢より移動してこの者に従った青木氏である可能性がある。
二宮氏の一個人が移動しても勢力を持つ事は出来ない。出来るとすれば秀吉の時代の命令により一族の移動が考えられるが3百年も時代は新しいことになるので可能性は低い。
それ以前であればここは北畠氏の領域であるので戦いが起こるが無かった。
戦いが起こらないただ一つの大量の移動はこの青木氏の移動以外に無い。
この意味から鳥羽地方に住む藤原秀郷流青木氏の近江か滋賀地方への移動説が現実的である。
伊勢鳥羽に僅かに残った藤原秀郷流青木氏が土地の鳥羽氏との血縁で男系相続不可にて茗荷紋に変紋したものと見られる。
二宮氏が現在の所先に出たとされていると滋賀佐々木氏系青木氏ともなる。
しかしこの可能性はく低く戦国期を挟んでいるために確定は困難。
土地が両方にまたがっているので移動説がなくては成立しない。
半国司とは伊勢は元は平安中期までは伊勢青木氏の所領であつたが、伊勢北部の伊賀地方を中国後漢光武帝の子孫(帰化した阿多倍王)の功績に対して恩賞として伊勢を切り裂いて特権を与えて領国とさせました。(桓武期前後)
その後、村上源氏の支流北畠氏に伊勢の東部永嶋と鳥羽地方を切り裂き国司として任じました。
結局、伊勢は3つの国司が存在しました。この状態の伊賀と永嶋の2つを半国司という。
伊勢鳥羽と近江山下の地方には僅かであるがこの藤原秀郷流青木氏が存在する。
伊勢松阪と玉城を中心として西には奈良の名張、伊賀地方から東は桑名地方まで帯状に分布する施基皇子を元祖とする伊勢王の子孫の皇族賜姓青木氏とは異なり、又、皇族賜姓近江青木氏と皇族系近江、滋賀佐々木系青木氏の慣習に基ずく住み分け地方が異なることから、このことから移動の出来る藤原秀郷系の伊藤氏に着き従った青木氏である事となる。
この藤原秀郷流青木氏が土地の鳥羽氏との血縁にて男系継承相続が困難となり
家紋を抱き茗荷家紋として引き継いだものと考えられる。
61もの紋様はこの旗本の100余りの旗本の家紋である。
これ等は鳥羽氏、稲垣氏、小沢氏を発祥元とした氏の家紋であり、通説の元祖二宮氏から出たものであろう。
この紋様は大変に杏葉紋と酷似する。この変紋ではないかと見られる。
比較的新しいこの家紋を使用している氏の青木氏には戦国時代の為、系譜等の資料は全くなく確定は困難であり、以上の状況判断によるものである。
明治以降の第3の青木氏との関係は一般武士であることから見て無いと見られる。
この抱き茗荷紋の主要紋は次ぎのとおりである。
他の2つの家紋も家紋掲示板に掲示しますので参照して下さい。
|
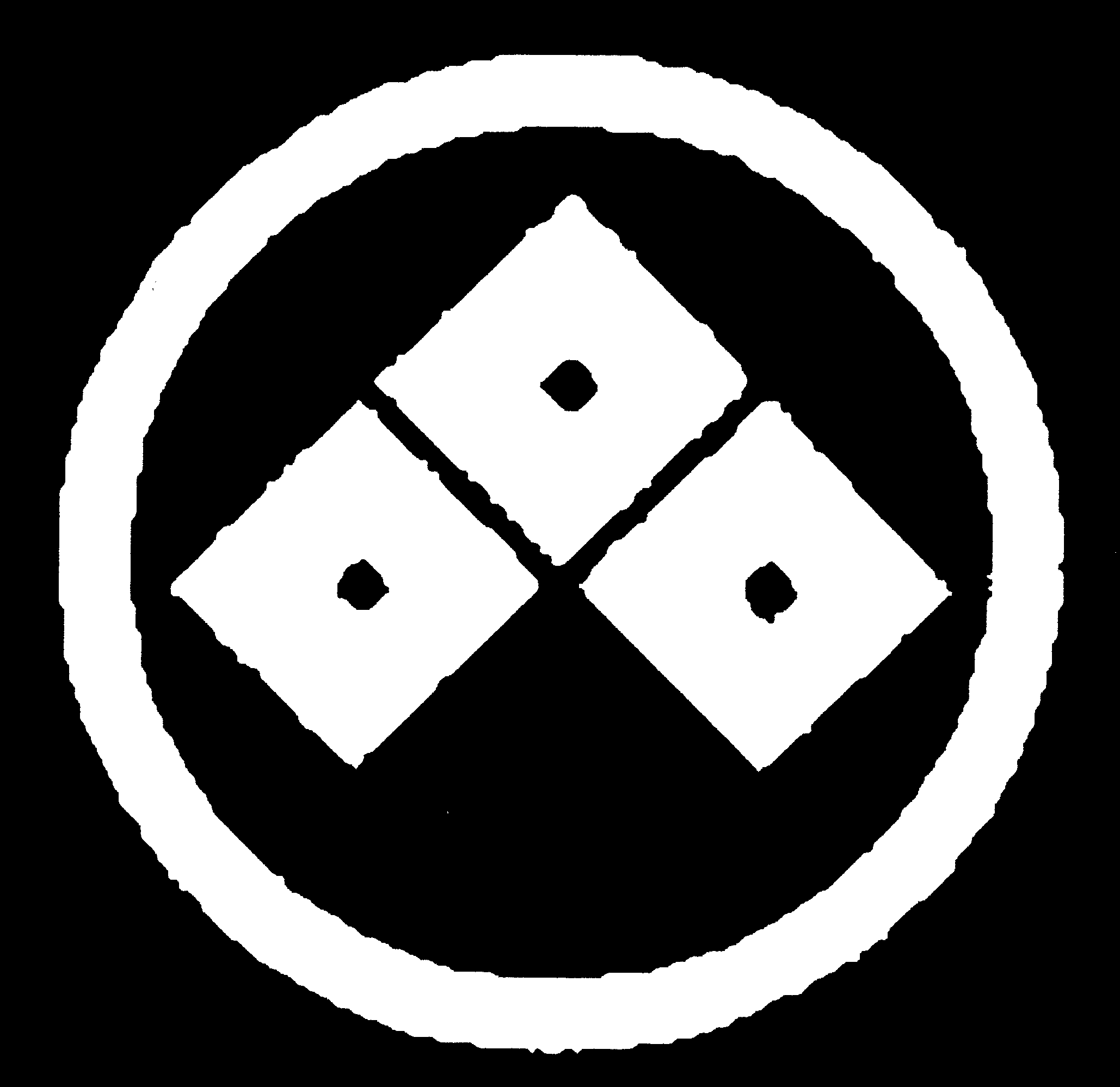
Re: 青木氏と血縁族(家紋)-16(目結紋)
青木研究員 さん 2006/04/26 (水) 11:36
第15番目の紋様である。
この紋様は81の紋様がある。
家紋200選にもある紋様である。
この内、青木氏の紋様は3つである。
この3つは次ぎの紋様である。
1番目は丸に隅立て4つ目紋である。
2番目は隅切り角に4つ目紋である。
3番目は丸に三つ目紋である。
青木氏以外に次ぎの氏がこの家紋を使用している。
1番目の紋は児島氏、鍋島氏が使用している。
2番目は不詳
3番目は磯部氏、由井氏、飯田氏、二松氏が使用している。
この家紋は最も古くから使用していた氏は佐々木氏である。
この佐々木氏の流れを汲む一族としては室町幕府の足利氏の御家人の六角氏を始めとする主要大名がこの紋様を使用している。
佐々木氏には天智天皇の近江佐々木氏と宇多天皇の滋賀の佐々木氏がある。
云うまでもないが、近江佐々木氏は天智天皇の第7位の皇子の近江王の川島皇子の末裔であり、伊勢王の施基皇子の青木氏と並んで特別に第6位に対しての賜姓の令外として第7位の弟の川島皇子に土地の地名を採って佐々木氏の賜姓を授けたものである。これが近江佐々木氏の始まりでこの佐々木氏から近江青木氏が発祥している。この青木氏には佐々木系青木氏と二つあるが血縁である。
この近江青木氏の方は後に何らかの理由で滋賀と攝津の二手に分かれて移動している。(既にレポート済み)
この青木氏は後に宇多天皇の佐々木宗綱、高綱の末裔の氏との間でも血縁をむすんでいる。
この3つの青木氏のうち2つの青木氏は何れもが前者の近江佐々木氏の血縁であるが、一方の滋賀の宇多天皇の佐々木氏の青木氏もあるいずれにしても皇族系青木氏である。
近江青木氏は皇族賜姓青木氏の直系と支流青木氏と言うことになる。
宇多天皇の佐々木氏系青木氏は時代は後になる。
つまり、奈良時代に発祥した後の近江源氏と平安後期の滋賀源氏の2流となる。
近江佐々木氏の2つの青木氏は総宗本家の家紋は皇族賜姓青木氏と同じ「笹竜胆の家紋」である。剣豪の佐々木小次郎はこの近江佐々木氏の末裔である。
宇多天皇の佐々木氏も皇族の賜姓源氏であるので総宗本家は「笹竜胆紋」である。
この上記3つの家紋の氏は支流一族である。この3つの青木氏は江戸初期あたりにて上記の各氏と後に血縁を結んだものであると見られる。江戸初期にはこの家紋を持つ氏が約70も出来ている。
男子継承が不可となり、家紋の変紋を余儀なくされた支流一族である。
したがって、この3つの青木氏以外に近江と滋賀地方で笹竜胆の家紋を持つ青木氏が確認されればこの一族の本家筋となる。
この研究室にルーツ依頼があつた方が居たがこの一族は攝津に移動した青木氏
であり、川島皇子の末裔の皇族賜姓青木氏であった。滋賀の青木氏は非常に確認が難しく豊臣時代には青木氏の継承をめぐり争いを起している。
この結末は青木氏の氏を買い取るかまたは奪い取ったか政略結婚かにて出世方の元上山氏の方に2度の戦いの末に軍配は上がった。(レポート済み)
後にこの上山氏の青木氏はこの家柄の獲得の結果10地方の守護をつとめている。このことから見ると政略結婚にて妻方のほうに青木氏を引き継ぎ家柄を高めて守護になりえたものとみられ、この結果、後に総宗本家との間に争いが起こったものと見られる。
この青木氏は現在も末裔が現存している事が確認出来る。
この近江の青木氏の二手に分かれた一方の滋賀の青木氏の詳細は不詳である。
この青木氏は伊勢の青木氏をはじめとする5家5流の近江青木氏の末裔となる。
この紋様は元は平安末期から鎌倉時代にかけて用いられた染め文様から図案化されたもので幡などに用いられて後に家紋化されたものである。
後には江戸時代の初期に徳川の御家人になった者がこの紋様を80前後も多く用いた。この結果、81にも成った。
この主要紋を次ぎに掲示する。家紋掲示板にも掲示するので参照して下さい
|
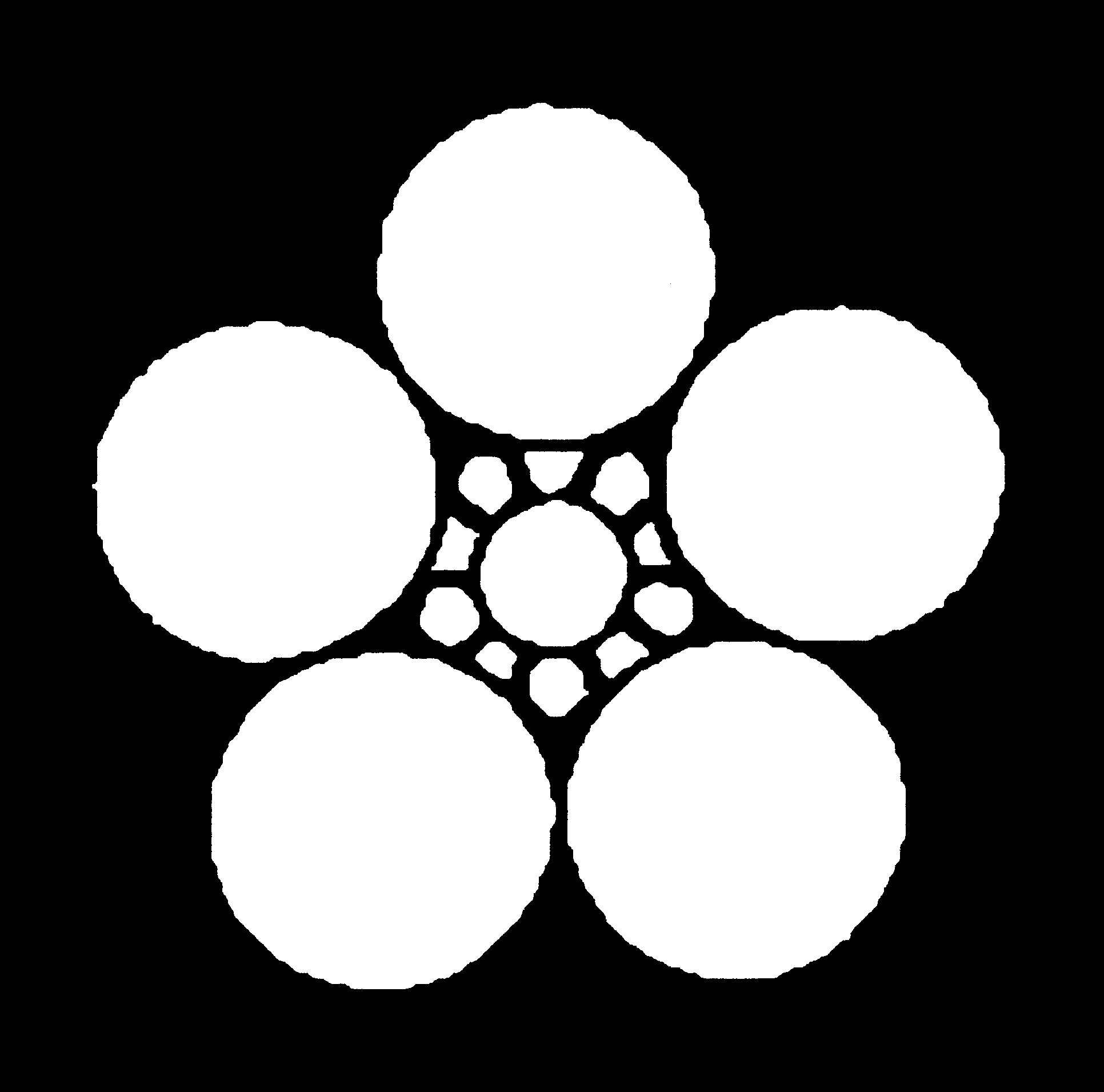
Re: 青木氏と血縁族(家紋)-15(梅紋)
青木研究員 さん 2006/03/28 (火) 21:42
第14番目の紋様である。
この紋様は全部で127もある。
家紋200選に選ばれている有力氏である。
この内、青木氏に関わる紋様は3つである。
第1番目は梅鉢紋である。
第2番目は丸に梅鉢紋である。 第1番目の分家である。
第3番目は加賀梅鉢紋である。
第1番目と第2番目には菅原氏、佐々木氏、松任氏、筒井氏、平氏がある。
第3番目は前田氏、斎藤氏、堀氏である。
これ等の青木氏は藤原秀郷流の支流である。
平安期の菅原氏はこの文様を最初に使用したといわれている。
藤原秀郷氏との何らかの血縁関係を持つたと考えられ、主要支流の一族が男系跡目相続の可否で家紋掟によりこの家紋を使用したものと見られる。
佐々木氏は皇族賜姓青木氏と並んで極めて古い皇族系の近江の佐々木氏(佐々木氏は天智期と宇多期の2期に発祥)であるが、この一族の支流がこの菅原氏の血縁を受けたのではと考えられる。
藤原秀郷流青木氏には116氏もあるが、この氏は主要9氏があり、
この主要9氏は直系1氏、直流4氏と、支流4氏から成っている。
(詳細は藤原秀郷一族の行き方のレポート参照)
この支流4氏のうちの一つの梅鉢紋の青木氏である。
数多い116氏中の主要支流4氏の末裔である。
藤原秀郷流青木氏は秀郷の子の千国が秀郷が貴族に昇進したことからこの護衛役として任じられた。
(大化の改新の中大兄皇子から始まった)5代に渡り天皇を守る親衛隊として皇族賜姓青木氏が臣下して賜姓を受けた慣例から、藤原秀郷は朝廷からその許可を得て、千国に青木氏を与えたものである。
上記した第1番目の平氏との関わりは千国の母方がこの平氏一族から出たもので、後にこの一族が平氏を捨てて藤原氏に名乗り換えをした。
藤原秀郷流青木氏の支流4氏のうちの末裔の多くはこの平氏家紋の揚羽蝶紋と丸に揚羽蝶紋である。
貴族になると武力を自ら使用することが出来ないためにこのことになったのである。
既に何度もレポートしたが、藤原秀郷は平将門の乱を鎮めた勲功により武蔵国と下野の国の守護に任じられ、更に貴族に昇進した。このことの経緯は (詳細は藤原秀郷一族の行き方のレポート参照)前レポートに記述した。
このことによって藤原秀郷流青木氏が生まれたのであるが、この青木氏を朝廷の許可を得て名乗った理由はこの皇族賜姓青木氏の母方は伊勢青木氏を除いて全て藤原氏系である事による。
嵯峨期の令により皇族還俗者以外の者が氏として名乗っては成らないことに成っていたが上記のこととその権勢により藤原氏はこの令外として許されたものである。
(その後、嵯峨期より第6位の皇子がを変名して青木氏を賜姓源氏とした。)
この紋様は勿論、丸は花弁を表しており、古く奈良時代末期から仏教に用いられていた文様である。
この文様は2つの文様の形に分けられる。
芯の有無に関わる。
この藤原秀郷流の支流青木氏は芯のある梅紋である。
主要家紋は次ぎの家紋です。
家紋掲示板にもこの藤原秀郷流青木氏の家紋3つを掲示します。参照して下さい。
|
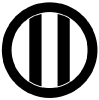
Re: 青木氏と血縁族(家紋)-14(引き両紋)
青木研究員 さん 2006/03/12 (日) 18:08
第13の紋様は引き両紋である。
この紋様は38の紋様がある。
家紋200選に選ばれた鎌倉期から室町期に勢力を持つた一族である。
この紋様に関わる青木氏の紋様は4つある。
次ぎの通りである。
第1番目は丸に一つ引き両紋の家紋である。第2番目の足利氏系青木氏の主家が一門の新田氏との血縁を結んだ青木氏である。
第2番目は丸に二つ引き両紋の家紋である。この4氏の青木氏の中でこの丸に二つ引き両紋が主家筋である。足利氏の家紋で足利系青木氏
第3番目は丸に三つ引き両紋の家紋である。下記のいずれかの一族との血縁を深くした第2番目の主家足利系青木氏である。
第4番目は八角に木瓜二つ引き両紋の家紋である。第2番目の主家の足利系青木氏と木瓜一族との血縁を結んだ一族である。
足利氏一門の主要一族である。
この4つの家紋類は明確に足利一門の家紋であり、この一族との血縁による青木氏である。
この青木氏は武田氏と同様に信濃の皇族賜姓青木氏と土地の豪族であった足利氏との血縁による足利系青木氏である。
つまり、この主流足利系青木氏は皇族賜姓青木氏の5家5流の支流24氏の主要一族である。
足利氏は以前のレポートでも記述したが、土地の豪族足利氏が衰退し続けていたが、この一族の一部が藤原秀郷の一族との血縁を図り態勢を戻そうとした。
しかし、皇族賜姓青木氏の血筋を入れていた本家筋はこの動きに反発して二派に分かれた。
しかし、本家筋を率いる者の力が不足していて分家筋の動きを止めることはできず、結局、藤原秀郷一族の血筋を入れた分家筋の勢力が勝った。
そして、この分家筋は政略的な行動から更に清和源氏から上位の跡目を入れ清和源氏支流の一門となった。(詳細は研究室のレポートを参照)
そして、この分家が本家筋も引き込み足利氏の本家として一門を統一していった。
この皇族賜姓青木氏の血筋を持つ足利系青木氏がその後に他の分家と支流の足利一門との血縁を深くした。
二つ引き両紋の青木氏から分家してこの一門の一つ引き両紋、三つ引き両紋の分家筋が一門との血縁を広げていつたものがこの青木氏である。
その後、二つ引き両紋の分家一族が男系相続が不可能となり、木瓜一族から跡目を採り、止む無く家紋の変更を余儀なくされたものである。
木瓜一族との血縁を結んだのが第4番目の一族となる。
この足利系青木氏の4氏がこの家紋を引き継いでいる。
この内、一つ引き両紋は一門の新田氏であり、二つ引き両紋は主流足利氏、で三つ引き両紋はこのほかの足利一門が使用している。下記
例えば、他に有名なところでは吉良、渋河、石橋、斯波、細川、畠山、上野、一色、山名、大館、今川、三浦、山名の各氏が使用している。
他にこの一族と血縁した紋様の一族は違い鷹の羽の家紋族、上記の木瓜族、巴族などがある。
足利系青木氏は上記の木瓜族のみである。
そもそもこの紋様は陣幕の色で武将の居所を明示することに用いたものが、後にその幕に八卦の卦を入れて武将の居所を占めすものとして使われた。それが主家の足利氏は二つ引き両が目印とし、これに丸をつけて家紋とした。
新田氏は一つ引き両で丸に一つ引き両紋の家紋とした。
丸は通常は家紋掟により分家がつけるものであるが、この場合は居所を示す使用目的から初期から丸つき紋である。
上記した様にこの紋様は中国の八卦の卦を紋様化したものと言われており、この両は竜、領であるとする説もあるが、卦が通説に成っている。
古くは盾などの紋様として用いられていた。
下に主要家紋の丸に二つ引き両紋を示す。家紋は家紋掲示板を参照。
|
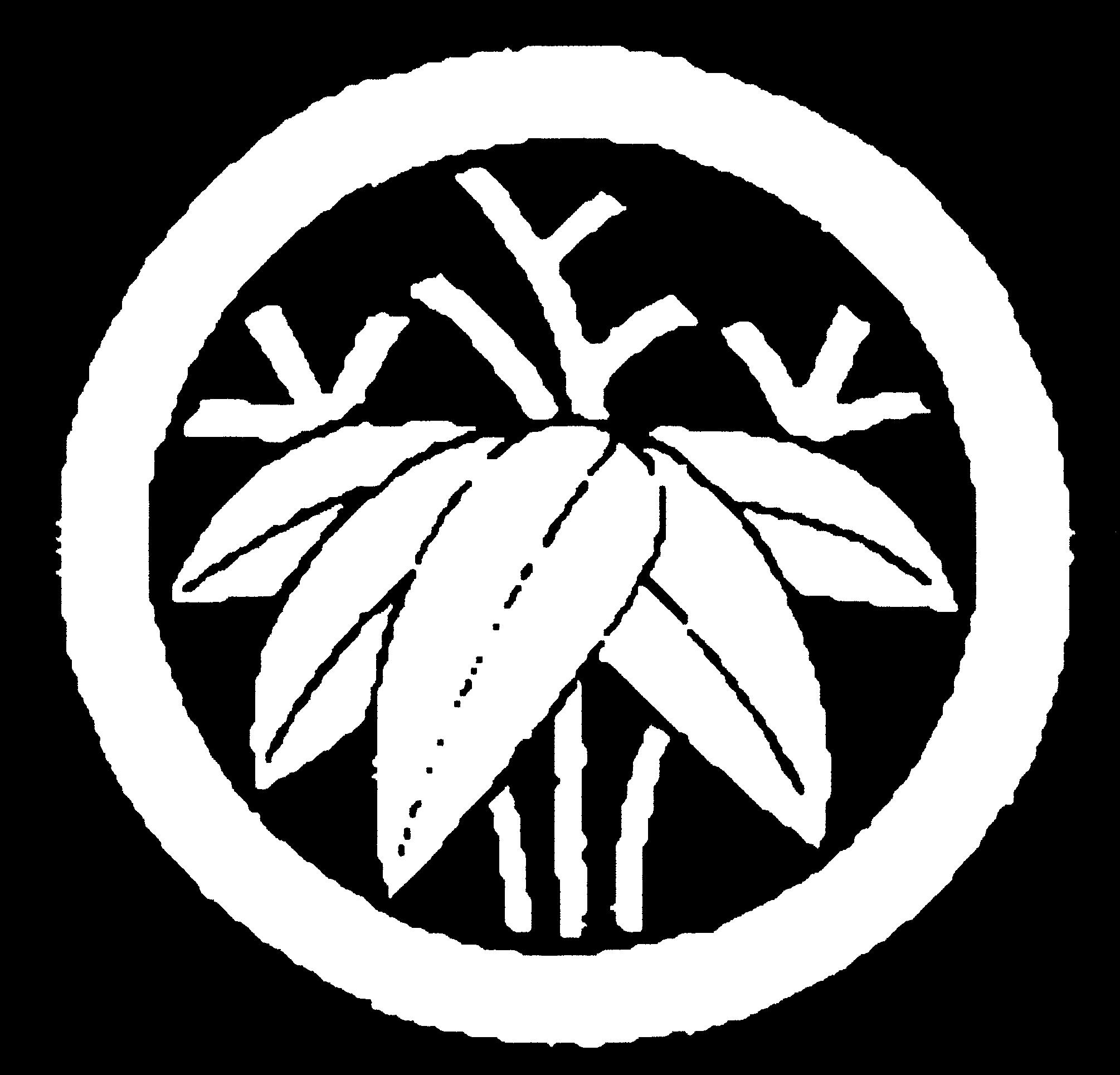
Re: 青木氏と血縁族(家紋)-13(竹.笹紋)
青木研究員 さん 2006/03/04 (土) 10:50
第12の紋様は竹、笹紋である。
この紋様は全部で141もある。
この内、青木氏に関わる紋様は4紋様である。
家紋200選にも選ばれている有名な紋様であり、比較的新しい紋様で最初に使われたのは鎌倉の末期ごろである。
この4つの紋様は次ぎの通りである。
第1には丸に根笹紋である。
第2には三枚笹紋である。
第3には九枚笹紋である。
第4には二階根笹紋である。
第1はこの紋様を使用したのは桜井氏と二木氏の支流である。
第2は野々山氏である。
第3は秋月氏である。
第4は不明
第1の丸に根笹紋の青木氏は根笹紋の分家筋に当る支流紋一族である。藤原秀郷流青木氏の支流一族の幾重にも分派した氏の血筋を持つ青木氏である。
第2から4は江戸期に名乗った新しい氏との血縁であるのでルーツの如何は藤原秀郷系の青木氏の支流一族の可能性があるとする範囲の青木氏である。
しかし、何分新しいので野々山氏や秋月氏の系列から判断すること以外には確定の元は見出せない。その範囲で藤原秀郷流青木氏の一門に加えた。
この第1の氏も比較的にかなり新しい青木氏でもあり、桜井氏か仁木氏との血縁にて男系維持が出来ずに養子元の家紋を使用するという現象で定めたものである
これ等は主に初期は貴族や公家などが鎌倉時代に使用し始めたもので江戸期に入り、必要に迫られて家紋をつけた。
大名や御家人では約10程度、一般武士では200にも及んだが明治初期には家系断絶で120程度にも減った。
これ等の青木氏では共通することは関東の一族である。
特に代表的な紋様として最初に使用した武士では次ぎの2氏があげられる。
先ず、下総守の千葉氏と、東下総守の師氏である。
これ等の一門がこの竹と笹紋の変紋を多く作り上げた。
公家では2門である。
これ等の流れを汲む室町時代からの有名な大名としては東氏、粟飯原氏、朝倉氏、上杉氏、最上氏、伊達氏である。
では、この青木氏は主要青木氏の2流のどちらの青木氏かと言う問題であるが、140もの各紋様の発祥の確定は困難だが、全体の流れから見ても、上記した大名のルーツから見ても関東に定住していた藤原秀郷流青木氏の流れを汲む氏であると云う事ができる。
藤原秀郷の主要9氏の支流4氏の中から広がり、その内の24氏程度の藤原氏秀郷の末裔から更に男系維持を困難として家紋掟から変紋した氏である。
皇族賜姓青木氏との関係は見つからない。
江戸時代にはこの竹と笹紋が皇族賜姓青木氏の家紋の笹竜胆と類似しているものから源氏系と見られて多くの下級武士がこの紋様に似して家紋を作った。
まったく違うものであるが、この141の紋様はこの傾向のもつた紋様に成っている。
笹竜胆に似せた家紋が多いのはこのことから来る現象である。良く見ないと見間違えるくらいである。
この4つの青木氏の家紋は第一の丸に根笹紋に付いてそのルーツの確証は比較的取れるが,第2から4までは江戸期のものであるので困難である。
しかし、関東系の氏である事から男系跡目が困難な中での変紋であるので夫々の主要氏の流れを汲む氏である事は確認出来るが直系ルーツの確定までは困難である。
しかし、江戸期までは武士であった事は否めない。室町期の下克上と戦乱の中での台頭で家を興した者が殆どであるので、この時期を境にしてルーツの確定はよほどのことでなくては困難である。
概して、この4つの紋様が青木氏の紋様としていてそのルーツは藤原系のものとみなされる。
この家紋類に付いての真偽は一部を除いて、明治期の苗字令に基づく「第3の青木氏」も否定することは困難でもある。
ルーツの調査の内容は矛盾の範囲を超えているものもある。
この家紋は現代でも用いられている松、竹、梅の瑞祥的なものから来た紋様である。
今までの12の紋様の家紋のとは確定の点では少し異なる。
主要紋様は次ぎの紋様があげられる。
4つの家紋に付いては家紋掲示板を参照して下さい。
|

Re: 青木氏と血縁族(家紋)-12(抱き角紋)
青木研究員 さん 2006/01/31 (火) 19:46
第11番目の抱き角紋の紋様である。
この紋様には22の紋様がある。(鹿角紋と抱き角紋)
このうちは青木氏の家紋は4つである。
家紋200選にもある有名な家紋である。
この家紋は次ぎの4つである。
第1番目は抱き角紋である。
第2番目は丸に抱き角紋である。第1番目の分家筋である。
第3番目は四つ又抱き角紋である。
第4番目は隅切り角に抱き角紋である。
これ等の家紋は「皇族賜姓青木氏」の系列の武田氏一族諏訪氏の家紋類である。
つまり、研究室のレポートにも何度も書いたが、皇族賜姓青木氏がこの甲斐の地に守護として赴き青木村を形成して子孫が定住していたが、その後この地に藤原秀郷一族と共に移動してきた陸奥の国の武田氏(陸奥の国にて藤原秀郷一族と血縁関係を持つた陸奥の豪族武田氏)がこの地で勢力を上げて甲斐の豪族となった。
この武田氏と皇族賜姓青木氏との血縁を結んだ。この武田系青木氏は矢張りこの武田氏の一族に組み込まれた。
もとより平安初期からこの地に古くから定住していた諏訪一族(中国後漢の阿多倍王の渡来系人)は武田氏に吸収されたが、この諏訪族との武田系青木氏との血縁族である。
第1番目がこの氏である。第2番目がこの分家筋として分流したのが丸に抱き角紋の氏です。
第3番目はその後、この一族の子孫が跡目上の男系相続が出来ずに支流化して家紋掟により家紋を変紋を余儀なくなったものである。
第4番目は第1番目の武田諏訪氏系青木氏の抱き角紋の一族子孫が隅切り紋族との血縁をした青木氏である。
この一族も男系相続が出来ずに隅切り族から跡目をいれて、この結果、家紋掟から隅切り紋との組み合わせた族を作った支流族である。
この一族の子孫の方がこの研究室のサイトにルーツ依頼のありましたし、家紋掲示板にも最初に投稿された方です。(一読ください)
(他にも、賜姓族の青木氏からの投稿が掲載されています。)
皇族賜姓青木氏は天智天皇から始まった伊勢の青木氏をはじめとして天武天皇、聖武天皇、文武天皇、光仁天皇から第6位の皇子が臣下した5家5流の青木氏であるが(土地は伊勢、近江、美濃、信濃、甲斐の5地である)この青木氏は同時に5地の土地の豪族との血縁族青木氏を発祥させている。
この賜姓青木氏の子孫の拡大は比較的少なく5家5流から24氏までである。
5家5流の青木氏の主要家紋は「笹竜胆」紋である。この伊勢をはじめとし直系5氏と大半が現存している。
又、嵯峨天皇期より皇族賜姓青木氏から変名した同じ第6位皇子の賜姓により源氏が生まれたが、この源氏もこの5土地の同じ豪族との血縁族を発祥させている。
清和源氏の分家の頼信の末裔より上位跡目を入れて出来た支流源氏がある。
元を質せば皇族賜姓源氏(主に実質は嵯峨天皇から11代目の花山天皇まで)で皇族賜姓青木氏とは同じルーツである。
嵯峨天皇期から青木氏の姓は皇族関係者が下族した時に名乗るものとして以外者がこの姓を使用することを禁止した。
原則的にはこの規則は江戸時代まで守られた。
(明治初期にこの名誉の姓を高額の金品を使い寺社に頼み込み偏纂した第3の青木氏がある。)
この家紋は元は兜などの前立ちに使用されていたが、鹿角(おずか)紋として使用されたのは近藤氏であり、抱き角紋として使用していたのは諏訪氏である。
皇族賜姓青木氏の血筋を持つ諏訪氏系青木氏の主要家紋は次ぎの通りです。
この4つのうち3つの家紋は家紋掲示板に掲載します。
|
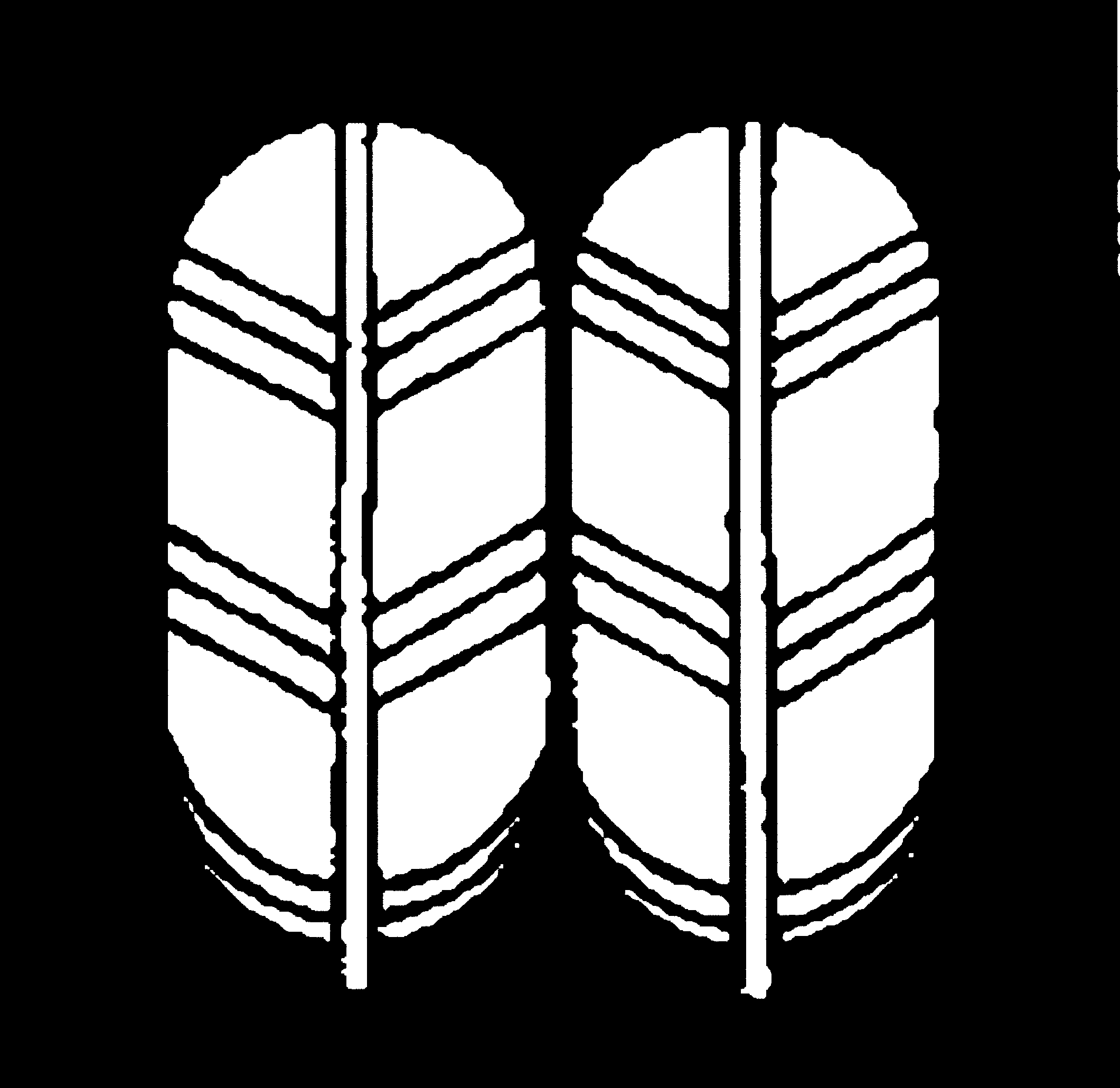
Re: 青木氏と血縁族(家紋)-11(鷹の羽紋)
青木研究員 さん 2006/01/21 (土) 21:38
第10番目の青木氏の紋様である。
この紋様は全部で各氏70の紋様がある。
この内青木氏に関わる紋様は4つである。
この紋様は主要家紋200選にも選ばれている。
その青木氏の家紋は次ぎのとおりである。
第1番目は並び鷹の羽紋である。菊地氏の家紋である。
第2番目は違い鷹の羽紋である。浅野氏の家紋である。
第3番目は丸に違い鷹の羽紋である。第2番目の分家筋に当る。
第4番目は五瓜に違い鷹の羽紋である。五瓜紋を家紋とする氏との血縁族である。
この家紋は藤原秀郷流青木氏の一族である。
第1番目のこの青木氏は比較的新しく鎌倉幕府の蒙古襲来事件(1274-81)の前後に当時に九州北部勢力を張っていた土豪の菊地氏一族と血縁を結んだ藤原一族の青木氏である。
この藤原秀郷流青木氏は主要9氏の中で次ぎの土地に赴任している藤原秀郷総宗家に関わる者は次ぎの通りです。
筑前国と筑後国の守護かそれに類する官職で赴いた者
為成、為重、長経の親子孫
利仁流としては次ぎの通りです。
豊前国に付いては貞宗 利仁より7代目
肥後国に付いては長成 利仁より17代目
筑後国に付いては18代目(長成の子)―20代目
豊後国に付いては重光 利仁より4代目
以上4者である。
鎌倉幕府樹立後離散した藤原秀郷の一族は仕官先を求めて各地に移動したが
上記の菊地氏との関係があったと考えられる藤原氏である。
(1333年倒幕)
浅野氏に関わる一族としては安芸国と美作国付近に移動して江戸期に出世していた藤原一族と備後国に赴任した公則の2つの流れがある。
しかし、この美作付近に移動してきた一族はそのルーツは史書によりまたその末裔も明確になっている。(研究室にルーツの投稿のあつた岡山の青木氏の方で家紋は「五瓜に剣片喰紋」一族との血縁を持っている)
従って、元は同じ一族であるが、備後の国の公則に着き従った藤原秀郷流青木氏である事になる。
そこでこの家紋を最初に使用したのは菊地氏(並び鷹の羽紋)であり、江戸時代には多くの武家がこの紋様を変紋して使用した。
この事から次の事が云える。
第1は、「並び鷹の羽紋」は上記四者の何れかの者(後述)で藤原総宗本家に付き従った藤原秀郷流青木氏であるが、この青木氏が土地に定着した一族と土地の豪族との血縁を結んだ事により発祥した一族で家紋は男系問題での跡目相続の結果等で変紋を余儀なくされた結果による。
第2は、「違い鷹の羽紋」は江戸時代前ごろから台頭した浅野家の家紋であるが、この家紋に関わった者としては備後国の守護(公則)として赴任に付き従った藤原秀郷流青木氏の末裔であると考えられる。
第3は、また、「丸に違い鷹の羽紋」はこの分家筋に当ることから同族である。
第4は、美濃付近から広がって阿波国と瀬戸内海を隔てて更に安芸国と美作国まで拡大し土豪となった五瓜紋(藤原系長良一族)を持つ一族と第2の一族との血縁から生まれた子孫と考えられる。
この第4の土地付近には四国阿波国に赴任した藤原総宗本家の宗政と時宗親子に付き従い讃岐付近まで伸びこの一族が美作の国に移動してて出世した上記の藤原秀郷流青木氏の一族がいる。
さて、上記の四者のうち、土地柄から筑前と筑後と豊前国のうちの何れかが可能性が高い。
時代性からみると肥後国は鎌倉幕府樹立の直前頃に菊地氏が隆盛を極めてい
て元寇の役に参加して勲功を立てている事から考えると、当時としては長期に筑前と筑後の官職を務めた土地に根ずいた事から長成から親子4代の時の護衛役の青木氏一族末裔と考えられる。
このことから、4代(30-50年間)と実に長い間に続いた時に定着した藤原秀郷流青木氏である事が考えられるし、鎌倉後も土豪化していたと見られる。兎も角武蔵と下野の国の本拠地以外にと4代と続いた実績のある藤原秀郷一族の氏の赴任先は他にない。(普通は最低は5年程度で役目は終わる)
元寇の役から鎌倉幕府が滅亡した時間までの間とすると52年間である。
この鎌倉幕府の初期ごろはまだ全ての武士が家紋を持つという事は無かった。
殆ど主要な豪族だけであり、この役の時には菊地氏は既に家紋を持っていたことが「蒙古襲来絵詞」(肥後国の御家人の竹崎秀長が書いた絵詞)に描かれている。大きな豪族であった。
この菊地氏と藤原一族との血縁を結び勢力の拡大と安定を計ったものとみられる。
数年前までは戦場となつた所は守護の立場にあつたし、菊地氏とは藤原系青木氏はこの事件をともに戦った背景からの結果であったかも知れない。
この間に血縁が起こったと見られる。
つまり。「並び鷹の羽紋」の青木氏は菊地氏との血縁による。
この紋様は勿論鷹の印象から来る紋様で作紋されたもので、勇猛なイメージを持つものである。この紋様は江戸時代に多くの大名や御家人が家紋とした。
大抵は下克上と戦国時代で家紋の持つ家柄は滅亡し衰退して新しい勢力が台頭して安定期に入った江戸初期にこの新しい勢力が家紋を定めたものである。
この意味で並び鷹の羽の家紋は伝統的である。
違い鷹の羽紋類は上記の新しい勢力の江戸期前後からの氏の家紋である。
4つの家紋は家紋掲示板に掲載します。
|
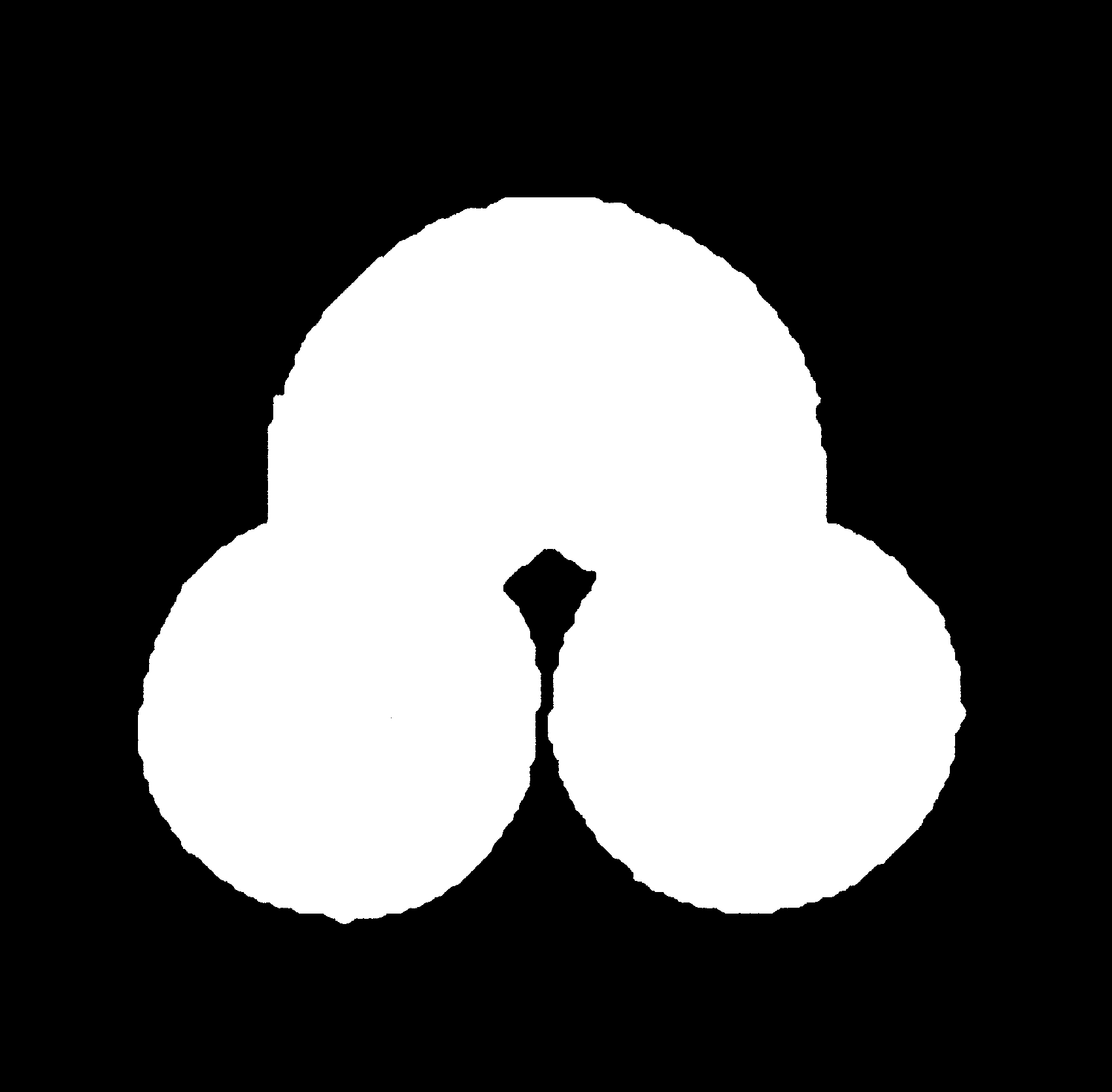
Re: 青木氏と血縁族(家紋)-10(州浜紋)
青木研究員 さん 2006/01/03 (火) 12:55
第9番目の紋様は州浜紋である。
この州浜紋には33の紋様がある。
この内青木氏に関係する紋様は5紋である。
家紋200選にも選定されている有名な家紋である。
この青木氏に関係する家紋は次ぎの通りである。
1番目は州浜紋である。
2番目は丸に州浜紋である。一番目の分家筋に当る。
3番目は三つ盛州浜紋である。
4番目は三つ盛蔭州浜紋である。
5番目は5瓜の州浜紋である。
5番目を除いて陸奥の小田氏一族の家紋である。
陸奥小田氏一族の流れを汲む青木一族である。
この青木一族は当然に陸奥の小田氏であるので、藤原秀郷一族の流れを持つ小田氏である。
この青木氏は陸奥に赴いた藤原秀郷の一門の守護に付き従い護衛役として入り定住し、土地の小田氏との血縁にてこの地に根づいた藤原秀郷の兼光系青木氏である。
兼光系青木氏は一度秀郷から18代目に男系の跡目がなく総宗本家の藤原秀郷の家から行久なる者が青木家の跡目を相続している。
上位の跡目相続であるので姓氏など変化しない事になるので青木氏は引き続き継承されている。これは藤原秀郷家にとっては藤原主要5氏のうちの青木氏であり、護衛役を担っている青木氏を潰すわけには行かず上位の総宗本家から跡目を入れたのである。
この陸奥には秀郷の総宗本家からの藤原兼光が守護として赴いている。
当然、この兼光は秀郷から4代目の兼光であり、上記した3回目の18代目の行久による跡目と、第2回目の兼光の跡目があり、初代の秀郷の3番目の子の千国から出た青木氏が鎌倉時代までこの3回の跡目が入っているのである。
初代の青木氏の系統は4、5代目程度までは男系の跡目を引き継いだが、兼光の所で跡目を総宗本家から入れて建て直し、兼光系青木氏が続いた。
其れまでは直系の千国系青木氏である。3回目の行久も兼光の子孫であるので
兼光系青木氏である。
藤原秀郷流青木氏は兼光系からのみ出ていないことになる。
この4代目の兼光が陸奥に赴いたときに自らの子孫の護衛役の青木氏を引き連れて陸奥に赴いたのである。
この兼光系直流の青木氏がこの陸奥に定住し土地の豪族の州浜紋を持つ小田氏と婚姻をし男系の継承問題で小田氏より跡目を入れて止む無く家紋掟により
家紋を変紋する結果となったものである。
これが藤原秀郷の4代目兼光の直系の青木氏の分家が陸奥にて青木氏を広げて州浜一族の小田氏との血縁関係を持った氏である。
直流本家は護衛役の任務を持つことで子孫を留保し武蔵と下野国にて藤原総宗本家を護る役目から赴任地の土地に留まらず帰国した。
これは直系、直流と支流の夫々の青木本家筋は戻っている。
多くは多くの嫡子以外の者が藤原氏の戦略として土地に残り護衛と子孫拡大の役目を担っていたのである。
藤原秀郷の総宗本家一門は鎌倉時代の前までに24の守護地とそれに類する官職で赴任している。
この陸奥も最初に朝廷より命じられた守護地である。
この守護地は当時まだ征夷の領域(東北北陸北海道の蝦夷を含む征夷地域はまだ十分には安定はしていなかった。)である。
そこで、第一の勢力を誇っていた藤原四家のうちの北家一族は北家の主家の摂関家との連携を取りながら、この征夷の護りとして出向いたのである。
朝廷から任じられた官位は「鎮守府将軍」であった。
この「鎮守府将軍」は代々藤原秀郷の一族の継承官位であった。
この官位は後に勢力を起した清和源氏の官位と変化して行くのである。
そして、江戸時代まではこの官位の無い者は幕府を開く事が出来なかったのである。
(豊臣氏はこのために関白の官位、徳川家康は家系譜偏纂にて源氏支流とを名乗り「征夷大将軍」の称号を得たが、朝廷は内々はこれを認めていなく、源氏頭領の称号は拒絶した。「源氏長者」として妥協した経緯がある。)
この「鎮守府将軍」から源氏の時代には変名して「征夷大将軍」と変わったのである。
「鎮守府将軍」は藤原秀郷氏、「征夷大将軍」は源氏の専属官位である。
清和天皇の第6位皇子の経基王が臣下して賜姓を受けた源氏の満仲の分家筋(総本家筋は嫡男頼光系 伊勢源氏など)の頼信の血筋を引く頼朝が鎌倉幕府を開く事が出来たのはこの官位の権利があったからである。。
この州浜紋の青木氏の元祖は藤原秀郷の4代孫の第1回目の跡目に入った兼光系初代の直流の青木氏である。
この陸奥より子孫を拡大した州浜紋の持つ一門の小田氏と青木氏であるが、この他にこの陸奥の藤原兼光一族との血縁を持った武田氏がある。
この藤原一門から同じ血筋を受けたこの地方の豪族であった菱紋の武田氏は藤原秀郷の総宗本家の赴任地の移動に伴い甲斐国に移動して、そこで勢力を上げて土着豪族との血縁関係を持ち大勢力に伸し上がったのである。
この州浜紋は小田氏のみと青木氏との血縁であるので判り易い。
この州浜紋の一族が後に三つ盛州浜紋と三つ盛蔭州浜紋に分流していくのである。
五瓜の州浜紋の一族は次の経緯を持っているものと見られる。
この州浜紋の一族が後に何らかの理由で四国付近に移動して五瓜紋の一族との血縁を持ったか、或いはこの五瓜紋一族が陸奥付近に移動し、この一族との血縁を持った結果で跡目継承問題で家紋を変紋せざるを得なかったものではないかと見られる。
(四国阿波付近には五瓜紋の氏が多い。 四国国境土佐郡土佐町には「土佐州浜紋」が確認できる。)
しかし、この瓜紋は藤原流の長良氏とその一門の肥前の大村氏が用いていたものである。
このことから土地柄からまた藤原北家一門とのこの長良氏との血縁ではと考えられるので、州浜一族がこの地方に移動してきて(時代は江戸初期か室町後期の発祥であることから)岐阜美濃付近の長良一族との血縁関係を持った一族ではとも見られる。しかし、確証は困難である。(四国か岐阜か北陸か)
主要紋を次ぎに掲示します。
(家紋掲示板に以上の家紋を掲示しますので参照して下さい。)
|
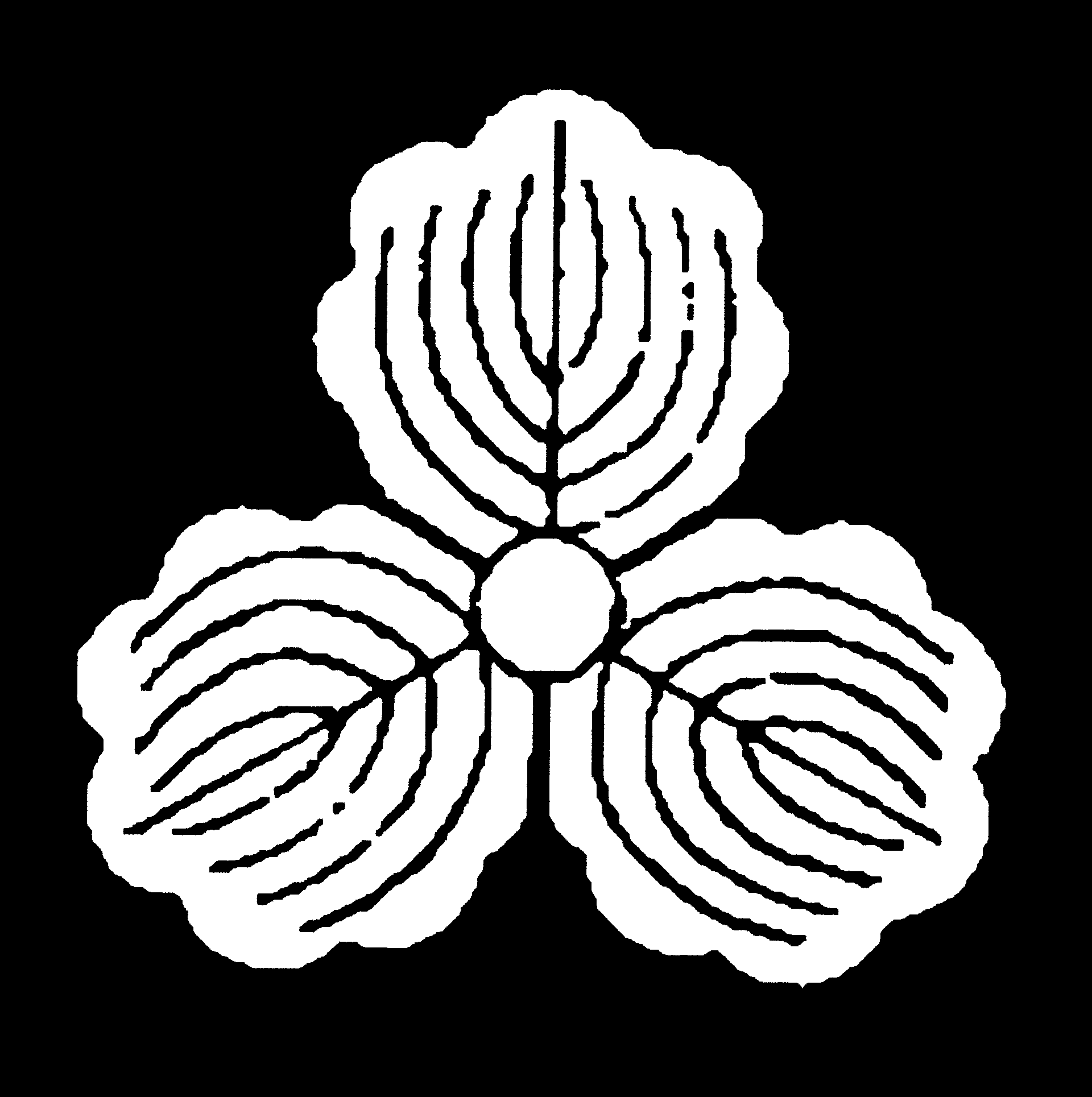
Re: 青木氏と血縁族(家紋)-9(柏紋)
青木研究員 さん 2005/12/22 (木) 19:21
第8番目の家紋の氏は柏紋である。
この家紋は132もの紋様があり、紋様としては大きい方である。
この内青木氏の紋様の数は6家紋である。
この家紋は家紋200選に挙げられている。
有力氏である。
この青木氏の家紋は次ぎの通りである。
第1は三つ柏である。
第2は丸に三つ柏である。第1の柏紋の分家である。
第3は牧野柏である。牧野氏の家紋である。第2の紋と良く似ているが丸の太さが異なる。
第4は違い柏である。
第5は丸に蔓柏である。
第6は二つ葉蔓柏である。
これ等の氏には第1と第2には山内氏と五味氏である。
青木氏はこのいずれかとの血縁を持ち家系問題上で家紋の変紋を長い歴史の間に実行せざるを得なかったものと思われる。
第3は当然牧野氏である。
青木氏がこの牧野氏との血縁を持ち家系問題上で家紋を変紋を長い歴史の間に同様に実行せざる得なかったものと思われる。
第4は星野氏、倉橋氏、嘉納氏、横地氏、中川氏である。
この青木氏はこの何れかの氏との血縁を持ち家系問題上で家紋を変紋を長い歴史の間に此れも同様に実行せざるを得なかったものと思われる。
第5は長田氏と山本氏である。第2の丸に柏紋の青木氏が蔓紋の氏との血縁にて家系問題上で変紋を実行せざるを得ずこの青木氏の氏系譜を明らかにするために二つの家紋の組み合わせの家紋とし、長い歴史の中で起こった現象である。
第6は単独の青木氏である。
この氏は青木氏一族の神職をして二つ葉の蔓柏紋を初期の段階で定めて跡目等の問題もなく男系で維持してきた一族で、この家紋を使用している他の氏は無い。
青木氏のみである。しかし5家5流系のどの一族かは不明である。
紋様の所以は次ぎの通りである。
勿論この紋様は柏の葉を図案化したものである。
柏は奈良時代から旅に出た時はこの柏の葉に飯を盛食べたとされるものである。所謂食器の代わりにつかったもので、万葉集にも多く載せられているものである。
有名なところでは中大兄皇子(大海人皇子)(天智と天武)と皇位争いで戦い和歌山の海南市藤白峠で死んだ有間皇子のこの時に読んだ歌がある。
家に居れば飯盛るしいも草枕、旅にしあればしいの葉に盛る。(しい:柏)
解釈
柏の葉は関東と関西では異なり、関西ではこの柏の葉の役目をする葉は丸く掌くらいの大きさの葉で表面がつるとしているが、おおきくて幅広で細長い葉の柏の葉ではない。
しかし、関西では餅や握り飯を包む葉は”かしわ”と呼んで用いられている。
矢張り神聖な葉として今でも3月や5月の祝い事には扱われている。
ここで云う”椎の葉”は親指くらいの葉であり飯(いい)は盛れない。しかし、”道端にある椎の木を読み込んでの旅の情景”と”いい(飯)”と”しい(椎)”と”柏”とを架けて神聖な木を用いて心の歌の情景を詠んだものである。
歌心は”私は決して皇位を望んでいない。神聖な心である”意を含めているのである。
この意味から柏の葉は神聖なものとして神木として扱われていたので、朝廷の神職に関わる氏の家紋は柏紋としたものである。
この氏には朝廷神官職の官僚の吉田氏と、熱田神宮の千秋氏と、宗像神宮の宗像氏と、備前の吉備津神宮の大守氏がある。
他に皇族賜姓族として青木氏に関わる神職として青木氏と佐々木氏が有名である。
この青木氏や佐々木氏の氏は神職は朝廷関係の神職である。
研究室にもレポートしたが、この系統の青木氏が上記の神職関係の血縁から家系上の問題で三つ柏紋に家紋を変紋しものとみられる。
従って、この青木氏は皇族賜姓青木氏の血筋を持つ5家5流の支流青木氏の青木氏である。
当時は皇族賜姓青木氏と藤原氏との高位の氏はは専門に一族だけを祭る菩提寺と合わせて、神社をも持っていた。
この神社を自らの一族が神官として司っていた。そして、この神社は5家5流の夫々の神社があった。
藤原氏は佐々木氏の神官が多い。今でも佐々木氏の神官が藤原氏を祭る神社の神官として存在する。
藤原氏の神職が何で源氏一族と青木氏一族の血筋を持つ佐々木氏であるかは別レポートとする。
この氏らの家紋は三つ葉柏を基本としている。
上記のようにこの紋所は神職の紋所として使用されていた。しかし、後に江戸期に入って葉数や形や他の家紋との複合紋として使用されるようになったのである。
葉の数は9つまである。
そしてこの家紋を使用した氏は殆ど132氏はこの上記の神職との血縁関係からこの家紋を用いたものである。
NHKの大河ドラマの山之内氏もこの千秋氏との血縁関係からこの家紋を出世の時に用いたものである。
戦国時代をのし上がった多く者は江戸時代に家紋を定める必要から一族は自己の古い言い伝えなどから家紋を定めたものであり、その紋様に近い家紋を作った。
主要で有力な家紋200選以上の家紋はこの室町から江戸に架けての家紋である。特に江戸期には下級武士と御家人が多く定めた。
この原因の一つは江戸幕府はこれ等の武士に宗派を定めることを政治上から勧めたのである。
特に最も少なく厳格にその階級派を守ってきた浄土宗には江戸幕府は御家人の武士階級には力を入れた。
そのことから影響を受ける事で家紋を定める事にて家系の維持と尊重を推奨し政治の安定を目指したものである。
この柏紋の青木氏は5家5流の青木氏の血統を持つ支流青木氏である。
この青木氏の中には二つ葉に蔓柏紋の青木氏があるのはこの神職氏の一統である。
この様にこれらの6つの家紋の青木氏は青木氏の神社の神官職の一族で血縁関係も他の氏の神職との間で行われて子孫を拡大した。
ここの6つの青木氏の家紋は家紋掲示板に掲載する。
三つ柏の主要紋は次ぎに掲げます。
|
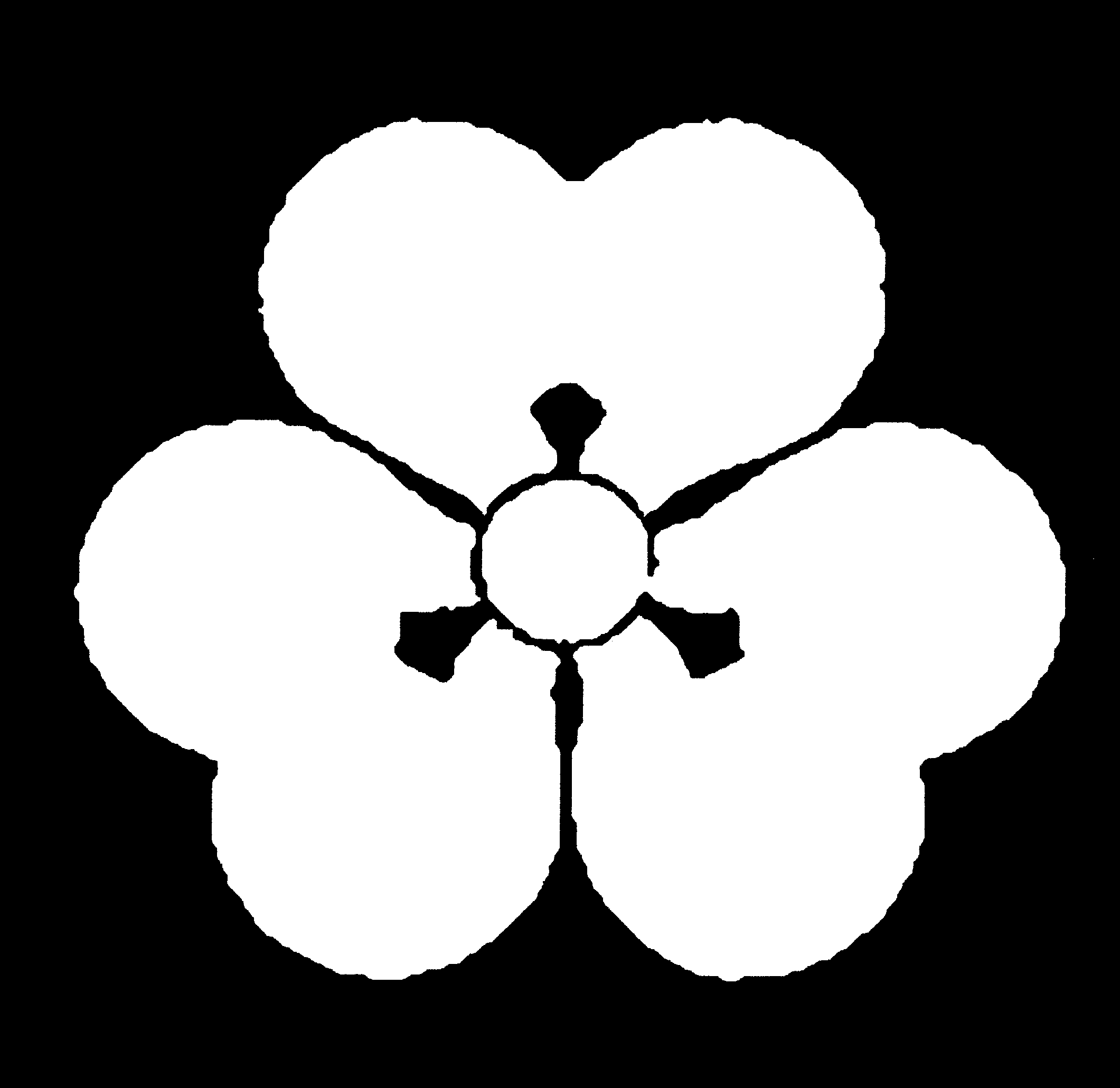
Re: 青木氏と血縁族(家紋)-8(片喰紋)
青木研究員 さん 2005/12/17 (土) 19:58
片喰紋は125の紋様があります。
この内青木氏の片喰紋は6紋です。
この氏は大変に多い氏がこの紋様を使っています。
家紋200選にもある氏です。
この青木氏の紋用は次ぎの通りです。
第1は片喰紋です。
第2は丸に片喰紋です。この家紋は第1の分家に当ります。
第3は隅入り平角に片喰紋です。
第4は丸に剣片喰紋です。
第5五瓜の剣片喰紋です。この家紋は第4と同じ片喰紋のなかの剣片喰の一族です。
第6は子持ち亀甲剣片喰紋です。この家紋も第4と第5の剣片喰一族です。
以上が青木氏の家紋です。
参考のためにこの紋様を家紋としている氏は次ぎの通りです。
この氏は本家の片喰一族と剣片喰一族の各氏です。
島津氏、堀越氏、岡田氏、本田氏、鳥山氏、太田氏、山田氏、武田氏、早川氏、竹本氏、河村氏、長谷川氏、中村氏、宮本氏、中原氏、中沢氏
これ等の氏は主に藤原秀郷一族の流れを組む支流一族と考えられます。
特にこの長谷川氏と中沢氏は藤原秀郷の主要5氏の一つです。
更に剣片喰一族はの宗家は酒井氏の代表家紋である。
第4と第5と第6の剣片喰紋の一族は江戸時代に大大名であつたこの酒井氏一族との婚姻により家紋を剣片喰紋としたものである。
藤原秀郷一族の護衛役の藤原秀郷流青木氏の支流子孫が家系の問題(男系の断絶問題等)で止む無く家系を維持する目的から家紋を変えざるを得なかったものと考えられる。
その後、木瓜紋の氏と又亀甲紋の氏と血縁関係を持ち、矢張り家系問題で家紋を剣片喰紋に木瓜と亀甲紋を加えて家紋として維持してきた一族である。
剣片喰一族は藤原秀郷一族として武蔵の国入間郡を中心に関東一円を取り巻くように護衛親衛隊役として守っていた。
特に、この一族関東の八王子方面を役務として其処に一族は根を降ろしていた。
武蔵の国の入間に近いほど直系1氏、直流4氏、支流4氏の本家筋が二重、三重に取り囲む態型を採っている。
それら9氏の116氏に及んだ支流一族は藤原秀郷の本家の朝廷の赴任先24地に赴くの連れて護衛役として付き従った。
そして、赴任地でその一族の者と土地の氏との婚姻を持ち土地に根付き子孫を遺してきたものである。
五瓜紋と子持ち亀甲紋の剣片喰紋の氏はこの根付き組み一族である。
第5の五瓜の剣片喰は阿波国に赴いた藤原秀郷の総本家一族の宗政と時政の親子の赴任に伴い護衛役として付き従った藤原秀郷の支流剣片喰一族の者の子孫である。この一族剣片喰一族の分家の丸に剣片喰一族と縁者関係にある。
丸に剣片喰一族は丸に片喰一族の本家として八王子に残ったもので五瓜の剣片喰一族の本家筋に当る。
片喰一族の藤原秀郷の一族の同門の片喰紋を使用する中沢氏系との血縁関係を持った一族である。
第2の丸に片喰紋の一族はこの分家筋に当る氏である。
同じく第3の隅入り平角に片喰紋もこの中沢氏との支流血縁族である。
この片喰紋は上記の通り本家片喰一門と支流剣片喰一門の2つの流れになる。
片喰族と剣片喰族の藤原秀郷流青木氏である。
前者は中沢氏一族との血縁族、後者は酒井氏一族との血縁族である。
中沢氏と酒井氏は両者とも室町期から江戸期までの豪族である。
この片喰紋は鳩酸草とも云う。
この紋様は平安期から使用されている紋様である。
この紋様は三つ葉が基本である。葉の数は1から7まである。他の紋様と組み合わせて家紋としている紋様としては最も多いものである。
公家も使用した。
大名では160もの者がこの紋所を使用した。
桐紋などの植物紋としては最も流行した。
この家紋に付いては家紋掲示板に記載します。参照して下さい。
主要紋を左隅に載せます。
|
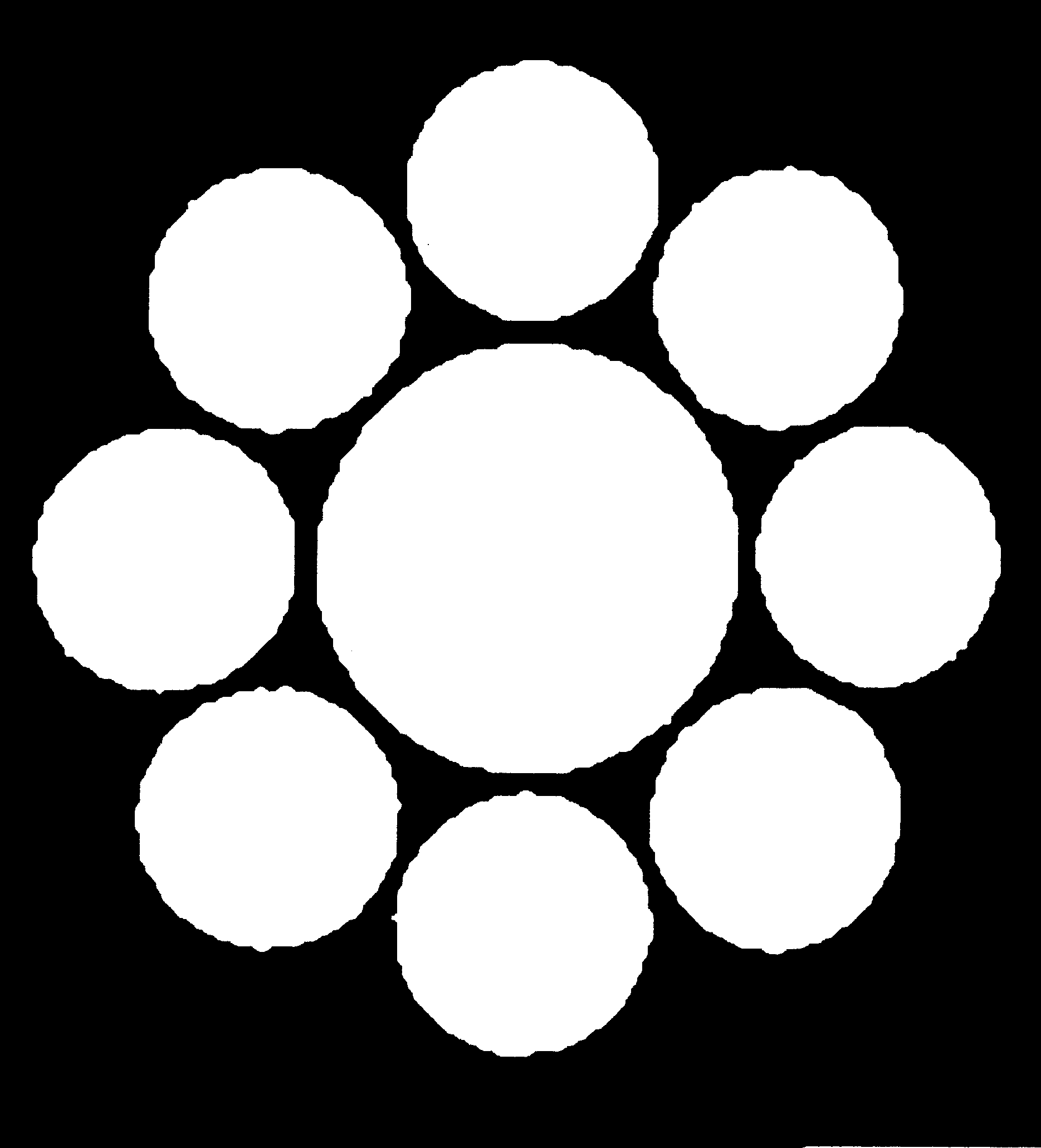
Re: 青木氏と血縁族(家紋)-7(星紋)
青木研究員 さん 2005/12/13 (火) 21:02
第6番目の家紋は「星紋」である。
この紋は全部で71家紋あり、この内青木氏に関係する紋様は6つである。
この家紋は家紋200選に選択されている。つまり、歴史ある有力な氏である。
この氏の8つの家紋は次ぎの通りである。
第1には九曜紋である。
第2には丸に九曜紋である。この家紋は第1の分家に当ることになる。
第3には三ツ星紋である
第4には丸に三つ星紋である。この家紋は三つ星紋の氏の分家筋に当る一族である。
第5には三つ星に一つ引き紋である。
第6には亀甲に三つ星紋である。
第7には扇に三ツ星紋である。
第8には長門三ツ星門である。
以上が青木氏の家紋である。
この8の家紋は2つの氏に分けられる。
一つ目は九曜紋と二つ目は三つ星紋である。
九曜紋は家紋掟により本家筋と分家の家紋と言うことになる。
丸に三つ星紋は三つ星紋の分家筋に当る一族である。
そして、この一族と足利系の支流一族との血縁関係を持ち、何らかの理由(嫡子が無いか、養子縁組か、戦略的な跡目を受けたか等)にて家紋を変えざるを得ない仕儀に落ち至ることになったために家紋が変わったと見られる。
氏家制度では男系相続であり、厳格な家紋掟があり、この結果、元の家紋を引き継ぐ事が出来なかったもので、現在と違い寿命も50と短く、又嫡子が生まれても生存率が低く、戦死や、嫡子に値しない場合などで抹殺されるなど死することが多かった。このため家を維持するという事は最大の命題で本家や宗家にとっては大変なことであつた。
男子が生まれても成人時に一族郎党をまとめていく能力が無い場合は多くは排除されると言うことが起こった。その者に依ってその一族全体の運命が決まるのであり、自分たちの運命も左右する事であるからである。
この歴史的な有名な史実は数え切れない程にある。
参考に日本だけではなく蒙古などはもっとはっきりしていたのである。
蒙古ような集団指導体制のなかでは首長の子供と云えど掟で殺されるのである。
義経のジンギスカン説はこの掟によりその後に後継者がなくなり、天から降りてきた者が一団の指導者となったと記されている。蒙古では其れまでの指導者の系譜が明確であるが、この時だけは天からと記されているこの時期が義経の生きた1192年ごろの出来事であり、またこの指導者の紋所は殆ど笹竜胆と酷似しているのである。
その者は武術に優れ戦いに長けいつも軍団の先頭にたって戦いに臨んだとある。しかも、この者にはいつも二人の家来がつき従っていたとある。
話は戻して
第1の九曜紋の氏には土屋氏、松平氏、相馬氏、戸田氏、松平忠興等の一族がこの紋所を使用していた。
この九曜紋の分家である第2には戸沢氏、吉川氏、細川氏、伊藤氏、千葉氏等である。
青木氏ではこの九曜紋は武田系青木氏の支流一族が使用していた紋所である。
従って、第1と第2は武田系支流青木氏である。
皇族賜姓青木氏の血筋と源氏の血筋を引く武田系青木氏である。
この一族一団は後の徳川時代にも大いに出世する。
第3の丸に三つ星には児島氏がある。
第5の三つ星に一つ引き紋には渡辺氏がある。
この星紋は家紋200選にもあるが、歴史的には新しい家紋となるが、
この紋所としては一字紋つきで毛利系、とその一族吉川氏の使用紋である。
この毛利氏などの一族と青木氏との関係はない。
判断は難しいが、中国地方に多い家紋であるので平家の一門と見られるがこの平氏からは規則を遵守した平家には青木氏は出ていない。
とすると、岡山や広島に藤原秀郷一族の者が朝廷の官職で赴任し、それに動向した護衛役の青木氏の史実があるのでこの子孫を広げたと推測する。
この青木氏が上記した跡目の問題で家紋を変えざるを得なかった結果、縁組でこの家紋の使用となつたものと思われる。
つまり、この星紋様は前四つは武田氏系青木氏と、後ろ四つは藤原秀郷青木氏の家紋と見られる。
この星紋の紋様の発祥はもとより北斗七星への信仰から生まれた紋様である。
星門の主要な紋所を次ぎに掲示します。詳細は家紋掲示板に掲載します。
|
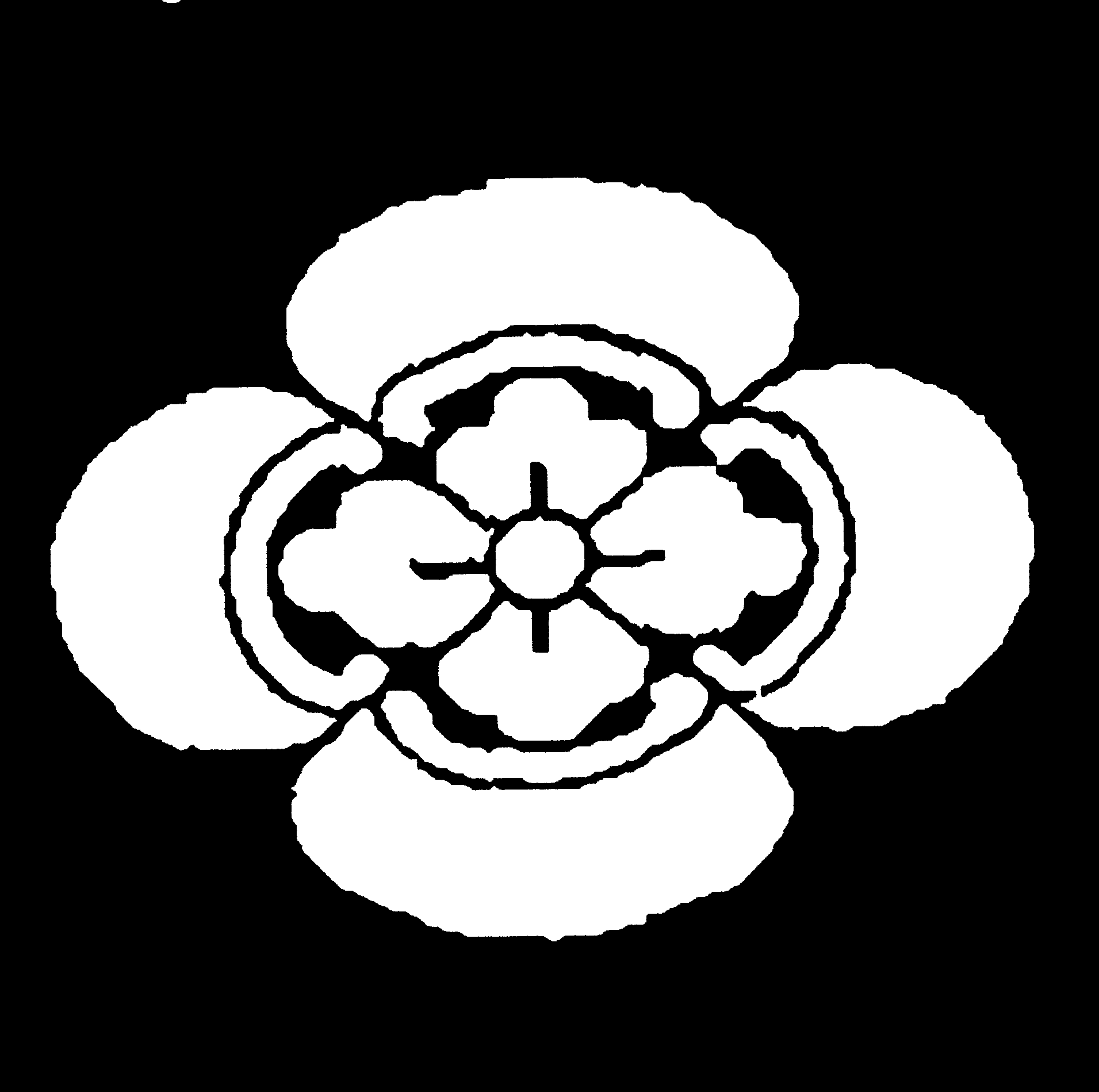
Re: 青木氏と血縁族(家紋)-6(木瓜紋)
青木研究員 さん 2005/12/09 (金) 19:52
第5番目は木瓜紋である。
この木瓜紋は全部で87の紋様がある。
家紋200選にある家紋である。
この木瓜紋の青木氏の家紋は87の内6紋である。
この家紋は次ぎのとおりである。
第1は木瓜紋である。
第2は丸に木瓜紋である。第1の木瓜紋の分家である。
第3は横木瓜紋である。
第4は丸に横木瓜紋である。第3の横木瓜紋の分家である。
第5は糸輪に陰木瓜である。
第6は五つ木瓜である。
以上が青木氏の使用している家紋である。
第1、第2の木瓜紋と丸に木瓜紋は次ぎの氏が使用している。
日下部氏、伴氏、紀氏である
この3つの氏は共に奈良朝期の有力部族である。
新しいところでは関口氏、平賀氏、野村氏が使用している。
第3、第4の横木瓜と丸に横木瓜は次の氏が使用している。
田中氏、大原氏が使用している。
この家紋は木瓜紋を横に伸ばしたものである。唐花木瓜とも言う
此れに対して竪木瓜がある。
第5の糸輪に陰木瓜は次ぎの氏が使用している。
竹内氏、岸氏、堀氏、馬渕氏が使用している。
第6は五つ葉の木瓜紋である。
通称織田木瓜とも言われている。
織田氏が使用していたのであるが、普通の木瓜紋は4つの葉である。
この木瓜紋は通常ボケの花の紋様をデザインしたものであると云われているが別の説もある。
胡瓜の切り口とも言われている説もある。
一般的には天皇の座にある御簾の部分に使用されているのを紋様化したものと考えられている。
このことから奈良時代に色々なもの例えば車紋に使用されていたもので、天皇家の権威紋や象徴紋と皇族賜姓青木氏の笹竜胆紋や他の紋様と同様に奈良末期から平安初期に家紋扱いとして用いられ始めた。
一般的には多くの家紋は保元、平治の乱以降の公家や上位の武家が使用し始めたのである。
この意味では天智天皇の皇子(施基皇子)から始まった皇族賜姓青木氏の伊勢青木氏の綜紋(5家5流の青木氏)は天皇家に次いで早い家紋使用となる。
矢張り賜姓であるので当然とも考えられるが、どちらかと云うとこの5家5流の青木氏の綜紋を経緯に皇位系にあるの豪族は家柄を誇示し権威を強調する目的からこぞって使用し始めたと見る。
その証拠に第5番目の天皇の賜姓青木氏の後の天皇は自分の母の実家の阿多倍の高尊王の京平氏を賜姓した桓武天皇であり、この頃から家紋や象徴紋や権威紋など律令制度の完成で次々と定められた経緯がある。
参考
(殆どの家紋の文献はこの時期からの資料をもとに編集されているが、この時期前の家紋の使用の研究資料は少ない。
しかし、この時期前の天皇から賜姓を受けた氏は慣例からこの賜姓を明示することから3つのことを行うのが義務である。
この賜姓族は氏を示す綜紋として保持していたのである。
司馬遼太郎氏等の歴史家がこの史実を表している。
この時期前に受けた賜姓族(数は少ないが)例えば青木氏や藤原氏や大蔵氏や内蔵氏や坂上氏等の高位の氏は賜姓を示す綜紋(ソフト)と、そのステイタスを証拠を示す拝領の仏像等(ハード)と氏神と菩提寺の神社仏閣の建立の3義務が伴うのである。
それだけに賜姓を受けることはそれだけの力を保持している者に下されるのである。この事に付いては笹竜胆の家紋のところで詳細をレポートする。)
又、天智天武の時代から天皇家の天皇の紋や天皇家の家紋や権威紋や象徴紋や車紋等多く定められた。これは後漢の阿多倍王の一族の影響が働いたのでは考えるし、この律令政治と制度の完成はこの一族が朝廷に入り、中国の漢の国の知識を導入したことから始まっているのである。
(参考 阿多倍は天皇家との血縁関係を持ち、その子供は大蔵氏、内蔵氏、坂上氏の賜姓を受けて官僚のトップに立った事と朝廷の3つの官職の3蔵内の2蔵と軍事とはこの3人の者が担ったのである。3蔵とは大蔵と内蔵と斎蔵でその役職から賜姓を受けた。斎蔵は藤原氏)
桓武天皇から子供の嵯峨天皇からは賜姓を元に戻して青木氏を変名して源氏として戻した。そして、綜紋を天皇から与えられた青木氏の綜紋と同じ笹竜胆紋とした。その後の16代の源氏は笹竜胆を綜紋としたのである。
そして、元の青木氏の姓と綜紋を皇族のみが使う氏姓の紋として嵯峨期に禁令を発したのである。
その後、阿多倍の子孫の京平氏は摂関家の藤原氏を押さえて5代で清盛の太政大臣に上り詰めたのであり、この京平氏が車紋などに紋様を多く使い始めたことから爆発的に拡がったことが資料では確認出来るのである。
従って、家紋の使用の始まりは青木の綜紋から起こり現代の8000とも言われる家紋数ともなつたのである。
余談であるが、この家紋と同時にステイタスとしての仏像を持つ事も皇位の者の象徴と権威を示す手段となつたのである。
皇族賜姓青木氏にはこの仏像を保持している。5家5流の初代の伊勢青木氏宗家本家が現在も保持している。
(後日このレポートを研究室にこの仏像の写真と共に掲載します。賜姓青木氏系24氏のステイタスです。)
この木瓜紋は24氏のうちの武田氏系、足利氏系、土岐氏系の3氏のうちのどれの家紋かということであるが確定は困難である。
しかし、家紋の分布と、武田氏と足利氏とは藤原秀郷系であるのでこの氏にはこの家紋は余り見られないこと、朝倉氏が使用していることの3つのことから美濃国の土岐氏系青木氏の支流紋であると見て間違いはない。
現にこの木瓜紋は朝倉氏や織田氏が使用していることが有名である。
この家紋の多くは真ん中に唐花を入れるのが普通である。この理由は古来の中国の官僚の服の模様に使用したとされているためでこの唐花紋を使うのである。
それと竪と横の形、外側の葉の枚数の数で変化させる。葉数は5から8枚である。
木瓜紋以外の4家紋は比較的新しい氏の紋様で下克上と戦国時代以降に生まれた氏の家紋である。
従って、第5と第6の紋様の青木氏の出自は確定は難しい。
第1から第4までの青木氏の紋様は上記した古代氏の紋様であるので皇族系と賜姓青木氏系の出自である。(詳細は皇族賜姓青木氏を参照)
嵯峨天皇期に定められた青木姓の禁令の適用外の氏として源氏を含む皇族賜姓青木氏は直系の5家5流の家紋は笹竜胆の家紋である。この皇族賜姓青木の血筋を受けた武田氏系青木氏、足利氏系青木氏、土岐氏系青木氏の3系と、3系の支流青木一族24氏の持つ家紋の一つである。
時代は戦国時代になるが、信長に滅ぼされた朝倉氏は村上源氏の支流とされているので五つ木瓜紋は青木氏系の家紋と一致する。
6つの青木氏の木瓜紋様の代表紋を次ぎ左隅の家紋である。
6つの青木氏の家紋は家紋掲示板に掲載しますので見てください。
|
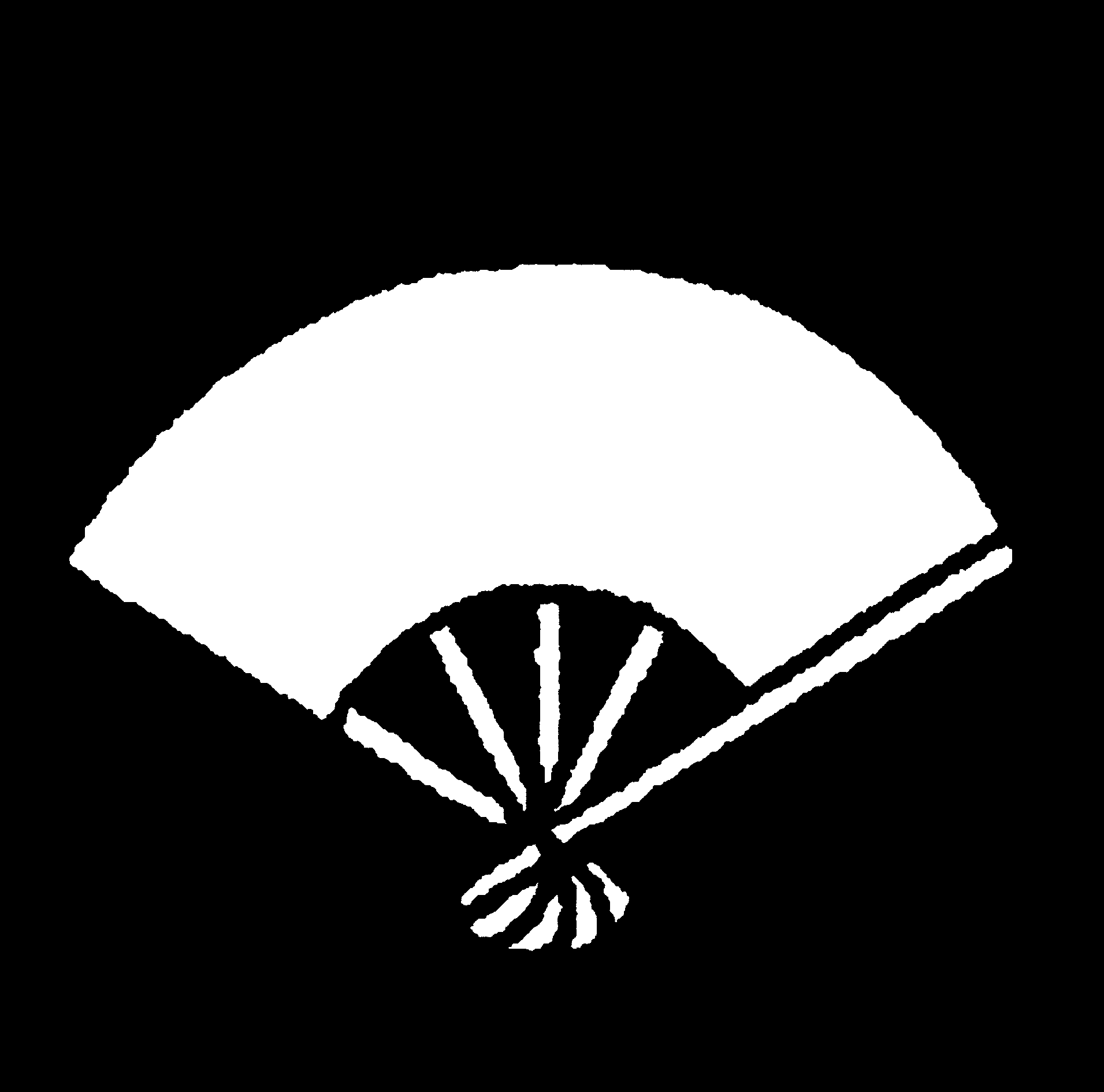
Re: 青木氏と血縁族(家紋)-5(扇紋)
青木研究員 さん 2005/12/05 (月) 19:19
第4番目は「扇紋」である。
この紋様は89紋あり、この内青木氏は6紋である。
家紋200選の一つである。
この家紋は各地に松平氏があるがこの内、松平深溝氏の綜紋である。
この血縁を受けた一族である。
この6紋は次ぎの通りである。
「扇紋」、分家の「丸に扇紋」、「丸に違い扇紋」、「丸に並び扇」、
「隅切り角に扇紋」、「丸に日の丸扇」
以上が青木氏の扇一族の家紋である。
比較的に新しい一族である。
この紋様は末広の意味として用いられていて「子孫が発展」の縁起を期待しての家紋である。
そして、開き扇と閉じ扇がある。
扇紋は扇の骨の数によって氏を見分けられるようになっている。
ちなみにこの家紋を使用しているのは、元々は松平氏の前には佐竹氏が最初である。5本骨と月を組み合わせたもので家紋としていた。
松平氏は3、5、7本骨で、雨宮氏は10本骨、飯室氏は5本骨の黒餅
である。
この青木氏は何れの青木氏か確定できない。
皇族賜姓青木氏か藤原秀郷流青木氏かは資料による検証でも鎌倉以前の出自が不明であったとしても矛盾がある。
松平一門であるのであるが、戦国時代の皇族賜姓青木氏(5家5流系青木氏を含む)動向と主要藤原氏の鎌倉時代の衰退によりその仕官先は大方は徳川家系の藩に仕官していること、各地の松平藩系との血縁を結んでいることから藤原秀郷流青木氏の116氏の支流一族の一つとみられる。
6氏の扇紋の関係についても不確定である。
ただ家紋掟から見て扇紋と丸に扇紋は親族関係である。
以上の家紋6つは家紋掲示板に掲載しますので参照して下さい。
主要の扇紋は次ぎの紋です。
|

Re: 青木氏と血縁族(家紋)-4(藤紋)
青木研究員 さん 2005/11/22 (火) 11:10
第三番目は「藤紋」である。
この藤紋は144もの紋様があり、この内青木氏の紋様は6紋である。
当然、この紋用は家紋200選にもあり、最も巨大一族である藤原氏の紋様である。
しかし、この紋様は藤原氏の家紋とされているが、現実に藤原一門の一族がこの紋様を使用したかというとそうではないのである。
と云うのもこの紋様には藤原一族として嫌う事があり、次第に家紋として使わなくなった。その嫌う事とは、藤原一門は「下がり藤」紋であるのだが。「下がる」という意味を嫌ったのである。一門の繁栄に陰をさすという事である。
以前にも記したが藤原一門には四家の家がある。最も栄えた北家と京家、式家、南家がある。夫々が勢力争いをして、結局、北家が生残る。
この北家の内、藤原秀郷の一門がこの下がり藤紋を使用した。
公家の中でも元来武家的な性格の持つた秀郷の一門がこの紋を使用したのである。
この四家の藤原氏は多くの支流子孫を遺したが、この地方に分散した子孫はこの藤紋を変化させた家紋を作り、144紋までになった。
特に江戸時代にはこの末梢子孫が名乗りを挙げて藤原氏を名乗って家紋を藤紋にした経緯がある。
元は「下がり藤紋」が後に述べるが歴史的には原型とされる。
次に藤原秀郷流青木氏の家紋を広い出すと次の様になる。
藤原氏の青木氏には直系1氏、直流4氏、支流4氏の9氏がある。ここから分派分流して116氏にもなったのである。
第一に「下がり藤紋」である。
云わずと知れた藤原秀郷直系一族の家紋である。
直系の藤原秀郷第3子の千国流の直系青木氏である。
藤原秀郷の青木氏の宗家である。武蔵の国の入間付近を居住地域していた。
この青木氏たちは武蔵の国を入間を中心に周囲を取り囲む様に各青木氏が守っていたのである。この中心にいたのが直系の青木氏である。
元来、この藤原秀郷流青木氏の支流は揚羽蝶と副紋などの家紋を使っているのである。
この家紋を使っている氏としては北家の代表の九条氏である。
第二には「上り藤紋」である。
秀郷流直系青木氏流れを持つ一門でもこの「下がり紋」を嫌い途中で「上り藤紋」に家紋を変えた一族が居た。
第三には「上り藤上一紋」である。
第二の青木氏の一族が官職で地方に赴任して移動した一族が子孫を繁栄させて後に家紋を判別させるために「上一」の紋様を追加したのである。
藤原秀郷直系の青木氏の分家となる。
第四には「下がり藤に州浜」である。
この一族は後に「州浜紋」を持つ陸奥の小田氏との血縁関係を持つ藤原秀郷流青木氏である。
この小田氏は元は陸奥の国の守護をしていた藤原秀郷の一族の血筋を引く一門である。
後に、州浜紋の頃で述べるが、更にこの小田氏の家紋の「州浜紋」を持つ藤原秀郷流の青木氏も存在するのである。
藤紋系の州浜青木氏と州浜紋系の青木氏とが存在することに成る。
元は藤原一門である。
第五には「対四つ藤紋」である。
第三の青木氏と同様に、地方に赴任して子孫を繁栄させて一門を構え、家紋を変化させたものであり、直系青木氏の分家支流紋である。
第六には「加藤藤」がある。
これは秀吉の家来の加藤清正の家紋である。
藤原秀郷流の血筋を持つと名乗った加藤清正が用いた家紋であるが、この家紋を持つ青木氏とは藤原秀郷流青木氏の一族の支流分流は不明であるがこの加藤氏の一族との血縁にて「加藤藤紋」を家紋掟の要領にてこの紋を採用したものと考えられる。
藤原秀郷の直系の青木氏には「下がり藤紋」を引き継いだ青木氏と、平家の家紋の「揚羽蝶紋」を引き継いだ直系青木氏がある。
この後者の青木氏は、千国の嫡男の「下がり藤紋」に対して、分家をした次男の者が母方の家紋を引き継いだ「揚羽蝶紋」の家紋としている。
特に、この同じ直系でも「下がり藤紋」の青木氏に比べて、この揚羽蝶紋の藤原秀郷流の青木氏の一族の支流が繁栄した傾向がある。
以上六家紋の氏が藤原秀郷流直系青木氏の子孫である。
この「藤紋」の謂れは次のとおりである。
この紋様は、藤の葉と花を図案化したものであるが、平安朝に特に好まれた花でこの藤の花を万葉歌に読まれている。
丁度、醍醐天皇の時代にあたる頃で、このブームとなつた時期に藤原氏はこの藤花紋様を好んで紋様化して用いていた。そこから、藤原氏の家紋化したものである。
この様な経緯から全ての藤原氏の家紋となり得なかったもので、歌の好きな公家の藤原氏系の九条家とか二条家が使用したのである。
藤原秀郷はその昇進の経緯から、特にこの公家藤原氏の一門である事を誇示する意味からも、藤紋を使用し、九条家の流れを汲む秀郷としては「下がり藤紋」を強固に用いたものである。
特にこの一族の近藤氏、後藤氏、斎藤氏、加藤氏などがこの紋様を用いた。
前記したようにこの紋様は江戸時代には爆発的に用いられた。
藤紋には、花の房を変化させて家紋を作る方式と、藤の形とで変化させる方式と他ノ家紋を加えて家紋とする3つの方式がある。
藤原秀郷流青木氏の主要紋の「下がり藤紋」である。
青木氏の6つの「下がり藤紋」は家紋掲示板に記載します。
続く。
|
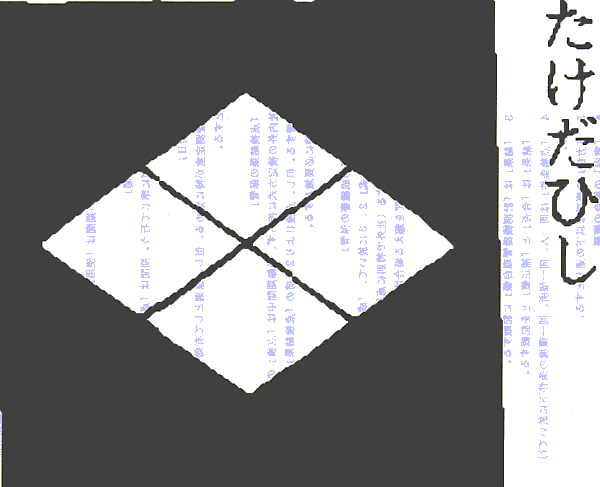
Re: 青木氏と血縁族(家紋)-3(菱紋)
青木研究員 さん 2005/11/16 (水) 20:37
次は「菱紋」の青木氏である。
この「菱紋」には10の青木氏の家紋がある。
この文様は3つに分類されます。
一つは武田菱紋です。 これには5つの文様があります。
二つは割り菱紋です。
三つは唐花紋です。(花菱紋)
この菱に関する紋様は101の紋様がある。
家紋200選に選ばれている。
この紋は武田一門の代表紋である。
この一族の青木氏は以前のレポートで詳細を記しましたので除いて、菱紋としては101氏もあり、大方は武田系の一門の家紋であるが青木氏はこの内10氏である。
この青木氏に関するルーツは次の通りである。
賜姓青木氏と陸奥の国に赴任していた藤原秀郷の一族の血縁を受けた一族が甲斐に赴いて付き従い、その地で勢力を高めて豪族となり、賜姓青木氏と婚姻関係、更に清和源氏の頼光一族の跡目相続など行った。
この賜姓青木氏との武田氏との婚姻にて生まれた武田系青木氏が武田氏の多くの一門と婚姻を続け10
氏の武田系青木氏が生まれた。この9氏の家紋が次の家紋になる。
先ず、第一の家紋は、「割菱紋」である。
この家紋の氏は栗原氏、岩出氏、岩手氏、駒井氏、今井氏等が使用している。
このいずれかとの氏との血縁による青木氏である。
この家紋は第四の家紋の武田氏系青木氏の支流の分家の青木氏が使用している。
第二の家紋は、武田氏支流の「三階菱」の氏との血縁による武田支流系青木氏である。
第三の家紋は、「丸に三階菱」の青木氏である。第二の分家に当る。つまり武田氏の支流の三階菱の青木氏の更に支流である。
この家紋は他に曽根氏、近山氏、斎藤氏、五島氏、早川氏、今福氏とのいずれかと血縁を結んだ青木氏が使用している。
第四の家紋は、「武田菱」である。本家の武田氏の家紋である。賜姓青木氏と血縁した最初の主家の青木氏である。
第五の家紋は、武田氏支流の「剣花菱」である。この家紋は溝口氏と血縁を結んだ青木氏の支流紋である。
第六の家紋は、第五番目の青木氏の支流の支流「丸に剣花菱」である。この家紋は溝口氏の分家と血縁を結んだ青木氏の支流紋である。
第七の家紋は、武田氏の支流の「松皮菱」である。この家紋はこの武田氏と血縁を結んだ末裔青木氏の支流となる。
第八の家紋は、武田氏の支流の「丸に一つ目菱」である。この家紋はこの支流武田氏と血縁を結んだ末裔青木氏の支流となる。
第九の家紋は、「四方瓜に重ね菱」の末裔支流青木氏である。
第十の家紋は「花菱紋」と丸付き紋のその分家支流紋である。
この文様は儀式用として用いていたものが、武田氏の支流末裔末孫が家紋化したものである。
元はこの家紋の紋様は織物の模様から作られた家紋である。
池などに浮かぶ食物の菱の形に似ているので菱と呼ばれた。
この菱紋(割り菱紋含む)と、中国から伝わった花唐紋様の菱紋様との二つがある。
この花菱紋と武田氏系一族などの食物の菱の家紋とは別門で大内氏の代表紋であるので、二つに分けられる。
しかし、武田氏の一門にもこの花菱紋を紋様を家紋とする一族がある。大内氏との血縁による武田氏系大内氏一族である。
武田氏系青木氏の主家を始めとして分家と支流一門の家紋である。
多くの武田氏の一族一門と武田氏系青木氏の主家とその支流一族一門との血族関係の家紋である。
武田菱紋には丸付き紋は家紋の菱紋を変紋することで支流紋としているので原則としてない。
あるとすると其れは明治以降の第3の青木氏の家紋類と成る。
この賜姓青木氏の血筋を持つ家柄であるので、この青木氏等は武田氏一門との血縁だけで血筋を保ったものである。
各家紋は家紋掲示板に掲載するので参照して下さい。
菱紋の代表紋
続く。
|
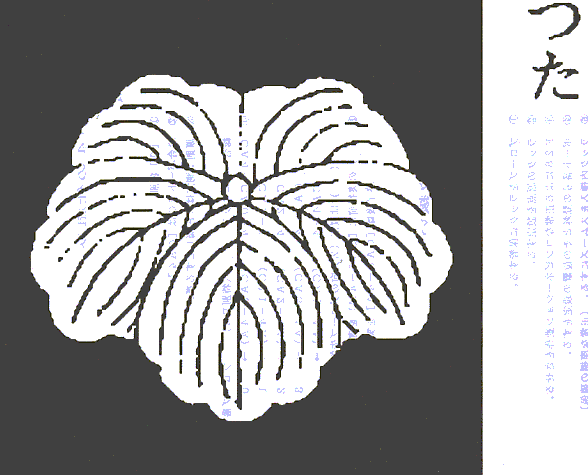
Re: 青木氏と血縁族(家紋)-2 (蔦紋)
青木研究員 さん 2005/11/12 (土) 19:45
日本の青木氏を家紋別に分けてみると33種になる事が前レポートで判断出来るが、この家紋種の一つ一つには又違う家紋になっていて、支流、分派などで変化しているのでこの内容を次に記述する。
先ず、最も多い家紋種は「蔦紋」である。この「蔦紋」には8種に家紋に分けられる。
蔦紋の種類
1は「蔦紋」の青木氏である。
この蔦紋は松平三木氏と松平石川氏の2氏の主要家紋である。
いくつかある松平氏の中でこの2氏の松平の一族はこの家紋を使っているが、この中で青木氏もその一族である。
この青木氏のルーツは賜姓青木氏か藤原秀郷流の青木氏かは確定は困難で判らない。
しかし、室町から江戸期の氏であるので、土地柄からは多くの血縁関係が行われているが、賜姓青木氏ではないと考えられる。藤原系の青木氏であろう。
鎌倉期になって守護職でなくなり、各に飛散し仕官した藤原秀郷流青木氏の流れの持つ青木氏と松平氏との婚姻関係での血縁と見られる。
江戸期に爆発的に子孫を多く残したこの青木氏が最も栄えた青木氏であるとは不思議である。
2は「陰蔦紋」の青木氏である。
この陰蔦紋は山本氏の家紋とされていて、矢張り藤原流の青木氏と思われるが、この青木氏が山本氏との婚姻関係でこの家紋を引き継いだと考えられる。
青木氏を名乗っている事は山本氏から嫁を迎えて、その子供になんらかの理由で山本氏の家紋を引き継がせたと判断される。
この山本氏には小高氏も繋がっていて、この小高氏も「陰蔦紋」を使用している。
3は「鬼蔦紋」の青木氏である。
この鬼蔦紋は小高氏の家紋とされている。藤原流青木氏が上記した様な理由でこの家紋を引き継いだと思われる。結局は青木氏と山本氏と小高氏との三つ巴の婚姻関係を結んだことになる。
4は「隅切り角に蔦紋」の青木氏がある。
この氏に付いては不詳でデーターを保持していないので不明である。
4は「八角に蔦紋」の青木氏がある。
この氏に付いても不詳でデーターを保持していないので不明である。
5は「五瓜の蔦紋」の青木氏がある。
この氏に付いても不詳でデーターを保持していないので不明である。
6は「二重瓜の蔦紋」の青木氏がある。
この氏に付いても不詳でデーターを保持していないので不明である。
7は「丸に蔦紋」の青木氏がある。
この青木氏は1の蔦紋の青木氏の支流となる青木氏である 同系列である。
1の青木氏から子孫が拡がったが家紋は丸がついているので、婿養子を取ったか、娘が跡目を継いだ事から生まれる一族である。
8は「丸に陰蔦紋」の青木氏がある。
この青木氏は2の陰蔦紋の青木氏の支流となる青木氏である。同系列である。
1の青木氏から子孫が拡がったが家紋は丸がついているので、婿養子を取ったか、娘が跡目を継いだ事から生まれる一族である。
以上が蔦紋に関わる青木氏である。この青木氏の元祖は藤原秀郷流の青木氏であると考えられる。
そもそも、この文様の蔦紋は蔦を図案化したものであるが、この蔦の持つかえでと同じに様に、紅葉する美しさに引かれての紋様化したものと思われ、昔は風呂敷などに唐草模様と同じく良く用いられた。
江戸時代に吉宗が好んで使用したので、松平氏が用いたものと云われている。
この為に、高安氏、富田、椎名氏らがこの紋を変化させて家紋化した。
この紋は葉が全縁状と鋸状との二つがある。
葉の紋と花つるの紋があり、それぞれ一葉、二葉、三葉の紋様と変化させいる。
これ等の紋をあわせて見ると85もある。
次に記している氏を見てみると大方は松平氏の縁者である。
この縁者の支流、分派などの子孫である。
この青木氏以外に家紋として使っている氏は数種の文献を調べると、松平形原氏、大岡氏、仁科氏、志賀氏、植木氏、愛知氏、根木氏などがあると文献にある。
特に、徳川氏に仕えた青木氏を広い出すと次の様になる。
1 松平土佐守に仕え後に徳川綱吉に仕えた青木忠英の藤原流青木氏がある。
この青木氏の主家の家紋は「丸に揚羽蝶」で「二葉蔓柏」と二門である。
2 甲府綱重に仕えた後に家宣に仕えた青木安明があり藤原秀郷流青木氏である。この一族は代々組頭などの役職に着いた。
主家の家紋は「丸に違い鷹羽に一文字」「揚羽蝶」「開き蛤」の三門がある。
3 家綱に仕えて代々組頭として仕えた青木正命があり藤原秀郷流青木氏がある。
主家の家紋は「丸に一文字」「稲丸の内一文字」「丸に揚羽蝶」の三門にがある。
4 綱吉に仕えて組頭として仕えた青木政之があり藤原秀郷流青木氏がある。
主家の家紋は「丸に蔦」「青木葉二枚」の二門がある。
この一族が間違いなくこの紋様の蔦紋の一門である。
5 綱吉に仕えて組頭として仕えた青木正胤があり藤原秀郷流青木氏がある。
主家の家紋は「丸に抱き柏」「梅鉢」の二門がある。
6 家斉に仕えて小普請としてつかえた青木長貴があるが藤原氏ではない。
主家の家紋は「丸に揚羽蝶」の一門である。
7 家康に仕えた青木義勝があり藤原秀郷流青木氏があるが、丹治氏の説もある。
主家の家紋は「丸に揚羽蝶」「三つ頭左巴」「三つ頭右巴」「筋船」「鎧蝶」の五門がある。
8 池田輝政に使え後に家康に仕えた青木重直があり藤原秀郷流青木氏があるが、丹治氏の説もある。
主家の家紋は『丸に鱗」「富士山」「三銀杏」の三門がある。
9 家康に仕えて秀忠に仕えた青木満定があり丹治氏青木氏がある。
主家の家紋は「花菱」「九曜」の二門がある。
10 綱吉に仕えた青木清光があり丹治氏或いは藤原秀郷青木氏がある。
主家の家紋は「丸に葛花」「州浜」「蔦」の三門がある。
この一族が間違いなくこの紋様の蔦紋の一門である。
11 綱吉に仕えた青木覚左衛門があり上野国館林市青木村の出身であることから藤原秀郷流青木氏である。
家紋は不明である。
以上11が徳川家に仕えた藤原秀郷流青木氏がある。
こりらの一族は代々徳川家に仕えた。
蔦紋を使用しているのは2つの青木氏であるが何れも秀郷流青木氏であるから
元は一族である。この一族の2つと残りの9氏のいずれかの青木氏が8氏の青木氏に広がった可能性がある。
資料では家紋種は6種に留まっているが、持ち合わせのデーターが無いため不明である。
前にも記したか゛直系1氏と直流4氏と支流4氏のあわせて九氏から末裔が広がっている。この末裔は116氏に及ぶ。
又、家紋が元は「蔦紋」の紋様でなくても、後に婚姻関係の内容で家紋掟に従い、元は蔦紋のない藤原秀郷流の青木氏である限り「蔦紋」に紋変えした事も考えられる。
蔦紋は吉宗から正式にその一門が家紋として用いたもので、綱吉あたりから色々なところで象徴紋として使っていた。
これらのほかに徳川家との関わりで葵紋の変化紋様を用いた藤原秀郷流青木氏もある。
鎌倉期の守護職の崩壊にて離散した藤原秀郷の青木一門は多くは松平家に仕官した事がこの11のパターンでも判る。
この蔦紋の家紋から見てみると既に25氏にも末裔が広がったことに成る。
これ等の家紋の文様は判る範囲で引用したので、暫くお待ちください。
準備が出来た際に添付の項を開いて参照してください。
又、現在、家紋掲載の欄にも記載する準備をしていますので暫くお待ちください。
続く。
|
Re: 青木氏と血縁族(家紋)-1(綜合2)
青木研究員 さん 2005/11/02 (水) 21:11
第十三の家紋は「引き両紋」である。この内4氏である。
引き両紋の種類は38ある。
家紋200選にある。
第十四の家紋は「梅紋」である。この内3氏である。
梅紋の種類は127である。
家紋200選にある。
第十五の家紋は「目結紋」(めゆい)である。この内3氏である。
目結紋の種類は81ある。
家紋200選にある。
第十六の家紋は「茗荷紋」(みようが)である。この内3氏である。
茗荷紋の種類は61ある。
家紋200選にある。
第十七の家紋は「揚羽蝶紋」(あげはちょう)である。この内2氏である。
揚羽蝶紋の種類は97ある。
家紋200選にある。
第十八の家紋は「矢紋」である。この内2氏である。
矢紋の種類は38ある。
家紋200選にある。
第十九の家紋は「沢潟紋」(おもだか)である。この内3氏である。
沢潟紋の種類は82ある。
家紋200選にある。
第二十の家紋は「桔梗紋」(ききょう)である。この内2氏である。
桔梗紋の種類は126ある。
家紋200選にある。
第二一の家紋は「松紋」である。この内2氏である。
松紋の種類は114ある。
家紋200選にある。
第二二の家紋は「銀杏紋」である。この内2氏である。
銀杏の種類は79ある。
家紋200選にこの2氏の銀杏紋はない。
第二三の家紋は「柊紋」である。この内2氏である。
柊紋の種類は40ある。
家紋200選にこの2氏の柊紋は無い。
第二四の家紋は「桐紋」である。この内1氏である。
桐紋の種類は162ある。
家紋200選にある。
第二五の家紋は「鱗紋」である。この内1氏である。
鱗紋の種類は26ある。
家紋200選にある。
第二六の家紋は「橘紋」である。この内1氏である。
橘紋の種類は85ある。
家紋200選にある。
第二七の家紋は「釘抜き紋」である。この内1氏である。
釘抜き紋の種類は20ある。
家紋200選に無い。
第二八の家紋は「字紋」である。この内1氏である。
字紋の種類は391ある。
家紋200選に無い。
第二九の家紋は「立ち葵紋」である。この内1氏である。
立ち葵紋の種類は85ある。
家紋200選にこの1氏の紋は無い。
第三十の家紋は「梶の葉紋」である。この内1氏である。
梶の葉の種類は59ある。
家紋200選に無い。
第三一の家紋は「角紋」である。この内1氏である。
角紋の種類は79ある。
家紋200選に無い。
第三二の家紋は「升紋」である。この内1氏である。
升紋の種類は18ある。
家紋200選に無い。
第三三の家紋は「笹竜胆」である。この内1氏である。
笹竜胆の種類は47ある。
家紋200選にある。
以上の33の家紋種は青木氏に関する氏の家紋である。
これ等の家紋種に付いて注意するべき点は次の通りである。
同じ家紋種の中でも、極めて限られている。これ等に関係する氏を次のレポートに記することにするが、中には家紋200選の主要氏を示す家紋の中に無い氏もある。
同じ家紋種でも同じ氏であるとはいえない。特に、江戸期に入って各氏は挙ってよく似た紋あるいは同紋を使うという現象が起こった。
この時、幕府は禁止令を出したが守られなかった。
つまり、再び家柄を重視する社会現象が起こったのである。
同紋の一門であるから、必ずしも同氏とはいえないのである。
この家柄が家紋で判断出来る時代は鎌倉時代中期以前の氏姓制度の確立していた時代である。
このことは次のレポートで記する事にしている内容で判断が出来ると思う。
合わせて、家紋をなんらかの方法で記載したい。
121氏中で個別に家紋で見ると107となるが、14氏は類似紋を使用して同門となり、血縁を複合的に行われていることを示す一つのデータである。
家紋200選に無い氏を示すものは7家紋もあり、血縁がかなり時代の変化によって末支流の青木氏が誕生さしている事を示している。
続く。
青木氏と血縁族(家紋)-(綜合1)
青木研究員 さん 2005/10/28 (金) 21:03
青木氏は皇族賜姓青木氏と北家藤原秀郷流青木氏と第3の青木氏に大別されるが、中でも前者の2つの青木氏に付いてはどのような氏と血縁を結んでいたかを知る事は興味深い。
当時の子孫を遺そうとする死に物狂いの戦い具合が読めるのではないか。
先祖のこの努力を知る事が今ある自分の存在の証になるのではと考える。
先祖があって今の自分があると言う考えの前提になると思う。
時代は違うが、今の自分の生きようとする戦いも後世の子孫にとってはその生き様を平成の戦いとして興味深く思い、その意味でも遺す必要がある。そのためにも自分を確固たるものにする意味で先祖のことを知る必要があると思う。
そこでその資料として、このことを家紋というパラメータで検証してみる。
何故ならば、家紋には今にして歴史的な生き様が残っているからである。
皇族賜姓青木氏のことに付いては前レポートで詳しく述べてきたが、5家5流の青木氏は伊勢、近江、美濃、信濃、甲斐に存在し、
又、その土地の豪族との血縁により伊勢を除く、佐々木氏系、土岐氏系、足利氏系、武田氏系青木氏が存在する。
更に、2次的な血縁による土岐氏の支流族、足利氏の支流族、武田氏の支流族との血縁による青木氏が存在する。
この足利氏と武田氏の2つは藤原秀郷の血縁族であるから、藤原秀郷流青木氏とは別に、分けるとすれば、三次的な血縁による青木氏が存在している。
つまり、直系5氏の青木氏、支流4氏の青木氏、分流3氏の青木氏、分派の青木氏と藤原秀郷氏との血縁族とあわせると全部で24氏になると見られる。
藤原秀郷流青木氏地元の下野と武蔵の国はもとより守護先14地(類する官職を入れると29地)に多くの子孫遺してきたが、まとめると直系1氏の青木氏、直流4氏、支流4氏、分派と合わせると161氏もある。
藤原秀郷の子孫は青木氏を入れての主要氏の進藤氏、長谷川氏、長沼氏、永嶋氏とあわせて20氏の直系と支流分流あわせると362氏となるが、このなかの121氏である。約1/3である。如何に大きい氏であったか物語る。
この121氏の青木氏の中の氏を家紋を中心にもう少し詳しく見てみる事にする。
家紋から分類すると、7000から8000の家紋のうち青木氏の家紋は家紋類にまとめると33家紋となる。
かなり限られた範囲で血縁を結び子孫を遺して行ったことが覗える。
これは、賜姓青木氏と云わず藤原秀郷流青木氏は何れも藤原氏の血筋を持ち天皇家にも通ずるその家柄から氏姓制度の社会体制の中では血縁族は必然的に限られてきた事による。
同じ家紋類の中でも、僅かな氏との血縁であり、その血縁は主要紋の範囲を大きく外れるような血縁は少ない。本家がせいぜい分家の範囲にとどまっている。
そして、後で記するが出て来る氏姓はよく聞くものである。
この様にその家紋の歴史的な由緒を見てみると面白いので、家紋の決まるまでの内容をも併記することにする。
では先ずは、家紋の多い順から記してみる。
家紋200選とは7000から8000といわれる氏の中で、日本有数な氏を選出したものである。
第一の家紋は「蔦紋」(つた)である。この内8氏ある。
蔦紋の種類は全体で85ある。
家紋200選にある。
第二の家紋は「菱紋」(ひし)である。この内8氏である。
菱紋の種類は101である。
家紋200選にある。
第三の家紋は「藤紋」(ふじ)である。この内6氏である。
藤紋の種類は144である。
家紋200選にある。
第四の家紋は「扇紋」(おおぎ)である。この内6氏である。
扇紋の種類は89である。
家紋200選にある。
第五の家紋は「木瓜」(もっこう)である。この内6氏である。
木瓜紋の種類は87である。
家紋200選にある。
第六の家紋は「星紋」(ほし)である。この内8氏である
星紋の種類は71である。
家紋200選にある。
第七の家紋は「片喰」(かたばみ)である。この内5氏である。
片喰紋の種類は125である。
家紋200選にある。
第八の家紋は「柏紋」(かしわ)である。この内5氏である。
柏紋の種類は132である。
家紋200選にある。
第九の家紋は「州浜紋」(すはま)である。この内4氏である。
州浜紋の種類は43である。
家紋200選にある。
第十の家紋は「抱き角紋」(だきつの)である。この内4氏である。
抱き角紋の種類は22である。
家紋200選にある。
第十一の家紋は「鷹の羽紋」(たかのは)である。4氏である。
鷹の羽紋の種類は70である。
家紋200選にある。
第十二の家紋は「笹紋」(ささもん)である。この内4氏である。
笹紋の種類は141である。
家紋200選にある。
続く。
Re: 伊勢青木家 家訓4
副管理人さん 2008/06/29 (日) 14:18
伊勢青木氏の家訓10訓
以下に夫々にその持つ「戒め」の意味するところを説明する。
家訓1 夫は夫足れども、妻は妻にして足れ。(親子にして同じ)
家訓2 父は賢なりて、その子必ずしも賢ならず。母は賢なりて、その子賢なり。
家訓3 主は正しき行為を導きく為、「三相」を得て成せ。(人、時、場)
家訓4 自らの「深層」の心理を悟るべし。(性の定)
家訓5 自らは「人」を見て「実相」を知るべし。(人を見て法を説け)
家訓6 自らの「教養」を培かうべし。(教の育 教の養)
家訓7 自らの「執着」を捨てるべし。(色即是空 空即是色)
家訓8 全てに於いて「創造」を忘れべからず。(技の術 技の能)
家訓9 自らの「煩悩」に勝るべし。(4つの煩)
家訓10 人生は子孫を遺す事に一義あり、「喜怒哀楽」に有らず。
今回は、続きにより家訓4とする。
家訓4 自らの「深層」の心理を悟るべし。[性(さが)の定]
(性[さが]とは、”男女の神から与えられた逃れ得ない異なる思考の差異の様な宿命”と定義する)
[序]
最近、社会では男女間の思考の違いが発展して争いが起こり、「不幸な出来事に」繋がっている事が多いと考えられる。多くはこの思考差の違いの無理解が起因していると見られるが、この家訓4は理解を得て、この解決の一助となればと敢えて多面的に検証して長文とした。
この家訓4の内容の事は、現代に於いては科学的に証明されているが、明治以前に於いては未だ解明されていなかった事である。(家訓2で概略を記述した)悩める若者に対して先人の教えとして漠然と言伝えられていた程度の訓であっただろう。
しかし、この青木氏の家訓4は「先人の教え」程度のものをもう少し掘り下げて仏教的意味合いも含めて「人生訓」として遺されて来たものと観られる。
そこで、この「家訓4」が摂理であるのかどうか若い頃に研究に取り掛かった。
動物進化論、脳医学、精神医学等の雑学の関連書を長い時間を掛けて読み漁った結果と、自分の体験則と合わせて未来の子孫に判りやすく家訓論に添え書きとしてまとめて観た。そうすると家訓4の理屈の内容がほぼ一致して納得出来たのである。
その結果の概容を取りまとめたのが、次に記述する検証結果となる。
先ずは雑学論で有る事をご理解頂き、それを、早速、次に論じる事とする。
「性」の検証
人は、進化して知恵を持った事により問題が起こると、人の脳は、「計画し、目標決め(取りまとめ処理)し、実行する」という「3つの働き」を瞬時に、「無意識」の中で行う仕組みと進化した。この脳の働きにて、より「性」(さが:以下”さが”とする)の進化は進んだ。
その進化の結果は上記の「性(さが)の思考」へと成った。
この男女個別の「性」の進化が起こり、「体の仕組み」、「心の仕組み」とその二つに付随する「仕種の仕組み」に決定的な変化が起こり、個別の働きをする様に進化したのである。そして、その結果、脳の一部にこの個別の「性の働き」を管理する「脳」が発達し出来た。それが「脳幹」の後ろ左にある餃子のような形をした「脳陵帯」であり、「管理脳」として独立したのである。
この「脳陵帯」が存在する限りに於いて、男女の上記する「3つの性」(体の仕組み、心の仕組み、仕種の仕組み)は管理される。その事で、「性」は絶対に逆転する事は無く成ったのであり、恒常的に多数子孫を遺す事が出来たのである。(他に、男性のみに左脳の一部が「中紀帯」と言うものに進化し独立脳が出来た)
この「体と心と仕種」を支配する脳に依って、男女の「深層思考の原理」では、夫々の「生きる目的」は同じでは無くなり、別目的を果たす「性」として決定付けられたのである。
そして、その思考(脳)の基本的経緯は次の様に変わったのである。
[基本経緯]
生物は神から「二つの性」に対して「子孫を遺す事」を主目的としてこの世に「生」を受けている。その子孫を遺す「目的要素」を二つに分離してその役目(男と女の性)を夫々に担わせたのである。そして「体、心と仕種」(3つの性)を管理する「脳の働き」(無意識の思考)にもその目的に合わせて変化を与えたのである。それが「深層思考の原理」である。
基本経緯の一つとして、この原理を理解するには先ず「進化の過程」を紐解くと事が必要であるとする。
「性」の「進化の過程」
ではその「進化の過程」を概略に辿って観る。
進化の過程として、この世にミネラルを持つ海に生物が生まれ、特に、動物の単細胞として生まれた「ミトコンドリア」は、動物性プランクトンの様に、他の動物の格好の餌食と成り、子孫を多く遺せない定めを負っていた。現代も昆虫類に見られる仕組みの様に、それは一つの体の中である環境において突然に「性の転換」を起し繁殖して子孫を遺す仕組みであったからで、生きることでの利点はあるが、他の生物の餌食に成る事は両性を無くす事に成り子孫を遺す事に不利であった。
そこで、「ミトコンドリア」はその「生存競争」に対してより確実に子孫を遺す為に進化を起し、次にはミミズに観られる様に、繁殖期に於いて一体の半分を「他の性」として「性の合体」をして一体と成り強くした。しかし、結局、これも競争に負けると「2つの性」を同時に無くす事となり、返って単細胞以上には子孫を遺す事が出来なかった。
そこで、「性の転換」「性の合体」の進化過程の極めて長い期間を経て、再び、どの生物にもある「生存本能」により、今度は夫々の子孫を遺す「目的」に合わせて分離して、それを「2つの性」にして「性の分離」方式とし「2体化」させた形で再び分離したのである。その事で、片方の「性」のバランスが生存競争に負けて大きく崩れても、全滅を防げれば、この中からも片方の「性」の一部が遺せる限りに於いて、交配にて他方との性のバランスを保つ事が出来る様に成り、絶滅を避けて生き遺す事が出来た。この仕組みが爆発的に子孫を拡大する事が出来る事と成り、終局、多くの動物、生物に観られる様に、これが最も「生存に適した進化」へと繋がりより「2つの性」はより発達した。
「2体化」とする「2つの性」である「性の分離」方式のその証拠には、動物の身体下部の「生殖機能」の「形状」では、その部位は全く同じである。その形状の機能もほぼ同じである。
男性(凸)が持っているものは女性(凹)にも持っていて、それが、凸に突き出るか凹に下がるかの差だけなのである。人の種は、女性(凹)の生殖機能部位より入口より9C程度の内部のところには親指1.0C弱程度の凸器官(医学名も同じ)を保持し、その周りに保護皮膚が覆っている形である。この凸器官が突き出れば同じと成る。同様に内外部の違いで卵巣精巣も同じである。異なる所は子宮の袋の存在だけである。
これが「性の合体」方式から「性の分離2体化」方式への進化の証拠(なごり)である。
又、これは「性の転換」方式でも、猿系には「なごり」の機能として存在する。その「なごり」は精子が卵子に進入後、細胞分裂が起こり、その40日後に突然、莫大なエネルギーを発しアルカリ性反応(海)を呈し男女の「性の決定」が起こる。
これは「ミトコンドリア」の2つの「性の進化の過程」即ち、「性の転換」と「性の分離」の「なごり」が遺されているものである。
その「性の転換」「性の合体」「性の分離」と過程を経て発達した「2つの性」はその知恵を以ってより安全な場所へと移動する事が出来、遂には、海と陸との間で生きられるように成り、これが「環境と適応機能」を発達させて順応して両生動物として進化と発達を遂げた事に成り、この域での天敵の減少も伴い大爆発的に繁殖が起こった。
進化した「ミトコンドリア」の原始動物は、この時、海に生存している時にはその必要性は無かったが、生存し続ける為には陸付近では海に居た最低条件(ミネラルの補充)を維持する事が必要に成ったのである。
ところが、この段階では未だ、「脳」と云う独立した機能帯は無く、「脳」で管理する部位の進化は大きくは起こっていなかった。この時点では現代呼称の「腸」が管理源として働いていたのである。つまり、現在に於いてでも、その「なごり」が厳然として遺されている。
人間に於いては「脳」は「腸」を管理していないのある。今だ「腸」は独自の「脳」に匹敵する管理力を保持している。つまり、余りにも大きい進化と発達の為に「腸」の一部が管理力を独立させ新たに進化発達させたのであり、「体の機能の部位」を管理する「独立帯」を創造したのである。
これが「脳」なのである。但し、この「腸」より独立した「脳」で管理する「体の部位」には「海の条件」を保持させる3つの要素の必要性が起こった。
それは、先ず自らの独立した「脳」の機能を働かせる為にNaイオン(キャリパー)の補充を必要とした。次には、その「独立脳」で管理される「体の部位」への「栄養の搬送」とその「体の部位」を保持する「骨格」を維持する為にCaイオンを必要とした。
更には「独立脳」を働かせる為の栄養源(Naイオンとエネルギー)を含んだ搬送液(血液)が必要と成り、その為に「脳」はポンプ役としての「心臓筋」を働かせる為の刺激の電気信号を送り、刺激反応を受けるMgイオンを確保する「3つの進化」が必要と成った。
この「3つの進化」の「3要素」を陸で補充し確保する事で、大きく進化を起し長期に陸に上がる事が出来たのである。これらは所謂、海に居た「なごりの機能」である。この脳の発達に伴ない「3つの栄養源(NaCaMg)」を分解する酸素を供給する「肺機能」も発達進化したのである。この両生期の名残として肺機能を持った海洋動物は現在でも沢山存在する。
この様に、「腸」から「独立脳」へと進化し「ミネラル」の3要素の大進化が起こったのである。
更に、この結果で、「酸素吸入力」が増し「肺」「心臓」などの臓器がより拡大し進化したのである。そして、未だより安全であった陸にあがり、子孫を大きく伸ばした。
そして、「進化と良環境」による臓器拡大は、この時点で、陸では超小型「原始ネズミ」の様な小動物から進化分離して徐々に大型化し、その「拡大体力」と「陸環境」の適合に依って進化し得るエネルギーを確保出来て、超小型「原始ネズミ」からその2つに適した異なる分離が起こり多くの「種」が誕生したのである。
機能としては充分ではないが、「生存に適した肺臓等」と「2つに分離した生殖機能」を夫々の種は独特な発達と進化をさせた。より豊かな陸上には、今度はその「環境に合せた進化」が起こり多くの種の動物が生まれたのである。これ等の原始性機能を保持した超小型「原始ネズミ」から性機能を進化させ「原始猿」そして「猿系類人猿」へと進化したここが人間の単純な性機能の原点(基点)である。
「性の基点」
この時、「腸」から「独立脳」と進化した単純な管理をする「脳」は、更に、この家訓のテーマである「性の進化」へと発展して行った事に成る。「腸」を進化させ「独立脳」を保持して発達させ陸に上がった両生動物は、超小型「原始ネズミ」へと進化したのである。
その「原始ネズミ」の「なごり」として特有のものを保持している。それは、現代でも「三角耳」が原始猿等に観られる様に、人間にもその丸い耳の頂上部位の最上部に耳が尖っていた跡形が1箇所5ミリ程度のものとして小さく存在する。これがその名残の証拠なのである。
又、馬などはこの「原始ネズミ」が環境に適した形で大型化の「突然変異」が起こって生まれたもので、これが種として拡大したものである。所謂、「突然変異による進化」した「原始ネズミ」の直系子孫である。つまり、平易に云うと、「馬」と「人」は猿以前のルーツは親類であった事に成る。
これより、爆発的に増殖した種の動物は、陸に於いても夫々の生存競争が激しく成り、ここでも弱い小型猿類と成った種は、食の豊富な森から、食の欠乏と危険が多くある見晴らしの良い平原へと追い遣られた。ここで止む無く危険を察知し易い様に、より高い視界を得る為に「2足歩行」が始まり、目の位置は物体を立体的に捉えられる様に平行の位置に移る様に進化した。その結果、この二つの事で「脳の集約性」が高まり、他の動物に較べて急激な「猿類の進化」が始まった。
特に、他の動物に較べてその「脳の進化」、即ち上記の「性の分離と進化」の継続が続き、それに伴なう「2つの性」の完全分離の進化が起こった。
結局、「増大化し繊細化する性」の傾向に対して、「脳」はそれを「管理する独立した脳陵帯」というものを拡大創造したのである。そして、より確実に子孫を遺す仕組みへと進化した。
この「増大化し繊細化する性」から来る情報量と合わせて、リンクして「感情」と「理性」を司る「前頭葉」「側頭葉」が発達拡大し進化したのである。
当然、そこで起こる記憶を収納する部位の左脳には、この著しい「増大化繊細化」の「情報の収納化」が起こり、その記憶量に基づく「脳」はより「性の進化」と「性の分離」と「性の整理」をして進めたのである。
必然的に、その情報の種類は、「脳陵帯」に管理されて、夫々の「性」に由来する物が多くなり、結果として「脳」の整理方法は「3分轄の方法」と進化して、「体系化」が起こった。
その「体系化」、それは「計画的」な「基本思考」と、「処理的」な「標準思考」と、「実効的」な「現実思考」とに、3分離されて記憶保存する形(3段階の体系化)へと進化したのである。
当然に、女性はその「性の目的」から「感情的な情報量」が多くなり、必然的に「感情主観」を中心として「3段階の体系化」が成され、男性は「性の目的」から「理想的」なもの即ち「合理主観」を中心とする様に「3段階の体系化」が起こった。
ここで、この「脳陵帯」に管理された情報の「3段階の体系化」で、男女の思考原理が完全分離したのである。
生物に於いて、特に動物に於いて、この体系化の緩やかな種では思考原理の分離も緩やかになり違いが少ないと成ったのである。「脳」の変化要素(増大、拡大、発達、進化、変異)の差異、即ち「知恵」の差異で、この「思考原理」にも差異が生まれた。脳の変化要素の最も多くなった「猿系の人」はその最たるものと成ったのである。
更に、人間には、他にその最たるものとして、より優れた「独立脳」を創造させた。
陸に於いても海と同じく危険性は極めて増し、今度は「体の機能」からそれを「脳の進化」で対応したのである。「脳の進化」の最もその増大し拡大した左脳の「線状帯」の中間部に、「未来予測」する機能を持つ「中紀帯」という部位が、進化分離し「独立脳」を造り、それを進化させて「男の性」を守る為にだけに独立して出来上がり発達したのである。
当然、頭部も、目と耳と鼻と口と皮膚から入る情報源を管理し記憶する為に、「連鎖反応」が起こりその「五感の機能」は進化発達した。その結果、運動量も増大し、頭部は「大脳」を含めた「脳の拡大」が起こり、左右前後に拡大し大きくなった。
ところが、この時、「進化」に伴ない「退化」が起こった。
上記の「情報量と左脳の進化」がある一つの「原始機能」を低下させてしまったのである。
それまでは、額の中央部の「前頭葉」と連動する予知機能としての「第3の目」」(原始動物に存在する「複眼機能」:「テレパシー機能」)を発達させていたが、「前頭葉」と「側頭葉」が拡大するに従い、「前頭葉」の真後ろに追い遣られて「脳幹」の前の下側に小さく存在する事に成ってしまった。そして、必然的に奥域に移動したその「第3の目」の必要性が低下して、何時しか機能は低下したのである。それまでは、特に、女性はこの機能を「2つの目」と連動して「感情と理性」を司る「前頭葉」と「第3の目」」(複眼機能)を使って、その「性」(子孫を育てる)を護っていたのである。この時までは右脳もこの情報を取り扱う機能として大いに働いていたと観られ、退化に伴い右脳の働きは限定されて行ってある特別な脳の働き(ベータ波による連動)に限定される結果と成った。
しかし、ある時期から、上記の進化と人間社会に起こる知恵により、科学による付加価値の増大が起こり、その奥に追い遣られた「第3の目」(複眼機能)は必然的に機能低下が起こった。
現在に於いても、この「複眼機能」を連動させられる「深層思考(感情)」を持つ女性に限り訓練すると、その能力をある程度まで復元出来る能力を未だ持っているのである。(広域ない実の子孫を産み育てる母性本能により連動)
女性にはその差はあるが、「テレパシー性」が強いのは、この「第3の目」の「複眼機能」から来る「なごり」ここから来たものである。
ところが、「感情」の精神を一点(元複眼のあった額の中央上)に集中させて「2つ目」と「前頭葉」と、この「脳」の奥の未だ死んでいる訳ではない「第3の目」との間にシナプスを通じてアルカリ性のNaイオンの「キャリパー」を飛ばし、「神経細胞」を繋ぐ訓練をする事で、神経回路(ニューロン)が復元できて退化したこの「複眼機能」を復元出来る事が判っているのである。
古来から、邪馬台国の卑弥呼やこの占い師の巫女などの役目は女性が行っていたのはここから来るのである。迷信的なことではなく根拠あるもので、このトンボや蝶(鯨、象)や原始的な猿類の動物に未だ存在する「第3の目」」(複眼機能)を使った能力なのである。
そして、機能低下したのはそんなに古い時代では無いのである。紀元前後はまだこの能力を保持していた女性は多く居たのである。(卑弥呼の所以の源である)
”原始的な方法として「占い」で全てを見極めていた”として、現代に於いて、その行為を現代的な視点から観て軽視する傾向があるが、実はこの様に「複眼機能」が未だあった事での自然な社会行為であった。
この様に化学的根拠はあるのであるし、今だ、女性が占いを信じやすい事や、この詐欺まがいなものに騙されやすいのは、まだこの「なごり」が「性の遺伝子」の中に、左脳の記憶の中にあるからに過ぎない。
男性はその「深層思考」が「合理主観」に左右されているので、この様なものには納得しない傾向があり、従って、この「第3の目」」(複眼機能)は著しく低下、又は消滅に近い事に成っている。
その機能を「左脳データ」を使っての別の「中紀帯」の進化過程を採り、発達させた事による低下(退化)なのである。
追記
更に、附帯的に追記すると、これ等の女性の直観力即ち予知能力は鯨、象の特定な予知の脳機能にある様に、類似する機能が哺乳動物の人間にも存在する事が云えるのである。
つまり、それは上記する複眼より発した振動は脳機能レベルを一時的に高めてベータ波を発しその返波を得て直観力を働かせる機能や、掌から発する微細波(遠赤外線波)や触手により得た情報で複眼機能と右脳を連動させた「予知、直感力」を働かせるこの2つの機能は、大きく退化したとは云え存在する。
それは「性の特質」から女性には現在でもその保有は、退化して千差万別と成っているが、訓練することにより復元する。これは女性専有の職業などの領域に観られる現象と成ろう。況や、つまり、「母性本能」は本来持ち得ている能力であるが退化の例外ではない事を意味する。
結果的に、女性はこの様にその子孫を産み育てると言う「性の特質の保持」から2つ脳(複眼-前頭葉-右脳)を同時に使うことが出来る得意技を持っているが、男性は合理主義の「深層思考原理」の結果で「単脳反応」の仕組みと成ってしまった。
つまり、女性は{感情主観}であるので古来から発達させた「右脳」を依然として使っている事に成るのである。「複眼」と「前頭葉」と「右脳」を使って「予知、直観力」を高めてその「性の特質」を現在も発達させているのである。
故に女性は脳波のアルファ波(8-13Hz)から直ぐに切り替えて脳レベルを上げてベータ波(14-30Hz)を発し、子供の脳との連動を起こし複眼を働かせて「予知、直感力」の能力を発揮し保持しているのである。
又、同様に退化しているが本来は女性は、精神集中する事により無駄な血液を脳に送り脳レベルを上げてこのベータ波を高めて、手先から遠赤外線(300−250ナノ)を発し情報を得て複眼に戻し、右脳を働かせて「予知、直感力」を連動させる能力を元々は保持していた。
アルファ波の巾5Hzに対してベータ波は15Hzと3倍もありその脳レベルの巾は広いが、これはその集中力を高めてベータ波に切り替えられるレベルの多さを示すもので、15レベル範囲で「予知、直観力」を果たすものと、30Hzレベルの高度な「予知、直観力」を果たせるものとがある事を意味する。
つまり、脳はその状況により脳レベルをコントロールしているのである。
だとすると、掌から発する遠赤外線のレベルもこれに比例する事ともなる。
ところで、古来よりこの様な能力の持つ女性の掌を「福手」又は「福の手」と呼ばれていた。
古来からの言伝えの言葉の”掌(たなごころ)は母心”という言葉はここから来ている。
女性の右脳を使うこの「2つの能力」は近代化で著しく退化し、保有する者は少なくなったとされている。
その能力の有無の見分けの方は、「掌(たなごころ)」が「温かさ」と「柔らかさ」と「ふくよかさ」のある女性によく観られるとされていて、現在は化学の進歩により「死語」とは成っているがその確率が古より高いと云われていた。
確かに、母親のその掌で子供の顔や頬をはさみ撫ぜると子供は癒され落ち着き、頭を母親の掌で撫ぜられれば癒されるのは、この脳のベータ波と掌の遠赤外線の上記した効能から来ている。
この母親の仕種がその「なごり」として今も遺されているのである。この2つの仕種は決して指先ではなく
これが”掌(たなごころ)は母心”の所以なのである。
鯨や象は規模は違うがこの類似する能力を現在も大きく保持しているのであり、3キロ先まで「低周波」を飛ばして「予知、直観力」を働かして生きている。つまり、複眼を振動させて目の上額に溜めた油に伝えて飛ばし返波で脳と連動させて「予知、直観力」を発揮しているのである。
(人間は複眼などから発した信号をNaイオンアルカリ液体をシナプス[神経の繋目]に飛ばしこの中をこの電気信号を伝導させてニュ-ロンの右脳に伝達させベータ波を発する仕組み)
人に於いては集中して考える時に額の眉間にシワを寄せる今もある仕種は複眼機能を働かせる仕種の「なごり」である。
因みにキリストが各地に布教している時、このキリストの掌を額に当てられた者は病気が治癒したとされ、この史実がキリスト教の布教に最大の効果を発したと言われている。
つまり、キリストはこの潜在的にその能力を大きく持っていたことを示すものである。
日本に於いては、天理教の教祖(おみきばあさん)もこの「複眼」と「ベータ波」と「遠赤外線」の「3つ能力」が超人的なレベル力を保持していた事がある超有名大学の化学実験の史料に遺されている。
アスリートなどが集中力を高め「予知、直感力」を高めて右脳を働かせてより高いレベルの能力を発揮させられるのは、このベータ波を発する能力をより高める訓練をしているからなのである。
故に大なり小なりに女性はこの本来の野生本能(母性本能)を「性の保持」(母性本能)の為に未だ保持しているのである。つまり、「性」を管理する「脳陵帯」がこの管理能力を未だ女性に与えている事を示すものである。「脳陵帯」が女性の性として記憶している限りこの能力は存在し続ける。
問題はその「能力の低下」に関わる事に成る。従って、訓練すれば、シナプスの回路は開かれて再びその能力は高まる事を意味する。
戻して、ところが最近は、一方科学の付加価値の増大による障害(ストレス)に依ってか、男性の複眼に変わるこの「中紀帯」の活用の低下が起こっていると云われていて、この機能を活用している個人差が大きいとされている。男性の特有の未来を見据えた機能、即ち「性」が低下して、場当たり的な行動(フリーター、女性化)の様相を呈しているのはこの為であろうと考えられている。
男女に於いて同様の事(退化)が起こっている事に成る。
男性にはこの「中紀帯」によるデータを元とする未来を予測する直観力、女性には「第3の目」(複眼)の機能よる本来の野性的本能による直観力、即ち予知能力が存在し、その「訓練と活用」が必要となる。
況や、「訓練と活用」の如何ではより「退化」へと進む事になる。
その事からすると、女性はその「性」の目的の「子孫を育て護る」という機能手段を一つ失いつつある事を意味する。科学進歩により護られて「第3の目」の必要性が低下して、機能低下が起った事であり、これも明らかに「科学の付加価値の増加」による弊害(ストレス)とも云うべきものであろう。
「性」と云う観点から見れば、「母性本能」の低下で、これも場当たり的な行動が目立ち、結婚願望の欠如、離婚、男性化などの様相を呈しているのもこのためであろうと思われる。
所謂「科学に適応した進化(退化)」であり、現代は未だその途中であろう。
「性」の「進化と退化」
事程左様に、上記した過程に示すように「生存に適した進化」と「環境に適した進化」と「科学に適した進化」による3つの「性の進化」は何れに於いても現代2000年代には例外では無い。
「家訓3」でも記述したが、直近の1800年代の「産業革命」をきっかけに、再び下限域から「Nパターン」のサイクルは繰り返されて、約200年毎に起こると云われている「Nパターの摂理」は、200年後のこの2000年代には積分域と上限域に既に到達しているだろうと考えられる。
その現代に於いては、そして、更なる「科学の付加価値の増加」は起こるだろう事が予測出来る。
それは集積回路(コンピータ)の論理的な進歩が起こり、特に更なる「時間の進歩」が起こるだろう。当然、それにより歴史に観る「進化と退化」は起こると観られる。
依って、女性の「性」の目的「子供を育て護る」と云う事で「育てる進歩」と、周囲の「時間の進歩」の差異が生まれ、上記の「テレパシー機能」とは別に、更に「性」の手段機能の一つの機能の低下を起すだろう事が予測されている。
その一つとして、「時間の進歩」の一つの現われであるファーストフードの様に、作る事無く何でも既に揃っている「食の進歩と進化」の時代により、女性だけが特別に保有する「育てる機能:乳房」の一つが低下するだろうと言われている。現在もそれが進んでいて、その「対の目的」は低下して傾向として対の片方が縮小していると云われている。これは体の一部の変化であるが、これに伴なって「心の性:本能」、つまり、その「母性本能」の低下と欠如が連動しているのである。その為に、最近、この「母性本能」低下欠如の事件が多発している。
女性は、その「感情主観」の「性」を持つ為に、「科学の付加価値の増加」のストレスに敏感に反応する。この事と合わせて、「退化」はこの原因である「性」の働き(3つの性の一つの「体」部の低下)からではと見られている。
それに較べて、「中紀帯」があるからとしても、男性には、複雑でスピード化してより尖鋭な「合理思考」が要求され、且つ、その左脳の情報量より「時間の進化」が早く成り過ぎて、その経験側のデータが間に合わないと云う事が起こる。結果はその思考機能の限界に来ているとも云われているが、より「左脳」を大きくし、「中紀帯」を進化させ無い限りは同じくストレスで潰れることが予測できる。
現代ストレスにて女性と同様に、過労死の社会問題化しているのもこの現象から来ているのであろう。又、男性の寿命の延長も進まないのである。これは、現代の社会現象である自然を求め、自然に帰ろうとする傾向は、「脳」(前頭葉と左脳連動)の中に「性の限界」の「拒否反応」が無意識の内で起こっているのであろう。
「性」の機能の検証
そこで、では、その「性」がどの様に反応しているのか、更に、より詳しく「性」(さが)の機能に付いて検証して見る。
人間は先ず問題が起こった場合には、無意識の内に「脳」は次の3基本動作をする。
その先ず最初に動作する脳の「計画」思考とは、
男性では「理想的」に計画する。
女性では「感情的」に計画する。
この動作は「無意識」の中で行われる。それが出来ると、瞬時に「有意識」となる。
そして、それがまとまれば、再び「無意識」と成り、
次ぎは取りまとめの動作、即ち「処理」(目標)思考と移る。
男性では「理想」を「合理的」に取りまとめて考え動作する。
女性では「感情」を「勘定的」(数理的)に取りまとめて考え動作して「有意識」と成る。
この取りまとめられ動作した思考は、再び「無意識」と成る。
脳の動作は最終の思考として「実行」へと移る。
男性では合理的に「現実的環境」を洞察した上で、思考の行動は「実行」へと移り、「有意識」の中に入る。
同様に、女性では勘定的に「周囲環境」を洞察した上で、思考の行動は「妥協的」な実行へと移し、この段階で「有意識」の中に入るのである。
これが、「脳」が行う「深層思考」の「無意識」の「原則パターン」である。
そこで例を挙げてみると次の様に成る。
「性」の思考の例
例1の場合
例えば、ある問題が目前で起こったとする。
男性は、その状況を観て、先ず「理想的な形」で解決すべきとして「無意識」に脳の中に描く。
そして、それをその「理想」から導き出される方法として、「無意識」に「合理的」な「解決目標」を引き出す。
その「目標」を達成する為に、周囲の実情を検証し考察して、「無意識」に「現実」の中であり得る手法を採用する。この段階で「有意識」の行動として働く。
文明の付加価値を除いた人間の一場面の問題として観てみると、次の様に成る。
ある男Aが居た。そこに他の部族の男Bが生存競争で直前に襲撃したとする。
男Aは、先ず、脳は「無意識」に働く。そして、先ず、男性は「理想的な形」での最も「戦いに叶う」とする解決方法を思考する。先ず絶対に避けられない生存競争であると認識する。敵の弱点を志向する、そして、衆敵を圧して自らの安全を確保する姿を描く。
次に、そのための具体的で合理的(目標:手段)な危険の少ない「捕縛」作戦を考えるように働く。そこで、それを実行する。行動は「状況判断」(過去と現実を対比洞察)をして、先ず身を隠す、引き込む。捕らえる等の戦術を実行する。そして、自らを「戦い」から護る。
女性は、何とか戦わず仲良くする「感情的な形」を思考する。戦わずして仲良くし犠牲(勘定)を少なくするには、先ず引いて可能の可否は別として、「相手との話」等と考える。そのまとめ方は「損得(勘定)」で計算する。そして、「道義、正義、勧善、懲悪」に拘らず「妥協」してまとめ様とする。
例2の場合
この思考原理の差異で起こる最たる例は「夫婦喧嘩」であろうが、これで観てみると判りやすい。
「計画段階」では、男性は「理想」を描くが、女性は「感情」で事を描こうとする。「理想と感情」では「次元」が異なる。これでは、性格が合うかどちらかが引くかしない限り、余程の事でなくては話は絶対に合わない。そこはどちらかが何とか逃げてたとする。
次ぎは「目標(処理)」の議論の段階と成る。
男性は「論理の合理」で思考する。女性は「数理(損得)の勘定」で思考する。
「合理」と「勘定」とは一見同じであるかに見えるが異なる。
男性の場合は、「理想」に基づく「論理性の合理」である。
女性の場合は、「感情」に基づく「数理性の勘定」である。
「論理」と「数理」との違いである。つまり、論理は縦と横と巾の立体(過去、現在、未来)で思考する3次元性、数理は+(縦)と−(横)の面(過去、現在)であり、+と−には巾に相当する要素が無い為に思考するものは2次元性である。
男性の場合の論理性は1次元多い思考範囲で処理するという事である。
この世の現実の出来事は「3次元要素」に依って起こっている。故に男性の「性」は「現実的な実行」となる。この世の現実の最良の状態を「理想」と描く事であるので、「理想」には中間の思考も最良のものであれば存在する。従って、「理想」のメカニズムは「思考の和」に依って生まれるのであるから、中間は含まれる。故に、思考の「理想」は現実の世の出来事(3次元)から生まれたものである事になる。
この事は、「現世の3次元」と「理想思考の3次元」の次元が一致して「理」が合う事になり、つまり「合理」で決める事となる。
(この事は上記した様に左脳の理想の経験則の記憶収納方式から起こる。)
因みに、この思考の「理想」には考えの個人差が生まれる為、この「理想」とは、「三相」(人、時、場所)の「3つの要素」が、同時に、合わせて、「最良の状態」を意味すると定義されるだろう。
そうすると、「3次元」の3つの要素と「三相」の3つの要素が絡まって思考される事に成る。
つまり、「脳」の中ではどの様に働いているのか、この事を解析してみると、次の様に複雑に働いている事に成るだろう。
「未来」の事に付いて決める議論が及ぶ場合、人間の脳の中では、「過去、現在」の2つの要素に合わせて、「三相」の3つの要素を絡めて思考している事に成る。
方程式であらわすと次の様に成るだろう。
「未来」の決定(C)=(「過去+現在」)*「三相」=「過去の三相(A)+「現在の三相」(B)
解説
「過去の三相」の理想(A)はこの様であった。「現在の三相」の理想(B)はこの様である。
故に(A)の理想と(B)の理想の2つの理想形から、未来の理想(C)は”この様にあるべきだ”と論理的に思考する。
「過去」と「現在」の決定の関係式も代替して同様に式が出来る。
男性の場合は式にすると次の様に成る。
思考関係式 「理想」=3つの対比する「思考の和」 故に「3思考和」=「論理」の構成=「合理」
(「3つの対比」とは「過去の三相」、「現在の三相」、「未来の三相」を言う)
この関係式からも「理想」を論理で描いたものである為に「目標(処理)」はその延長上の「合理」で決める事になるのは当然であり、これが「感情」や「勘定」で処理する訳は無い。もし、そうだとしたら、「精神分裂」とも成る。思考の面では「精神分裂」とはこの様な現象を示す事ではないだろうか。従って、「実行」の段階では「過去、現在」までのこの「世の現実」から来る「理想形」を描いた訳であるから、「現実的」に実行する事に以外には無いだろう。
只、男性の場合には、「理想」の中には「中間的思考」もあり得ると考える思考形態である筈で、故に、「戦略的」に「理想」を叶える為には「妥協」と云う一時的な「戦術」を採る事もあり得る。それも最良の三相「人、時、場所」の条件を整える為には、男性の思考には「現実的」と捉える思考形態を持っている。それは過去の歴史的史実を見てみると判りやすい。
この多くの史実の中で、古来より、この「世の処理」は「6つの戦術」と「3つの戦略」に依って分類されると考えられている。
「世の処理」=「3つの戦略」+「6つの戦術」と成る、その事を多くの人が知っている例として次の事が良く判る例ではと思う。
彼の有名な「諸葛孔明」は敵を「欺く手段」として良くこの手(妥協)を使ったと言われている。だから、敵は”何をするか判らないので、警戒して動かない”と言う行動を採り、良く勝利に導いた。
例えば、「諸葛孔明」が死んだ時、云い遺して、”全ての城壁の城門を開け放ちかがり火を焚けと。”
つまり、「戦い」の 理想の両極の「戦う事」、「退く事」のどちらとも取れないこの策は、軍師の居ない時の「妥協」の戦術である。敵は、結局”、何かの仕掛けであり、何が起こるか判らない”として警戒して引いてしまったのである。これこそ”戦わずして勝つ”の「理想」の戦いの達成である。
「理想、合理、現実」からでは、次にうつ手の戦略戦術は、”将棋の様に次にはこの様に来るだろう”と完全に読める。しかし、これでは軍師ではない。それを「妥協」と云う一時的手段で欺いて、「戦う事」と「退く事」の両極を、より効果的に「理想」(勝利)を導けるのである。
故に、この女性の思考の「妥協」は、男性にとっては「実行の補助手段」と認められるのである。
つまり、男性の「妥協」は「実行の補助手段」であるので、「諸葛孔明」の様に、有意識の中で「戦術の訓練」で補える。
逆に、男性の「現実」を女性が用いるとすると、元が「感情主観」であるが故に、「実行の補助手段」の思考としては「脳」の中で、無意識で拒絶して用い難いものであろう。
あくまでも、この「実行の補助手段」は論理性から来るものであるからだ。
例外的に、女性がこれを思考として用いるとすると「脳」の訓練で左脳に「合理と現実」で創り上げた経験則のデータを蓄積して引き出し、有意識の中で故意的に使う以外に無かろう。
同様に、男性が女性の「感情主観」を利用するとすると、かなり難しいものがあろうが、感情主観の経験則のデータを蓄積して引き出し、有意識の中で故意的に使う以外に無かろう。
あらゆる男性芸術家はこの域の例であろう。只、男性には3次元思考の形体であるが故に、描かれる芸術はより「豊」「深」をもつ事であろうから、芸術家は男性に多い事となるのであろう。
従って”誰でもが”と言う事ではなく例外的ではあろう。ここで云う論処は例外を含めてのものではない。例えば、女性では「6つの戦術」と「3つの戦略」を駆使する女性政治家の様な例外的なものであろう。
同様に、女性は好き嫌い良い悪いの「感情主観」であるので、「感情」には中間の思考は無い。”どちらでもない”と云うものは「感情」では基本的にないので、中間の思考には「感情」は生まれない事に成る。つまり、「感情」のメカニズムは2つの対比する「思考の差」に依って生まれるのであるから、中間との差は少ない。故に、「小さい感情」と成り、左脳の思考の保存には留めないものと成る。
故に、中間を含まない両極差の感情と成り、女性は「2次元要素」と成るのであり、現実の世の出来事(3次元)から一次元を差し引いた思考で主張する事と成る。
つまり、結局は「目標段階」では、結果としては、「思考差」の多い少ないの量的な「勘定」で決める以外に無くなる訳である。
(これは上記した様に左脳の感情の経験則の記憶収納方式から起こる。)
方程式で表すと次の様に成るだろう。
「未来」の決定(C)=「過去+現在」*「感情」=「過去の感情(A)」+「現在の感情(B)」
解説
「過去」の感情(A)はこの様であった。「現在」の感情(B)はこの様であった。
故に(A)の感情と(B)の感情の2つの感情形から、未来の感情(C)はこの様にある筈だと思考する。
「過去」と「現在」の決定の関係式も代替して同様に式が出来る。
ここで、女性の「三相」の取り扱いであるが、基本的には、「一相」(人)と成るであろう。
男性の場合は「理想」であるが故に「三相」の重要度は同等と考えられるが、女性の場合は「時、場所」の「二相」は「感情主観」であるが故に、「時、場所」の二相にはその主観は生まれ難いであろう。その重要度では「人」に較べて低いと考えられる。
思考関係式 「感情」=2つの対比する「思考の差」 故に「2思考差」=「数理」=「勘定」
(2つの対比とは過去の感情、現在の感情、を言う。未来への感情は論理性で無いことから低いと考えられる)
女性には、「左脳域」の未来を予測する「中紀帯」が存在しないのはこのことを証明している。
性の相違の考え方(三相)
これは良し悪しの問題ではない。この世は3次元で思考しなければならない時、2次元で思考としなくては成らない場合もある。事は「人、時、場所」の「三相」に依ってその最適な処理方法は異なるであろう。だから夫婦の主張はここでも平行線と先ず間違いなく成る。
この「三相」を排除した思考ではどちらも正しいと思い込んでいる。「計画」「処理目標」の2段階の議論も平行であれば、両者の感情はどちらも高ぶるであろう。普通は殆どここで喧嘩となるであろうから話は次へは進まない。
しかし、そこで、無駄であるが、止む無く無理に「実行」の段階に話は移るとする。
男性は現実の環境から洞察して「左脳」から過去の「論理的経験則データ」を引き出し、類似的な「現実的データ」で実行しようとする。
女性は感情に基づく蓄積データの「数理的経験側データ」を引き出し、損得の「勘定思考」に基づき「妥協的」な計算方法を見出す。
「良い悪い」と「多い少ない」では中間の思考差は無い為に、2次元の「妥協」での実行以外に無くなる。例えば、この場合は本来は5:5であるが、感情論を持ち込んで6:4でまとめようとする。
ここでも平行線となる。
男女間の議論は適時適切に正しい判断を導くとすると、「三相」[人、時、場所]によりまとめる以外にはないが、しかし、この仏教説話でもある「三相」の考えは、男性の「論理思考」に基ずくものであって、女性には「感情主観」であるので、「不得手」とするものであろう。
多分、この段階で「感情主観」を超える思考と成り、パニックに近い状態(脳の思考停止状態)となるのが普通であるだろう。
この思考原理から考えれば、女性は「議論」そのものを受け付けなくなるだろう。
「家訓4」は、上記の関係式から、このポイントを深意として誡めている一つのものと考えられる。
[思考の傾向]
この様な男女の思考原理をある一つのものに当てはめて考えてみると次の様になるだろう。
例えば、この「思考原理」で「義」と云うものに対する思考採用度に付いて考えて観る。
この「義」は女性には理解され難い難物である。
男性では、「理想」を描き「合理的」に思考し「現実問題」として処理しようするため「義」が無くなることは論理的に考えれば人間としての「根幹」を失うと考えを重んじる。
人間は、他の動物と異なり、その「差」を「軌範」と云うものを以って「人」としている。
然し、女性では、「感情主観」を求め「勘定的」に思考し「丁度良い具合」で処理しようとするため「義」が人の根幹を占めているとは考えない。多少、「軌範」が崩れても、仲良く傷つかないように成るのであれば、譲り解決しようとし、「義」は思考の「根幹」としては女性は重んじない。
同様に「戦う」「争う」とか云う事に対しては、よりその思考原理の違いは顕著に現れる。
男性は解決する為には「戦う」[争う」も一つの解決手段としては決着がはっきりとする事から必要と考えるが、女性は、女性本能(母性)が働き醜い犠牲のある事を避けて「皆仲良く」とする「感情論」を引き出し、双方が傷がつかない手段として「妥協的」に納めようとするだろう。
結果的には抜本的な問題は解決していない訳だから、「一時的な手段」に過ぎないとして、合理的、論理的に考える為に男性は納得しないだろう。
(注 母性本能は子供が産む前に於いても、「思春期」という急激な経緯(体と心と仕種の変化)を経て以降は、母性本能は基本的に育つ事に成る。同時に女性のこの思考パターンも育つ。産む事に於いて「体の変化」で全て整う仕組みと成っているのである。)
男女の性を決める脳の「継電機能」
女性の性の代表的なものとして、「母性本能」がある。この医学的メカニズムは、次の様に成る。
「前頭葉」や「側頭葉」に対して、マイナス電位0の地球とその人の身長差分だけの電位が「脳幹」に働き、その結果「電源」と成った「脳幹」から発した電気信号は、回路となる「脳神経」(ニューロン)を通じて流れ、「前頭葉」や「側頭葉」の直前で、この部位との神経の繋ぎ目(シナプス)にNaイオンから成るアルカリ性のキャリパーという呼称の液体が飛ぶ。この液体の+Naイオンに電気信号が載り、「前頭葉」や「側頭葉」に繋がる。通常は通電0.2秒間程度である。しかし、女性は一般的にこの通電時間が長く約2-3倍程度であり、この通電時間が長く繋がった状態に成るのが、「感情」の最たるものの「母性本能」である。「母性本能」は産む事だけで起こるとは限らず、それに近い状態の刺激が起これば通電状態と成り、「母性本能」は発生する事と成る。だから女性は、幼子でも、男性より「可愛い」と云う感情をより示すのはこの通電時間の長さに起因する。
他に、「うつ病」はこの繋がった状態である。次第にリード(通電)する神経が疲労し、「脳」も通電状態と成っているので、エネルギーが莫大に必要とし、それを補う為に、栄養素や、Naイオン等のミネラル分を多く必要となる。これは無意識の中で起こる現象なので、自己の意識能力では直せない事に成る。外部から電気信号を切る手立てを考えなくては成らない。最も良い方法は「環境」を変化させてこの信号を切るのが効果的である。
電気回路学では「自己保持回路」と云う方法である。別の神経回路から信号が入り、回路は目的とする負荷の脳の感情部を繋ぐ。するとこの刺激でこれと同時に感情部から自分で神経回路を作り、元入って来たの所に繋いで感情を維持させる方式である。元来た回路信号のON−OFFに関係なしに保持されてしまう方式である。
女性は男性に較べて脳医学的ではなく電気回路学的にも、この回路方式を強く持っている。だから「感情主観」が主体と成るのである。
女性は「感情主観」を原理としている以上、この現象になる可能性が高いのである。逆に言えば、この機能があるから、「感情主観」の証拠と成るとも云える。
男性では、これではその男性の「性」を達成できない為に、「側頭葉」で感情を抑える機能が働き、この自己保持回路の現象を出来る限り防いでいる。
男性が「戦いの殺戮」を平然としてできるのは、この「抑制機能」が働くので、出来るのである。女性はこの「抑制機能」が無い為に「戦いの殺戮」等の行為は出来ないのであり、必然的にも、「体」も必要が無い為にそれに順応して筋肉質ではない。脂肪質である。男性はこの逆である。
ところが”男性のうつ病は何故起こるのか”と言う疑問がある。
回路としては同じ自己保持回路である。
しかし、ここで違う点がある。それは、男性の場合は同じ事を何度も繰り返すとその回路の保持状態が容易に成る。つまり、同じ事を悩んだりすると、何回もこの回路が入る。癖に成る。最後は自分の脳で事故保持が切れなく成る。これが男性の「うつ病」である。女性は「感情」の思考原理から、この回路が入る事を「性の機能」(産み育てる)として「心と体」の機能を維持するために本来出来ている。
もし、女性がこの自己保持回路の状態が「性」以外の所で起こったとすると、「妥協」と云う手段でこの回路を外す思考原理を持っているのである。その問題が合理的に完全解決にならずとも「妥協」という手段で逃げられるように脳の機能は出来ているのである。
男性から観ると、女性のこの意味の無い日常の「しゃべくり」がこの最たる行為であろう。この「シャベクリ」が「うつ」を抑える役目をしている。
男性のこの「うつ病」は厄介である。
「妥協」は解決もしていないのに、”中途半端で済ますのは卑怯だ”と男性は考えるだろう。それは男性の考え方であり、男女の共通の思考ではないのであり、「正悪」(性悪)の問題ではない。
それは、その様に「神」が創造したのである。文句をつけるのは「神」に文句をつけるが如くであり、人間として不尊そのものである。
男性の場合のように「論理、合理」とすれば、その問題の合理的に解決しない限り、回路は外れない。
「戦いの例」
男性にとっては、次ぎの様に考えるだろう。
この2000年の有史来、感情的にはそうあって欲しいが、「仲良く」で解決したものは無いし、「戦い」は常に起こっている。人間の生存競争はそもそも「戦い」である。種の「民族」がある限り民族間利害が起こる。「利害」は争いを起す根源である。この根源がなくならない限りは「戦い」の「仲良し」の解決方法では絶対に納まらないとして、以上の「経験則データ」を割り出して、論理的に納得しない様に脳が働くのである。
脳の働きは、兎も角としても、先ず、未来に於いても「戦い」はなくならないだろう。進化がどんなに進もうと、この「世の摂理」である「種」の存在は無くなる事は無い。依って、男性の論理的結論はこの摂理がある限りに於いて正しい事に成り、「現実的対応」が必要となる。故に、男性の「現実的対応」の思考原理は正しいことを意味する。
女性はこの「戦い」を最悪として考える。多くの感情が渦巻く最たるものであるからだ。
男性に於いても、「戦い」が好きな者はいないであろう。居るとすれはそれは思考錯乱者であろう。
男性の「戦い」は事の終局的解決の最終手段として「論理的な合理思考」の中に置いているに過ぎない。「戦争反対」と叫ぶ女性の多くは、自分を「正の位置」に置き、他を「悪の位置」に置いて他の責任を叫んでいる感情傾向がある。「思考原理」から止むを得ないのであるが、「戦争」に成る原因の一端も民族社会の中で同等に担っていることを忘れて叫んでいる。「叫ぶ」と云う事は、他の者が恣意的に「戦い」を選んで好んでしているとして、その「責任の所在」を叫んでいる事になる。
そんな人間は居るのか、自分の責任は何処にあるのかとなる。これが女性の感情主観の男性側から観た理解に苦しむ言い分となろう。
この様に「戦い」と云うキーでは「性による思考」の差は異なるのである。
思考データの体系化
つまり、男性は、今まで長い間の「遺伝と体験」で「会得し学習」した「知識:データー」を左脳に一つの形で「体系化:理想」して主体的に記憶して置くのである。
目標として、この記憶の「体系化(理想)」に沿って、一つの「構成要素(系列:ツリー)」の最も良いもの(合理)を導き出す事を行うのである。
得られた「合理の目標」を実現するために、「学習経験則:ウェーブ」に従って、その過去の類似する経験則を選択して、意識の中で事に当り行動するのである。
この思考パターンを採る事から”「皆仲良く」「傷がつかない手段」”と云う形では、過去の「遺伝子的データ」にも、「個人の経験則」からも系統化されていないので、割り出されたデーターで解決しない事と成る。多少の犠牲はあるとしても、男性思考は本来の抜本的な理想的な解決を求めようとする。
女性の場合は、この「理想」(計画)の記憶領域は、主体は「感情主観」として分類化、系統化されて「勘定理」(目標)に基づき収納されている。従って、論理的な思考は原則的には採らない。
採らなければならない時は、「訓練」してその経験側を左脳に記憶量を多くする以外にない事に成る。感情的で勘定的に処理しなければならない時は男性も同様である。
従って、女性はその感情思考のデータ以外の出来事(感情主観を超えて理解できない出来事:災害や悲惨事)が起こるとパニックになり易いのはこの事に成る。
この様に「深層思考の原理」が、元より下記の様に、元来、「脳の収納方式」そのものが異なるのであるから、「男女の思考」は完全一致は難しい。無理にまとめ様とすれば対立し、何とかまとめ様とすれば何れかが譲歩する以外にない。
何はともあれ、この世の神が創った摂理は、男女「6つの思考」があってこそ、この世の出来事に対応出来る様になっているのである。
神の成させる仕組みである。
「性」の差異の解決策
神仏が創ったこの解決策は「三相」(時、人、場所)を「適時適切」に採用する事以外に無いのである。
男女は「三相」を「理解、認識、訓練」し「性」の弊害を超える事が必要と成る。これに尽きる。
しかし、実生活ではこの事「三相の認識」が核家族で忘れ去られている。
昔は、三世帯家族が主体で有った事から、自然に「三相の認識」が教えられていたのである。
祖父母の年寄りは、口癖の様に日常生活の中で、「時が悪い」「相手が悪い」「場所が悪い」等を云ったものである。時には好んで、占い、八卦、方位、祈祷等を駆使して決めたものであった。
今でも遺されていて、結婚、建前、慶事、祝事にはこの「三相」を選んでいる筈である。
これは過去の「仕来り」の中に「性の弊害」を取り除く為に、「先人の知恵」として戦前まではこの「三相による解決策」が自然に生活の中に組み込まれていたのである。
不幸にしてかこの「先人の知恵」はアメリカナイズされて消えうせて行ったのである。
「家訓4」に遺されているのは、この「先人の知恵」として、上記の論理的根拠を得ずしても、それを忘れさせない為に、先祖は書き記していたのである。「自然の摂理」の弊害を克服する術として、人間の「性の弊害」を克服する術として、「深層思考と三相」を併用して教えているのである。
裏を返せば、今ほどではないが、先人達の時代にも徐々にではあるが、「性の弊害」が起こっていた事を意味している。
先人達の長い歴史の中にも有ったとすると、男女はこの上記する「性の深層思考」が有る事を認識し自覚する事、即ち、家訓4を知ること以外に無い事になる。
知らなければ、自然に男女の「対の相性」が合わない限り、又どちらかが引き下がる事をしない限り、「歪みの無い解決策」は有り得ない事に成る。
古来に於いての「日本的解決策」は、この”どちらかが引き下がる策(特に女性)”を「社会の掟」(謙譲の美徳)として採用されてきたが、現代に於いては、アメリカナイズされた社会でありながら、又、科学による付加価値も急激増大している社会でありながらも、未だ「男性の思考」に於いては、この「掟、慣習」が強く遺されている。地方によりその慣習、掟が遺されている気がする。否、全ての男性の心の奥底に持っているものであろう。表に出すか出さないかの違いであろう。
従って、この過渡期の社会では、男女はこの「家訓4」を知ること以外に無い。
そして、その「三相」を「採用する訓練」、男女の「人間性を磨く」必要がある事に成る。
先祖は、問題の発生原因は別として矢張り多くあったのであろう。
多分、先人は平安初期から江戸初期までの長い期間の「戦い」から来る問題、現在人は1800年代からの「付加価値の増大」から来る問題と成ろう。
どちらにしても。この思考形態を理解する事を根拠として、この家訓4はこれを説いているのである。
「脳の収納方式」
そこで、この事に付いてより理解を深める為に、「脳の収納方式」を解いて見るとよく判る。
人間の脳は進化して、脳の中は、判りやすく云うと、「幹、枝、葉」の形の3分類の形でデータ−化されて収納する仕組みと成っている。
(コンピータもトラック、クラスター、セクター、として最低8進法でこの仕組みを使っている。)
「幹」の収納庫は、論理的に組み立てられた形(理想:感情)で収納され、「枝」は幹を構成するものとしての要素群(合理:勘定)がまとめられて収納さる。幹枝を生かす「葉」に相当する収納庫(経験:個別データー)には内容別が収納される仕組みに成っている。
男性の場合は、この男性の「感情」(計画)の記憶領域は、経験側の領域、即ち、葉の部分に別々の収納庫に保存されていて幹枝として体系化されていない。
この様に、脳の動作原理は、先ずは無意識の中で起こり、次に意識へと戻る仕組みと成っている。
それは、「無意識の中」即ち、”人は自分の意識で「管理出来ない意識」がある”という事である。
そして、この「管理出来ない意識」は男女共に異なる意識を持っていると言う事である。
この意識の「有無」を認識しないで行動する事は、人生にとって「本道」を歩めないと言う事なのである。
つまり、究極、人間は他の動物と寸分違わずして、この世に生まれて来た目的は「子孫を遺す」事に有る。その過程での「喜怒哀楽」は目的ではない。
従って、この「管理出来ない意識」の存在有無を認識しない事は、人本来のこの世の目的の[子孫を遺す」と云う事に障害を生む結果と成るのである。その障害の過程は「喜怒哀楽」の「怒哀」の割合が人生の中で大きく占める事となり、結局、最終、「子孫を遺す」と事への確率は低下する事に成る。又、人生上の問題を起す事に成る。
最近、世情が近代化と科学化に依って付加価値が急激に増大して、人生を全とうする事に難しさが生じて来ている。そして、結果として人心に余裕が無くなり、且つ、人間性が低下する現象が生まれて来ている。
この様に成れば、思考に余裕が無くなり必然的に人の思考は仏教で云う「刹那思考」と成って来る。
この「刹那思考」から、人間本来の生の目的「子孫を遺す」と云う事よりは、「目先の喜楽」にその目的を見出そうとして来る。「刹那思考」つまり、「子孫を遺す」と云う長い目的ではなく、死を直前にして起こる「追い込まれた心情」と成り、人は「目先の享楽」とその継続を追い求める心情事に成る。
この様に成れば、必然的に人本来の目的から離れ、「歪みの人生」が生まれる。
特に、この様になれば、家訓4の云うその「深層思考」からすると、女性の思考が大きく左右される。
恐らく、未来はより近代化(付加価値の増大)が起こり、「人、時、場所」の「三相」の内、「時」が大きく変化するだろう。その「時」はより「加速度的な速度の進化」で起こるだろう。
必然的に、「科学」による「速度の進化」で有る事から、「合理の進化」と成るだろう。
そうすると、女性の「深層思考原理」の「感情主観」からすると、大きな「ストレス」が生まれるだろう。当然、女性に起こる以上、この影響が男性にも影響が出て来る事は必定だろう。
この事は、これからでなくても、家訓が遺された頃からも同じ事が云えたのではと思える。
つまり、「原始の生活環境」から男女の役割は、次第に「進化と付加価値の増大」が進み、より変化して女性側にストレスが掛かるものと成ったと見られる。故に、日本社会は女性側に対して女性の弱点を補う為に、且つ、本来の女性の幸が存在する場所を求める為に、「女性の慎み」を求めたのであろう。決して、女性蔑視から来るものでは無かったと「家訓4」の意味として理解している。
青木氏の「家訓10訓」の深意は概してはこの一点に通ずると理解している。
多分、主にこの「家訓4」は鎌倉末期頃の下克上と戦国時代の激しい「戦い」の中で生まれ追記されたと観ている。全体の家訓群は平安末期から鎌倉末期頃までの乱世の「訓や戒め」が追記されてきたものであろう。
その影響の典型的なパターンは、人間本来の目的とする子孫を遺すと云う行為「子育て」であろう。
「子を産み育てる」という事からすると、女性の思考原理ではなくては「産み育てる」は無理であろう。世の常として、災難や災害が起こると、先ず、女性と子供を助けると言う行為はこの事から来ている。男性が多くあっても子孫は遺せないが、女性が多く遺せれば子孫は再び蘇る摂理はここにある。昭和の大戦を始めとして、有史来2000の戦いの結末は男性が多く死するが、子孫は再び蘇っている。この摂理からすると、神は女性に「人間の本質」を与えたものであろう事が判る。遺伝子的にも卵子の中に人間の種の遺伝子を保持しているのはこの証明であろう。
決して蔑視差別から来る「慎み」では無い事が判る。神もこの「慎み」を以ってより安全に長く生き延びさせる「性」を与えたのであろう。
その証拠に、医学的にも女性には「女性ホルモン」で45歳程度まで病原体から体を保護する仕組みにも成っているし、「脂肪」で外的環境からその体を護っている。男性にはこの仕組みはまったく無い。神は”勝手にしろ”である。
それどころか、現代脳医学では、「側頭葉」には、「戦い」などの「人間の殺戮」の際には、この「感情」を司る部分の感情を停止する機能もある位である。つまり、「戦い−死」のシステムは本能的に出来ているのである。そのために神は更に重ねて、都合良く左脳の記憶集積回路と連動する「中紀帯」という小指の先ほどの「独立脳」を創り上げているのである。「戦い−死」と言う行為をより効率よくするために「未来を予測する脳」である。「原始社会」(食うか食われるか)の環境を「2足歩行」に成った事からより確実に生き抜く為に、この二つの脳は備えられた機能である。
男性が、養育期の子供を「育てる」と言う事に成ると、男性的な思考で「良悪、優厳、仲良く」の人間的な基本感情を教えると成ると無理が生まれる。逆に、成長期、思春期の子供に対する子育てとなると、女性には「良悪、優厳、仲良く」では厳しい世間を渡れる力を付けてやる事は無理であろう。
雑である男性ものと違い、女性の「心」細やかで伝えるものの養育でもこの様に成るだろうが、「体」の面でも「筋肉質」の男性では養育期の子供に伝わるものも本来のものとはならないだろう。同様にして「仕種」の「滑らかな仕種」でない男性のものは養育としては難しいものが一般的にある。
思春期(13歳頃)までの養育としては女性の「性(心、体、仕種)」でなくては成らないだろうし、15歳以上は男性の性が必要に成る。
昔の成人は寿命の関係もあるが、15歳と成っていたのは社会に出て鍛えられる「現実感覚」をこの時期から必要とされていたものであろう。
つまり、「養育」という言葉を分析すると2つに成るだろう。1つは「育てる」、2つは「鍛える」と成るであろう。そこで、女性は「性の思考」は「育てる」に有って、男性の「性の思考」は「鍛える」にあるとなる。本来2つの「性の思考」はもともとこれで「一対」なのである。
子孫を遺すと云う本来の「性」の目的はこの様に異なるのであり、神はそのように創造したのである。
家訓の活用具合例
事程左様に、あくまでも思考原理の「善悪の問題」ではなくて、「人、時、場処」の「三相」に対して、「適時(適切)」に、その「思考原理を保有する事の特長」で対処する事が必要である事に成ろう。
上記したが、現代に於いては、この「適時」(「適切」)が狂って来たと観られる。
言い換えれば、人間本来の目的「子孫を遺す」という前提に於いて、この世の「万事万象」に対して、この「二つの深層思考原理」が必要で、初めて「万事万象」に対応できる事に成り、”「合わせて一つの思考」”となる。
つまり、「男女の深層思考原理」は夫々が一つではないのである。その役割を分担しているのである。神はそのように定めたのである。
「家訓2」にも記述しているが、例えば、男性は成人まで母親に育てられ、父親に鍛えられて養育されるが、その後、嫁に引き渡されて婚姻後の養育を任す事に成る。
筆者は家訓の意を重んじて、かねがね嫁娘に3人の孫を含む「4人の子供」を育ててくれるように頼んでいる。そして、息子の結婚時には、”これからの社会に通じる養育は我々から、貴方が息子を自分の子供として孫と共に任せて育てるのであり、バトンタッチしたのだ”と、そして、”その心は「お釈迦様の掌の中で」としてお願いする”と、”決して一人の男性のみに偏らないでと、親としてお願いする”と懇願した。そうすれば、”貴方は貴方の育ての素晴らしい母親以上の「天下の母親」になる”と、”天下の本当のあるべき姿の女性になる”と付け足したのである。”何時しか貴方が我々の役目を果たす時がくるまで”と。いつも理解してくれて嫁はこの事(4人の子供)を云い笑い話に成っている。何よりも有り難きかな、そのように嫁は息子と孫の養育には社会に通じる様に育ててくれている。
我が家では、「家訓10訓」の前提として、”孫は息子夫婦だけのものではなく、先祖を含む家族のものである。息子夫婦はその養育に主責任を担っている。それに必要とする「経済的負担と精神的負担の軽減」は家族全体が担う。と云う考えにしている。
その考え方から、全ての思考が出ている。端的に云えば、孫が素直に元気に育ってるとすると、「ありがとう」と嫁に云う。
現在は、夫を只の男性と見なしている事に問題があり、女性のその人生での働きの重大さを認識していない所から来ていると思っている。
しかしながら、むしろ、本来は、男性よりは女性の方が難しい「人生負担」を担っていると考える。男性の難しさは本質は「単純無比」で、女性の方が「複雑繊細」であろう。
その思考原理から見ても、「産み育てる」と云う機能原理に思考形態が出来ているが故に。現在の社会では苦労が多いであろう。
先人も時代は異なれど、家訓10訓から観ても同じ考えに至っていたと思っている。
この言い分は「家訓1−4」を一まとめにした筆者の結論であった。
[結論]
ところが、この家訓4には、次ぎの事が簡単に書かれている。
”この家訓4に拘ってはならない”としている。
これを理解するには大変な時間を要した。
「性」に違いがあることは医学的にも調べても理解できたし、その解決策も理解できる。
知っておいて対処すれば、男女共に問題は無い筈だ。別に蔑視している訳ではない。
後で気がついた事であるが、大きな落とし穴があった。
先祖は科学的根拠は何も無いのにここまで摂理を的確に見抜いてまとめられたものであると驚いているのに、しかし、確かに拘っては成らない事である事が判った。
これは難しい。仏教禅宗の禅問答である。”家訓4は摂理である。しかし、摂理に在らず。これ如何に”である。昔は先祖は邸に禅僧が常に長投宿させていたし、代々漢詩や漢文による禅問答をしていたので”禅ボケか”とも感じたが違った。筆者は根からの理屈の技術屋だから、”それを理解しそれを「三相」を以って適応すれば、それはそれで良いのではないかとも思ったが。後は、個人の資質の問題であろう。”と考えていた。
”むしろ人を理解すると言う点では良い事で一歩も二歩も前進では。”とも考えた。
では”何故拘っていけないのか”を検証して見る。
1 仏教の説法の「色即是空、空即是色」から如何なるものに対しても「拘り」を誡めているのか。
2 「性」の摂理と解決策では何か問題が出るのか。
3 男女の何れかから不必要な反発を受けるのか。
究極は、1の答えとしては”「拘り」を誡めている”事に到達する訓であろうが、この2つの「深層思考」はともに脳に依る無意識の中での事であるのだから、例えば、男側が女性側に争いを避ける為に、この摂理の「理解」を受ける様に説得しても、男女にはそれぞれの思考を持ちえていないのだから、「理解」を得られる事は出来ない理屈となる。つまり、「永遠のテーマ」となる。
なにせ、「論理的思考」をベースにしている男の「性」と、「感情的思考」をベースにしている女の「性」では”根本的に相反する位置に”あるのだから、”「理解」を求めて一致させ様とする事態”が間違っている事になる。融通利かせる別脳があるのであればいざ知らず、無いのであるから、止む終えず少なくとも間違いであるだろう。
むしろ、この家訓4では、”一致させない事”が本来あるべき姿であり、”相反している事”で”物事が6つの思考から正しく導かれるのである”としているのだろう。
それを”如何にも正しい行為かの如く無理に「理解」という形の解決策に持ち込もうとする事”が”その行為に歪みを生む事になるのだ”としているのだろう。これが2の答えであろう。
この「行為」そのものが、過去の社会では「慎みの美徳」として女性側に求めていたが、何れかの「性」の方に「我慢、妥協、諦め」を生む事になり、それが何時しか「ストレスと成って爆発する事」(不必要な反発)の結果を生み、「営みに失敗を被る事」になるのだろう。これが3の答えであろう。
伊勢青木氏に於いては、この「慎みの美徳」を「社会の掟」の様に、当然の如くに求め理解を強いた結果、「900年も続いた紙問屋」や「伊勢青木氏の家柄」の大母体を維持する事に目が向き、”女が青木を潰す”という「一方的な戒め」として伝えられ来たのであろう。
明治35年に「慎みの美徳」の歪みが出たのか、”女が青木を潰す”(松阪大火の火元)の結果がまたもや出てしまったのであろうか。先祖伝来のステイタスの生仏像さまの戒めであろうか。
伊勢青木氏の失態は、家訓4がありながらも、この事に拘った為に、この訓の本質を見失っていたのかも知れない。
では、この「拘っては成らない」の本質とは、どの様に解せば良いのかということである。
幸い筆者の時代では、先人の失敗を繰り返したくない事から、この「性の摂理」の科学的根拠を探求して得ることが出来た事から、先人と違う「慎みの美徳」とは違う本質なるものを得たと見ている。
幸い時代と環境が違った事から得られたものであるが、未来に於いては、再びそのような環境が生まれて、「慎みの美徳」の方式に戻る事もあり得るだろうが。
何れが真実かは知り得ないが、兎も角も、”「拘り」の戒めの解釈”の答えは、現代では少し違うと考えている。
本「家訓4」の「拘りの誡め」の結論は、次の様に成るだろう。
そこで、つまり、”何れか一方が永遠に「理解」の得られない「性の摂理」がある事を知り、その「性の知識」を以ってして上手く処理せよ”という事であろう。
そして、現代に於いては、”過去の「慎みの美徳」環境から脱却して、その事により、「我慢、妥協、諦め」の環境をより少なくする様に努めよ”としているのであろう。
”世の「理解」というお題目は、「性の摂理」にだけは通用せず”と認識し、”「性の摂理」があるからと言って拘らず、””「性の摂理」を決して相手に求める事は相成らず。としている事になる。
兎角の「理解」の「衆生の論」は金科玉条の様にもてはやされるが、決して「家訓3」でも誡めている様に「性の摂理」に関しては惑わされては成らないものであろう。
「性の摂理」は上記した通りであるが、少なくとも、この「家訓4」の「性の知識」を知る事で、より相互に「求める理解」ではなく、「自然の理解」(「自然に生まれる理解」)が生まれるであろう事を期待する事であろう。
しかし、不幸にして、この「自然の理解」が得られにくい社会環境に成っている事は否めない。
まず、「性の摂理」の知識が、現代社会の相互間のコミニティーが低下して、伝わらなくなっている事で、この「自然の理解」が得られず、男女間のトラブルが多発しているのもこの原因であろう。
そして、再び、日本的という言葉を使い、「慎みの美徳」が短絡的に叫ばれる様に成っている事も事実であろうし、両極の「求める理解」もマスコミでは誠しやかに論じられているのには疑問を感じる。
そこで、少なくとも、「家訓1」から「家訓4」では、この知識の提供の一助になればとして家訓だけを期する事だけではなく、その理を論じている事に理解を得たい。
[重要ポイント]
「性」による深層思考
脳の無意識の3基本動作 「計画 処理(目標) 実行」
「性」の無意識の思考原理
女性の無意識思考 「感情 勘定 妥協」
男性の無意識思考 「理想 合理 現実」
「性」の働き
「3つの性」(体の仕組み、心の仕組み、仕種の仕組み)
「性」を管理する脳
「脳陵体」「中紀帯」
「合理」と「勘定」との差異
男性の場合は、「理想」に基づく「論理性の合理」である。
女性の場合は、「感情」に基づく「数理性の勘定」である。
「性」の目的
男性の目的は、子孫を「鍛える」にある。
女性の目的は、子孫を「育てる」にある。
「性」の進化
「生存に適した進化」
「環境に適した進化」
「科学に適した進化」
「突然変異による進化}
「性」の過程
「性の転換」
「性の合体」
「性の分離」
「性」の管理源
「腸の管理」
「脳の管理」
「性」(脳)の管理)
「性の進化」
「性の分離」
「性の整理」
「性」(脳)の3つの進化(栄養素)
「Naイオン」
「Caイオン」
「Mgイオン」
「脳」の性情報の体系化
「3段階の収納体系化」
「幹、枝、葉」の形の3分類
「性」の変化要素
「増大化」
「拡大化」
「発達化」
「変異化」
「進化」
次ぎは「家訓5」に続く。
Re: 伊勢青木家 家訓3
副管理人さん 2008/02/27 (水) 16:26
家訓1と2に続いて家訓3に入る。
青木氏の家訓10訓
家訓1 夫は夫足れども、妻は妻にして足れ。(親子にして同じ)
家訓2 父は賢なりて、その子必ずしも賢ならず。母は賢なりて、その子賢なり。
家訓3 主は正しき行為を導く為、「三相」を得て成せ。(人、時、場)
家訓4 自らの「深層」の心理を悟るべし。(性の定)
家訓5 自らは「人」を見て「実相」を知るべし。(人を見て法を説け)
家訓6 自らの「教養」を培かうべし。(教の育 教の養)
家訓7 自らの「執着」を捨てるべし。(色即是空 空即是色)
家訓8 全てに於いて「創造」を忘れべからず。(技の術 技の能)
家訓9 自らの「煩悩」に勝るべし。(4つの煩)
家訓10 人生は子孫を遺す事に一義あり、「喜怒哀楽」に有らず。
家訓3 主は正しき行為を導く為、「三相」を得て成せ。(人、時、場)
関連訓
「三相の論」
「衆生の論」
「万物の輪廻」
「女子と小人養い難し」
摂理「5つの変化」(上限変化 微分変化 変曲点 積分変化 上限変化)
摂理[S字パターン」「N字パターン」(回帰法)
この家訓を理解する上で、伊勢青木氏の歴史的な経緯が大きく左右しているので、先ずそれを先に述べる。
歴史経緯
伊勢青木氏は大化改新で発祥し、1315ー20年頃から「2足の草鞋」で商いを営み明治35年まで「紙屋」として続き、男系継承は耐える事なく現在に至っている。
ステイタスも笹竜胆紋と生仏像様を維持している。又、後150年は孫の時代であるので確実に継承する事が約束されている。
この間には多くの波乱万丈の歴史を保持しているが、この過程では、伊勢青木氏の子孫繁栄の秘訣を家訓10訓として何時しか遺されている。此処まで来られたのはこの家訓のお陰げであり、これを先祖は人生の最大目的軌範として護り続けたものであろう。現代も護る軌範としている。
この歴史事から、侍として、商家としての長い歴史の経験から「戒め」としてのものが出来上がっているが、特に、この家訓3となった経緯が大きく左右している。
従って、最大の理解を得る為にその経緯を先ず優先して次に示す。
歴史的事件に直接関与
その由来を調べると、日本の歴史上の大きな出来事に直接的に殆ど大きく関わっていることが判る。
例えば、1 647ー780年頃の大化期の大化改新で発祥(647)し、勢力拡大して皇親政治の主役となった
2 その後、150年後の桓武天皇の母方の阿多倍一族の引き上げ事件とその一族との軋轢(781ー806頃)
3 その阿多倍一族の末裔の京平氏と嵯峨期から発祥した同族の源氏の勢力争いの戦い「保元平治の乱」(1153--59頃)
4 青木氏と源氏が衰退する中での青木氏の遠祖の源頼政の「以仁王の乱」で合力(1178-80頃)
5 それ4を引き継いだ「治承寿永の乱」での一族一門の同族としての戦い(1180-85頃)
6 頼朝の旗揚げと「伊勢青木氏の本領安堵」、鎌倉幕府樹立後の北条氏との軋轢と「2足の草鞋策」の自立(1195-1235頃)
7 室町幕府の伊勢の国の半国割譲(伊勢北部伊賀と伊勢南部長島)での衰退(1465-73頃)
8 紙屋長兵衛が後ろで糸を引く伊勢の一向一揆から始まった信長の「伊勢長島攻め」(伊勢大河内城)での北畠氏への合力(1569-75頃)
9 台頭著しい信長の伊勢攻め「伊賀天正の乱」で名張城、度会の山城青木城での敵対(1573-77年頃)
10 蒲生氏郷(秀吉命)の伊勢青木氏(本拠地五日森の松阪城:平城松ヶ島城)の「松阪攻め」(1578ー82頃)
11 戦いでは最後となった家康の「大阪の役」の参戦(1614-15年頃)
12 明治の初期に「地租改正」が起こり三重から各地に伝播した「三重大一揆」(1870-72頃)
13 明治35年の(出火元)松阪の大火と600年以上続いた紙屋の倒産と賠償(この時期数年立て続けに悲劇が起こる)
これ等の主だった歴史上の大きな事件と戦いに直接的に巻き込まれた。
647年から1620年までの他の政治軍事の権力闘争の戦いではいくらかの関与はあったと見られるが、上記のこれ等が史実として明確に成っている青木氏の存亡としての大きな分かれ目の戦いであった。
この様な戦いの中でありながらも無事生き残れた。
(参考 1185-1300は安定期:1315-1325は「2足の草鞋策」期:1330-1573は下克上戦国で苦難期)
「2足の草鞋策」と「不入不倫の権」での生き残り
それは、商家として手広くしていた「2足の草鞋」と、古来奈良期よりお墨付き「不入不倫の権」で護られていて救われた青木氏始祖の「伊勢青木氏」があったからこそ、この二つ事で生き延びる事が出来たのである。
当然に、この様な経緯からその家訓は必然的にその影響を色濃く繁栄する事となろう。
この全家訓は、この事の背景を理解した上で、とりわけ家訓3にはその深意を汲み取る事が出来る。
「商家と武家」
家訓が出来る経緯の中で、ここには、”何故に商家なのか、何故に「2足の草鞋策」なのか”という疑問が残る。これを示す事件があるので特筆して紹介する。
天正の直接事件
この事件は信長と直接伊勢青木氏とが戦った有名な事件である。
900年間も護られてきた天皇家の本宮の伊勢には、天武期と嵯峨期に定められた「不入不倫の権」があった。
しかし、室町期の混乱期でありながらも護られてきた。然し、信長の「天下布武」の方針の下で、これ等の神社仏閣の既存権威は破壊された。
その護られてきた「比叡山焼き討ち」を始めとする一連の信長の禁断を押し切った「伊勢攻め」で、信長の一の家来の滝川三郎一益と信長の息子信雄を特別にこの伊勢攻めに差し向けた。
この時代では、周囲では信長の一斉討伐が行われていた。都に向かう掃討作戦の一環としてである。
先ず、この伊勢に於いては、それは信長が安心して京に進むには、最大の戦略課題であるこの伊勢路を確保する必要があったからである。
ここは青木氏の勢力圏と紙屋青木長兵衛の伊勢シンジケートのテリトリーである。
南北朝時代の楠木正成の10万の兵を打破した歴史的善戦でも知られるように、この域は伊勢シンジケートの膝元である。
この為に、伊賀に差し向けられたこの二人はこの為の拠点として伊賀の入り口の丘の上に山城(丸山城)を築こうとした。
しかし、材木が極端に不自然に高騰し入手できない。築城は全く進まない。
当然である。この域は伊勢青木氏で伊勢の豪商のテリトリーである。
紙屋長兵衛は、伊勢一帯を海の伊勢水軍と共に、戦乱で敗退した豪族を集め組織化し養いしたシンジケートで押さえている。それでなくては大きい商売は不可能である。
政治的、軍事的、経済的には、主に3つの護り城郭等を持ち、名張から桑田、員弁まで押さえている。
名張の青蓮寺城と度会の山城青木城と松阪郭館(五日の森の松阪城平城)で伊勢青木氏が押さえている。まして、大船を数隻を擁して海外を相手とする堺町にでも大店を出している。材木どころか搬送の船、人夫さえも確保できる筈は無い。
1年2年と全くと云って進まない。滝川氏は痺れを切らして紙屋長兵衛が密かに差し向けた人を頼りに、長兵衛と材木と人夫調達を頼む為に会う事となった。
商人としての顔も持つ長兵衛は誘いに入ったと見て、了解した。密かに、シンジケートに指令を出す。
材木は調達できた。城は長兵衛の意を汲んだ人夫達はゆっくりと建て始めたが、長期間の末に、やっと出来て天守閣がもう少しで建つというところで、念願の滝川氏と信雄はその城を見にきた。ところが、その時、爆発と共に城から火の手が上がったのである。長兵衛の伊勢ルートのシンジケートが仕組んだ作戦であった。
苦労の末に経済的に底をつく様なところで出来たが、水の泡と化した。一方、長兵衛とそのシンジケートは大もうけであり無傷の戦勝である。
再び元の状態に戻り、伊勢攻めは始まらない。この間、もう一方の武家の顔を持つ青木民部尉長兵衛信定と伊賀氏側では、名張(青蓮寺)城と青木本山城と伊賀城(柏原城)とで、次ぎの本戦に向けての作戦が着々と進められていたのである。この猶予期間を作りだす戦略であった。この二つの顔を持つ長兵衛であった。
これが滝川氏と織田信雄が「蟄居謹慎」に会った彼の有名な「信長烈怒」の史実である。
信長唯一の完敗である。それも影の商人に負けたものである。この後、信長は方針を変えて確固攻撃で無理押しの「伊賀攻め」に入った。
矢張り、本戦が出来ない伊賀特異のゲリラ作戦に入った。青木氏は、その信長の陣地を側面から崩す作戦に出た。つまり、2面の陽動作戦である。信長側は夜昼は無い。シンジケートの邪魔で食料は届かない。皆疲れ果てる。戦意は落ちる。
真に南北朝のこの地域で起こった「楠木正成の戦い」に類似する。
同じ紙屋長兵衛が指揮する伊勢のシンジケートが動いているのである。当然である。またもや長期戦である。
しかし、伊賀側でも消耗戦でありジリ貧である。最後は、青木氏の名張城から青木氏の本軍が伊賀城(柏原城)に入って共同決戦となった。
多勢に無勢である。結果は長期戦で伊賀城は落ちた。しかし、城は落ちたが伊勢青木氏は無傷である。
ところが信長は此処までが精一杯の戦いであった。伊勢青木氏の本拠地の伊勢松阪までは入る事は出来なかった。
その後、この前も秀吉をも同じ手で矢張り「伊勢長島攻め」で苦労するのである。そして、最後には秀吉の命を受けた蒲生氏郷の「松阪攻め」の青木氏の敗戦で終わる。
その後では、新宮に避けていた青木長兵衛は1年後に同族(清和)の血を引く氏郷の招きで紙屋長兵衛として再び松阪に戻る。
その後、秀忠を待つ為に名古屋に留まった「大阪夏冬の陣」の家康の要求に合力して、紙屋を中心とする全伊勢シンジケートを結集して伊勢路沿道警備として250人で参戦した。
徳川時代に入り、紀州徳川の松阪飛地領として青木氏と親交を続け、紙屋長兵衛では吉宗の「享保の改革」に依頼されて一族の者を同行させ勘定方として貢献する。親交は大正14年まで続いた。
(歌人でもある猛将の蒲生氏郷は、近江源氏で近江日野12万石から伊勢松ヶ島城(1584:元北畠氏の城で養子織田信雄の居城)に入り、松阪の四五百の森に石築の平城松阪城(1588:6万石)を築き近代的な商業都市を最初に築いた人物:伊勢青木氏と親交)
「伊勢で起こった2つの大一揆」
他に、伊勢国に長く関わり確固たる経済的基盤と権威を築いてきた1365年の歴史をこの地で持つ伊勢青木氏は、確たる証拠は失い無いが、1570の長島一向一揆に続き、1876年の2度目に起こった明治の「地租改正」に反対する住民の有名な大暴動の「三重大一揆」にも、立場上(伊勢国玉城町の面積の8割が長兵衛の蔵群であった事と松阪屋敷町2区画とその経済力)から考えると充分に裏で関与していたのではないかとも思われる。
実は、10年前の徳川時代に、この三重の豪族で紀州徳川氏の重臣で、伊勢を治めていた加納一族(吉宗の育親)との血縁がこの時期に伊勢の青木長兵衛の家とあった。
この加納家も青木氏と同じく「2足の草鞋策」で加納屋として大商いも営み地元の地主として君臨していたのである。
伊勢でこの二つの両氏が「地租改正」で土地を奪われるという事は氏の存亡に関わる一大事であり、伊勢で一ニを争う両者の経済力で、「伊賀天正の乱」の様に、この騒ぎの紐を操るとしても不思議は無い。又、一揆としても人間の成す事に変わりは無い。一時的な感情で動いたとしても続かないのが常である。経済的な裏づけがなければ長続きできない。当然、全国的な一揆としは繋がらない筈である。だとすると、証拠は遺さないであろうがこの推論は考えられるのではないか。
以上の1635年間で数多くの事件の三重付近で起こったこれらの史実事は、我が家の「口伝」内容を考察すると、上記の史実とがほぼ一致して伝わっている。
これは真に、「2足の草鞋」でなくては成し得ない生き残り策であり、この方策を先祖が時代の「三相」を見据えた深い判断で採った策であった事が判る。まぐれの1度や2度での事件の繰り抜けではない。「政治、経済、軍事」の3権を保持する事の明断であった事は疑う余地は無い。
それには欠けていたものとして、何度も繰り返される事件に対して、「武家としての権威による経済」では無く、実効の行動基盤の整った「商家としての実質の経済の力」の保持であった。その必要性を痛感し、自前であった「武家としての権威による経済」を活かし発展させて1315ー25年頃にこの策を判断したものであろう。
そこで、この事例でも見られる様に、この家訓3は「商家」と「武家」との両方での時の「生き抜く術」(人、時、場処に適時適切に動いた術)の結論であったものと見なされる。
故に、時の武力と政治の権威の信長を打ち負かす程の「力」を持ち得ていたのである。
そこで、これらの事を背景に生まれたこの家訓3を紐解いてみる。
簡単な文章の単語の全てに大きな意味を持っている事が判る。
「主の思考」
例えば、先ず、主語の「主」(あるじ)である。
「主」(あるじ)商家であろうと、武家であろうと、上に立つ者としての裁量の如何に依って氏や家の浮沈は決まる。
だから、「主」がしっかりとしていれば、1365年の間の上記の様な歴史を生き抜いてくる事が出来た。そして、何事もそのキーワードは”「主」に成る者の如何である”と結論付けたのは頷ける。
その重厚な経験から「主如何」と言えるからではないか。
私は、昨今では、それが全ての事件に欠けている様に思う。
もう少し、上に立つ者の「主」が、しっかりと「自覚」し、事細かに「目配」りをし、「厳しさ」を示し、「事の理」をわきまえて居れば防げた事件が多い。
確かに、世の中は一昔と較べて物事全てが「煩雑化」し「緊迫化」し「科学化」し「スピード化」している。
故に「主」の負担が大きい事が頷けるが、それで、適格者ではないと思えることが多いことも言える。
そこで、例えば、10の力で経済成長が進み、更に経済成長させようとすると10以上の力でなくては進まないのが道理である。
車に例えると判りやすい。車が40キロで走るとする。更に速度を上げようとすると、40キロ出力のパワーでは40キロ以上のスピードは出ない。当然に、出力をそれ以上に上げる必要がある。80キロで走るとすると一見倍の力だと思うだろう。
現代の日本はその域にあるから、我々の時代と異なり、その負担はより大きい。従って、組織を動かす者にとっては動力と思考の負担は格段に違っているだろう。だから指揮不足、不適格者とも思える事象が多く成っているのかも知れない。
と考えるのが普通であろうが、そうではない。私は少し違っているのではと思っている。
何故ならば、この思考には上限の「絶対値」というこの世の中に存在する生物、或いは動体には存在する思考が欠けているからだと考えているのである。
つまり、当然に、その社会になれば、指揮する者に課せられるそれなりの思考が存在するという事である。
それがこの家訓3にこめられた訓であると言うのである。
上記した先祖が遭遇した事件の「時代性」は、丁度、現代の社会の「時代性」と共通するものがあるからである。
その「時代性」とは、下記に述べる「5つの変化」のうちの「積分社会」の「上限域の変化」に遭遇していた事による。
当時の時代の基盤では成長の上限に到達していて、それに対する改革が成されなかった結果、上限に持つ特性の破壊、即ち、「下克上や戦国時代」と言う谷底に陥った「時代性」であったという事である。
故に、それを解決すべく長い期間の人間の葛藤が起こってしまったと云う事である。
現代もその谷底に落ちる手前に来て居ると観ている。化石燃料の枯渇や温暖化や世界の国格差などで、騒乱が起こる手前の時代性と一致する。(破壊に繋がるのは、私は論理的に矛盾を多く持った中国の結果次第が引き金と観ている)
この手前の社会の思考には、”無限に高一定率(「微分変化」)で伸び続ける動体は無い”と言う肝心な「自然摂理」の思考に欠けている事である。
現に、一般界、マスコミなどで、比較的、或いは殆どの「衆生」の判断には、この思考(微分変化だけではなく「5つの変化」域に限界値がある事)に欠けたのものが多い。
まだその認識に意識が至っていないことを意味する。安易な「衆生の論」に終始している。
此処で、時事放談をする。
先刻の選挙で民主党が大勝ちした。民主党は当初”「永田町 民意民意と せみが無く」”であった。
果たして、この「民意」は”「せみの声 正しい民意 民民ぜみ」(正しいせみの声)だろうか。
”「寒空に 民意ねじれて せみが死ぬ」”である。
”「せみの声 民(ミン)が悪くて 自民負け」”(ジーミン)でないのか。
”「せみ騒ぐ 感にさわるは 民(ミ-ン)の声」”
”「民意鳴く 好きと嫌いと せみの声」”(ミーンィ)
”「一つ鳴く 孤独の民意 せみの主」
「民意」と言うが、国政が滞り適時適切に施策が実効されなくては本来の国会の目的はない。
この「民意」は「衆生の論」でなかったか。果たして「民意」を何でもかんでも政治には「民意」では無い。
もし、「民意」が何時も「真の民意」であれば政治家は要らない。アンケートすればよい。それを官僚が実行すればよい。
「民意」はとかく「衆生の論」である事が多い。「三相の論」と「5つの変化」(下記)から導かれた論でなくては世界を相手に打ち勝てない。そのために、「主」としての「政治家」を送っているのではないのか。
ただ、この「主」の政治家が「衆生の論」の見本の様な「おてて繋いで」「仲良しクラブ」に「主」に値しない資質の者を用いてしまったトップの「主」が居た事に寄るのではないか。
この様な人事をするトップの「主」の思考(資質)の低さ(三相の論)があったのではないか。
又、何も、「民主」が良くて「民意」が民主に傾いたという事ではあるまい。(どの世界にもこの様な人物が居る)
時に、「民意」に反して、「三相の論」と「5つの変化」から「主」の者は、一人孤独で思考を巡らして、国を導かなくては成らないのではないか。だから、国を委ねる大事な立場なのだ。「民意」(衆生の論)で出来れば苦労はしない。
真に西郷隆盛の「女子と小人養い難し」ではないか。「感情」で政治が出来れば政治家が要らない。
「民意」は兎角「感情」が主体と成っている事に、「主」たる者が知る事の「主の資質」なのだ。
政治は「歴史と現実」を背景とした読み取り論理である。これは、況や、「5つの変化」から「三相」を読み取る資質なのである。
即ち、下記の「色の理論」「波の原理」とする世情の「流」を読み取る資質である。
この見識なくして「正しい民意」を「衆生」が出来るというのか。
では、その「正しい」ものを導く思考(主の思考)とは、一体何なのかを次ぎに示す。
万事万物万象には摂理「5つの変化」なるものがある。
自然摂理「5つの変化」[万物の輪廻(りんね)]
「上限の限界値」
ものには、先ずその一つその主力の絶対値、つまり、「能力の限界」(出力限界:上限の限界値)があるからだ。その出力限界に近くなれば、エンジン過熱や、燃料の燃焼、各部品の耐力、環境条件、空気水分、等の条件が限界値に到達して比例的に出力は上がらないのである。
S字の上の曲線部の末端部である。(末端の短い部位は若干下向き線が多い)
この時の直前の変化は、「積分的変化」を起すのである。
この世の全てのものはこの変化を保持している。例外は無い。
従って、その出来事の評価、判断はこの摂理に従って行わなくてはならないのであるが、ところが、マスコミなどで示される評価、判断は殆ど「微分変化」だけの思考で、無限の「微分変化」は無い事を知らず、「積分変化」の有無も知るか知らずか、殊更に自慢げに自身を持って述べている。特に解説者やコメンテーターなどは100%である。
この上限の末端の特性はその物質を構成する分子の「破壊」の現象が起こる。
「積分変化」
つまり、上限の手前のその変化を曲線で現せば「積分曲線」(双曲線)と成る。
1のものに対して2乗分の1とか3乗分の1とかの変化しか起さない事を意味し、急激に出力は低下する。最後には、殆ど確認出来ない程度のものとなる。これが「積分変化」と言う。(1/Kの乗数:積分率)
S字の上の曲線部である。(この曲線部の末端前は上向き線が多い)
この域では変化率が低いので一定域が広い。その為その万物万象の特長を時系列的に明確に良く示す。
変化率が低い、その「時系列」が判り易い、下限から観て位置は高い、比較的に「微分変化」より「積分変化」の域が長いことも特長である、変曲点の右だから変曲点の特長に類似する等、特長を万物万象に適用して当て填めて思考する事で対処法が見出せる。
「微分変化」
比例的に変化する領域を「微分曲線」(直線)と云う。
僅かな曲線(変化)を示すが殆ど直線で出力した分だけ期待通りの比例的にほぼ変化する。人間であれば青年期の若い時の勢いである。自動車であれば80キロ程度以下のパワーとなる。この様なときに示す変化率が「微分変化」と言う。
この「微分変化」域(変曲点まで)では1に対して増加率が一定(K)で変化する。(1/K:微分係数)
S字の斜めの直線部である。(この斜めは実際は右上の逆斜めになる)
この域は比例的である、比例値が明確である、比較的この域は小さい、変曲点の左であるので特長を造り出す域である等で、特長の構成質が観える等万物万象に適用して当て填めて思考する事で対処法が見出せる。
「変曲点変化」(上)
ところが、この二つの変化の間には、必ず全てのこの世の物体には、このどちらとも云えない変化を示すところが生まれる。
S字の上の繋ぎ目(角部)のR部である。(このR部は笹波の短波線が多い 下側のR部は基本的に少ない)
これを「変曲点変化」と呼び、その曲線の変わり目の変化点を「変曲点」と呼ぶ。
この変曲点には、万事万物より、その呼び方は変わるが一般的にはこの呼び方となる。
この変曲点を確認出来ると、その万物万象の特長が大まかに把握できるポイントであり、その特質を調べるデーター採りをする際はこのポイントを見つけ出す事に重点を置く。ところがこの「変曲点」を見つけ出すのが難しいのである。
この点は全体の65ー70%に相当する所にある。
この世の万物万象のこの点を感覚的に把握するのが難しいのと同じである。
それは何故かと言うと、この点を以ってその以下の所(微分変化)で「行為と行動」をすれば、その全ての面で問題が起こらず都合が良い域事になる。
材力設計をする等場合にはこの以下の所で行うのもこの理由からである。
殆どデータを拡大しないと瞬間的でこの点が無いと言うものもある。
この点には、一定の短期間横ばいの波線を示すのが普通である。
(万事万物には本来、主に「5つの変化」を示すが、後一つは下記に述べる。)
この様に、夫々「5のつの変化」の曲線の特長を見つけ出し、それを万物万象に適用する事で思考する。
そこで、元に戻して、10の力で進めれば、現状維持となるだろう。この繰り返しが続けば続く程に、その10の努力は積分的に増加する事になる筈である。同様にその指揮者の能力も積分的に伸びなければ成長と指揮力とに差が出て来る。
同然、積分的に伸びるだけの力を、猿から進化した者にそんな力を神仏は与えず備わってはいない。
故に、その差のはけ口が事件となる事は必定である。
事程左様に、この世の成長では、例えを戻して、現在の経済成長も、中国の成長率と、日本の進んだ経済の成長率とを同じに比較することがよく発表されるが、あれは比例、即ち積分ではなく「微分比較」となる。
これは技術系の者としてはおかしいと何時も思う。文科系の数理論であろう。もし、技術屋がデーター採りでこの様なことを言うと相手にされないおかしな事である。
上記した様に、この世の中には「絶対値:臨界値:限界値」なるものがあり、これを考慮に不思議に入れていない。
考慮に入れると判らない人が殆どだからか、説明している人が苦手だからかであろうか。否。
本当は、この世の万事万物の変化の「摂理」で、「微分的」から「積分的」に事態は変化する。(間に変曲点が入る)
例えば、現在、日本と中国は経済的に約8-10倍の力の差がある。1の中国の経済成長18%と10の日本の経済成長3.8%は、同じではない。
普通の人の評価は、これでは日本は中国並に頑張っていない事を言うだろう。日本の経済力は落ちたと言うだろう。
普通は中国の経済成長の方が5倍で伸びたと判断するだろう。
これは「間違いの判断」である。況やこれが「衆生の論」の判断である。「三相の論」に準じていない。
日本は高度な経済成長を遂げ、高度な社会を維持している事に成るから、これは「積分社会」に到達していることを意味する。しかし、此処にこの「積分」の摂理を用いて正しく判断すると、多分、中国を日本のレベルで評価すると、概して4-5%程度に過ぎないのではないか。
つまり、日本が4%で中国は5%になる筈である。つまり、ほぼ同じ程度で伸びたとなる筈だ。
逆に、中国に合わせれば日本は17%程度と言う事に成る。(%計算には比と率がある)
判りやすく簡単に例をあげると、若い普通の野球選手の打率(比)が、若い経験の少ない普通投手から警戒されていないので、4割を維持した。卓越したイチローの様な選手が一流投手をあてがわれ警戒されて4割を維持したとする。
この二人の同じ4割は同じではない。
普通選手はイチローの環境で対したとすると1割、イチローが無警戒で普通選手の環境では10割と成るだろう。
イチローはその優れた資質を持ち「積分域」か「上限域」の人物(秀才)で、普通選手は「微分域」の初期であるからだ。
これが、先ずは普通は正しい判断となる。より「正しい判断」となる。「三相の論」は「人」と「時」と「場」を論じている。「衆生の論」では無く成っている。
ところが、又、違うのである。
というのは、これでは、厳しい社会を切り抜けていく事には、途中で問題が出て、「主」としての充分な指揮力ではないのである。
「下限の限界値の存在」
此処で、更に、上記した「上限の限界値」に対して、上記の5つ目の変化の「下限の限界値」なるものがある。
殆ど「外資」に頼る中国経済が、特に中国の日本からの「外資」に頼る経済は、その国(日本)以上の能力を示す事は物理的に、数理的にある事は無い。「下駄」を履いているのである。
つまり、判りやすく云うと「底力」と言うべきものが無いのである。(ファンダメンタルパワー)
「微分曲線」は、上の「変曲点」に入る手前までは、この「下限の限界値」が大きく左右し、次に、上「変曲点」を過ぎた時には、「積分曲線」に大きく左右する特長を持つのである。基になる影響点となる。
例を挙げて、判りやすく云うと、自動車でもエンジン出力の大きい方が小さいものより100キロ以上の能力は明らかに違ってくるだろう。この「下限」の品質程度が「積分変化」の時にも左右するという事なのである。
S字の左の末端部位で極めて緩い右上の短曲線を示す。
(微分変化の始まり点と下限線との接合部の変曲点(下)を示すものは少ない)
この「下限」で示される変化は、殆どのものをデーター化すると、直線に近い極めて小さい変化率の「積分変化」を示す。上向き曲線は小さい(ー)の放物線で、上限は下向き曲線で(+)の双曲線である。
この下限域の末端はその物体を構成している分子の停止現象が起こる。(上限の末端は破壊)
説明を戻す。
判り難いと思うので、例にあげると、次の様な事である。
自然界のものとして観ると、太陽から来る光(YMC)は可視光線としての波長のこの「下限変化」の色は、最初は太陽光に近い目にまぶしい白色域の色を呈する。
次に、次第に「ハーフトーン」と云い、人間の肌なのに現されるピンク色等の淡い「中間色」の域の色と成って行くのである。
そして、次に「微分変化」を起して、混合色はうす黒いグレー色に近づき、「変曲点変化」付近では短い平行線を示し標準グレー(18%K)となる。全色の中間の色である。この時点で全ての原色(BGR)は一点に集中する。
次に、「変曲点」(18%K)グレーから離れる頃には、紫色のグレー色に変化する(原色が影響してくる域)。
原色(BGR)は次第に夫々離れて行き、この離れ巾で原色の個性が出て来る。グレーからくっきりはっきりの原色の混合色と成り始める。
この付近から、次第に「積分変化」を起して、ゆっくり(双曲線)と成り、3原色のRGBはより離れ、1に対して複数分の一の影響で、3つのけばけばしい混合色に変化して行く。
そして、最後付近(上限の限界値)では、3色大きく分離した混合色は、ほぼ平行線に近い変化を占めし黒色と成って行くのである。(中には色以外には下向きのものもある)
これを「CCカーブ」という。
参考に、カラーフェリャー論の一例
ところがこの「5つの変化」にはカラーフェリャ−現象と言うものが起こる。
それが次ぎの通りである。
光の3原色=Y:イエロウ M:マゼンタ C:シアン
色の3原色=B:ブルー G:グリーン R:レッド
光と色は補色関係にある。
つまり、Yの補色(反色):B Mの補色(反色):G Cの補色(反色):R の関係にある。
Yの光は人間の可視光線の見える眼にはBの色に変化して観える。M、Cも同じ理屈である。
これでどう言うことが起こるかと言うと、黄色(Y)の光を放つ服を着ているとする。そうするとその光(Y)でその周りの色は、その元の色にBが引き込まれて、B傾向の色が出る。例えば顔にはBが入り顔らしい中間色の色と成らないのである。他のM、Cも同様である。
この様な理屈が摂理として起こる。
この原理の下限域末端の白は全てのYMC、BGRを含有しているので、この原理で「微分域」から「上限域」まで影響する理屈事に成るのである。
事程左様に、下限域から微分域までの間には、”Yと見えていたもの実はBであった”(逆も言える)と成る事が起こる。
これを万事万物万象に当てはめると、この下限域から微分域の変化を起す域では、よく洞察しないと実は全く違ったとする現象がよく起こると言う事である。
これが一つの「5つの変化」の特質を踏まえた応用思考である。
この下限の白色には沢山の白(ミルキーホワイト等)がある。この白に依って「微分域」から「上限域」までの混合色は変わるだろう。これが、全てに影響すると言う下限特有の資質なのである。
これが、自然界で起す「5つの変化」の典型的な現象である。
この「5つの変化」の夫々の変化には、万物万象に示すものと同じそれぞれの特徴を持っている。
(これを「カラーフェリャ−論」と言う。時間があれば詳しく別にレポートする)
これが理解できれば、4子(孔子孟子荘子老子)の論の書物の様に、この世の万物万象の出来事に少なくとも正しく対応する事が出来る。
仏法の「般若経」は「色即是空 空即是色」と「色」で人生訓を説いているが、真にこれである。何千年も前にこの理論の概容を感覚的に把握していたとは驚きの限りである。
この世の中の万事万物万象はこの摂理に従っていて例外はない。もし、例外があると思う事はその万事万物万象の洞察が甘い事を裏付けている。つまり、この思考は積分域に達していないと言うことである。まだ更に、悟らねば成らないと言う事である。
仏法の「般若経」の概意はこの事を説いているのではないか。
私は、特に、「見えない」は、その事を観る「方向性」にあると考えている。
事例のように人生は真にこの「5つの変化」を起す。
更に、例を上げると幾らでもあるが、鉄の強度も、この摂理に従う。
最初の「下限域」は短平行線で、直ぐに高い変化率で「微分変化」を直線的に示し、「変曲点」で「降伏点」(YP)という短小波の変化を示し、ここを過ぎると「積分変化」を起して、最後に「下限域」の平行線域を呈して、「上限域」で短い下向きのラインで急速破断(BP)する。
この「5つの変化」は夫々次ぎの変化に影響を与え特長を以って与えるのである。
これが、万事万物万象の摂理(自然法則)であり、これに従う。
これも、夫々の域でその域の特徴を持ち、その特徴は万物万象の事例と一致する。
(その特長を現す此処にも理論があり「FC状態図」と言う)
話を元に戻すと、経済科学の面に於いて、若い中国のファンダメンタルと、老練な日本のファンダメンタルとは明らかに違う。
中国のファンダメンタルには、「2律背反」の政治経済、他民族、自己資本力の不足、五行思想、多発暴動、低い民度等の危険性を多く孕んだ下限域のファンダメンタルを持っている。
この下限域の環境条件を考えずしての思考はきわめて危険で、将来の正しい判断と結果を導くには余りにも危険である。つまり、「白の色合い」如何である。
若い普通の選手とイチローとはファンダメンタルは異なる。
このファンダメンタルを考慮に入れての結果は、日本4%は12ー14%で、イチローの10は15と成る。
全ての万事万物万象には、この下限の「下限値」が「5つの変化」のどの域にも大きく影響する要素を保持しているのである。
「下限域の変化」はこの様な特質を持っている。
これ(「三相の論」)は、基となる「下限値」を考慮に入れた事になり、正しい判断と成る
これで、「衆生の論」から脱皮した「主」としての思考であり判断となる。この判断を以って指揮する事になる。これを「速やか」に判断出来る「思考訓練」が必要に成る。「主」としての孤独な厳しい務めである。
「摂理のS:N字パターン」(回帰法)
もし、これ等の変化が、繰り返したとした場合、S字は「上限域」での限界に達して破壊が起こり、急激に元の「下限域」に到達し繋がり、周期性を示し、N字パターンと成る。
この原理を法則にまとめて数式化したのが、統計や科学分析に用いる「回帰分析法」である。
つまり、全ての万事万物万象はS字パターンを起し、元に戻り、このサイクルを繰り返すと言う摂理を統計的に積分法により理論化したものである。「カラーフェリァ−論」や「FC状態図」と同じである。
このS字パターン(5つの変化)は歴史的に見れば大きい期間でも観られるが、決してそれだけでは無くスポット的に観てもこのS字パターン(5つの変化)は起こっているのである。
(下記の波理論)
上記の例を判りやすくする為に、複数の変化の比較による思考であったが、一つの変化の中でも、この摂理は適用する事も可能である。
この現象は摂理である。
「波」の原理と「5つの変化」の摂理
SとNのパターンに付いての大事な特質がある。
それは、例えば「波」に例えられる。
「波」は動いているとお考えであると思うが、実は「波」は動いていないのである。
「波」は3つの波で構成されている。
先ず、最初は外力で「波」が上側に凸に成る。そうするとこの凸の重みが引力で下に押しやられる。押しやられると隣りには凹になる。次ぎにその凹に成ったその勢いで上に押し上げられ、隣りに又凸が出来る。この繰り返しが「波」になる。
本来、一つの凸は重力で隣りに伝播するだけで、移動してはいないのが原理である。
海の波が移動しているのは潮の流れと月の引力に依って移動している。所謂、外力で移動しているのである。
宇宙から来る波は障害が少ないのでこの本来の原理で遠い地球まで届いている。
もし、エネルギーであるとすると、波の何処に地球まで届く莫大なエネルギーを潜ませているかと疑問が出るだろう。エネルギーであればこの遠い地球まで届かない。並みの線状の何処にエネルギーを潜ませるスペースがあるかと言う事に成る。
太陽光も同様である。光子と言う束の波の原理で届いている。
これはこの世の摂理にも働いている。
万物万事万象はこの波の原理で動いているのである。
一見エネルギーかの様に見えるが、決してそうではない。エネルギーと見えていると思考するは「衆生の論」であり、主たる者は波の摂理の原理で思考すべきのなのである。
つまり、事件、物事が起こる。その次に起こる物事は前の物事のエネルギーで次に出て来ると考えるのではなく、「波の原理」で押し出される様に移動して出て来ると思考する事が必要であり、それが正しい間違いの起さない指揮能力になるのである。
もし、エネルギーと思考すると、そのエネルギーの如何に捉われて、油断や判断ミスが生まれるのである。
歴史上の事件をこの思考基準で観察すると、間違いを起こし滅亡しているのは、エネルギー、例えば、判りやすく「相手の戦力」を見限って失敗したと云う事が起っているのである。
成功例のこれは、「主たる者」が「波の原理」として捉えて対処しなかった結果による。
例えば、その最たる主者の家康の判断は、この「波の原理」(流にも通ずる)の思考にあったからである。
次に、ところが、この線状「単波」だけではこの原理は起こらないのである。
この「波」の中を分析すると、この「波」の中にもう一つの「小波」がある。
つまり「波」の曲線の線上の中に同じ原理で「波」が起こっている。だから伝播が起こる。
巾の持たない線のそのままであれば、宇宙の磁場磁力や宇宙風や宇宙塵で歪み、伝播は引っ張られて壊されてしまう。この子の小波がある事で波の曲線が、太く成るだけではなく、生きた波巾を持つことに成る。
だから障害に左右されずに地球まで届くのである。
中にはこの子の小波が2つある事もある。そして、これ等の「波」は幾つか続くと周期的に「大波」が発生する。この原因は周期の微妙なズレが集積されて一つになり「大波」が生まれる。
この「大波」が又、波の伝播の動力源となるのである。
この周期のズレは障害に対する影響度で「大波」には差異が発生する。宇宙からの波はこの大波は殆ど無い。
これが「波の原理」である。
この世の万事万物万象も波に表される事が出来、この原理(摂理)に例外なく従っている。
S字からN字にパターンが移動していく過程はこの「波の原理」に従う。
この様に、ミクロ的に、局部的(スポット)にも、この5つの変化(S字パターン)は起こっているのである。
長い歴史の複数の「5つの変化」の繰り返しはこのN字パターンの摂理に依って起こっている。
つまり、俗に言う「歴史は繰り返す」と云う言葉がある。
この「繰り返す」はこの波のN字パターンであり、色の「波の原理」で起こっているのである。
ある大きな歴史事件の「積分域」の変化が起こり、遂にはその果ての「上限域」では戦いなどの破壊が起こる。そうするとその破壊のエネルギーで再び元の下限域の変化が起こり、その持ち得ていた力で「微分域」「変曲点域」「積分域」の変化へと進んで行く。
これは「波の原理」又は「色の原理」と同じである。
大宇宙のビックバーン(上限域末端)とブラックボックス(下限域末端)はこの現象(5つの変化)である。
ある出来事の短い期間の出来事に対しても、”今はどの域にあるのか”よく洞察して、その域の特質を駆使して対処する必要があるが、そこでこの「5つの変化」での「三相の論」は適用できるのである。
「流」と「5つの変化」(S字パターン)
更に、俗に言う「ものの流れ」とは、このS字パターン(5つの変化)であると考えている。
この「5つの変化」(下限変化ー微分変化−変曲点変化ー積分変化ー上限変化)として世の万事万物万象は動いている。この「流」を分析すると「5つの変化」が起こっているのである。
しかし、残念ながら、その「流の力」に打ち勝つだけの力を人間には神は与えていない。
だから、”「流」に逆らうと良くない”と言うのは、”逆らわず「流」を理解し適応せよ”との「戒め」である。
その「理解」とは、”「5つの変化」のどの位置にあるかを見据えて、その域にあった動きをせよ”と言う事である。
そして、その変化の特徴の把握にはより確率を高くする「訓練」が必要であるとしている。
このS字パターン(流)は真実摂理であるが故に、消滅する事無く、今まで言伝えられているのである。
「仏法 万物の輪廻」
余り一般の人には知られては居ないが、自然界に存在する「万事万物」はこの法則に従っているのである。
人間の指紋と同じく、その万事万物の特徴や個性を現す手段として、Sパターン(Nパターン)のデーターを採れば現されるのである。特に、この中間点の変曲点を見つける事が、大変難しいのだが、そのものの特長を掴む事が出来るのである。
仏教では、これ程には詳しくは論理的ではないが、この摂理を説いている。これが「万物の輪廻」であろう。
または、統計学で言う回帰法であろう。
「先祖の力:評価の応用例」
余談だが、イチローなどの野球選手などのトップクラスの談話を聞くと、この「匠」と言うか「真のプロ」と言うか、その域(積分変化域)に達した者の発言は、この摂理に従った思考をしている事に驚く。これが簡単に言えば、「プロの思考」条件と言うものであろう。
「5つの変化」の特質を把握すれば、選手が「微分変化」域の者か「積分変化」域の者か「変曲点」域かは判別できる。
素人域の者は「下限の変化」域で見極めることが出来る。「上限の変化」域は破壊であるので、無いか異質者(天才)であると観える。
何でもそうだと思う。テレビの解説者やコメンテーターや政治家や企業家や小説家の言を聞けば、その人物の到達域がどの程度のものかは判断が着くし、信用に値するかは判断が出来る。
私は常にこの「5つの変化」の思考で聞いて判断している。この者がどの域の者であるのかが見極める事が出来ると思っている。
この家訓3に従い余り間違っていない。
「経験則と自然の摂理」
先祖は、「経験則」でこの思考を獲得していた事が頷ける。
昔の先祖は此処までの科学根拠は知り得ていなかったであろうが、イチローと同じく「経験則」から習得した心得であったのであろう。
実は、私はこの家訓3は、現在では科学が進み知識として習得が容易に出来て、自分が納得できれば、自らのもの「思考原理」として用いて訓練(技術屋として)し、人生の生きる術として使う事が出来たが、別の意味で、先祖がこの「自然の法則」を知り得ていたことに驚いている。
家訓として遺している以上、この思考を駆使していたのであろう。
だから、一族家臣を統一させ、事に遭った結果、此処まで青木氏を生き遺させる事が出来たと見ている。この家訓3の理解が無ければ1365年も子孫繁栄は成されず、先ず他の氏のように消滅したのではと考える。
そして、その理解は「経験側」と「仏法の輪廻」の知恵から成したものであろう。上記する自然の摂理に叶っていたのである。つまり、我等青木氏の先祖はこの積分域に到達していたからこそ「主」としての孤独な思考が出来て、「衆生」を導いてき来たのであろう。
「思考評価例」
話を戻すが、この知識を下にせずに、中国の経済成長と単純比較して、”中国は将来日本を追い越すだろう”とする経済学者や政治家がいるが、この摂理の理論で見れば間違いとなる。
その者等の思考域は積分域ではないと言える。
中国のファンダメンタルは外資を頼りに伸びた故に日本より低い。又科学的にもない。
下限の限界能力での評価は、充分な分析史料はないが先ずは3-4%程度であろう。
中国はこの「変曲点」を越え、「積分社会」に入った時点で、その能力は明確になると観られる。それは4ー5年先の範囲であろう。現在は「微分変化」の社会である事には間違いはないだろう。
比例、即ち、「微分社会」が未来永劫続く事は物理的にあり得ない。必ず、歪み(オーバーヒート)が起こり破壊(バブル)する。
その内に、上手く行けば、必ず「変曲点社会」と「積分社会」が起こるが、まして、外資と共産国と他民族国家である。この2つの社会に移れるだろうかハンディはあり過ぎる。
このハンディを乗り越えられるかは、その「微分社会」の比例値の如何に関わる。
現在の「微分社会」は低い値の下限値に影響を受けている事からすると、何か大きな外部からの変革(産業革命のような)を受けないと可能性は低いと観ている。
もし、その影響を起す国があるとすると、多分、日米の何れかであろう。私は、日本であると考えている。
然し、日本も「積分社会」に突入している。苦しいが大きな鍵を日本が握っている事になる。
薬物やガス田などで逆らう中国はこのことを理解しているだろうか。
「積分社会の脱皮改革」
「下限の限界値ー微分曲線ー変曲点ー積分曲線ー上限の限界値」
この世の全てのもののパラメーターを曲線に現すと、「下限の限界値ー微分曲線ー変曲点ー積分曲線ー上限の限界値」に現す事が出来る。(応用物理学ではこれを「Sカーブ」と云う)
否、これ以外のものはこの世にはない。
あるとすると、大変な「世紀の大発見」である。ノーベル賞ものである。現在の物理理論ではエントロピー、エンタルピーの摂理理論に従っているが書き変えなければならなくなる。
つまり、言い換えると、この世の全てのものは、万事万物万象の何事に於いても、「下限の限界値」と「上限の限界値」とを持っていると言う事である。
従って、本来は正しく処理するには、本命である「微分思考」、「積分思考」が要求されるのである。特に、現代のこの様に社会の成長が進めば、むしろこの思考が必要である事になる。
しかし、その思考は遅れているか、時代性で欠けてしまったか、忘れられてしまったかのどちらかであろうが、私は歴史史実から遅れていると考えている。
何故ならば変化率の低い積分域の変化に入っているからである。
それは大きな歴史的事件(戦争の歪み)と、余りにも人間の進歩に対して、万事万物の摂理の変化よりも、相対的に科学的付加価値だけが増大した事に依ると見ている。
思考の意識がそこまで到達しないのであろう。つまり、余裕が無く成っていることを示すのであろう。
これは悪い事ではないと見ている。何故ならば、2000年代の産業革命的な変化の兆しを意味しているからである。
200年前の1800年代の産業革命時代も科学の進歩(科学的付加価値)だけが、同様に増大してたからである。
この様に、もし、人間の能力をこの理屈に当てはめると、成長が進み、変曲点以降、後になる程に「主」は負担が大きい理屈になる。指揮する者だけではない。される者も同じ理屈が適合される。
昔のサラリーマンより今のサラリーマンの方がこの摂理、理屈からしてハードであろう。
更に将来のサラリーマンはもっとハードと成る。例外ではない。
ただ指揮する者とされる者との負担の違いの差がある。イーブンでは無い筈で、だから指揮する者と呼ぶのだろう。同じであれば指揮する者と呼ぶことは同じだからない筈である。
「積分延命策の産業革命」
つまり、此処に来てその指揮能力が行き届かない事件が多発しているとすると、この辺が成長に対して、人間としての能力即ち、「上限の限界値」の限界に来ているのではないだろうか。
「人間社会の発展」に対して人間としての限界に来ている。自然環境も「温暖化」という事から見て地球が駄目になる所まで来ているとする例に示される。
そこで、何かこの「積分曲線」を「比例曲線」(微分曲線)に変える変化が故意的に起こさない限りに、この摂理は変わらない。それは温暖化の行く末に似て暗示している。
例えば、人間の知恵を最大限に伸ばして生き延びた「産業革命」のような出来事が、この世に再び起こらない限りに於いて「積分変化」に入り、延長は無くなる事を意味する。
一部に、医学界のES細胞や量子集積回路(CP)や宇宙産業の分野にその片鱗が見えてはいるが。さて、これが彼の産業革命のようなものに繋がるものか疑問点もある。
というのも、温暖化の「地球の存続」の問題や、上記の「科学進歩の片鱗」の偏り(日本アメリカに限定されている)はそのけん引役の「日本の積分変化」の社会に打ち勝つ事が出来るかに掛かっている。
そして、それは、この家訓3の意味するところの思考に、昔にあった思考の社会(微分社会)の蘇りが起こり、日本社会が入れるかにあると観ている。
しかし、兎も角は、時代は続く限りに、組織の「主」は依然として務めなくては成らない。
限界の「主」として務めなくては成らないのだから、この家訓3の昔の「主」と違い、更に上記する思考の革命に戻れるかにあり、その多くは「主」としての適格性を問われる事になると観ている。
この「限界社会」での指揮する「主」に課せられる思考(微分積分思考)はこの家訓3の意味する所となる。
「衆生の論」と「三相の論」(積分思考)
昔であれば、「微分社会」の緩やかに「人、時、場処」を思考していた指揮する姿は、「積分社会」の限界の時には、「人、時、場処」を思考し綿密に指揮しなければならなく成る事を、この家訓3は示すものである。
それだけにこの「三相」の重要性が増す事を意味する。
そうすると、当然に、この「三相」の理解の仕方如何に関わる事になる。
昔であれば、一次一局の単純明快な勧善懲悪で考える「三相」が、複雑極まる善悪で「三相」を考えなくては成らない。
況や、「微分思考」と「積分思考」(下限の限界値と上限の限界値)、更に「変曲点思考」の考察が要求される。
この様に、今はマスコミなどでは、単純思考(微分思考:二次元思考)即ち、「衆生の論」でものを評価思考しているが、今の社会では、正しく、且つ、間違いなく処理するには、「変曲点思考」や「積分思考」でものを判断する力が必要になると、平易な表現ではあるが、口伝や遺蹟文面から解釈すると説いている。
西郷隆盛は「女子と小人は養い難し」(衆生の論)と同じ事を言い遺している。
明治初期から観ると、江戸期3百年の安定期は積分変化の社会であったと観られ、その後に上限域末端期に入って日進日露から始まり第2次大戦等の戦争状態となったと見られる。
その直前の西郷隆盛は、この明治初期の時代(積分社会の特徴)の「衆生の論」に遭遇したと観られ、時代の「主」として苦しい孤独の立場に追い込まれてこの発言となったと見られる。
この言葉で通ずる様に、この時の西郷隆盛は「三相」(三相の論)をベースとする「5つの変化」の変化毎の「三相の思考」で判断していたのである。
この事は此処で言う家訓3が今にも通ずるものであると考える。
「正しさ」の理解
そこで、この上記の思考原理で行くと、問題に成るのは「正しき行為」とは何ぞやとなる。この理解に関わる。
普通の家庭として観た場合に、「衆生の論」である一次一局の感情的「勧善懲悪」だけを意味する「正しさ」では無く、子孫を遺し、滅亡を避け、「生き抜く」という目的に向かって、それが達成されたとき、その行為は「正しい」とする事を意味しているのではないか。
現代社会に於いて、「社会の付加価値」が進み、人の成す「行為と行動」は変化して、一次一局の「正しさ」は必ずしも、誰でも、何時でも、何処でも「正しい」と言うことでは無く成っている。
その事が社会の物事に増えているのではないか。
”「悪さ」がむしろ「正しい」という事の方が結果として良い。”と云う事象が多く成っている気がする。
「衆生の論」の一次一局の「正しさ」は「間違い」とは云わないが、「悪い」と云うことが多く成っていると考える。
この判断力は「積分社会」に入れば、その変化率の低さ(一つの事に敏感)から益々増大する筈である。
(微分社会では変化率が大きいので、少々のことも吸収して増大する勢いがある)
簡単に云えば、「積分社会」においては、その吸収力のキャパシティー(上限の限界値がある為)が小さいので、”「主」が思考する「正しさ」とは、「一次一局の感情的正しさ」であっては成らなず、摂理「5つの変化」の見極めの思考と「三相の論」であるべきだと”という事であろう。
(仏法「三相の論」は、「衆生の論」を対比させてのものであるので、この摂理「5つの変化」見極めの思考を含んでいる事にも成る)
これは、情報メディア−が取るどんなアンケートにも現れている。”どちらともいえない”と云う回答が30%以上を常に占めていることである。これは”「一次一局の正しさ」では判断できない”と応えているパラメーター(証拠)であろう。
この様に、「衆生の心理思考」が知らずがともに、「積分変化」の社会にある事を無意識の中で変化して来ている事であろう。
この傾向の増える事が、”衆生の多くは積分思考に入った”と認識するパラメータと観るべきであろう。
私は、誰でもが同じ方向を向いている「微分社会」よりは、「摂理理論」でみれば、この方が良い傾向に日本の衆生意識は傾いていると見ている。
上記のような列記した歴史的死闘事件や戦乱や、はたまた「伊勢一向一揆」や「三重大一揆」の紙屋青木長兵衛の背後での関わりを、勧善懲悪論で「悪行」とするのか「正行」とするのかは、その思考の如何であり、「衆生の論」の一次一局の思考の表面的な評価より、「三相の論」(摂理5つの変化含む)の人の営みから観た綜合的(多次多極)な評価が要求される事を意味しているのである。
その時が良くても、結果として、弊害になるという事はそれは正しくなかった事を意味する。「三相の論」を元にした「判断力」とは、この事が大事であるとしている。
これが直接的に戦い生き抜いてきた者が成し得る思考であろう。
究極の全ての「良悪の評価」は「子孫を遺す」と云う人間の目的を成し得て初めて意味を成すものである。
子孫が滅亡しては良し悪しどころの話ではない。人が居てこその「良悪」である。
それでなくてはこの長い年月を子孫を遺して生き抜いてくる事は不可能である。
判りやすく云えば、若干の誤幣があるが、「机上の論」や「学者論」、砕いて云えば「お手繋いで幼稚園の論」や「ホームルーム論」や「耳ざわりの良い論」であっては成し得ない事を意味しているだろう。
(現在のマスコミはこの傾向が強い:「衆生の論」)
従って、この「主」の意味する所の指揮能力、即ち、換言すれば重厚な判断力を保持する者でなくては成らないのである。
しかし、この場合はこの思考が下の者にも共通する思考ではないことを心得るべきとしている。
つまり、当然に「主」として此処に含まれるものは、「孤独な思考」であり、それに耐えられる「精神力」が要求される。
そして、衆生は安易なその場だけの「勧善懲悪論」である。最終的で複合的な目的の「良悪」論では決して無いことを知るべきであるとしている。
決して、「衆生の論」ではないことを意味している。そして、これを成しうる事が出来る者が「主」であるとしている。
「主」の質は「三相」の訓練
そこで、何故に、「衆生の論」では「主」ではないのかと言う疑問が出る。
それは、思考の中に「三相」の有無が左右していると云うのである。
つまり、「衆生」は兎角、「人間の性」、即ちその場の「感情的思考」に左右されての論であるからだ。感情論では瞬時的なもので、上記の混乱の中から生き延びてくる事は不可能である。
「感情的思考」はその感情を越えることが起こると人間の脳の思考は止まる。況やパニックである。これでは子孫を遺す事は出来ない。
そこで、”「主」とする者は、「人、時、場処」を総合的分析して、その事に対して瞬時に思考できる能力を着けよ”としている。しかし、”その「主」の質は直ちには得られず、「主」としての「訓練」に委ねよ”としている。
例えば、上記の様な「5つの変化」の中の戦乱の中で、”「人」は適切なのか、「時」は適切なのか、「場処」は適切なのかの3つの要素を考え合わせて、結論を出せ”としている。そして、”その思考を常とせよ”としていて”訓練せよ”としているのである。
これが「主」としての資格であり、この訓練のできる資質の有無があるので、出来ない者は「主」と成ってはならないとしている。つまり、資質のない者が「衆生」であるとしている。
そして、「三相思考」を、それは「衆生の思考」(感情的思考)ではなく、上記の「孤独な思考」を導き出す”「正しき行為」の基準とせよ”としているのである。
これを獲得できる「主」は「人としての目的」を達成し続ける事の出来る者であるとしているのである。
「積分変化の現代」
現在の世の中は、上記した「積分社会」の中で、この「主」としての資格を保持していない者が組織の上に立っている事から、物事に行き届かない社会現象が生まれているのであると観ている。
これが、「微分社会」であれば、その「成長出力」が強いことから、これでも「主」の資質の無い者でも何とか成る程度の社会である。
私は、現代は、「積分社会」と観ていて、人としての「資質の限界」に来ていると観ている。
それは「積分」に「相当する進歩」と「科学的付加価値の急速な増大」で起こっていると観ている。それを越える者が少ない事を露見している。
故に、この様な環境の中では、無意識的に起す人間の性(さが)で、無難にこなそうとして、人は、組織の「主」として選ぶ方法を自らの仲間うちの「仲良しクラブ」的選択から選ぼうと走る傾向が強くなるのが自然である。それが現代社会の歪みでもある。
「主」としての資質のある者を選ぼうとしていない社会となっていて、頻繁に倫理に欠ける事件を起しているのであろう。
「微分社会」では、社会の中に主としての「潜在的資質」を保有する者の量で、充分にこれに対応できていたが、しかしながら、「積分社会」では、、「主」条件の”その思考を常とせよ”としていて”訓練せよ”の事のより強い「訓練」をより要求される社会と成っていると見ている。
現在の日本は、その「微分社会」と「積分社会」と混在し、「積分社会」にやや入って変化して行く基点域(変曲点域)かやや入ったところに来ていると観ている。
故に、この家訓3の意味する所が大事となる社会と成っていると考えられる。
これは、企業の中や社会の中での指揮する立場の者に要求される資質であるとしている。
家訓3は青木氏の家訓として遺されているので、その生活環境と子孫の存続の範囲としての維持訓に過ぎなくなっているが、現在社会にも適応される大切な思考ではないかと考えている。
「結論」
纏めると、何はともあれ、家訓3は、”「主」としての「資質の確保と訓練」を怠らず、その基点となる「正しさ」は「衆生の論」に左右されず、多次多極での実質的正しさを極め、その思考は「5つの変化」の夫々の特質に対応して「人、時、場処」を以って事に当り処理せよ。”と説いている。
さすれば、”本来のあるべき適時適切の正しさが求められて、人本来の人生の目的の幸せは確保できる”としている。
そこで、”その思考の原点を「自然摂理」に基づき、「下限限界ー微分思考ー編曲思考ー積分思考ー上限限界」(5つの変化)に求めよ。”としている。
”衆生の所以でないが為に、「主」は孤独である。故に、この思考と共に「訓練せよ」”としている。
”その質に在らず場合は、「主」に留まらず速やかに辞せよ”としている。
家訓3に付いては、「結論」に示す通り、「事の処理」に対する思考原理で、重心を下げた「自己形成」の基盤となると考える。
注釈
伊勢青木氏家訓10訓は、祖先の時代に交流があり、同じ境遇にあった観られるところから、共通する5家5流の家訓とも考えられる。
この家訓は伊勢青木家の口伝と先祖の忘備禄なるものに伝え書かれた説明をもとに解釈し、筆者が現代の自然物理学の摂理とその経験で習得した同様の論理を加えてより判りやすく説明したものである。
この「思考を獲得」して「自己形成」により「時局」を違えず、「人の幸せは一定で絶対値があるの論」(青木氏の幸せの論)から「幸せ」を減少させる事は少なくなる。即ち、「幸せ」多く確保する=「子孫繁栄」の理屈が生まれる。
この「幸せ論」は別の家訓10で説明する。
参考
青木城は江戸初期まで伊勢には次の所に戦いの拠点となる館や山城や平城を含めて城があった。
戦国時代や信長の三大伊勢攻めで多くは消失した。
柏野、柏原、名張、伊賀、脇出、松阪、滝川、青蓮寺、中将、羽津、浜田、蒔田、福地
但し、藤原秀郷流青木氏の須賀川城(青木玄蕃)、信長の丸山城(信雄)などもある。
以上 次は家訓4である。
Re: 伊勢青木家 家訓2
副管理人さん 2007/07/29 (日) 22:02
伊勢青木氏の家訓10訓
前回の「家訓1」に続き、今回は「家訓2」に付いて述べる。
この「家訓2」に付いては、「家訓1」の意味する所に付随しての内容となる。
「家訓1」の意味する所は、纏めると次の事となる。
「家訓1」 夫は夫足れども、妻は妻にして足れ。(親子にして同じ)
「家訓1」の関係口伝
”青木の家は「女」が家を潰す。”(口伝1)
”自尊心の必要以上に強い女は不幸”(口伝2)
”妻はお釈迦様の掌で遊ばせる心を持て”(口伝3)
”夫は第一番目の子供である”(口伝4)
”大事な決め事は夫が決めよ”(口伝5)
”「口伝」の下に、神が与えた「女の本質」を理解して、「母性本能」で妻は成長して、「妻は妻にして足れ」で「家=妻」で務めよ”としているのであった。
以下に夫々にその持つ「戒め」の意味するところを説明する。
「家訓2」 父は賢なりて、その子必ずしも賢ならず。母は賢なりて、その子賢なり。
「家訓2」の関係口伝
”教育とは学問にあり、教養とは経験にある”(口伝6)
”教育は個人の物(知識)”「素質と素養」(口伝7)
”父親は、「背中で育てよ」、母親は、「胸(肌)で育てよ」”(口伝8)
家訓3 主は正しき行為を導き成す為、「三相」を得て成せ。(人、時、場)
家訓4 自らの「深層」の心理を悟るべし。(性の定)
家訓5 自らは「人」を見て「実相」を知るべし。(人を見て法を説け)
家訓6 自らの「教養」を培かうべし。(教の育 教の養)
家訓7 自らの「執着」を捨てるべし。(色即是空 空即是色)
家訓8 全てに於いて「創造」を忘れべからず。(技の術 技の能)
家訓9 自らの「煩悩」に勝るべし。(4つの煩)
家訓10 人生は子孫を遺す事に一義あり、「喜怒哀楽」に有らず。
(家訓は禅問答的な表現方法で漢文的にて表現されていて判り難い、敢えて、現代用語として、書き改めて紹介をする)
解説
父のその能力で、その家の先頭にたって「家の事」を「仔細」に渡りすべて差配し考えを強要する家は、その子供は良い子供が育たず、又賢くならず、母が賢(家訓1)なれば家は纏まり、子供は良い子に育ち賢に育つ。
家訓1で言う「家」は妻が仕切る事の結果で、家は栄え、子供は賢い子供に育つとする。
それでは、ここで言う「賢い」とは、一体どう云う事か。
「賢」とは、「頭が良い」と言う事でなく、「総体的に優れた素質と素養」を身に付けた子供という事に成る。
その「素質と素養」は家訓1で言う「母の如何」に関わる事である。
それでは、父親が「賢」であっては成らないとするはどう云う事か。
父親という者は、その「賢」を家族の中では、決して曝け出しては成らないとしている。
子供は、曝け出したその父親の「賢」を見て、自らもその「賢」と成ろうとして無理をし、周囲との関係を無視し、偏りのある人物に成り、総体的な「素質と素養」が得られない。又、父親の「賢」を見て萎縮し、適性に成長せず、「素質と素養」を持つ事は出来ない。
この何れかの子供が育つとしている。
この結果、「家訓1」で言う「家」を継ぐ事と成った暁には、「家」は衰退させると説いているのである。
つまり、「賢」であっても良いが、曝け出しては決して成らないとしているのである。
では、家庭には、それを維持する芯なるものが必要である。では、どうして父親の存在や威厳を示せばよいかと云う事になる。
つまり、父親の「賢」は、直接見せるものではなく、[父の背中」で見せる事が肝要であるとしているのである。
父親が、(賢であろうが)、「愚」であろうが、子供はその「愚」を見て自らを律する子供になる事の方が、”総体的な「素質と素養」の持った子供に育つ”としているのである。
では、”父親が「愚」で有ればよいか””「愚」であっても良いのか”と云う事になる。
そう云う事だけを言っていない。あくまでも、「家訓1」の中にある「環境」の父親である事としているのである。
当然に、この「環境」とは、”大事な決め事は夫が決めよ”(口伝5)の範囲にある事である。
「賢愚」に於いて、曝け出しては成らないとしている。あくまでも、間接的な「背中で見せる行為」と「環境」の”大事な決め事は夫が決めよ”(口伝5)で家庭の「芯」なるものは維持出来るとしている。
父親の「賢」とは、同じく「頭が良い」と言うことを言っているのではない。「父親の賢」とは、「家訓6」で詳しく説明をする。
「家訓1」での補足では、男女の異なる「性(さが)の定」とする「家訓4」であるとしている。
「家訓2」での補足は、「家訓6」であるとしている。
(故に家訓4及び家訓6は相関するが、シリーズ中で解説する)
では次は、「父親の賢」とは、本質は何なのかと云う事になる。
つまり、家訓6に起因するので概容を述べる。
「父親の賢」とは、「教育」で得られた事ではなくて、「教養」を身に付けた事にあるとしているのである。
言い換えれば、(詳しくは「家訓6」で解説し説明する)”「教育」と「教養」は違う”と説いている。
「教養」は、「教育」を受けなくても自身の努力と経験にて得られるものとして「本質」は違うのである。
では、どう「本質」が違うのかと云う事になる。その差違は次の通りである。
この関係口伝では、主に、その主意は ”教育とは学問にあり、教養とは経験にある”(口伝6)としている。
つまり、”「教育」とは「育む」(はぐくむ)ものであり、「教養」とは「養う」(やしなう)ものである。”としている。
では、この事に付いて少し検証してみる。
必然的には、その論理的な差違は、人の社会では、次の様に定義付けられるのではないか。
定義
「育む」とは、学問的に得た「知識」で、更に「知識」を生伸し、「直線的拡大」を果たす事であり、大意は「枝葉」を伸ばす成長事を意味する。
「養う」とは、人生的に得た「経験」で、更に「徳識」を着実し、「増幅的拡大」を成す事にあり、大意は「果実」を着ける成長事を意味する。
故に、数式にすれば、教育=「育む」=学問=知識 教養=「養う」=経験=徳識 式−1 が成立する。
「家訓6」はこの「経験」(徳識)を重視しているのである。
父親の子供への影響は、関係口伝の”教育は個人の物(知識)”(口伝7)として、物(知識)は周囲(子供)には影響を与えないとしているのである。
父親の「知識」は、子供には、何らかの手段を用いなければ伝授できない。その手段とは「教育」でしか得られない。
何もしななければ、その「知識」は、子供には移らず「養う」事にもならず、その「着実」も成せない。
確かに個人のものである事が頷ける。だから、親は、この手段として、「教育機関」にて子供にも再び同じ「知識」を「個人の知識」として得させようとしてするのである。
しかし、その複雑な「経験」(教養 徳識)は、「父親の背中」で伝えることは可能である。
真にそれ以外に無いであろう。
人に依って異なる「経験」は、「教育」としてはこれは「教育機関」では得られない。あくまでも、「父親の背中」でしか伝えることは出来ないのである。
「言葉」で伝えてたとしても、しかし、「知識」は同じ量を記憶すれば、個人差が無くなる事から「即効果」であるが、「個人差のある経験」は、子供に取って「参考」にしかならないのである。
あくまでも、「経験」の滲み出る「父親の背中」で感じ取った「徳識」(教養)は、口伝の「環境」の中で、重厚な感覚として、無言で子供に充分な影響を与えるとしているのである。
故に、、「父親の賢」=「教育」+「教養」=「父親の背中」 式−2 が成立する。
依って、(式−1)+(式−2)+「母親の賢」=「子供の賢」=「素質と素養」 式−3 が成立する。
附帯して、「母親の賢」=「家訓1」=「母性本能」 式−4 が成立する
三段論法ではあるが、「家訓2」の連立方程式の上式が成立するのである。
昨今は、この説に対して、昨今の唯物史観が余りにも横行し、その視野が「父親の背中」と云うものの観念史観を許容できないで、このために「教育は教養」として定義付けられている様な風潮がある。
しかし、これは間違っている。「家訓6」で詳しく述べるが、”教育に依って教養が身に着く”かの事としているが、これはおかしい。
「教育」は「知識」であり、「知識」が身に着いたからと言って、教養が身に付くとはならない。
例えば、受験勉強中の様に、「知識」は覚え詰め込めば出来る。受験勉強した者が、「教養」が身に着いたとはまさか誰も思わないであろう。又、大學の教授が全て「教養者」であるとは限らない。
しかし、現代はここが社会の間違いの点で有ろう。
例えば、世間では俗説として次の事が言われている。
特に、テレビなどでは、論説を証明するために、”...大學の教授が言っている”などと巧みな手を使って持論誘導をしいている場面がある。
つまり、”学者の言うとおりにしていて、上手く事が運んだ試しは無い”
即ち”学者の説は、学者バカ”との説があるが、この様にそれを非難される点は、この「知識」での結論だけで、社会の「諸事」を論じるから言われる言葉であって、これは「教養」の不足に関わることから来ているのである。
つまり、総体的に優れた「素質と素養」の中から発する言ではない事に起因しているからである。
又、社会では、”父が家の先頭にたって「家の事」を仔細に渡りすべて差配し考えを強要する家”は、正論であるが如く言われる傾向がある。”これが何が悪い”と言う言葉が耳に入るが、全ては悪いと言う事ではないと考える。
しかし、この場合、ここに二つの問題があり、この点に関わると好ましくない。
一つ目は、”仔細に渡り”である。
「仔細」に事細かく口うるさく言うは、家訓1で言う「妻の立場」が無くなり、妻に依って育てられる「養育部分」が欠落し、偏った子供が育つ事になる。子供の育つ「養育部位」は殆どが母(妻)に依るところが大きいからである。
ゆわんや、”「母性本能」から来る愛情の部分が多い”とするのである。
この「養育部位」は「子供の基本部分」になると言うのである。
つまりは、愛情の部分=子供の基本部分=「母性本能」 式−5 が成立する。
故に、関係口伝では、母の愛情の発露である ”胸(肌)で育てよ”とされるのである。
”仔細に口うるさく言う”は、この式を欠落させた子供が育つとしているのであるから、子供は「賢」ではなくなるのである。
では、父親はどうすればよいかと言う事になる。
それは、家訓1の口伝5でも述べたが、「大事な決め事は夫(父親)が決めよ」と「背中で見せよ」の二つである。
関係口伝との結論は、父親は、「背中で育てよ」、母親は、「胸(肌)で育てよ」”(口伝8)と言う事に成る。
二つ目は、特に、男子を育てる場合にある。
昔では元服期(15歳頃)より18歳頃までの4年間の思春期は、父親の「指導」を必要とする。
これは、脳の中での「性(さが)の芽生え(目覚め)」により、「男子の自我」が生まれる。
これは女性としての母親の経験する思考範囲を越えているからである。
つまり、「母性本能」では処理しきれない「行動や思考」を示す事から来ている。(家訓4で詳しく解説し説明する。)
但し、この場合も、父親の”仔細口うるさく”では無く、あくまでも「背中で見せよ」であり、その「背中」が示す「人生経験」で、「強要」ではなく、「指導」する事にあるとする。
男子の子供には、父親で無くてはならない「特定の養育期間」があるとしているのである。
「世の中の成り立ち」や「男の性(さが)」に付いて経験を通して、「人生の先達、友人」として「指導」する事であるとしている。
参考 家訓4で説明するが、概略注釈する。
「男の性」には、意識でコントロールできない脳の中で起こる「深層思考の原理」の事であり、「理想、合理、現実」の三連鎖の思考原理が脳の中で無意識の内で起こる。
これを余りに追求する結果、「人間関係」の中で、「争いや問題」を誘発させる辛い性質を潜在させる。
因みに、「女の性」の「深層思考の原理」は、「感情、勘定、妥協」の三連鎖の思考原理が起こる。
これ等は、何れも良し悪しの問題ではない。各々の「性の仕組み」に合った思考原理に出来ているのである。
(参考 三連鎖の思考原理とは、物事に対して、脳は連鎖的に次の三つの反応で思考を纏める。
物事の処理に付いて、基本となる考え方[理想]を引き出し、それを基[合理的]に判断し、[現実思考]で実行しょうとして、瞬時に無意識の内で、綜合思考する脳の働きを云う。)
(但し、驚く事は、伊勢青木氏の「生仏像様」のご先祖が、現代の脳医学で解明されている事柄に近い人の仕組みを理解していた事である。この事柄に付いて調査した所、大概に合っているので、現代の解明されている仕組みで解説した。)
神が定めるこの世の全諸事に対応する6つの思考であり、この男女合わせて6つの思考で初めてこの世の1つの諸事が解決できるとしている。
故に夫婦は互いに持ち得ていない2種の思考を補い組み合わせて始めて1つと成る。
夫婦は、1種の思考の足りない所を補わせるのでは決してないのである。
(現代の世情はこの考えである所に問題の病巣がある。)
これは、「家訓1」のミトコンドリアのところで述べた神の成せる技である。
ゆわんや、「家訓1」にはこの点を補足しているのである。
だから、「家訓2」の特定期の男子にはこの「思考原理」が芽生える故に、父親の「背中と指導」が必要とされるのである。
この二つの問題事を、父親が上手く処理できれば、”何も言わない「愚」であると見えている父の姿が、それは「賢」と子供の心に残るのである”としている。
故に、必要以上に ”父親は「賢」を曝け出すな”としているのである。”「背中で見せる」だけでよい”としているのである。
つまり、”魑魅魍魎の世間で揉まれた後姿”で充分であるとしている。これは言い換えれば男の人生の「経験」である。
上記の(後姿=経験)であるならば、「教養」=「経験」であるとしていると、故に、「後姿」=「教養」 式−6 である事になる。
何も、俳句や活花やお茶等のソフトな事だけが「教養」だけではない。ハードな「男の後姿」も立派な「教養」であるとしている。
ここでも、次の事が言える。
家訓1では、女性(妻)が優位の立場を認識していない現状を訴えた。現代の病巣であると。
家訓2でも、男性(父親)の「後姿」が「教養」であり、父親の本来のあるべき姿である事が、認識されていない事に痛感している。
父親が、この”認識の無さから口うるさく言うこと”が「子供を教育」していると勘違いしていることから、「賢」なる子供が育たない病巣であると考えている。
又、母親も、この4年間の間の養育期間は、「父親の指導」を強く求められる期間である事を知るべきである。
青木氏の家訓にある事から、何時の時代にも、この「勘違い」が、強い母性本能からこの勤を見誤り起こっていると言う事であろう。
家訓1でも、記述したように、成人になれば、今度は、子供の妻(嫁)が育ててくれる事になる。それまでの家訓2である。
(注意 家訓1の別意である永遠のテーマ「嫁姑の関係」は、この戒めを守っていないことから始まる)
ここで、丁度、「家訓2」を説明出来る様な自然界の法則が起こっている「木の事」に付いてその成長過程を述べてみる。
面白いことが、起こっているので最後に参考に注釈する。
但し、判りやすくするために下記の用語は次の意味を持たす。
「果実」:賢なる子供 「3又枝葉」:夫婦 「中枝葉」:父 「着実枝」:母 「成長枝葉」:「育む」 「成養期」:「養う」
「変態期」:子供成長期(15-18) 「深切り」:背中 「雑木態」:曝出環境 「剪定」:大事な決め事 「選定の習慣」:経験
「着実」:素質ある子 「着果」:素養ある子 「葉色」:育と養 「記憶的学習」:知識 「木勢」:家庭 「木の経験則」:徳識
それは、この上記で説明した事柄の「家訓2」の「育む」「養う」等の過程が起こっているのである。
説明する。
木は、季節の春を得て芽を出す。この時、多くの木の木芽は「3又枝葉」を出す。つまり、5本の指の親指と小指を折った3本の形で枝葉を出す。この枝の真中の「中枝葉」は「成長枝葉」である。木を大きく伸ばしたい時は、この「成長枝葉」を残し、左右を剪定する。伸ばさずに将来に着実させたいときは、「成長枝葉」を切り落とす。そうすると着実のために「成養期」に入る。
この時期の「成長枝葉」を残すと勢力が「成長枝葉」に採られて、直線的に伸びる。余り着実せず収穫量が低くなる。これを続けると何時か、着実の悪い「木態」となる。
そして、この成長過程は7月/20日前後(「変態期」)を境にして、「生育」に突然に変化する。その変化は「3又枝葉」の何れもが「生育期」に入るのである。
そして、「中枝葉」を切り落とした場合は、残りの2本の「着実枝」は実を着ける為に枝を強くして準備する。
この時の「3又枝葉」の「葉色」は、左右の「着実枝」が次の年に実をつけるために出す「葉色」とは異なるのである。
この様に、木の「育と養の差違」は、「葉色で見分け」が外見でも出来る様にする。
木全体が来年、将来に向けて自らの木を大きくする。勢力は全てこの成長に向けられてしまって、枝葉の多過ぎる木態となり、次の年以降の着果は全体的に低下する。何時しか着実は殆ど無くなる。梅や柿はこの現象が顕著に表れる。
一度、この様な「雑木態」と成ると、「深切り」をして元の状態にしなければ成らないのである。この様に成ると、木は長い間の「記憶的学習」(年輪の記憶)を消されて、数年は元に戻るまで「着実」「着果」はしない。(最低は2年程度)
だから、この「変態期」までには必ず、「母性的な愛情」を掛け過ぎずに思い切って、「着実」の目的のために「父性愛的」な「剪定」をする事が必ず必要である。
そうすることで、「3又枝葉」の「着実枝」(左右枝葉)だけを養えば、次年度からは「熟実」が倍増的に拡大して行く。この枝に定量的に確実に着実する。
この二種の枝葉の「選定の習慣」で、「木の経験則」が起こり、そうすると見事な果実(賢なる子供)が出来る様に成る。
しかし、放置しては「木勢」は維持できず、着実しても着果せず自らの木態を守る為に実や葉を落とす。
但し、木には、成長過程の7/20(春)タイプと、逆の2/20(秋)タイプとがあり、木に応じて選択する必要がある。
真に、この「木の生態」は、「人の生態」(子供が賢に養育する様)と一致する。
この様に、自然界の神の成せる業であり、この「家訓2」は事の本質を意味する事になる。
この法則は木だけでは無い。筆者の専門域の自然界の鉄などを顕著として金属類にもこの法則の現象は起こっているのであるが、又、時間が有れば放談として何時か投稿したい。
兎も角も、「3つの口伝」を心得て、家訓2 ”父は賢なりて、その子必ずしも賢ならず。母は賢なりて、その子賢なり。”を理解してもらい子孫繁栄の一助に成ればと考える次第である。
次は、「家訓3」である。
主は正しき行為を導き成す為、「三相」を得て成せ。(人、時、場)
賢なり。
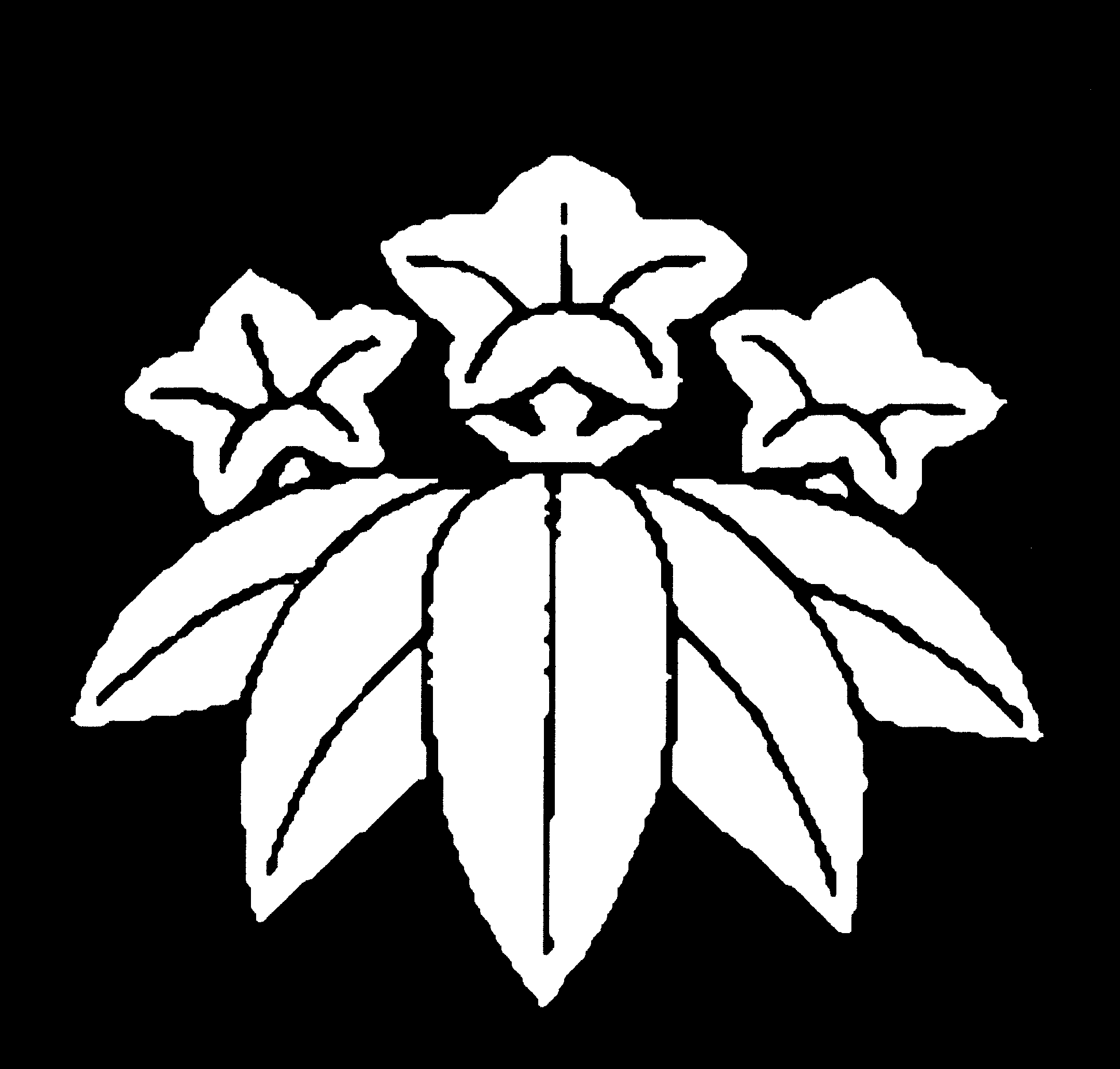
伊勢青木家 家訓1
副管理人さん 2007/07/21 (土) 09:39
伊勢青木氏の家訓
「家訓10訓」
この「家訓10訓」を全国の青木さんに紹介し、「生仏像様」の存在と合わせて、人生の子孫繁栄の一助に成ればと思い、ここに投稿する。
前回のレポートで「生仏像様」が青木氏のステイタスとして、共鳴して一致結束の象徴として、人括りの先祖として、戒めの象徴として、擬人化された「生仏像様」として崇められてきた。
そして、この擬人化された「生仏像様」が発する「戒めの言」が、家訓として位置付けられていたのである。
しかし、本家訓の経緯を推察すると、いつの時代に纏められたかは定かではないが、大化期から1360年間の伊勢青木氏の宗家としての歴史の苦難の中で、自然に培われて、言伝えられたものであろう事がその内容からして判る。
それは、主にその皇族賜姓族としての立場にあった。
当時の氏家制度の習慣から、血縁関係も同等の範囲での狭い血縁を余儀なくされていた環境であった。
その環境の中で「家」を維持するという最大のテーマと5家5流の一族を取りまとめるべく目的から、この「生仏像様」と「家訓」という手段を利用せざるを得なかったのである。
現在の核家族した社会での常識では考えられないものであろう。確かに家訓の内容もその様なものが含まれている。
究極、突き詰めると、筆者はこれが真実ではないかと心得ている。それは現代社会が「消失した思考」であって、欠陥点では無いかと見ているのである。
そこで、このことに付いて、その論所を次に論じる事とする。
家訓は、それは次の二つに分類できる。
その中には、「忘備禄」の中に記述されているものと、「口伝」にて代々親から伝えられてきたものとある。
本来は守護や豪商であったことから、上に立つ者の心得として習得しなければならないし、長い期間その立場を保ってきた氏としての実績からは「家訓」は当然のことであった筈である。
そして、親族縁者や店の者を導く為に統一して誡めるためには、一つのものに書き記されていた可能性が高い。
しかし、それが無く成ったその原因は、明治35年に950年以上続いた伊勢松阪の紙問屋「紙屋長兵衛」が、出火倒産した際に全て記録が消失した。書籍的な記録が無く成ったことによる。
これ等の復元が、父の時代の大正と昭和の戦前戦後の混乱期の時代には無理であった。この事から、父から筆者に「青木氏の由来書」を復元し纏めるように頼まれていた。
以後40年間に渡り、「青木氏の由来」と「生仏像様」存在とあわせて調査した結果、この「家訓10訓」はその一つとして、次のものから出てきたものである。
祖父や両親から既に厳しく誡められていた「先祖口伝」による内容がある事から、別に何らかの形で何処かに遺されていると見て調査していた結果、紙屋の倒産後に、祖父が書き残した「忘備禄」(別名)等の中にその文面を発見し、そこに書かれていたものとを咀嚼して纏めた。父から聞いていた事とほぼ一致するので「10訓」として纏めたものである。
伊勢青木氏の「由来書」を復元する調査の際に、前期した「生仏像様」と関連して整理されたものであり、その基となったこの二つから来る「戒め」は、元は一つとして、何らかの形で纏められていたものである。
祖父に於いては、この「忘備禄」に書かれていた内容から判断して、日頃、伝えられている「口伝」以外に、是非に代々子孫に伝えられて来ていて、必ず伝えなくては成らないものを、明治35年以後の早い時期に、ここに書き記したものであろうと考える。それは祖父の代に倒産し消失した焦りから家を再興するに必要とする大事な事柄を書き残そうとしていたと文面内容から見られる。
以下の内容から見てみると、敢えて分類すると「家」を保つに必要とする「人生訓」と、「商」を維持するに必要とする「商訓」とに分けられる。
それが、「忘備禄」(別名)と「口伝」の差に依っているのではないかと考える。
「口伝」は家訓に関する言葉としても数多くある。
それらはこの家訓を裏打ちする平易で生活に密着した言葉で伝えられている。これに付いては関連するものを次の家訓の説明時に添えて説明する。
そして、これ等は、全て「生仏像様」(一括りの先祖)の「教え」として位置付けられていたものとされる。
家訓は禅問答的な表現方法で、漢文的にて表現されていて判り難いので、敢えて、現代用語として、書き改めて紹介をする。
伊勢青木氏の家訓10訓
以下に夫々にその持つ「戒め」の意味するところを説明する。
家訓1 夫は夫足れども、妻は妻にして足れ。(親子にして同じ)
家訓2 父は賢なりて、その子必ずしも賢ならず。母は賢なりて、その子賢なり。
家訓3 主は正しき行為を導きく為、「三相」を得て成せ。(人、時、場)
家訓4 自らの「深層」の心理を悟るべし。(性の定)
家訓5 自らは「人」を見て「実相」を知るべし。(人を見て法を説け)
家訓6 自らの「教養」を培かうべし。(教の育 教の養)
家訓7 自らの「執着」を捨てるべし。(色即是空 空即是色)
家訓8 全てに於いて「創造」を忘れべからず。(技の術 技の能)
家訓9 自らの「煩悩」に勝るべし。(4つの煩)
家訓10 人生は子孫を遺す事に一義あり、「喜怒哀楽」に有らず。
解説
家訓1 夫は夫足れども、妻は妻にして足れ。(親子にして同じ)
”青木の家は「女」が家を潰す。”(口伝1)
”自尊心の必要以上に強い女は不幸”(口伝2)
”妻はお釈迦様の掌で遊ばせる心を持て”(口伝3)
”夫は第一番目の子供である”(口伝4)
”大事な決め事は夫が決めよ”(口伝5)
簡単に意味する所は、次のとおりである。
「夫婦」として、夫が夫らしくなくて、又、その能力が無くても、妻は夫のそれを責めるのではなく、妻は本来あるべき妻の立場としての責務を全うするべきである。これは、「親子」にも言えることである。この考え方が「家」をまとめ、発展させる秘訣である。
このために、口伝では、この関係する「戒め」がある。
「関係口伝」として、”青木の家は「女」が家を潰す。”(口伝1) この言葉が代々言い伝えられていた。
”妻は妻にして足れ”が守られなければ、仮に、”夫は夫として足りていた”としても、「家」は「女」が「しっかり」していなければ”「家」は潰れる”と説いているのである。
つまり、「女」=「家」としているのである。
では、ここで言う「しっかりした女」とはどう云う意味であろうか。
現実には、「家」は男の夫が差配する社会であり仕来りである。なのに「しっかりした女」とはどう云うことなのか疑問が残る。
更に、別の口伝の中で、”自尊心の必要以上に強い女は不幸”(口伝2)はその「自尊心」が災いして「家」を乱す事から、結果として家を潰す”とある。
つまり、「しっかりした女」とは「自尊心」の強弱にある事になる。
このことから、普通は、「しっかりした女」とは、現代では「自尊心の強い女」を言う事になるであろう。しかし、違うと説いているのである。
これには、「伊勢青木氏の立場」と「250人を抱える商家」と「青木氏宗家」と言う3つの条件が働いているものと考える。
核家族時代の現代では、、「しっかりした女」=「自尊心の強い女」が普通は正しいのであろう。
しかし、筆者は、矢張り究極は、「夫婦」という単位集団からしても、「口伝」の説が正しいと考えている。
その根拠は、「家訓4」でも証明できている。
何はともあれ、検証して見る。
妻或いは女は、自尊心が強ければ、その自負心から夫の足りない所を攻めるであろう。さすれば夫婦間は乱れる。乱れれば、結果として子や周囲にその欠陥が現れて「家」は正しい方向に向かないで自然衰退の方向に向かう。
この家訓は言い換えれば、「夫は夫足れども」の場合は、「かかあ天下」の有るべき本質を言い表しているものであろう。
長い歴史のある「家」の中では、「夫は夫足れども」の場合は必ずある。この時の「妻の有るべき姿」を言い表しているのである。否、「夫は夫足れども」で無くても、この「家訓」は、これを主張しているのである。
現に、筆者の知る範囲では、この家訓通りの通称「かかあ天下」であり、伊勢松阪の紙屋長兵衛の時代の繁栄には到底は到達は出来ないが、総称の「家」を苦難を乗り越えて子孫を多く遺し「家」は旧家を並以上に維持してきている。
これでなくては、現代まで直系で宗家としての「家」は長く保ち得なかつたであろう。
昨今は、女性は自らのこの素晴らしい立場を自ら否定し、間違った女性の権利を固持し、必要以上の「自尊心」をさらけ出している。
筆者は、むしろ、女性がこの世を維持していると見ている。
長い歴史の中で「ひがみ」の心が脳の一部に学習記憶として残り、これが表に出て来るのであろう。
何故に、上記のこの家訓の本質を見ないのであろうか。これが疑問の一つである。
現代の最大の病巣であろう。
ともあれ、このことに付いては次からの家訓にても証明している。
又、青木氏の他の「口伝」にもある。
”妻はお釈迦様の掌で遊ばせる心を持て”(口伝3)とある。
又、次の口伝の言葉もある。
”夫は第一番目の子供である”(口伝4)とある。つまり、親から引き継いだ子育てを、妻が再び次の目的で引き継ぐ事を意味するのである。
つまり、”子供から成人するまでは親の務め”で、”成人から一人前の夫にするは妻の務め”であると説いているのである。
筆者はこの口伝の言葉に大賛成である。真に、男の共通心理の深層を言い当てている。
共通心理では、男は「母親への慕情」が大変強いのもこの深層心理があるからである。
変な話であるが、医学的には、子孫を遺す行為、又はその発露として女性の体を求める行為は、この「母親への慕情」の「深層心理」が変位しての本能であるといわれいるからである。
「母親への慕情」=妻の第2の「母親役への慕情」となるのである。
子孫を遺す本能として働くのである。
現に、遺伝子的には、面白い証拠がある。
女性の卵子には「人間種の遺伝子」が組み込まれているのである。男性の精子の尾の付け根にある遺伝子情報は人の個人遺伝子情報のみである。
遺伝子操作でそのルーツを探るのは卵子からである。その人の種を求めるには精子ではなく卵子、又は女性の遺伝子からである。この様に女性の本質は男性より基となる優位の物(母)を神が与えたのである。
事ほど左様に、遺伝子的に見ても神はこのことを定めているのであるから、明らかに「人の生」は、女性から発祥しているのである。この説は納得できる本質である。
別に生物的にも説明できる。
生物がこの世に現れたとき、単細胞(ミトコンドリア)であつた。然し、これでは、動物性プランクトンの様に、他の強い生物との生存競争に飲み込まれて子孫を遺せない。食われる事により単細胞の雌雄のバランスが狂い子孫を遺す事の確率が低下してしまう。
そこで、この人の単細胞は、互いの同じ種の単細胞の雄雌を合体させる事でより子孫を遺す確率の高い方を選んだ。それが雄雌が合体した方法であった。しかし、弱い生存競争力ではこれでは子孫の維持は出来ても「拡大」は望めない。
再び、分離して双方に共通の能力を保持させ、その子孫を引き継ぐ遺伝子を分離し、合体の部位を変異させて雌雄の目的にあわせて造り上げた。そのことで、弱い生存競争にても、子孫を増やして行くことが確実に可能に成った。
その例えの見本として、単細胞的なミミズは現在もこの原始的合体方式を保持している。太く大きいミミズの真ん中付近に繁殖期には白い部分が出来る。左右は雌雄である。ここからある時期に雌雄が分裂するのである。
他にも、樹木でもこの逆の方式が見られる。現代では多くは雌雄合体であるが、逆に、果物のキュウイ等のように雄雌の別樹があり、この二つの樹で受粉する事が可能にして子孫を遺すのである。
この様に、元は別々であったオスメスの単細胞の生き物が合体してミミズのような物体となり、再び共通式分離したのである。この時、主な重要な遺伝情報を雌に与えたのである。雄の遺伝情報は単に子孫拡大の繁殖情報のみとしたのである。
つまり、昨今、問題に成った”女性は産む機械発言”の逆である。雄はその本質は「繁殖機械」程度のものなのである。あの問題の間違いは、むしろ、雄が「繁殖機械」であって、雌は上記の優位性を持っているのである。だから、謝罪でなのである。
それは、別には、「繁殖機械」=「働く機械」でもある為にも、種の保全の危険性が高いことから、男性には、遺伝子的に負担を少なくしたのである。
従って、女性は多くの重要な遺伝子情報の負担が大きく、そのエネルギー負担が大きいので体格的には小さい事になり、又、生理的にも難しいのである。
この様に神は家訓どおりに本質を創り上げているのである。
時代が変化しても、この本質は神が決めた事なのであるから、故に、「家訓1」は現代にしても正しいのである。
男女の本質が「家訓1」であるとすると、当然に、この本質(理屈)は他の同等の関係にも適用される事は出来るはずである。
そうでなければ、”夫婦間だけに本質だ”とする事の説明はつかない。
親子の説にしても、この家訓1は同様であると説いている。
”親は親足れども、子は子足れ。”である。家族や家や氏の関係に於いてもこの様な関係はある。
この本質を、この関係に於いて心より務めれば、夫婦、家族、家、氏は正常な関係を保ち子孫繁栄は維持されると説いているのである。
少なくとも、上に立つ者はこの「本質の心」を養えとしているのである。
そして、これを悟らせる為に、仔細にした心得の口伝が存在するのである。
ここで、お読みに成った人は、疑問を持たれた筈である。
「口伝4」で「夫は第一番目の子供である」としている。そして、”夫を掌の中で育てよ”とある。、”成人から一人前の夫にするは妻の務め”ともある。
つまり、「家訓1」と矛盾するのではないかと言うことである。
この3つの言葉からすると”妻は夫を指図して思いのままにせよ”とも受け取れる。悪しき意味の「かかあ天下」である。
ここがこの家訓の意味のあるところである。「先祖」は、「生仏像様」は、”これを悟れ、成長せよ”としているのであろう。
”足りずとも、妻の務めとして、足りる夫に子供の感覚で掌の中で育てよ。育つ時間の余裕を与えて”。この「掌の中で育てよ」に大きな隠し意味を持たしているのであろう。
但し、それを裏付けるこの家訓には次の口伝5がある。
”「かかあ天下」で全てあれ”と言う事を言っていない。”大事な決め事は夫が決めよ”(口伝5)とあり、決事の事の良し悪しの如何に拘らず、夫が決めることだと言っている。
つまり、”事の良し悪しの是非は後の時代に判る事”であり、今に判っていたとしても、それは上辺のことで、”真の良し悪し”ではないと説いているのである。
だから、これは「性の定」により、男が決めるべきであるとしている。
これは「性の定」としてこの注釈が附帯されている。(この事は「家訓4」で詳しく述べる。)
この家訓の裏を返せば、次の事を言っている。
”この難しい立場の役目を、女の「母性本能」で遂行し、妻が成長する事が秘訣である。と説いている。
”妻は妻にして足れ”は、”大事な決め事は夫が決めよ”(口伝5)を「妻の心得」として、このことを意味するのであろう。
この意味からすると、上記したように、「家」は「妻」如何による事になる。
上記した「妻」=「家」の数式はここに起因するのである。
これが結果として、先ずは、長く「家」を維持する(子々孫々)秘訣と説いているのである。
この家訓1は、他の家訓でも立証できる本質であり、この「訓言」は他の家訓の基本に共通している。
この事は、随時、説明をして行く。
次には「家訓2」である。
家訓2 父は賢なりて、その子必ずしも賢ならず。母は賢なりて、その子賢なり。
|
皇族賜姓青木氏の背景2
副管理人さん 2008/05/06 (火) 21:10
(皇族賜姓青木氏の背景1に続き、背景2の記述)
背景2−1
5家の青木氏特に伊勢青木氏は桓武天皇期に前述した5つの牽制策で衰退の一途を辿ったが、桓武天皇の子の嵯峨天皇(786−842 位809−823)は渡来系一族の平氏の賜姓を実行した事に同じ方法を採らなかった。
超貢献度のこの一族に対して普通であれば賜姓し続ける筈であるが、実行しなかつたのは一体どの様な背景があったのだろうか。
検証項目
1 皇族として賜姓したが事実は渡来系であり異なる事
2 天智から光仁天皇までの皇族賜姓青木氏の身内の伝統を護る事
3 今度は渡来系一族への牽制をする必要がある事
4 再び増え続けた皇族一族の維持費の軽減を図る必要がある事
5 律令制度が整った現状の今政治への見直しが出た事
以上が考えられる。
この事に付いて詳しく検証する。
1 に付いて
前記したように高尊王や高望王、同一住居の伊勢北部伊賀地方等、明らかに皇族と見せかけた賜姓であった事から、衰退して行く伊勢青木氏などを見て、矢張り一族賜姓の族を護ろうとしたのではないか。そうでなければ結局、身内を無くすことは天皇家を弱くする事と父のやり方を見て認識したのではないか。その証拠として、嵯峨天皇に即位する前は平城天皇(現状維持をしていた)が即位していた。この天皇は兄弟であるが3年で病気で嵯峨天皇に譲位した。そして、その後、再び、810年「薬子の変」が起こるが、天皇としての考えを持っていたと見てこの変を察知しつぶした。この変を企てた藤原式家は衰退した。そして、嵯峨天皇の考えを後押ししていた秀郷の北家が台頭した。
桓武天皇が採った伊勢青木氏の牽制策で伊勢国司に成った藤原藤成の子供(豊沢:藤原秀郷の祖父)の時の出来事である。
この藤成は5−6年程度の任期であり、その後、810伊勢青木氏は守護に戻っている。秀郷の祖父が初めてこの功績で下野国と備前の守護に成っている。(下野の豪族の娘を母)
ここで伊勢青木氏と藤原秀郷とはここで初めて繋がっているのです。
青木氏牽制策で祖祖父の藤原藤成(秀郷の祖祖父)が伊勢の半国国司に。
伊勢青木氏を伊勢に戻した天皇を補佐した藤原豊沢(秀郷の祖父)。
下野の守護になり坂東に根着いた藤原豊沢。
豊沢の影響を受けた孫の押領使の秀郷が藤原秀郷流青木氏(始祖の第3子千国)を出した。
この経緯から伊勢青木氏にしてみれば、この北家藤原氏は恩人である。
2 に付いて
嵯峨天皇はこの考えのために、賜姓を青木氏から変更して、同じ方式で第6位皇子を源氏とした
父の手前上、青木氏の姓に戻す事は角が立つので避けたのではないか。そして、この時、弘仁5年に詔書を発して、天智天皇の時に定められた「皇位4位6位臣下方式」から正式に「皇位4世6位臣下方式」に変更し定めた。この時8人の皇子皇女は臣下した。そして、このうちの6位の皇子を源信として初代の源氏が誕生した。この時、同時期に伊勢青木氏も伊勢神宮の護り守の守護として戻っている。つまり、朝廷の守護神の伊勢神宮の守りは、藤原氏ではなく、皇族一族の者に戻す事が本来とした証拠であり、渡来系一族(たいら族:平氏)では「皇親政治」を築こうとするには困るのである。
渡来系平氏族を賜姓し続けることは天皇家として得策ではなく出来ないのである。桓武天皇の施策(母:高野新笠:阿多倍一族の引き上げ策)は間違いとして嵯峨天皇が改めたことになる。
そして、嵯峨天皇は伝統ある伊勢青木氏の衰退はこのためには困るとした。
伊勢青木氏に付いてのこの考え方の伝統は、織田信長の伊勢永嶋攻めの1576年まで続いた。(後述する)
この伝統を守るために、この時から詔で皇族以外の一般の者が青木姓を名乗ることを禁止した。そして、源氏はこの後の天皇の第6位皇子の賜姓で16代続いた。(実質11代:花山天皇期)
17人の皇子と15人の皇女の臣籍が行われた。15家15流(実質11家11流)ある。
(16家16流とする説もある)
賜姓を外れた者は比叡山か門跡寺院への入山が主となり、学僧となった。この者たちが還俗したときは青木姓を名乗ることを許した。皇女は斉王か他家に嫁いだ。
嫁いだ先は家紋の違う未勘の源氏一族としてその男子の子供は名乗りをあげた。本来の皇族賜姓の家紋は笹竜胆である。しかし、家紋の違う源氏一族は源氏宗家の許可を得ていない事を主に意味する。(又上記の皇子皇女の数からして青木氏と源氏の名乗る数は多すぎる。前記した戦国時代の家系偏纂である。)皇族賜姓族は青木氏5家を含むと24氏となる。
賜姓青木氏から還俗青木氏までの賜姓源氏からは家紋違いの源氏がでた。
正規には、家紋笹竜胆は賜姓青木氏5流と佐々木氏2流と大島氏1流の3氏が使用する。
(大島氏は源為朝の逃亡先伊豆大島での子孫)
背景2−2
(背景2-1の続き)
皇族賜姓青木氏と還俗青木姓と皇族賜姓源氏からは家紋違いの源氏一族がうまれた。
桓武天皇の施策によって政治構成が大きく変化したが、この変化に対して、嵯峨天皇は反対派を押し切って修正を実行した。
律令国家の形態が完成したが、この行き過ぎを嵯峨天皇は修正したのである。
兄の平城天皇が病気理由で譲位したが、譲位後、戻ろうとして、薬子の変が起こる。つまり、変が起こるという事は現状派と修正派の戦いであろう。そして、これに藤原氏が両者に絡み戦った。そして、式家が落ちて修正派の北家が上がった。桓武天皇に命じられ青木氏に代わり、伊勢の国司に成った北家の藤原藤成であったが、修正派の勝利で伊勢の守を退き、伊勢青木氏に戻した。
そして、藤原秀郷の祖父藤原豊沢が修正派として藤成と行動した。この結果、北家が力を持ち孫の秀郷の代へと繋がるのである。
3について
嵯峨天皇は渡来系への牽制策の必要性があった。余りにも大勢力の超一族が朝廷内に存在して来た。修正派として勝利した古来から朝廷内に血縁を広げて確固たる勢力を敷いて来た藤原氏にとって、この渡来系一族の存在は放置することは出来ない。しかし、余りにも大きく貢献度もある。建前上も到底武力では排除できない。
桓武天皇を背景とした渡来系一族は、勢力の出した青木氏を牽制し、今度は藤原氏が渡来系一族を牽制しょうと画策する。多分、薬子の変はこの策の延長線にあったのであろう。しかし、嵯峨天皇(809)から1185年までこの戦いが続くのです。この間にこの戦いが朝廷内にくすぶるのです。そして、数多くの乱(保元平治 1159)などに結びついてゆくのである。
戦う北家は摂政関白にありながらも殆ど権力を失った状況の中(1150頃)で、渡来系一族を横目に見ながら、その後の11代の天皇(1070頃まで)は源氏を賜姓し北家の協力を得ながら着実に親衛隊の育成に勤めるのである。特に、清和源氏が勢力を挙げて積極的であった。
この証拠に清和源氏の妻は殆どが藤原氏北家の娘である事。特に清和源氏の源氏の勤め先は藤原北家の侍所で、頼光や頼信などは長く摂関家に勤めたのである。(1148頃)このパイプを利用して約10年程度で、5家青木氏の守護地は全て頼光の守護地に変わり青木氏との血縁を進めた。(990頃)
ここで源氏と摂関家との結びつきが生まれ、清和源氏と皇族賜姓青木氏が古来からの守護職を清和に代譲し、且つ、5家青木氏の跡目に入るなどの同化策に出た。
つまり、(1150年頃まで)渡来系一族追い出しの長期共同作戦である。
背景2−3
(背景2-2の続き)
青木氏への牽制策が、今度は藤原氏が子孫を守るために余りに大きい渡来系一族に対して天皇譲位と言う変化を捉えて牽制を始めた。渡来系一族にとっては「青木氏との摩擦」から今度は「藤原氏との摩擦」になりつつあった。そのなかで、皇族一族の維持経費が増大した。
4に付いて、
天智天武期の改革で皇族の維持費が財政上の問題として大化の改革は行われたが、それから160年経った嵯峨天皇期には再び膨大していた。嵯峨天皇には多くの皇子皇女がいた。そして、8人の皇子を臣籍した。そして、皇族を賜姓しなかった桓武天皇にも皇子が居たので、天武からの第4世以降の王が嵯峨天皇の時には膨大に成っていた。それまでは第6世以上の者は坂東に移して土地の者(坂東八平氏)とした。
これが、「坂東八平氏」で”ひら族”と呼ばれていた。しかし、この「ひら族」以外に天皇が代わるたびに増える6世王がたまって来ていた。王には高位王と低位の王とが居た。この低位の王の存在が朝廷と天皇家の財政上の問題と成っていた。よって天智天武期と同様に嵯峨天皇は弘仁5年8月に詔書を出した。そして、それまで、大化改新時に実施した皇位継承の制度を正式に制度として発した。天武期のそれと一部改善して皇位4世第6位臣下方式を発した。
代々出る低位王の数を減らした。
この事も桓武天皇との考えの違いがあったのではないか。譲位すると直ぐに実行したのはその証拠である。桓武天皇はこの臣下の策を皇子の中では採らなかった。律令制度を構築した天皇でありながら
も財政上の改革を身内の中で実行しなかった唯一の天皇であった。
それどころか、渡来系一族の引き上げを一族と見せかけて賜姓したのである。(これが将来、朝廷内のもめごとの一つになるのだが)
重複するが、嵯峨天皇以降の15天皇(11天皇)はこの方式を踏襲して第6位王を臣籍して、それ以外の王は比叡山か門跡寺院の僧として入った。皇女は伊勢神宮の斉王や門跡寺院の尼僧として入ったのである。一部には豪族の他家に嫁ぐなどした。この皇女を受け入れた豪族は源氏一族として生まれた嫡子に名乗らせたのである。これが家紋違いの源氏一族の支流族である。(豪族の跡目方式として出来る源氏一族もある)これらは全て、家紋違いの源氏である。
入山した学僧や尼僧が還俗する時は[青木姓}を名乗る事もこの嵯峨天皇から後15代の天皇に引き継がれた。(多くはない)
歌舞伎などで演じらる5家の賜姓青木氏に対して、徳川家の殿様が上座を外す、外さないともめる場面がある。慣例では賜姓青木氏は上位であるので結局外して上座を譲るという場面である。
たとえ嵯峨天皇から臣籍してきた源氏であっても、古代の賜姓青木氏に対しては下座した。特に、伊勢王を先祖として持つ伊勢の賜姓青木氏に対しては、江戸時代になっても行われたと伝えられている。
天武天智から引き継いだ賜姓族の制度で朝廷の財政は改善されたのである。
(実際の効果は花山天皇期までで後二条天皇まで行われた)
背景2−4
(背景2-3の続き)
嵯峨天皇が譲位したこの頃、阿多倍一族の勢いに対して賜姓青木氏も北家藤原氏も何とか対抗しようとしてあがいていた。
しかし、余りにも大きい相手である。この渡来系の一族は益々実績を挙げて、更に力を付けて拡大した。過去誰もなし得なかったが長男の息子坂上田村麻呂は征夷征伐の大成果を成し、征夷大将軍となり、次男と三男は大蔵氏と内蔵氏として、朝廷の律令の国体を完成するなど3蔵の官職のうちの2つまで握り、又一族は九州全土を統治する大宰府の大監になり、「遠の朝廷」(とうのちようてい)と呼ばれ3権を委ねられた。室町時代までこのように呼称されて3権を与えられた者はいない。この様な一族の働く中で、嵯峨天皇は源氏を賜姓し、上記の1から4までの改革を進めた。歴史では簡単に云う大変な軋轢と争いがあり、例えこの「勢力争い」の中で、天皇でも身の危険もあり言語に絶する大変なことであったと思う。
嵯峨天皇と藤原氏はこれだけでは納まらなかった。
絶大な反対勢力の中で桓武天皇の「政治」を改めたのである。また、北家藤原氏も着実に勢力をた高めた。それは次のことである。
5に付いて
律令体制が完成したが、一つの問題が出てきた。
それは、官職と官職の間の不備である。この問題に藤原氏は大いに関わったのである。
それは「令外官制度」である。(令の規定にない官職)
戦略1
嵯峨天皇は渡来系一族の対策として次の政治見直しにかこつけて、対抗する勢力を藤原氏北家に次の役職を与えて政治力を強めさせたと考える。
戦略2
それと「侍所」や「右大臣」などの政治の場での役職を与えて、身内の源氏一族の引き上げをした。
令外官は次の通り。
内大臣、中納言、参議、勘解由使、検非違使、按察使、蔵人、摂政、関白、近衛府 以上を出来上がったばかりの律令制度外に設置した。(財政、司法、行政、立法の官)
この「政治と行政」の「見直し機関」を設置し、これに全て藤原北家氏が関わったのである。これにより、力の出てきた藤原氏の秀郷も祖父の豊沢と共に70年後位に押領使として下野に赴くのである。
そして、この「令外官制度」は次第に常駐となった。この常駐となる事で藤原北家は朝廷政治の中では、渡来系一族に負けない絶大な力をもったのである。阿多倍の末裔一族に対しては軍事や経済力は依然として劣っているが朝廷政治では同等とまで成ったのである。(880−920)
しかし、矢張り渡来系一族は巻き返し強かった。1120年頃には再び藤原北家族と源氏は権勢は無くなるのである。
戦略3
しかし、藤原氏北家は朝廷内では衰退したが、坂東では930−940年頃には、豊沢や村雄や秀郷らに役職を与えて勢力を高めさせていた。
そして、この時、遂に、朝廷内でも940年頃に、更に台頭のきっかけとなる事件が起こったのである。「平の将門の乱」である。
「平の将門の乱」では、秀郷は掛けに出た。将門の独立国家樹立の動きに対して、朝廷内には、2分する勢力の為に、この勢力を征圧する事が出来なかった。
阿多倍一族の平貞盛もこの掛けに出た。そこを見越した秀郷は、混乱する朝廷に2つ条件を朝廷に出した。平貞盛もこれに載った。この二人は決死で戦った。5年後に征圧した。条件の貴族に成る事と武蔵、下野国の領国化を2つを獲得した。この二つを基盤に低迷する藤原氏の勢力を付けて行ったのである。当然共に、たいら族の貞盛を始めとする阿多倍一族も勢力を高めて行ったのである。
また、一方近畿では、源氏が誕生して村上源氏(9代目)まで一族が拡大していた。そして「清和源氏」や「村上源氏」や「醍醐源氏」が3源氏は、軍事と政治に力を持ち始めていた。清和源氏の3代目の頼光、頼信の兄弟は、摂関家の侍所、村上源氏では、具平親王が右大臣になり、遂には朝廷内にこの3源氏は藤原北家氏と勢力を二分するまでに成長した。しかし、まだ一氏だけでは渡来系族には劣っていた。
(15源氏中この3源氏が子孫を遺し勢力を拡大した。)
令外官で政治の場に台頭した藤原北家氏、関東では北家秀郷氏らが勢力拡大、近畿では軍事力を保持した親衛隊の源氏3家が台頭、力の盛り返した賜姓青木氏の4勢力がスクラムを組んで対抗した。
この4つの勢力が一体となって渡来系一族に1160年を境に立ち向かうのである。
1−5の政治、軍事の改革変化の中で、戦略1−3を実行して、2分した天皇家をも巻き込んだ双方一進一退の状況であった。
背景2の最終。
>
Re: 皇族賜姓青木氏の背景 1の追記
青木研究員 さん 2005/06/27 (月) 09:50
2の佐々木氏の元祖の盛綱について、疑問の点があるので追記します。
宇多天皇の末裔としている事の説に付いて、
宇多天皇は15源氏を賜姓した天皇の一人です。したがって、盛綱は賜姓外の第7位以降の皇子となり、佐々木氏の跡目に入ったとなります。ここから佐々木氏は始まっていなく天智天武期からですから、必然的に跡目となります。しかし、元祖と記しています。
もう一つの疑問は盛綱は清和天皇の源氏で、父は源の頼憲としている説もあります。摂津多田源氏となります。
清和源氏盛綱は1の天智天武期の元祖の衰退した佐々木氏の跡目に入ったとする説です。そして各地に佐々木氏子孫を遺したとすると理屈はあいます。
同時期に源隆綱という者がいました。この隆綱も佐々木隆綱として記しているものもあります。しかし、隆綱は清和源氏源の頼政の子孫となつています。そして、太田氏の元祖となつています。
隆綱は頼政の子の広綱の子供です。つまり孫。しかし、佐々木氏です。頼政の子の仲綱の子の宗綱が佐々木宗綱と記しているものもあります。
清和源氏の同時期の者で盛綱と隆綱と宗綱の3人は佐々木氏の者としているのです。同時期に同姓同名の者が源氏方に居たとなりますが、明らかに疑問です。この3人は明らかに清和源氏源の頼光系の子孫です。源平の乱の始まりの以仁王の乱で没しています。
これらの3人の子孫は別の氏に引き継がれています。佐々木氏ではないと言う事です。
このように、どちらが正しいのか判らないほどに系譜には矛盾点を精査してよく検証する必要があります。
多分後刻に氏の欠落を没した者を使って都合良く埋め合わせたものと考えます。
結論は、多分、当時の15源氏の中では最大勢力の清和源氏一族が源盛綱をして1の佐々木氏の跡目に入り盛り返したと見ました。
賜姓青木氏と同様に跡目に入り、一族を盛り返しの策に出たとする説です。理由は32/66国の渡来系平氏の勢いに対する対抗策です。
背景 1の前段として。

皇族賜姓青木氏の背景 1
青木研究員 さん 2005/06/25 (土) 11:48
写真は青木氏の発祥木
(木名 あおき 古代の神木 三象徴物の一つ)
前背景では青木氏は順調に150年も伸びてきたが、桓武天皇期にはそのいくつかの政治的施策(前記)により急に衰退へと追い込まれることになり、反面、藤原氏は勢いを伸ばしてきた。
生きる為、子孫を残すための戦略のズレがこの場面を引き起こしたのである。
少なくとも、桓武期には皇族賜姓青木氏は約35年程度の間には子孫を多く増やす程に力は無くなり、否、減らす方向へと進んだと見られる。
特に、藤原藤成氏に守護を奪われるなどして、伊勢青木氏は直接の影響を受けたと見られる。藤原秀郷流青木氏と違い、その子孫が少ないのはこの時の影響も働いている。
(5地に少なく関東伊豆付近に移動している傾向がある)
後には、次々と難題が降りかかる。検証では10の難題が降りかかっている。繰り返し来るこの難題は皇族賜姓族と言う宿命と地理的要因によると考える。
しかし、950年には又立ち上がれるほどの力を保持して来ていた事が清和源氏と藤原氏との3者連携のその動きで判断出きる。
多分、この時の影響で、近江の青木氏の末裔が極端に少ない原因に成ったと見られる。近江から離れたのは桓武天皇の青木氏への圧政であったと推測する。近江青木氏は再び戻るが佐々木流青木氏が存在するのはこの戻った時の生き残る妥協策であろう。
何故なら、近江佐々木氏は生き残っている。そして、丹波や大江にも佐々木氏の子孫が繁栄している事が証拠である。
ここで、近江佐々木氏のことに付いて多少述べる事とする。
近江佐々木氏には二つの流れがある。
1 天智天武期伊勢青木氏と同じくして第7位の川島の皇子が天武天皇により、地名の近江の佐々木村の名を採って、特別に賜姓を受けたとされている。本来は第7位からは賜姓をださない慣例になっていたので、伊勢王と兄弟の川島の皇子を天武期の朝廷に対する貢献を鑑み丁重に扱ったことが伺える。(日本書紀にも伊勢王に近いその貢献が多く出て来る)
(参考 文武天皇以降と桓武期の賜姓青木氏以外の皇子はこの当時、神社仏閣門跡院などに入山した。還俗時は青木姓を名乗った。これが第三の青木氏で室町から江戸の初期までと明治初期の2回にわたり青木氏の名が利用された原因です。皇子にとっては厳しい定めであったことを追記する。当時は皇子はだれでも栄華を受けない事が子孫を少なくした原因の一つです)
他の文献では明確に佐々木氏を書いているものは少ない。
2 宇多天皇の時(867−931 位887−897)の末裔の者で臣下した佐々木盛綱を祖とする佐々木氏で、この佐々木氏は全国10国に及び守護を務め、この江州佐々木氏が全国に広がった。
(参考 盛綱は以仁王の乱で伊勢青木氏の跡目を継いだ「京綱」源の頼政一族に加担している)
この佐々木氏から、上記の丹波佐々木流青木氏(元の姓は上山氏でこの系譜をなんらかの方法で引き継いだ)が誕生した。
1は 桓武期前の佐々木氏(近江)、
2は 後の佐々木氏(丹波) 後に戻った近江青木氏と佐々木流青 木氏系を造る。これを上山氏が城持ちになった時、この系譜を 買い取り引き継いだと思われる。
この様に近江丹波には桓武天皇期前には佐々木氏と青木氏とが住み着いていた。しかし、後に第2の佐々木氏が元祖佐々木氏の跡目を引き継いで、全国(北陸、越後、近江、山城、大和、淡路、阿波、土佐、伊予、石見)に佐々木氏の子孫を広めた。
もう一つの広めた理由はこの各地の佐々木氏の菩提寺の住職を務めたこともその一つである。
藤原秀郷流青木氏もこの菩提寺住職を務めたことに子孫を多く遺した理由でもある。
しかし、子孫の少ない理由のもう一つは賜姓青木氏にはこの努力が足りない事が伺える。(調査中)
賜姓族5家の青木氏は桓武天皇期頃(790−850)を境にして大きく変化している。そして、975年頃を境に再び、息を吹き返している。
次のレポートは嵯峨天皇期からの青木氏の行方源氏と平氏と藤原氏の絡み合いの中での事を記する事にします。
(参考 三つ象徴:笹竜胆の綜紋 生仏像様 青木の神木)
|
Re: 日本書紀と青木氏 10
副管理人さん 2008/04/24 (木) 16:35
前節と本節には、関連性がある為、前節の内容を念頭に以下をお読み頂きたい。
検証する青木氏に関わる内容は次の通りである。
検証項目
活躍 第1節 「白雉の年号」
活躍 第2節 「伊勢王の薨去」
活躍 第3節 「伊勢国の重要度」
活躍 第4節 「諸国の巡行」
活躍 第5節 「紫の袴着用の許可」(最高位の身分扱い)
活躍 第6節 「天皇の名代」
活躍 第7節 「天武天皇の葬儀」
活躍 第8節 「善行説話の編集」
活躍 第9節 「伊勢行幸」
活躍 第10節 「大隈の首魁(阿多倍)」
本書記録
活躍 第10節 「大隈の首魁(阿多倍)」
”天武没(朱鳥)元年5月22日 皇太子は公家百官を率いて、もがりの宮に詣で慟哭された。隼人の大隈:阿多の首魁が夫々の仲間を率いて互いに進んで、しのびごとをした。”とある。
”天武没(朱鳥)元年7月9日 隼人の大隈:阿多の首魁等337人に物を賜った。”とある。
”天武没(朱鳥)3年8月16日 伊勢国伊賀郡(阿多倍の国)の身野2万代に禁猟区を設けて守護人を置いて、河内大鳥郡に順ずるものとした。”とある。
”持統3年5月15日筑紫大宰率「河内王」等に詔して「沙門を大隈と阿多とに遣わして仏教を伝える様にとご下命。”とある。
”持統6年5月13日 隼人の大隈に饗を賜った。”とある。
”持統6年5月21日 隼人の相撲を飛鳥寺の西の槻の木の下で行われた。”とある。
”持統7年 直広1位の位を宿禰大隈に授けられ、伊賀に水田40町賜った。”とある。
検証
本記録は「伊勢王」とは異なるが、「伊勢王」に大変関係する不可欠な記録であるので、特記する。
上記に、その大隈首魁の阿多倍と阿多倍一族の事だけの抜粋とした。何故ならば、この首魁の行動は、相対の関係で、青木氏の「栄枯盛衰」に大いに関わる事と成って行く事だからだ。
大変に奈良時代、否、現在の日本の国体の基礎を築いた帰化人の一族なのだが、余り知られていない。それだけに、特記する必要性を感じている。
この知られていない理由には、日本書紀の研究の遅れと、近代の日本の軍国主義と、左傾主義の本書の否定から、これ等の史実に対して葬って来た事が上げられる。
しかし、本書の裏づけが、韓国(高句麗)から発見された僧道顕の著「日本世記」や「海外記」「海外国記」等から、日本外交史の事に付いて最近裏づけが取れた事から、史実である事が判り、理解される様に成ったのである。
僧道顕は天智天皇の無二の政治の相談相手であり、共に生活した為に、その書は天智、天武天皇の政務や出来事をかなり詳しくその日の出来事を日記的、且つ、記述的に書き込んだのもので、日本書紀より詳細に書かれている。(本書外にも、青木氏の賜姓、由来、仏像授与もここにも記録)
しかし、「日本世記」に拘らずとも、本書の前後関係だけから見て史実である事は明白である。左傾主義者が間違いの多い事を殊更に喧伝した思惑否定の為に一般には信用されていなかったのである。だから、知られていなかったのであり、そのことを頭の隅に置いて頂き次の事をお読み頂きたい。
先ず、研究室のレポートに各処に記述しているが、本書の目的の面から概容を改めて記す。
この大隈の首魁の阿多、即ち、阿多倍王は、後漢光武帝より21代末帝の献帝の孫(石秋王の子)阿智使王と、その子の阿多倍王である。
最終、後漢は隋に圧迫(610)され、唐に潰されて(618)、これ等の阿多倍らに率いられた民は、北九州に上陸した。その入国は1次と2次とに分けられる。
入国経緯
第1次(前期)としては、隋が後漢を含む朝鮮半島を征圧する為に東征したが失敗し、そのために隋は弱体化して、結局、後漢と共に唐に618年に滅ぼされる。この時の2度の圧迫(隋唐)で難民が生まれ、その時、第1次(前期)は、先行して、後漢(高句麗)の漢氏(東漢氏)、司馬氏、秦氏、陶部氏、鍛冶部氏、等が先ず入国(582年頃前後)したとあり、渡来人の秦人、秦人部、秦部等(弓月君始祖)の秦氏の一部族だけでは約7053人居たと記録(宣化、欽明天皇期頃の記録:570-580年)にある。
この数字から観ると、従って、新羅百済の朝鮮系の渡来人を入れると、「部」の技能組織は、記録から調べると40−50程度と観られ、590−630年の間には40−50万人は入国していたと見られる。
第2次(後期:最盛期)としては、次に唐に圧迫(616-618頃)された後漢も滅亡し、618年前後頃か難民で入国、孝徳天皇期(650頃)が頂点となり、以後下降(670年頃)となり、後漢民の終わりは710年頃で200万人とある。(全難民は250-280万)
これ以後、全国的に各処で度々不法入国事件が続く。最後は、1019年の博多下関での西夷大乱入事件があり、朝廷は政治的に「遠の朝廷」の太宰大監の「大蔵種材」に命を正式に出し、「難民受け入れ」は打ち切った。
第1次の ”「阿智使王」(阿多倍の親)が率いた”との説があり、間違いである。
史料に依ると異なる。後漢が滅亡していないのに[阿智使王}だけが先に来るのは疑問である。他に史料では阿智使王は孝徳天皇期(650)に入国したとある。本書の記録と一致し後者が正しい。
又、前者の説では阿智使王は朝鮮系と成っていて、漢氏の始祖と成っているが疑問である。
前者の説は、全て朝鮮系としたいとする意図が見られ、史実を無視している。([日本世記」を無視)
第1次の一族の入国と本格第2次の阿多倍集団は、九州全土と中国地方を無戦征圧し帰化した(17県の200万人)技能集団であった。(研究室の阿多倍の関連レポート参照)
この集団が何故にここに出て来るかと言うと、「伊勢王」即ち、伊勢青木氏の「栄枯衰退」と「子孫繁栄」に大きく関わる集団なのである。
先ず、この阿多倍の本書の記録から検証して、次に本書「伊勢王」(青木氏始祖)との関わりを論じたい。
兎も角も、その前に理解を深める為に大筋の経緯を述べて置く。
孝徳天皇期前後(第2次)から、更に、後漢から遼東半島の湾を経て、先ず北九州に上陸入国してきた。これ等の民は中国の進んだ技能を持ち込んだ。所謂、「部」(40-50部)の民である。
その首魁阿多倍王等に引き入れられた軍と技能集団は、北九州から南九州にまで殆ど無戦の状態で征圧した。むしろ、大和の九州の民は進んでその配下に入り、その優れた技能を吸収して生活レベルを向上させたのである。そうして、彼等の首魁の阿多倍は南九州の大隈に定住した。
その後、続々と上陸してくる後漢の民と後漢に圧迫された朝鮮半島の民は、朝鮮半島を経て、中国地方の下関付近に上陸し中国地方へと更に進出して、ここも無戦征圧して、関西の西域まで到達した。
後に、この中国地方は第1次の後漢の「陶部一族」(すえべ)が勢力を高めて征圧し、室町末期まで大豪族として統治した。
この時点で、朝廷は彼等の貢献度を認めて帰化を許し、彼等は帰化人として正式に各地に定住した。
しかし、新羅の政情不安からも難民が出て、ここまででいっぱいに成り、朝廷は後漢の民と共に中部地方の未開発地域に配置した。特に、本書記録でも後漢の民が持ち込んだ外来馬の飼育に適する地域として、美濃(岐阜付近)と信濃の西地域に配置したと本書に記録されている。
朝廷は、この地域が開墾開発が進み、戦略上、主要穀倉地帯でもあり、幹線道路でもある事から天領地として定め、ここに、「美濃王」として第6位皇子を配置したのである。
(この子孫が美濃青木氏である)本書にもこの記録が出て来る。
朝廷は、南九州の隼人に定住していたこれ等の帰化人の首魁阿多(後漢阿多倍王)を都に呼び寄せて、その貢献に報じて賜物を授けた。この時、彼等は天皇の前で337人と言う大勢で踊りを披露したとある。
その後、伊勢北部伊賀地方を割譲されて定住した首魁大隈の阿多倍の一族関係者が、一同挙って天皇の前に集まった事である。しかし、337人と言う定数が面白い。先ず第1の疑問1(違和感)がある。
普通、記録しては”集まった”で良い筈である。
その理由の詳細はまとめて下記に記するが、ある目的で誇張したかったのであろう。
概して、”彼等の技能が国の発展に大きく貢献した事”であり、阿多倍一族らを「伊勢北部伊賀地方の割譲」をして、そこに住まわせた「理由と経緯の明示」(疑問1)を喧伝したかったのである。(詳細下記)
その後、天武天皇が崩御して、彼等は伊賀から都に出てお悔やみをしたのである。
2月後、再び、呼び出して、改めてその功労に対して、勲功を受けたのである。
「帰化人に割譲」の「理由と経緯の明示」の目論見は目立っていて、ここまでは問題はない。
しかし、”6年後に、大隈に居る阿多倍一族と、伊賀に住んでいる阿多倍に仏教を伝える様に命じた。”とあるが、何で彼等にわざわざ命じたのか疑問が湧く。第2の疑問(疑問2-1)である。
そして、何で仏教なのか疑問が湧く(疑問2-2)。
「仏教」と「阿多倍一族」の2つの疑問である。(疑問2)
それには明確な必然的理由があるのである。本書のこのままの記録ではこの疑問は解けない。
「仏教の伝来の経緯」の中に有ったのである。そこで先ず、その経緯を説明する。
仏教伝来の実際の経緯
実は、仏教伝導は「蘇我氏と物部氏の戦い」で決まったもので、聖徳太子の時の問題であった。この時は「決まった」だけであって、「伝導:広まった」ではない。誤解されている。
しかし、第9節でも述べたが、持統6、7年頃は政情は不安定で、特に畿内では国内問題を持っていた。しかし、現状の「仏教布教」は未だ天神文化と共に上位階級のものでしかなかった。
騒いだ割には大きく進まず、民までのものでは無かったのである。依然として、神物信仰が主流であり、天皇家自ら伊勢神宮を興隆させているくらいである。
そこで、朝廷は、矢張り、「民の心」を治めるには、仏教の宗教で納める事であるとして、進んだ中国の仏教典を持つ彼等に仏教布教を命じたのである。疑問2-1の解決である。
そこで、”何故、彼等にこの「仏教」をなのか。命じたか。神物ではないのか。”と言う第2の疑問中の疑問があるだろう。
それを説明すると、第2の疑問が解けるのである。
実は、阿多倍の配下で、初期(第1次)に入った「司馬達等(馬の鞍造を造る技能人鞍造部の頭領)」と云う人物が居た。この人物は大和国高市郡坂田原(天智天皇の高市皇子の里)で草堂を営んでいた。
彼は後漢から持ち込んだ仏教を、故国から離れて「部の民の心」の頼り所として、私伝で「部の民」に伝えて導いていたのである。(司馬達等:仏教私伝の祖と呼ばれる)
そして、その為に鞍を作る技能で仏像をも彫り、祭祀していた。(他書記録による)
次第に彼等の帰化集団者と彼等の配下となって技能を磨いている「大和の民」にもその仏教の広がりを見せ、大隈国と伊賀国の民を始めとして、彼等に従う関西以北の大和の民の心は穏やかであった。
この時期、少し後に、南九州では独立運動(700-713年頃)が起こり、朝廷の命に従わなかった。
分轄した日向、薩摩、大隈の内、薩摩と日向(朝廷大官僚の弁済使の伴氏と血縁した九州大豪族肝付氏)は従わず、朝廷は720年に遂に討伐した経緯がある。
朝廷は、この阿多倍等の生活態度の事前情報を得ていて、(この時は、半国割譲の大隈の首魁阿多倍一族とその技能集団は平穏であり、その原因は仏教布教にあった事。)そこで、国政不安定の中、持統天皇は、九州全土を統治している太宰大監の「三河王」に命じて、全国に彼等のこの仏教を伝え布教するように命じたのが、この経緯なのである。(この段階では、太宰大監は阿多倍一族ではなくこの直ぐ後である)
半国大隈地方と半国伊勢北部伊賀地方の阿多倍一族の彼等に、問題と成っている関西域にも、布教する様に命じたのである。
これが第2の疑問の解答である。
それだけに、この意味するところは、持統天皇は帰化人の彼等に頼まなければ成らないほどに窮していたのである。これ一つでも「治安人心が不安定」の証拠になる。即ち、疑問2の大元が証明出来る。
しかし、この時、本書の記録を良く調べてみると、後漢の東域の朝鮮半島の新羅と百済からの難民も入っていて、この仏教を信じていた。しかし、よく調べてみると、この新羅、百済の難民の事に付いては、本書記録ではこの期間の1年間で40件程度と本書にしては、目だって多く記録されている事に気づく。(新羅、百済からの難民は応仁大王の事件と共に、5世紀頃から始まっている。)
むしろ、その中を分析すると、犯罪的な事を起し、処罰されているのが約半数弱もあるのである。反面、後漢の民の犯罪記録は全く無い。
現在に於いてでさえ、外国人が多くなると犯罪や揉め事が多くなる。この時は、250万と言う難民帰化人が入国したのである。普通である筈ではない。
そう云う環境の中で、それどころか、隼人の大隈の一族の者を呼び出して、その功労に対して、天皇自ら宴を催して褒め称え、更には、隼人相撲大会を飛鳥寺で行っているのである。
この意味するところは明らかである。まして、「飛鳥寺」と言う場所に意味がある。一般公開である。宮廷ではない。
これは、”どの様に解せば良いのか”と言うことなのであるが、第3の疑問である。
実はこれも明確な理由があったのである。
持統天皇は、不満を増大している大和の民、阿多倍の帰化人の民、新羅、百済の難民の民、この3つの民の安寧を納めるには、静かに帰化してくれ、穏やかに生活している「阿多倍一族の扱い」にあると読んだ。
そこで、相撲大会である。
単純に相撲大会如き行事は何処でもある。しかし、この二つの行事をそれも「隼人相撲」を「大々的」に記録しているのである。相撲ならば何処にもある。何も遠い隼人から呼ぶ事は無い。
また、舎人親王は、得意技で何かを意味するところを含ませているとしか思えないのである。
そこで、本書の得意技と他史料をも調べた。そうすると観えて来た。
つまり、他の時期にも新羅百済の事は記録されているが、この行間前後の本書記録としては適さない40件もあり、その中約1/3の百済、新羅の民の「犯罪」と、何処でも日常茶飯事の「懲罰」がこの時期にわざわざ集中して記録している。
新羅、百済でなくても大和の民も犯罪を犯している筈である。歴史記録に値しないその茶飯事の事を記録しているのである。
明らかに記録の編集には違和感を抱かせる。
その反面、比較対照として貢献している阿多倍の集団を相撲というものでクローズアップさせて、際立たせ、その「品行方正な民」である事を目立てさせる事が、持統天皇の企みなのであり、その天皇の「治世の苦労」を何とか記録として、舎人親王は得意技で編成の配慮をしたのであろう。
これが、第3の疑問の検証の解答である。
この本書が完成する頃31年後には、この阿多倍の帰化人は、政治の官僚の中に「事務方」として本レポート序文に記述した時(天智、天武期)よりも、多く既に入り込んでいる。
この時期、多くの「律令整備」が進んでいる事が証拠である。
そして、”本書のその編成も当然に彼等達が行っていた”と言う事である。
留学生以外の大和の民ではその学識から無理である。留学生にしても量的にもこれだけの「律令整備」を賄う事は実務的に無理である。
そこで、実は、その記録が存在するのである。
”天武期4年2月9日 大和、河内、摂津、山背、播磨、淡路、丹波、但馬、近江、若狭、伊勢、美濃、尾張の国に勅して管内の人民で歌の上手な男女朱儒技人を選んで奉れといった。”とある。
”天武期5年4月14日 朝廷に仕えたいとする者で一般の者でも能力のある者は雇え。”とする直接命令の記録がある。この一つでこれ以後、如何に忙しく成っているか物語っている。
前者の記録は、畿内と中部の王の守護統治領から、政務とは別に、文化や祭祀に拘る体制を民間(渡来人)から集めて確立させようとしていたのである。
後者の記録は、天智天武期から始まった「律令整備」の計画に対して、始まった頃に天武天皇は先読みして準備してこの手を打ったものである。
この2つの記録に付いては、この時期には、天武は民間の力(渡来人)を生かして国の力を付け様としていたのである。
それが持統期には、効果を発揮して律令体制の整備は大いに進んだ。
因みに、彼等による「律令整備」は、「帝紀」、「八色の姓」、「庚寅年籍」、「飛鳥浄御原令」、「藤原京遷都」、「大宝律令」、「養老律令」等が上げられるが、この中味たるは大変なものである。(詳細は大化の改新のレポート参照)
既に(686-692頃に)天皇家に血筋的に食い込んでいる阿多倍一族を、舎人親王は時代性を演出する為に故意的に挿入したのである。
むしろ、当然に、彼等の進んだ知識を以って入り込まなくては成らない程に「政治機構化」していたし、大和の民では、その内容を検証すると到底無理の一言の内容であり、既存の知識、学識ではその範疇が小さかった理由もある。従って、その後漢の民の活躍記録としては、主体がかれらの活躍でその記録になる。
その証拠に、天智天皇から持統天皇までの律令の制定は急激に多く成っている。(参考記述)
特に、この持統期の時期にすれば、689年の「飛鳥浄御原令」の令(民法、行政、訴訟法)と、701年の太上天皇(持統天皇)の「大宝律令」の律(刑法)の2つの大きな完成がある。
これ等は彼等の知識抜きでは成し得ない。
それならば、ここで疑問が湧く。
本来であれば、このような政治、経済、軍事の全能力を持った集団が、殆ど無戦で九州全土中国地方を征圧している事から、「独立国家」を宣言してもおかしくない。
しかし、”行わなかったのは何故なのか”
第4の疑問である。
彼等の軍事、政治、経済のどれを執っても朝廷より遥かに優れている。
また、その技能に依って民の生活レベルが急激に上がり、土地の人心も掴んでいる。従って、戦略補給は充分である。既存の朝廷が到底成し得ない力である。
なにせ、17県民200万と言う人口が津波のように押し寄せてくるのである。朝廷は戦っても絶対に勝ち目は無い。彼等の軍事、経済、政治の力を除いても、この真に津波のように「押し寄せる力」に打ち勝つ力は無い。「押し寄せる力」で充分である。
中国では隋に討伐されて漢が滅亡して漢民は西に逃れたが、西の土地(ネパールチベットベトナム等)の者を追い出し、そこに定着している経緯もある。(正式に元国のときに中国と制定)
その一方の東に逃れた漢民(光武帝に率いられた民)が、東中国と朝鮮半島北部を征圧して後漢を樹立したのである。
その経緯から考えても、後漢難民と言っても、普通の難民ではない。大和国に入った彼等は独立国を樹立するに充分な条件を備えている。大和朝廷としては、歴史上最大の国家存亡の危機問題である。
ところが、関西直前で彼等の進軍は突然に止まったのである。真に「一大決戦」と言うときにである。この時、既に、大和国66国中32国を征圧しているのである。
”進軍停止は何故なのか”第4の疑問(独立)の中の疑問が出る。
それには、ほぼ200年前にも同じ事が起こっているのである。この事は朝廷は知識として知っている。迫る阿多倍の集団に対してどう出るべきかを悩んでいる。
朝廷の事前知識
応仁(応神)大王が、朝鮮半島の百済を始めとして南部の民から構成された大船団を整えて、堺の港に上陸した。
当時、関西域は4つの豪族(巨勢、平群、葛城、紀の4族)の連合体で「ヤマト王権」(大和朝廷前進の連合政権)を樹立していたが、この連合政権と戦った。
先ず、上陸後、4つの豪族は水際の前哨戦で負けた。しかし、この4つの豪族は一端奥に退いて長期戦へと持ち込んだ。大王側は各個攻撃へと変更し、紀族を制圧、紀伊半島を回って新宮から奈良盆地に入った。ところが、残りの豪族達は奈良盆地(当時は未だ奈良盆地は中央に大湖があり、現代は地殻変動により湖面が下がり湖底の所にある。現代の「猿澤の池」がその元と言われている。)
の水際作戦のゲリラ戦を採用し長期戦に持ち込んだのである。
結局、この応仁(応神)大王の船団は補給不足となり、戦いを中止し講和した。そして、5つの豪族による「ヤマト政権」を樹立し、初代の大王に応仁(応神)大王が成った。(この時期は未だ「天皇」では無く「大王」と呼んだ。)
これが類似する事前知識である。
今回の阿多倍の集団には、違う点としては次の事がある
大和の民が彼等に従っている事である。
入国側の民は土地に生活基盤(技能集団)を作り定着している事。
戦いとなると、阿多倍側は勝利は確実であるが、この2つの事(軍人ではない2つの民を巻き込む)で良民に大きな犠牲が出る事になる。かれらも悩んだ。無戦で勢力下に入った人民である。
彼等の首魁の阿多倍は、”犠牲を払って勝利で独立国家を樹立するか、無傷に平和裏に帰化して実利を獲得するか”の二者択一の選択に迫られた。そして、都に入る直前に、選んだのは後者であった。
第4の停止の疑問の答えである。
この様な彼等の態度に対して、事前知識を持ちながらも、朝廷は悩みに悩んでいた事が、阿多倍集団の「実利の決断」と朝廷の「事前知識」とが一致した結果となった。
朝廷は平和裏に解決した事に対する安堵感で一杯であった筈である。多分記録には無いが下交渉はあった筈である。
決着した。そこで、彼等の首魁を呼んだ。阿多倍らもその恭順の意を表す為に、天武天皇崩御(686)に対して、都に出て葬儀に大勢(337人)で参加すると言う姿勢を示したのである。
これが、帰化申請後の「最初のもがりの参加記録」である。
又、この337人は上記のデモもあろうが、多分にして、騙まし討ちを避ける為の阿多倍を護衛する為に付き従った者達であろう。
そして、その返礼として持統天皇は再び彼等を2度も招き、次の記録の経緯と成るのである。
持統6年5月21日 隼人の相撲。
持統7年 爵位直広1位の位を授け、姓は宿禰とし、半国大隈国を授けられ、伊勢半国割譲の伊賀地方(水田40町)賜った。”となるのである。
見返りとして、下交渉の約束で、持統天皇は彼等に先ずはこれだけの事をした訳である。
これが第4の疑問の検証である。
(下交渉の記録はないが、これだけのことを下交渉がなくして出来ない)
しかし、これだけでは収まらず、持統天皇は次から次へと藤原氏以上に引き上げて行く事に成ったのである。(参考 藤原氏は720年頃から台頭:藤原不比等)
朝廷側も事前知識で彼等を敵とせず、味方に引き入れる戦略を採り、「独立国家」に相当するものを与えたのである。事前知識と全く同じ経過を辿ったのである。
むしろ、記録には明確なものは見当たらないが、下記の事も含めて、水面下の交渉の末でのこの「帰化条件」であったのではないかと思われる。
それは次の記録から判断出来る。
帰化の条件の説明
持統天皇としては、この200万人と言う技能大軍団の犯罪を起さないおとなしい帰化人が、第1次産業の技能を持たらし、それどころか国政の事務に長けて律令の根幹を作り、国の発展に貢献している事にうれしくて成らないのである。
その証拠に、「阿多倍」は「敏達天皇」の曾孫の「芽淳王の娘」を娶り、「天皇家と縁結び」となり、且つ、「准大臣」に昇格し、「宿禰族」に列せられ(830年頃)、「半国大隈国東部を割譲」し、「国の首魁」を認め、「伊勢北部伊賀地方を割譲」し与えられ、更に、この半国に「不入不倫の権」を与えられたのである。文句の付け様のない扱いである。
これが持統7年頃のことである。
それどころではない。血縁となり、3人の男子を産み、長男は坂上氏を、次男は大蔵氏を、三男は内蔵氏を、「賜姓」(690-705年頃)を授けている。
まだまだである。少し後では、この3人に、夫々、坂上氏には「朝廷軍」を任し、大蔵氏には朝廷の「財務大蔵」を任し、内蔵氏には天皇家の「財務内蔵」を任したのである。
参考として、朝廷の役所は「3蔵」と呼ばれ、大蔵、内蔵、斎蔵で構成されていた。
斎蔵は藤原氏である。彼の名声と権力を欲しい侭にした藤原氏(不比等)である。しかし、未だ、この頃は、斎蔵を任され祭祀を含む朝廷全般の政務と総務を担当していただけなのである。
その事から、考えたら、恐ろしい程に朝廷の実権を握っていたのである。藤原氏どころの話ではない。(藤原氏の名声は知られているが、それ以上の比べ物にならない名声と実績を持ったこの阿多倍一族は余り知られていないのが、不思議の一つである)
もう終わりと思うであろう。ところが、皇族の「三河王」に代わって、九州全土の行政長官の「太宰大監」(博多別府大宰府:大蔵春實938頃:種光950頃)に任じたのである。(この時、奥州は藤原氏の鎮守府将軍となる)
まだあるのである。今度はこの「太宰大監」に、軍事、行政、経済の「3権」を委ねたのである。
そして、更に「遠の朝廷」(940年)と名付けるのである。遠いところの「九州の朝廷」とまで命名した。
又、「征西将軍」(1017年)に任じられるのである。
最後に、この「遠の朝廷」の阿多倍一族の「太宰大監」に「錦の御旗」を正式に与えたのである。
この「錦の御旗」(830頃:天慶3年:大蔵春実と孫の大蔵種材)は個人に与えた記録は他に無い。
最後の最後と言いたいところであるが、この「太宰大監」を阿多倍一族大蔵氏の「世襲制」としてしまったのである。(追加:この末裔の太宰大監の大蔵種材という豪傑がいたが、この者を四天王のモデルにしてしまった。)
この位で止めて置くが、この事で、もうお判り頂けたと思う。
「独立国」を選ばす、「実利」を選択したが、実利以上の無血の「九州独立国」そのものである。
これで疑問は史実で解けた事になる。850年代で完全達成している。
これより以後もまだ続く。
伊勢北部伊賀地方の阿多倍の孫娘の「高野新笠」が光仁天皇の妻となる。その子供が「桓武天皇」に成る。桓武天皇は母方の伊賀の「阿多倍王」別名「高尊王」(既に没)に対して、架空の「高望王」(平望王)と呼称し、「第6位皇子」の扱いをして、「たいら族」として氏の「賜姓」をしたのである。(詳細下記)
そして、その末裔孫の2代目「平国香」より「平貞盛」で勲功を挙げて、5代後に「平清盛」で太政大臣と成った。
これで、朝廷の政治も思うが侭である。九州だけではなく、全国の政治、経済、軍事の覇権を握ったのであり、独立国どころではない。
本書の持統期(700年頃)では、この一族は未だ60-70%程度であろうか。そして、最終(100%)は1120年頃であろう。そして、1175年頃から没落し1185年で平氏滅亡(京平氏)である。
反面、伊勢青木氏は全くこの逆である。
伊勢の国を割譲されて、伝統ある近衛軍の役職も押さえられ、更には、伊勢の守護も半国司の藤原藤成(藤原秀郷の祖父:826年)に任してしまったのである。
当然、皇親政治として活躍していた天智天武期から、何時の間にか(645-720)この阿多倍一族に全て国と役職を奪われたのである。国と役職を奪われては基盤は無くなる。衰退は避けられない。現実に衰退した。
一方、阿多倍の一族は半国伊賀国を与えられ、そして、遂には、この首魁「たいら族」(平氏=京平氏:桓武平氏:伊勢平氏:781年頃)の一族に天皇から賜姓を受けた。
この賜姓は「大化改新」の目的の一つ経費削減で、第6世以降の皇族の者は皇族を外し、平に成った事から「ひら族」(坂東平氏として賜姓:坂東平氏:8氏)として、天智、天武、持統期に代替わり毎に坂東に配置した。
この「たいら族」の賜姓は、この「ひら族」にかけて阿多倍一族に名付けたのであるが、実は、皇族に並び続く「7世族」として位置付け、「ひら族(平氏)」を「たいら族(平氏)」として「高尊王」(阿多倍王の日本側呼称)に賜姓(桓武天皇期)したのである。
しかし、記録では、伊賀の国に住む「平望王」(高望王)と成っている。これは「尊と望」の編集時の間違いか、平氏賜姓後の呼称なのか、生没も含めて一切の記録は不明なのである。
この時、阿多倍は没している筈であるので、皇族系(第6位皇子)である事かをほのめかす為に「平望王」(高望王)は、「高尊王」に因んで、後付したのではと考えている。
この当時(持統期)は未だ、帰化人には偏見があり、次第に皇族との血縁族とは成りつつあるが、皇族に列する処置が出来なかったのである。
史料から観て、帰化人(渡来人)の字句が消えるのは桓武天皇期の書物からである。
(桓武期頃より以後、難民、帰化人は九州「太宰大監」の大蔵氏が、記録では朝廷の命で盛んに博多、下関の水際で食い止めている事件が記録されているので判る。)
これは、伊賀の国に住む阿多倍の末裔孫]娘「高野新笠」が光仁天皇の賓(みめ)と成り、後の「桓武天皇」を産む事により、世間は、最早、「天皇まで成る時代」として世間の意識の中で、渡来人では無いと考えたからであろう。つまり、日本民族の完全融合(参照 日本民族の構成のレポート)の完結期の経緯である。
賜姓を受けた伊賀の国に住む阿多倍一族は、その末裔孫の「平国香」(900頃)より始まり、「貞盛」(950:繁栄の基礎:平将門の乱鎮圧、常陸の押領使)、「惟盛」、「正盛」(中央政界)、「忠盛」(平氏繁栄の基礎)、「清盛」と続き、5代後で「平清盛」(1180)の太政大臣にまで上り詰める。
遂には、後漢から帰化した阿多倍一族の集団は、上記の本書の記録に示す持統天皇期から政治に関わり、天皇(桓武天皇781)まで上り詰め、政治、経済、軍事と産業の基盤を創り上げたのである。
この伊賀に住む後漢阿多倍王の末裔(渡来人:高野新笠)を母に持つ桓武天皇は、その彼等の力で「日本の律令制度」を完成した天皇としても位置付けられている。
阿多倍の上陸後、上記した経緯でその独立国を樹立せず、200年間でその効果と同じものを持つ実利以上でその立場を確保したのである。はっきり言うと、乗っ取ったとも取れるものである。
しかし、大事なことは、悪い意味での「乗っ取り」ではなく、むしろ現在の日本の政治、第1次産業の基盤を築く程の国としての国体を作ったとしても過言ではない。
「単純な帰化」ではなく、日本の国体を「構築した帰化」であった。阿多倍の卓見である。
ところが、古事記域に入るが、元明、元正天皇と女性天皇が続き、聖武天皇と成り、矢張り第5位後継者までは絶えた。
暫くすると、第6位皇子である「伊勢王」(施基皇子)の子供を、皇位継承者が無かった事から、伊勢より皇位継承者を出す以外に無く成った。光仁天皇である。(伊勢青木氏とは縁続きになる)
一時、一族の光仁天皇により息を吹き返したかとの予測も付くが、甘くは無い。伊勢隣りの伊賀の娘を娶ったのである。
しかし、、前節でも記述したが、その孫(光仁天皇の孫)の嵯峨天皇は賜姓を戻し青木氏を救ったのである。
「伊勢王」を始祖とする伊勢青木氏を含む5家5流24氏の青木氏、更に母方で繋がる藤原秀郷流青木氏主要9氏116氏の元祖は、日本書紀の中で、その「生様」を検証して来たが、大変な、激動の時代(645-710)を乗り越えて来たのである。
日本書紀は編年体であるが、上記した様に真に、舎人親王著「編年体小説」と名付けたが、余り、伊勢王をキーワードとして、限定して検証している書籍はない。
また、本書内の舎人親王の「詩文体」とも言うべきものを考えて、それを年頭に記録を徹底して検索して詩文の環境を導き出すという手法を採用した。
結果は、本書には30箇所以上の伊勢に関する記録が出て来るし、他書籍にある史実以外のものが見えてきて、その背後関係を導き出す事が出来た事は、驚くに値する事であった。
検証する者としてわくわくとして検証した。
幸い、筆者の先祖代々は紀州徳川氏の漢文、漢詩、南画の師たる者でもあった事が”門前の子童習わぬ経を読む”が幸いしている。
古事記の序文ではないが、青木氏も同じ事が言える。”今を逃すと青木氏の史実は消える”と。
これが、本レポートの思いである。
近い将来、時間が有れば、青木氏一族としての藤原秀郷主要5氏の2氏(永嶋氏と長沼氏)との関係についても検証レポートを投稿したいと思っている。
参考
「坂東八平氏」とは、千葉、長尾、上総、秩父、土肥、梶原、大庭の8氏である。
北条氏や熊谷氏は支流である。
阿多倍の天皇家との血縁の年代推定は686-692の間の年代であろう。
”阿多倍次男の山本直が大蔵氏を賜う。”とあるが、その前の時期に敏達天皇曾孫の芽淳王の娘と血縁により次男が生まれ賜姓を受けている。(長男は忘手直、三男は波木直)
「平貞盛」とは藤原秀郷と共に、「平の将門の乱」の鎮圧平定者である。
大隈国 日向国を713年に4群を割譲して大隈の国を造り、正式に阿多倍の首魁一族に与えた。
4群以外はこれに従わず独立国家を主張720年に征圧した。
「司馬達等」は鞍造部の始祖で、仏教私伝者であり、日本初代の仏師「鞍造部止利」は彼の孫である。伊勢青木氏のステイタスの大日像の生仏像様は「鞍造部止利」作である。
文武天皇期の養老律令(718)は藤原鎌足の子供の不比等が編纂したものがあるが、これは大宝律令の修正版である。
光仁天皇は709-781 位770-781
桓武天皇は737-806 位781-806
嵯峨天皇は786-842 位809-823
「陶部の陶氏」は、後漢の阿多倍の配下で、第1次の後期の陶磁器の技能集団の部の頭領で、室町末期までその勢力は中国全土を占有していた。毛利氏に潰された。村上水軍はその末裔と言われている。
「日本書紀と青木氏」 完
Re: 日本書紀と青木氏 9
副管理人さん 2008/04/24 (木) 16:18
前節と本節には、関連性がある為、前節の内容を念頭に以下をお読み頂きたい。
検証する青木氏に関わる内容は次の通りである。
検証項目
活躍 第1節 「白雉の年号」
活躍 第2節 「伊勢王の薨去」
活躍 第3節 「伊勢国の重要度」
活躍 第4節 「諸国の巡行」
活躍 第5節 「紫の袴着用の許可」(最高位の身分扱い)
活躍 第6節 「天皇の名代」
活躍 第7節 「天武天皇の葬儀」
活躍 第8節 「善行説話の編集」
活躍 第9節 「伊勢行幸」
活躍 第10節 「大隈の首魁(阿多倍)」
本書記録
活躍 第9節 伊勢行幸
”持統3年2月19日 伊勢行幸を決める。”とある。
”中納言三輪朝臣高市麻呂は農時の妨げになると諫言した。”とある。
”持統3年3月6日 再度の諫言に従わず、伊勢に行幸した。”とある
”持統3年3月17日 伊賀伊勢志摩の国造等に冠位を賜り調役を免じた。大赦をされた。行宮造営の者たちに免じた。”とある。
”持統3年5月13日 伊勢神宮の神官が天皇に奏上し、「伊勢の国の今年の調役を免じられましたが、2つの神郡からの納めるべき赤引糸35斤は来年に減らす事にしたいと思います」と言った。”とある。
”持統3年9月21日 班田収授の法の制定で役人長官を伊勢国等の4畿内に遣わした。”とあり、”伊勢の国の嘉采を見て嘉稲2本を立て奉った”とある。
”持統3年12月24日 太夫を遣わして、新羅からの調(税)を伊勢、住吉(すみのえ)、紀伊、大和に立て奉った。”とある。
検証
伊勢の国の事に付いて記録されている内容であるが、ここで違和感を感じる。
と言うのは、先ず、記録3月6日までの3つの記録である。
”何故、中納言が行幸に反対した事をわざわざ記録したのか”。(疑問1)
何事に付いても、反対はあるものである。天皇が行動すると言う事は官僚が計画し段取りをする。当然、検討段階では問題もあろうが、内部の問題であり、その内部の検討段階のそれを記録として遺したのは普通ではない。
普通は、編年体であるから、結果を書く事になるだろう。しかし、舎人親王は結果に対して、その結果の深意やその背景をそれとなしに書き足すと言う手法を執っている事は前記でも彼の得意技として論じた。
今回は、この「検討段階の内部事情」を書いたのは何故か。(疑問1-1)
わざわざ、2度も諫言していることを記録している。記録は一度で良い筈である。
それには、先ず、次の事から研ぎ解す。
「持統天皇の反論理由」
天皇家の守護神のある伊勢の国に天皇が行くことが、何が問題なのか。(疑問1-2)
問題として、”農事の妨げになる”とあるが、別に伊勢神宮に行くのである。今までもあり問題はない筈である。
まして。天智天皇が建立して定め、天武天皇が斎王、斎宮や三種の神器(鏡)などの祭祀を正式にシステムを作り定めたものである。その場所に”行くな”と言う方がおかしい。むしろ、”行け”であろう。
それも「注意程度」のものであるなら未だしも「2度の諫言」である。
「農時」と言っても、天皇が「農時」をするのではない。邪魔といっても伊勢路せいぜい1-2日で通り神宮に参詣するのである。
「梅雨の農時」を言うのであれば、「春畑の農時」、「夏の取入れの農時」、冬の「仕度の農時」がある。この程度の理屈を言い立てれば”行けない”となり理屈が成り立たない。
そもそも、伊勢の国に伊勢神宮を定めたのである。この時点からこの事は承知の事実である。
まして、「壬申の乱」で伊勢に集結して大儀を立てた土地ではないか。天武死後の混乱後の”けじめ”として、”行く”が正しい事であろう。
これが持統天皇の反論になるだろう。
そこで、次の事が考えられる。
1 中納言が何故「諫言」したのか。
2 舎人親王が何故この事を意図的に「記述記録」したのか。
3 持統天皇は「伊勢行幸」を何故強行したか。
4 何があったのか。
そこで、これ等を導き出すために、舎人親王の事だからどこかに得意技があると見られるので、この前後の1年間記録を調査すると次の記録が出て来る。
”持統3年6月9日 諸国の長吏(このかみのつかさ)遣わして、名のある山や河に祈祷を捧げさした。”とある。
”持統3年6月11日 畿内に太夫を遣わして、雨乞いをした。”とある。
”持統3年7月11日 使者を遣わして、広瀬と竜田とを祭らせた。”とある。
”持統3年9月9日 班田収受の役の太夫の長官(ただまいのまえつきみ)らを四畿内(よつのうちつくに)に遣わした。”とある。
”持統4年3月17日 詔して、全国に桑、カラムシ、梨、栗、青菜などの草木を勧めて、植えさせた。五穀の助けの為にした。”とある。
”持統4年4月17日 太夫を遣わして、全国諸社に詣でて、雨乞いをした。
”持統4年4月17日 使者を遣わして広瀬大忌神と竜田風神とを祭らせた。”とある。
”持統5年4月13日 使者を遣わして、広瀬大忌神と竜田風神とを祭らせた”とある。
”持統5年7月14日 使者を遣わして、広瀬大忌神と竜田風神とを祭らせた”とある。
記録では、” 持統3年5月15日から4年4月17日までの1年間で、農作業の免除や録や食封などの勲功賞として民臣に与えたのが7回記録されている。特に顕著である。”(詳細割愛)
4月17日以後は全く状況が変わって、免除的な関係記録的なものはない。概ね、一年間の全記録数は140件程度であるが、この中の記録である。
この1年間で盛んに与えている。論功行賞は毎年年賀と祭祀と祝事にまとめて行う程度であるが、この様な盛んな行動は他に記録はない。
それどころではない。
”伊勢北部伊賀地方、伊勢南部志摩地方と南北を割譲して功労者に与えた。”(第10節)
「伊勢王」の伊勢国を次から次へと、3割譲してしまったのである。
この意味するところは推して知るべしである。
先ずは、以上8つ記録から明確に見えてくるものがある。
この1年は大水飢饉(渇水、旱魃)であった事。(概ね2年間続く)
この1年に、特別に通称(租庸調)の年貢に関わる免疫追封の勲功賞を散在している事。
天領地の伊勢3割譲(伊勢、伊賀、志摩)が起こっている事。
舎人親王の得意技(間接表現:8記録配置)を駆使している事。
班田法で問題が各地畿内で起こっている事。
この事柄を考え合わすと、疑問1-2の答えでは次の事が言える。
持統3年から5年に掛けて著しい水飢饉が起こり、田畑の収穫は激減し、大飢饉となりながらも、逆に民臣に勲功賞を散在し、大判振る舞いをしたお陰で、朝廷の大蔵と天皇家の内蔵は火の車と成った。まして、大盤振る舞い最たるものは、「天領地」の伊勢をも割譲してしまった事である。間違いなく収穫激減である。「伊勢王」の伊勢松阪付近のみと成ったのであるから当然である。
そこに、全国各地とりわけ畿内では班田法施行の不満(参考)が勃発した。
この様な事であろう事が観えて来る。
つまり、答えは大旱魃が起こったのである。
持統天皇の政治に対する配慮が欠けていたことを記録として直接表現できないので、舎人親王は周囲に記録として18箇所(10+8)を配置し、「伊勢行幸」のところで主表現に違和感を持たせて、それとなしに、連想させる手法に出た。
上記1−4に付いては、
1番目の中納言の諫言理由は、即ち、「伊勢割譲不満と水飢饉と政情不安」である。
2番目の舎人親王の意図は、即ち、「直接表現の回避」である。
4番目の”何があったのか”は、即ち、「水大飢饉と政情不安」と成る。
以上の説明が付く。
しかし、問題は、3番目の持統天皇の「伊勢行幸の強行」である。
1、2、4のある事は雨乞いなどもあり充分に知っていた筈である。にも拘らず、3番目の強行をしたのは、「持統天皇の反論理由]であろう。
特にその中でも、「けじめ」ではないか。そして、自らが、守護神の伊勢神宮に「雨乞いと、政情不満の解消の神仏加護」を祈願するデモンストレーションを実行したとすれば、納得できる。
実は、記録を遡り、この様な事が無いか調べた。そうすると出てきた。そして、上記の説が当っている事が判る。
天武期の経緯は概ね次の通りである。
天武期4年の1月頃から旱魃が始まり、制定したばかりの伊勢神宮に斎王を行かせて祈りをさせたが、旱魃は続き、5年の9月頃にやや納まり、再び、6年の5月頃まで続いている。そして、この時4年、初めて、風の神を祭る事ととして竜田に社を建立し、広瀬には忌神を祭る事として社を建立した。ところが、全く効果は無く、全国的に凶作で民は飢えた。そして、国司は天皇に現状を訴え救いの対応を願い出たが受け入れられなかった。
それどころか、山の木々草木を切ることを禁じて、保水と保湿の対応と、竜田の風神と広瀬の大忌神に祈った。神頼みだけである。
結局は大旱魃となり、民は飢えてしまった。半年後に一時雨は降ったが、解決には至ら無かった。1年半の天武期の大旱魃であった。
以上の記録が出て来た。
天武期では、事態を明確に集中的に時系列に記録しているし、天武天皇の対応のまずさと無策までを暗に非難して記録している。
ところが、持統期では、この様な事は一言も記録で触れていない。
同じ事が起こっているにも拘らず、片方は書かないのは不思議である。
それは、舎人親王は編集上、「政情と財政」が揺らぐ位の救済の対応をした持統天皇に対する配慮を示したのである。
これは上記の通り「政情不安」の中で、そこまでした女性天皇の持統に対する「配慮、思いやり」があって、故意的に直接的に触れずに、舎人親王の得意技を遣って状況説明をしたと観られる。
これで、疑問1-1は解けて、疑問1-2と合わせて疑問1のこの証明が付く。
その得意技を記録から調べると次の様に成る。
それが舎人親王の得意技(配慮)であり、次の各処から抜粋した時系列記録である。
”天武期2年4月14日 大来皇女を伊勢神宮の斎王にするために、先ず泊瀬の斎宮にお住まわせになった。ここで先ず体を潔めて神に使えるところである。”とある。
”天武期4年1月1日 大来皇女は泊瀬の斎宮から伊勢神宮に移られた。”とある。
”天武期4年2月13日 十市皇女、阿閉皇女は伊勢神宮に詣でられた。”とある。
”天武期4年4月10日 美濃王と佐伯連広足を遣わして「神風」を竜田の立野に新たに建立して祭らせた”とある。
”天武期4年4月10日 間人連大蓋と大山中曽根連韓犬を遣わして大忌神を広瀬の川原に新たに建立して祭らせた。”とある。
”天武期5年4月4日 竜田の風神と広瀬の大忌神を祭った。”とある。
”天武期5年5月7日 下野の国司から国内の百姓は凶作の為に飢えて子を売ろうとする者があります”と訴えた。とあり、”天皇は許されなかった。”とある。
”勅して、南渕山と細川山の草木を切る事を禁ずる。又畿内の山野の元からの禁制の所は勝手な切り焼く事をしては成らぬ。”とある。
”天武期5年6月 大旱魃があった 各地に使いを出し、神々に祈った。雨が降らず五穀は実らず百姓は飢えた。”とある。
”天武期5年7月16日 竜田の風神と広瀬の大忌神を祭った。”とある。
”天武期5年9月 雨あり、旱魃は雨乞いの祈りは無くやや解決した。”とある。
”天武期6年5月 又、旱魃があり京や畿内で雨乞いをした。”とある。
兎にも角にも、これだけを各処に配置して状況を演出している。最早、これでは編年体ではない。明らかに「編年体小説」と言うものである。
更に、舎人親王の記録表現の最たるものは、上記の神宮の「神官の申し出の記録表現」であり、これにもその事が良く出ている。
持統3年3月17日から12月24日までの4つの記録からも、そのための対策を実行している。
それは次の通りである。
朝廷に納められた新羅からの「調」税を、この伊勢にわざわざ移して与えて減免量分を補充している事や、”伊勢国(畿内4域に)に嘉采を見て嘉稲2本を立て奉った”とした「新良種の稲」を与えて「収穫量の増大」を賄って不満を押さえている。
この「新良種の稲」の記録は、次の記録がある。
”天武8年12月2日 嘉稲が現れた。それを称えて、関係した親王、諸王、諸臣、百官の人々に禄物を賜り、罪人の大恩赦をした。”とある。
恩赦するほどの良品種であったことが覗える。それを育て、「伊勢国」に与えたのである。
持統天皇は諫言理由の処置は、上記の事で出来ると観て、”ケジメとデモンストレーション”を専制的に強行したのである。
持統天皇の判断は、「衆生の論」に左右されない主長たる積分域(伊勢青木氏家訓3 苦しい時の明断)の判断である。正しい判断であったと考えられる。
それも然る事ながら、言い換えれば、又、舎人親王の各所に表現記録している「持統天皇の人物像」の「見識眼」も大したものである。
舎人親王は、皇子たちから信頼され、慕われ天皇に推されるに価する相当な人物であったことが覗える。
この記録は信頼に値する。
但し、上記の疑問1が解け判った以上、いよいよ本題の伊勢のことである。
ここで見逃して成らない事がある。
「伊勢国3割譲」と「伊勢王の努力」である。
持統天皇が採った「伊勢国3割譲」は、無二の朋輩しての「伊勢王」に対する裏切りではないか。つまり、「努力貢献」に対する無視である。
この「無視」は末裔の我等青木氏の者でも今でも、”ムカ”とする。
単純な「無視」ではない。それは、これが為に、「青木氏衰退」の”きっかけ”が出来て始まるのである。
つまり、持統天皇のこの事件の「専制的強行」は大きな犠牲の上に成り立ったのである。
今までの最大の朋輩で、「兄妹」に対して、「後ろ足で砂を蹴る」が如きである。
それに付いて次に論じる。
第1節から8節まで「伊勢王」は朝政務に誰よりも貢献して来た。本書に記録されていて出て来る人物の最高功労者である。身分も第6位皇子でありながらも、他の皇子より爵位上位でもある位に貢献してきた。8節までで説明は不要であろう。
しかし、朋輩「伊勢王」没後(689)には、この持統天皇の後期では、伊勢の国は3分割割譲されてしまった。
これではたまったものではない。末裔青木氏は一度に勢力を衰退させただろう。恐らくはこの段階では近江青木氏も衰退の傾向があったであろう。
第1期の皇親政治は、「伊勢王」や大津皇子の薨去後、必然的に持統天皇の独壇場となり、「皇親政治」の本筋は次第に変化して行ったのである。この一つの現われとして、本節の伊勢行幸問題が位置付けられるのである。単純に「伊勢行幸」だけではない。
敢えて、「専制的強行」と記したのは、大津皇子と伊勢王薨去後、舎人親王の心の中に、「皇親政治」から「専制政治」況や「院政政治」へ移行の「寂しい気持」があったから、多くのスペースを採り記録を多くしたのであろう事が観える。
この後も、「持統天皇」は草壁皇子の子供の文武天皇に譲位したが、この文武天皇の時も、「太上天皇」(皇太后)として「大宝律令」の制定に大きく関与したのである。
所謂、第1期の「皇親政治」から「院政政治」への始まりである。
「持統天皇」後も「太上天皇」と呼称した事がその専制の決定的証拠である。
しかし、一面、心情的には、必然的に生まれる「流」で、この事(専制、院政)は止む無き事かなとも咀嚼される。(第8節記述)
当然、伊勢国はこの強い「院政政治」の影響を受ける事に成ったとしても不思議ではない。
その仕打ちは、国の割譲の問題だけではないのである。
この「割譲を受けた氏」(阿多倍一族)にも影響を受けて、実は伊勢青木氏には大きな衰退問題が潜んでいたのである。
この一族と青木氏は相対の関係にあった。
(その内容は続いて、次の第10節で詳しく記述する。)
持統天皇が慌てた真因は、この「班田収受法」の施行にあった。人、時、場から観て拙い時に施工したものである。
その法の中の問題としては、「6歳6年」である。
班田収受法とは、戸籍に基づいて、6年毎(班年。籍年の翌年)6才以上の班田農民に口分田を支給し(6年1班:2反)、死亡後国家に収納する土地制度の仕組みである。
蘇我氏の横暴を防ぐ為に、大化改新を実行しその反省から採った公地公民の制で、土地人を国に帰し、その仕組みの一つとして、施行したもので、6才と言う幼児の年齢から土地を貸し与えて、その税の負担を課した。それを6年というサイクルで早くし税の収納を大きくした。
班田法の不満とは、これ等の「重税と飢饉」に対する不満が合致膨張して人心は大きく離れていった。この時、畿内の中、伊勢は最も割譲、重税、水飢饉、衰退、専制で苦しんだ事になる。
この時、「伊勢王」を始祖とする青木氏一族は不満の中、衰退の方向に傾く(桓武期まで)のである。
参考
文武天皇の第6位皇子も美濃王として青木氏を遺す。
次は、活躍 第10節 「大隈の首魁(阿多倍)」である。
以下をお読み頂きたい。
Re: 日本書紀と青木氏 8
副管理人さん 2008/04/24 (木) 11:30
前節と本節には、関連性がある為、前節の内容を念頭に以下をお読み頂きたい。
検証する青木氏に関わる内容は次の通りである。
検証項目
活躍 第1節 「白雉の年号」
活躍 第2節 「伊勢王の薨去」
活躍 第3節 「伊勢国の重要度」
活躍 第4節 「諸国の巡行」
活躍 第5節 「紫の袴着用の許可」(最高位の身分扱い)
活躍 第6節 「天皇の名代」
活躍 第7節 「天武天皇の葬儀」
活躍 第8節 「善行説話の編集」
活躍 第9節 「伊勢行幸」
活躍 第10節 「大隈の首魁(阿多倍)」
本書記録
活躍 第8節 「善行説話の編集」
”天武没3年6月2日 施基皇子と他朝臣、連、忌寸、宿禰等の豪族6人に撰善言司(よきことえらぶつかさ)を命じられた。”とある。
検証
施基皇子はここでは、全国から善行の言伝えや話を集めて、それを民に示して、模範のマニアルとしたものである事が考えられる。しかし、良く調べてみると律令制定に繋がっている事が判る。
これを施基皇子をその長に命じられたものである。
この時代には、本書の記録から世情の一番騒がしいものとして、朝鮮半島北部と新羅、百済からの帰化人[難民)が大量に難民として上陸して来たことである。そして、朝政はこの取り扱いに懸命に活動している。
各地の未開の土地に配置しているし、騒乱状態でその長を呼びつけて沈静を命じたり、罰したりしている。これは本レポートの目的ではないので記述しないが、その記録は30箇所位ではないかと思われる。
例えば、”百済の使者が貢物と調を朝廷に納める為に、新羅の者と同行して大和に来るが、新羅の者は百済の使者を捉えて牢に入れて御調の物を盗り挙げてしまう。何とか百済の者は逃れて大和の国にたどり着き入る。百済の使者は、新羅が裏切った事を述べる。朝廷は新羅に使いを出した。言い逃れして裏切った事を朝廷の調査使者は察した。
そして、新羅との争いで難民が生まれた。これが日本書紀に出て来る記録の一つである。
この様な経緯の中で、難民が入り治安状態が悪化し、犯罪が各地で頻発して、特に大和古来の軌範の崩れが起こっていたのである。
そこで、上節で記した様に、施基皇子(伊勢王)は天皇に命じられて各地で活動して得た経験、その土地の話、逸話、物語、掟事に明るい事を買われてのことであろう。
それを取りまとめて軌範を作ろうとしたのである。そして、この帰化人、難民などの世情の乱れを正そうとしたのである。
丁度、施基皇子没(689年)前1年前の事である。
妃は出来る限りその彼の知識を遺させて向後に役立てようとしたと思われる。草壁皇子とのいざこざが取り沙汰されている時期でもある。
この時期に、全国を長期に度々飛び回って治めてきている人物は少ないので、伝達手段のない時期としては大変に貴重な知識であったであろう。
ところが、また、この時期は上節でも書いたように、新羅以外にも、後漢、百済の他民族が大量に上陸して来て、当時の慣習等が上手く護られなかった時期でもある。当然、他民族との揉め事が起こる等して、必然的に全体の軌範意識が薄く成っていたところでもあろう。
これ等の帰化人、難民たちに依って未開発地域がどんどん開発されて行く。帰化人の持ち込んだ技能を得て生活レベルが向上し豊かになる。全国は伊勢王の努力の検地などで少し治まったが、依然として、反面、犯罪が増えてきて、朝廷は頭を悩ませていた時期でもある。記録では罰則の変更を何度もしている。
本書記録では新羅、百済の難民などに褒めたり罰したりしている記録が頻繁に出て来る。
しかし、ここで、何故か、同時期に帰化してきている後漢の阿多倍が引き連れて来た技能帰化人が呼び出されての処罰はない。むしろ、下記するが、褒められていて大隈と伊勢半国を与えられて居るくらいである。(下節に記述)
この様な騒がしい状態であり、このために民に対して、その行いの模範とするところを示して、その軌範の基準を作ろうと考えたのであろう。つまり、律と令の法の基本形を整えて作ったのである。
そこで、この時期の律令の状況はどうであったのか検証するとこの説話の目的がわかる筈である。
律令制度は桓武天皇期(800年頃)に完成したが、100年掛けてこの原型から本格的な法が出来た事に成る。
その意味からして、持統の妃は、人、時、場処では、適時適切に指揮したと考えられる。日本最初の「検地」を実行し、又、坂東までを概ね「征圧」して治安を治し、朝廷内務をこなし、これまた、法体系の基礎のその大事な一翼を、我等青木氏の始祖は担った事に成る。
それには施基皇子が適材であり、その補助人も臣連など全国の国司を勤めた人物である。
つまり、妃は施基皇子に最後の仕上げの仕事をさせようとしたのであろう。
つまり、妃はなんとなく朋輩で功労者の施基皇子の健康状態を慮っていたと観られる一行である。
別面では、編成者舎人親王はこの状況を経験しているので知っている筈であるから、検証すると判る。
舎人親王はわざわざこの事の記録を後で編集時に組み入れたのではと考えられる。
舎人親王は、全巻をよく観ると編年体であるが故に、この様な手法を各所に多く取り入れている。
詩人でもあり、学者でもあり、温厚実直な性格でもあり、よく争い毎を嫌う人物であったと他書では記録されている。必然的に詩の如く、本書の状況表現する手法も同じであろう。
事実、上記にも記した各所で遣っている。それ故に、この本書を検証する際は、この点を配慮して注意して検証すると隠していたものが見えてくるのである。実に配慮の行き届いた書と思える。
この時、舎人親王は、妃の優しさ、施基皇子の実績の評価、施基皇子の状況、その時代の環境、等を実に上手く隠して間接的に表現している事が読み取れる。
当時は、字を読める人口は限られていて、尚且つ、漢文で編年体である。物語のように状況を表現する事は、記述(物語)体と違って、漢文に含まれる深意を表現するには難しい。そこで、採った手法が詩文などに観られる間接記述表現であろう。そのための深い配慮から間違いもしたと観られる。
日本書紀はこの様なことを念頭に置いて観ると筋書きが読めてくるのである。
確かに、豊富な情報がこの治安悪化の時期に必要であったが、”この任務を伊勢王(施基皇子)に与えたのか”という疑問もあり、他にも理由があると見たのである。余りにもタイミングが合い過ぎいている。
そこで、次の説を採っている。
持統天皇(妃)は「伊勢王」に対して、この「軌範つくり」を与えて、草壁皇子から遠避ける工夫をした事も合わせて考えている。
其の侭であれば、伊勢に返せばよい筈である。返せば大津皇子事件と同じく勅命が出る。
(大津皇子も避けて近江にいた。)
妃(持統天皇)は自分の側に置いて見守ることを選んだのである。2度と同じ失敗を繰り返さないように、兄妹として保護したのであろう。
1年後の689年に薨去するのであれば、「伊勢王」の姿を常に見て来た妃としては、この時点では何とか荒立てずに是非守りたかったのではないか。
何はともあれ、妃の配慮により、「伊勢王」は律令体制の基盤となる基準つくりに晩年貢献した事に成る。
しかし、この後、天皇となり、悲しきかな「戦友」とも言うべき「全ての朋輩」を失う持統天皇は、「太上天皇」とも成って、院政を敷き専制的な方向に進むのである。
しかしながら、よく調べてみると、この史料を基にして、現実に、持統天皇は「飛鳥浄御原令」(689年)の民法、行政、訴訟、その他の規定(制令)を制定(未完説あり)した。
この「飛鳥浄御原令」は未完成であり、その内容は法令と言う形までなっていないとされる説がある。これが通説と成っている。
この時の施基皇子らが「撰善言司」(よきことえらぶつかさ)でまとめ挙げたものである。
そのまとめたものが4つに区分けした一種の「令集」(令解集 基本集)とも言うべきものであった。
つまり、検証の答えは、「令解集」であり、この時の事(「撰善言司」)を記録しているものである。
この構想は「伊勢王」が各地に飛び回っている時(681-682年頃 第4節記述)より天武の指示で「原稿集め」を行い始まり、688−689年に責任者として妃から最終の取りまとめを命じられた行ったものである。
この事から、「令」と言うべきは「令集」と見なされて、「未完集」の説が生まれている。
更に調べると、施基皇子の作った「令解集」それを基本として編集した本格的な「大宝律令」(701年)を、持統天皇は「思い出多き令解集」を「自分の手で完成」を目指して、この後、「草壁皇子」の息子の「文武天皇」に譲位しながらも、この時代に、「院政」を敷きながらも完成させたものなのである。院政はこの為なのである。
況や、思い出多き朋輩等の「人生の集大成」の完成を目指した事が第1−9節からの記録で読み取れる。そして、時代は進み「大宝律令」は、更に見直されて、次の「養老律令」と成るのである。
「令解集」即ち、「「飛鳥浄御原令」は「大宝律令」へ「養老律令」への「見直しの史実」から証明されるのである。
この行の記録を入れる事により、舎人親王は後勘に委ねた「思い」として、この事を読み取ってもらいたかったのではなかろうか。
「令解集」の内容そのものの記録であれば、その内容を続けて記録するであろう。しかし、この記録以上の事は全く記録されていない。
「本書前後の記録」から見て、わざわざ、舎人親王は、「伊勢王(施基皇子)と持統天皇」の「8年間の人生苦労」を、「伊勢王薨去1年前の朝務の司」を記録として編入したのであろう。
特記
史料によると、舎人親王は、一時その人柄と有能さから政務(皇太子役)に押されたが、固持し本書の編集記録のみに専念したとある。確かに政治の場面では出てこない。
それだけに「記録の羅列」だけに人生をかける事はこの人物にして無く、本書にかける親王の「心意気」が見える。本書の持つ意味はこの一点に有り、この「政務(皇太子役)に押されたが、固持」の一行を放念してはならない事であると考える。
本書の記録もほぼ終わりに近い巻末に来ているところで、編集して締めくくったのである。
次は、活躍 第9節 「伊勢行幸」である。
> Re: 日本書紀と青木氏 7
> 副管理人さん 2008/04/24 (木) 11:21
> 前節と本節には、関連性がある為、前節の内容を念頭に以下をお読み頂きたい。
Re: 日本書紀と青木氏 7
副管理人さん 2008/04/24 (木) 11:21
前節と本節には、関連性がある為、前節の内容を念頭に以下をお読み頂きたい。
検証する青木氏に関わる内容は次の通りである。
検証項目
活躍 第1節 「白雉の年号」
活躍 第2節 「伊勢王の薨去」
活躍 第3節 「伊勢国の重要度」
活躍 第4節 「諸国の巡行」
活躍 第5節 「紫の袴着用の許可」(最高位の身分扱い)
活躍 第6節 「天皇の名代」
活躍 第7節 「天武天皇の葬儀」
活躍 第8節 「善行説話の編集」
活躍 第9節 「伊勢行幸」
活躍 第10節 「大隈の首魁(阿多倍)」
本書記録
活躍 第7節 「天武天皇の葬儀」
”天武没年10月22日 皇太子は公家百官と諸国の国司、国造を率いて大内陵の築造に着手した。”とある。
”天武没2年8月11日 浄大1位の「伊勢王」に命じて、葬儀の事を取り計らうように命じた。”とある。
検証
着工1年後の喪(2年喪中)に服した後、天武陵の完成(天武没年12月22日に着手)を見て、山陵に埋葬の正式な葬儀を行う事を、天皇は敢えて「伊勢王」に命じたのである。
この事はこの意味では終わらないのである。
本来は、この行為の責任者は皇太子の草壁皇子が執り行うものである。しかし、伊勢の守護で第6位皇子「伊勢王」なのである。
「天武天皇葬儀」と言う最も形式の慣習を重視する儀式の域をはるかに飛び越えている。
この事に付いて、草壁皇子には、絶えられないことであろう。
この「葬儀の件」、「大津皇子の事件」も含めて、「即位」出来なかった事、「爵位」が「伊勢王」や高市皇子よりも低い事、などを含めて、葬儀の事でも物語る様に、何か「人間的な欠陥」があったのではないかとも思える。これだけ立場の無い事は普通では、考えられない。
兎も角、この儀式は天武天皇の崩御の2年後の事である。
”崩御後に密葬して、天皇陵を造って埋葬の儀式をする。”とするが、本書記録では喪中を実行する為の肝心な「密葬の正式葬儀」は無かったのである。
この事を知りながら、大津皇子のこともあり、草壁皇子の猜疑心を考えると、かなり重大な危険性を持った任務を「伊勢王」は取り計らう事になったのである。
この時は、未だ草壁皇子は健在である。難しい仕事である。
実は、天武天皇崩御から10月まで草壁皇子は御陵の造営の指揮を取っている。
ところが、翌年の8月には、最後の仕上げの儀式では、「伊勢王」である。
つまり、草壁皇子にしてみれば、”下準備の工事は自分で本式の自分の親の葬儀は違う”では、納得しないであろう。本来はこの逆であるべき話である。
ここでも、違和感を感じる。
依然、草壁皇子が皇太子である以上、勅書で起した「大津皇子の謀反」の事件を再び起こす事の可能性の少ない「伊勢王」に決めたのであろう。
更に、次の事が記録から観察される。
持統天皇は、高市の皇子に対して、草壁皇子の死後に、身分、勲功、爵位、最高位官職、褒章、労い等の不思議なくらいに様々な持ち上げをしている事もある。
又、他の天武の皇子が無くて、後に、持統天皇は舎人親王一人だけを爵位(昇格)を授けている事もある。考えられない事でもない。
大津皇子は天武天皇発病から政務代行をして来た。そのために草壁皇子に猜疑されて一命を落としたが、この事で同じ事が起こっては拙い。そこで、前節からも「伊勢王」の有能さから見れば、政務代行は適切な登用で無難であろうが選択はしなかった。
しかし、”崩御後に「密葬」して、「天皇陵」を造って「埋葬儀式」をする。”の3つのことに付いて、「伊勢王」に全て指名実行しなかった。「天皇陵」は草壁皇子に、「埋葬儀式」は伊勢王にし、「密葬」は指名せず実行しなかった。
その理由は次の事ではないかと思われる。
1 天智天皇が定めたばかりの皇位継承順位第4位(継承者が無い場合第5位)と定めた事を覆すは法の尊厳から天皇の信頼を失う。
2 高市皇子、大津皇子等の天武天皇の上位皇子が居る。幾ら天武天皇の子供扱いとして可愛がられ信頼されていたとしても、この順位を狂わす事は大きな争い事を招く。
3 皇太子草壁皇子を覆す為の理由(上記)を天下にあから様に出来ない。より無難で身分、実力、年齢、何れの条件を以ってしても、草壁皇子より優れているし、問題は無いと見たので、誰しもが必然的に2人の一人を選ぶ手段でもある。
ここを境に、事前相談していた母親の妃は、草壁皇子を天皇にしない事を決断したのではないかと思われる。
そこで、決断した以上、草壁皇子は感情を高めているので危ない。
その時、葬儀責任者は、高市皇子にするか、「伊勢王」かの問題が出る。
「伊勢王」に指名したのは、上記の検証の第3番目の理由からであろう。
以上で、天武、持統天皇の二人は、相談の結果、政治、経済、軍事に長けて総合的力量を持つ「伊勢王」を選ばず、この選択肢(密葬、天皇陵、埋葬儀式の3つの行事)を全て「伊勢王」に任する事は、崩れたと観られる。軍事に長けた高市皇子も草壁の皇子の猜疑心の配慮から失う事を配慮して選択しなかった。
草壁皇子の天皇陵、「伊勢王」の埋葬儀式、とし、高市皇子を二人の「抑え」として、万全を期したのであろう。
そして、この3つの選択肢の行動で、間接的に、草壁皇子の即位は無い事を暗に諭したと観られる。
相談していたとするその証拠に、舎人の親王は次の事を3箇所に書き添えている。
それは、持統妃は大変に利発で政治性を持った女性であったのである。
直接の輔弼の記録である。
”天武元年6月 兵に命じて味方を集めさせ、天皇と謀を練られた。”とあり、又”妃は勇者数万に命じて要害を固めさせた。”とある。
”天武2年 始終、天武天皇を補助し、助けて天下を安定させた。常に、良き助言者であった。政治の面でも積極的に輔弼の任をはたした。”とある。
”朱鳥元年9月9日 天武天皇崩御以後、皇后即位式もせずに、大津皇子の代行まで、自らが政務を執った。”とある。
これは、舎人親王の追記の得意技でもあり、特別にこの事を3度もわざわざと書き込んだ事で、妃が朝政務に積極的に関与していた事を明らかにしているのである。それも、目立つように、女性が軍に命令を発したと書いて故意に際立たせたのである。普通は書かないであろう。
余りにも有能な「伊勢王」を政務代行に、そして次の皇位継承候補に選ばなかったのは、天武、持統の二人は綿密に相談した事から、上記の理由が出て実行しなかったのであろう。
舎人親王はこの記録でそれを強く故意的に物語させたのである。
この事から、即位に付いても、草壁皇子、高市皇子、大津皇子、伊勢王の4人の扱い方を、病気治療期間中の2年間の間には、相談していた事が充分に覗える
更に、次の事が記録から観察される。
持統天皇は、高市の皇子に対して、草壁皇子の死後に、身分、勲功、爵位、最高位官職、褒章、労い等の不思議なくらいに様々な持ち上げをしている事もある。
又、他の天武の皇子が無くて、後に、持統天皇は舎人親王一人だけを爵位(昇格)を授けている事もある。考えられない事でもない。
大津皇子は天武天皇発病から政務代行をして来た。そのために草壁皇子に猜疑されて一命を落としたが、前節からも「伊勢王」の有能さから見れば、政務代行は適切な登用であろう。
相談の結果、計算が合わなくなったのは、「大津皇子事件」であろう。それで、”妃は狼狽した。そこで、暫く、妃自らが朝政務を執り、その間、じっくりと周囲の様子を見てどうするかを考えた。その結論は、自分が皇后となり、周囲の目から観て実子草壁皇子を廃嫡し、天皇に即位し、高市皇子を太政大臣にし、伊勢王の皇子を実務補佐として人心を納めた。”となるであろう。
しかし、兎も角、誰も「伊勢王」の研究している者が居ないのでこの疑問を抱かなかったと思われる。又、舎人親王の詩文体形式の得意技で検証を試みなかったからに過ぎないと考えられる。
詩文体の検証だから出てきたのである。
その持統期以後も、新しい政争の相手が現れたが、後の活躍から立場を保っているし、「伊勢王」の末裔の我々は記録、口伝では厳然とその立場を悪戦苦闘しながら保ち、その後も生きている事からすると、これでよかった事でもあると見ている。
「伊勢王」は、大きい荒波の中で、実力を遺憾なく発揮し、自らその強運を上手く引き寄せて、生き抜いてきた人物であると評価できる。全青木氏始祖として申し分ない人物であり、末裔の者として大いなる誉れである。
「伊勢王」も危ない橋を渡っている。「伊勢王」は成功裏に終わらせている。
そして、その後、この3年後に、「伊勢王」(施基皇子)の記録は出て来ないで、他の記録から689年(6月2日以降薨去の記録を含む全ての活動記録なし)に薨去している。
ところが、同じ689年(天武崩御3年)4月13日に草壁皇子も薨去している。2月前である。
草壁皇子の薨去がそれも突然である。皇太子であり、天武没後の2年間は頻繁活動しているし、記録もされている。しかし、突然に病気でもないのに27歳で薨去している。違和感を感じる。考えられる事は一つである。
第2節でも記述したが、疑問1がある。
本書では天智(中大兄皇子)期には「伊勢王薨去」が2度も出たが、編年体であるので、689年のところ以降では、後の「伊勢王薨去」は出て来ないのである。
50歳を平均寿命とすると、690年代の前後の時期での「伊勢王」は寿命とも考えられるが、草壁皇子の方は27歳で早すぎる。
編者の舎人親王に書き難い何かがあったのか想像する。
書くに充分な立場(天皇に継ぐ浄大1位)の身分である。一つ下の浄広1位と同勲功の高市皇子と天智の兄弟の川島皇子は記録されている。
他の皇子全部と、高位4(5)世王の大半は記録されている。689年の「伊勢王」だけである。
最後に残った高市皇子が太政大臣として政務をとる事になった時代なのであるから、何かあるのではと調べたが、この事(同年死去、記録なし、高市皇子と川島皇子の処遇)から、前後の文章にそれらしき表現がないかを観察してみるが、矢張り記録は全く無い。
「伊勢王」の薨去なしの疑問に対して次の様になる。(第2節記述の追説)
先ず、次の様になる。
上記の一つ目の推理は、再び、本書記録の葬儀の件で、草壁皇子の何かが充分に働いたとも考えられる事。
二つ目の推理は、「第2節の伊勢王の薨去(こうきょ)」の所の「斉明7年の薨去」と「天智7年の薨去」のどちらかの薨去が編集時に間違えたとの推理である。
第2節では二つ目の推理としている。経緯から先ず間違いないことである。
”「斉明7年」は「天武17年」となるのを間違えた。”と推理する。(第2節の説)
天武天皇は668-686 持統天皇は690-697であり、持統天皇は天武没5年後に即位したので、689年は天武期から計算すると、17年後となる。天武没後の4年である。
その一年後に持統天皇は即位している事になるので計算は合う。
編年体で書いているので、舎人親王が故意的に書くことをずらしたが編集(計算間違い)間違いを起した。(編集故意説間違い)
伊勢王薨去が無いが為に、後の時代で書き足し(書き間違い)間違いを起したとも考えられる。
(後刻書き足し間違い説)
この記録の編年体の年号の入れ方を調べると、次の様になる。
「年号」は変化したときだけに「年号」を入れて、後は、「月日」だけである。
天智、天武、持統の3天皇の没後と即位までには年数のズレが有る。
天智と天武では2年間、天武と持統では5年間である。普通は天皇が没すると直ぐ即位である。
この間の期間を計算する事に間違いやすい。
天智、天武、持統元年の正月に年号が入り、その後、年を一度入れて、月日毎に記述されて行く。
この場合だけは、記述部位は、一行で、6月だけで、日はないのである。後全ては、行続きの日の重ね書きである。
全ての場合は月日が書かれているが両方にない。月だけはこの伊勢王の件だけである。
この「伊勢王」の2つの薨去だけに日が無いのは何か違和感を感ずる部位である。
この事からも、考えられる事は、先ずは、舎人親王らの編集時(故意的編集時)の間違い説であろう。
「舎人親王」は676−735年 淳仁天皇の父で、元明朝から聖武朝にかけて活躍した人物である。
日本書紀の編集は720年完成で、「伊勢王」没31年後(持統没23年後)の事である。
間違いを起こす事は充分考えられる。
もし、この推理だと、第1節からの全ての疑問は解消する。
これは、薨去に付いて、本書の大きな疑問1の一点である。
私は、一つ目の推理に付いては、「伊勢王」の失態ではなくて、それ故、編者が最高勲功者の「伊勢王」であるが故に、同月の薨去に対して、「大津皇子事件」の様に、草壁皇子との疑いを抱かれる紛らわしい事を編する事を避けたとも観ているが証拠は無い。
有るとすると、舎人親王の得意とする”記する事をわざわざせずにして、暗示”すると言う事で後勘に問うという思惑もある。だから、先に書いたが、”「斉明7年」は「天武17年」と間違えた。
31年も経っているし、記録人が渡来人で、多数人から成っている。更に、天智から天武即位までが2年のブランク、天武から持統までの即位は5年ブランクである。持統が即位宣言して1年後に即位したブランクなどの間違いやすいこともある。
舎人親王がチェックしているが、編年体で有るから最初に二つの「伊勢王薨去」が記録されていることに気が付きやすい筈である。私は配置は故意的であるが、2つ有るが故に間違えたのであろう。
参考
持統天皇の即位は天武天皇崩御後の4年1月1日 即位
持統1年7月5日 高市皇子は太政大臣に任じられる。
持統2年7月5日 高市皇子に5000戸に加増される。
持統2年7月5日 丹比嶋真人(たじひのしままひと)右大臣になる。 丹治流青木氏の始祖
持統2年1月13日 川島皇子浄大3位に食封(へひと)100戸加増される。(昇格)
持統2年9月4日 川島皇子こう去 近江佐々木氏始祖
持統4年1月2日 高市皇子に浄広1位を授ける。(昇格)
持統6年1月5日 故大津皇子に浄広2位を授けた。(昇格)
持統6年1月5日 舎人皇子に浄広2位の爵位を授けた。(昇格)
持統7年7月10日 高市皇子こう去
持統8年8月1日 文武天皇に譲位
「妥女」とは、大化改新の詔の第4の所に、”郡の少領(すけのみやつこ)以上の者の姉妹子女で、容姿端麗の者を奉れ。従丁1人と従女2人を従わせる。百戸で妥女1人の食料を負担せよ。”とある。つまり地方豪族の子女が人質として朝廷に仕えたのである。
藤原秀郷流青木氏は、この後、直ぐに勢力を高め摂関家として母方で皇族賜姓青木一族と繋がる。(呼称青木氏の許可の根拠)
次ぎ、活躍 第8節 「善行説話の編集」である。
Re: 日本書紀と青木氏 6
副管理人さん 2008/04/24 (木) 11:11
前節と本節には、関連性がある為、前節の内容を念頭に以下をお読み頂きたい。
検証する青木氏に関わる内容は次の通りである。
検証項目
活躍 第1節 「白雉の年号」
活躍 第2節 「伊勢王の薨去」
活躍 第3節 「伊勢国の重要度」
活躍 第4節 「諸国の巡行」
活躍 第5節 「紫の袴着用の許可」(最高位の身分扱い)
活躍 第6節 「天皇の名代」
活躍 第7節 「天武天皇の葬儀」
活躍 第8節 「善行説話の編集」
活躍 第9節 「伊勢行幸」
活躍 第10節 「大隈の首魁(阿多倍)」
活躍 第6節 「天皇の名代」
”朱鳥(あかみどり)元年4月27日 伊勢神宮に多紀皇女、山背姫王、石川夫人を遣わされた。
5月9日 多紀皇女等は伊勢より帰った。”とある。
”朱鳥元年6月16日 「伊勢王」及び官人等を飛鳥寺に遣わして、衆僧に勅して「この頃、わが体が臭くなった。願わくは仏の威光で身体が安らかになりたい。それ故に、僧正、僧都及び衆僧たちよ、仏に祈願して欲しい」と言われ、珍宝を仏に奉られた。”とある。
”天皇の御病平癒の祈願して、朱鳥元年8月15日 施基皇子(しきのみこ)と磯城皇子(しきのみこ)2人に食封200戸を加封された”とある。
検証
この頃、天武天皇は病気である。この年(686)、年号を朱鳥とした。「大化」期から始まった年号は次には「白雉」となり、直に廃止し、天武期の終わりに「朱鳥」の元号とし、又、直に廃止した。
第1節で述べた様に、「即位、瑞祥、災難」で年号を変える慣習であり、この時は災難に当るだろう。そこで、天武天皇が身内の者を遣わして、「伊勢王」の居る伊勢国に、天武天皇が斎宮、斎王を置き正式に定めた伊勢神宮に祈願した。
この節で判る様に、「伊勢王」、「施基皇子」と2月毎に差し向けている。
この平癒祈願の3つの記録に少し違いがある。
1つ目は、「氏神」の「伊勢王」の国許に祈願した。
2つ目は、「伊勢王」を「菩提寺」の飛鳥寺に祈願させた。
3つ目は、「祈願努力」の「施基皇子」に加封した。
1つ目は、名代人物の表現が疑問である。
天皇家祈願実行を受ける「天智天皇」の息子である「伊勢王」の立場と成っているが、本来は、実父(天武天皇)の祈願であり、皇太子があるのだから「伊勢王」ではなく「草壁皇子」であろう。
2つ目と3つ目にも違和感がある。逆の表現の疑問が出る。
2つ目は、本来、寺に遣わすのであるから、その正式な皇子名で「施基皇子」とするべきであろう。
「伊勢王」は役職名である。
3つ目は、その努力は氏神を護る役目として「伊勢王」とするべきであろう。逆ではないか。
1つ目では既に役目柄同行している。これは良いとして、2つ目の「伊勢王」の使い方は、伊勢神宮の「神」の護り役であり、その者が飛鳥の「寺」に行くのはおかしい。
神に仕える者が寺に祈願に行くには、役目を外した施基皇子の名であろう。
3つ目の使い方は、身分柄でなく役目柄に対しての勲功であるから、「伊勢王」である。
さて、この1−3(疑問1)をどう解くべきかである。記録から観てみる。
上記した様に、草壁皇子は天皇崩御後は、活発に没後の祭祀(もがり)を盛んに行っている。
しかし、崩御前は活動はない。崩御後は、草壁皇子薨去までの活動は、3年間で10回(正味2.0年)で、薨去直前1年は祈願を含めて全く無いのである。
そして、天武天皇発病で(胃病:信濃より螻蛄[おけら]という薬)胃薬を取り寄せる。
天武14年9月18日後、崩御(朱鳥元年9月9日)までの一年には、草壁皇子の治癒祈願は全く行っていない。治癒祈願外もない。
崩御したからと言って、突然活発に動いた。この事の持つ意味は何を示すのであろうか。
経緯
1 上記の「伊勢王」の「身分柄」、「役目柄」の使い分の事、
2 病気中の皇太子の「本来役目」に対する活動のない事、
3 崩御後の活動が多い事、
4 皇太子薨去1年前は突然活動はなくなる事、
5 崩御2年は喪に服する当時の慣習(本書に明記)がありながら、活動は「もがり」以外にも活発である事、
6 この皇太子薨去1年前は母親の妃が皇后になり、天皇に成れない事を知った年でもある事。
7 本来、これ等全ては皇太子の草壁皇子が全て行う「仕事柄」であるにも拘らず、周りの者(伊勢王)が行っている事。
8 何を於いても、率先して行わなければ成らない仕事柄である事。
9 民の範たる立場である皇太子である事。
これ等の事(1-9)から考えて推理すると、舎人親王の「得意の手法」であろう。
その推理とは次の事に成ろう。
推理
つまり、崩御前後の本来あるべき皇太子の行動に対して「病的異変」(参考参照)があったと観られ、編集上、舎人親王は記述する事は出来ない。そこで、それを代行する「伊勢王」の行動に、先ず「違和感」の変化を与え、「疑問」を持たせて、本書の天武天皇崩御前後の記述に、皇太子の行動に「目立つ変化」を付けた。そして、皇太子薨去1年前にも政治が動いているにも拘らず、全くで記述しない。これで、”皇太子に何かある”と見せた。
喪の終わった時のこの1年には、妃が皇后になり、天皇に即位すると決意した時である事を明示した。即位決意して1年後に即位した。
そして、編年体の項目に関係ないのに、特別に喪の期間を2年と記述した。
これで、舎人親王はこの間(4年)に起こっている経緯を意を含めて編年体で描く事が出来ると観ていたと考えられる。
何はともあれ、前節までの草壁皇子の疑問の行動の検証部分からも考えて、それまでの舎人親王の得意技から考えても、この疑問もこの様に成るのではないか。
この疑問の答えが正しいとすると、「伊勢王」は、大変な環境に居た事を示すものである。
前節までの「伊勢王」の政治行動は「役目柄」で「身分柄」を演じている事である。
本来、「伊勢王」は伊勢の「守護の役目」で、他の王と同じく伊勢に於いて果たす事が主務であり、「朝政務の役目」ではない事は明らかである。しかし、本書では、他の皇子は全て身分柄で記述されているのである。
既にお気づきと思うが、この「伊勢王」と第6位皇子「施基皇子」の全体の扱いの使分けには疑問はある。この事は「伊勢王」のすば抜けた有能さを持ち得えていた事を本書は示しているのである。
即ち、舎人親王が力を特に入れていた編集処であろう。それ故に、第2節と下節の「伊勢王の薨去問題」でも編集時の配置ミスをしたのではないか。
参考
持統天皇は天智天皇の第2女である。天智天皇(中大兄皇子)の同母(遠智娘:おちのいらつめ)弟である天武天皇(大海人皇子)の妃となり、後に皇后と成った。正式名は高天原広野姫天皇(たかまのはらひろのすめらみこと)。幼名は鵜野讃良皇女(うののさららのひめみこ)、俗称は新田部皇子
叔父の天武天皇との血族結婚による。その子供が草壁皇子である。
当時の皇位の血縁は血族結婚を主体として、純血を守る為に慣習化されていた。その代わり、その為に地方の豪族の娘を妥女(うねめ:宮廷女官:人質:妻の階級外)としてとり子孫を護った。
故に生まれは遅いが、妃の子供であるので皇位第一位皇子で皇太子なのである。
伊勢青木氏の始祖の伊勢王(第6位皇子)は越道君の郎女で妥女である。身分の低い皇子となる。
(天智天武の皇子皇女の系譜レポートを参照)
第3親等までの血縁は障害異児の危険性があり、隔世遺伝による危険もあるので、妥女からの子孫存続を図り、当時は可能な限りに於いて2代毎に新しい血筋を入れている。
持統天皇の孫(草壁皇子と後の女性天皇の元明天皇との子供)が次の天皇に成っている。つまり、文武天皇である。元明天皇は天智天皇の子供。持統天皇とは姉妹で、草壁皇子と叔母と血縁した子供が文武天皇である。
妥女の子の伊勢王、施基皇子の子供が光仁天皇であるが、光仁天皇は大隈首魁阿多倍の孫娘「高野新笠」(帰化人)の血筋を入れている。この後、「高野新笠」を母とする桓武天皇からは律令制度の確立に基づき、法的方針として、血族結婚は藤原氏や、阿多倍らの帰化人などの血筋を入れて避けた。
阿多倍は敏達天皇の曾孫の芽淳王の娘を娶る。(詳細は第10節)
次は、活躍 第7節 「天武天皇の葬儀」である。
Re: 日本書紀と青木氏 5
副管理人さん 2008/04/24 (木) 10:50
前節と本節には、関連性がある為、前節の内容を念頭に以下をお読み頂きたい。
検証する青木氏に関わる内容は次の通りである。
検証項目
活躍 第1節 「白雉の年号」
活躍 第2節 「伊勢王の薨去」
活躍 第3節 「伊勢国の重要度」
活躍 第4節 「諸国の巡行」
活躍 第5節 「紫の袴着用の許可」(最高位の身分扱い)
活躍 第6節 「天皇の名代」
活躍 第7節 「天武天皇の葬儀」
活躍 第8節 「善行説話の編集」
活躍 第9節 「伊勢行幸」
活躍 第10節 「大隈の首魁(阿多倍)」
本書記録
活躍 第5節 「紫の袴着用の許可」(最高位の身分扱い)
”14年12月30日の翌年の1月20日を朱鳥元年とし、その前の1月2日 大極殿で諸王を召して、宴を行い、詔を発した。””王たちに無端事を尋ねる”と言われ、”答を得ると賜物を授ける。”とあり、戯にしてこれまでの勲功に対して2人に論功行賞を行った。
壬申の乱と政務などで天武天皇を助け最も活動した勲功者として、二人に論功行賞をした。
”高市皇子に秦擦の御衣(ハンの木の実で編んだ染め衣)を三揃い、錦の袴を二揃い、絹20匹、糸50斤、綿百斤、布百反を賜った。”とあり、次に、”「伊勢王」も答が当り、黒色の御衣三揃い、紫の袴二揃い、絹7匹、糸20斤、綿40斤、布40反を賜った。”と記録されている。
”14年7月26日 勅して、明位以下進位以上の者の朝廷服の色を定めた。
浄位以上は朱花(はねず)、正位は深紫 直位は浅紫 勤位は深緑 務位は浅緑 追位は深葡萄 進位は浅葡萄 と定めた”とある。
(注 「伊勢王」は「朱花」色である。前節レポートにもあるが、衣は「黒擦」袴は「紫」の最高職を許されている。)
検証
”14年9月24日 天皇は病気に成られた。”とある。”朱鳥元年の9月9日 正宮で崩御した。”とある。
病気に成って、丁度1年後である。多分、信濃から螻蛄の胃薬を取り寄せたとある事から、胃がんで有ったのであろう。死期を悟り、最も、自分の御世に貢献してくれた伊勢王と高市皇子の2人に、特別に感謝を込めて賜物を授けたのであろう事が判る。
それを、感謝だけを以って正式な形としては出来難い事もあり、高市皇子と「伊勢王」の2人に特別に論功行賞の宴を催し行ったのである。50人もの諸王が居るにも拘らず、このたった2人にである。如何にこの二人だけに信頼されていたかが判る。
壬申の乱では殆ど「高市皇子」と「伊勢王」(施基皇子)の働きで天皇に即位できたし、その後の政務の2人の働きは段突である。この節では活躍 第1節−4節のそれをはっきりと記録しているものである。
特に、「伊勢王」の紫の袴は最高位の者(皇太子)が着用を許される色袴である。
高市皇子の錦の袴は天皇以外に着用を許されていないものである。
(平安後期では紫は僧位の最高位の者が許可されて着用を許された。)
そして、「伊勢王」は黒色の御衣の着用を許された。これは、政務官僚の長としての式服である。
皇太子が即位する時に着る冠位束帯の「黒染(くりそめ)御衣の法服」である。つまり、身分は第6位皇子、4位(5位)の王位、浄大3位(この時)であるが、皇太子扱い以上を意味しているのである。
どんな爵位を与えられてもこれ程の名誉は無いし、50人中の皇族の中にはこれ以上の者は他に居ない。
因みに、草壁皇子の皇太子の爵位は浄広1位で1階級下である。それ以上の身分扱いとなる。
(最高位の爵位は明大1位 2位 次は浄位1−4で大広に分ける 全48階級)
この2人は朝廷内外にその最高位の勲功があった事を発表したものである。
その有能さに付いてはこれ以上の説明は必要は無い。
伊勢王は、最終浄大1位に成る。
朝廷服の実務服は壬申の乱の従軍者への取立ての一環で、朝廷に上がる役人として登朝時に着る服でその勲功の印としたのであろう。
身分制度を明確にし、その実力に応じた勲功と身分を与えて、「皇親政治」のピラミッドの基礎が着々と進められていることが判る。
その例として、その朝廷方針として、今後の「律令制定計画」として「官僚体制」を確立する為に、上節記述の様に「官吏」を臣連はもとより、民間からも「優秀な者」の採用を積極的に行っている。
第6位皇子の「伊勢王」や「高市皇子」の二人は、空洞化していた皇太子身分より下でありながらも、爵位と実質身分が「伊勢王」等の方がはるかに高い事でも判る。
この辺に身分は前提になるが、その中でも「実力主義」である事が判断出来る。皇太子より他の皇子らは低い。
実力といえば、施基皇子を始めとして、大津皇子と高市皇子の3人は確別である。
しかし、大津皇子は実質は天皇に代わり政務を取っていたが、余り、彼だけが何故か昇進の記録が少ない(疑問1 上節の草壁皇子の猜疑心から来る反対である。追記)
その後、天武天皇崩御20日後に皇位継承第3位の大津皇子の謀反の事件が発生した。
(持統天皇崩御3年前に大津皇子没後に爵位昇格を与えている)
追記
大津皇子に対しての編者舎人皇子の評価は実に良い。
余談だが、記録から、次のような記録がある。
”朱鳥元年10月3日に、訳語田の舎で死を賜った”とある。
”24歳であった。妃の山辺皇女は髪を乱し、裸足で走り出した。見る者みなすすり泣いた。
”大津皇子は天武天皇の第3位皇子で、威義備わり、言語明朗で、特に、叔父の天智天皇にその才能を認められて可愛がられていた。成長されるに及び有能で才学に富み、特に、文筆を愛された。この頃の詩賦の興隆は大津皇子にある”と本書は記録し断言している。
その証拠に、”この謀反に関連したとされる人物は30余人(皆天武期の大物の朝臣族 僧侶も多く含まれる。)である。罰は軽くした”とある。この記録がある。
又、”伊勢神宮の斎宮の大来皇女が同母弟の大津の謀反で任を解かれて都に帰った”とある。
大津皇子のその身分は皇太子より低い事への不満があり、余り実力の無い皇太子に天武天皇崩御直後に謀反したとも考えられるが、既に没した天武天皇にではない。まだ誰が権威者に成るかわからない時である。
そんな時に謀反するかとの疑問が湧く。有る程度天智天皇の時の壬申の乱のように大友皇子が成ると決まっていて乱が起った事であれば判るが、この場合は、皇太子とは限っていなかった。
この天智天武期は最も純血血縁度の高い者がなる掟であった。従って、天智の時は大海人皇子か大友皇子と成るが、本来は大海人皇子である。兄弟優先と決まっていた。
この場合は天武の皇位継承者は草壁皇子か大津皇子かの問題が出る。
順序では皇太子であるので草壁皇子ともなるが、実務、実力、権威、信頼、経験、性格に関わるであろうから、優先的には大津皇子となる。
大友皇子の時も、この性格人格が左右して、人心がついて行かなかったのである。
しかし、その条件中の性格は、大津皇子は温厚で文学的な素養を持ち人徳ある人物と特筆されていることからも充分である。
事件の記録されている中では、処罰された者の中には高僧も多いのである。これ等の処罰者は全て軽い刑に終わっている。
この大津皇子の事件の真因は、実刑実罪が見つから無かった事から、草壁皇子は他を罰する事に躊躇したのであろう。
この事件からも覗える事であるが、厳しい身分制度を確立しながら、ある身分の範囲では、実力主義であり、つまり、この後で起こった謀反説が、逆にこの時期には実力主義の考え方が常識化していたことを意味する。多分、上記した条件も含めて、時代の混乱期としては、大津皇子への周囲のラブコールが大きく起こっていたのではないか。
そして、そのラブコールをした人物を30人として罰したのであろう。
だから、ラブコールだから、高僧が多かったのではないか。謀反では高僧は入らないであろう。
しかし、狭量で凡庸な猜疑心の強い病的な草壁皇子には、謀反と捉えたのではないか。
だから賢く政治力の持つ母親は、心情的には草壁であろうが、息子に譲位しなかつたのである。
この時代の「皇親政治」が「実力主義」で無かった場合は、この事件は起こらなかったと考えられる。つまり、草壁皇子に政務を執らせ、爵位も高くして今までの「御座成り」の体制を敷いていた場合、「病的な猜疑癖」が頭をもたげなかったとも考えられる。
立場、仕事、身分、能力等何を採っても、本来は皇太子が上である事になる天智期の時代システムが、既に改革させられているのである。
そして、しかし、現実には天武期では「皇太子」と成っている矛盾がある。
「強い猜疑心」が湧くのは草壁皇子ならずとも、「人の性(さが)」から観ても必然とも思える。
同じ「猜疑心」での「大友皇子事件」、つまり「壬申の乱」は相互に「猜疑心」を持った事から起こったのであるから、若干、天皇になる慣習システム(純血順)が異なってはいたが、何れも「猜疑」と言うキーワードでは同じではないか。この乱は条件的なもの、例えば純血、勢力バランス等が均衡していた事で、勅書を相互に出せる立場にあったので、「大津皇子事件」と違い、勅書を遣わずに、「戦い」と言う手段で解決した事に成ろう。
中大兄皇子との「有間皇子事件」は、燻る孝徳天皇派との軋轢が左右した事もあり、「争い」が表沙汰にしなくて、「暗殺」と言う事で解決したが、この事件は「戦い」と「猜疑」との何れもが使えなかった事件ではないだろうか。
この事からすると、3つの要素の「暗殺」「戦い」「猜疑」から逃れられたことになる。
この様に「伊勢王」はあらゆる危機を乗り越え、真に「壬申」ならぬ「人心」に評価されてその幸運に恵まれている事をこの記録は物語る。
現在でも、同じで実力があっても昇進しないということは同じでは無いか。この3つの何れかで昇進しても潰されることが世の常である。
これは真に「伊勢王の人徳」と言うものであろう。
況や、我々青木氏の末裔は、遺伝子的にこの始祖の人徳を引き継いで持っているのである。
参考
爵位の朝廷で着る実務服は、浄位では朱色である。
袴では全体として最高位は錦と紫である。儀式では黒の御衣である。冠では逆である。
「八色の姓の制」の八色とは元は7色の定めであったが八色に変更したがこの色からきている。
真人、朝臣、宿禰、忌寸、道師、臣、連、稲置(684)である。宿禰までが皇族系
紫の色の高位性は、大化3年12月 「7種13階の冠位」を制定した。
第1服の色は冠と揃い深紫 第3は冠は紫、服は浅紫とある。
次は、活躍 第6節 「天皇の名代」である。
Re: 日本書紀と青木氏 4
副管理人さん 2008/04/24 (木) 10:45
前節と本節には、関連性がある為、前節の内容を念頭に以下をお読み頂きたい。
検証する青木氏に関わる内容は次の通りである。
検証項目
活躍 第1節 「白雉の年号」
活躍 第2節 「伊勢王の薨去」
活躍 第3節 「伊勢国の重要度」
活躍 第4節 「諸国の巡行」
活躍 第5節 「紫の袴着用の許可」(最高位の身分扱い)
活躍 第6節 「天皇の名代」
活躍 第7節 「天武天皇の葬儀」
活躍 第8節 「善行説話の編集」
活躍 第9節 「伊勢行幸」
活躍 第10節 「大隈の首魁(阿多倍)」
本書記録
活躍 第4節 「諸国の巡行」
”天武12年12月13日 諸王5位の「伊勢王」を始めとして、大錦下羽田公八国、小錦下多臣品治、小錦下中臣連大嶋と官僚の判官、録史、行匠等を遣わして全国を巡行し諸国の境界を区分させた。”とある。”期日通りに出来なかったと報告した。”とある。
又、”天武13年10月3日 「伊勢王」等を全国に遣わして、諸国の境界を正式に定めさせた”とある。
”天武13年 詔を発し、「伊賀、伊勢、美濃、尾張」の4国は、今後、調ある年は役を免除し、役ある年には調を免除せよ”とある。
(伊勢伊賀北部を含む伊勢の国には後に不入不倫の権を与えた)
”天武14年10月17日 「伊勢王」を始めとして、諸臣を東国に向かわせ、衣袴を賜った”とある。
東国の各地で揉め事が多発した様子で、これを治めに出向いた。特に、境界による戦いであろうと考えられる。
”天武14年1月2日 爵位を改めた。施基皇子、川島皇子、忍壁皇子等に浄大三位を授け、諸王、諸臣に爵位を授けた。”とある。
(後に、伊勢王は皇子では段突の皇位の爵位の浄大1位に昇進している)
検証
活動 第3節で検証した通り、乱後の平定を狙っての全国的な行動である。
最初の12月の仕事は1年掛かりである。大仕事である。
助手の公、臣、連の高位3人と、事務処理官、記録史、測量士のスタッフを連れての仕事である。
これには、ただ測量だけではすまない。検地と言っても(表の目的とは別に)裏の目的は燻る全国を治めに出かけたと云う事であろう。
本来の目的は境界を決めることではある。現代でも尽く揉める事が当り前である。相当な政治的な能力がなければ、俗人には出来ない。戦いも争いもあったであろう。
案の定、”命じられた日時で出来なかった”と報告しているのが何よりの証拠である。
しかし、10ヶ月後に完成していて、再び正式決定の巡行に出たのである。
終わったと思う間もなく、今度は4国の問題に関わっている。この4国は自分の国(伊勢)を含む上位王の国である。つまり、揉め事の東国の処理後、次は逆に、安定化の為の防備で身内の処理である。主要天領地である。
天領地の豊かさを確保する為には、免税処理をして安定化を図ったのである。そして、経済的だけではなく、政治、軍事的な処理も「伊勢王」は行ったのである。記録されている通り「伊勢国東付近の不可侵の詔」を与えて護ったのである。
つまり、不満の強い坂東の第7世族(ひら族)から4国との西境界域を経済、政治、軍事で強くし、バリヤーを築いた事になる。
同様に、関西以西の勢力には、どの様な「バリヤー」が敷かれていたのか疑問1である。
(第10節で詳しく朝廷の姿勢を述べる。)
しかし、それでも、揉め事は起こったので、沈静化させるために、再び2年後に出向いたのである。
この仕事は大変な仕事であるので、天皇は「伊勢王」にその労を労って「衣袴」を送ったのである。
普通、出かける時には、物は送らない。帰ってからの事である筈。
それだけに、”本当に申し訳ない”と労う天皇の気持ちが伝わる。それを表現する舎人親王の配慮も覗える。
そして、爵位を挙げて「伊勢王」に天皇に次ぐくらいの「権威」をつけて「交渉の特使」として送る段取りをしたのである。そして、納まったのである。
”納まった”と云う事は、政治的に「天武天皇期の権威」が定まったことを意味し、それは合わせて天武期の「皇親政治」の基盤を確立した事を物語る。即ち、天皇の権威を護る仕事をしたと言うことである。これだけのことを任される人物は天皇の周りには少ない。
軍事や事務に強い高市や大津の皇子でも出来ると云う事ではない。全ての能力が備わっての事である。この事からも、天皇から信頼されるほどに「伊勢王」の有能さそのものである事が言える。
しかし、ここで見落としては成らない大事なことがある。
居並ぶ50人の諸王が居る中で、順位は第6位皇子で第4位王(5位)で有りながら、まして、皇太子を差し置いて天皇に匹敵する立場と身分(浄大1位:最終皇子最高位)を確保するに至り、諸臣からも信頼も厚い。実績も挙げた。申し分のない環境である。後は、ここまでの者であれば、世の常、二つの事が起こる。
一つは人の「ねたみ」である。二つは「慢心」である。この結果、大抵の者は身を持ち崩すのである。
”この事はどうであったのか。”と言う疑問2が湧く。
これ以後の日本書紀の記録記述を注意しながら読み、舎人親王の記述表現にも現れていないかを観察するが、不思議に出て来ないのである。
むしろ、益々であり、最後には、「有終の美」を飾っている。
この事に付いて、「伊勢王」の努力もあったであろうが、「大津皇子謀反」が起こった事により、反省し自らを誡めたものでなかろうか。(成行きは後節記述)
「伊勢王」がこの様な事に巻き込まれなかった理由(反省)として大津皇子事件を更に検証して見る。そうする事で伊勢王の環境がより理解できるだろう。
伊勢王を検証するための大津皇子事件
”朱鳥元年9月24日 もがりの宮を南庭に建て、天武天皇の喪がりをした。大津の皇子が皇太子に謀反を企てた。”とある。
大津皇子の件も、その命令を出した主役は、妃の後の持統天皇か、草壁の皇太子かは本書では記録していない。
しかし、前後の関係から執務を取っていた大津の皇子に対して頼んだ妃が行うのは疑問がある。
まして、妃が「壬申の乱」(後節記述)で高市皇子と大津皇子と共に戦い、危ない橋を渡ってきて、尚且つ、自分に代わって天武天皇崩御の直前まで政務を執ったのである。人の道や義理人情に於いて朋輩に成し得ない事である。
ところが、記録をよく観察すると、反面、事件後の皇太子の行動の記録は一度に出てきて頻繁に行動して活発である。この活発な行動は奇異である事から、皇太子の命令で有ろう。
天武天皇崩御後の”朱鳥元年9月9日 皇后(妃)は崩御の式も出来ずに”と記録している事から、皇太子が実行したと見られる。崩御から20日経ってからの事件である。
その経緯は、次の通りとなろう。
”天武天皇が崩御して、次は自分がなるものだと思い込んだ。ところが、自分ではない事が判ってきた(後節記述)。そこで、これは実務をしている「大津皇子の反対」に合っているものと思い込み、今の中なら手を打てると見て、皇太子命(勅書を出せる)で実行した。”となるのが世の常であろう。
実際、政務を執り行う大津皇子に対して、本来は自分(草壁)が取るべき立場にありながらも、皇太子草壁皇子の凡庸さの所以から、「ねたみ、そねみ」から嫌疑を掛けたのではないか。
というのも、本来は自分が執務を執り、そして、天皇になる筈でありながら、この時、妃(持統天皇)が成ったのである。
草壁皇子は年齢的(24-5)にも充分である。しかし、この時、成れなかったのは、この辺の皇太子草壁皇子の「人徳の不足」(病癖 後節記述)から来たものではないかと考えられる。
現実に、史実は皇后(持統天皇)で、次は「文武天皇」に譲位と続き、皇太子草壁皇子は遂には天皇に即位出来なかった。病気で無いのに突然、27歳で薨去している。
”天武没3年4月13日 皇太子草壁皇子が薨去した。”とある。
病気であれば、盛んに草壁皇子の行動を記録していて、渦中の人物であるから、舎人親王であれば、病気と書くが、前後に関係する何も記録なし。これもおかしい。舎人親王の得意技であろう。
(後述)
”普通であれば書くが、それを書かないで、想像させる。”と言う手法である。
ここで、更に追求して、推測だが、草壁皇子に即位させなかったのは、一体誰なのかと言う疑問3である。検証して見る。
即位に反対できる次の有力者は4人であろう。反対する条件は次の様になる。
1番目は、最有力は母親の妃(持統天皇)である。
2番目は、大津皇子 皇位第2位、出生順3位 実力2位 人徳1位 政務担当 壬申の乱功労者2位
3番目は、高市皇子 皇位第8位、出生順2位 実力1位 人徳3位 軍事担当 壬申の乱功労者1位
4番目は、「伊勢王」(施基皇子 天智)第6位 出生順1位 実力3位 人徳2位 実務担当。壬申の乱功労者3位
5番目は、舎人皇子 皇位第3位、出生順7位、実力4位 人徳4位 編集担当 壬申の乱功労者0位
長皇子は4位、出生順5位、弓削皇子は5位、出生順6位 壬申の乱功労者
(人徳は本書の中での記録、活躍、爵位、勲功、昇進の度合いを参考にした)
これらの2人物は、皇位第4、5位は順位はあるが、発言するに必要とする「実力」がない。
継承の「順位」と「実力」と固有の「人徳」の3つの条件が備わっていなければ継承者が多ければなれない。
条件の順位はこの時期では、「実力」で「皇位」で「人徳」となろう。この条件に無関係の人は妃(持統天皇)がある。
(舎人親王はその実力と人望は抜群でその声が出たが、断わり編集に専念した記録経緯がある。)
さて、ここで、草壁皇子から4人に対して「猜疑心」を抱かれるトップは、母親を例外として、矢張り、全ての条件で大津皇子となろう。余りに条件的に整いすぎている大津皇子が居る為に、草壁皇子は高市皇子にしろ施基皇子にしろ、先ず即位はないと見ていたであろう。そして、母親への猜疑は本能的に出なかったのではないか。
しかし、結論として、即位に反対したのは、無条件の母親であろう。(後述)
その証拠的記録がある。
何故ならば、天武天皇崩御後、暫く(5年間)は葬儀、即位を実行しなかった事。
次に、本書では、”壬申の乱から、妃は天皇に対して政務に対して助言をよくする積極的な人柄であった”。と記録されている。
別のところでは、”朱鳥元年9月9日より、2年を経て、立って妃から皇后となられた。皇后は始終天皇を助けて天下を安定させ、常によき助言者で、政治の面でも輔弼の任を果たされた。崩御後、5年間政務を自ら積極的に執った。”とある。
更に、”「2年後に」”、”「妃から皇后」”になって、”「更に1年後に」”、草壁皇子は”「薨去」”している。(689天武没3年後)
本書記録とこの4つの意味は何を示すのであろうか。
明らかに一つの経緯の推理が生まれる。
天武天皇没(686)後、大津事件(上記経緯)があった。即位の問題が出た。妃は悩んだ。暫く考える時間(1年:687)を執った。周囲の様子を見る事にした。しかし、矢張り決断した。自分(妃)が朝政務を執った(1年:688)。兄の「伊勢王」(高市皇子にも)に補佐を頼んだ。皇后になる必要がある。天武天皇の葬儀をした(688)、皇后で即位を決意(689)した。しかし、1年間は即位しなかった。この時、皇太子は自分が即位出来ない事を知った。意気消沈、大津皇子への懺悔、周囲の目から心の病、翌年(689)死亡(27)、兄の「伊勢王」も没(689)、補佐なくした皇后は翌年即位(690)。高市皇子太政大臣(693)。故大津皇子の嫌疑回復(爵位昇格:695)。持統崩御(697)
上記した事件の経緯と合わせて、この推理は、皇后の性格人柄から明らかであろう。
本書の記録もこの編のところを暗示させる為に、突然に行間の経緯から離れて、舎人親王はわざわざ記述したのであろう。
草壁皇子の人間を見て母親は長く悩み決断したと考えられる。
草壁皇子の取り巻きを本書の中で調べたが、はっきりしない。むしろ、大津皇子に関わったとする30人の高官は天武期の高官である。唆されたとする傾向はない。
この事から、草壁皇子の人間性から猜疑心を起し焦って皇太子の権限で実行してしまった。
(この時期、皇太子までは「詔書:天皇」「勅書:皇太子」を出せる仕来りであった)
焦った母親の皇后は、草壁皇子を押さえて暫く天皇を置かずに居たと考えられる。
そして、落ち着いたところで、後に、故大津皇子の嫌疑を回復する爵位の昇進を決めている事でもこれを証明する。
ただ、疑問4なのは、上記の天武期の3羽烏の一人高市皇子の動向である。
この事件を押さえることが出来る実力を持っていた。壬申の乱の功労者である。草壁皇子も一目は置いていた筈である。軍事力、政治力、経済力でも優位であった事から、草壁皇子を押さえ込む事は出来た筈である。
この場合は、中立的に軍を動かすだけの軍事的行動で抑圧して牽制する事で押さえる事は出来る筈であろう。軍事的対立での決着ではなく、「猜疑心」の嫌疑である。
謀反を起すとしたら、「軍事的行動」であろう。記録によると、大津皇子は軍事的行動を起した訳ではないのである。記録には全く無い。その周囲(30人)として挙げている者は僧侶達が多いのである。要するに狭量な嫌疑であり、記録では、ある日、「突然の死」の皇太子命令が下ったのである。
「軍事的行動」とすると事前に知っていた筈だから、その様な事は予期しているから錯乱する事は無い。それだから、大津の后(山辺皇女)は錯乱したのである。又、軍事的でないから、高市皇子や「伊勢王」も助けを出す暇がなかった事が言える。だから記録の通り”周囲の者は涙した”のである。「軍事的行動」であれば、”周囲の者は涙する”は無いだろう。まして、”周囲の者は涙した”は編年体の記録対象では無いだろう。
ここが舎人親王の「詩文的表現力」なのである。この一行を書く事に依って、その「様」を全て表現したのである。
もし、そうでないとしたら、何故、草壁皇子の正当性を表現し記録にしなかったのであろう。
(他説では”自殺”とあるが、本書では”訳語田「おさだ」の舎「いえ」で死を賜った”即ち、”命が伝えられた”とある)
「伊勢王」にしても、17歳年上の叔父であり、実務に長けているし、天智天武期を乗り越えてきて人格的な信頼度が高い。大津皇子との繋がりも高い。実務もし、身分も近いから頻繁に顔を合わしているから事前に説得出来た筈である。
だから、編者舎人親王は、それとなしに、事実を書かずに、大津皇子の性格を故意に書き添えて後勘に委ねたのであろう。
その証拠に持統9年1月5日 持統天皇は事件後9年後に、故大津皇子に浄広1位の爵位を授けている。持統天皇は、自分の子供の皇太子の人徳のなさで起した事件に申し訳ない気持ちを長く持ち続け、持統崩御3年前に嫌疑を回復させたのであろう。(活躍 第5節に記述)
この「故大津皇子の嫌疑回復」は”念願の心のしこり”を解消する為、高市皇子が太政大臣に成って提案し実行したと見られる。
妃である母親は途中(5年と7年計12年間)で、皇太子に問題なければ、譲位する事が充分に出来た筈である。しかし、譲位しなかった。一説では、”直前(1年前)で死んだから”と理由付けしている説もあるが、(持統天皇690年即位に対して草壁皇子689年薨去)天武天皇崩御(686)からの5年間がある。皇太子(27没)23歳で即位は充分である。
「伊勢王」ついては、この事件でも補佐と言う大変な立場にあったし、事態の変化に依っては草壁皇子の病的猜疑心から、場合に依っては嫌疑を掛けられて滅亡に至ったことも考えられる。
結果として、草壁皇子に説得を試みた様子の記録が見当たらないが、幸いしていたとも考えられる。
只、次に、「衣袴の授与」には「衣:つねみごろも」の深意をどう解釈するかである。(疑問5)
(参考の衣袴の解説参照)これを解釈すると、多少の努力はあったことも理解できる。
ともあれ、草壁皇子の性格を見抜いていた行動とも取れる。第一に高市皇子が動かなかった事から見ても、2人は乱の大事になる事を、壬申の乱の後だけに、人心に目を向けて、犠牲を最小限に押さえるために避けたとも考えられる。
壬申の乱の危機の後に、大津の事件の危機である。「伊勢王」は重要な政務と共に、気の休まる暇はなかったと思われる。人心も3度の「天皇家の争い」にはもう目をそむけて離れる事は必定である。
ところが、一難さって又一難である。更に「伊勢王」伊勢青木氏にはすごい試練が未だ待っていたのである。この事件の陰で試練は侵攻していたのである。
今度は、態勢が余りに大きく回避する事は出来なかったのである。(下記の第7節)
参考
天皇の妻 (皇后、后、妃、賓)の4階級と、妥女、女官の階級外で構成、女性天皇には皇后の位が必要。(皇后、妃、夫人、賓:の説もあり)
伊賀国は伊勢の国の分割国で後漢の阿多倍(大隈の首魁)に与えたものであると本書にも記録されている。
皇族賜姓青木氏の5家5流の一つ甲斐は、後の光仁天皇期であるのでやや先であるが、この4つの国には皇子を王として送っている。
信濃国(三野王)であるが、この当時は尾張の一部が開発されていた。
この当時は未だ開発は、現在の信濃までに及んでいなかった。この直ぐ後に後漢の阿多倍が率いる帰化人が入植した。(馬部、磯部等が入植)
大型外来馬を持ち込み牧畜による開発は信濃、甲斐までに及んだと本書に記録されている。
”持統天皇は、天智天皇の第2女で、母は遠智郎娘である。落ち着きのある広い度量の人柄である。”とあり記録されている。 天武天皇の妃になる 天智元年に草壁皇子の母となる。
「衣袴」とは、この字句には意味がある。この「衣」とは「つねみごろも」と読むが、皇位の者が日常に着る衣のことである。”私事(公務外)でも衣が磨り減るほどに頑張って貢献してくれた。”と言う意味があって、又、「袴」とは、今の袴(はかま)の意味ではない。この袴は「法衣」(ほうえ)又は「法服」(ほうふく)と言い、宮中で着る儀式や政務の時の衣服であるが、”政事(公務)でも袴の磨り減るほどに貢献してくれた。”だから、衣袴を与えよう”とする天皇はその意をこめて与えるものである。次の第5節でも、これをはっきりさせる勲功式があった。
次は、活躍 第5節 「紫の袴着用の許可」(最高位の身分扱い)である。
Re: 日本書紀と青木氏 3
副管理人さん 2008/04/24 (木) 10:34
前節と本節には、関連性がある為、前節の内容を念頭に以下をお読み頂きたい。
検証する青木氏に関わる内容は次の通りである。
検証項目
活躍 第1節 「白雉の年号」
活躍 第2節 「伊勢王の薨去」
活躍 第3節 「伊勢国の重要度」
活躍 第4節 「諸国の巡行」
活躍 第5節 「紫の袴着用の許可」(最高位の身分扱い)
活躍 第6節 「天皇の名代」
活躍 第7節 「天武天皇の葬儀」
活躍 第8節 「善行説話の編集」
活躍 第9節 「伊勢行幸」
活躍 第10節 「大隈の首魁(阿多倍)」
本書記録
活躍 第3節 「伊勢国の重要度」
”天智天皇没(壬申の乱) 飛鳥にいる高坂皇子に駅鈴(駅馬の使用許可の公用の鈴:通行手形)の確保の命令を発した。結局、得られなかった。”とある。
”止む無く、大分君恵尺が走り、近江に居る2人の皇子に伊勢に集まるように命令を伝えさせた。”とある。
”(壬申の乱の最中に)大海人皇子(天武天皇)と高市皇子と大津皇子を都の近江からわざわざ呼び寄せて伊勢国に味方の軍を集結させる様にした。”とある。
(軍はその後、)”伊勢の鈴鹿に移動し、伊勢国の伊勢王の代理行政官(国司)の三宅連石床が出迎えて伊勢の入り口を固めさせた。”とある。
(その後、日を置いて)”大海人皇子とその皇子たちと軍は伊勢神宮を遥拝された”とある。
”天武14年7月27日 詔を発して、東山道は美濃以東、東海道(うみつみち)は伊勢以東の諸国の有位の者に課役を免ずる”とある。
検証
この時、伊勢は天智天皇の第6位皇子の伊勢王(施基皇子)が務めていた。当時は30歳程度である。年齢、仕事でも油が乗っている。周囲の信頼も定着している。
従って、本来は天智天皇の子供の大友皇子に味方する筈である。味方になれば勝負は戦わずして尽く。しかし、この伊勢国に大海人皇子(天武天皇)の軍を集結させると云う事は、第6位皇子と第7位皇子の天智天皇の皇子は、初めから大海人皇子に味方する事をはっきりさせていた事になる。
だから、二人の最大の味方が相手側に移った事から、日本書紀に記録されている様に大友皇子の周囲の王や官僚はどんどん離れていったのである。(この様子が詳細に記録されている)
むしろ、「伊勢王」の味方を背景に、皇子等を呼び寄せる時間を保ち、伊勢に集結すると云う事を見せつけて、大友皇子の陣中の分断を図ったと見られる。
それ程に、この「伊勢王」に対する乱の前の諸王公家百官等からの信頼は抜群であったことを意味する。
普通の5位王は赴任地に出向いて務めているが、守護地に代理行政官を置いて伊勢王と近江王は天皇の側で仕事をしている程に信頼をされている。まして、父の天智時代からである。
この乱の後、大海人皇子が即位した後に、この天智天皇の二人(施基皇子と川島皇子)を自分の皇子として扱い、政治面で自分の子供より特別に重用している。(後の節に記述)
しかし、ここで、何故、大友皇子に味方しなかったのか疑問が残る。(疑問1)
その前に、天武天皇の重用の記録の例の一つとして、次の記録がある。
”天武8年5月6日に、天智天皇の子供の皇后と川島皇子と施基皇子の3人と、天武天皇の子供の草壁皇子、大津皇子、高市皇子、忍壁皇子の4人の計7人(皇子12人中)を都に呼んで、母は違うが全て兄弟であるから力合わせて政務に励み忠誠を”とあり誓わせている。
この後、”天武12年2月1日 実際に大津皇子が天皇に代わって朝政の指揮を取る事になった。”
と記録されている。
(しかし、その直ぐ後(4年)の朱鳥元年8月24日(686) 大津皇子は天武天皇死後の半月後に草壁皇子の皇太子に謀反している事に成っている (疑問2 後述)
疑問1に付いて
本来ならば、例え敵にならずとも中立でも排除される筈である。天智天皇が行ったと同じく尽く潰されるのが運命である。この乱の中では、大海人皇子の敵ではないが、疑われて多くの王が抹殺されている。
記録では乱中、”大友皇子は、”中立であっても疑わしきは討て”と直接命令した”とあり、この事が記録されている。どちら側にしても同じであろう。生きるか死ぬかである。
壬申の乱の模様を事細かく記録されている。しかし、あくまでも、大海人皇子(43歳位)側からの記述である。
特に、大友皇子(24歳)が、”中立であっても疑わしきは討て”と言ったとあるが、おかしい。
相手側の事の仔細な発言の内容をどの様にして判ったのか。この件だけではない。近江軍の動きを仔細に記録しているし、描いている内容は、群臣の忠言を無視したとか、近江軍の負けや、失敗や、愚鈍な行動表現ばかりである。、吉野側は良い事ばかりで、勝利表現だけである。
吉野側を身びいきで故意に良く表現している。
例えば、中立を採った実力者の筑紫王(第4位栗隈王)とその子供の二人の王(三野王と武家王)さえも、”疑わしきは”の命令が出ていて、危なかった事が詳細に記録されているくらいである。
これは、大海人皇子の子供舎人皇子が書いた記録である事からも、当然であるが、故意的表現を除けば記録自身は大方は事実であろう。
大海人皇子は吉野から動いて伊勢路を採ったのであるから、伊勢も例外ではなかったと観られ一族が潰されていた事もあった筈である。その証拠に、「伊勢王」の代理行政官の「三宅岩床連」が出迎えている記録で、つまり、事前に味方する事を明確に伝えていた事が判る。
この様に、第1には、皇族賜姓族であっても極めて危ない「人生路を卓越した読み」(青木家の家訓参照)で生き抜いて来た事が判る。
更に、第2には、もう一つの助かりは、大海人皇子の妻(4階級)は殆どが天智天皇の娘である事が左右したのではないか(兄妹)。
特に、「大海人皇子の妃(皇后)(持統天皇)には抜群に信頼」されていたことが記録されている。(後の節で記録記述)
妃等に事前にしっかりと「根回し」をしていたことであろう。この二つの事が一族全体の生残りの結果となったと観られる。
乱前には、大友皇子と伊勢王との兄弟争いは記録されていない。又、叔父の大海人皇子とも特別に仲が良いとかの記録も無い。(後述 信頼で連携)
だとすると、疑問1の答えは上記3つの事であろう。
即ち、「卓越した読み」「抜群に信頼」「根回し」である。(後述でも証明)
「青木家の家訓3」にも記述したが危機は多くあった。、この様に発祥直後にもあったのである。
この事でも「伊勢王」が如何に有能であったかを物語る。
「有能さの証明」はこれだけではない。次々と驚くほどに出て来る。
更に、この事に付いて、以下の検証を進める。
”天武14年7月27日 詔を発して、東山道は美濃以東、東海道(うみつみち)は伊勢以東の諸国の有位の者に課役を免ずる”とある。
この記録に対しては、壬申の乱の後処理の記録で、伊勢王のお膝元の伊勢の処置が記録されている。
伊勢以東の国に免税した事は、壬申の乱(672)で中立を保って平静を維持し、乱は都の範囲での結果となり、最小限の犠牲での戦いで済んだ事と、乱後の平静を維持する事の狙いの2つで、免税したものである。
特に、この地域には大化期から天武期までの改新で発生した新しい皇族第7世族に成った者等を、それまでの都から坂東に追い遣り配置した地域である。
所謂、1150年代までの坂東八平氏(皇族から平になった「ひら族地域」)である。(源の頼朝の後継者に成った「ひら族」である。)
天智、天武が実行した改新の不満を持っている地域である。
ただの地方の豪族ではない。天武に於いては場合に依っては敵側一族でもある。
事と次第では、不満も燻っている地域でもあり、敵側として飛び火するに充分な地域であったのである。
素早く、乱後対策を実行したのである。
実は、これ等の政策を提言したのは、「伊勢王」ではないかという事である。何故ならば、この後、「活躍 第4節 諸国巡行」のところで記録した史実がある。
その史実の一つを述べると、特に、この東国の不安定地域を安定させる為に、検地をした。しかし、その事で後に揉め事の煙が上がった。そこでその煙を消しに回ったのである。一連の仕事をしていたことを意味する。これを実行したのは「伊勢王」である。
この様に、「伊勢王」は一触即発の戦いにもなる難しい問題解決に当り、全国を天皇の名代で指揮官として、飛び回って活躍している。この様な問題解決には、高市皇子、大津皇子やその他の皇子は記録では出て来ない。有ってもせいぜい都範囲の神社仏閣への使い走りである。
この節外にも、文章の主語が「伊勢王」とは成っていないが、主語(高市、大津)の違いがあるが、その記録には確実には「伊勢王」が組み込まれているだろうと観られる内容も沢山ある。
軍事に強い高市皇子、事務に強い大津皇子はこの様な役目を命じられていない。
如何に、「伊勢王」が政治、経済、軍事の3面にその能力が長けていた事を物語る。
ところが、面白い事がある。別述するが、「全国善行話」の収集を命じられている。
これは全国を飛び回っている経験で、よく知っていてをその知識を買われたものであろう。
参考
「ひら族」
第7世族以下の皇族系は大化の改新により天皇が代わる度毎に、”ひら”(下族させる)にして坂東地域に送り、地域の護りとして配置した。この族の呼び名を「ひら族」と呼んだ。
これが350年程度で、坂東には八平氏となった。「坂東八平氏」と呼ばれた。
「たいら族」
これに対して、後漢から帰化した技能集団の首魁が、九州大隈の半国割譲と共に、伊勢の国をも割譲して、伊勢北部伊賀地方に半国を与えられた族がある。首魁阿多倍一族である。この一族は後に、平国香より5代後で太政大臣(清盛)になった「たいら族」(後に伊勢衆)があり、天皇家(敏達天皇の曾孫の芽淳王の娘)との血縁をした。
現代日本の第一次産業の基礎を確立し、中国の進んだ知識を取り入れて律令国家の完成に最も貢献した。軍事、政治、経済に手腕を発揮して、国の国体の様を確立させたその勲功で「たいら族(平氏:京平氏)」と賜姓を受けた。この平氏がある。俗称「京平氏」と言う。坂上、大蔵(永嶋)、内蔵、阿倍氏が主流族である。(第10節記述)
「駅鈴制度」は、大化改新の詔で定められたもので、第2の条に書かれている。
都城(みやこ)を創設して畿内の国司、郡司、関塞(せきそこ)斥候(うかみ)防人駅馬(はいま)伝馬(つたわりうま)を置く。「鈴契(すずしるし)」(駅馬、伝馬を利用する時に使用する鑑札)を造り、地方の区画を概ね定めたもの。
Re: 日本書紀と青木氏 2
副管理人さん 2008/04/24 (木) 10:25
前節と本節には、関連性がある為、前節の内容を念頭に以下をお読み頂きたい。
検証する青木氏に関わる内容は次の通りである。
検証項目
活躍 第1節 「白雉の年号」
活躍 第2節 「伊勢王の薨去」
活躍 第3節 「伊勢国の重要度」
活動 第4節 「諸国の巡行」
活動 第5節 「紫の袴着用の許可」(最高位の身分扱い)
活動 第6節 「天皇の名代」
活動 第7節 「天武天皇の葬儀」
活動 第8節 「善行説話の編集」
活動 第9節 「伊勢行幸」
活動 第10節 「大隈の首魁(阿多倍)」
本書記録
活躍 第2節 「伊勢王の薨去」
斉明7年(660)に”6月 「伊勢王」が薨去した(死去)”と記録されている。
1年後の ”秋7月24日、(斉明)天皇は朝倉宮に崩御する”と記録されている。(661)
ところが、後のページのところには、この年(661:斉明7年)の7年後(668:中大兄皇子即位)に”天智(斉明没)7年6月 「伊勢王」とその弟王とが日をついで薨去(死去)した。”とある。
注意
斉明天皇崩御から7年間中大兄皇子は即位しなかったので、本書では天智7年(天智元年:668)と記録している。
本来の元号方式では、中大兄皇子は天智天皇に成った年は668年であるから、従って、天智4年までである。
斉明天皇崩御から観ると、天智7年である。
検証
この二人の「伊勢王」とは一体誰なのか疑問が湧く。
第1節の「伊勢王」と、第2節の2人の「伊勢王」の3人の「伊勢王」は誰なのか。(疑問1)
第1節での働きがあって、”概ね6−7年後に薨去した。”とあり、更に、7年後に、又、”薨去した。”とある。「伊勢王」が何人もいる訳が無い。
先ず、この大化の改新で定められた「第6位皇子」の臣下方式で考えると「施基皇子」となるが、この人物で検証すると、無理は無い。
大化期の皇子順位の第6位皇子を「伊勢王」(689没)として配置し、臣下させ、賜姓(青木氏)し鞍造部止利の作の大日像を与えたと複数の古書録にある事から、検証すると次の推理が生まれる。
第1節の時の「伊勢王」が天智天皇の子供の「施基皇子」とすると12歳前後である。
第2節の前の「伊勢王」を「施基皇子」とすると17歳である。
第2節の後の「伊勢王」を「施基皇子」とすると24歳である。
「施基皇子」と「伊勢王」は689年(45−46歳)に平均寿命で死去している。天武天皇死後の天武没後3年に死去している。
この後、「伊勢王」は、未だ30回程度は日本書紀にその活躍の内容で記録されているのである。
この活躍具合から観て、天智天皇や天武天皇が常に「伊勢王」を側に置いて補佐させて働いている状況を観ると、身内の子供であり、天武天皇からすると甥であり、同じ天智の子供の大友皇子との皇位争いの「壬申の乱」の時の味方でもある。
天武期に於いてはこの様な補佐をさせられる信用の置ける人物(30歳)は他にない。
この事から、兎も角は年代は別として、経緯から、本節の前者は「施基皇子」であり、後で出て来る「伊勢王」であろう事が判る。
この時代の王の祭祀や儀式には6-10歳程度で補佐役を伴ない出て来る。このことから考えれば第1節の儀式の「伊勢王」は「施基皇子」と考えても問題は無い。現実に中大兄皇子の補佐が明示されている。中大兄皇子が軋轢中の孝徳天皇の子供の「伊勢王」に天皇権威の演出劇の補佐をさせる事は無い。
そうすると689年の死去までこの人物で一貫して考えられる。
現に、”持統天皇に、歳を取っているがと言い、特別に懇願されて、天武天皇の葬儀の指揮を取る様にした。”とする様子の記録は納得できる。持統天皇は天智天皇の子供であり、「伊勢王」(施基皇子)と腹違いの兄妹でほぼ同年2歳下である。
そうすると、疑問が出る。
つまり、疑問2として、この間のこの2つの記録の「伊勢王」は”どのように説けばよいのか”難しい。
ここで、実は、”孝徳天皇の子供(詳細不明)が3人居て、一人が有間皇子であり、更に一人は「伊勢王」に成り、直ぐに孝徳天皇と中大兄皇子との軋轢で、天智天皇により排除された”とする記録(病死)があり、この時は大化のすぐ後の事である。647−648年頃である。
(有間皇子は中大兄皇子の命で、蘇我赤兄により暗殺された。)
中大兄皇子は伊勢神宮を天皇家の守護神として天照大神を定めて祭り、三種の神器を内、「八た鏡」をご神体と定めたが、この初期にこの孝徳天皇の皇子の人物は外されている。
伊勢国に対して「不入不倫の権」を定めた。そして、正式には伊勢神宮は天武天皇が大増築して斎宮を置き、天武元年(実質4年)より正式に祭祀を行い定め徹底した。
この伊勢神宮の記録から、「伊勢王」は孝徳天皇の子供ではない。
伊勢神宮の制定の前の「伊勢王」は孝徳天皇の子供となる。
この経緯論からすると、後者の記録は、孝徳天皇の子供となる。
有間皇子(暗殺)と兄弟二人(病死:暗殺)で3人となり一致する。
この一環の施策の中で、守護神と決めた段階で、天智天皇(中大兄皇子)の子供を、その土地の伊勢国の守護職として、自らの子供の第6位皇子を臣下させて護らせたものである。
この時期に孝徳天皇の子供は外され病死している。(抹殺されたか)
この後、直ぐに第6位皇子に「伊勢王」を任じている。
同時に、大日像のステイタスを与え青木氏を賜姓している。
第7位皇子の川島皇子にも同時に近江王の佐々木氏を賜姓している。
この事からも、前者はこの孝徳天皇の子供の人物ではない事に成る。
固有名詞で「伊勢王」に任じたとする記録は、日本書紀では正式記録されていないので、判断が尽き難い。
何はともあれ、日本書紀に記録される人物である。
真人族や朝臣族程度の者でなくては記録されていないところを観ると、まして、舎人親王が偏纂したのであるから、親の政敵の子供の事であり、大化始めの事の人物をわざわざと記録するかの疑問もある。
日本書紀にはよく出て来る者は19人中の高位王では「伊勢王」と「近江王」と「栗隈王」程度の王だけである。
研究室の「天智天武の皇子皇女の系譜」史料にも記述しているが、天智天武の皇子は合わせて12人で4世王位の者までを入れると日本書紀に書かれている王は19人である。
しかし、特に、その活躍具合を詳細記録されている人物は草壁皇太子と高市皇子と大津皇子と施基皇子(伊勢王)と川島皇子(近江王)と栗隈王(筑紫王)程度である。
この検証から観て、明らかに前者は孝徳天皇の子供の「伊勢王」ではない事に成る。
推理1
孝徳天皇の子供を病死としていたが、第2節の後者は実は病気中であって死んだので、「前」と書かずに記録したとも考えられるが、軋轢の子供を史実として書くほどの話かは問題である。
では、”前の「伊勢王」は誰なのか”と成る。(疑問3)
前の「伊勢王」の第6位皇子はこの時は17歳であるので、平均寿命は当時は45−50程度であった事からすると、充分に補佐役なしで仕事が出来る歳である。
後の「伊勢王」の記録には補佐役は出てこない。
推理2
この時点で、第6位皇子は上記したように第1期の皇親政治で政務官職が忙しく、天皇から都に呼び出しが掛かっている記述が後節に出て来るので、この時「伊勢王」を子供に任したが、この子供が若くして死んだ。”伊勢王にした若い子供の「伊勢王」だから、代理政務官の大物の三宅の連を国司に当てたとも考えられる。
止む無く、続けて死んだので、次に”「伊勢王」は自分がした”とすると、後に10回出て来る事から考えても”2人の子供も死んだ”とすると理屈が合う。
しかし、”続けて死んだ”の根拠はどの史料でもない。
身内の者で政治をリードする体制の「皇親政治」は、この時期から始まったのであるが、この時、呼び出しがあったので、天武天皇期では皇子第6位と第7位の皇子も呼び出しを受けて補佐として活躍している。
普通は大化改新では皇子の第4位(5位)までの者が政治に関わる事を決めたのだが、この二人は特別であった。日本書紀に記録されている天武期では草壁皇太子より働いているのである。
このシステムは「皇親政治」の所以である。
ところが、後での記録で記述するが、疑問の決定的その答えが出て来るのである。
先ずは、その答えから述べる。
答えは、編集ミスである。
”天智7年6月 「伊勢王」とその弟王とが日をついで薨去(死去)した。”
「天智7年」は、「孝徳7年」の間違いである。
つまり、孝徳7年は651年である。
中大兄皇子が実行した645年の大化の改新の政変劇からすると、7年である。
孝徳天皇には、この時二人の皇子(中大兄皇子と争いで有間皇子は既に死亡)が居て、「伊勢王」であったとされ、この二人は”同日病死”と成っている。
651年は第1節で述べた軋轢の政変劇のところである。
この”同日病死”は史料の一説では「暗殺」であったとされている。有間皇子の事から考えれば充分に考えられる。有間皇子を暗殺して残りの皇子を其の侭では理屈は合わない。
経緯
前節のところで記述したが、慎重で、戦略的家であり、センシティブな中大兄皇子は、この650年前後の孝徳天皇との争いで「向後の憂い」を無くす目的から、この孝徳天皇の二人を有間皇子と同じく抹殺したと見られる。
そして、その後に自らの皇子を「伊勢王」にして体制を保ち、第1節の動きと成った。空かさず、その為のデモンストレーションを演じた。と考えられる。
その証拠に、二人、病死、7年、粛清、暗殺、伊勢王、孝徳、年数、年号、月、年齢等の全ての条件に矛盾は無くなり一致する。
では、前の「伊勢王」の薨去は、どの様に理解すれば良いのかという問題に成る。
斉明7年(660)に”6月 「伊勢王」が薨去した(死去)”は次のように成る。
これには大変苦労した。
実は、本書の末の689年頃に「伊勢王」、「施基皇子」、「第6位皇子」、「爵位浄大1位」、「朝臣族」、「伊勢の首魁」等の固有名詞での薨去の事に第一全く放念し気づかなかったのである。
よく調べてみると、15人程度の上位皇子、王位の薨去の記録があるのに、本書で最も活躍した「伊勢王」等の薨去の記録が編年体であるのに無いのである。
そして、この事に気づいて、この第2節のこの二つ目の疑問の解決の為に、調べ直したのである。
その事で長く放置していた疑問が解けたのである。
その答えは、編集ミスである。
つまり、”斉明7年”は”天武17年”である。
天武崩御686年後、4年間は天皇不在で、持統天皇は2年間は喪に服する時を経て、妃から皇后になり、草壁皇子の病変問題、伊勢王の薨去等があり、その1年後にも即位を宣言したが即位しなかつた。4年目の690年でやっと即位したのである。
政治的にも揺れ動いた期間であり、本書記録的にも煩雑を極めている。(後の節で詳しく述べる)
後者の伊勢王は、上記の病死事件の経緯から、孝徳7年(651年)である事に成る。
中大兄皇子の650年ごろからの前節の時系列から観て、651年は納得できる。
天智7年は孝徳7年の編集ミスである。
その間、崩御前「朱鳥」の年号に改元するが直ちに廃号した。
天武期となる期間が690年まで続く事に成る。この辺のややこしい所の編集配置ミスをした事に成る。
崩御で年号を変えるか、即位で年号を変えるかの問題である。
この時は、まだはっきりと定まっていない。
従って、性格に間違いなく言うと、天武没3年後の689年は天武17年(天智没差)となる。
天智没671年で、 天武即位673年で、2年間即位なしがあるので一致する。
斉明7年は、天武17年の「編集間違い」である。
これで「伊勢王」薨去なしの疑問は解決し、本節の2つの「伊勢王」の薨去問題と、3人の「伊勢王」と、第1節の後付の白雉年号の問題も根拠があり全て一致して解決する。
即ち、多すぎる「伊勢王」薨去の記録と、薨去記録なし(後節でも記述)は解決する。
以上、出て来る「伊勢王」はその記録のくだり内容から無理は無い事になる。
第1節の所で、「特記 日本書紀の編成」でも「編集ミス」等のその特長を記述したが、第2節の既に、「編集ミス」もあった。
兎も角も、本節は後の記録の内容でも判断出来る。
この説を詳しく検証した第7節でも「編集間違い説」を記述した。
そこで、次節以降の事前情報として、留意して頂くべき内容を特記する。そうする事でより検証が巾広くご理解いただけると思われる。
特記
本書以降(持統期以降)の内容としての情報である。
光仁天皇までの第6位皇子(青木氏)には多くの子供がいて優秀な人材が多く居た。その一人は桓武天皇の前の光仁天皇である。
大化改新で定めた皇位継承順位では、平安期初期の当時は、即位できる4位(又は5位)までの皇子が少なくて、5人の女性天皇が存在している程である。結局、継承外の子供の多い施基皇子の一族に天皇を当てる以外になかった事を示し、この光仁天皇も第6位皇子(施基皇子)の子供であり天皇にした経緯がある。
この間、草壁皇子の子供(文武天皇)や舎人皇子の子供(淳仁天皇)も短期間の天皇に成っている。
桓武天皇期(781)には第6位皇子の賜姓を嫌って無かった。その代わり、母(高野新笠)方の「阿多倍の一族」の末裔を「たいら族」として、阿多倍の呼称「高尊王」に似せて「高望王:平望王」 を架空設定して伊賀に住む第6位皇子と見せかけて賜姓して引き上げた。
これが5代後の後の清盛の京平氏である。
この経緯からすると、賜姓は「第1の流」を「青木氏」とすると、阿多倍一族の京平氏は「第2の流」であり、「第2の流」は以後興隆を続けるが、この2つの「流」は共に相反する「流の勢い」を持つ。
持統天皇末期から始まり、この時点でも「伊勢王」を始祖とする「第1の流」の5家5流の青木氏は衰退を辿って行ったが、この光仁天皇の孫、つまり、桓武天皇の子供の嵯峨天皇は、前の平城天皇(兄弟)と、この相反する「流」の族に対して反目(政治争い)があった。嵯峨天皇は反対を押し切って皇族賜姓に戻し、問題の多かった天智期からの皇位継承方式を弘仁5年に変更の詔を発している。そして、第6位皇子を源氏と変名した。11家11流続いた。これが「第3の流」である。
これより賜姓の発祥時期から観ると、この第2と第3の二つには約30年の差が有り始まった。
この2つの「流」も当然に、繁栄衰退では共に相反する「流」に成る。
{「第1の流」と「第3の流」とは「同流」の族となる。繁栄衰退は共存の流を持ち、後には、第2の流に対抗する為に、同族血縁し「統一流」となった。
この時、今までの第6位皇子の青木氏の「第1の流」の氏は、皇族の者が下族する際の氏として定めた。これが「第4の流」であり、3家の氏を発祥させた。要するに第1と第3の分流族である。
「第2の流」と「第3の流」の間で、何とか「第1の流」の子孫繁栄は維持できた。
「第3の流」11家11流は、結果的に本流の何れも子孫繁栄を維持する事は出来なかったが、「第1の流」が「統一流」としてこれを保持した。
この様な経緯と関係を持つ「第1−4の流」は、本書では「第1と2の流」の記録と成るが、持統天皇末期から桓武天皇までの間では、伊勢の青木氏は上記の摂理で衰退の一途であった。
しかし、この嵯峨天皇は、桓武天皇の治世を見直した為に、伊勢の青木氏はやや一族は息を吹き返すのである。(後述)
嵯峨天皇の詔ついては、皇位継承は「4位方式」から巾を広げて「4世方式」に変更した。この時、臣下方式は第6位皇子を其の侭にしたのである。青木氏(朝臣族)が還俗下族する時の氏姓として変更し、他の者の使用禁令を同時に発した。これが原則明治初期まで維持された。
参考
「譜搾取偏纂期」(弘仁の詔が護られなかった時期)
第1期の室町末期 第2期の江戸初期 第3期の明治初期では護られなかった
「皇親政治」
第1期の天智天武の皇親政治 第2期の桓武嵯峨期の皇親政治 第3期の醍醐村上期の皇親政治
「還俗、下族」
還俗と下族は皇族の者が皇位より外れ僧となって比叡山や門跡寺院などに入るが、その後、下山して一般の者の俗人となる事を言う。皇族の者の下族は僧にはならず俗人となり氏を立てて一族を構成する事
「嵯峨期以降の青木氏」
詔を発した嵯峨期以降の青木氏が現存するのは3氏のみである。
「嶋左大臣の青木氏」、「多治彦王の丹治流青木氏」、「宿禰橘流の青木氏」であり、全対象者は18人であったのみである。殆どは比叡山の高僧僧侶となり子孫は遺していない。
この他、清和源氏の頼光系の高綱ら3人が日向に配流されて、保護した土地の娘との末裔が、逃亡中朝臣族であるので、青木氏を名乗った記録があり、未勘青木氏として日向青木氏(末裔確認済み)がある。
美濃に伊川津7党の中に青木氏があるが、未勘青木氏と見られる。
「有間皇子」は「中大兄皇子」との皇位争いで命を受けた「蘇我赤兄」が和歌山県海南市藤白の藤白神社近くの熊野古道沿いの所で、白浜温泉から帰りに、後ろから絞殺された。
次は、活躍 第3節 「伊勢国の重要度」である。
日本書紀と青木氏 1
副管理人さん 2008/04/24 (木) 10:08
日本書紀と青木氏
日本書紀には、下記に列記する通り青木氏の始祖の活躍が多く出て来る。
その活躍具合を現して、我等の先祖がどの様に生き有能であったかを検証する。
特に、この日本書紀が編成された時期は、未だ大化期とその直ぐ後の事柄について書かれているので、主に青木氏の始祖の伊勢青木氏と近江佐々木氏の活躍具合が現せる。
今回は伊勢青木氏とする。
以下の項目をで10シリーズに分けてレポートする。
検証する青木氏に関わる内容は次の通りである。
検証項目
活躍 第1節 「白雉の年号」
活躍 第2節 「伊勢王の薨去」
活躍 第3節 「伊勢国の重要度」
活躍 第4節 「諸国の巡行」
活躍 第5節 「紫の袴着用の許可」(最高位の身分扱い)
活躍 第6節 「天皇の名代」
活躍 第7節 「天武天皇の葬儀」
活躍 第8節 「善行説話の編集」
活躍 第9節 「伊勢行幸」
活躍 第10節 「大隈の首魁(阿多倍)」
序として
日本書紀はその時期の出来事を事細かく日記的(編年体)に書きとめているものであるので、その活躍具合を表現するには、全編を見た上で、その[活躍どころ]がどの様なものであったかをまとめて、その行間前後の「活躍姿」を考察して、個々の活躍の「役目柄と背景」を見定める必要がある。
大化改新の詔に依って生まれた(伊勢)青木氏の始祖は、主に「伊勢王」と「施基皇子」(芝基)言う形で出て来る。
従って、その「伊勢王」(30箇所程度)として出てきたところの前後の文章の背景と予備知識(研究室)を考察して纏める事にする。
と言うのは、この日本書紀は天武天皇の皇子の舎人親王らが編集したものであるが、この日本書紀はただの文章と言う事であり、見てもその内容をよく理解できない。
大事なことは、日本書紀が出来た時の政治体制や、その状況や、天皇家の構成や、朝廷の状況や、50人に及ぶ皇子皇女の活躍具合や、身分制度や、公家百官の状況等を把握した上で、その行編を外から見る必要がある。又、舎人親王の人柄とか、書き難い事を間接表現している事もあり、又、後の行間でこっそりと簡潔に記述していることもあり、内側からも見る必要もある。
更には、それでなくては、ただの文章の羅列で何の面白みも生き様も見えて来ないのである。
その史料として、研究室にこの時代の史実をレポートしているので、それを大まかに把握されている事を思い起こして、お読みいただきたい。未だお読みに成っていない方は研究室の右メニューの「おすすめレポート」を参照しながら読まれると、よりご理解が頂けると考える。
「大化改新レポート」「天皇家皇子皇女の系譜」「阿多倍一族の活躍」、「青木氏の綜紋」、「青木氏のステイタスの生仏像様」等、を先にお読み頂きたい。
この時代は、日本の歴史上から観て、例が無く想像を絶する位に、「変化と活動」が大きく、政治、経済、軍事全般に及んで改革が進んでいる社会である。何せ、三権をリードしていた蘇我氏が倒れたあとでもあり、後漢が滅亡して帰化人(17県民)が押し寄せ、進んだ技能を持ち込んで民は潤い始めた時期でもある。高句麗、新羅、百済から政治難民が上陸し、国内で問題を起して騒がしく成っている時期でもある。
従って、当然、民の人心は、下記の「清素仁政」とは裏腹に、百花繚乱ならぬ百花騒乱の如くであっただろう。
以上の事柄を念頭に以下のレポートをお読みください。
活躍 第1節 白雉の年号
本書記録
”白雉元年(650)2月9日に長門国の司の草壁の連の醜経(しこぶ)と言う者が、天皇に珍しい白の雉を献上した。”とある。
”そこで、百済から来ている皇太子の百済君が、天皇に漢の国で白雉が多く出ると大変珍しく吉兆であるとされている”と述べた。”とある。
”周囲の高官が、更に、わが国でも白の鹿や白の雀などが出て大きな休祥(よきさが)で、唐から持ち帰った三本の足を持つ烏(やたがらす)の時もめでたい事だとしています。””まして、白の雉ともなれば、益々祥瑞であります。と述べた。”とある。
”重ねて、天皇の師で国博士の留学僧の「ミン」が、王者の行いが清素で仁政である時に、必ず白の雉が現れます”と述べた。”とある。
その後、”この事を知った天皇は皇太子達を呼び共に、儀式として、公家百官を集めて白の雉を庭に放つ儀式をした。この時、この儀式の為に「伊勢王」と他二人がこの雉の篭を天皇の前に置いた。”とある。
”天皇は過去にもこの吉兆が漢の明帝の時と、国では仁徳天皇の時には竜馬が現れたことが2度程ある。めでたい印であるので、以後、白雉元年と改元する”とあり述べている。
”全国に恩赦を発し、長門の国の連に恩賞を与え、3年間の免税とした。”とある。
検証
年号制定時の朝廷のエピソードである。
この様に、「伊勢王」は儀式のところで白の雉の篭を置いたと書かれている。
この白の雉のことで、「伊勢王」は動いた。
白の雉を「醜経」に命じて天皇に献上さして、それを使って天皇の権威を演出し、国政の道筋を国に示す裏段取りをしたのである。ただ単に、白の雉の篭を天皇の前に置くくらいの事は第6位皇子である「伊勢王」の仕事ではない。他の官僚が充分に行えることである。
しかし、敢えて、「伊勢王」にさせ占めた事には意味がある。
後の記事にも出て来る事であるが、「伊勢王」は「天皇の補佐役」として働き、皇太子などより重く用いているのである。そして、主に、軍略所(天皇の裏仕事を任ずる役)として、天皇の命で問題が起こると全国各地に飛び回っている。
日本書紀には段突に最も多くの場面に出て来る人物である。
むしろ、日本書紀では、天武天皇の死去の葬儀を皇后の持統天皇に、その有能さを認められていて、懇願されて、草壁の皇太子があるにも拘らず、代わって取り仕切っている程にはっきりと明言している。(後節記述)
伊勢青木氏では、先祖伝来の口伝で「軍略所」であったと「口伝」で言伝えられている事でも納得できる。
つまり、この記事は、「醜経」から届けられた珍しい「白の雉」を使って、「伊勢王」は一計を按じて、天皇(斉明の説)の威徳を全国に高める為に演出を計画したものである。
世情には「孝徳天皇」と「中大兄皇子」との軋轢、「有間皇子」(孝徳天皇の子)との軋轢、大化改新の歪み問題などの経緯もあり、又、人心と天皇の権威に不透明部分があった。
ここで、天皇の威徳を高める為に、この「吉兆、休祥、祥瑞」と説得力の持つ人物の各人に述べさせて、お膳立てを行い、儀式を行い、そこで、人心を一新させる為に年号をこの白の雉を使って改元する事の演出の裏仕事をしたのである。
ここで、疑問が湧く。
孝徳天皇死去(654年)時に年号を一時保留(廃止)した経緯がある。
しかし、日本書紀の記録で検証すると、上記のこの辺のところの解決策として改めて演じたのではないかと見られるのである。
その経緯を検証すると、疑問が出て来る。
実は、645−650年の「大化」年号の後、654年から701年まで(47年)年号が無かった事になるのである。
後の、天武天皇崩御の686年の「朱鳥」(あかみどり)の年号は直ぐに廃止された。
この白雉の年号も検証すると、国博士の僧のミンは654年没(653説あり)であるので、この儀式は孝徳天皇の650年とするのか、「大化」を一度廃止した上で、後(654年頃)に、元号の復原儀式を改めて行い「白雉年号」の元号化を図った儀式とも考えられる。
本書記録では何れとも明言していない。
そこで、どちらなのかを観てみる。
孝徳天皇は645年から650年までの大化期の天皇であり、650年から654年までの孝徳天皇の皇位の威厳は中大兄皇子に移り実質無かった。
この時期は中大兄皇子との軋轢がはっきりとして時系列で確認出来る。
2度の遷都劇で既に追い落とされた経緯がある。
遷都劇の時系列 飛鳥宮 650.10 −難波柄豊碕宮 651.12 −飛鳥宮 653.8 −近江大津宮 668
時系列では、故に、650-654年前は孝徳天皇は軋轢と病気と遷都劇から天皇としての権威は全く無かった事になる(疑問1)。
更に、中大兄皇子の子供の「伊勢王」を儀式の中心にするのもおかしい(疑問2)。
既に、日本書紀の記録では白雉の年号に成っている(疑問3)。
又、この儀式は何処で行ったかと言う疑問も出る(疑問4)。
誰も居なかった権威の無い難波ではおかしい(疑問5)。
これ等の疑問1−5を解消するには次の4つの説が考えられる。
この事から、
第1には、大化年号を650年に一度廃止し、数年(4年位)して、再び斉明天皇(654)の天皇の権威を挙げるために、中大兄皇子が「伊勢王」を使って”改元(復元)”劇を演じたとも考えられる。
何故ならば、日本書紀の記録では、この劇の日は既に2月9日以降(650)である。白雉改元から実質3月以上も経っている。年号が始まっているのに、年号儀式はおかしい。(疑問6)
第2には、推測として、天皇が代わる事の度に年号が変わるが、しかし、これ以後、4人の天皇が代わっているが、年号が無い事に対して、後で追記したとも考えられるのではないか。
その為に、後で権威付ける為の僧ミン等の発言を入れたが、日付の矛盾が出た事になる。(654年説では可能)
第3には、653−654年頃にこの儀式を、斉明天皇共に中大兄皇子の元で行い、再び年号を復元儀式をして5年遡ったところを白雉元年としたか、儀式日を5年としたとも考えられる。
この第3の説が、始まったばかりの当時の年号意識からは自然ではないか。そうすると全て疑問(1−6)と矛盾は解決する。
第4には、650年説とすると、軋轢の真最中の時であるし、白雉の演出劇の日の記録がおかしい。(疑問7)
そこで、「軋轢問題」の検証で観てみると、時系列の記録では次の様になる。
650.3月 白雉の儀式
650.4月 造営開始
650.10月 造営中の仮小屋に遷都
651.12月 天皇移動
652.12月 完成
653.8月 飛鳥遷都となる。
これを観ると、儀式の1月後、直ぐに遷都劇の造営を開始している。つまり、権威失墜を開始したとなる。軋轢はその前となる。
650.10月では、中大兄皇子の皇太子が移動している。
650.4月の造営開始とは、本書記録 ”4月には土地、住居、墓の撤去の保障をした”とある。
650.5月には ”将作大匠荒田井直比羅夫(たくみのおおつかさあらたいのあたいひらふ)に境界標を立てさせた”とある。
保障し境界杭を立てた時期である。
従って、この時系列記録では、計画立案はその前に行うので、649.4月頃以前である事になる。
つまり、遷都劇は軋轢真最中の649年の始め頃に、わざわざ、遷都劇の計画で、天皇の権威を下げようとしている時に、”天皇の権威を高めることを「伊勢王」を使ってするか”と言う疑問が出る。(疑問8)
もし、したとすると周囲から”何をやってんだ”となる。慎重で計画的な政治戦略を実行する皇太子中大兄皇子は「伊勢王」にそんなバカな事はさせない。
要するに、自然に失墜したのではない。失墜させたのである。
実は本書記録にその証拠がある。
”皇極4年6月14日 皇極天皇が中大兄皇子に譲位を打診した。中大兄皇子は即答を避けて、中臣鎌足に相談された。 中臣鎌足は、古人皇子は兄上です。軽皇子(孝徳天皇)は叔父上です。古人皇子がお居でになる以上、殿下(中大兄皇子)が行為を継がれた場合、弟が兄に従う人道に背く事に成ります。 暫くは、叔父上を立てられた上で、人心の望みに暫く叶うようにしてはいかがでしょう。とあり、中大兄皇子は大変褒められて、密かに天皇に奏上した。”とある。
ここでキーワードは4つ有る。
舎人親王は敢えて、明らか様に記録しているのである。
”暫く”1は、”叔父上を立てられた上で2”であり、”大変褒められて3”、”密かに天皇に4。”である。
1から4から観て、5年の前から、初めから大儀名文を得る為に譲位前より失墜を決めていた事に成る。
即ち、叔父を立てておいて、後に人心が落ち着いたら、戻す。その戦略が良い事を褒めた。そのため密かに、計画を進めた。と言うことである。 実に戦略的である。
現に、3月後には計画を進めて、古人皇子を先ず打った。
その記録は次の通りである。
”大化元年9月12日(645年皇極4年 多説あり) 古人皇子を謀反の嫌疑で打たせた”とある。
645.6月で失墜計画は始まる。
白雉儀式劇の650.3月では、軋轢のピークとなる。
650.4月の時点で、既に権威は完全失墜している。
公家百官も知っている。改新の実績者は皇太子である。権威どころの話ではない。
この事から、全疑問(1−8)を解決するには、次の筋書きが当然に生まれて来る。
検証筋書き
先ず、権威の失墜した”孝徳天皇の大化は終わったのだ”とし、”斉明天皇の時代(中大兄皇子)の新しい時代が始まるのだ”と宣言する為に、654年にめでたい「白雉年号」を持ち出し演出して「遡り年号」として後に、直に廃止した。そして、軋轢などが国中に伝わっている暗い人心の払拭をも狙ったと考えられる。これが最も有力な説であろう。
この疑問解消説を証明出来る記録を更に次に示す。
年号の疑問解消の有力説の証明
日本書紀には、当時の事情が不明であるので、この様な矛盾が出る事が多いのである。後にも続々と出て来る。
わが国の年号の最初は、「大化」からであるが、「即位や瑞祥と災難」等で一応”改号”される仕組みであった。
従って、年号に対しての考え方は未だ臨機応変に緩やかであった筈である。
大化改新の改革内容を始めとして、自らが天皇に成らず、傀儡天皇の「孝徳天皇」を押し立てて、自らは皇太子(中大兄皇子)として政務を執り行うなど、実に人心に気を配っている。
孝徳天皇の子の有間皇子を暗殺し、そのカモフラージュで孝徳天皇に天皇の座を譲り、自分は蘇我氏の事件では「興国の士」としての立場を保持して、人心の矛先を逸らした位である。
まして、天智天皇の皇位は、23年間の政務の内、最後の3年間だけである事からも、物事にお膳立てをして、期を熟してから実行するなど、実に慎重で戦略的な性格である事が言える事でも本説は頷ける。
又、「孝徳天皇」との軋轢の解決も、突然に都を移し、「孝徳天皇」をそちらに引き込み、又、ある日突然に再び「孝徳天皇」だけを置き去りにし、突然に元に戻り、暫くして遷都とする等の早業を実行して解決している。
白雉の儀式劇程度の本説有力説は納得出来るだろう。
これ等の一連の戦略は天智天皇(中大兄皇子)が自ら描いた筋書きだけではなく、裏で「伊勢王」等が描いた筋書きではと観ている。年号の儀式もこの範疇にあったと観ている。
第一、次の疑問9として、何故に50人もの皇子が居る中で篭を置く仕事を「伊勢王」だけなのか疑問も湧く。
疑問9の検証
それは、15人(19人)もの第4世高位王までの者が赴任地に居ながら、後に第7位皇子の兄弟の近江王の川島皇子と共に、「伊勢王」は都で天皇の下にて働いている。
そして、伊勢国には、代わりの行政官として日本書紀にも出て来る大物の「三宅の連」を国司として派遣しているのである。
この様な背景を下に、前後の歴史的史実を考慮すると、この記事は明らかに、後でも記事を読んでいくと、”白の雉の篭を天皇の前に置いただけの行為”だけでは無い事がよく判る。
つまり、権力闘争の政治性が働いている。
日本書紀のこの前後の行間を読んでいると、大変気を使っていることが判る。つまり、この時期には「人心」が大きく動いていたのではないかと推測できる。
だから、皇子の一人の有能な「伊勢王」を特別に天皇と皇太子(中大兄皇子)の側に置いていたのである。この「伊勢王」には補佐役(三国公麻呂 倉臣小糞)として2人が付いていたと見られる。
実は、この時期の慣習として、「白雉」を使うと云う事は偶然の一致ではなく、一つの「儀式の象徴的物」として捉えているのである。
この記録が他にもあるのである。上記の有力説の証拠でもある。
有力説の証拠
この同じ演出記録がある。
「天武天皇」の即位(668)の”天武元年3月17日にも、この白の雉を備後の国司が亀石郡で捕らえた。”として朝廷に届けている。
そして、”亀石の郡には課役の全免除を与え、全国に大赦令を出した。”と記録されている。
更に、”天武元年4月14日(668) 「大来皇女」に初めて最初に伊勢神宮の斎王を命じた。”とある。
(これが伊勢神宮の正式認定であるが、記録から天武4年が実質であろう。それまで「大来皇女」は泊瀬の斎宮に居た)
「天智天皇(中大兄皇子)」は、伊勢に天皇家の守護神の「伊勢神宮」を建立し、お膝元の伊勢の「伊勢王」に演出させて、人心をここに集めて「伊勢神宮」と「伊勢王」の存在価値をももくろみ演出したものである事が判る。
即ち、全く同じ事を「天武天皇」も行った訳である。
「斎王斎宮の設定」と「白雉の儀式」と「年号の改号と廃止」も、遅れてこの天武14年7月20日に「朱鳥」(あかみどり:686年)と改号した上で、「直に廃止」している事からも証明出来る。
慣例的、且つ、象徴的に用いられた「白雉」の年号の結論は、「中大兄皇子」も「孝徳天皇」没の年(654)の「中大兄皇子」の政権となった斉明天皇の斉明元年(654年)に「白雉儀式」を行った上で、白雉の元号を「直に廃止」したとなる。
つまり、天智天武の2人の天皇には共通する3つの条件、即ち、「伊勢神宮」「白雉の儀式」「年号の改号と廃止」を伴なわせた慣例を造ったと成る。
「伊勢王」
「伊勢王」の働きは、これが本書の記録では最初である。
当時は、寿命が45-50前後と短い。従って、記録によると、社会は6歳頃から一人として扱う時代であった。時代が進み寿命が延びるに従い、10歳、15歳へと変化し、現在では18歳程度に成って社会に出ている。
「伊勢王」(643?-689)も、この時点では補佐が付いていたと見られ10−12歳程度であろうが、記録から実に利発で賢い人物だったと観られる。
「伊勢王」の生誕は不明であるが、皇子皇女の生誕のわかる人物から計算すると、640-645年頃となり天智天皇(626-671)の年齢から当時の可能な範囲では642-644と成ろう。
既に、天智天皇(中大兄皇子)は自分の3人の皇子を朝廷で働かしている事は、この利発と賢さを将来に見込んで鍛えていたと見られる。その一つがこの白雉の年号儀式に中大兄皇子は「伊勢王」を用いたと見られる。
本書編者の舎人親王も、この利発で賢い皇子の「伊勢王」の活躍具合に対して、「畏敬の念」を持っていた事が判る。本書の登場回数とその表現内容でも判る。そのことを念頭に次をお読み頂きたい。
この舎人親王の伊勢王に対する「畏敬の念」は後でも記録されている。
参考
「白雉年号」は一説では650−654年(大化645−650)とされているが、654年以前の5年間も日本書紀の年号から見ると途中から記録上で続いている。
斉明天皇の女性天皇になった時期の654年に廃止してから、天武天皇の朱鳥元年の686年(686年廃止)まで年号は消えたとの説がある。
更に、「朱鳥」の年号も廃止されているから、この説では次の大宝は701−704年であるので、この事から654年から701年までの47年間年号が無かった事になる。
高市皇子は「壬申の乱」の時、19歳で全軍の指揮を執っている事が記録されているので、10歳程度では政務は可能である。大友皇子は太政大臣で24歳であった。
日本書紀の改新詔の第1のところにも、青木氏発祥の概容が書かれている。
本書は賜姓に関しては個別には記述を一切していないが、次ぎの様に記録されている。
”「公地公民の制」に基づき、今までの身分制度を改めて、皇族4位と5位王以上(以前は6世7世王まで)を大夫(まえつきみ)として、人民を統治させる。そして、食封(へひと:戸口による給与)を与える仕組みとする。”とある。(この時期は646-647年頃である)
全体像を見るために、他の史料と合わせると、次ぎの様に表現されている。
”この時(646-647)、この定め(改新の詔)により、第6位皇子(施基皇子)で4(5)位王となり「伊勢王」の「伊勢大夫:(統治者)」と成り、賜姓にて青木氏と仏像を賜った”とある。続いて”川島皇子も例外として5位王として近江の地名より佐々木氏の賜姓を受け「近江王」と成る。”とある。
(これ等の当時の事は、天皇側近として日記を日本書紀より詳しく書き遺し、韓国に持ち帰って遺している最近発見された韓国の「日本世記」にも書かれている。)
「斎王」とは、天皇の皇女が伊勢神宮の祭祀や儀式を執り行う事として、この皇女は永久未婚を通す定めであり、長くこの仕来りは護られた。伊勢青木氏はこれをサポートする役目でもあった。
「斎宮」とは、「斎王」が身を清める所である。
「舎人親王」は676−735年 天武天皇の皇子 淳仁天皇の父 元明朝から聖武朝にかけて活躍 日本書紀の偏纂 文学に秀で先駆的な歌人 性格穏やかで知者 皇子の中でも最右翼の実力者 淳仁天皇733-765 位758-764の親 一時その有能さから天皇に推された経緯事もある。
皇極天皇(斉明天皇)594-661(660) 皇位642-645 皇位654-661(660)
孝徳天皇は597−654年 位645−654年
天智天皇は627−671年 位668-671年である。
天武天皇は630?−686年 位は673−686年
斉明天皇は594−661年 位642−645 665−661
持統天皇は645−702年 位690−697年(太上天皇)
国博士僧みんは654没 653年説もある(632帰国)
施基皇子は643?−689年
草壁皇子は662−689年
高市皇子は653−696
大津皇子は654?−686
考謙天皇は718-770 位749-758
聖武天皇は701-756 位724--749
文武天皇は683-707 位697-707
特記 日本書紀の編成
史料によると、”日本書紀は天武天皇の発意で始まり、元正天皇の時(720年:養老4年:親王は45歳)に編集は終わった。”となる。
本書は漢文で出来ているが、全巻を通して、用語や用字の方法が巻毎と部分的に著しく異なる。これは多数の人が分担し執筆した事によると見られる。これを総裁の舎人親王が自分が観てきた時代の内容をチェックして、編年体での表現方法等の工夫や、非適切な表現等の修正や、文章の配置等の編成をし、編成責任者として1つにまとめ上げたものである。
ところが、31年経過完成という年月から、記録人、時、場処、史料が違う事から、矛盾、間違いが起こっているのである。
初めての大事業であるので、そこまで舎人親王はチェックを成し得なかったのであろう。否定するものではなく理解はできる。
特長として挙げられることは、この記録人の中には、帰化人が多く、史料の間違いを母国から大和を見て書いたそのままを移書きしたものがあり、史料の間違いどころから見て、後漢、百済、新羅の国の帰化人が殆ど多く関わった事が判るのである。この事から来る問題も多く含んでいる。
文章から、諸氏伝、地方伝、個人伝、覚書、中国古籍類などの特長が出ていると言われる程に確かに異なっている。この様なことから、全体として、整理、統一、修正が充分では無かった事が判る。
故に、古事記(712年:和銅5年)は、書き始め(序)で明記している様に、これを見直し編成した史籍であろう。
因みに、古事記の史料では、次のように表現している。
噛み砕いて言うと、”諸々の用いている史料や日本書紀は、経年から見て観察すると、事実と異なり間違いや虚偽や不揃いがあると見られる。現代(和銅)から見てそのミスを改めなければ、何時かはその史実は消滅するだろう。”と記述されている。
ただ、この事を否定要素と捉えて、本書の「日本書紀」の史実を政治目的の為に打ち砕く思惑のあるグループも存在する事も配慮せねばならない。
しかし、確かに疑義や違和感を抱かさせるが、「初めての大事業」の所以であろう事が、文章の前後関係や舎人親王の優秀さや多史料での照合の検証をする事で理解できる。
むしろ、日本書紀は「編年体」であって「記述体」(物語風)の赴きを持ち得ている事(詩文の様に)が判るのである。
つまり、詩文や和歌、連歌、俳句の様に、”想像して疑念を抱かせ、楽しませる”と言う技法を採用しているとも取れる。その方が、検証していると、推理が解けて喜びが湧き楽しいのである。
丁度、試行錯誤してやっと魚が釣れた時のあの感情に似ているのである。
舎人親王は、編成に当って、この技法で故意に後勘に委ねたとも受け取れる。
私は、日本の「詩漢の祖」(詩文興隆の祖)と言われる舎人親王の経歴と巾のあるその有能さを本書の編成に持ち込んでいると考える。
小説でも作文でも、戸籍簿の様に無為ではなく、千差万別の作者の個性が色濃く出るが如く、「日本書紀」も同じではないか。それの方が面白味が出ると言う事で正しいと考えている。元来、本(記紀)の本質は個性=面白味の表現であろう。
「詩漢の祖」(詩文興隆の祖)の舎人親王ならば、”ただ歴史の史実を単純にまとめた”と言う訳では無かろう。ロボットではあるまいし、それならば誰でも出来るだろう。
他書の「日本書紀評価」はこの辺の検証がない。私はかねがね疑問を感じていた。そこで、検証して見ると、案の定、「詩文的表現方法」を駆使して「魚釣りの極意」を披露している。「後勘」に委ねる「楽しみ」即ち「趣心」で編成していると見える。
多くの資料の突合せでは無理であった。その中で舎人親王の史料を見て、ハッと閃いたのである。詩文的に状況や趣を表現している筈だと。そして、再度挑戦し、この手法のお陰で、大分苦労したが長い年月を経て、遂には本書の「伊勢王」の詩文的記録で青木氏の「生様」が観えて来たのである。
特に、次の節の疑問の答えが第1節の証拠とも成り得るのである。
これらの点も留意して、続々と出て来る「伊勢王」の活躍具合を、次からの「伊勢王(青木氏)」の日本書紀の記録検証を、長文ではあるが我慢して是非お読み頂きたいのである。
次は「伊勢王の薨去」と云う項目で青木氏の関わりを記述する。
天智、天武天皇の皇子皇女系譜
副管理人さん 2008/01/03 (木) 19:57
天智天皇、天武天皇の皇子皇女の系譜
皇族賜姓青木氏5家5流24氏の始祖と成り、初代の伊勢青木氏の発祥の環境史料
その始祖となる天智天皇、天武天皇の皇子皇女の血縁一族
この系譜から、多くの史実が読み取れる。特に、当時の「大化改新」の模様の一つが読み取れる。
この系譜から日本書紀を始めとして多くの資料と付き合わせることで、その当時のドラマが見えてくる。
その意味で、この史料を単独に提供する。(研究室レポート中にも記述)
A 中大兄皇子(天智天皇)の子孫
系譜元 妻 娘 子供 順 備考
石川麻呂大臣ー遠智娘 ー大日皇女 1 蘇我氏分家 石川麻呂は大化改新で中臣鎌足の説得を受けて味方となる。 石川麻呂大臣ー遠智娘 ー宇野皇女 2
石川麻呂大臣ー遠智娘 ー建皇子 3 8歳で死亡
石川麻呂大臣ー芽淳娘 ー太田皇女 4
石川麻呂大臣ー芽淳娘 ー沙羅皇女 5
石川麻呂大臣ー姪娘 ー御名部皇女 6
石川麻呂大臣ー姪娘 ー阿倍皇女 7
阿倍倉悌麻呂ー橘娘 ー飛鳥皇女 8 阿倍麻呂は中大兄皇子の補佐役を演じる。阿多倍の裔の阿倍氏
阿倍倉悌麻呂ー橘娘 ー新田部皇女 9 天武天皇の皇后になる。
蘇我赤兄 ー常陸娘 ー山辺皇女 10 中大兄皇子に味方、政敵の有間皇子を熊野古道の藤白で暗殺
地方豪族 ー後宮女官ー 男 2 11 地方豪族の娘 人質奴隷の妥女(女官)4階級の妻外
地方豪族 ー後宮女官 12
地方豪族 ー後宮女官ー 女 2 13
地方豪族 ー後宮女官 14
忍海造小竜 ー色夫古娘ー大江皇女 15 地方豪族の娘 人質奴隷の妥女(女官)4階級の妻外
忍海造小竜 ー色夫古娘ー川島皇子 16 第3皇子 近江王 近江国の佐々木氏を賜姓?ー692没
忍海造小竜 ー色夫古娘ー泉皇女 17
栗隅首徳万 ー黒媛娘 ー水主皇女 18 第5世王
栗隅首徳万 ー黒媛娘 ー ? 19
越道君 ー伊羅都女ー施基皇子 20 越後越前の地方豪族の娘 人質で奴隷の妥女(女官) 4階級の妻外 第2皇子 伊勢王 伊勢国の青木氏
賜姓 ?ー689没
伊賀君 ー宅子娘 ー伊賀皇子 21 地方豪族の娘 人質奴隷の妥女(女官)4階級の妻外 第1皇子 皇位継承者大友皇子 648ー672没
以上 中大兄皇子(天智天皇)の子供である。
大海人皇子(天武天皇)の子供
NO 子供 順位 出生順 備考
1 草壁皇子 1 3 皇太子 668ー689
2 大津皇子 2 2 ? ー684
3 舎人皇子 3 7 日本書紀の偏纂 歌人 多くの皇子に信頼された。
4 長皇子 4 5 ? ー693
5 弓削皇子 5 6 ? ー693
6 新田部皇子 6 8
7 穂積皇子 7 9
8 高市皇子 8 1 653ー696 武勇に優れる
9 忍壁皇子 9 4
10 磯城皇子 10 10
11 大来皇女
12 新田部皇女
13 但馬皇女
14 紀皇女
15 田形皇女
16 十市皇女
17 泊瀬部皇女
18 話基皇女
19 阿閉皇女
以上が大海人皇子(天武天皇)の子孫である。
皇子の各国の守護として確認出来る王
伊勢王、近江王、甲斐王、山部王、石川王、高坂王、雅狭王、美濃王、栗隅王、三野王(信濃王)、武家王
広瀬王、竹田王、桑田王、春日王、(難波王、宮処王、泊瀬王、弥努王) 以上19人/66国
以上が皇子で配置されていた。
注釈
これ等の施基皇子を始めとして皇子と王は「日本書紀」によく出て来る。
皇子順位は直系順位ではなく、天皇家一族の天皇に対して純血順を主とし母身分と合わせて順位を決める。
古人、有馬、軽、大海人、建、伊賀、施基、川島、草壁、...と続き24人等が居たとされるが、大海人皇子を遺し、皇位争いで上位3人と不明2人(孝徳天皇の皇子2人同日病死)と建皇子は病死で19人となり、大海人皇子と伊賀皇子との争いで18人となる。
天智天皇の後は大海人皇子が順位1位であるが、天智天皇は慣例を破り、直系の伊賀皇子(大友皇子)を大海人皇子の了解を得て後継者と定めた。しかし、天智天皇の死後皇位争い(高市皇子が中心になった)が起こる。施基皇子と川島皇子は中間の立場を採った。戦い後、施基皇子と川島皇子が中心になって天武天皇に代わって政務の実務をこなした。天武天皇死後も持統天皇に依頼されて葬儀を含めて皇太子の草壁皇子に代わって政務を代行した。
当時は、天皇家の純血を守る為に、同族血族結婚を主体としていた。
中大兄皇子(天智天皇)の多くの皇女(新田部皇女など)は大海人皇子(天武天皇)の妻となる。
天智天武天皇の不詳不明の皇子皇女をあわせると40人となり、確実な所は34人と言われているが、皇子皇女の不明があるので確認記録は30人である。
中大兄皇子と大海人皇子の皇子達は別々に記しているが、当時は、皇族合わせての皇位順である。
慣例で行くと天智天皇の施基皇子(伊勢青木氏)と川島皇子(近江佐々木氏)は第6位と第7位皇子と成る。
天智天皇はこの時、第4位皇子までを皇位継承権を与え、第4世まで王位を与え、第6位皇子には賜姓して親衛隊の任務を与え臣下させる方式に変更した。第6世以降はひら族にし、坂東に配置した。後の坂東八平氏である。第5位皇子と第5世皇子はその中間として、皇子が少なくなった場合は上位に上がる方式である。
光仁天皇まで女性の天皇が続いて起こるくらいに皇子が少なくなり、光仁天皇は施基皇子の子供である。
(伊勢青木氏の勢力が強くなる。次ぎの桓武天皇はこれを嫌い母方の阿多倍一族のたいら族を賜姓する。5代後の平氏:このため青木氏勢力が低下)
この反省から、嵯峨天皇期(光仁天皇(桓武天皇の子供)の孫から上記の方式を緩めた。
4世を6世に変更した。
第6位皇子の賜姓臣下は継続し、青木氏より再び源氏と変名し同族を強化し平氏に対抗した。
第6位施基皇子(伊勢王 賜姓青木氏)と、特別に、川島皇子の第7位皇子も賜姓(近江王 佐々木氏)を受けた。(施基皇子は芝基皇子 川島皇子は河島皇子とも書く)
この他に、第4(5)世皇子(王)まで(親族の有間皇子、軽皇子、古人皇子等)を加えると50人程度と成る。5世王を入れると65人程度と見られる。
大化の改新の実施理由の一つの皇子皇女への財政的負担が逼迫する程度に内蔵大蔵に大きく担っていたことが確かに明白である。
皇位順は出世順ではなく母の身分(4階級:皇后、后、妃、賓と妥女)と父の皇位順の身分で異なる。皇后、后程度までは身内であり、子供は避けている。
多くは大豪族の大臣や連の娘で妃か賓か妥女からである。近親婚の弊害を避けている。
この時代は妥女が多い。
妥女とは全ての地方豪族から人質をとり、後宮の女官として入り、一種の奴隷扱いである。
当時の皇位は子供ではなく血族結婚である為に血縁純血順の兄弟順の組み合わせとなる。
叔父叔母兄弟と従兄弟の関係は親近婚の血族結婚であるので、判別がつかない。故に上記の皇位順の方式が用いられた。
参考、天武天皇の末の皇子の磯城皇子(しきのみこ)は別人である。
この時代の唯一の史書の日本書紀との組み合わせて検証するとドラマが見えてくる。
「大化改新」のレポートと参照して見るとその活躍が浮き出て来る。
皇子皇女名は地名から来ている故に、その土地の子孫の存在も読み取れる。地方の豪族も判る。
藤原秀郷一門の赴任地と発祥氏と主要五氏の分類
副管理人さん 2007/11/01 (木) 13:34
原秀郷一族の赴任地と発祥氏と主要五氏
藤原北家の鎌足より8代目の秀郷は関東の武蔵の国と下野の国の守護と成ったが、それ以後、朝廷より命じられた赴任地がどの様なところと成って居るか、又、発祥氏がどの様に成っているかを具体的に列記する。
藤原秀郷(元祖)は「藤原秀郷一族とその生き方」で詳細にレポートしたが、彼ら一族は戦略上その勢力を拡大し保つ為に、全ての赴任地に末裔を遺し土地の豪族との発祥氏の血縁族を作った。
当然、この護衛役を全て担った秀郷の第3子千国を始祖とする最古参の藤原秀郷流青木氏も同じ戦略を採った。
この史料から多くの事が読み取れるが、青木氏を理解する上でも、他の同門の末裔一族との大事な資料となる。
そこで、調査資料のその内容を次に纏めた。
順不同(鎌足 初代)
(内容は編集続行中とする)
赴任地 赴任者 注釈
武蔵 秀郷 8代目 平貞盛と「平将門の乱」鎮圧 (勲功:貴族 領国)
武蔵 千国 9代目 鎮守府将軍 秀郷の3子 青木氏始祖
武蔵 利仁 9代目
武蔵 忠正 14代目 利仁(秀郷進藤氏と利仁進藤氏と深く同族血縁)
陸奥 秀郷 8代目 鎮守府将軍(東北北陸の統治の将軍)
陸奥 千時 9代目 鎮守府将軍 秀郷の第1子
陸奥 千常 9代目 鎮守府将軍 秀郷の第5子
陸奥 千万 9代目 鎮守府将軍 秀郷の第6子
陸奥 文脩 10代目 鎮守府将軍
陸奥 文修 10代目 鎮守府将軍
陸奥 兼光 11代目 鎮守府将軍 青木氏元祖
陸奥 頼行 12代目 鎮守府将軍
陸奥 有象 8代目 鎮守府将軍 利仁の叔父
陸奥 時長 8代目 鎮守府将軍 利仁の父
陸奥 利仁 9代目 鎮守府将軍
近江 千種 9代目 秀郷の第4子
出雲 宗綱 19代目
美濃 秀忠 16代目 美濃大屋氏の始祖
伊予 行長 21代目 永嶋氏の始祖
下野 豊澤 6代目 秀郷の祖父
下野 正頼 10代目 秀郷の曾孫
下野 有象 10代目
下野 政頼 11代目
下野 行尊 13代目 介 太田氏の始祖 領国に成る
下野 宗郷 13代目
下野 朝政 16代目
下野 秀綱 19代目
下野 定秀 20代目
下野 貞朝 21代目
下野 秀貞 22代目 三代続く
下野 高朝 22代目
下野 義政 24代目
淡路 宗政 16代目 中沼氏の始祖
淡路 時政 17代目 宗政の子
淡路 時宗 18代目 時政の子
淡路 宗秀 19代目
淡路 宗行 20代目
淡路 政信 22代目
淡路 正信 22代目
淡路 秀直 23代目
淡路 嘉秀 24代目
淡路 義政 24代目
淡路 宗秀 25代目
淡路 憲秀 26代目
淡路 秀光 27代目
淡路 秀宗 28代目
淡路 氏秀 29代目
上野 朝光 16代目 結城氏の始祖 頼朝に合力し本領安堵
相模 公光 13代目 介
駿河 景親 14代目 権守
駿河 公則 15代目
駿河 景頼 16代目 権守 近藤氏 嶋田氏の始祖
駿河 常嗣 :
駿河 宗親 20代目 権守
駿河 長久 :(37)
加賀 吉信 11代目 介 利仁 半国に分轄 吉備氏の祖
加賀 忠頼 12代目 介 利仁
加賀 忠親 13代目 介 利仁
加賀 至考 14代目 介 利仁
加賀 良時 14代目 介 利仁
加賀 政任 15代目 介 利仁
加賀 義俊 24代目
豊後 重光 12代目 滝口氏の始祖 利仁
豊後 忠綱 19代目
豊後 忠景 20代目
豊後 忠宗 21代目
豊後 秀久 23代目
出羽 有久 23代目
伯き 豊久 23代目
備後 公則 15代目
越前 高房 7代目 利仁の祖父
越前 大束 10代目 権守 利仁 利仁の子
越前 伊傳 11代目 押領使 利仁
越前 為延 13代目 押領使 利仁
越前 則重 14代目 利仁
越前 秀行 20代目 権守 利仁
越前 長範 20代目 介 利仁
相模 千春 9代目 権守 秀郷の第2子
相模 家綱 15代目
近江 脩行 12代目
能登 助忠 14代目 利仁
能登 伊経 26代目 利仁
能登 時員 17代目
豊前 貞宗 15代目
隠岐 文紀 12代目 讃岐に赴任 利仁
肥後 長成 22代目 利仁
飛騨 伊忠 22代目 利仁
筑前 為成 19代目 利仁
筑前 為重 20代目 為成の子 利仁
筑前 長経 21代目 為重の子 利仁
筑前 長範 20代目 利仁
越中 経泰 12代目 利仁
越中 則高 13代目 権守 経泰の子 甲斐 武田系青木氏始祖 柳沢青木氏 利仁
越中 延忠 14代目 介 利仁
越中 重吉 26代目 介 利仁
越後 興善 10代目 利仁
(筑後 長治 37代目)
(筑後 長定 39代目)
(筑後 長房 40代目)
讃岐 千常 9代目 秀郷の5子 (讃岐に隠れた純友の乱鎮圧)
讃岐 文紀 12代目
伊勢 藤成 5代目 特記(秀郷の曾祖父)
伊勢 基景 16代目
伊勢 基経 25代目
周防 忠頼 12代目
周防 知員 18代目
周防 忠綱 19代目
河内 村雄 7代目 特記(秀郷の父)
河内 秀能 18代目
河内 秀長 21代目
河内 秀貞 22代目
河内 久逸 25代目
(河内 長恒 37代目)
上総 公行 12代目
尾張 公郷 14代目
尾張 公澄 14代目
尾張 知昌 16代目
尾張 知忠 17代目
安房 国基 18代目 永嶋氏
安房 師綱 21代目 永嶋氏
伊豆 行信 22代目 行久曾孫(青木氏)
美作 末茂 5代目
大和 春岡 7代目
大和 秀宗 17代目
大和 信房 20代目
大和 頼房 24代目
常陸 時長 8代目 介
信濃 有綱 17代目 足利氏
信濃 高久 20代目
土佐 行政 20代目
備前 秀春 23代目
出羽 長村 18代目
出羽 宗朝 20代目
美濃 秀忠 16代目
紀伊 正長 20代目 以下は長沼氏支流中沼氏
下総 忠氏 21代目
山城 忠光 21代目
近江 時久 21代目
安芸 資久 21代目
尾張 資忠 21代目
但馬 氏忠 22代目
薩摩 用久 23代目
若狭 忠弘 25代目
摂津 頼久 25代目
遠江 勝久 25代目
相模 友久 25代目
この赴任地から秀郷勢力を隣国に広げたがこの国は含まずとする。
この赴任地は末裔を広く広げた官職の介や権守以上に限定した。
当レポート以前の史料は兼光系ルートの史料として記述しているが、ここには文行系も含んでいる。
秀郷一門としている利仁系も秀郷一門として扱われた。
それは進藤氏を仲介として同族血縁を繰り返した事による。
その結果、秀郷の領国の武蔵、下野国内で圏域を広げ、また守護職も勤めた利仁流系である。
短期間の赴任も含む為に末裔を遺していない国もある
赴任地は平安末期までとする。(...)は鎌倉幕府以降の1200年以後の赴任地とされる。
藤原秀郷一門は鎌倉幕府樹立(1185-1192)により官職を全て失う。
藤原勢としては、朝光が関東一円で合力して勲功を立て、本領安堵されて平家に取られていた上総の結城は戻る
当時、平均寿命50歳とすると、この時期(平安末期)までの代は、17代(+1−1)位から25代(+1−1)位と見られる。
系譜には同名がある。
利仁系に付いて、次の系譜になる。
鎌足−不比等−房善−魚名−藤成−豊澤−村雄−秀郷
鎌足−不比等−房善−魚名−鷲取−藤嗣−高房−時長−利仁
(藤成の弟の鷲取の系譜と成る。)
長沼氏の赴任地は短期間である。(宗家を除き赴任期間は通常2年から5年程度である。)
参考として当時の日本の国は66国である。
藤原秀郷一族一門の発祥氏
秀郷主要五氏は次の通りである。
4代目兼光系―青木氏 永嶋氏 長沼氏
4代目文行系―進藤氏 長谷川氏
この主要五氏は以下の氏を発祥している
秀郷の4代目から次の様に分流する。
但し、青木氏は秀郷2代目より初代となる。
途中、4代目兼光系より13代目で総宗本家より行久が跡目に入る。
青木氏は秀郷の子の千国より出ているので末裔の最古参である。
青木氏主要9氏は直系1氏 直流4氏 支流4氏である。
下記の氏以降の支流分流分派は列記していない。
以下の氏は綜紋を「下がり藤紋」とし直系主要氏である。
秀郷主要5氏
兼光系 青木氏 永嶋氏 長沼氏
文行系 進藤氏、長谷川氏
但し、進藤氏は秀郷流進藤氏と利仁流進藤氏とがある。共に相互に血縁を繰り返している。
(他に、支流とする清和源氏進藤氏、綾氏進藤氏、未勘の諸流進藤氏もある)
名前 発祥氏 注釈
千国 青木氏 主要五氏の祖 青木氏116氏に末裔広がる 秀郷の3男
秀忠 大屋氏
考綱 長沼氏 秀郷主要五氏 52氏に末裔広がる
成俊 佐野氏
成行 足利氏 本家を排斥して分家に跡目入れて本家を継ぐ
行長 永嶋氏 秀郷主要五氏 伊勢より東の永嶋氏の祖 34氏に末裔広がる
行久 青木氏 秀郷主要五氏 宗家より鎌足24代目で跡目
兼行 渕名氏 秀郷一門24氏主要5氏外の支流系分派の初代
行尊 太田氏
政光 小山氏 陸奥小田氏末裔
親実 松野氏
為輔 進藤氏 利仁流 元祖
景頼 近藤氏 (嶋田氏も祖)
景頼 嶋田氏
行景 進藤氏 秀郷流主要5氏 48氏に末裔広がる
知廣 尾藤氏
公清 佐藤氏
朝光 結城氏
宗政 中沼氏 長沼氏末裔
行義 下川辺氏
重光 滝口氏
助宗 斎藤氏 始祖
叙用 斎藤氏
実景 斎藤氏 勢多
親頼 斎藤氏 美濃
実盛 斎藤氏 長井
宗重 長谷川氏 秀郷主要五氏 111氏に末裔広がる
吉信 吉備氏
則明 後藤氏 元祖
公澄 尾藤氏 元祖
公郷 後藤氏 祖
基景 伊藤氏
以上24氏である。
主要5氏―24氏―361氏に成った事になる。
秀郷主要五氏の系譜
秀郷の主要五氏の一族を夫々について分類すると次の様になる。
進藤氏
藤原秀郷流進藤氏
藤原利仁流進藤氏(秀郷流の斎藤氏が中間血縁族)
未勘の諸流進藤氏
未勘の諸流進藤氏の末裔支流分流
清和源氏進藤氏(乙部氏が中間血縁族)
清和源氏進藤氏(武田氏が中間血縁族)
綾姓進藤氏(羽床氏が中間血縁族)
藤原姓進藤氏
清和源氏吉良氏族進藤氏(吉良氏が中間血縁族)
藤原秀郷流進藤氏(近衛氏が中間血縁族)
以上が未勘である。
長谷川氏
藤原秀郷流長谷川氏(尾藤氏系)
藤原秀郷流長谷川氏(下川辺氏系)
藤原秀郷流長谷川氏(長久系)
藤原秀郷流長谷川氏(重吉系)
藤原姓長谷川氏(利仁系進藤氏)
藤原利仁流長谷川氏
未勘の諸流長谷川氏
未勘の諸流長谷川氏の末裔支流分流
(藤原氏外)
本宗橘氏系長谷川氏
菅原姓長谷川氏
長沼氏
藤原秀郷流長沼氏(渕名氏が中間血縁族:一門)
藤原秀郷流長沼氏(小山氏が中間血縁族:一門)
藤原秀郷流長沼氏(土岐氏が中間血縁族)
藤原秀郷流長沼氏(藤原秀行流:一門)
藤原秀郷流長沼氏(宇都宮氏が中間血縁族:一門)
未勘の諸流長沼氏
未勘の諸流長沼氏の末裔支流分流
藤原秀郷流中沼氏(島津氏が中間血縁族:室町期)
藤原秀郷流永沼氏(織田氏が中間血縁族:室町期)
藤原秀郷流長沼氏(桓武平氏)
藤原秀郷流長沼氏(源姓)
永嶋氏
藤原秀郷流永嶋氏(佐野氏が中間血縁族:一門)
藤原秀郷流永嶋氏(結城氏が中間血縁族:一門)
肝付氏系永嶋氏(肝付氏系:九州永嶋氏:後漢の阿多倍一門)
阿多倍系永嶋氏(大蔵氏系:九州永嶋氏:後漢の阿多倍一門)
日下部氏系永嶋氏(大蔵氏系:九州永嶋氏:後漢の阿多倍一門)
未勘の諸流永嶋氏
未勘の諸流永嶋氏の末裔支流分流
村上源氏北畠氏永嶋氏
藤姓佐野氏永嶋氏
藤姓永嶋氏
青木氏
上記の赴任地24地方の末裔24氏の青木氏 116氏
直系1氏、直流4氏、支流4氏
直系
藤原秀郷流青木氏(千国:一門)
直流
藤原秀郷流青木氏(行久:一門)
藤原秀郷流青木氏(佐野氏が中間血縁族:一門)
藤原秀郷流青木氏(玄審:一門)
藤原秀郷流青木氏(安明:一門)
支流
藤原秀郷流青木氏(忠英:一門)
藤原秀郷流青木氏(正命:一門)
藤原秀郷流青木氏(正胤:一門)
藤原秀郷流青木氏(政之:一門)
未勘の諸流青木氏
第一期の室町後期、第2期の江戸初期、第3期の明治初期の第3青木氏が存在する。
この3期の系列は確定できない。
藤原秀郷流青木氏の未勘氏
美作国 吉野郡青木村、真庭郡に末裔青木氏
越後国 古志郡
佐渡国 加茂郡青木村
三河国 渥美郡、額田郡
因幡国 八東郡
豊前国 下毛郡
下総国 猿島郡
岩代国 安達郡青木村
磐城国 袋内
以上赴任地外に室町期から江戸期にかけて赴任地、転封により移動定住したと観られる末裔。
家紋等不詳である。
注意:千国、行久、佐野氏から血縁発祥した青木氏以外の玄審から政之までの青木氏は、系譜が取れる範囲のものとして表示し、これ等は行久、佐野氏からの系流の青木氏である。
以上に分類できる。
以上、3つの内容に付いて、分類し整理した。
この分類から、藤原秀郷一門のその当時の活動状況等が解り、他の史料と組み合わせたりすると更に多くの考察が出来るので大いに利用して頂きたい。
Re: 先祖と宗教(キリスト教の教え−7-1 質問)
アキノリさん 2007/10/23 (火) 21:09
副管理人さんへ
こんばんは、お久しぶりです。雑談をさせてもらいに、帰りました。
師匠の論文は大変に参考になります。理解が第一とのお叱りを受けましたが!
私は単細胞なのでお許しを願います。
キリスト教に関するご批判を、超論文を拝読させて頂きました。多少の誤解があるかと感じます。
私は少なくても20〜30年ぐらいの経験がありますが、反論はキリスト教関係者に委ねます。
5 人は全て悪の子供であると否定する事
==========================
少なくてもこの箇所は、誤解があるかと感じます。
罪と悪の区別が為されていません。
私は:人間は肉体を持った魂である。と解釈しています。肉体は朽ちて死にますが、魂は霊の存在に関わります。霊は人間ではありません。霊魂は様々です。悪霊もあり神様もいます。
魂は霊に影響を受けます。聖霊は悪霊を近づけません。
人の魂は聖霊に導かれる時に真理を悟ります。---悟り--すなわち理解と解釈しますかな!
キリストの理解は、聖書を読み教会で学ぶ事が必要になりますが、教会も色々ありますので、これが問題になります。聖霊に導かれてキリストとの出会いがありますようにお祈りさせて頂きます。
キリスト教の伝来と植民地主義がアジア、アフリカ、ラテン アメリカの諸外国にあった事は事実
です。ヨ−ロッパ人は植民地主義で搾取の歴史を刻みました。
しかし日本も、大東亜共和圏といった覇権を作り出した歴史も事実です。
----------------------------------------------------
私の仮説を述べるのは控えますが、
物質 = エネルギ-: 物質が消滅してエネルギ-に変化する事は?アインシュタインが相対性理論で証明しました。
人間は物質と魂と霊を持っています。魂と霊はエネルギ-ではなく、超次元世界---3次元や
多次元空間は時間とエネルギ-に形を変えます。
重力は空間を曲げる、光、電波、熱、電気、電流----等は広義にエネルギ-であります。
これらの問題は現代数学で、証明されつつあります。
------------------------------------------------------------------------------------------
以下は先生の論文の一部です。
更に、キリスト教は、”人は悪の子供”と設定していますが、仏教では”悪の子供であるも普通であり悪と拘るな”であります。それが「人」だと説いています。
これが私の若い頃にキリスト教の説法を4年間聞きに行って知ったポイントでした。
===========================================================
以下 キリスト教教え−7 主題4を参照(メモリー為)
Re: 先祖と宗教(キリスト教の教え−7 主題5)
副管理人さん 2007/10/23 (火) 07:01
5「仏教とキリスト経の妥協の余地」
設問1−10は主題4に関わりますが、6からは主題5にも関わります。
では、キリスト教の設問として、6番の続き、7の問題の説明に入ります。
設問
1 他宗を少なくとも先ずは強く排他している事。
2 教えがかなり強引である事。
3 キリスト個人を神扱いにしている事。
4 兎に角にも、”先ずは信じよ”である事。
5 人は全て悪の子供であると否定する事。
5「仏教とキリスト経の妥協の余地」
6 中間的考え(柔軟性)は無い事。
7 全体が闘争的な発想に成っている事。
8 特定者(若い者)には受け入れられ易い合理的な教えに成っている事。
9 先祖に対する考えは全体として希薄である事。
10 「民族的」と言う考えを認めていない事
7番目の事です。(全体が闘争的な発想に成っている事)
この設問を説くには、仏教と対比しながら、教義より現代のキリスト教の行動を検証する事の方が明確に成ると考えます。
仏教の様に、他教の聖域に入り、積極的に布教をすると言う事は仏教には少ないと考えます。
。むしろ、インド(ブッタガヤ)から中国を経由して日本に伝教してくるまでの東中国(後漢)過程には、多くの弾圧があった事は史実であります。
そして、最初の伝導は、司馬氏の始祖(馬の鞍等の武具を製作する鞍作部の技能職人である)司馬達等が日本に帰化してきた時に、私伝として広げたのが最初(535-550年頃)であるとしています。その中国後漢(618年)が滅びて、阿多倍に率いられた17県民200万(帰化)に依って爆発的に広がったとされています。
(参考 阿多倍:後漢光武帝から末帝21代の献帝の子石秋王の子供阿智使王と孫阿多倍の二人が引き連れた200万の中国の民が九州へ上陸し全土を平定し、関西手前までの32/66国で征圧し帰化する。)
これが次第に周囲の中国(後漢)の渡来人の部技能職人以外に、彼らから技能を教わって恩恵を大きく受けている日本人にも自然の形で瞬く間に爆発的に(国32/66の範囲)伝わったものであります。
書籍的には、552年(538)百済から経典が入ったとされています。585年の物部氏と蘇我氏との戦いだけで伝導は決定します。594年の三法の詔に始まります。(後に神道と融合する)
この仏教の伝播の勢いは、この技能集団の部制度の影響が最も大きく、又、民族の融合もスムースに進んだ原因はただ伝わったと言うだけでは無く、技能集団の彼らがもたらした仏教の影響が大きかったのではと考えています。
現在、世界の民族の融合を観察するに、中東では民族戦争が多く起こっていて絶え間なく1000年経ったいまでも融合は余り進んでいないのが現状であります。
まして、日本は7つの民族が全て分離することなく、それも300年程度(史料的には阿多倍の孫娘を母に持つ桓武天皇期以降には出て来なく成る。この原因の詳細は研究室の阿多倍関係のレポートで参照)で一つになるには何か特別な要素がなければ出来るものではないと思います。
その要素とは、「天神文化」の「神道との融合」と、この「技能集団と仏教」の結びつきがもたらした結果であると考えています。
つまり、そして、その伝播の経緯は、「神道的仏教伝播」と「民族融合」が相互に関連して平行して進んだと観ています。
日本仏教、特に奈良期から鎌倉期までの「顕密仏教」では、この背景があったことを念頭に留意して比較評価して観るべきだと考えます。
これは「顕蜜仏教」と「新鎌倉仏教」とに日本仏教の違いを区分けされている一つの要因でもあります。
その仏教の姿や役割がこの境の時期を以って異なっている所以であろう事ははっきりしています。
民族と仏教の2つの融合過程はこの域を境に一度に変化した時でもある事が言えます。
これらの事が欠けての評価は判断に間違いを起すとも考えます。
そこで、先ず、上記の事を留意して、キリスト教では、この様な仏教の自然に近い伝来と言うよりは、歴史的には植民地侵略をベースとして政治的施策を施して爆発的に伝播して行ったのが、近代に於いての基本伝導の姿であろうと考えます。
この時、伝導や教義はその植民地の民族的背景を配慮してのものでは無かったであろうし(価値観の配慮と伝統の無視)、
むしろ、それを行うと、世界各地に異なる教義のキリスト教が出来てしまう事になります。
この事は、その民族間のキリスト教の争いともなり、キリスト教の存亡にも成りかねないことを意味するであろうと考えます。
主題4の所で記述したキリスト教の教義の矛盾がある事を論理的に充分に知りえながら、一つの教義を押し通す事を実行したのであろう事が覗えます。(強引で闘争的)
日本の仏教は主題4で記述した様に、「天神文化」と言う「神道と仏教との融合」と言う手段と「民族融合」も備わって伝導を成し得たのです。
仏教もキリスト教も同じ政治性を含む伝導ではあったが、仏教は融合と言う形でその対立を避けたのであるから、キリスト教とはその体質は異なります。
又、仏教伝来のほぼ直ぐ後に儒教が伝導しているが、この儒教も何処に教義の考えがあるのか判らない程に同化し融合しています。
しかし、儒教は大きく伝播せずに単独の形でのものは無ったのであります。
儒教は江戸時代にその社会情勢から突然に学問として世に出されたが江戸幕府の禁令で更に突然に消えました。
しかし、社会慣習の中には、儒教の慣習や作法や思考姿等の生活の慣習の中などに気づかずに多く残っています。
例えば、葬儀のときは儒教では正座や豪泣、仏教では胡座、不泣と宴の様に遺されているのです。つまり、これも小さい「融合」であります。
現在に於いても、世界各地で紛争が起こっています。
その紛争を武力とキリスト教で世界平和を大儀にして解決しようとしている様に見えます。
キリスト教の彼らにしてみれば、この二つの事で扮装は収まると真剣に思っているであろうと思いますが、しかし、そう簡単ではありません。ここに、「民族」(価値観の配慮と伝統の無視)という遺伝子に絡む大問題を無視している強引さが彼らキリスト教にはあります。
各民族には、その特異な妥協し得ない「事情や環境」がある事は否めません。当然に、必然的に、その特異性からそこには心の悩みを解決する為に独特の宗教が存在する筈であります。
キリスト教側では、その教義で民の安寧を計ろうとするでしょうが、結果は火を見るより明らかであります。
”宗教戦争”に変化して行き、中東の様に国と民を巻き込んでのイスラム教とキリスト教との益々の争いと発展して行く事は必定です。
イスラエル、イラン、イラク、アフガン、インドネシア、フィリピンの様に国をあげての宗教戦争に成っている事が証明しています。この全て裏にはキリスト教の浸透策が潜在しています。
先日の韓国のアフガン拉致問題は7の設問のその象徴的出来事です。
弱り目に祟り目でありますが、日本も例外では無く、大戦の敗戦後は、この危険性はあったのです。
しかし、神道仏教の融合教義の完成度が高い事により、明治初期の「廃仏毀釈」だけで、戦後の内乱は避けられたのであります。
確かに、我々から観ると、イスラム教にも強引とも攻撃的とも思われる「聖戦」や考え難い「宗教作法」などもあります。
しかし、キリスト教やイスラム教などにしても、それはその国の民が良し悪しに関わらず「良し」とするのであれば、それはそれで良い事であります。
「悪い」とするも、当然に、何処に於いてもその「攻撃的強引さ」は「宗教の代理戦」の形として現われて来る事になるでしょう。
この問題には、その特異な妥協し得ない「事情や環境」がある事は否めないし、解決出来ないからであります。
国民の一致団結(融合)を成し得なければ、その民の選択と決断に関わる事に成ります。
この様に、宗教だけを見るのではなく、政治の裏には必ず、現実には、この様な体質を持つキリスト教の動きが存在しているのです。(そもそも、”信じよ”には反意として攻撃的の語意を持ちます)
仮に、キリスト教の伝播と浸透のそれを成し得るには、日本の仏教と民族の融合過程のように、先ずは少なくとも「キリスト教と仏教の融合過程」が必要であります。
この論理で言うと、宗教界では、現在そのような教義を前提とする宗教団体(生長の家)があり、徐々に日本の国に浸透しています。
この教義の姿や前提が伝播過程の通るべき道として正しいのではないかと推理しています。
しかし、この手法ではローマ法庁のようなキリスト教の全体の形は採れずに、本体はいつかキリスト教の一括統治が働かなくなり出来ずに崩れることを意味します。従って現実には無理なのです。
しかし、私には、体質的に出来ることならば、避けたいキリスト教義とその否融合の手法と観ますが、皆さんは如何ですか
Re: 先祖と宗教(キリスト教の教え−6 主題5)
副管理人さん 2007/10/20 (土) 10:14
5「仏教とキリスト経の妥協の余地」
設問1−10は主題4に関わりますが、6からは主題5にも関わります。
では、キリスト教の設問として、5番の続き、6の問題の説明に入ります。
設問
1 他宗を少なくとも先ずは強く排他している事。
2 教えがかなり強引である事。
3 キリスト個人を神扱いにしている事。
4 兎に角にも、”先ずは信じよ”である事。
5 人は全て悪の子供であると否定する事。
5「仏教とキリスト経の妥協の余地」
6 中間的考え(柔軟性)は無い事。
7 全体が闘争的な発想に成っている事。
8 特定者(若い者)には受け入れられ易い合理的な教えに成っている事。
9 先祖に対する考えは全体として希薄である事。
10 「民族的」と言う考えを認めていない事。
5「仏教とキリスト経の妥協の余地」を検証するため、設問(6−10)に入ります。
第6番目の事です。(中間的考え(柔軟性)は無い事)
1から5までの設問に対する考えが、共通することで大半を説明していますが、「柔軟性」はキリスト教には少ないと考えます。
むしろ、本来、(日本のように融合民族であるが)、融合していない他民族の集合体の自由の国であれば、その考え方に幅を持たせて、柔軟に教義が出来ていると考えられるのが普通であると思うのですが。
しかし、ヨーロッパも日本と違い周囲に他民族が多く存在しますので、当然に、民族の重複部分地域は、キリスト教の教義ついてはこの柔軟性はあると考えられます。
しかし、矢張り「信じよ」ですから、この教義からはこの柔軟性は考えられません。これは言葉の性質からも来るのでしょうが、仏教は、般若心経の教義一つを観ても代表的な言葉として、(何度も書きますが、)「色不異空、空不異色」「色即是空、空即是色」を始めとして、「不生不滅、不垢不浄、不増不減、是故空中無色」等は、”この語意は一体何を意味するのだろうか”と思える位に、柔軟であります。
仏教は以前、その「反意や深意や真意や裏意」が大きく働く教義であると書きましたが、上記の語意は、判断の経験を大きく左右するものである事は、多くを調べていると理解出来ると思います。
ここに書いている”「色」とは、「空」とは、何ぞや”から理解する必要があります。(前説に記述)
この理解で全体の解釈も充分に異なるであろうと思います。それでよいとしています。
仏教では、”その人その人の受け取り方はそれはそれで良いのだ”という。宗教関連者では、職業柄、定説的なもを主張しますが、一般の者の理解としては、”その人が、経験もしないのに、その人も立場や環境もあろうことなのに、そのことを解いても、それは「悟り」(理解)とは言わないのである。そして、経験を通じてその理解が深まれば、それはそれなりの「悟り」(理解)と言うのだし、それは「真の悟り」へとに近ずく”としています。
仏教の教えの一つとして、次の様な仏教言葉がある。
1「人を以って法を説け」という言葉があります。
2「三相を得よ」と説きます。
更に、次のその言葉として、代表的なのはがあります。
3「縁無き衆生動し難し」という説法があります。
この3つの言葉を組合すと上記の理解事を物語る言葉でなります。
況や、その真意、深意は、この意味が柔軟性を物語る先ずひとつであります。
この「三つの法意」(3つの言葉1、2、3)がその「柔軟性」を物語るものです。
1は”人は夫々立場、性格、職業、男女、家柄、生立ちなどでその理解は異なる。説法だからと言って仏教の教義をそのものをずばりを以って伝えても意味がない。その立場などに生おじて噛み砕いて伝えよ”としているのです。
2”1が成し得たとしても、人、時、場処にあわして説法をしなくては法意は伝わらない。伝え得るには1と2の術を身につけるべし。何事もそうである”としているのです。
3は”1と2を経たとしても、理解できない者はある。全て者を理解させようとするはその心根は「拘り」である。理解できない者はそれはそれで縁無き常の者として動かし難いものとして扱いを別にしろべし”としているのです。
この仏教の「3つの法意」は一言で言えば、”柔軟に対処せよ”としている事に成ります。
つまり、”それはその人の今の[悟り](理解)である。””「悟り」は、この様で、この如くでなくては成らないと限定するものではない。人の世では、次第にその「悟り」が増せば良い”としています。
これに較べて、キリスト教の「悪の子」は「悪」と最初から決め付けていることからも、「柔軟性」が無いと見えます。
ただし、私が言うこの「柔軟性の有無」が教義の「良悪」の事を説明しているのではありません。
それはそれで彼らが納得するのであれば関知するところでないと考えます。
当然に、国民性や常識は違うのだから、「良悪」の問題ではありません。差違や適応性の問題です。
ただ、キリスト教は、その語意は、(「悟り」理解が難しい」が、)経験が共にするので「判断は容易」であると思います。
しかし、逆には、「反意や深意や真意や裏意」があるので、、(「悟り」理解が易しい」が、)「判断は難」の仏教だと思います。
故に、キリスト教は個人の悟りに差が余りに無く(個人受け取り方)これが一つの特徴であり、中間的考え(柔軟性)は無い事に成ります。仏教は様々と成ります。第一、キリスト教には「悟り」という概念が乏しいのではと考えます。
次は7番の事に続きます。
Re: 先祖と宗教(キリスト教の教え−5 主題4)
副管理人さん 2007/10/20 (土) 10:12
4「キリスト経の教え」
キリスト教の設問として、4番の続き、5の問題の説明に入ります。
1 他宗を少なくとも先ずは強く排他している事。
2 教えがかなり強引である事。
3 キリスト個人を神扱いにしている事。
4 兎に角にも、”先ずは信じよ”である事。
5 人は全て悪の子供であると否定する事。
6 中間的考え(柔軟性)は無い事。
7 全体が闘争的な発想に成っている事。
8 特定者(若い者)には受け入れられ易い合理的な教えに成っている事。
9 先祖に対する考えは全体として希薄である事。
10 「民族的」と言う考えを認めていない事。
5番目の事です。人は全て「悪の子供」であると否定する事
先ずは、上記の4の脳医学の証明でも、人は「悪の子」ではない事はわかります。
ただ、その「悩み」(拘り)はキャリパーの流れが続いていることから、悩み(拘り)が起こっているに過ぎないのです。
切れば、「悩み」(拘り)から脱出できるのです。「善の子」であるかは別として、「悪の子」等では到底有りません。
仮に、「悪の子」としても、切れば、「悪の子」から脱する事が出来るという事は、生まれながらに、本質は「悪の子」でないことを意味します。
その前に、このことを注釈しておきたいと思います。それで次の事もお考え下さい。
「悪の子供」であるとする教義から、”この悪を全て捨てよ”として”「悪」の無い人として出直せ”と成るのであろう事は想像出来ます。
このことは4番目の事にも繋がる事に成るのでありますが、本当に「悪」なのであろうか。実に疑問と思うのです。
と言うのも、子供が生まれた時のことを考えても、子供そのものは「悪」は持っていないでは有りませんか。
子供は持っているのですか。子供の心にどのような悪を持ち得ているのでしょうか。人は、子供の心に「悪」を持ち得ていないから、子供は可愛いと思うのではありませんか。
可愛いという「心根」の本質は、「善」の全ての姿であるが故の発露ではありませんか。
そして、又、持ち得ていないから、「善」成るが故に、子供を産もうとするのではありませんか。「悪」を産もうとしているのでしょうか。
「産む」という「行為と行動」は真さに、人として、人生の最高の「善」ではありませんか。
まして、人の生誕のその「行為と行動」は、1/250兆の確率で「善」を作り出そうとしているのですよ。
1/250兆のすごい確率の「善」です。これだけの確率で生まれてくる人なのです。悪である筈が有りません。
悪と考える方が異常というべき「ひねくれ思考」です。
人生の「喜怒哀楽」以上の「善」の「最大の善」です。これに勝るもの無しです。
「最大の善」から「悪の子」が生まれると言うのですか。どう言う根拠で「悪の子」と成ってしまうのですか。
この人の世は、「善」から「善」が生まれるのです。生まれながらに「悪」であるならば先天的ですから「悪」から「善」に変わる事はありません。
だから人生の中での一過性の「悪」を「善」にするとキリスト教は言っているのであれば理解は出来ます。
基が悪から何にしようとしているのですか。
仮に、「善」に変わったとして、千差万別の「善」が出来てしまうのでは有りませんか。
キリスト教の宗教を信じない人は信じる人より多いはずです。そうすると世の中、悪ばかりですね。少し独善的ではありませんか。
もし、人がキリスト教国外に出ると、「善の国」に戻り、中に居ると「悪の子」ばかりですから「悪の国」に成るのですか。
これは、「善」即ち「是」である事を認めている証拠です。
子供と人は「悪」で有るとすると、もし、、「悪」であれば、究極、その世は殺し合いの末路となり結果は絶滅となり、存在する事は不可能ですね。そうでは無いとするならば、何処までを「悪」とするのですか。そんな「悪」の限界を決められるのですか。
だから、キリスト教は”この世は何年後かに滅亡する”と予言しているのですかね。確かに予言していましたですよね。(Y2006でしたか、起こりませんでした。)
しかし、人は益々と増え存在しているのですから、滅亡しないで存在しているのだから、その後の大人の人生では「善」の人も居るとなりますよね。その人々は宗教を信じる事なしに「変化」したという事になりますよね。
そうすると、宗教を信じる事や頼らなくても、先天性の潜在的な「悪」が変化して、後天性の「善」に「悪」は変化したという事に理屈は成りますね。
先天性は変化するのですか。しないから先天性であるのでしょう。
もし、そうだとすると、つまり、突き詰めると、”宗教は要らない”となりませんか。
では、更に、キリスト教を信じていない人々の方が多い世界の世の中で、救われない「悪」の人の方が多く成ってしまいますよね。そんな「悪」の世の中は成り立ちますか。無理ですよね。自分も含めて周囲が全て悪魔とは到底考えられません。
しかし、全て尽く人は「悪」を持つのですか。そんなことは無いでしょう。
もし、生まれた時から「悪」を持って生まれたとしたら、その子孫を遺そうとする行為と行動は「悪」という事になるではありませんか。子孫を残す「行為と行動」は「悪」と言う事に成りますね。
つまり、「悪」の定義は、人そのものを「否定」していることに等しいのではありませんか。
この矛盾を繰り返していても仕方が有りませんから、そこで、「動物学」か何かで、証明しましょう。
では、他の動物はどうなのでしょうか。人間は最終に偶然に知恵を持った事により、より他の動物との差違が生まれたに過ぎません。
動物は動物で特別に変わった所はありません。人は高い知恵を取り除けば他の動物と変わりません。
変わる所はありますか。だとすると、他の動物も悪の動物なのでしょうか。
他の動物だけは違うとする根拠がありますか。有りませんよね。
猿の進化から、人はチンパンジーからボノボに変化して類人猿となっただけですよね。その知恵の存在となった直立人の差だけですね。
学問的に検証してみますと、猿とチンパンジーとボノボと人間が、人間が住むような同じ環境の部屋に入れて共同生活させた実験結果がアメリカでありました。
その結果として、ボノボだけは不満をあらわにしたとする結果が出ています。
それは、チンパンジーと自分ボノボとは、猿類としての身分、又は、優越感が違う事に対して、同じところに扱ったとして怒り不満を持ったと言うものです。
人間が持つ猿に対する感情と同じものを持っていたのです。
そして、自分ボノボは、”何故、人間と言う優れた猿に成らなかったのか悲しくて寂しく残念である”という感情を表現したと記録されています。
この様に、ボノボの感情を示す様に、猿類からも人間を同じ(なかま)サル類として観ていたのです。
故に、人間は猿の一つなのです。つまり、動物なのです。キリスト教が言うように、特別なものではないのです。科学的な付加価値のある高い知恵を持ったただの猿なのです。実験結果の様に持っている基本的な感情は全く同じなのです。
この様に、学問的には、チンパンジーやボノボの研究で、彼らもほぼ人類と同じ程度の感情と科学的な進歩の知恵を除く基本的な知恵を持っている事も証明されていますから、彼ら動物も「悪の子」なのでしょうかね。
でも、「悪」とするとしても、子孫を遺すという動物の本来のこの世の目的として「善の行為と行動」をしていますよね。
何処から考えても「悪の子」であるとする根拠は出てきません。有るとしても余りにも無さ過ぎるのでは有りませんか。有ったとしても少なくてこれでは「悪」とする根拠は希薄となりますね。
私は、この矛盾は、次ぎの4つの理由から出ていると考えます。
その宗教の出所1と、祖師の過去の位置付け2と、時代の変化に対する教義の修正の不足3と、民族の土地柄の修正が出来ていない結果4から、教義に対してこの矛盾が起こっているのだと考えます。
では何故に、修正を加えないのでしょうか。
それは、キリスト教の排他性から来ている事に成ります。
その排他性の根拠は、キリスト教の出所地域の先進性から来ているもので、上記したボノボの「優越感」に相当しているからでしょう。
しかし、最近、その優越感が揺らいでいるのです。
その一つには、日本人がその優越感を変えさせたのです。
経済成長に伴い日本の仏教文化の優越性と、その国民の先進性がキリスト教国をはるかに凌ぐ結果を彼らは確認した事によります。”アジアの野蛮国が先ず有り得ないこと”と観て居た筈です。そう云う発言も公式に戦前にはありましたよね。
第2次大戦の発端は、この有り得ないことが起こりつつある事から、アジアの野蛮国に圧力が掛かりその圧力に対抗した結果の所以でしたですね。この傾向の最初は大国ロシアに勝った日露戦争の勝利が彼らに衝撃を与えたのです。
その大きな勝利は突き詰めると、3つの要素が浮かびます。秋山兄弟の頭脳働きと、軍艦の大砲の改良と、火薬弾の開発でした。
これを観た英国とフランスと米国とロシアの白色国は日本の底力を恐れ始めたのです。
(7つの融合単一民族なのです。遺伝学的に動物は融合すると進化して優秀な人間を作ります。アジアの中で日本人は違うのです。)
そして、大戦より50年以上経ったところで、戦後の占領下15年頃の発言に対して、今の発言は、同等の発言となっています。
私は、まだ若い頃、技術者としてヨーロッパ系の技術者との会話したことが幾度もありましたが、軽蔑とまではいかなくても、見下げた言葉尻で、”又か。”という経験が何度もありました。
技術的には、日本の冶金学は世界一段突であるのだが。
そして、どの宗教も、その矛盾を大きく社会に露出している時代なのだと考えています。
特に、キリスト教での争いが目立ちます。
ただ、仏教では、上記した様に、1000年もその教義に矛盾がありません。
特に、日本仏教では、”その矛盾の事が余り起こっていない”という事でも同等間を持ったのでしょう。
だから、仏教と他宗教との間の差違の矛盾が露見しているのだと考えています。特にキリスト教との差違が目立っているのだと考えます。
その理由の一つは、上記の優越感のあらわな表現もあり、世界に対して、余りにもキリスト教は嫌われて問題を起しているという事です。
特に、中東の社会に於いてです。それはこの教義の強引さから来ているものと推測しています。
では、何故に日本仏教は、その差違が出ないのかと言う点です。
それは次の点になると考えます。
先ずは、「色不異空、空不異色」、「色即是空、空即是色」の教義の考え方です。
次は「天神文化の融合」です。
更に、日本民族の゜単一融合民族」の特質です。
最後に、その教義を「宗教学」としての学問の発展です。
”信じよ”では無く、「悟れ」(理解)、「拘り」を第一の教義にしている事です。
この結果、次の設問の事にも関わることですが、「時代性」という点で、キリスト教の「悪の子」を始めとする時代性の矛盾と較べて、仏教は時代との教義のそのズレが無く仕上がっていると考えています。
それの仕上がりは、「人間の本質」を、「有るがままに見つめた教義」としている事だと考えています。
つまり、「人間の本質」が時代(時、人、場所)に対して特別に大きく変化しない限りはその教義は生きている事に成ります。(この科学の世が発展し別質の「宇宙人間」なる者が誕生しない限り、本質は変わらないから本質である)
余談ですが、奈良期から平安末期までの「顕密仏教」を経て、この「融合教義」を作った日本仏教の比叡山天台宗と、それを大きく広めた次の「鎌倉新仏教」の法然の浄土宗が優秀であったことを意味します。
そして、その時代をリードした為政者の天智、天武の両天皇の荒波を乗り越えた「大化改新」の政治統治の基盤を成した偉大さが如何に大きかったかを物語っています。
その時の「天神文化」の融合の判断も適時適切を突いていて、現代までも大きく矛盾なく持ちこたえて来たのも偉大という以外にありません。多分、天神文化の融合政策がなければ、日本仏教は安土期から江戸期に掛けてキリスト教に取って代わられていた事は間違い有りません。アジアの諸国の現状がその証拠です。
そして、1650年程度と続いた現在の日本文化は、上記した考え方の違いで、異教に破壊されて無く成っていた事をも意味します。
私は更に、多分、文化どころでは無く、当然に異教の思考原理の浸透で、日本人に肌身に合わないし適合しない事から政治情勢も混乱し続けていたと思っています。
この様に、日本の融合を基盤とする仏教文化は「すごい文化」であったかと考えます。この様な文化はこれ以後出ていません。
その「教義」は、大した矛盾もなく日本人の民族の遺伝子と生活環境と成って引き継がれて来ているのです。
その、最も優れた思考は、「仏=先祖」の思考であったと評価しているのです。
何をか況や、これは真さに、「大化改新」であり、上記した基盤がそれを成し遂げたもので、施基皇子を中心とする「皇親政治」を実行した第6位皇子の子孫の5家5流の「青木氏一族」が、奈良期の「基盤政治」をリードし、7つの民族の「融合政策」を牽引して、「優秀な民族」を創造し、「天神文化」を築いた我が「先祖」の成せる技であります。
これは、前説のわが先祖の「行為と行動の逆進性」の「流」の条件が整っていたことを意味します。
次は6番の事に続きます。
Re: 先祖と宗教(キリスト教の教え−3 .4 主題4)
副管理人さん 2007/10/20 (土) 10:10
4「キリスト経の教え」
キリスト教の設問として、2番の続き、3と4の問題の説明に入ります。
1 他宗を少なくとも先ずは強く排他している事。
2 教えがかなり強引である事。
3 キリスト個人を神扱いにしている事。
4 兎に角にも、”先ずは信じよ”である事。
5 人は全て悪の子供であると否定する事。
6 中間的考え(柔軟性)は無い事。
7 全体が闘争的な発想に成っている事。
8 特定者(若い者)には受け入れられ易い合理的な教えに成っている事。
9 先祖に対する考えは全体として希薄である事。
10 「民族的」と言う考えを認めていない事。
3番目の事です。(キリスト個人を神扱いにしている事)
キリストと云う現存した個人を崇拝する宗教は、ある意味で、創り上げた教義であります。その教義の良し悪しの如何を論議しているのでは無く、それはそれで宗教とするは、信じる人が納得できるのであれば、特に問題ではありません。
現存した個人を万能の神扱いにすると言う事は、仏教国の民としては何か納得出来ません。
キリスト教の教義を以って、それを人格形成の絆とするは、特に問題ではなく、この事は仏教でも同じであります。
キリスト教徒に言わせれば、この反論として、生きていた者が死んで、生きている民を導く「仏」となる事に対して疑問を感じるとの反論意見もあります。
結局は、死んだ後のキリストと同じではないかと言う論理です。
確かに、その通りですが、日本の仏教では、更に、その上に万能の「神」が存在し、「仏」はこの「神の裏打ち」を受けている論理に成っていますので、違うと云う事に成る訳です。
そして、「神」は「仏」が精進する事で神と成り得るとする教義です。
「仏」とは、”死して民から全ての煩悩を取り除けた時に成り得るものである”とする論理設定です。
仏教では多くの神が存在し、「武勇の神」とする「神」は、その元は現存した人物を元と成っているのもこのことから来ています。
仏教では、この様に、現存した人物の「仏」が「神」となったものには、民の全ての生活職種に対して「神」が存在し、その中でも万能の全種の神が存在するとしています。
(例えば、渡来人の阿多倍子孫の大蔵種材という武勇に優れて人物が居ましたが、この「武勇の神」の「真利四天王」等の様に成った。)
キリスト教でも、釈迦の弟子が神と成っている様に、キリストの弟子が神扱いとしているのも現実ですが、日本の仏教の様に、全ての種の神が存在する事はありません。
又、キリスト教の祖師のキリストと同じ位置にある、仏教の祖師のお釈迦様を直接拝する行為は日本の仏教徒では少ないでしょう(日本では一部にはあるが直接ではない。アジアの他国の仏教では直接崇拝がある)。
ここが「天神文化」から来る差で、違う所だと思います。
つまり、お釈迦様を特別のものとして扱い特別崇拝するは、「神道」の神との融合から、「神道」の神を引き下げてしまう結果が起こり、且つ、避ける結果とも成ってしまう事にもなり、日本では出来ない設定となります。
況や、「一軍の将、ニ将合い立たず」「一国の神、二神合い立たず」で有ります。
日本の仏教には経緯として2つあるとされている。この2つの仏教(顕密仏教と鎌倉新仏教)には、この個人を神扱いする崇拝の傾向が少なくなったのです。
故に、キリスト教に対しては、万能とする個人の「個人崇拝」的イメージを我々は持つのだと思いますし、「万能」とするところにキリスト教には疑問が残るのでしょう。
しかし、これは、キリスト教徒がそれで納得すれば当り前と成り、故に問題は無く、仏教徒にしてみれば疑問点と成るのだけと考えます。
「個人崇拝」は「人、時、場所」の三相にて正否の如何は異なりますので、世界的に観て、「個人崇拝」の起こり難い土壌の所謂「天神文化」を持つほどに、「融合民族」の「融合文化」を持つ日本人の方がおかしいのかもしれません。
但し、融合は進化を及ぼしますから、この「おかしさ」は愚劣のものではなく、優秀の「おかしさ」と考えます。
故に、日本仏教は禅宗などの「仏教学」が生まれたものであると観ます。
4目のことです。(兎に角にも、”先ずは信じよ”である事)
2でも述べていますが、この言葉の前提には、「個人の考え」を先ず排除して、教義を信じさせる事から始まっています。これは受け取り方では”信用していない”と言う事に成ります。
仏教では、個人の考え方の差違は問いません。
その考え方の中で、「悟りなさい」としていて、その「悟り」の障害は「拘り」であるとしています。
そして、”今の自分を是として、あるが侭に、受け入れなさい”としています。
人は、”今の自分を是”とする仏教と、”悪の子供”とするキリスト教の「教義」とは、全く反対ですし、”「信じよ」”と”「悟りなさい」(理解)”では大きく違います。
ただ、もう一つ疑問になる点があります。
アメリカを始めとするキリスト教徒は、主に自由の国にあります。自由な考えの中での宗教では、その個人の考え方を認めたうえで、教義が起こる筈です。
しかし、”先ず信じよ、信ずれば救われる”とするは、個人の考えの前提になっていないのではないかという事です。
これでは、仏教では”今の自分を是”とする”としていますが、この様に、仏教の個人の現在の考え方を是としたところから始まる導きの方が、アメリカのキリスト教的では無いかと思えるのです。何か逆であると感じます。
仮に、アメリカとすると、他民族の集合体であり、必然的に自由な考え方を認めなければならず、結果、あり過ぎる事から、否定で入らないと教義の伝播は困難である事から来ているのであるのでしょうかろうか。
収拾が取れないので、”全てを捨てて”としている事はこのことを物語っている証拠となり得るだろうとわ思います。
この逆に、同じ他民族の集合体では有るけれど(日本は7民族の融合単一民族で有るので)、融合という優れた手段で考え方が殆ど統一されている故に、その考え方に左程に差違はないとして、「是」としている事と成ろうと思うのです。
この理屈が適切とすると、大きな問題が出て来ます。
それは、アメリカでは、”全てを捨てて”は適切な事として納得できるが、この理屈を変化させずに、直接、単一民族の考え方の少ない「是」する日本人に、キリスト教のこの”全てを捨てて”の手段(教義)は、間違っている事に成るのでは無いだろうかと思います。
私を含む多くの日本人に、安土桃山時代からこれ程キリスト教が伝導した歴史がありながら、その比率が少ないのは、上記の疑問のこの点が大きく影響していると考えられます。
この設問の提起された方の疑問の 「”全てを捨てて”」は、私も含めて、個々に問題があると思うのです。
そして、キリスト教にはもう一つ矛盾があるのです。
それは、”全てを捨てて”とありますが、全てを捨てられれば、既に”何も宗教は要らないのではないか”と言う事です。
捨てられないから、宗教に頼るのではあれませんか。又、”全てを”とありますが、全てどころの話では無く、一つさえも捨てること自体が出来ないから、宗教に頼るのではありませんか。
仏教では、ここは”ありのままでよい”と説いています。
そして、”それが人間なんだ”と説いています。
捨てられればそれは、人間ではなくなるではありませんか。理屈では有りません。
つまり、人間の性(さが)なんです。人間の性(さが)を全て捨てられれば、それは、仏教では「仏」です。生きている人間が「仏」になる事はおかしいのではありませんか。
仏教では、”ありのまま”即ち、「拘るな」と説いています。
「悟れ」即ち、「理解せよ」としています。
これなら、”捨てる”という「行為や行動」より、人間として成し得るものです。そして、それは更に可能な「心の道」として、”冷静に正しい心根”と説いています。これならば、この程度の事を成し得ないとするは、それは人間ではなく、獣と変わりません。
よって、その努力は可能です。そして、”1度にではなく、日々積み重ねよ”としています。
更に、続けて、”その行為は五感を通して”としています。
つまり、”聞く(耳)、観る(目)、嗅ぐ(鼻)、触る(皮膚)、味わう(舌)で日々精進せよ”としています。
ここで、問題に成るのは、”「拘り」を少なくする事が出来るのか”という事です。
そこで、”出来る”という論所を脳医学的に説きます。
このことを知る事で仏教の上記した証明の例と成りますので特記します。
医学的「否拘り」の可能性の証明
人間の「感情」の主体は、「前頭葉」(側頭葉含む)と言う所で管理されています。
この「前頭葉」の動作反応は次の様なメカニズムで働きます。
人の脳は、頭の中心(渦)の所に「脳幹」と言う部分があります。
この部分は電極の役目をしています。
地球がマイナスの電極体ですので、人間はプラスの電位が掛かり、ほぼその身長に等しい値と成ります。
この電位をもって脳の中を小電流が流れます。
この電流は脳神経を通じて流れ、脳神経と脳神経の継目には、キャリパーと言うNaアルカリイオンが継目に流れます。
このキャリパーが流れている間だけ電流が流れて目的の脳の部分に流れて行きます。
この場合に、「前頭葉」に繋がります。
この部分は「感情」を司るところですので、この「感情」はこの「キャリパー(Na)」の液体が流れている間は、この「感情」が維持されます。
例えば、最も顕著な感情として、女性の「母性本能」です。
全ての女性が例外なく、子供が生まれたと当時にこの感情が出て長く続きます。これはこの電流が前頭葉に繋がったままで流れている事に成ります。
これは無意識のうちです。
では、そこで、この物事に対する「拘り」の心は、この「前頭葉」のこの部分に脳神経の継目が繋がった状態を意味します。
つまり、このキャリパーが流れているのです。
大体は普通は0.2秒間程度ですが、特に女性はこの時間が長く持ち続ける傾向があります。
だから、物事が感情的に捉えてなかなか外れないと言う現象が起こりやすいのです。
ところが、男性は、その性の目的から、この部分の繋がっている時間は短く出来ています。又、意識的に切ることさえ出来る様になっています。原始の時代に生活の糧を得る為に生存競争の中に飛び込み戦い殺戮の中で勝てを得る必要があります。従って、殺戮のこの感情を押さえて敵と生死を賭けて戦わなくては成らない為に、脳はこの感情を押さえる能力を保持しています。それで、この電気信号の継電部をきりキャリパーを止めることが出来る様に成っているのです。
この場面に備える為に武士は「武士道」を創り上げて「静かなる心根」を保てるように訓練するのです。
例えば、その切る事の感情は、側頭葉のところで感情の管理を行っていますが、この側頭葉への信号を自発的に切れる様にして管理されているのです。
戦場では相対して殺戮します。もし、女性の様に、感情を維持し続けると、この事はパニックと成って思考が停止して出来ません。しかし、男性は戦場とする場では、正統な行動して思考を固め、側頭葉の感情を押さえることが出来る仕組みに成っています。思考が停止しパニックには成り難いのです。
この様に[拘り」即ち、脳医学の「キャリパー保持」は訓練でコントロール出来る事を証明できます。
「拘り」と言う点では、当然に、この理屈から女性の方が強く成りますし、「感情」を主体とした深層思考原理(無意識の脳の中での思考する原理)ですので、長く続く事に成ります。
つまり、女性は本能的に「拘り」が強いと言う事に成ります。
兎も角も、男女は別として、この「拘りの感情」を短くする事、又は、外す事には、この液体のキャリパーの流れを止めればよいわけです。
では、どうして止めるかです。
それは、その「環境」から先ず外に出る事、つまり、その「感情」を持ち得ている「環境」を変える事に成ります。
簡単な事は、「環境」を変えることで直ぐに変わりキャリパーは止まります。そうすれば電流は切れますので「感情」は停止します。
ひどく「拘り」が強くなった脳が「うつ状態」の現象ですが、この治療は静かな都会を離れた環境が良いとするはこの理由からです。ただ、この時、上記の五感の一つでは効果は少ない事に成ります。
仏教が言う「拘り」とすれば、静かにして正しくする時間を長くする事で次第に流れは変化して停止します。
これが一つの方法として、周囲の「環境」を整えて「念仏」を唱え「一心無我」になる、又は、上記の「五感」を通して冷静になる事です。僧が行う座禅はこの事によります。(医学的に最も効果的手段)
大きい「拘り」はこの訓練を続けることで、「停止」し、「拘り」の「感情」を外す事が出来るのです。
つまり、この理解で大きく「静かなる心根」を得られれば、必然的に医学的に[脳機能」の通電は止まり、「拘りの心」は無くなるのです。
だから、この脳医学の原理と同じく、仏教では、上記した「冷静に正しく理解する姿勢」(悟り)と解いているのです。
そして、その”「今の侭の自分を是」として、「理解」し、「次第」に、この「理解」を深めて行け”としているのです。
明らかに1000年昔の仏教の教えは、現代の脳医学の対処法と完全合致しています。
これは、明らかに、仏教を信じようが、又、信じなくても、万人が成し得ることに成ります。
ただ、仏教は、最適のこの場(環境)の提供をしていて「助け」と成っているだけなのです。
重ねて、当然、このことの「拘り」を無くする修行を成した経験者、即ち伝道者、修験者や先達人(僧侶)がそこには居る事にも成り助けとも成ります。これが本来の仏教の導く姿です。
キリスト教の”信じよ”と較べても明らかに間接的です。
これが、脳医学から見た仏教であります。矛盾はありません。
近代医学では、この様な宗教の本質の所を解明されつつあるのです。
だから、宗教もこの時代の進歩、つまり、「科学的進歩での付加価値の増加」を加味して、教義を修正しなくては、現代との間に”ずれ”が出るのです。
現代病の「うつ」は、この「科学的進歩での付加価値の増加」に起因する「拘り」の結果から来る病気ですが、この処方箋は、上記の脳医学のメカと対処法の所以と成ります。
この様に、医学的で「拘り」を捨てることを証明出来るのです。
実は、私は、この様な事から、現代の「付加価値の進歩拡大」の為に、「五感」に加えて、ここに「考える(頭)」を追加したいのです。
これが、仏教の「心経」、即ち、(頭「考える」は)「こころの道」であると説いています。
この「五感」(考える追加)を正しくし、敏感にして冷静にすれば、「悟れる」とし、”自ずと理解できる方向にと近づく”としています。
これであれば、仏教の、誰でもが、宗教に帰依する有無に関わらず、「救われる」とする事は、理解し納得できます。
「信じる者」だけではないのです。これが「万能の神」が成す所以ですから。
例えば、都会から離れて、自然に親しみ、生活する事でも、より「悟り」に近づいている事の実感を得ます。
私も、この様なキリスト教の矛盾と、この点の疑問も大きく伸し上がって来て”合わない”との結論を出したのです。
次は5番の事に続きます。
|
|
| | 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| |
 ワード検索
ワード検索